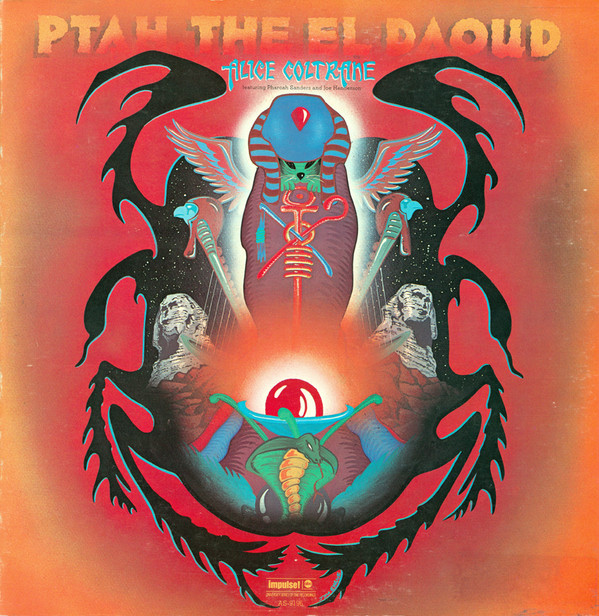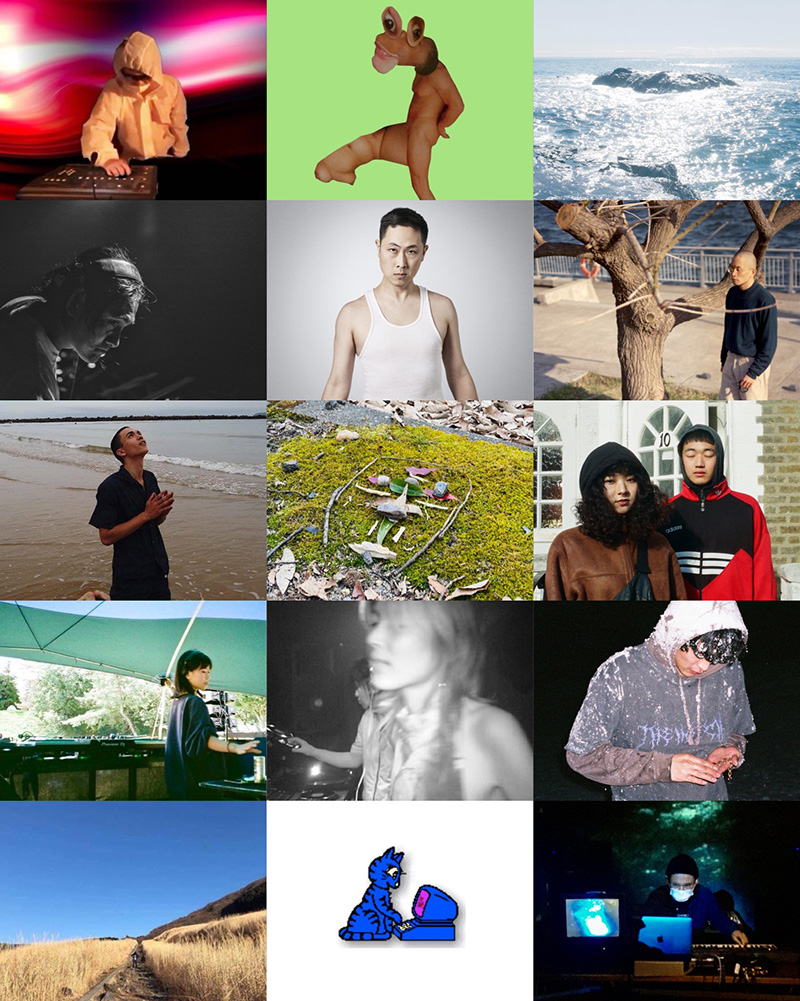1981年に歌謡テクノユニット“ゲルニカ”に参加して本格的な音楽活動を開始した戸川純。そこから今年で40周年となるのを記念し、アルファ/YENレーベル時代にリリースしたソロデビューアルバム『玉姫様』(1984年)と、ライヴアルバム『裏玉姫』(1984年)が、カラーヴァイナル仕様のLP盤で再発売されることが決定した。『裏玉姫』は当初カセットテープだけで発売されたもので、今回が初のLP化。濃厚な個性と多彩な活動で80年代を牽引し、現在も後進の女性ロックアーティストに多大な影響を与え続けている彼女の足跡を振り返る重要な機会となりそうだ。
〈シンガーソングアクトレス 40周年記念 『玉姫様』『裏玉姫』VINYL REISSUE〉
2021.9.29 IN STORE
完全生産限定盤
各定価:¥4,070(税抜価格¥3,700)
発売元:ソニー・ミュージックダイレクト

戸川 純/玉姫様
30cm 33 1/3rpm Vinyl: MHJL-198
Original release: 1984/1/25
●完全生産限定盤
●2021年ニューカッティング
●クリアレッドヴァイナル(透明赤)仕様
●封入特典:特製ステッカー
ゲルニカ活動休止を受け、自己プロデュースで1984年リリースしたソロデビューアルバム。女性の生理をテーマにしたタイトル曲や、バロック曲(パッヘルベルのカノン)に自作詞を付けた「蛹化(むし)の女」を含み、唯一無二の世界観が存分に表現された本作は、彼女を一躍80年代サブカル女王の地位に押し上げた。現在も日本の女性ロック史に刻まれる名盤としての存在感を放っている。
Side 1
1. 怒濤の恋愛
2. 諦念プシガンガ
3. 昆虫軍
4. 憂悶の戯画
5. 隣りの印度人
Side B
1. 玉姫様
2. 森の人々
3. 踊れない
4. 蛹化の女

戸川 純とヤプーズ/裏玉姫
30cm 33 1/3rpm Vinyl: MHJL-199
Original release: 1984/4/25
●完全生産限定盤
●2021年ニューカッティング
●クリアピンクヴァイナル(透明ピンク)仕様
●封入特典:特製ステッカー
前作『玉姫様』と同年に、当初カセットテープだけで発売された初のライヴアルバムを、今回初めてアナログLP化。1984年2月19日、東京・ラフォーレミュージアム原宿で収録。バックのヤプーズ(泉水敏郎/中原信雄/比賀江隆男/立川芳雄/里美智子)と共に全編パンクでハイテンションな演奏を展開。現在でも戸川純のライヴの大詰めで歌われる「パンク蛹化の女」収録。
Side A
1. OVERTURE
2. 玉姫様
3. ベビーラヴ
4. 踊れない
5. 涙のメカニズム
Side B
1. 電車でGO
2. ロマンス娘
3. 隣りの印度人
4. 昆虫軍
5. パンク蛹化の女
戸川 純 ソニーミュージック特設サイト
https://www.110107.com/jun_togawa40th/
同じく初ヴァイナル化されるヤプーズ作品。
8月18日(水)発売
ダイヤルYを廻せ!
品番:PLP-7171
価格:¥3,850 (税込)(税抜:¥3,500)
★初回生産限定
ダダダイズム
品番:PLP-7172
価格:¥3,850 (税込)(税抜:¥3,500)
★初回生産限定
戸川純のユーチューブ「戸川純の人生相談」もはや18回目を迎えています! 戸川純が欽ちゃんファミリーに?