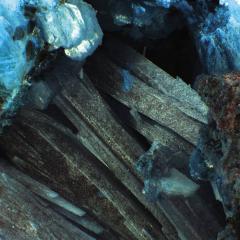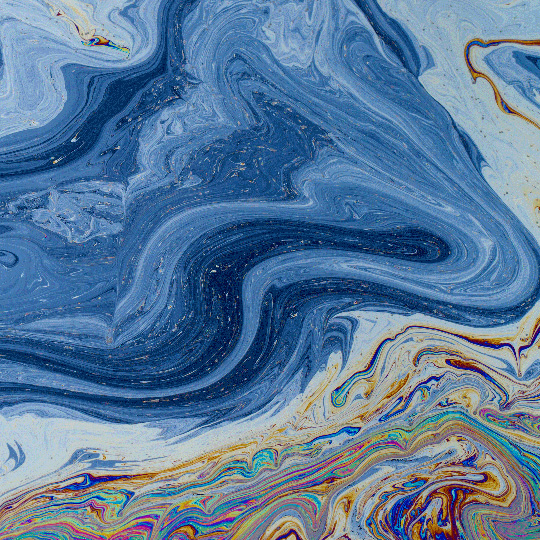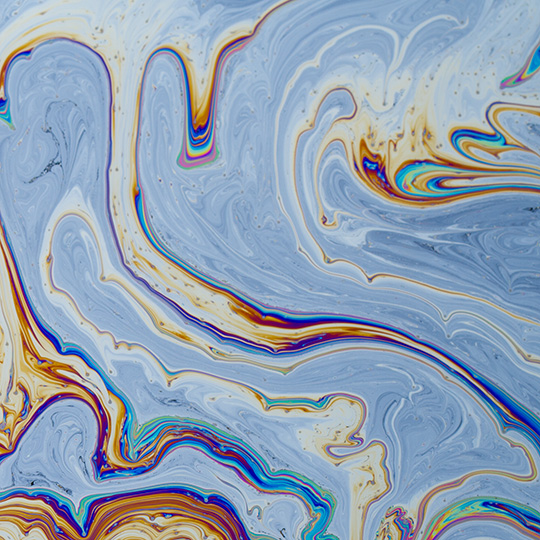00年代における最重要作と言っても過言ではない『Untrue』(2007)以降、いっさいアルバムを発表していないベリアルだけれど、10年代に入ってからも「Street Halo」(2011)や「Kindred」(2012)、「Truant」(2012)、「Rival Dealer」(2013)に「Young Death」(2016)に「Subtemple」(2017)にと、〈Hyperdub〉から気まぐれにEPをリリースし続けている。今年の初夏にも「Claustro」が出ているが、レーベルが15周年を迎えるこの年に、それらのEPをまとめたコンピレイションCDが発売されることとなった。収録曲はベリアル自身が選んでいるとのことで、『Untrue』以後の彼の歩みを振り返る良い機会になりそうだ。

artist: Burial
title: Tunes 2011 To 2019
label: Hyperdub
release: December 6th, 2019
tracklist:
CD1
01. State Forest
02. Beachfires
03. Subtemple
04. Young Death
05. Nightmarket
06. Hiders
07. Come Down To Us
08. Claustro
09. Rival Dealer
CD2
01. Kindred
02. Loner
03. Ashtray Wasp
04. Rough Sleeper
05. Truant
06. Street Halo
07. Stolen Dog
08. NYC