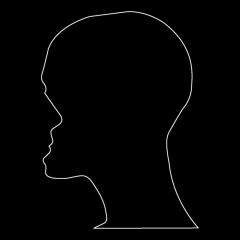なんというか、思い切りましたよね。消費税増税で庶民のサイフに大きくダメージを与えてから発生直後の新型コロナウイルスを国内におびき寄せる。高齢者の致死率が高いという情報は春節前からわかっていたわけだし、物流で動いている経済が麻痺し、株も大幅に下落すれば中流以下の国民がもっとビンボーになることは確実。そう、所信表明演説で言ってましたからね。今年は「出生率をアップさせる」って。名付けて「貧乏人の子沢山」作戦でしょうか。英語で言えば「オペレーション・ロッツ・オブ・プアー・ピープル」? 国民が貧しくなれば必ずや子どもをたくさん産むはず。どんな審議会が提案したんでしょうねー。いろんな審議会があるみたいですからねー。議会で話し合うのが筋なんですけどねー。
というわけで『モンティ・パイソン』です。70年代のイギリスで炸裂したブラック・ユーモアの総本山。BBCのTV放送で初めて「シット!」と発音したのはセックス・ピストルズではなく、コメディアンのジョン・クリーズでした。クリーズと毎晩のように論争を繰り広げていたテリー・ジョーンズは、この1月に亡くなり、『ライフ・オブ・ブライアン』(79)をコメディ映画の最高峰と位置づけるブライアン・イーノも「安らかにお眠りください」とツイッターにメッセージを挙げていた。故人となったテリー・ジョーンズ、同じく故グレアム・チャップマン、そして、ジョン・クリーズ、エリック・アイドル、マイケル・ペイリンの5人は毎週、毎週、会議に会議を重ね、シャンデリアからぶら下げるのはヒツジがいいのかヤギがいいのかで朝まで議論し続けたというなか、モンティ・パイソンの一員でありながら、この会議に一度も参加しなかったのがテリー・ギリアムであった。「15秒空いたから、なんか作って」と言われて、いつもピッタリの長さでアニメを製作していたのがテリー・ギリアムで、彼はそう、『モンティ・パイソン』が83年に放送を終了してから、メンバーのなかでは最も知名度を上げた映画監督となっていく。『未来世紀ブラジル』(85)『フィッシャーキング』(91)『12モンキーズ』(96)と立て続けに管理社会を風刺しまくった挙句、『ラスベガスをやっつけろ』(98)ではゴンゾー・ジャーナリズムのハンター・S・トンプソンをアイコン化し、FKAトゥイッグスが本誌16号のインタビューでフェイヴァリットに挙げていた『ローズ・イン・タイドランド』(05)では貧困とサイケデリックを同時に描くという離れ業までやってのけた。そんなギリアムが構想から30年かけてようやく完成させたのが『ドン・キホーテを殺した男(原題)』。ジャン・ロシュフォールとジョニー・デップをキャスティングし、最初に撮影を始めたのが1998年(以下、ゴシップに属する話題は割愛)、ジェラール・デュパルデュー、ロバート・デュバル、ユアン・マクレガー、ジョン・ハートと次々にビッグ・ネームの配役が決定しては降板となり、最終的にジョナサン・プライスとアダム・ドライバーという布陣で最後の撮影を開始したのが2017年。プロデューサーも最終的にはデ・ラ・イグレシアやケン・ローチの作品を実現させてきたヘラルド・エレーロとマリエラ・ベスイェフシに落ち着いたという結果も興味深い。

テリー・ギリアムの映画に出ることを熱望していたというアダム・ドライバーがまずはいい(ドライバーいわく、景色がとても美しいので「演技がひどい時は、山を見てくれればいい」!)。オープニングでドライバー演じるトビーはスペインに赴き、『ドン・キホーテ』をモチーフとしたCMを撮っている。近いところではマーティン・スコセッシ(スコシージが正しい)監督『沈黙 -サイレンス-』やスパイク・リー監督『ブラック・クランズマン』(https://www.ele-king.net/review/film/006767/)でシリアスな演技が印象づけられていたために、CMの撮影がうまく進まず、いらいらしているだけで彼の演技は妙におかしい。プロデューサーの妻(オルガ・キュリレンコ)と浮気をしているトビーが、そして、怪しげな物売りから買ったDVDを再生してみると、それは自分が学生時代に撮った『ドン・キホーテを殺した男』。撮影した場所は自分たちがいまいる場所の近くで、CMの撮影現場を放棄したトビーは彼の映画に出てくれたハビエル(ジョナサン・プライス)やアンジェリカ(ジョアナ・リベイロ)がいまはどうしているのかと探しに行ってしまう。学生時代にトビーが撮った『ドン・キホーテを殺した男』は絶賛され、彼を映画界へと導いてくれたものの、彼が実際に進んだ道はCM業界であり、新しい時代に生きる古い男という原作の主題がここではそれとなく重ね合わされている。CM業界では生きられない。彼が本当にやりたかったのは映画ではなかったのかと。そして、彼はかなりややこしい手順を踏んでハビエルを見つけ出す。トビーが学生時代に出会った時、ハビエルは靴職人で、トビーの描いていたイメージにピッタリだったという理由でドン・キホーテを演じてもらったのだけれど、(以下、ネタバレ)10年経ってもなお、ハビエルはドン・キホーテであることをやめていなかった。「戻ってきたのか!」とハビエルは叫ぶ。囚われの身となり、見世物にされていたハビエルを解放すると同時に火事を出してしまったトビーは警察に追われることになり、気がつくと自分はサンチョ・パンサの位置にいる。そして台本通りに2人は、そのまま冒険の旅に出る!(……あとはもう滅茶苦茶でござりまする)。

こ、これが30年かけて撮りたかったことなのかと驚くほどくだらない。管理社会とか様々なディストピアを描いてきたテリー・ギリアムはどこへ……。わー。この作品はしかし、17世紀に書かれた原作がメタフィクションであることを忠実に再帰させているだけでなく、ドン・キホーテの物語が語られているということを何度も思い出させるところは『バロン』や『12モンキーズ』との接点も見えやすい。テリー・ギリアムだけでなく、吉田喜重監督『血は乾いている』(60)やデヴィッド・クローネンバーグ監督『ヴィデオドローム』(83)など「現実と虚構の区別がつかない」というセルバンテスの主題を20世紀以降のメディア社会にあてはめて反復させた作家たちは少なくない。それらは複製に疎外される主体というモチーフを好み、悲劇として描かれることがほとんどだったけれど、リアリティTVの浸透とともに様相は変化し、ロン・ハワード監督『エドTV』(99)では「見られる」は「見せる」へと能動的な主体に転出し、ケイシー・アフレック監督『容疑者ホアキン・フェニックス』(10)になるとリアリティTVのフェイクを先に仕掛けるという荒技まで飛び出してくる。もはやセルバンテスのような滑稽さは存在せず、リアリティTVが民主化したともいえるSNSが普及したことで、たとえばツイッター上でメタフィクショナルな人格を交錯させることはごく日常的な操作となり、複数のアカウントを持つことで人格分裂も簡単になってくると、アバターを機能させない主体の方が人間存在として不自由だと言えるほどである。『ドン・キホーテを殺した男』は、そういった意味ではノスタルジックなメディア環境を思い出させ、「なりすまし」がまだ「なりきり」だった時代のユーモア感覚を蘇らせた作品だと言える。ナチョ・ビガロンドやアリ・フォルマンといったインターネット世代の監督たちが現代の悲劇を炙り出す一方、複製によって主体が疎外されていた時代そのものを喜劇として捉え直すことで『ヴィデオドローム』や『12モンキーズ』の時代が終わったことを告げ知らせているとも。表立ってはいないけれど、移民差別の問題を盛り込む手腕も見事だし、全体に美術やヘア・メイクの完成度の高さ、あるいは原作を尊重してスペインをロケ地に選び、ペドロ・アルモドバルの諸作でおなじみロッシ・デ・パルマをキャスティングしていることも嬉しい。

蛇足ながらこの冬、細野晴臣がTVドラマ初出演となった清水康彦監督『ペンション 恋は桃色』(フジテレビ系)や山下敦弘監督『コタキ兄弟と四苦八苦』(テレビ東京系)もコメディとして出色の出来であったことを付け加えておきたい。斬新な設定を用意するわけでもなく、ごく日常的なドラマを描きつつも新しさを感じさせた前者に、『傷だらけの天使』の右肩下がりヴァージョンみたいだった後者と、どちらもまだまだ観たかった。笑いたかった。

映画『テリー・ギリアムのドン・キホーテ』予告編

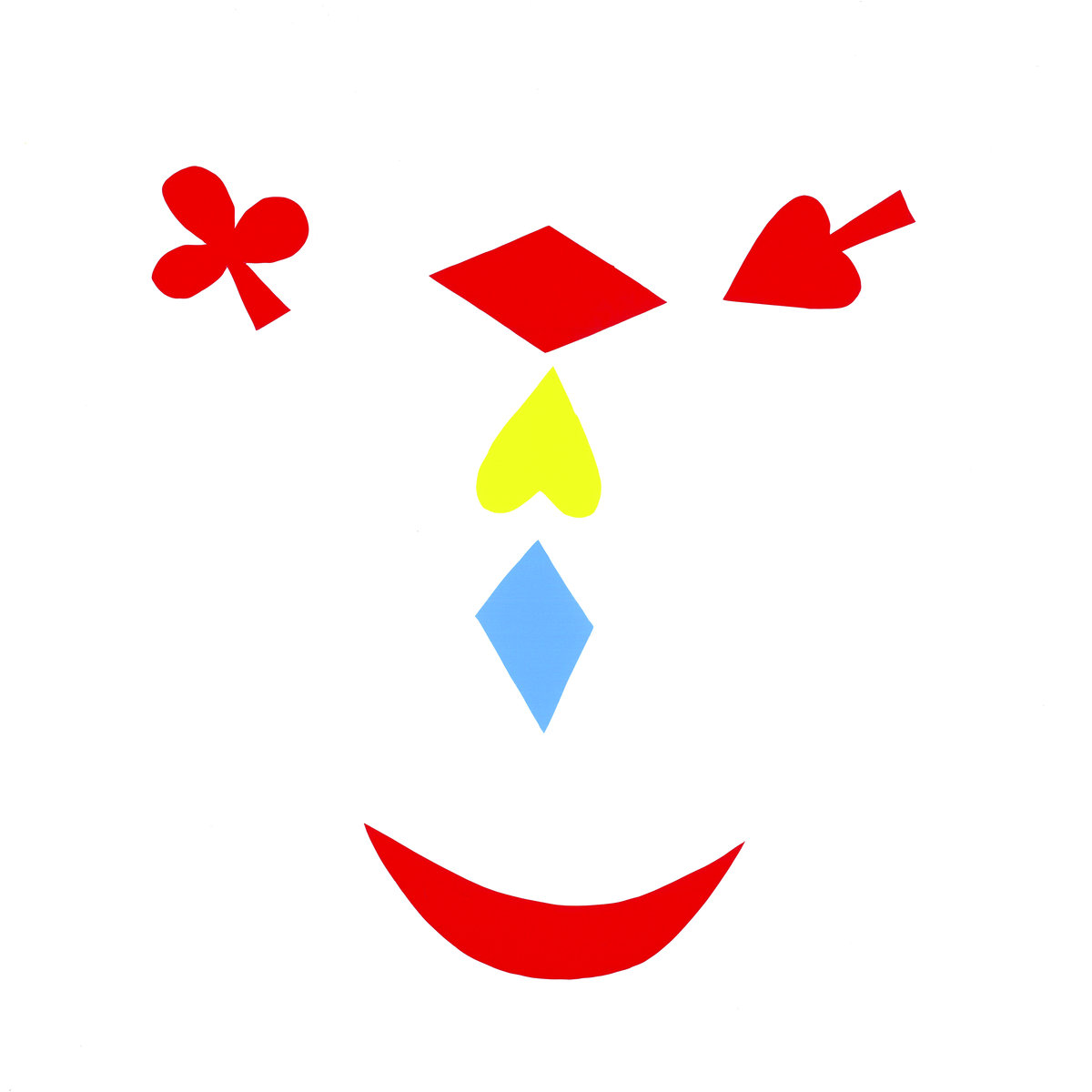 DJ Nigga Fox / Cartas Na Manga
DJ Nigga Fox / Cartas Na Manga
 Tunes Of Negation / Reach The Endless Sea
Tunes Of Negation / Reach The Endless Sea
 Sequoyah Murray / Before You Begin
Sequoyah Murray / Before You Begin
 Ultramarine / Signals Into Space
Ultramarine / Signals Into Space
 Caterina Barbieri / Ecstatic Computation
Caterina Barbieri / Ecstatic Computation
 Tenderlonious / Hard Rain
Tenderlonious / Hard Rain