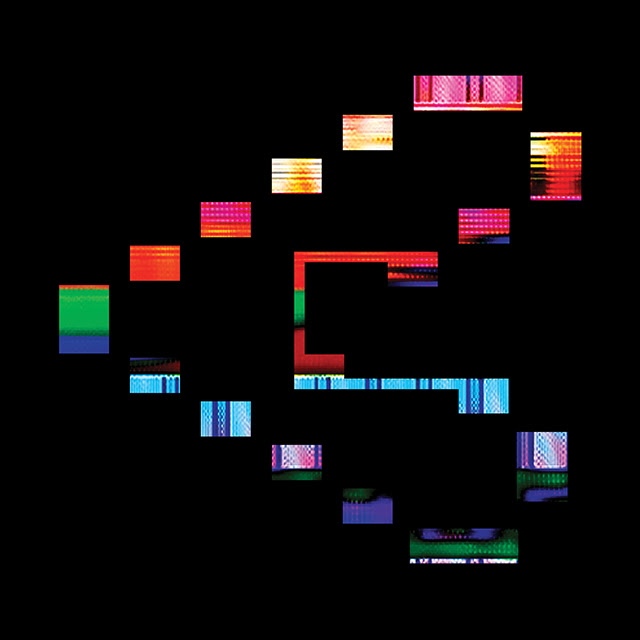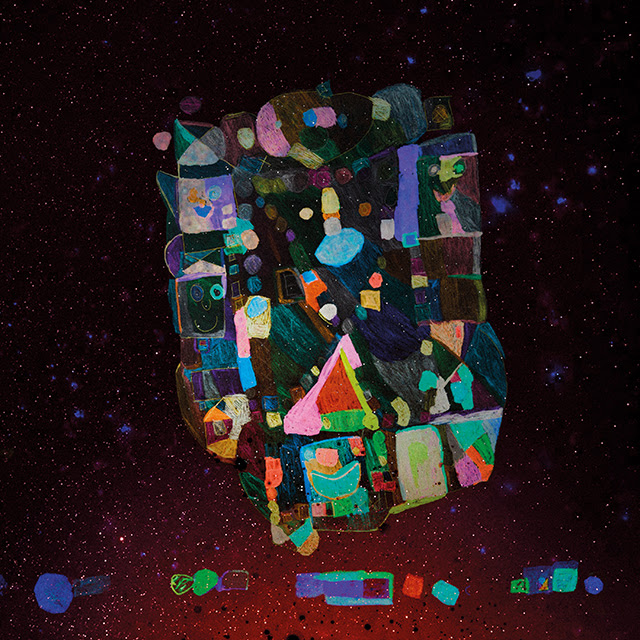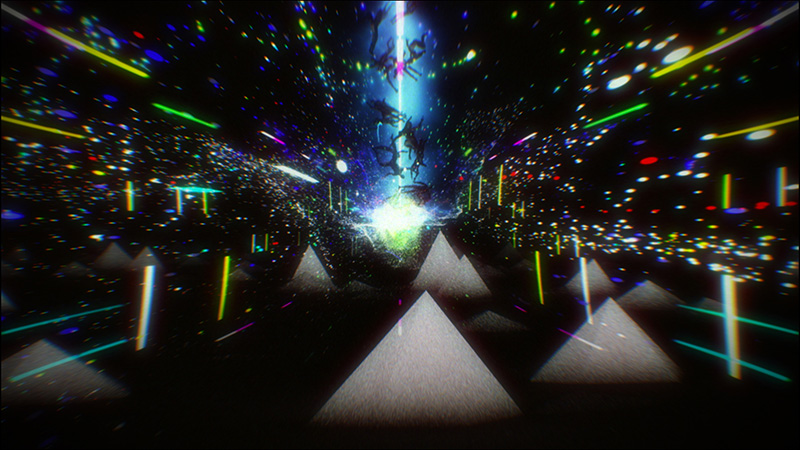4月に新作『It Is What It Is』(リディム・イズ・リディムの名曲とおなじ慣用句ですね)をリリースするサンダーキャットが来日! 大阪・名古屋・東京の3都市をまわることが発表されました。アルバム発売直後という絶妙のタイミングでの公演です。これは見逃せニャい。しっかり予習しておきましょう~。
THUNDERCAT
大注目のニューアルバム『IT IS WHAT IT IS』をひっさげ
待望のジャパンツアー開催を発表!!!
チケット主催者先行は本日18時スタート!!!

THUNDERCAT JAPAN TOUR 2020
4月21日(火) 大阪 BIGCAT
4月22日(水) 名古屋 CLUB QUATTRO
4月23日(木) 東京 THE GARDEN HALL
TICKETS : ADV. ¥6,800+1D
OPEN 18:00 / START 19:00
※未就学児童入場不可
その年を代表する傑作として名高い前作『Drunk』で、超絶技巧のベーシストから正真正銘の世界的アーティストへと飛躍を遂げ、唯一無二のキャラクターで音楽ファンを虜にするサンダーキャットが、3年振りのニューアルバム『It Is What It Is』と共に単独来日決定!
ベースプレイヤー、ヴォーカリスト、ソングライター、メロディメイカーなどなど、そのどの肩書きにおいても超一流の天才&奇才、サンダーキャット。音楽だけでなく、水面から顔をつき出したジャケ写でも話題をさらった前作『Drunk』から3年、盟友フライング・ロータスとの共同プロデュースで遂に完成した待望のニューアルバム『It Is What It Is』には、チャイルディッシュ・ガンビーノ、スティーヴ・レイシー、スティーヴ・アーリントン、カマシ・ワシントン、リル・B、タイ・ダラー・サイン、バッドバッドノットグッド、ルイス・コール、ザック・フォックスら、超豪華アーティストが勢揃い! アーティスト達からの絶大な信頼を物語る驚愕のゲスト陣もさることながら、そのベースプレイ、見事なソングライティング、美しい歌声には、さらなる磨きがかかっている。デニス・ハム(key)とジャスティン・ブラウン(dr)という、これまた間違いない超一流ミュージシャンによるトリオ編成での鉄板パフォーマンス。超絶即興演奏もお約束! さあこの来日公演、見逃すわけニャ~いかないでしょう! 完売必至!!
TICKET INFO
全国共通 チケット先行
2/5 (水) 18:00〜 BEATINK 主催者先行
2/7 (土) 12:00〜 イープラス最速先行 *2/12 (水) 23:59まで
4月21日(火) BIGCAT
2/17 (月) 12:00〜2/20 (木) 18:00 イープラス先着先行
2/22 (土) 一般発売:
チケットぴあ (P:178-293) *English avilable、ローソンチケット (L:55574)、BEATINK 他
INFO: SMASH WEST 06-6535-5569 [https://smash-jpn.com]
4月22日(水) NAGOYA CLUB QUATTRO
2/13 (木) 10:00〜2/17 (月) 18:00 チケットぴあ *English avilable / ローソンチケット 先行
2/15 (土) 12:00〜2/17 (月) 18:00 QUATTRO WEB先行
2/17 (月) 12:00〜2/20 (金) 18:00 イープラス・プレオーダー
2/22 (土) 一般発売:
イープラス、チケットぴあ (P:176-246) *English avilable、ローソンチケット (L:43092)、LINE TICKET、クアトロ 店頭、BEATINK 他
INFO: 名古屋クラブクアトロ 052-264-8211 [https://www.club-quattro.com/]
4月23日(木) THE GARDEN HALL
2/13 (木) 12:00〜2/16 (日) 23:00 ローソンチケット プレリクエスト
2/13 (木) 11:00〜2/20 (木) 11:00 チケットぴあ プレリザーブ *English avilable
2/17 (月) 12:00〜2/20 (木) 18:00 イープラス・プレオーダー
2/22 (土) 一般発売:
イープラス、ローソンチケット (L:73722)、チケットぴあ (P:177-137) *English avilable、BEATINK 他
主催: SHIBUYA TELEVISION
企画制作・INFO: BEATINK 03-5768-1277 [www.beatink.com]
サンダーキャット超待望の最新作『It Is What It Is』は、4月3日(金)に世界同時リリース! 国内盤CDには、前作の大ヒット・シングル “Show You The Way” でも共演したマイケル・マクドナルド参加のボーナストラック “Bye For Now” も追加収録され、歌詞対訳と解説書が封入される。また数量限定でTシャツ付きセットも発売決定。基本の黒ボディのデザインに加え、BEATINK オフィシャルWEBサイト限定の赤/白ボディデザイン(受注生産:3月15日予約〆切)も登場! アナログ盤は、レッド・ヴァイナル仕様、クリーム・ヴァイナル仕様、特殊パッケージ入りクリア・ヴァイナル仕様、特殊パッケージ入りピクチャーディスク仕様の4種類が発売される。
BEATINK.COM Tシャツセット全フォーマットはこちら!
https://www.beatink.com/user_data/thundercat_iiwii.php
必聴の新曲 “Black Qualls (feat. Steve Lacy & Steve Arrington)”
https://thundercat.lnk.to/it-is-what-it-is/youtube


label: BEAT RECORDS / BRAINFEEDER
artist: Thundercat
title: It Is What It Is
release date: 2020/04/03 FRI ON SALE
国内盤CD BRC-631 ¥2,200+税
国内盤CD+Tシャツ BRC-631T ¥5,500+税
国内盤特典:ボーナストラック追加収録/解説書・歌詞対訳封入
BEATINK.COM (全フォーマット)
https://www.beatink.com/user_data/thundercat_iiwii.php
TOWER RECORDS:
CD: https://tower.jp/item/5013704/
CD+T-SHIRTS SET (S): https://tower.jp/item/5018898/
CD+T-SHIRTS SET (M): https://tower.jp/item/5018900/
CD+T-SHIRTS SET (L): https://tower.jp/item/5018901/
CD+T-SHIRTS SET (XL): https://tower.jp/item/5018906/
AMAZON:
CD: https://www.amazon.co.jp/dp/B083XVTHYN/
HMV:
CD: https://www.hmv.co.jp/product/detail/10603078
TRACKLISTING
1. Lost In Space / Great Scott / 22-26
2. Innerstellar Love
3. I Love Louis Cole (feat. Louis Cole)
4. Black Qualls (feat. Steve Lacy, Steve Arrington, & Childish Gambino)
5. Miguel's Happy Dance
6. How Sway
7. Funny Thing
8. Overseas (feat. Zack Fox)
9. Dragonball Durag
10. How I Feel
11. King Of The Hill
12. Unrequited Love
13. Fair Chance (feat. Ty Dolla $ign & Lil B)
14. Existential Dread
It Is What It Is (feat. Pedro Martins)
16. Bye For Now (feat. Michael McDonald) *Japanese Bonus Track