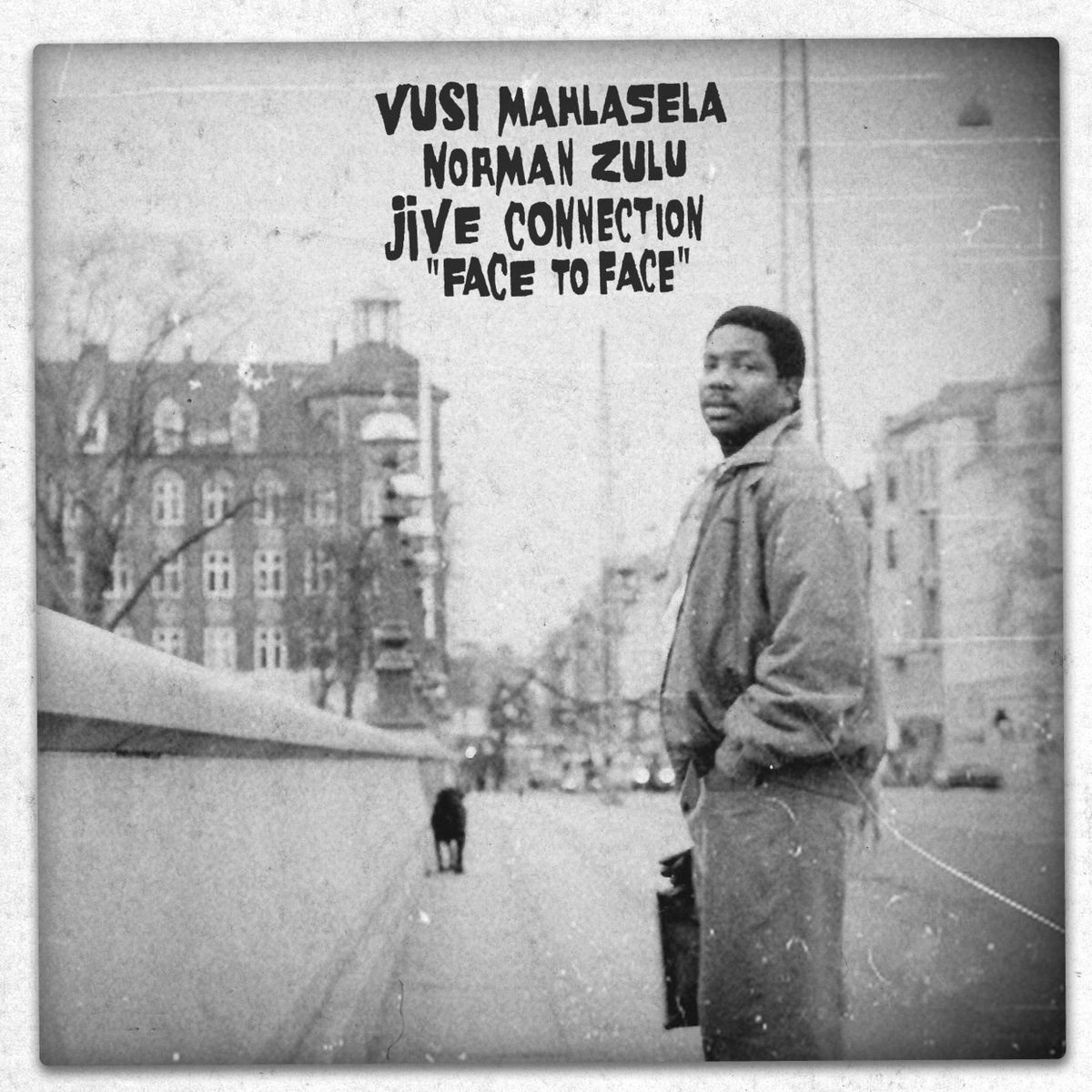昨年末からTikTokが『ソルトバーン』を観た人のリアクションであふれている。とくに目立つのはバリー・キヨガン(と聞こえる。日本ではコーガンと表記)演じるオリヴァー・クィックがバスタブの残り湯を啜るシーンで、ガールフレンド(?)が撮影しているのか、このシーンを観ている男たちが一様に気持ち悪がり、「ノー」と叫んだり、あっけにとられたりしている。バスタブの残り湯にはジェイコブ・エロルディ演じるフィリックス・キャットンのザーメンが混じっているという設定で、同作のプロモーションのためにエロルディがジミー・ファロンのレイト・ナイト・ショーに出演した際は、バスタブの残り湯を連想させるロウソクのビンが6種類ほどデスクに並べられ、ひとつを選んでエロルディが口をつけようとするとスタジオの観客から悲鳴が漏れる。多岐に渡るTikTokのショート・ムーヴィには押し黙って観ている老夫婦をどうだと言わんばかりに映し出すものや2人組の女子がバスタブのミニチュアに白濁した液体を入れて飲み干すなどあまりに品がなく、リアクションの数が増えれば増えるほど僕が最初に『ソルトバーン』を観た時の印象からはどんどん遠ざかっていく。さすがにハイプだと非難する声も上がり、しかし、「ソルトバネスク」などという言葉が生まれるほど作品の訴求力が高いことも確かで、考察系の動画などTikTokや他のSNSではシリアスな内容のものも増えている。イギリス流のブラック・ユーモアを理解するために過去の映画や文学の知識が総動員され(イギリスを代表するブラック・ユーモアの作家、イヴリン・ウォーは「キャットン家の先祖を題材に小説を書いていた」というセリフもある)、あれこれと観ていたら迷路の中心に置かれたミノタウロスのほかにも作品のあちこちに銅像がちりばめられていたことや窓の外のドッペルゲンガーなど指摘されるまで気がつかなかったことも多かった。
06年、オックスフォード大学の入学式。オリヴァーはおどおどと大学の構内に足を踏み入れる。食堂では「お前、友だちいないだろ」と嘲られ、出身地がリヴァプールに近いプレスコットというだけで指導教官からも妙な表情をされる。ポッシュ(富裕層)とサイコパスがオリヴァーの周囲ではひしめき合い、導入部だけで気が滅入ってくる。ある日、オリヴァーが自転車で図書館に行こうとすると、フィリックスが壊れた自転車の前で座り込んでいる。自分は歩いて行ける距離だからといってオリヴァーはフィリックスに自転車を貸す。フィリックスは有力者の息子で、陽キャに手足が生えているようなリーダー的存在。人に指図することに慣れきった風で、フィリックスがオリヴァーに礼を言ってもどうも素直な感じは伝わらない。ここからはスクール・カーストの存在を思い知らされるようなエピソードが畳み掛けられる。オリヴァーはフィリックスの「おもちゃ」にされながら、しかし、フィリックスには「おもちゃ」を大切にする側面もあり、対等なのか主従なのか、簡単には割り切れない奇妙な関係が育まれていく。ある日、オリヴァーの元に父親が倒れたという報が入る。オリヴァーはフィリックスの部屋に飛んでいき、オリヴァーの境遇に同情したフィリックスは優しく彼を慰めてくれる。舞踏会の日、タキシードを着込んだオリヴァーに級友たちが「似合ってるじゃないか。レンタルだろ」と続けざまに皮肉をぶつけていくなか、フィリックスはオリヴァーを会場とは正反対の方向に連れていく。小川を目の前にしたフィリックスは死んだ父親の名前を石に書いて川に投げ込めとオリヴァーに促す。しかし、石は川沿いのゴミの上に落ちて水の中には落ちなかった。
夏休みになると、フィリックスはオリヴァーを屋敷に招待する。タクシーを降りるとオリヴァーの目の前には広大な敷地が広がっている。巨大な玄関が開くと高圧的な執事が慇懃無礼にオリヴァーを招き入れ、フィリックスが広大な屋敷の内部を案内していく。部屋の装飾はヘンリー7世の飾り棚やヘンリー8世のザーメンなど王侯貴族の遺産にルーベンスの絵画やシェイクスピアの初版本など計り知れない資産価値のものが並んでいる。フィリックスは適度に下品な言葉でそれらを紹介し、家族が待つ部屋にオリヴァーを連れていく。オリヴァーの到着を待っていた家族が「去年の人…」という言葉を使ったところで2人が部屋の扉を開け、オリヴァーは様々に声をかけられるものの、その内容はあまりに無神経でオリヴァーは体を硬くするしかない。「夕食は正装で」と言われたオリヴァーは「カフスは持ってきた?」と訊かれても「持ってない」と答えるしかなく、貸してもらうことに。
その日からポッシュの暮らしぶりが毎日、繰り広げられる。BGMはMGMT〝Time to Pretend(それらしく振舞う)〟。イギリスのポッシュが性的に乱れると下品極まりないのはロネ・シェルフィグ監督『ライオット・クラブ』(14)と同じくで、オリヴァーの行動も少しずつ妙な方向に走り出す。フィリックスがマスターベーションしていたバスタブの残り湯をオリヴァーが啜るシーンは前述した通り。フィリックスの妹に誘惑されて自分はヴァンパイアだといって生理の血に顔を埋めたり(水の中から撮ったようなショットはとても秀逸)。ヘンリー7世や8世とつながりがあるかのように想像させる友人一家を招いたディナーでは食後にカラオケ大会が開催され、客人が自分は金持ちだという趣旨のフロー・ライダ〝Low〟をラップし、オリヴァーはペット・ショップ・ボーイズ〝Rent〟を歌わされる。歌いながら、歌詞の内容が金持ちに養われている人の気持ちだと気づいたオリヴァーは続きを歌えなくなり、キャリー・マリガン演じる友人のパメラが「自立すべきだ」とキャットン夫妻に言われて、事実上、屋敷を追い出されるエピソードも前後して差し挟まれる。パメラの生き方を評して「悲劇のヒロインぶってこちらの同情を集めている」というオリヴァーのセリフは後々に重要な意味を持ってくる。様々な心象風景が矢継ぎ早に展開し、フィリックスはオリヴァーの誕生日にサプライズがあるといって彼を車に乗せる。最初は喜んでいたオリヴァーだけれど、車の向かう先が自分の実家だと悟るや、行きたくないと騒ぎだす。オリヴァーの家に着いてみると普通に暮らしている夫婦が彼らを出迎え、すぐにもオリヴァーがフィリックスに話していたことはすべて嘘だったことがわかる。(以下、ネタバレ)オリヴァーは実は『聖なる鹿殺し』と同じく、計算通りにキャットン家に入り込んだのである。そして、フィリックスの父親による提案で200人規模の仮装パーティが開かれることとなり、翌朝、思いもかけない事件が起こる……。
『ソルトバーン』をひと言でまとめると「中産階級が下層階級の悲惨さをエサにして上流階級の富を脅かす話」となるだろうか。『太陽がいっぱい』のように持てる者と持たざる者を対極におくのではなく、「少し持てるもの」と「多く持てるもの」の対比であり、富裕層(ここでは代々の資産を受け継ぐソーシャライト)の価値観もグロテスクに映るなら、手段を選ばずにのし上がろうとする中流の欲望も醜く歪んでいる。富裕層がことさらに悪として描かれるわけでもなく、中流が野望を持つに至った動機もとくに説明がない。TikTokなどのソーシャル・メディアでは富裕層を批判する言葉として「イート・ザ・リッチ(eat the rich)」というフレーズが2010年代後半に広まり、映画だと『パラサイト』や『ジョーカー』がそれを映像化した例といえ、現実の政治でも2021年には地方選挙のスローガンとして使用されたり、中国では富裕層の屋敷が襲われたりもしている。いずれにしろ現在の格差社会において富裕層はそれだけで悪という気分が広く共有されているから成立している話だと思うしかなく、『太陽がいっぱい』も殺人の動機には説明がなく、当時は自明の理だったものがいつしか風化してしまったために、39年後に新たな動機を付け加えてリメイク作『リプリー』がつくられたように『ソルトバーン』も時代が変われば理解不能な作品になってしまうのではないだろうか。ここで共有されている気分は、そして、フランス革命が最底辺の人々には無縁のブルジョア革命だったことにも通じている。富の偏りに耐えかね、憤っているのは最底辺の人々ではない。中産階級が「悲劇のヒロインぶって同情を集めている」のだと。
ラスト・シーンはオリヴァーが全裸で屋敷のなかを延々と踊ってまわる。『ジョーカー』の階段のシーンを意識しているのは明らかで、これには賛否がかなり分かれる。僕も「イート・ザ・リッチ」という趣旨を体現するなら整合性のある表現だと思ったけれど、このシーンに使われているソフィー・エリス・ベクスター〝Murder On The Dancefloor〟のMVを観たところ、ダンス・コンテストで競争相手を次々と失脚させていくプロセスがあまりにチープで、オリヴァーの行動をこれになぞらえているとしたら確かに「Ruin(台無し)」だなと思うようになった(だから〝Murder On The Dancefloor〟のMVは観ない方がいい)。オリヴァーがキャットン家を「イート」していく過程はバリー・キヨガンにしか出せない説得力があり、その総仕上げとして全裸で踊っているというなら、こうした悪趣味にも意味があると思えたのに。
バリー・キヨガンという俳優が最初に目に止まったのはクリストファー・ノーラン監督『ダンケルク』(17)だった。戦場の臨場感をひたすら描く作品で、キヨガンはチョイ役だったにもかかわらず、どこか物言いたげな表情は妙に印象に残った。2ヶ月もしないうちに同じ顔に再会できた。 ヨルゴス・ランティモス監督『聖なる鹿殺し』(17)でキヨガンはマーフィー家を恐怖のどん底に突き落とす悪魔のような役だった。「ような」どころか後半は悪魔そのものに見えた。とんでもない存在感だった。かつて『狼たちの午後』が表していた失意をオバマ時代の終わりと重ねたバート・レイトン監督『アメリカン・アニマルズ』(18)でもキヨガンは腺病質な学生強盗団の一味を演じ、クロエ・ジャオ監督『エターナルズ』(21)ではアマゾンに隠れ住んでいた不老不死の宇宙人と、もはや彼に普通の役はオファーされないという感じになってきた。かつてデニス・ホッパーが歩いた道である。その道をキヨガンは着実に歩き出している。マット・リーヴス監督『ザ・バットマン』(22)ではジョーカーの演技を研究したそうで、本編だけでなく未公開シーンも強烈。マーティン・マクドナー監督『イニシェリン島の精霊』(22)でもややこしい役割が当てはめられていた。
エメラルド・フェネル監督 『ソルトバーン』を僕が観ようと思ったのは、そう、単にバリー・キヨガンが出ていたからだった。フェネルは『ソルトバーン』にも陰を落とす『アルバート氏の人生』(11)や『リリーのすべて』(15)などセクシュアリティを扱った重要作で役者を務めたのち(『バービー』にも出演)、イギリスで近年、問題となっているフェミサイドをひっくり返した『プロミシング・ヤング・ウーマン』(20)で初監督を務めたばかり。『ソルトバーン』は長編2作目にあたり、本作について本人は「狂気じみた愛の強迫性」を表現したとコメントしていて、参考にした作品は『時計じかけのオレンジ』『召使い』『テオレマ』『クルーエル・インテンションズ(『危険な関係』のリメイク)』『バリー・リンドン』と、わかったようなわからないラインナップを挙げ、パトリシア・ハイスミスによる『太陽がいっぱい』の原作ももちろんリストに加えられていた。また、上下を逆さにした構図や夜の植物の撮り方などフェネルの映像センスはかなり素晴らしく、スパイダーネットの衣装や『真夏の夜の夢』の仮装、そして、ポッシュの生活様式に『スーパーバッド』やDJシャドウなど隙間なくポップ・カルチャーが詰め込まれているところもたまらない。(2月16日に加筆・訂正)