大物同士の共演だ。坂本龍一とデイヴィッド・トゥープによる初のコラボ作が7月9日にリリースされる。『Garden Of Shadows And Light』と題されたそれは、2018年の6月、ロンドンはシルヴァー・ビルディングでのパフォーマンスを収録。レーベルは〈33-33〉で、これまで灰野敬二とチャールズ・ヘイワードの共作や、オーレン・アンバーチとマーク・フェル&ウィル・ガスリーらのコラボ作品を出してきたところ。当時の映像は、NTSによって公開されており、下記より視聴可能です。
「You meã€ã¨ä¸€è‡´ã™ã‚‹ã‚‚ã®
『Reflection』は、最近ぼくが聴いたクラブ系のアルバムとしてはダントツのお気に入り……なのだけれど、ロレイン・ジェイムズの音楽が生まれた場所はクラブではない。それは彼女が育った北ロンドンにある高層アパートのリヴィングルーム。エイフェックス・ツインやスクエプッシャー、ドリルやグライムを好んで聴いていた彼女が、窓からの景色を眺めながら、母のキーボードを時間も忘れて弾いたことにはじまっている。
アグレッシヴなデビュー・アルバム『For You And I』(2019)のアートワークに見える高層アパート群が彼女の故郷なのだろう。その1曲目、彼女のもっともずば抜けた曲のひとつ“グリッチ・ビッチ”は、ユニークなリズムを背景に「ビッチ、ビッチ」という声が反復される。ロレインは、黒人女性でありクィアである。彼女はそのアイデンティティと社会との複雑な関わりと向き合いながら、白い文化も黒い文化も男性性も女性性も折衷したエレクトロニカをじつに魅力的に展開している。
いまやロレイン・ジェイムズはUKエレクトロニック・ミュージック新世代を代表するひとりだ。彼女はAFXやテレフォン・テル・アヴィヴをただエミュレートするのではないし、いたずらにグライムやドリルをやっているわけでもない。喩えるならうまい料理人で、それもずば抜けて腕の立つコック、しかもその料理が満足させるのは耳だけではない。ハートもときには頭も直撃する。
コロナ禍においては、これまでの人生でもっとも集中的に多くの楽曲を制作したというロレインだが、昨年はグライムを咀嚼した「Nothing EP」やAFXのお株を奪うかのように楽しげな「Hmm」をリリース、リミキサーとしても売れっ子になりつつあるようで、ダークスターやケリー・リー・オーウェン、ジェシー・ランザやクーシェなどの楽曲を手掛けている。そして先週、待望のセカンド・アルバムとなる『Reflection』を出したばかりというわけだ。
それでは景気づけに“Simple Stuff”を聴いてみよう。
https://soundcloud.com/hyperdub/loraine-james-simple-stuff
UKガラージのミニマルな変異体で、シンプルに聴こえるがIDM的なアプローチがあり、しかも軽やかでなおかつ官能的という上質なダンス・トラックだ。これもそうとうカッコイイ曲だが、驚くのは早い。この手の曲はもう1曲ぐらいで、アルバムにはいろんなタイプの曲があり、その多くにはラップがフィーチャーされている。で、はっきり言うが、ほとんどそのすべてに心惹かれてしまうのだ。
ラッパーを起用しての曲がじつに面白い。たとえば1曲、初期フライローをドリーミーに進化させたようなトラックが秀逸で、ややメランコリックでありながら「目指すは山の頂上/その日が来るまでがんばれ」と前向きな言葉を吐くラップとの絡みも絶妙だ。この曲で思わず気持ちが上がったところに、続いてジャングルがズドンと突き刺さる。そして、その重低音とブレイクビートが恍惚と跳ね回ったあとには、くだんのガラージ変異体に繫がると。まあ、たいていのアルバムは3曲目あたりで力尽きてしまいがちなのだが、驚くべきことに『Reflection』は4、5、6曲目において、グローバル・コミュニケーション風の夢見るアンビエントをヒップホップのリアリズムに変換してみせているのだ。そして、ガラの悪いトラップやドリルでさえも彼女にかかるとエレガントな宝石のような輝きを携え、その夢幻めいた音響を特別なものにする。いずれにせよ、評判の良かった前作では控え目だったドリーミーで甘美な響き、あるいは内省やメランコリーが今作のサウンド面における特徴となっている。
ドリーミーといえば、彼女がファンだというLAのBathsが1曲参加しているが、これは予測されるようにエモい。でまあ、ポップなR&Bヴォーカル曲もトラック自体は悪くはないのだが、ハイレベルな本作においては歌のメロディがやや凡庸でベストな出来とは言えないだろう。しかし総じて言えば、これだけ聴き応えのあるエレクトロニック・ミュージックのアルバムはそうそうあるものではないし、『Reflection』には〈Warp〉のAIシリーズのラップ・ヴァージョンめいた側面がある。しかも……『Reflection』はたんに夢心地でうっとりするだけの作品ではないのだ。警察への怒りと黒人の連帯を主題にしている=つまりBLMとリンクする最後の曲におけるラップとジャジーなトラックとのエモーショナルな融和がみごとなように、90年代エレクトロニカのブラック・ヴァージョンとも言えるのかもしれないなと思ったりしている。そんなわけで、いまは時間が許される限りこのアルバムをただただ聴いていたい。
オリンピック村で配布されるコンドームの数が尋常じゃないと話題になってるけれど、どうせ東京オリンピックを強行するなら、いっそのこと夜のオリンピックも「OnlyFans」(https://onlyfans.com)で強行配信すれば収益もガーンと上がって、電通ウハウハなんじゃないでしょうか。セクシーな行為や姿を見られたい人が自作映像をアップする「OnlyFans」はディズニー女優のベラ・ソーンが主演作のリサーチ目的でアカウントを開設しただけで1日で1億1000万円も売り上げたというから、運営側が夜のオリンピックもコントロール下に置けば赤字も秒で解消でしょう! ああ、オレはなんて国想いなんだろう……つーか、見せたいバカはきっといる(https://twitter.com/onlyfansjapan_)。そうしたことを踏まえて、梅雨のサウンドパトロールです。
1 Cam Deas & Jung An Tagen / That (yGrid/C#) / Diagonal
https://soundcloud.com/diagonal-records/diag059-3-cam-deas-jung-an
https://presentism.bandcamp.com/track/that-ygrid-c
ケンイシイ “Extra”……かと思った。ロンドンから実験音楽系のキャン・ディーズことキャメロン・ディーズがパウウェルのレーベルに移籍し、オーストリーのステファン・ジャスターと組んだビート・アルバムの3曲目。“Extra” のダンス・ビートをゴムのミリタリー・ドラムに置き換え、全体にソリッドな質感で押し切っている。偶然にも大坂なおみを襲った病気と同じ『プレゼンティズム(Presentisim)』と題されたアルバム全部が様々なアプローチで “Extra” をアップデートさせた集合体のようで、オープニングはFKAトウィッグスの最良の仕事のひとつといえる “Hide” に通じるメキシカン・テイスト。
2 Ghost Warrior / Meet At Infinity / Well Street
https://soundcloud.com/oneseventyldn/premiere-ghost-warrior-meet-at-infinity
ハーフタイムなどドラムンベースの刷新に取り組んできたピーター・イヴァニ(Peter Ivanyi)による7作目のEPからタイトル曲。空間的な音処理に長け、ダークな余韻を残すことにこだわってきた彼が作品の質を落とさず、緊張感をアップさせた感じ。快楽的なんだかストイックなんだか。同EPからは複数のリズム・パターンを駆使した3曲目の “They Live” もいい。ハンガリーから。
3 kincaid / Slow Stumble Home / Banoffee Pies
https://banoffeepiesrecords.bandcamp.com/track/slow-stumble-home
https://soundcloud.com/banoffee-pies/premiere-kincaid-slow-stumble-home
ブリストルのニュー・レーベルからキンケイドとシューティング・ゲームに由来するらしいゼンジゼンツ(Zenzizenz)が2曲ずつ持ち寄ったEP「Single Cell」のオープニング。ロンドンのキンケイドは長らくオーガニック・ハウスをやっているという印象しかなかったけれど、ロックダウン下で取り組んだEP「Pipe Up」でハーフタイムらしき “Thirds” を聴いてから急に興味が湧いたひとり。そして、フィールド・レコーディングを素材に用いた “Slow Stumble Home” でダウンテンポというジャンルに新風を吹き込んできた。素晴らしくてナイス・チルアウト。
4 どんぐりず / マインド魂 / Victor
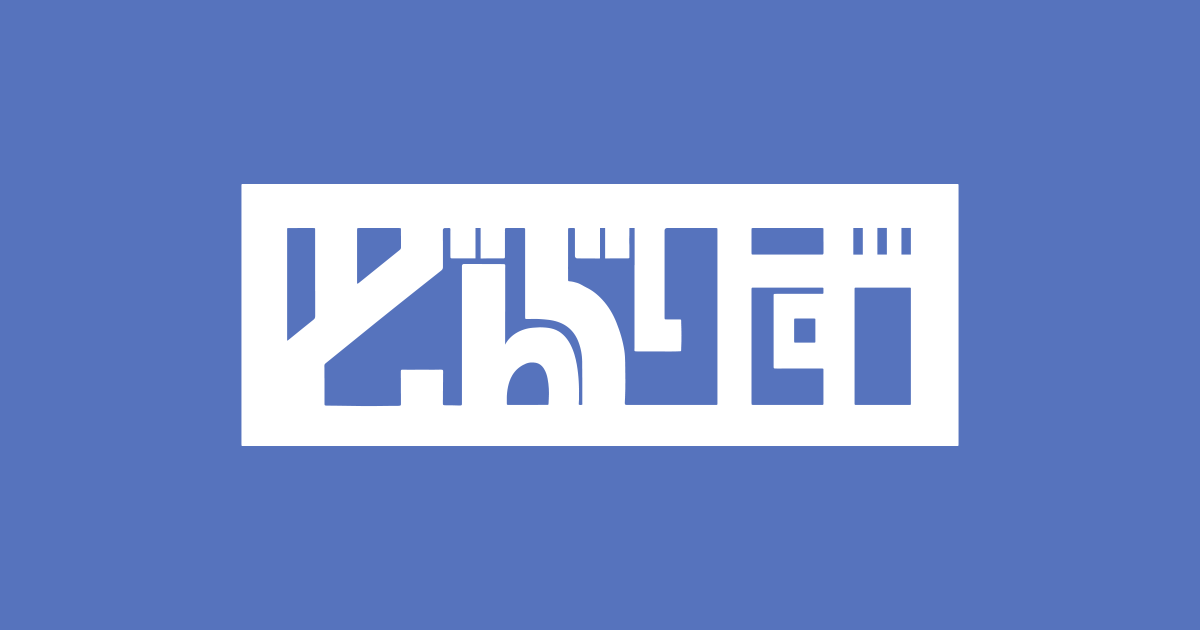
https://dongurizu.com/news/detail/80
本誌でヒップホップ特集を組んだと聞き、僕がたまにユーチューブでチェックしている群馬の二人組をピックアップしてみました。何を伝えたいのかさっぱりわからないけど、なぜか何度も観て(聴いて)しまう。
5 Kamus / Kult / Céad
https://soundcloud.com/cead_cd/kamus-kult?in=yungkamus/sets/kult
グラスゴーからキャメロン・ギャラガーによるアラビック・テイストのトライバル・ダブステップ。延々と宙吊りにされる快楽。かつてのトラップ趣味や妙な情緒の揺れは消し飛び、カップリングの “Wallace” とともにストイックでヒプノティックなパーカッション・ワークがとにかく素晴らしい。
6 ディノサウロイドの真似 a.k.a Dinosawroid-mane / 210212 / Opal Tapes
松本太のソロ・プロジェクト。カセット・アルバム『AOB』から6曲目。アルバム全体はエキゾチックなトライバル・ドラムやフェイク・ファンクなど、いい意味で懐古的なオルタナティヴ・サウンドみたいですが、“210212” はちょっと毛色が変わっていて、伸びたり縮んだりするスライムを音楽に移し替えたような面白い展開。関西の人なのか、自己紹介がふざけていてよくわからない。ネーミングの由来は→https://twitter.com/dinosawroidmane
7 Poté / Young Lies (feat. Damon Albarn) / OUTLIER
https://potepotepote.bandcamp.com/track/young-lies-feat-damon-albarn
パリ在住のポテによるアフロ・シンセ・ポップのデビュー作から8曲目。アフリカ・イクスプレスやブラカ・ソン・システマのレーベルを経て、ボノボが〈ニンジャ・チューン〉傘下に設立したレーベルから。癖がなくて聞きやすい曲が並ぶなか、ジェイミーXXのソロを思わせる “Young Lies” は重そうな歌詞をしなやかに聞かせていく。
8 miida and The Department - Magic hour
元ネゴトのマスダ・ミズキによるニュー・プロジェクト。渋谷系リヴァイヴァルというのか、さわやかで微妙にアンニュイな感じは懐かしのクレプスキュール・サウンドを思わせる。そこはかとなくダンサブルで、ロッド・ステュワート “I’m Sexy” のベース・ラインを思い出すのはオレだけか。
9 Maara / WWW / UN/TUCK Collective
「孤独なインターネット・インフルエンサー」を自称するマジー・マン(Mazzy Mann)による過去2枚のEPを素材としたリミックス・アルバム『MAARA 2.5: X MIXES & REMIXES』の冒頭に置かれた3曲のオリジナルから3曲目。リミックス部分は全部いらなかったという感じで、オリジナル曲では嘆き悲しむようなメロディをゴージャスに歌い上げ、確実にスキル・アップが達成されている。カンザス・シティのクイアーやトランスジェンダー専門のレーベルから。
10 Marjolein Van Der Meer & Big Hands / Kitty Jackson / Blank Mind
アラン・ジョンソンやラックなど秀逸なトラックものを連発してきたダブステップのレーベルがロックダウンを機に製作したアンビエント・アルバム『Comme De Loin』の5曲目。レイジーなウイスパー・ヴォーカルを軸にふわふわと頼りなげに漂う薄明のダウンテンポ。はっきりいって、良かったのはこれ1曲。
ニュー・オーの昨年のシングル曲“”のリミックス集が8月27日にリリースされる。バーナード・サムナーとスティーヴン・モリス、アーサー・ベイカーによるリミックスやadidas SPEZIALとのコラボレーション曲など全13曲が収録。
なお、現在アーサー・ベイカー(※エレクトロ・ヒップホップの始祖、NOが1983年の「Confusion」でフィーチャーしたことは有名)でによるリミックスがデジタル配信中。
New Order
Be a Rebel Remixed
Mute/トラフィック
発売日:2021年8月27日(金)
Tracklist
1. Be a Rebel
2. Be a Rebel (Bernard’s Renegade Mix)
3. Be a Rebel (Stephen’s T34 Mix)
4. Be a Rebel (Bernard’s Renegade Instrumental Mix)
5. Be A Rebel (Paul Woolford Remix New Order Edit)
6. Be A Rebel (JakoJako Remix)
7. Be A Rebel (Maceo Plex Remix)
8. Be A Rebel (Melawati Remix)
9. Be A Rebel (Bernard's Outlaw Mix)
10. Be A Rebel (Arthur Baker Remix)
11. Be A Rebel (Mark Reeder's Dirty Devil Remix)
12. Be a Rebel (Edit)
13. Be a Rebel (Renegade Spezial Edit)
[Listen & Pre-Order]
https://smarturl.it/BARremixed
ちなみに昨年3月に予定されていたジャパン・ツアーは、コロナ禍の影響により延期となり、2022年1月に実施されることとなっている。
■ジャパン・ツアー日程
大阪 2022年 1月24日(月) ZEPP OSAKA BAYSIDE
東京 2022年 1月26日(水) ZEPP HANEDA
東京 2022年 1月28日(金) ZEPP HANEDA
制作・招聘:クリエイティブマン 協力:Traffic
https://www.creativeman.co.jp/event/neworder2020/

...
うん、これは素晴らしいバンドが登場しました。ロサンゼルスの郊外、インランド・エンパイア出身の3人組、ブレインストーリーなるバンド。極上のメロウ・グルーヴ、ジャズ+AOR+サイケ+グローバルによる恍惚、ファンクと甘美なまったり感、たまらないですな。まずはこのPVで腑抜けになって下さい。
6月24日にブレインストーリーの7曲入りの「RIPE」が発売。初回限定先着80枚には、アーティスト・インタヴュー/歌詞対訳/写真など掲載の12頁ZINE付属。クルアンビンのファンはマストです。詳しくはレーベルのホームページをどうぞ。https://www.m-camp.net
過去5年の間、もしくは、これまでに観たなかで最高のライヴのひとつが、2017年の音楽フェスティヴァルFRUE(フルー)でクロージングを飾ったザ・マスター・ミュージシャンズ・オブ・ジャジューカだった。このモロッコ人たちは二度のアンプリファイド(音響ありの)・パフォーマンスで、メイン・ステージの観客の心を揺さぶる能力を披露し、すでにその週末のスターとなっていた。
そんな彼らの最終ステージは、会場を音楽祭のマーキー(大テント)に移しての深夜のアコースティック・セットだったが、PAなしで耳が聴こえなくなるぐらいの大音量を出すことのできるバンドには、そのような違いは、ほとんど意味を持たない。舞台のセッティングは、リフ山脈の麓にある彼らの村で毎年開催されているフェスティヴァルを再現したもので、舞台を覆うように敷かれた、すり切れたラグまでもが忠実に再現されていた。
そのイベントを二回ほど体験していた自分としては、何が起こるか、大方の予想はしていたものの、彼らの音楽がFRUEの数百人の観客にもたらした効果には、やはり驚かされた。その喜びに耽る夜は、本物の、ハンズ・イン・ジ・エア(両手を空にあげる)なレイヴのようで、4時間近くに及ぶパフォーマンスで、グループが新たな高みへと昇華する度に観客は喜びの雄叫びをあげた。
このような体験をレコードに収めるのは常に難儀なことであり、非常に優れたいくつかのリリースを含むマスターズのディスコグラフィでも、彼らのライヴ・パフォーマンスほどの恍惚感をもたらしたものはない。彼らの名を世に知らしめた1971年のアルバム『ブライアン・ジョーンズ・プレゼンツ・ザ・パイプス・オブ・パン・アット・ジャジューカ』では、サイケデリックな特性を際立たせるために、音楽に電子的な処理が施され、そのフィジカリティ(肉体的な衝動)が犠牲になってしまった。
それ以来、グループのリリース(バシール・アッタール率いるライヴァルの一団であるThe Master Musicians of Jajoukaも含む)は、フィールド録音から、2000年にアッタールがその一団とタルヴィン・シンとで制作した、グループの名を冠したアルバム(これはスルーしてよい作品。信じてほしい)のような作り込み過ぎたワールドビート・フュージョンのようなものなど、多岐にわたっている。しかし、2016年にパリのポンピドゥー・センターで行われた「ビート・ジェネレーション展」でのコンサートを収録した『ライヴ・イン・パリ』ほど、好き勝手に、力強くやっている録音はないと自信を持っていえる。
2017年の日本ツアーの際に限定盤として販売されたCDの、正式なLPレコードとデジタル音源のリリースは、1年以上にわたるCOVID-19煉獄の後では、より歓迎されるに違いない。これは、マスター・ミュージシャンズのアンプリファイド・モードであり、2017年のErgot Recordsからリリースされた『Into The Ahl Srif』のフィールド録音とは全く異なっており、私が記憶しているジャジューカのフェスティヴァルでのサウンドに近いものになっている。
とくにカーマンジャ(ヴァイオリン)奏者のアハメッド・タルハは、アンプの使用により、驚くべき微分音が際立つという恩恵を受け、より力強い演奏となっている。彼は1枚目のB-SIDEで中心的な役割を果たしており、故・アブデスラム・ブークザールがリード・ヴォーカルを務めた“ブライアン・ジョーンズ・ジャジューカ・ヴェリー・ストーンド”などの定番曲で、喜びにあふれんばかりの演奏を披露。裏面にも同じような曲がいくつか登場するが、ここでは音楽は曲がりくねったような、コール&レスポンスのリラ(笛)とパーカッションがヒプノティックにブレンドされており、複雑なポリリズムが各曲の終わりに突然跳ねて、アッチェレランドで加速していく。
しかし、最大の魅力は、アルバムの2枚目に収録された、トランス状態を誘発するような“ブゥジュルード”のフル・ヴァージョンだ。伝統的には、これはジャジューカ村のフェスティヴァルの最終夜に、火の灯された儀式のサウンドトラックとして演奏される組曲で、普段は寡黙なモハメド・エル・ハットミが、伝説の半人半獣(人間とヤギ)のブゥジュルードとして知られる生き物を体現する。
武骨な毛皮の衣装を身に纏い、悪霊を追い出すために人々を激しく叩くハットミの姿は、秋田県男鹿半島のナマハゲを思い出すが、音楽は全くの別物で、感覚を奪われるようなダブル・リード楽器のライタ(あるいはガイタ)が、雷鳴のようなパーカッションを背景に、群がり合い、渦を巻くように襲ってくる。
ライナー・ノーツのなかで、グループのマネージャー兼プロデューサーであるフランク・リンは、コンサートのこの部分は、音楽の原始的なオーセンティシティ(真正性)を保つために、ペアのステレオ・マイクロフォンを2つ使用したと洒落た言葉で説明しているが、これは、非常に激しくロックしているという意味だ。44分近くに及ぶ曲の中央部では、ライタが集結し、奇妙なフェイジングの効果を発揮して、音楽そのものが錯乱しているかのようだ。
グループのライヴを体験できる機会が不足しているなか、このもっとも純粋な形のトランス・ミュージックは、自分自身を解き放ち、身をゆだねるべき音である。唯一、このLPヴァージョンの批判をするとしたら、半分聴いたところで、こいつをひっくり返さなくてはならないことだ。リンによると、ポンピドゥー・センターでのコンサートでは、ステージへの客の侵入で最高潮に達したというが、これはスーサイドが演奏して以来の出来事だったそうだ。この証拠に基づけば、それこそが、道理にかなった反応だったと思う。
(アラビア語読み協力:赤塚りえ子)
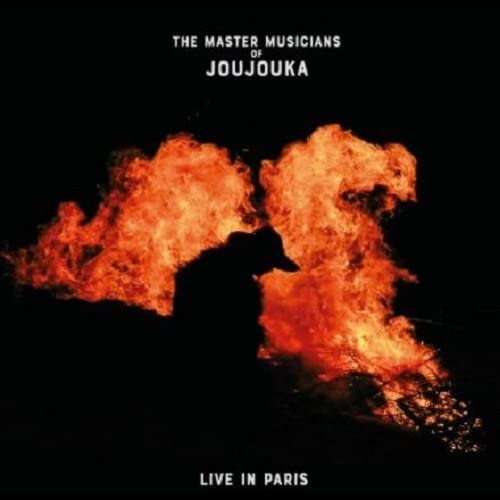
The Master Musicians of Joujouka
Live in Paris
Unlistenable Records
bandcamp
James Hadfield
One of the best shows I’ve seen in the past five years―maybe ever―was the closing set that the Master Musicians of Joujouka played at Festival de Frue in 2017. The Moroccans were the stars of the weekend, having already done a pair of amplified performances that demonstrated their ability to rock a main-stage crowd.
For their final appearance, they shifted to a marquee in the festival campsite for a late-night acoustic set―though such distinctions mean little to a band that’s capable of achieving deafening volumes without the need for a PA. The setting was a convincing recreation of the festival that the group hold each year at their village in the foothills of the Rif Mountains, right down to the threadbare rugs covering the stage.
Having been to that event a couple of times myself, I had a fairly good idea of what to expect, but the effect the music had on the assembled crowd of a few hundred people at Frue still took me by surprise. It was a night of joyous abandon: proper hands-in-the-air rave stuff, people howling with joy as the group kept ascending to new heights of intensity over a performance lasting nearly four hours.
Capturing that kind of experience on record is always going to be a challenge, and the Masters’ discography―while featuring some very fine releases―has never delivered anything quite as ecstatic as their live performances. On the 1971 album that first introduced them to a wider audience, “Brian Jones Presents the Pipes of Pan at Joujouka,” the music was subjected to electronic treatments that accentuated its psychedelic properties at the expense of its physicality.
Since then, the group’s releases―and those by rival outfit The Master Musicians of Jajouka led by Bachir Attar―have ranged from field recordings to over-produced worldbeat fusion efforts like the self-titled 2000 album that Attar’s troupe recorded with Talvin Singh (trust me: you can skip it). But I’m confident in saying that nothing has kicked out the jams quite as emphatically as “Live in Paris,” which captures a 2016 concert at the Centre Georges Pompidou, held as part of an exhibition dedicated to the Beat Generation.
Sold in a limited CD edition during the group’s 2017 Japan tour, the album has finally had a proper vinyl and digital release, and after over a year of COVID-19 purgatory it feels all the more welcome. This is the Master Musicians in amplified mode, and it’s very different from the field recordings heard on the 2017 Ergot Records release “Into The Ahl Srif,” which came closer to how I remember them sounding at the festival in Joujouka.
Kamanja (violin) player Ahmed Talha in particular benefits from amplification, letting his astonishing microtonal playing assert itself more forcefully. He takes a central role on the B side of the first disc, which features ebullient renditions of staples like “Brian Jones Zahjouka Very Stoned,” with lead vocals by the late Abdeslam Boukhzar. Some of the same pieces pop up on the flip side, though here the music is a hypnotic blend of sinuous, call-and-response lira flutes and percussion, with complex polyrhythms that leap into sudden accelerandos at the end of each piece.
However, the biggest draw is the album’s second disc, which contains a full version of the trance-inducing “Boujeloud.” Traditionally performed on the final night of the festival in Joujouka, this suite provides the soundtrack for a fire-lit ritual, in which the normally retiring Mohamed El Hatmi embodies the mythical half-man, half-goat creature known as the Boujeloud.
The spectacle of Hatmi, dressed in a ragged fur costume and vigorously thwacking people to drive out evil spirits, brings to mind the Namahage of Akita’s Oga Peninsula, but the music is something else altogether: a sense-scrambling assault of double-reeded ghaita that seem to swarm and swirl around each other, backed by thunderous percussion.
In the liner notes, the group’s manager and producer, Frank Rynne, explains that this part of the concert was recorded with two stereo pair microphones to “maintain the primordial authenticity” of the music, which is a fancy way of saying that it rocks very hard indeed. During the central stretch of the nearly 44-minute piece, the massed ghaita start creating weird phasing effects, like the music itself is becoming delirious.
Short of catching the group live, this is trance music in its purest form―sounds to lose yourself in, surrender to―and my only criticism of the vinyl edition is that you have to turn the damn thing over halfway through. The Pompidou concert culminated with a stage invasion, which Rynne says had only previously happened when Suicide played there. On this evidence, it was the only sensible response.
4月初旬、久しぶりに羽田からロサンゼルス行きのボーイングに乗った。去年、帰国した時と変わらず、羽田は閑散としていて手荷物検査場も10分掛からず通過できた。しかし手荷物検査場を出てすぐのところでパスポートに挟んでいたはずのフライトチケットが無いことに気付く。物をなくすというのはなんとも不思議な感覚である。数秒前まで大事に持っていたはずのものが跡形もなく消えているのだからちょっと笑ってしまった。搭乗まで時間もあったので再発行してもらいことなきを得たがなんとも幸先の悪い旅のはじまりである。
1. Vegyn - Like A Good Old Friend
本人主宰のレーベル〈PLZ Make It Ruins〉から、僕の最近の夜散歩のお供、ユルめなダンスEP。フランク・オーシャン等のアルバムに参加したりプロデューサーとしても名を馳せつつあるが自分の作品も感嘆の完成度。僕はエモいという言葉が本当に嫌いなのですが、これはなかなかエモいかもしれない。決して古くさい感じはしないけど、昔のことに思いを寄せたくなるような、寂しげなノスタルジーを感じる。余談だがVegyn(ヴィーガン)ことJoe Thornalleyの父親はPhill Thornalley (元ザ・キュアー)らしい!
今回の旅の目的は留学先に残してきた荷物の片付けである。ちゃんと自分で書くのは初めてだが、僕はここ3年ほどの間ロサンゼルスに住んでいた(といっても2020年は半分以上日本にいたので実質2年半だが)。去年の7月はまだパンデミック真っ只中で、通っていたカレッジもオンラインに移行したので登校できるようになったら戻ろうと荷物もほとんど置いて帰ってきたのだが、とりあえず日本で腰を据えて頑張ろうという決心がついたので完全帰国を決めた。
高校入学前に親から留学を勧められたときはなかなか勇気が出ず、流されるように日本の高校に入学し、2年生も半分終わるころやっと決心がつき突然ロサンゼルスの高校に編入し、卒業後もカレッジまで行かせてもらったのに途中でやめる中途半端さと天邪鬼な性格を両親と預かってくれていたゴッドマザーに詫びるとともに感謝したい。
2. Joseph Shabason - The Fellowship
テキサス州オースティンのレーベル〈Western Vinyl〉から。去年リリースされたChris Harris, Nicholas Krgovichとの共作、''Philadelphia''も素晴らしいアルバムだったけど、今作も繊細で気持ちの良いがより実験的なアルバム。 ''Philadelphia''で多用されてた笛みたいな音はShabasonの仕業だったのか。今作でもよく笛を吹く。曲によってだいぶ曲調が違く、アンビエント・ポップ的な曲もあれば、打楽器が複雑に重なっていく曲やギターでノイズを出すのもある。1人で真面目に聴いても良いし、暗すぎないので部屋でかけても良さそう。
LAX(ロサンゼルス国際空港)に着くと通常はイミグレーションで1、2時間は待たされるのだが空いていたので、ものの30分で出られた。入国の際のPCR検査や自主隔離の説明、体調の確認などもいっさい無く、入国してすぐにアメリカを感じさせられる。ゴッドマザーと幼馴染である彼女の娘が迎えにきてくれ、久しぶりの再会を喜び「フライトチケットなくしちゃってさ〜笑」などとお喋りしながら家へ向かう。このとき僕は空港のカートにパスポートを置き忘れているのに全く気づかず、アメリカの空はいつ見ても大きいな〜などとうつつを抜かしているのであった。パスポートをなくしたのに気付くのは2週間後のことである。
3. Shame - Live in the Fresh
前々回すでにアルバムのことは書いたのでバンドの説明は省きます。パンデミック中なので無観客ライヴのライブ盤。1曲目“Born in Luton”の冒頭のシーケンスでもうがっちり掴まれる。Youtubeにミニコント付きの映像も上がっています。なぜかYoutubeのほうが音が良いし映像あったほうが上がるのでYoutube推奨。 コントちょっと面白いけどコメントを見るとあんまりウケてないところも良い。
2週間隔離を終え街に出た。ワクチンの接種もはじまっていて徐々に人出も増えてきている。移転した〈Amoeba Music Hollywood〉も人数制限のせいもあるがレコードストアデイでもないのに入店待ちの行列。
以前より敷地面積は狭いがやっぱりデカイ。レコードコーナーが縮小してCD、DVDコーナーと半分ずつくらい。僕の好きだったグローバル・ミュージック・コーナーにいたっては棚四つくらいしかなく残念。

4.Tex Crick - Live In... New York City
マック・デ・マルコのレーベル、〈Mac's Record Label〉(そのまま)からTex Crickのセカンド・アルバム。 タイムスリップしてきたのかってくらいの、もろ70'sソフトロック。むしろ若いリスナーには新鮮であろう、70年代とはもう半世紀前だし、シティ・ポップのリヴァイヴァルがあるし、ちょっと前Tik Tokでフリートウッド・マックが流行ったりしてたし。力の抜けた歌も心地良いし、シンプルで嫌味のないピュアさがグッとくる良アルバム。
片付けとパスポートの再発行をすませ、パンデミック中に長居する理由もないので東京へ帰る。正直ロサンゼルスという街に飽きていたので未練はないが、少し名残惜しいのはタコス・アル・パストールくらいだ。アル・パストールはスパイスに漬けた豚肉を回転式グリル機でカリカリに焼いてパイナップルと一緒にいただく屋台タコスで僕の大好物。LAの渇いた空気と炭酸飲料とタコスのタッグの破壊力は凄まじい、本場メキシコにもぜひ行ってみたい。残念ながら東京には美味しいアル・パストールを出す店は無い。あの味を求めていつかまたロサンゼルスに行かなければならないだろう。
マン・オン・マンのデビュー・シングル“Daddy”のミュージック・ヴィデオには笑った。それは年の差ゲイ・ベア・カップル(「ベア」はゲイ・コミュニティにおいて肉づきがよくて毛深い男性のセクシーさを表現する意味で使われます)が半裸でイチャイチャしているだけのもので、イケてるダディ(「ダディ」はゲイ・コミュニティにおいて中高年男性のセクシーさを表現する意味で使われます)との性的な体験の期待がパンデミックによって邪魔されることの不安を歌った歌詞といい、いま世のなかは大変だけど、こんなに朗らかに過ごしているゲイ・カップルもいるんだな……とちょっと励まされたのだった。
しかし微笑ましく思っていた数日後、このヴィデオが「過度に性的である」という理由でYoutubeから消されてしまう。え!? いや、ヘテロセクシュアルのものでもっと過激にエロティックなものはいくらでもあるし、ゲイものでも(いわゆる)美青年のものだったらそう簡単に消されないでしょう。「ホモフォビアだ」とゲイのリスナーから抗議が出てしばらくするとヴィデオは復活したが、ダイヴァーシティ・マーケティングが当たり前になった現在、Youtube側にも悪気があったわけではないだろう。ただ、ゲイ度が濃すぎたのだ。ゲイを含め性的マイノリティの表現の受容において世界はこの10年で本当に進んだけれど、世のなかはまだ、ブリーフ姿のおじさんふたりがイチャイチャしているのは見たくないのかもしれないな。だけど僕は子どもの頃から、それがずっと見たかった。本当に。
ともあれ、当人たちは激しく抗議することもなく、自己隔離のなかでクリエイティヴィティを保つために作ったという音楽をたんたんと発表していく。セカンド・シングルのタイトルは“Baby, You're My Everything(ベイビー、きみはぼくのすべて)”だ。ヴィデオはやっぱり、ゲイ・ベア・カップルが半裸でイチャイチャしているだけのものだった。
マン・オン・マンはフェイス・ノー・モアのキーボーディストであるロディ・ボッタムが彼氏のジョーイ・ホルマンと組んだユニットで、これがデビュー作だ。ボッタムはハード・ロックやメタル・シーンのなかでは珍しくかなり早くからカミングアウトしており、『アダム&スティーヴ』とのタイトルのゲイ・ラブコメ映画のサウンドトラックを担当するなど、長年飄々とゲイ・コミュニティに貢献してきた人物だ。ただ、ロックのなかでもとくにマッチョなシーンに身を置いてきたために、ホモフォビックな言動は数多く目にしてきたし、実際、カミングアウトは多くのひとに止められたという……ファンを失うことになるぞ、と。それでもボッタムは堂々と「ゲイであり続けた」。元ハスカー・ドゥのボブ・モールドといい、いま60歳前後のゲイ・ロッカーたちが元気に活動していることには、いちゲイとして素直に尊敬の念を抱かずにはいられない。
アルバムはもっとシンセ・ポップ寄りになるのかと思っていたら、オープニング・ナンバー“Stohner”がもろに90年代オルタナ・ロック調なのを皮切りにして、かなりギター・ロック然とした1枚である。ホルマンは何でもクリスチャン・ロック・バンドのメンバーだったそうで、彼もまた同性愛嫌悪が強いシーンに身を置いていた人物なのだが、彼の音楽的嗜好が反映されたものなのだろう。エレクトロニックなダンス・ポップはゲイ・ポップスとしてはいまやクリシェになっている側面もあるので、ゲイネスをたっぷり表現したロック・ミュージック──1980年代からクィアコアと呼ばれてきた──はいま、かえって新鮮だ。いや音としては新しいものではないが、クィア性があまり目につかなかった90年代のハード・ロックやオルタナティヴ・ロックを新しい価値観から再訪しているようにも見える。そこにはボッタムをはじめとして、少なくないセクシュアル・マイノリティが存在したのだと。
だから、基本的にボッタムが年下の彼氏のことが好きで好きで仕方ないということが伝わってくるだけの本作は、他愛もないと言えばそうだが、その他愛のなさによってこそセクシュアル・マイノリティの生を祝福する。フワフワとした曲調で素朴に歌われる“It's So Fun (To Be Gay)(ゲイでいることはすごく楽しい)”はそして、21世紀の“Glad to Be Gay”だ。トム・ロビンソン・バンドによるアンセムのように闘争的な姿勢はこの曲にはないが、とにかく楽しく生きることで、マン・オン・マンはセクシュアル・マイノリティの現在と未来をエンパワーメントしているのだ。
同性愛を「不道徳」だとかトンチキなことを言う人間は残念ながらいつでもいるし、ゲイ度を濃くすると消去されることもまだまだあるだろう。だからこそ、僕たちは自分たちの性と生を謳歌しよう。彼氏のことが大好きなら、人前でイチャイチャしたってかまわない。ゲイ・シーンのパイオニアはかく語りき──It's so fun to be gay!
今日における最重要パーカッショニストと呼んでも過言ではないイーライ・ケスラー。ヘルム『Olympic Mess』からローレル・ヘイロー『Dust』『Raw Silk Uncut Wood』、OPN『Age Of』やダニエル・ロパティン『Uncut Gems』まで、数々の話題作に関わってきた異才──彼の新作がなんと、グラスゴーの〈LuckyMe〉からリリースされる。
日本でもコロナ禍によって街の音が変わったけれど、ケスラーの新作『Icons』ではロックダウン中のニューヨークでかき集めたさまざまな音がコラージュされているようだ。現在アルバムより “The Accident” のMVが公開中です。これは楽しみ。
Eli Keszler
盟友OPNとのコラボレーションでも知られる
唯一無二の鬼才パーカッショニスト、イーライ・ケスラーが
最新作『Icons』を〈LuckyMe〉より6/25にリリース!
新曲 “The Accident” のMVが公開
ニューヨークを拠点とするパーカッショニスト/作曲家/サウンド・アーティストのイーライ・ケスラー。これまでに、〈Empty Editions〉、〈ESP Disk〉、〈PAN〉、〈Shelter Press〉といった先鋭的なエレクトロニック・ミュージックのレーベルからリリースを重ね、前作『Stadium』では Boomkat のアルバム・オブ・ザ・イヤーに選出された。また、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーことダニエル・ロパティンが手がけたサフディ兄弟の傑作『Uncut Gems』のスコアへの参加や、ローレル・ヘイローとのコラボレーション、Dasha Nekrasova 監督の長編映画『The Scary of Sixty First』のオリジナル・スコアの作曲など活動の幅を広げ続ける彼が、最新作『Icons』を〈LuckyMe〉より6月25日にリリースすることを発表した。現在先行配信曲 “The Accident” のMVが公開されている。
Eli Keszler - The Accident
https://youtu.be/elWW-QQx8IQ
アルバム中、ドラム、パーカッション、ヴァイブラフォン、マリンバ、フェンダーローズ、その他多数の楽器がイーライ自身によって演奏されている。ゲストには往年のコラボレーターでもあるヴィジュアル・アーティストのネイト・ボイスがギターシンセで参加、更に中国やクロアチア、その他世界中のさまざまな場所で録音されたサウンドが使用されており、中には渋谷の富ヶ谷公園のサウンドも含まれているという。また、本作はアメリカの抽象主義、夢のような古代のメロディズム、インダストリアルなパーカッション、アメリカの1920年代ジャズエイジのフィルムノワール、帝国の衰退などの様々な要素の断片が散りばめられたコンセプチュアルな作品となっている。
『Icons』は、旅行や輸出入といったことが事実上停止していた時に作った音楽だ。僕は夜な夜なマンハッタンを歩き回って、車のアラームが数ブロック先まで聞こえるような、誰もいない静かな街の録音を集めた。そこでは、電気の音や自転車のギアの音といったものが大半を占めていた。昨年はずっとマンハッタンに滞在していたけど、1つの場所にあんなに長く滞在したのはここ10年の中でも初めてだった。マンハッタンは基本的に閉鎖されて、不規則なペースで動いていた。救急車、抗議活動、ヘリコプターなどの激しい状態から、美しくて奇妙な、穏やかな静寂のような状態まで、街が揺れ動いているように見えた。僕はそこで、何か奇妙で美しいことが起こっていると思ったんだ。権力が崩壊し、人々が変化していた。『Icons』では、僕たちの目の前で劣化して朽ち果てていく神話的な表現を用いて、僕らの壊れやすくて不安定な現実の中に美を見出すような音楽を作ったんだ。 ──Eli Keszler

イーライ・ケスラーの最新作『Icons』は6月25日リリース! 国内流通仕様盤CDには解説が封入され、他にも輸入盤CD、輸入盤LP(ブラック・ヴァイナル)、インディー限定盤LP(クリア・ヴァイナル)、デジタルと各種フォーマットでリリースされる。
label: LuckyMe
artist: Eli Keszler
title: Icons
release date: 2021/06/25 ON SALE
BEATINK.COM: https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=11877

tracklisting:
01. the Mornings in the World
02. God Over Money
03. The Accident
04. Daily Life
05. Rot Summer Smoothes
06. Dawn
07. Static Doesn’t Exist
08. Late Archaic
09. Civil Sunset
10. Evenfall
11. We sang a dirge, and you did not mourn
Eli Keszler Official Website
Facebook
Instagram
Twitter
Apple
Spotify


最新作『Magic Oneohtrix Point Never』が好評のワンオートリックス・ポイント・ネヴァーから、新曲 “Nothing’s Special” の到着です。どこまでも広がる交遊録、今回のコラボ相手は近年ポップ・シーンでぐいぐい名を上げている、バルセロナ出身の歌手ロザリア(ジェイムス・ブレイク『Assume Form』やアルカ『KiCk i』での客演が印象的でしたね)。同曲は『mOPN』最終曲 “Nothing’s Special” の更新されたヴァージョンで、また違った角度からアルバムの魅力を引き出してくれるような仕上がり。チェックしておきましょう。
ONEOHTRIX POINT NEVER & ROSALÍA
音楽シーンで異彩を放つ二つの才能
ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーと
ラテンポップの歌姫、ロザリアがコラボレート!
新曲 “NOTHING’S SPECIAL” を解禁!
2018年末、ラテンポップの歌姫、ロザリアが投稿したワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(OPN)とのスタジオ写真は、FADER や Rolling Stone などの海外メディアが取り上げるなど話題となり、音楽シーンで異彩を放つ二つの才能のコラボレーションに注目が集まった。
その後、2人のアーティストは、様々なプロジェクトで注目を集め、さらに大きな存在へとそれぞれ成長してきた。 2021年だけを見ても、OPN はザ・ウィークエンドと頻繁にコラボレーションを行っており、大きな話題を集めたスーパーボウルのハーフタイムショーでは音楽監督を務め、先週開催されたブリット・アワードでも共演。
The Weeknd - Save Your Tears (Live at The BRIT Awards 2021)
https://youtu.be/iKm5-XtXcII
現在次回作のレコーディング・セッション中というロザリアは、今年、すでに2つのコラボレーション・シングルをリリースしている。 ビリー・アイリッシュとの “Lo Vas A Olvidar” は世界的に称賛され、プエルトリコのバッド・バニーとの “La Noche de Anoche” は、リリース日にスペイン語の楽曲としては史上最多の再生数を記録し、ビルボードの「ラテン・エアプレイ」チャートで1位を獲得、米人気音楽番組「Saturday Night Live」でもパフォーマンスを披露した。
ますます異彩を放つ二つの才能がコラボレートした新曲 “Nothing’s Special” が本日新たに公開された。本楽曲は、高い評価を集めた OPN の最新作『Magic Oneohtrix Point Never』の本編ラストに収録されたものに、ロザリアがヴォーカルを提供し、OPN によって新たにアレンジを加えた曲となっている。

Oneohtrix Point Never & ROSALÍA - Nothing's Special
https://youtu.be/OX98ZrVoaGw
https://opn.ffm.to/nothings-special
TIME誌、Pitchfork、ele-king、 rockin'on など国内外の年間チャートに多数ランクインし、昨年最も評価の高い作品の一つとして挙げられている『Magic Oneohtrix Point Never』には、エグゼクティブ・プロデューサーも務めたザ・ウィークエンドが、“No Nightmares” でヴォーカル参加した他、アルカ、キャロライン・ポラチェク、ネイト・ボイス、ノーランベロリンらが参加。さらにシングル “Lost But Never Alone” のミュージックビデオは、映像作家のジョシュ・サフディとベニー・サフディが監督を務めている。OPN とサフディ兄弟は、長年に渡ってコラボ レーションを続けており、カンヌ映画祭で最優秀サウンドトラック賞を受賞した映画『グッド・タイム(原題:Good Time)』(2017)と『アンカット・ダイヤモンド(原題:Uncut Gems)』(2019)では、OPNが音楽を担当した。

label: BEAT RECORDS / WARP RECORDS
artist: Oneohtrix Point Never
title: Magic Oneohtrix Point Never
release date: 2020/10/30 FRI ON SALE
国内盤CD
国内盤特典:ボーナストラック追加収録/解説書封入
BRC-659 ¥2,200+税
国内盤CD+Tシャツ
BRC-659T ¥6,000+税
輸入盤CD WARPCD318
限定輸入盤2LP+DL WARPLP318Y (クリア・イエロー・ヴァイナル)
通常輸入盤2LP+DL WARPLP318 (ブラック・ヴァイナル)
BEATINK限定 輸入盤2LP+DL WARPLP318O (クリア・オレンジ・ヴァイナル)
BEAINK限定 カセットテープ WARPMC318
BEATINK.COM (CD/CD+T-Shirts/LP):
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=11445
BEATINK.COM (限定LP/カセット):
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=11446
Amazon
・国内盤CD (BRC-659): https://www.amazon.co.jp/dp/B08JYQ1YC1
・国内盤CD+Tシャツ
Sサイズ (BRC-659TS): https://www.amazon.co.jp/dp/B08JYX2LB6
Mサイズ (BRC-659TM): https://www.amazon.co.jp/dp/B08JYTDBW5
Lサイズ (BRC-659TL): https://www.amazon.co.jp/dp/B08JZ1VKP7
XLサイズ (BRC-659TXL): https://www.amazon.co.jp/dp/B08JZ3GWF5
Tower Records
・国内盤CD (BRC-659): https://tower.jp/item/5102397
・国内盤CD+Tシャツ
Sサイズ (BRC-659TS): https://tower.jp/item/5102399
Mサイズ (BRC-659TM): https://tower.jp/item/5102400
Lサイズ (BRC-659TL): https://tower.jp/item/5102403
XLサイズ (BRC-659TXL): https://tower.jp/item/5102460
HMV
・国内盤CD (BRC-659)
https://www.hmv.co.jp/product/detail/11242391
・国内盤CD+Tシャツ
Sサイズ (BRC-659TS)
https://www.hmv.co.jp/product/detail/11242392
Mサイズ (BRC-659TM)
https://www.hmv.co.jp/product/detail/11242393
Lサイズ (BRC-659TL)
https://www.hmv.co.jp/product/detail/11242394
XLサイズ (BRC-659TXL)
https://www.hmv.co.jp/product/detail/11242395

CD+Tシャツセット

限定クリア・イエロー・ヴァイナル

BEATINK.COM限定
クリア・オレンジ・ヴァイナル
TRACKLISTING
01. Cross Talk I
02. Auto & Allo
03. Long Road Home
04. Cross Talk II
05. I Don’t Love Me Anymore
06. Bow Ecco
07. The Whether Channel
08. No Nightmares
09. Cross Talk III
10. Tales From The Trash Stratum
11. Answering Machine
12. Imago
13. Cross Talk IV / Radio Lonelys
14. Lost But Never Alone
15. Shifting
16. Wave Idea
17. Nothing’s Special
18. Ambien1 (Bonus Track for Japan)
