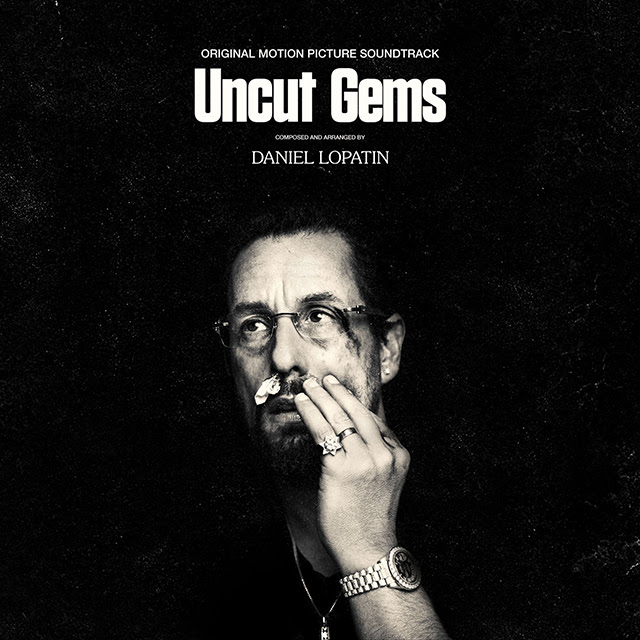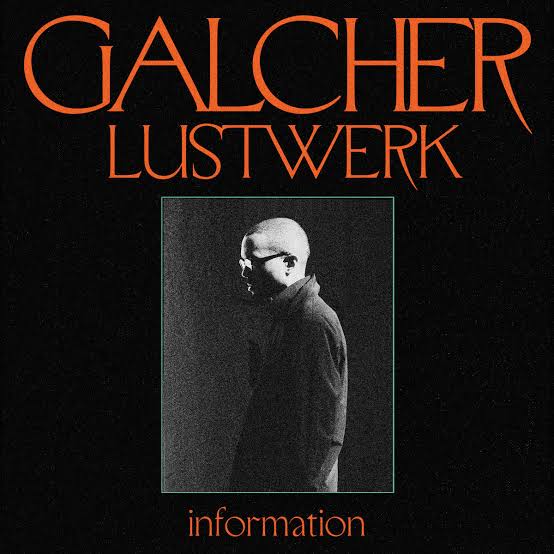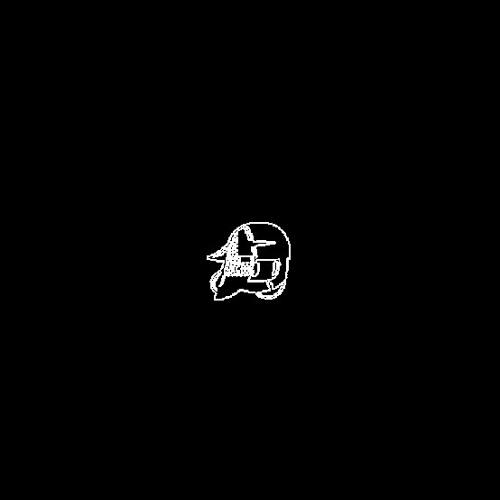アシッド・ジャズ以降、UKのジャズはヒップホップやハウスなどクラブ・サウンドと結びついてきて、ちょうどもはやそれは伝統と言えるものになっている。現在のサウス・ロンドンのジャズはそうした典型のひとつで、カマール・ウィリアムズのように最初はDJ/ビートメイカー方面からアプローチしていった者もいれば、シャバカ・ハッチングスやジョー・アーモン・ジョーンズのようにミュージシャンという立場からおこなっている者もいる。ブルー・ラブ・ビーツはそうしたジャズとクラブ・サウンドの交差点に位置するユニットで、プロデューサーでビートメイカーのNK-OKことナマリ・クワテンと、マルチ・インストゥルメンタル・プレイヤーのミスター・DMことデヴィッド・ムラクポルによる2人組。NK-OKの父親はアシッド・ジャズ時代にD・インフルエンスのメンバーとして活躍したミュージシャンで、近年はローラ・ムヴーラのマネージャーを務めるクワメ・クワテンである。
グライムやヒップホップにハマっていやNK-OKと、ジャズ・ミュージシャンとして大学で音楽を専攻してきたミスター・DMが出会い、2013年頃にブルー・ラブ・ビーツは結成された。北ロンドンを拠点とする彼らだが、北東ロンドンのトータル・リフレッシュメント・センターをホームグランドとし、南ロンドンのミュージシャンたちとも交流が深い。2016年の初リリース作の「ブルー・スカイズEP」、2017年のセカンドEPの「フリーダム」、そしてファースト・アルバムの『クロスオーヴァー(Xover)』にはモーゼス・ボイド、ヌビア・ガルシアおよびネリヤ、ジョー・アーモン・ジョーンズやエズラ・コレクティヴの面々、アシュリー・ヘンリー、ダニエル・カシミール、ドミニック・キャニング、カイディ・アキニビ、シーラ・モーリス・グレイはじめココロコのメンバーなど多数のミュージシャンが参加する。
また『クロスオーヴァー』にはラッパーやシンガーもいろいろフィーチャーされており、ロバート・グラスパーやサンダーキャット、テラス・マーティンなどに対するUKからの回答とでも言うような作品になっていた。ジャズとヒップホップやR&Bの融合から、AORやファンク、シンセ・ブギー調の作品、カリビアン・ジャズやボッサ・ジャズ、グライムやブロークンビーツ、フットワークを取り入れた作品とヴァラエティに富み、ジャズを媒介にさまざまな音楽を融合したアルバムと言えるだろう。そうしたバランス感覚や編集者的感覚に富むところは、ミュージシャンのバンドと言うよりDJ/プロデューサーが介在するプロジェクトであり、タイプとしてはジョー・アーモン・ジョーンズとマックスウェル・オーウィンが『イディオム』でやっていたことに近いが、全体的にヒップホップの影響が強い。2019年に入ると、セオ・クロカーやジョディ・アバカスらが参加したEP「ヴァイブ・セントラル」をリリースしたほか、オーストラリアのサンパ・ザ・グレートのアルバム『ザ・リターン』にも参加しており、そして2枚目のアルバムとなる『ヴォヤージ』も完成させた。
『ヴォヤージ』にはそのサンパ・ザ・グレートも参加していて、主なミュージシャンではカイディ・アキニビやシーラ・モーリス・グレイが目につくものの、『クロスオーヴァー』に比べてゲスト・プレイヤーは少ない。そのぶんミスター・DMの演奏の比重が増したのだろう。一方フィーチャリング・シンガーは多めで、ロンドンの若手ラッパーやシンガーがいろいろ参加している。『クロスオーヴァー』でもそうだったが、日頃からトータル・リフレッシュメント・センターなどでよくセッションする同世代の仲間が集まって録音したアルバムである。
スペイシーなイントロダクションに始まり、NK-OKの編み出すビートにミスター・DMのキーボードとギターが絡むエレクトロ・ジャズ・ファンクの“ハイ・ゼア”が、ブルー・ラブ・ビーツの基本形となるふたりのみの演奏。“オーシャン”“メモリーズ”“ノン・オブ・ザット”などもそうしたスタイルの演奏だが、特に“メモリーズ”に見られるようにヒップホップのビート感がブルー・ラブ・ビーツの根幹にあるようだ。タイトル曲の“ヴォヤージ”はそこにカイディ・アキニビのサックスが加わり、ギター・ソロと一緒にブロークンビーツを交えたジャズ・ファンク調の演奏を繰り広げる。いかにもブルー・ラブ・ビーツらしいジャズとクラブ・サウンドの融合を見せる曲だ。
サンパ・ザ・グレートがファニーな歌声を披露する“ネクスト(ウェイク・アップ)”、キンカイのラップがフィーチャーされた“ギャラクティック・ファンク”、さまざまなラッパーがマイク・リレーをとる“ワト・R・U・ヒア・フォー?”、サフロン・グレースが歌うネオ・ソウル調の“オン・アンド・オン”や“セカンド・ソウト”、DT・ソウルのヴォコーダーをフィーチャーした“ギャラクト・インフェルノ”はヒップホップ/R&B、もしくはソウル/ファンクを下敷きとした作品。
一方、カイディ・アキニビやシーラ・モーリス・グレイが参加した“スタンド・アップ”はアフロ・ビートで、エズラ・コレクティヴあたりに共通するタイプの演奏。ラテン・テイストの“キューバ・リブレ”やデミマがアフリカの言葉で歌う“ウモヤ”など、アフリカ~カリビアンの要素を取り入れるのもロンドンらしいアプローチだ。昨今はトム・ミッシュ、ロイル・カーナー、ジョーダン・ラカイ、ジョルジャ・スミス、エゴ・エラ・メイなどシンガー・ソングライターやラッパーとジャズ・ミュージシャンのコラボが盛んだが、ブルー・ラブ・ビーツのサウンドもそうしたいまのロンドンの新しい世代を代表するもののひとつだ。