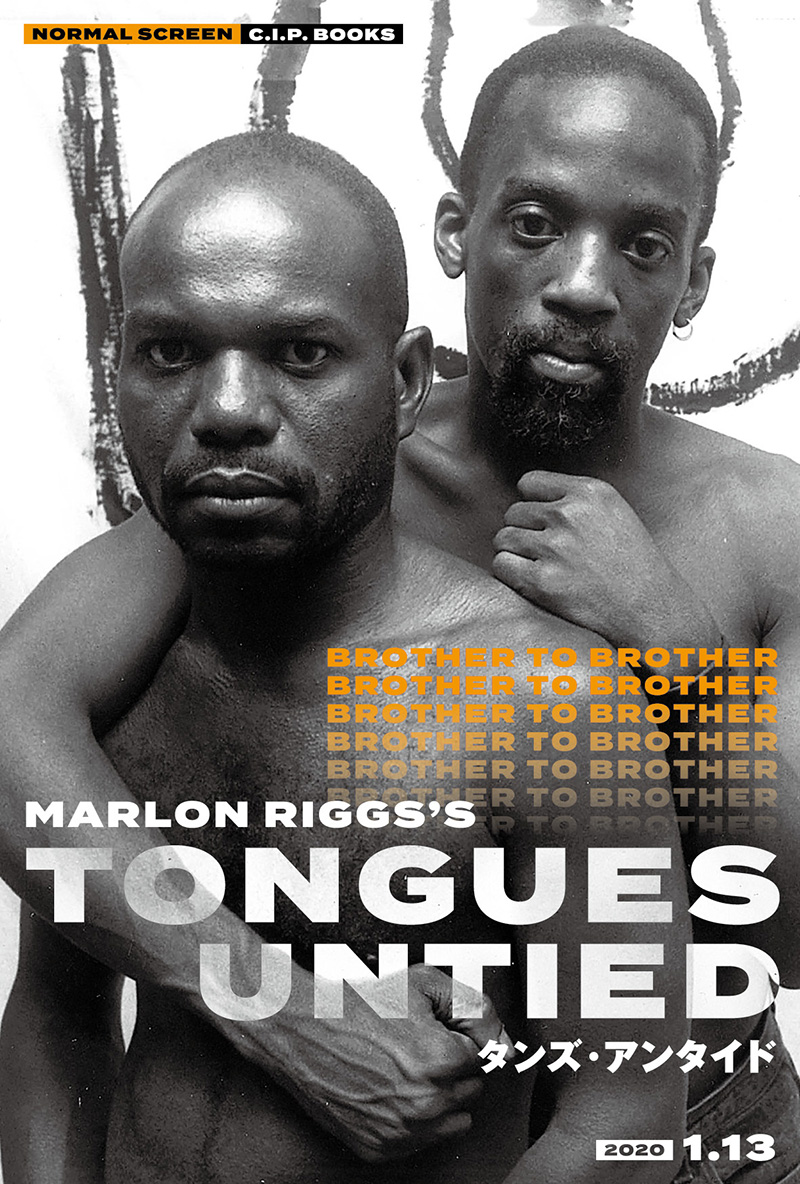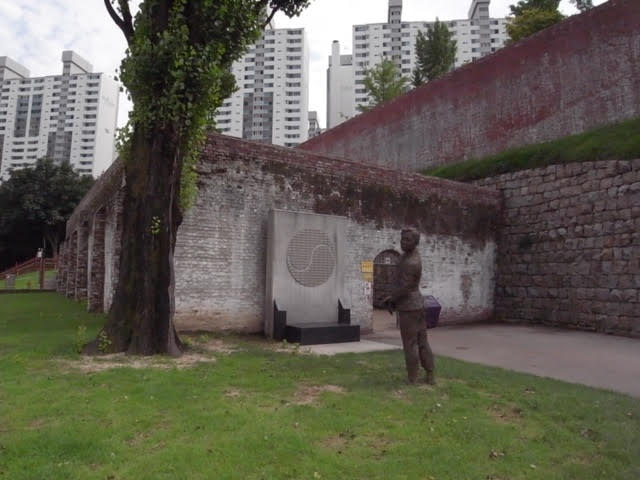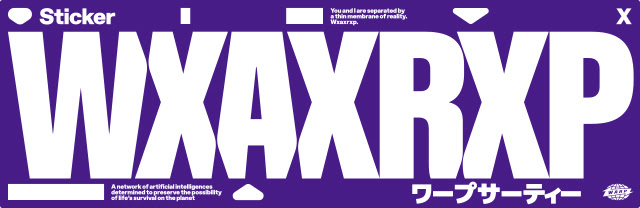世界は熱くなっているというのに、イギリスは冷えている──保守党の党色である青に塗られたイギリスの地図を見てそう思わずにいられなかった。総選挙ショックから1週間後、ボリス・ジョンソン英首相は議会演説で自身の率いる政権を「イギリスの新たな黄金時代の始まり」とブチ上げた。
この選挙の保守党の主要スローガンは「Get Brexit done(ブレクジットを済ませよう/片をつけよう)」。その通り、保守党が圧倒的な過半数を占める新議会はイギリスが後戻りするルートを早々と断ち切った。泣いても笑っても2020年1月31日午後11時にブレクジットが起きる。2016年の国民投票から3年半以上、離脱賛成派は求めてきたものをやっと手に入れる。
クリスマス休暇や師走のあれこれに紛れ、複雑な交渉/外交のディテールはしばし厚いカーテンの向こうに追いやられている──「ブレクジットはややこしいから、もう国民の皆さんをわずらわせません。後は我々政治のプロにお任せください」とばかりに。ジョンソンは選挙キャンペーン中に「ブレクジットはもう準備が整っていて、オーヴンに入れさえすれば出来上がり」(日本的に言えば「レンジでチン!」ですね)というレトリックを使っていたが、いったいどんな料理が出て来るのやら。
ブレクジットが最終的にどんな形に収まるのか、実はまだ誰にも分かっていない。交渉はこれから本格化するし、入り混じる楽観/悲観双方の予測、どちらを信じるかはその人間次第。1月31日という日付はある意味象徴的なもので、そこから離脱プロセスの完了まで11ヶ月間の交渉&準備&推移期間が置かれている。しかしジョンソンはその準備期間の延長を断固はねつける姿勢で、最悪のシナリオ=「Hard Brexit(合意無しの離脱)」も再浮上している。北アイルランドの立場やスコットランド独立気運の再燃も始め見通しの立ちにくい状況は続くだろうし、英音楽界への影響も当然のごとく不安視されている。
本来ブレクジットが起こるはずだった昨年3月末を前に『New Statesman』誌が掲載した記事(「The Lazarus Effect」by Andrew Harrison)に、2016年の国民投票時に〈ミュート〉のヘッドであるダニエル・ミラーがスタッフを集め「どう投票するか指図するつもりはないが、離脱賛成に投票した人間はカルネの記入をやってくれないと」と言った、との逸話があった。カルネはかつてミュージシャンがツアーする際に提出を求められた、各国間を移動する物品(楽器、各種機材、ケーブル1本1本に至る仕事道具)を逐一記入する面倒な書類。EU単一市場圏から離脱すると関税同盟から除外扱いになるのでこのカルネが復活し、ツアーのハンデが増える可能性を覚悟せよ、という含みのある発言だ。
人気アクトには煩雑な法手続きをこなす専門家を雇う経済的余裕があるだろう。だがインディな若手や自腹でツアーしている面々に、書類記入や入国許可他の手続き・コストが増えかねないこの状況はきつい。作品を発表しライヴでプロモートするという伝統的なスタイルが逆転し、音源よりもチケット代やツアー・マーチャン販売が重要な収入源にシフトした昨今であれば尚更だ。アメリカのアーティストはヴァンに乗って広い自国内をDIYツアーすることが可能だが、小さな島国イギリス出身のアクトにとって目の前に広がる欧州大陸は遠くなるかもしれない(逆に、欧州勢がイギリスを敬遠する可能性も指摘されている)。
CD・アナログ盤の価格上昇も予想される。英国内で流通するフィジカル・メディアの多くはEUでプレスされており、特にヴァイナルは(ビスポークなスペシャル版やダブ・プレートといった小規模生産を除き)チェコやポーランドの工場で生産されるケースがほとんど。過去数年の「アナログ人気復活」は英音楽業界の朗報のひとつだが、大手ショップのアナログ・セクションも、実はヘリテージ・アクトの名盤再発、ヒット作が支えている。ビートルズやストーンズ、オアシスやエイミー・ワインハウスの旧カタログの方がインディ・レーベル作品よりも恐らく確実に売れている。
ゆえにメジャー・レーベルにはまとまったプレス枚数の注文をかけ続ける「腕力」があるが、新人バンドのデビュー作や12インチといった地味なアイテムはそのしわ寄せで後回しになりがち。この影響はブレクジットに関わりなく既に存在してきたとはいえ、アマゾンのように巨大なストックを抱えられない、わずかなマージンと専門的な品揃えで踏ん張っているインディのレコード店にとって倉庫・流通網の安定とグッズのスムーズな移動を妨げかねないブレクジットは遠くからゆっくり迫って来る暗雲のようなものだろう。
サブスクリプションやネット・ベースの諸アウトレットの浸透で音楽を聴く手段そのものは増え、2019年の英音楽産業は2006年以来の高収益を記録した。だが新作アルバムのCD価格が現在8〜12ポンド、アナログは20〜24ポンド程度であるのに対し、1曲を1回ストリームして生じる実益は0.006ドルから0.0084ドルと言われる(これをレーベル、プロデューサー、アーティスト、音楽出版社、作曲家で分け合う)。ストリームのペイは多くのアーティストにとっていまだ雀の涙だ。
音楽業界ももちろん黙ってはおらず、政府審議会にミュージシャンを送り込んで現状を訴える等の活動がおこなわれている。だがボリス・ジョンソンの組閣が発表され、ディジタル・カルチャー・メディア・スポーツ部門大臣(Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport)は誰かと思ったら、総選挙前に「ジョンソン政権には入らない」と大見得を切って議員辞職したものの、ドサクサに紛れて返り咲いたニッキー・モーガンだった。「女性閣僚の数を増やして体裁を整えたかっただけ?」と斜に構えたくもなる、胡散臭い選任だ。
過去に同性愛結婚に反対し、宗教教育の自由に意義を唱えたこともあるコンサバである彼女がプロ・アクティヴに文化行政に取り組むとはちょっと考えにくい。ジョンソン内閣はブレクジット後の音楽やカルチャーに対して「なるようになる」の受け身な姿勢を取りそうな気配。逆に言えば、億産業である英カルチャー・セクターにはまだ充分に余力があるから助け舟を出さなくても大丈夫、ということかもしれない。

救済措置を急務とする課題は国民医療サーヴィス、住宅難等他にいくらでもあるし、そもそも文化のことなどよく分かっていない政治家に妙に介入されてもうざったいだけ。悲観的な見方をあれこれ並べてきたが、人種や世代やイデオロギーといった壁も越えて響き届くのが音楽の強さなのだし、イギリス音楽界は過去にもしぶとくバウンスバックしてきた。ディジタル・プラットフォームはDIYな活動の幅を広げたし、映画・CM他とのシンクロやブランドとのコラボといった機会も増えている。音楽界のクリエイターたちが貧すれば鈍する、とは限らない。
そんなディジタル時代のモダンなアーティスト成功例のひとつがグライムのスーパースター:ストームジーだ。ソーシャル・メディアを通じてファン・ベースを築き、クラブ・ファッション・映画他多彩なチャンネルを活用、メジャー〈アトランティック〉と合弁事業の形(通常の「契約」ではない)で発表したデビュー・アルバムで英チャート首位を達成。セカンド発表前にグラストンベリー2019のピラミッド・ステージでトリ──ブラック・ブリティッシュのソロ・アクトでは初──の快挙を成し遂げた#Merky(愛称・キャッチフレーズであり、彼自身のレーベル/フェス/出版社の名称でもある)は、黒人学生向けのケンブリッジ大奨学金を設ける等、敬愛するジェイ–Z型のアイコンへと成長しつつある。
彼や仲間のミュージシャンたちが総選挙前にジェレミー・コービン/労働党支持を表明し投票を促したのは、今回初投票した若者も含む18〜24歳層に大きく影響したと言われる(他にリトル・ミックスのメンバーやデュア・リパも労働党支持を表明)。俳優スティーヴ・クーガンを筆頭に音楽界からはケイノー、ブライアン・イーノ、マッシヴ・アタック、ロビン・リンボー、ケイト・テンペスト、ロジャー・ウォーターズ、クリーン・バンディッツが連名署名したコービンのマニフェストを支持する文化人集団の公開書状もそれに続き、イーノは総選挙直前に風刺曲“Everything’s On The Up With The Tories”を発表した。しかし大ヒット曲“Vossi Bop”で「Fuck the government and fuck Boris」と歌い、数多い若者の命を奪っているナイフ刺殺事件への怒りをこめてバンクシー作のユニオン・ジャック柄防護ベスト姿でグラストンベリーに登場した26歳のストームジーこそ、これからの世代の不満や不安をヴィヴィッドに反映している。

『ガーディアン』の日曜版『ジ・オブザーヴァー』紙は、選挙結果が出そろった2日後=12月15日付の付録文化誌『オブザーヴァー・マガジン』の責任編集をストームジーに任せた。労働党が勝利していれば、この号の意味合いは更に感動的だっただろうが──残念ながら現実はそういかなかった。実にほろ苦い。
選挙結果の分析はプロの政治評論家やジャーナリストに任せるべきだろう。しかしひとつ言えるのは、労働党や「反ブレクジット」を掲げた自由民主党(Liberal Democrats)が議席を獲得したエリアの多くはロンドン圏、および大学があり学生&若者人口率の高いブリストル、マンチェスター/リヴァプール、ニューカッスル等の都市部である点。これらの選挙区は伝統的に左派傾向が強いので不思議はないが、そのコアなメトロポリス部を囲む郊外やカントリー・サイド──特に、過疎化と老化・衰退の進む「取り残されてきた」北部地帯は長年の労働党信仰を捨て、保守党候補に票を投じた。18〜24歳代層の左派支持と60歳以上層の右派支持とは、鏡と言っていいくらい見事に逆になっている。
「田舎の年寄りは愚かだ」型の単純な話ではない。サッチャーに炭鉱を閉鎖され生活基盤やコミュニティを失った恨みを忘れていないこの世代が保守党に転じたのは重い決断だし、それだけ彼らは逼迫している。2008年の世界金融危機、緊縮政策に苦しみながらも労働党に希望を託し続け、それでも状況が改善しないことに失望した彼らは、その不満の表明としてオルタナティヴ=保守党とブレクジットに賭けてみることにしたのではないか。金持ちへの重税、無料ブロードバンド全国普及といった項目を含むコービンの利他的なマニフェストは「ユートピアン」、「ラディカル過ぎ」と批判されたが、このいわば理想の追求=体力も根気もいる遠いゴールよりも、衣食住・医療・治安の日常的な問題に追われる人々は──ナショナリズムや人種差別といったポピュリズムの常套甘言に乗せられた面もあるだろうが──応急処置を選んだことになる。
労働党の地方労働者階級支持基盤が崩れ、イギリスの伝統的な「豊かで保守右派の南VS貧しく労働党左派の北」のパラダイムが逆転した2019年総選挙は地殻変動だった。焦点のひとつはブレクジットで「実質的に第二の国民投票」の印象すらあったが、獲得議席数ではなく投票数でカウントすれば、実はEU残留(=再度の投票を求める声からブレクジット帳消しまで様々だが、トータルで言えば離脱阻止の可能性を探る方針)を主張する諸党への支持票が保守党票を上回ったのだ。その民意は政党政治の前に掻き消えたことになる。この厳しい教訓を野党勢が重く受け止め内省し、それぞれが政党としてのアイデンティティを立て直さない限り、国民との乖離はますます広がるだろう。
一方で、今回ブレクジットという博打に賭けてボリス・ジョンソンに追い風を送った層である、英中部/北部に対する保守党の責任も重い。南北格差の大きい公的資金配分システムを改造する動きも既に出ているそうだが、くも野郎(Boris the Spider)ならぬ嘘つき(Liar)で、前言撤回・有言不実行・不正確なデータ拡散の数々で知られるジョンソンだけに見張り(ウォッチ)を怠ることはできない──「北は忘れない(North remembers)」と思ってしまうのは、まあ、『ゲーム・オブ・スローンズ』の観過ぎかもですが。
少なくともこの先5年は保証されたジョンソン政権の「黄金時代」。その暗い現実にストームジーを始め多くのミュージシャンが落胆を表明したし、フォー・テットがBBCのポッドキャスト「100 Voice Notes About The Election」(選挙結果に対する若者100人の声)向けに音楽を提供する等、リアクションはこれからも様々な形で現れてくると思う。音楽ファンの中からは「ジャーヴィス・コッカーを2019年のクリスマス・ナンバー・ワンに」というSNSベースの愉快なプチ運動が生まれた。
ダウンロードやストリーミングで古い曲が復活しチャート・インしやすくなったことで、2009年に「レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンの“Killing In The Name”を1位に」の草の根運動が成功した。タレント発掘番組『Xファクター』勝者のシングルがクリスマス週にチャート1位になる……という、当時のイギリスで定番だった出来レースにウンザリしていた音楽ファンによる冗談/真剣半々のサボタージュ兼プロテストだった。その後も同様のアクションは折に触れて起きていたが、このジャーヴィス1位運動の発起人は、総選挙の悲惨な結果に落ち込みつつ、しかし少しでも左派への団結心をユーモラスに表明したい人々のためにこのフェイスブック・グループを立ち上げたという。
選ばれた曲はジャーヴィス・コッカーのデビュー・ソロ『Jarvis』(2006)に隠しトラックとして収録された風刺曲“Running The World”。ミソになるコーラス部の歌詞は以下。
If you thought things had changed, friend,
you’d better think again
Bluntly put, in the fewest of words,
cunts are still running the worldもしも事態は変化したなんて思っているのなら、友よ、
考え直した方がいい
手加減なしで、単刀直入に言わせてもらおう、
いまだにこの世を回しているのはムカつかされるくそったれ共だと
「cunt」は恐らくイギリスでもっとも熾烈な罵倒語のひとつ(くれぐれも安易に使わないように!)なので1位はまずあり得なかったとはいえ──この曲を爆音で流して2019年にわずかでもうっぷん晴らししたい人々の気持ちは理解できる。結果はチャート48位で、ジャーヴィスと〈ラフ・トレード〉は収益をホームレス支援団体に寄付した。
この曲はアルフォンソ・クアロンのディストピア映画の傑作『トゥモロー・ワールド』のエンディングで、ジョン・レノンの“Bring On The Lucie”に続いて流れたことでも知られる。筆者はクリスマス期になるとついDVDで観返してしまうのだが、13年も前の作品なのにいまだ現在とシンクロする面があることに改めて打たれつつ──今回の観賞はヘヴィだった。と同時に、究極的には希望と人間のオプティミズムを描いている『トゥモロー・ワールド』に励まされもした。“Running The World”は近年のジャーヴィスのライヴでもよく歌われる定番曲だが、ライヴで歌う際に彼は前述の歌詞の後にひと言付け加えるようにしているそうだ──「but not for long(でもそれも長くは続かない)」と。