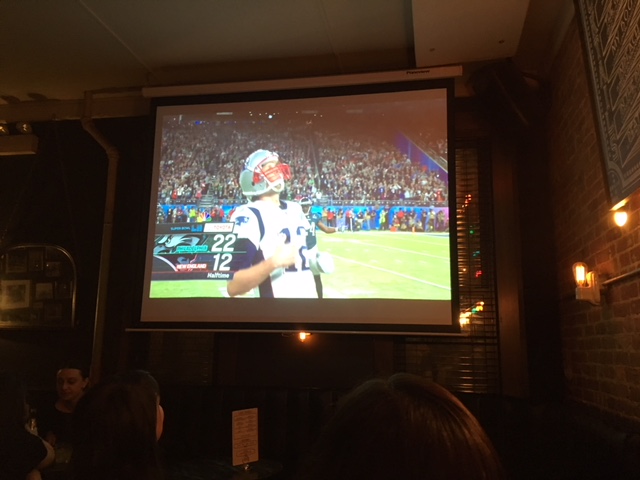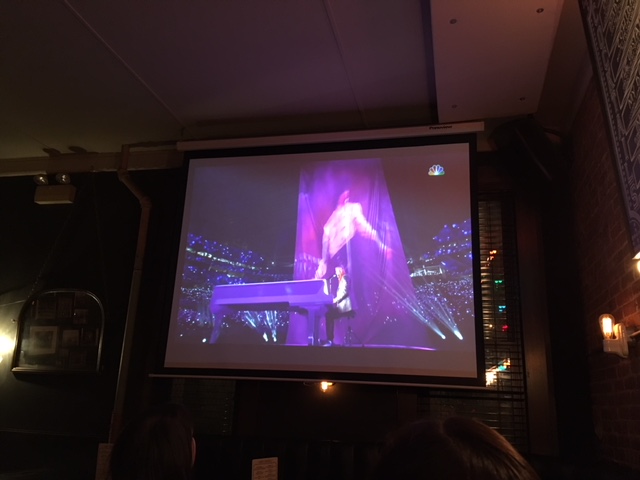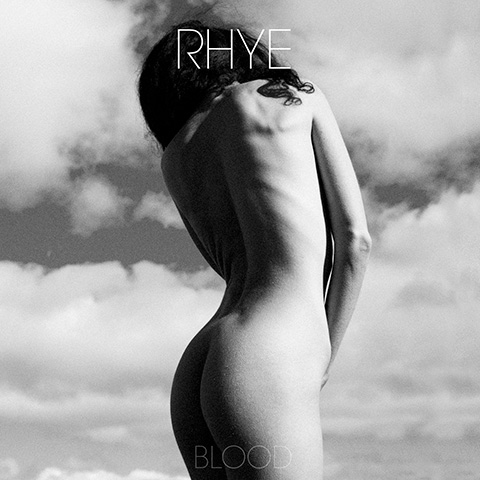続報が届きました。ヤイエルが3月7日リリースのセカンド・アルバム『Human』から新曲“Pale”を解禁、MVも公開されています。一見静かで落ち着いた曲に聞こえますが、後ろのほうで色々とおもしろいことが起こっています。ビデオも独特の雰囲気を醸し出していて、ますますアルバムへの期待が高まります。あわせて全国ツアーの詳細も発表されていますので、下記よりチェック。
ヤイエル、待望のセカンド・アルバム『Human』から
新曲“Pale”をミュージック・ビデオとともに解禁!
初となるレコ発ツアーのチケット一般発売は明日から!
新たに仙台公演も決定!

デビュー・アルバム『Flesh and Blood』たった一作で、コアな音楽愛好家たちを超えて同世代のリスナーへと鮮烈なインパクトを与え、一気に評価と信頼を勝ち得たyahyelが、3月7日(水)にリリースされる待望のセカンド・アルバム『Human』から、新曲“Pale”を解禁! 映像作家としても注目を集めるメンバー、山田健人が手がけたミュージック・ビデオには、ヴォーカルを務める池貝峻が出演している。
Pale (MV)
https://www.youtube.com/watch?v=sQexBpZDC7s
Apple Music: https://apple.co/2semWms
Spotify: https://spoti.fi/2nNsxL5
本作『Human』には、昨年リリースされたシングル“Iron”と“Rude”、韓国の気鋭のラッパー・Kim Ximya(キム・シムヤ)をフィーチャリング・ゲストに迎えた“Polytheism”など全10曲が収録される。また初回限定盤CDは、ボーナスディスク付きの2枚組となり、アナログ盤にはDLカードを封入。iTunesでアルバムを予約すると“Iron”と“Rude”、そして新たに公開された“Pale”の3曲がいちはやくダウンロードできる。
3月29日(木)の東京公演を皮切りにスタートする初のレコ発ツアーには、新たに仙台が決定! いよいよ明日からチケット一般発売がスタート!
yahyel
- Human Tour -

2016年12月に渋谷WWWにて行われたワンマンは、デビュー・アルバム『Flesh and Blood』の発売日を前に完売。その後も、FUJI ROCK、VIVA LA ROCK、TAICOCLUBなどの音楽フェスへの出演も果たし、ウォーペイント(Warpaint)、マウント・キンビー(MountKimbie)、アルト・ジェイ(alt-J)ら海外アーティストの来日ツアーでサポート・アクトにも抜擢されるなど、活況を迎えるシーンの中で、独特の輝きを放ち続けたyahyel(ヤイエル)が、1年3カ月の時を経て、2度目のワンマン・ライヴ、そしてレコ発ツアーが決定!
3/29 (THU) 東京 LIQUIDROOM
OPEN 19:00 / START 19:30
前売 ¥3,500(税込/1ドリンク別途)
INFO: BEATINK 03-5768-1277 www.beatink.com
チケット一般発売:2月7日(水)~
e+ (https://eplus.jp)、LAWSON (L: 70818)、ぴあ (P: 106-598)、BEATINK (www.beatink.com)
3/31 (SAT) 京都 METRO
OPEN 18:00 / START 18:30
前売 ¥3,500(税込/1ドリンク別途)
INFO: 京都 METRO 075-752-4765 https://www.metro.ne.jp
チケット一般発売:2月7日(水)~
e+ (https://eplus.jp)、LAWSON (L: 54039)、ぴあ (P: 106-352)
4/5 (Thu) 札幌 DUCE
OPEN 19:00 / START 19:30
前売 ¥3,500(税込/1ドリンク別途)
INFO: WESS 011-614-9999 https://www.wess.jp
チケット一般発売:2月7日(水)~
e+ (https://eplus.jp)、LAWSON (L: 12377)、ぴあ (P: 106-213)、TOWER RECORDS札幌PIVOT
4/6 (FRI) 名古屋 RAD HALL
OPEN 19:00 / START 19:30
前売 ¥3,500(税込/1ドリンク別途)
INFO: JAILHOUSE 052-936-6041 www.jailhouse.jp
チケット一般発売:2月7日(水)~
e+ (https://eplus.jp)、LAWSON (L: 42435)、ぴあ (P: 106-622)
4/7 (SAT) 大阪 "RETURN" なんばハッチ
OPEN 17:00 / START18:00
前売 ¥4,800(税込/1ドリンク別途)
INFO: SMASH WEST 06-6535-5569 https://smash-jpn.com https://smash-mobile.com
チケット一般発売:2月17日(土)~
チケットぴあ (P: 106-665)、ローソンチケット (L: 53922)、e+ (pre: 2/8-12)、iFLYER、Resident Advisor、FLAKE RECORDS、PARALLAX RECORDS、PALETTE art alive
4/8 (SUN) 高知 CARAVAN SARY
GUESTS: SummAny 他
OPEN 18:30 / START 19:00
前売 ¥3,000(税込/1ドリンク別途)
INFO: 088-873-1533 www.caravansary.jp/sary/topsary.htm
チケット一般発売:2/5(月)~
CARAVAN SARY店頭、ぴあ (P: 107-135)、LAWSON (L: 61395)、DUKE TICKET
4/11 (WED) 仙台 DARWIN
OPEN 19:00 / START 19:30
前売 ¥3,500(税込/1ドリンク別途)
INFO: ニュース・プロモーション 022-266-7555 (平日11:00~18:00)
★イープラス最速先行受付(抽選):2/6 (火) 18:00~2/12 (月) 23:59
チケット一般発売:2/24 (土) 10:00~
e+ (https://eplus.jp)、LAWSON (L: 22105)、ぴあ (P: 108-509)、タワーレコード仙台パルコ店

label: Beat Records
artist: yahyel
title: Human
release date: 2018.03.07 wed ON SALE
初回限定盤2CD BRC-567LTD ¥2,800+税
国内盤CD BRC-567 ¥2,300+税
国内盤LP+DL BRLP567 ¥3,000+税
【ご予約はこちら】
beatink: https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=9264
amazon
BRC567LTD: https://amzn.asia/hypOdKG
BRC567: https://amzn.asia/1P9YGdB
Tower Records
BRC567LTD: https://tower.jp/item/4673332/
BRC567: https://tower.jp/item/4673334/
HMV
BRC567LTD: https://bit.ly/2BWRM2D
BRC567: https://bit.ly/2Ej4MF6
2016年11月にリリースされ、コアな音楽愛好家たちを超えて同世代のリスナーへと鮮烈なインパクトを与え、一気にそのプロップスを引き上げたデビュー・アルバム『Flesh and Blood』。2010年代以降のR&Bと電子音楽のリアリティーすなわちジェイムス・ブレイクやフランク・オーシャン以降のオルタナティヴR&Bと、フライング・ロータスやアルカ、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー以降のエレクトロニック・ミュージックに対するリアルな共鳴を、今この世界で生きる自分たち自身が抱く違和感/思想をもってユニークな音楽表現へと昇華する存在として、たった一作で評価と信頼を勝ち得たのがyahyelだった。そんな彼らが自身のアイデンティティを突き詰め、よりクリアで強固なものとして具現化することに挑んだのが、今回リリースされるセカンド・アルバム『Human』だ。
以前の匿名性の強いアーティスト写真にも表れていた通り、結成~『Flesh and Blood』期のyahyelは、人種・国籍・性別といった、エスニシティをはじめ様々な個にまとわりつく付帯情報を削ぎ落とすこと=雑音を削除することによって、逆説的に、“出自による差異と先入観に縛られた社会”から純粋なる“個の存在”、“個の感情”を浮かび上がらせようという意識をもって音楽活動を行っていた。対して今回は、『Flesh and Blood』から『Human』へというアルバム・タイトルの変化にも表れている通り、そんな彼らの本来の目的にして本質と言っていい“個が有する生々しい感情とメッセージの発露”をダイレクトに際立たせる方向へと舵を切っている。
具体的には、それを実現するため、本作に関しては「ヴォーカリストである池貝峻の感情表現に寄り添うように突き詰める」、「池貝という人間の感情と生き方をどれだけ際立たせることができるのか? に重きを置く」ことを明確に制作の軸としたという。さらにはその過程で5人――池貝峻、篠田ミル、杉本亘、大井一彌、山田健人の互いの感覚の擦り合わせと音に対する思想/イメージの落とし込みをストイックに行っていった。世界のミュージック・シーンの文脈やトレンドと照らし合わせた相対的な解ではなく、5人の中における絶対的な解をひたすらに探す作業。結果、「自分たちの予測を超えた、ある種、自分たち自身の制御も超えた地点へと到達するアルバムとなった」と彼らが話す通り、歌はもちろん、音色にしてもリズムにしても前作以上にエグみも深みもある、美しく豊かな感情表現が息づく作品となった。格段に重層的に作り込まれ、織り込まれたひとつひとつの音のテクスチャー、アブストラクトなビートも多分に含んだリズムトラックの深化といったもの自体から、彼ら5人にしか生み出し得ない確かなオリジナ リティを感じることができる。