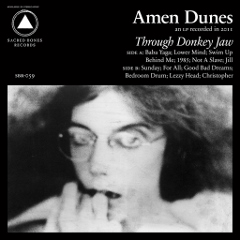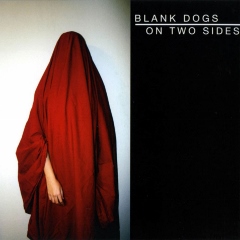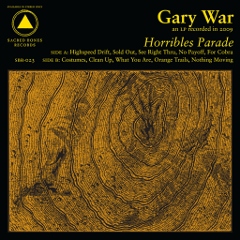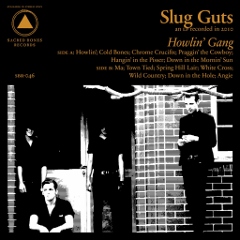Tomggg Butter Sugar Cream【初回限定お菓子の箱盤】 Faded Audio |
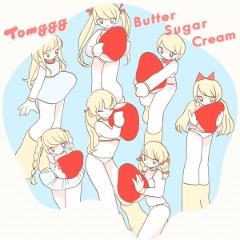 Tomggg Butter Sugar Cream【通常盤】 Faded Audio |
音楽をつくる仲間たちがスカイプを通じて集まってきて、互いの音を聴かせあったり、作業工程を見せ合ったり、他愛ない話をしたりというコミュニケーションは、インターネットの黎明期にあっては夢のひとつだったのかもしれないけれど、いまではそうしたことを当たりまえのようにできる環境が、次々と次代のプロデューサーたちを育んでいる。インタヴューの最後になってほほえましく語られた、彼らのささやかな音楽コミュニティの話をきいたとき、日本ではなかなか根づきにくいとされるUSのインディ音楽カルチャーのスタイルが重なってみえるような気がした。友だちの家でライヴをやる、いつでもやる、仕事や生活と両立してやる、音楽やそのアーティストに興味がなくとも親密な場所であればいっしょに楽しむ……芸能としてしか音楽の活動場所を築きにくい日本ではなかなか難しいけれど、そうした生活レベルの楽しみ方も音楽の尊いあり方のひとつだ。モニター越しではあるが、ネット環境の飛躍的な進化とともにそれは思いのほか一般化されているといえるのではないか──。
Tomgggといえば、歴史的なネット・レーベル〈maltine(マルチネ)〉からのリリースや、kazami suzukiのイラストのインパクト(サンリオと吾妻ひでおのハイブリッドだそうな……)、ラブリーサマーちゃんや禁断の多数決などのリミックス仕事も相俟ってか、ネットを主なステージとして、オタク、機材系ギーク、サブカル、ポップ・シーンをスタイリッシュに縫合する、時代性にあふれた若手プロデューサーのひとり……といったイメージを勝手に抱いていたが、今回話をきいて、案外本質はそんなところにないのかもしれないという気持ちがした。 いやいや、そうした印象が事実であることもたしかだと思うけれど、それだけではただわれわれが時代を人格化するのに適した一体のハイプを見つけだしたというに過ぎない。彼がもっと素朴に音楽行為を愛好するカルチャーの末端にいるということ、「アタマ10秒でつかまないと生き残れない」などという世知辛いプロデューサー意識と同時に、たとえそれが売れようが売れまいが、確実に音楽が生きることを楽しむためのきっかけになっているということに、格別な親しみを覚える。初の全国流通盤となる今作EPが「お菓子」をひとつのコンセプトとするものであり、それを自身が「生きていく上で絶対必要なごはん……以外の食べ物」として音楽と結びつけて語るのは、だから、不必要・不健康なもの、奢侈といった自滅自嘲的な意味ではけっしてなくて、生きる主体として必要な栄養だという認識からだろう。表題曲“Butter Sugar Cream”は音の言葉のカロリーや凝り方のわりには存外素直な、そして素直すぎるよろこびの表現なのだ。
※インタヴューのラストでティーザー音源をお聴きいただけます
■Tomggg / トムグググ
1988年生まれ、千葉を拠点とするプロデューサー。公募型コンピレーション「FOGPAK」や自身のsoundcloudなどインターネットを中心に作品を発表、これまでのリリースに〈Maltine Records〉からのEP『Popteen』がある。2014年は禁断の多数決やラブリーサマーちゃん、Porter Robinsonのリミックスなどを手掛け、カナダのトラックメイカーRyan Hemsworthとの楽曲制作も話題になった。2015年3月〈Faded Audio〉より『Butter Sugar Cream』を発表。
すごく強く、音楽では食えないという思いがあったもので──いまもですが。
■音大を出ていらっしゃるんですよね?
Tomggg(以下、T):そうなんです。
■しかも、国立音大ってかなりガチだと思うんですが。
T:ガチで、しかも作曲を学んでいたという──(笑)
■そうそう(笑)、作曲科なんですよね。それっていったい、どういう動機で何を目指して入る学科なのかなって。
T:そうですね、専門がコンピュータ音楽ってもので、アカデミックなほうのコンピュータ音楽になるんですが。具体的に言えばMax/MSP(マックス・エムエスピー)やらマルチ・チャンネルのスピーカーやらを使って、サウンド・プログラミングを行ったりしていました。もともとの入学の動機は、作曲もしつつ、そこの学科では録音とかPAとかっていうエンジニアリングもやっていたので、そういうことを学べたらいいなということだったんです。
■エンジニアリング。ではゆくゆくは何か、音楽に関わる仕事をしたいなという気持ちがあったわけですか。あるいは、職業作曲家として?
T:作曲家……というほどのことを思っていたわけではなくて、もうちょっと裏方のことでしょうか。
■へえー。16、17歳くらいの年ごろの少年の夢というと、裏方というよりは、ギターを手に、もっと前に出て行ってやるんだっていうほうが順当なような感じもしますけど(笑)。
T:ええ、ええ。
■具体的にそういう道へ進もうと思いはじめたのはいつ頃なんですか?
T:えっと、すごく強く、音楽では食えないという思いがあったもので──いまもですが。
■ハハハ! さすがシビアな現実認識が骨身に沁みた世代でいらっしゃる。
T:(笑)──でも、そんななかでも、実際的に職業にできるものは何かって考えたときに思いついたものですね。
■なるほど。音楽に憧れる最初のきっかけがあったと思うんですが、それはどんなものなんでしょう?
T:小っちゃい頃はクラシックとかをやっていたんですけど、中学……高校生のときかな? 父親が何百枚も入るCDラックを持っていて、60~70年代のロックとかハードロックが多かったんですが、それを1日に1枚聴いていくっていう作業をずっとやっていて。
父親が何百枚も入るCDラックを持っていて、60~70年代のロックとかハードロックが多かったんですが、それを1日に1枚聴いていくっていう作業をずっとやっていて。
■おお。いま図らずも「作業」って言葉が出ましたけれども。
T:そうそう(笑)、まあ、僕が中学くらいのときはBUMP OF CHICKEN(バンプ・オブ・チキン)とかL'Arc-en-ciel(ラルク・アン・シエル)とかって邦楽のロックを聴いていたんですが、その原点って何? って考えたときにこのへんのロックだろうと思って、父親のCDラックをひたすら聴いていたんです。うちにはパソコンとかなかったので、音楽の情報はほぼそこからのみという感じでしたね。
■へえー。いちおう認識としては、好きなもののルーツへと遡るという行為だったわけですね。具体的に名前出ます?
T:いや、ほんとにディープ・パープル(Deep Purple)とかツェッペリン(Led Zeppelin)とか(笑)。父親はそのへんが好きみたいですね。
■ハードロックなんですねー。メタルとかいかず。
T:そうですね。オールディな感じで。で、気になっていったのがキング・クリムゾンで。
■あっ、そうつながるんですね。プログレにいったんだ。
T:聴いてすごくびっくりして。1曲のなかにあんなに詰め込んじゃっていいんだって気づいて。
■ああ、なるほど。『宮殿』からですか?
T:そうですね、『宮殿』から入り……。あとは、父が棚に年代順に並べていたので(笑)。
(一同笑)
■かつA to Zで入れてますね、それは(笑)。
T:それは曲をつくるひとつのきっかけになっているかもしれません。
■なるほど、そうするとTomgggさんの音楽のわりと構築的な部分に理由がつく感じがしますね。
T:そうかもしれないですね。それまでは、ちゃんとつくられた曲というとクラシックだけしか知らなかったので。モーツァルト、ベートーベン……完成されているものですよね。でもキング・クリムゾンとかは別次元で変なものがつくられているという感じを受けて、でも同時にそこにこそ強度があると感じました。
■ツェッペリンとかも、プログレに連なるようなところはありますよね。牧歌的なハードロックというより。……すごく思弁的だったり。
T:そうですよね。あと、クラシックのようにすっきりとした音じゃなくて、もっとノイズにまみれたものを聴きたくなってしまったところもあります。でも、音はノイジーでも美しく完成されていて。
■クラシックはクラシックでお父さんのコレクションがあったりしたんですか?
T:そんなになかったですね。ピアノの先生に教えてもらったりです。
■おっ。やはりピアノされてたんですね。そこで弾いてたのは……
T:古典的なものですね。
■なるほど、印象派とかではない?
T:そこまで……いってなかったですね(笑)。印象派にたどりつくのは音大に入ってからです。
■でも、古典よりとっつきやすくないですか?
T:うーん、そうでもなかったですね(笑)。
■なるほど。Tomgggさんは2000年だと12、3歳くらいですかね。クラシック以外ではどんなもの聴かれてました?
T:SMAP(スマップ)とかですかね。テレビから流れてくる音楽です。
■なるほど、お父さんのアーカイヴに手を出しはじめたのはその後ですか?
T:中学は、ほぼ音楽には興味がなかったんです。だから高校からですかね。陸上部に入っていて……しかも砲丸を投げていたという激ヤバなストーリーがあるんですが……。
■ハハハ! それはヤバいですね。人はいつ砲丸に向かうんですか(笑)。
T:どこも人が多かったので、人のいないところを探したら砲丸だったというか(笑)。フォームはよかったらしいです。
■フォームね(笑)。Tomgggの音楽を語るときのキーワードになるかもしれませんね。
空間に興味を持った理由のひとつが、音楽のなかにどれだけの音の情報を詰め込めるかということだったんですよ。
■と、紆余曲折あって音大進学となるわけですが、「電子音響音楽と空間表現」ですか。ホームページのプロフィールかなにかで拝見したんですが、それが修論のテーマだったと。これはいったいどんな研究なんでしょう。
T:ヨーロッパのラジオ局からはじまって、現代音楽が盛り上がって、カセットテープやレコード……いわゆる電子音響、電気的に音楽が録音できるようになって。それ以降、音楽に何ができるようになったのかということをひたすら研究していました。そこでのひとつキーワードとしては「空間」。空間を使って作曲ができるかということを試みた人たちがいて、それがすごくおもしろかったんです。
■部屋一個ぶん使うくらいの音響装置とかエフェクターとか、そういうもののことですか?
T:そういうのもありますけど、たとえば、お客さんとステージという関係を前提とすると、音楽が前から鳴ってくることが普通のことのように感じられますよね。でも後ろから鳴ってもいい。そういうことが可能になったんだという研究があって、それは具体的に何をしているかというと、たくさんスピーカーを使っていたりってことなんです。電気的な装置を使って、それをどこまで拡張していけるのか。そういうことをひたすらやりましたね……。
■へえー。じゃあ、ハンダゴテが出てくるような研究というよりも、もう少しコンセプチュアルで抽象的なものについて考えていたわけですね。かたや、裏方でエンジニアやるってなると、ハンダというか、装置の中身の話にもなっていくと思うんですが。
T:そうですね……、サウンド・プログラミングをやって、ってくらいなんですが。自分でエフェクターをつくったりはしましたけどね。
■では、その頃に学んだものはいまのTomgggの音楽に大きく影響を与えていると思いますか?
T:そうなんでしょう。空間に興味を持った理由のひとつが、音楽のなかにどれだけの音の情報を詰め込めるかということだったんですよ。2チャンネルのステレオの中だと、詰め込める周波数が限られているんですね。でも、そのスピーカーを増やしていけば、詰め込める量が増えていくじゃんってことに気づいて。
■ははあ……、個数の問題なんですか。
T:どうなんですかね(笑)。2個よりも4個のほうが音を詰め込めるんじゃんって考えました。で、いろんなところから音がしたら、もっと表現も広がるなというふうに発展していったりとか。
■なかなか頭が追いつかないのですが……。恐縮ながらすごく具体的なところでどういうことをやったという例がないですか?
T:そうですね(笑)、たとえばヘッドホンで聴いたときに音が左、右、左、右って音が移動するように聴こえるエフェクトがあるじゃないですか。あれをもっとぐるぐる回したいとか。
■おお、音をぐるぐる回すってのは、それこそツェッペリンがすごく早くにやってたやつじゃないですか?
T:あ、ほんとですか。いちばんはじめが誰かわからないけど……。
大学を卒業すると同時にそういう研究はスパっと終わりにして。次にどんな音楽をやろうかというときにインターネットかなと思いました。
■おお、何かつながったということにしましょうよ(笑)。ぐるぐるやったりしてたわけですね。ご学友というか、まわりの人はどんなことをやっていて、いまどんな仕事に就いているんですか?
T:まわり、何やってましたかね。MVとか映像が流行りだしたころだったので、それこそ「映像と音の関係」とか。ミシェル・ゴンドリー(Michel Gondry)とかいろいろ出てきましたし。
■ああ、なるほど。真鍋大度さんだったりを目指すとか。こうしてお話をきいてくると、サブカルチャー的な部分との接点はありつつも、かなりハイブローなものからの吸収が大きいですよね。先日MiiiさんやLASTorderさんのお話をうかがったばかりなんですが、たとえばMiiiさんなんかがギークとしてのアイデンティティを持ちながら〈maltine(マルチネ)〉に接近していくのはよく理解できるんですよ。Tomgggさんはどうして〈Maltine〉なんでしょう?
T:本当に飛び石というか、大学を卒業すると同時にそういう研究はスパっと終わりにして。次にどんな音楽をやろうかというときにインターネットかなと思いました。imoutoid(イモウトイド)っていう、むかし〈maltine〉にいたアーティストがすごく好きだったんです。ああいう感じでやりたいなという。それでいろいろやっているうちにつながったというか。
■なるほど! 音源を送ったりしたんですか?
T:いえ、そういうわけではなかったんですが、卒業してからずっと、インターネットの音楽ってどんな感じだろうって思って探ってたんですね。潜伏していた時期があるんですが、たとえばRedcompassくんがやっているFOGPAKっていうコンピのシリーズとか、そういうところと接点を持ったという感じです。何曲か送りました。
■Redcompassさんも、いろいろなものをつないでいる方ですね。
T:そうですね。そうしているうちにtomadさんから連絡をいただいて。ボーエン(bo en)がはじめて来日するときに、リリパで出ませんかというふうに声をかけてくれたんです。もちろん、出ます出ますということで(笑)、それでここまできている感じです。
■なるほどー。たとえば、とくにドメスティックなこだわりのない音楽をされている方だと、海外の好きなレーベルから出したいって気持ちもあったりすると思うんですが、そういうこともなく?
T:そうですね……、ネットを探っていたといってもとくに〈maltine〉以外に見えていたわけじゃないです。あんまりたくさん知らなかったかもしれませんね。
■そうなんですね。tomadさんがつなげたものって、音楽というよりもヴィジュアルとかスタイルとか風俗とか、そのなかでのふるまいとして音楽もあるというか。そういうもの込みでのネット・カルチャーですよね。
T:ええ、ええ。
■〈maltine〉がなくてもアルバムをつくってました?
T:ネット・レーベルがすごく流行っていたころだったので、僕も友だちと「やってみるか」っていうことになったりもしたんです。でも結局それもふるわず。
■そうなんですね! 音源はタダだから経済的に成功してやるというような野心はあんまりないでしょうけど、わりとみんながネット・レーベルというものに夢をみた時期だった……?
T:そうですね、僕についていえば、関わってみたかったという感じでしょうか。
音楽をつくるなら歴史にアーカイヴされる必要がある、って思っちゃうんです。
■なるほど。同時にパッケージの必要性とか、あるいは「アルバム」「シングル」ってかたちで音をまとめる意義も自然と問い返された時期だったと思います。〈maltine〉からの3曲入りの「Popteen」は、どういう意識です? アルバムとかシングルとか。
T:アルバムでもシングルでもないですね。ふるいかたちを借りればEPということになると思いますけれども。3曲くらいあればまあ、かたちにはなるかなというところで(笑)。2曲だとまとまりにかけますし。3曲だと「集団」だなって感じがします。
■今回の『Butter Sugar Cream』は4曲+リミックスというかたちですよね。このサイズ感って、じゃあアルバムですか?
T:うーん、そうですね……。これでやっとひとつのものだぞという感覚が生まれましたかね。
■へえー。まあ、10数曲入っていたりするじゃないですか、プラケに入ったCD、アルバムってものは。
T:10数曲あると聴かないんですよね(笑)。
■ハハハ。そのへんはある種のユーザビリティみたいなものへの配慮もあるとか?
T:自分の制作ペースとかもあるんですけどね。僕、1曲をつくるのがけっこう大変なんで……。
■寡作なんですね。音づくりに手間ひまをかけるから? アイディアが出てくるまでの問題?
T:どっちも……ですね。『Butter Sugar Cream』も結局10月くらいからつくりはじめて、2月のあたまくらいにやっとできたので。繰り返し聴くのに耐えられるかってことをよく考えます。
■なるほど。
T:PC上では、何度もあたまから聴き返しつつつくるわけですから、それに耐えられるかというのは自然にイメージするところですね。「これ、つまんないな」っていうのは何度も寝かせました。
■私は「俺の歌を聴け」世代というか。グランジとかが直撃で、ロックがまだまだ洋楽のメインストリームだったんですが、そこではもうちょっと「俺の歌」が優先されていたと思うんですね。客が何度も聴けるかどうかなんて知ったこっちゃなくて、まずそれが我(おれ)の音楽だってことが大事というか。そのへん、Tomgggさんとかは真逆で、すごいユーザー視点なんですねー。
T:ああー、なるほど。僕の大学の先生が「中毒性」ってことをよく言っていて。その言葉が今回の作品のお菓子のパッケージにもぴったりだなと思うんですが、何回聴いてもまた聴きたくなる、そういうものをつくれるかどうかってことを考えていましたね。それから、音大出だからだと思うんですけど、音楽をつくるなら歴史にアーカイヴされる必要がある、って思っちゃうんです。
■ああ、はい。
T:音楽史っていうものがあって、そのなかにレジェンドな曲が配置されていて、それは何百年間も聴かれる曲で。……そういう思いも底にはあるのかなあって。
■なるほど。いま、それこそネット環境だと、音楽はタイムラインのなかで一瞬で消費されたりして、そのスリリングなスピードがつくる側にもおもしろさを生んでいたりもしますよね。そんななかで何百年も残るものを目指すというのは、何か、Tomgggというアーティストのスタンスを知る上で見逃せないところかもしれませんね。
T:そうかもしれませんね(笑)。
■このお菓子みたいなジャケだって。一回開ければ終わりでしょう(※)? それまた、替えのきかない一回的なものとして永遠に残ろうとするものだって解釈できますよね。

※市販の菓子のパッケージのように、ボール紙でできたジャケットを破るかたちで開封する
T:これは本当にお菓子のパッケージのイメージなんです。入口がお菓子、中身がCDという。お菓子だと、結局は中身が食べられて外側も捨てられちゃいますけど、音楽はなかなか消えない。
■すごくきれいに考えられてる。それに、音楽の歴史を意識しているっていうのは、なにか貴重な証言をいただいた気がします。
T:それほど意識するというわけでもないんですけどね。でも俯瞰して見ちゃうというか、そういうところはどうしてもありますね。
[[SplitPage]]
(歌詞のオーダーについては)甘いものを食べてる……部屋の中でひとりでお菓子を食べているというイメージでやってほしいと言ってたんです。
■そこでこの『Butter Sugar Cream』ですが、甘味三段活用。もう、甘いぞーってタイトルですね。ワン・ワード?
T:ワン・ワードでいいと思います(笑)。
■ハハ、この甘いものの三段重ねは、ご自身の音への自己評価なんですか?
T:ああー、なるほど、そうですね……。「バター・シュガー・クリーム」って言葉自体は、この歌詞をつくってくれた辻林(美穂)さんが使っていた言葉なんですよ、歌詞のなかで。僕としては、甘いものを食べてる……部屋の中でひとりでお菓子を食べているというイメージでやってほしいと言ってたんです。
■あ、そこまで明確にディレクションされてたんですね。
T:そうですね。けっして相手がいないかたちで、甘いものを楽しんでいる状態というか。で、実際にできた詞のなかの「バター・シュガー・クリーム」って言葉がとてもよかったので、タイトルとして使うことにしました。あと、「シュガー・バター」だとウェブで検索したときにノイズが多そうなんですけど、「バター・シュガー・クリーム」だったらこれしか引っかからないし。
■ハハハ。「バブルガム・ベース」なんて言ったりもしますけど、まあ、バブルガムとはニュアンスがちがうにせよ、「バター~」もポップで甘いってとこは共有してると思うんですね。そこで、ポップとか甘いとかって感覚が目指されているのは何なんですかね?
T:なんですかね、「カワイイ」を横にズラした感覚っていうんでしょうか。「カワイイ」を言い過ぎてしまうというか。手に余る感じをわりとポジティヴに表現してるんじゃないですかね。
■ははー。それはなんか、咀嚼したい回答ですね。なるほど。しかしそもそもクリムゾンとツェッペリンからはじまって、行き過ぎたカワイイまでいったわけですか(笑)。
T:ははは。やっぱり、遠回りしたほうがおもしろいなっていうのはあります。ルーツがそのまま出るよりも。それから、たとえばノイズっていうものは一部の人にしか楽しまれないものだと思うので、せっかくならいろんな人が聴く場所でやってみたいという気持ちもありますね。お菓子ってみんな好きですよね。漬物とか、限られたひとの嗜好品みたいなものよりもそっちをやりたい。子どもも大人も食べられるようなものを使って発信したいです。
■ということは、Tomgggさんの目指している音楽性は、Tomgggさんの考えるレンジ、リスナー層の幅に対応しているものだと。
T:そうですね。なんだろう、生きていく上で絶対必要なごはん、以外の食べ物。本当は食べなくてもいいもの、動物としてじゃなくて人間として必要な食べ物。お菓子ってそういうことですね。
■ああ、人はパンのみにては……バター、シュガー、クリームなしには生きられないと。
T:重要ですね(笑)。
■なるほど。ですけど、あえて反論するなら、たくさんのひとが快適で楽しめる感じの甘さであるには、『バター・シュガー・クリーム』はちょっと毒なくらい過剰に甘すぎませんか?
T:でも思いっきり濃くしないと。薄い甘さじゃ広がらないだろうなって思います。やっぱり10秒聴いてグッとくるかこないかの世界──インターネットってそういう場所だと思うんですけど、プレヴューで10秒、20秒、30秒って飛ばして聴かれるようなときに耐えられる甘さにしなきゃいけないわけですよね。
思いっきり濃くしないと。薄い甘さじゃ広がらないだろうなって思います。
■(担当さんに向かって)……いまのミュージシャンって、ほんと大変ですね。
T:自分もそうだし、みんなもそうだと思うんですよね。
■マジで絶句しましたよ。俺の歌を聴くまで待つとか、そんな悠長なことをいっていられないんだ。むしろ、あっちはお客様ってくらいの意識があるというか。
T:そうですね、自分もやっぱり聴く立場だし。SoundCloud(サウンドクラウド)とかも日々更新されるじゃないですか。時間をそんなに取れないから、こことこことここだけ聴く、みたいな。
■盤を買いにレコ屋さんに行って掘ってきたりってするんですか?
T:サンクラ……ですね。それこそ高校生の頃はディスクユニオンのプログレ館に行ったりとかしてましたけど。
■ハハハ。でもその頃は、ひととおり紙ジャケの再発ものがバンバン出ていて、聴きやすいし買いやすかったんじゃないですか? 解説も新しくついてるし。
T:そうですね。たしかに再発で新しく知るきっかけになったり。
■そうですよね。プログレ館まで行くんなら、聴いてたのはイギリスのバンドとかだけじゃないんじゃないですか? アレア(Area)とか。
T:アレア聴いてましたね。もちろんヨーロッパからですけど、イタリア系も聴いて。オザンナ(Osanna)最高、みたいな。
■ハハハ! マジですか。ジャズとか、ちょっとクラシックにも寄ってきますしね。頭おかしい合唱みたいのでアガったりとかしませんか。
T:どうですかね、マグマ(MAGMA)みたいのもやってみたいですけどね。
■いいですねー。バーバーヤガッ、つって。それぎりぎりカワイイなのかな(笑)。
T:ははは。
■でも訊いてみたかったんですよね。グロッケンとストリングスを禁止したら、Tomgggさんはどんなものをつくるんです?
T:やっぱひたすらマグマみたいになりますかね(笑)。ひたすら繰り返して……すげー盛り上がる、みたいな。
■あははっ!
T:やっぱりいまのスタイルは、グロッケンとかストリングスでメロディをつくるっていうところなので、それを禁じられるとメロディをつくれないだろうから、ひたすら繰り返すっていう方向になるだろうなあ……。
■いまもそういう方向がないこともないですけどね。カワイイをひたすら横すべりさせていって……
T:大袈裟な展開と音づかいにする。
■ははは。そういえば、アナログな音への憧れとかないんですか? ヴィンテージなシンセとか。
T:ああー。はっきり言ってしまうと、シンセにそこまで憧れがなかったりもするんですよね。
■ラスティ(Rusty)が好きって言っておられましたっけ。彼なんかはそういう憧れがちょっと逆に出てるのかなって感じもしますが。彼の音楽はどんなところが好きなんです?
T:はじめて聴いて、カッコいいなーっていうのがきっかけです。この感じがほしいなって。
■音のカロリー高いですよね(笑)。
T:そうそう!
■情報量も凝縮されていてね。逆に、チルな感覚ってないんですか?
T:僕は、重ねるというか、足し算で音楽をつくっていくタイプなんで、どちらかというとカロリー高めにはなりますかね。はじめの、スピーカーを増やして情報量を過密にするという話ではないですが。
■ああなるほど、じゃ北欧シンフォニックみたいにね、異常なエネルギーで過剰な情報量をさばいていくかんじのポップス、やってほしいですね。
T:ははは、いいですね。
■ポストロックとかは通ってますか?
T:そうですね、多少。ポストロックというかわかりませんけど、ゴッドスピード・ユー!・ブラック・エンペラー(Godspeed You! Black Emperor)とかはカッコいいですよね。
■ええー。なんだろう……素っ裸になったりしなきゃ。
T:いやいや、そんなストイックだったりはしないんですけど。あとはドンキャバ(Don Caballero)とか。
■ええー! そうか、お話を聞いていると、意外に底に沈んでいるものがハードコアですね。手数の多いドラミングとかは、まあ、情報量ですかね。
T:ああ、ドラムがメロディみたいになっていますよね(笑)。好きですね。
■なるほどなー。バターとシュガーとクリームの成分がわかってきました。
もともと人の声を切り取ってきてるわけなんですが……。ただ、ヴォーカルに還元したくないんですよね。
■でも、じゃああの甘さっていうのは仮面?
T:甘い餅にくるむみたいな感じ。どんな中身でも、食べちゃえばわかんないでしょっていう(笑)。
■ハハハ。でも甘いものは本当に好きなんでしょう? 戦略的な意図だけで劇甘メロディを入れている、ってわけじゃないですよね。
T:好きですよ。やっぱりそこは、たくさんのメロディがあったほうが楽しいなって思いますし。
■うーん。なんか、食えないやつですね、ほんと。
(一同笑)
■ご自身のピアノを生かしたいというような気持ちはないんですか? 作曲技法ってことではなくて、生音として取り入れたいというような。
T:そうですね、自分の曲をこのままバンドに変換できたりしないかなってことは考えたりするんですけどね。あまり生音に関心があるというようなことではないですね。
■おお。そうか、譜面が書けるんですね?
T:書けますね。
■ということは、バンドに手渡すということもできますね。それはそれで、おもしろい展開が考えられそうですね。この作品も2曲めとかにヴォーカル・サンプルが入っているわけですが、あれはトラックを渡してその上で歌ってもらうってことじゃなくて、声のデータをもらってつくっているんですか?
T:はい。素材としてもらって、それを打ち込んでます。
■ボーカロイド以降の感覚ってあります?
T:そうですね。でもボーカロイドっていうよりも、僕はコーネリアスが好きなので、コーネリアスのヴォーカルの使い方ってあるじゃないですか? あれをどうにか僕なりのかたちでやってみたいという感じなんです。
■一見、人間性みたいなものをばらばらにしてるような。
T:ええ、ええ。声らしき断片みたいなものがあって、声かどうかは一瞬わからないんですけど、やっぱ声でした、みたいな感じ。そういうイメージですね。
■では、生の声への信仰があるのかどうかってあたりをうかがいたいんですけども、どうですか。生のヴォーカルのほうが尊いっていうような。
T:生の声のほうが言葉になるっていう感じはあるんですけどね。メッセージが強く出ますよね。ボーカロイドだとただ音色になる部分もあると思うんですけども。
■ああ、なるほど。Tomgggさんのこの声の使い方は、声を音色にする方法論ではないんですか?
T:声を音色にしてるんですけどね……なんだろう、もともと人の声を切り取ってきてるわけなんですが……。ただ、ヴォーカルに還元したくないんですよね。
■人が能動的に歌うものにしたくないという? 歌い手が歌う歌にはしたくない?
T:そう、メロディではあるんですけど、ヴォーカルを切り取ってきたときには、無機質な状態のほうがやっぱりおもしろいって思います。
■なるほどなあ。人が歌う歌って、その人の人間性の限界みたいなものも出ちゃったりするじゃないですか。よくも悪くもとにかく情報量がノイジーで。……でも、そういう人間性みたいな部分がいらないわけじゃなくて?
T:そう、人間性もほしいんだけど、無機質さもほしいって感じですね。やっぱり、録音された素材はそれ以上広がりようがないじゃないですか。その状態を保ったままつくるというか。
■そこには人格とかキャラクター性はない?
T:僕の曲だと認識されやすくなるためのひとつのキャラクター性ではあるかもしれないですね。持ち味というか。そういうものは生まれているかもしれません。どの曲にもちょっとずつ混ぜ込んであるんですよ。
ライヴでは前でぴょんぴょん跳ねているのが楽しいんですけどね。
■なるほど。一方で、歌詞もきっちりついている“Butter Sugar Cream”ですが、これはさすがに「歌い手性」みたいなものも出ているかと思います。これは、「女の子ヴォーカルを歌わせる」っていうような意味でのプロデューサー意識はありました?
T:そうですね、さっきも少し触れましたけど、この曲は歌詞をつくるのにもけっこう口を出しているんです。あと、歌い方も指定してつくったものですね。いろいろ歌詞があって、最後「消えたりしない/溶けたりしない」って繰り返すのはぜったいやりたいと思っていました。
■へえ、それは──?
T:あの音色でこんな言葉を入れたらおもしろいだろうなって。「歴史にちゃんと残るんだ」っていう気持ちにリンクするなという気持ちもありました。
■ああ、なるほど、かなりコンセプチュアルなんですね。誰かシンガーを引っぱってきて歌わせたいという思いはあります? この作品でもフェニックス・トロイ(Phoenix Troy)さんがラップで参加されていますけど、トラックを提供して歌い手を歌わせるというふうに仕事を発展させていきたいというような。
T:そうですね。この2曲はうまくいったなとは思うんですけど、まだまだ発展はできるなと。
■彼にラップを入れてもらったのはなぜですか?
T:これは、あちらからアプローチがあって。それで、こういうリリースがあるからそのなかに入れましょうっていうふうになりました。「お菓子がモチーフなんだ」みたいな話をして(笑)。
■へえー。ボーエンさんもそうですけど、なんかそういう、日本人みたいな人たちいますよね。たんにインターナショナルだっていうことじゃなくて、日本人めいた人。
T:ははは。
■しかし、Tomgggさんって、自身がすでに歌ってるというか、トラックがものすごく歌うでしょう?
T:そうですかね(笑)。
■だから誰かに歌ってもらう必要がないようにも思うんですよね。こうやって歌い手と仕事をして、変化した部分もあったりしますか。
T:広がりましたね。いろんなメロディを重ねていくなかで、独自性のある声も出てくるし、さらにそこに自分の音が重なることで情報が増えるなっていう気持ちはあります。
■Tomgggさんの場合、そもそもの夢の方向が裏方を向いていたわけですけど、裏から糸を引っぱって踊らせるっていうプロデューサー志向が、かなり若い人のなかで強いような印象があるんですよ。そのあたりはどうですか?
T:ははは、でもライヴでは前でぴょんぴょん跳ねているのが楽しいんですけどね。記号的なオモテというか、前に出てくる出演者でもあるというところはほしいはほしいですよ。
■ああ、ぴょんぴょん跳ねてるっていいですね! 2曲めは、指をぱちんってやる音がサンプリングされてたりもするじゃないですか。ああいうのも不思議な空間性を生んでますよね。
T:音楽的に使わないであろう音色ってあると思うんですけど、それが普通の音楽に持ち込まれたらどうなるかっていうのを意識することはありますよね。エレクトロニカとかのモチヴェーションに近かったりするかもしれないですけど。ライヴでも、最近は曲と曲の間に雑踏の音を入れたりとかしはじめてます。
足、太い女の子が好きな人が聴く音楽になってほしいですね。
■いまのスタイルだと、ある種箱庭的に、すべての要素を自分自身の手で決定してつくってるわけですよね。ジャケットのイラストはkazami suzukiさんで、〈Maltine〉からのEPでもお馴染みの方なわけですけれども、最初のころからすでにけっこうご活躍の方だったんですか?
T:どうなんだろう。〈Maltine〉のときが最初なんですけど、あのときはtomadくんが見つけてこられたんですよね。Tumblr(タンブラー)にいい感じの人がいるって(笑)。……やっぱりそこにはtomadがいるという。
■ハハハ! すごい、さすが名プロデューサー。つなげますね。だってすでにTomgggさんの音と切り離せないようなものになってるじゃないですか。
T:そう、もうキャラクターが生まれているんで(笑)。
■Tomgggさんから見て、kazamiさんの作品の客観的な評価はどんな感じですか?
T:なんていうか、ロリっぽい感じだとは思っていて。僕の曲──声のサンプルもそうなんですけどね。そういうオタクくささみたいなものが絵のなかに凝縮されていると思いました。やっぱり、本人も吾妻ひでおがどうとかって言ってましたしね。
■ええー、そうなんですか。なるほど。……足、太いですよね。
T:そう。そう、足、太い女の子が好きな人が聴く音楽になってほしいですね。
■ハハハ! またニッチなところに投げましたけども(笑)。いや、でもこれはもっと概念的な太さだとも思うんですよね。実際に太いってだけじゃなくて。
T:ええ、ええ。
■この輪郭の崩れた感じとか。
T:カロリーを感じますね(笑)。
■ハハハ、そうそう(笑)。どうです、こういう絵は詳しいほうですか?
T:いやー、詳しくはないですけど、でも実写とか写真とかそういうものよりはぜったいイラストがいいとは思っていたんです。
■へえー。もし彼女に頼まなかったらどんなジャケになってたと思います?
T:どんなジャケになってましたかね(笑)! アクの強いイラストがよかったので……見つけてきてもらってすごくよかったですね。それから今回も思ったんですけど、キャラクターって重要だなと思いました。
■キャラクターですか。
T:やっぱり強いです。どこにいってもついてくるものというか。逆に言えばどこにでも連れていける感というか。これ俺だよっていう感じで。
■音楽性とか人格も宿っちゃいそうな……
T:それはあると思います。
■それはおもしろいですね。可愛くてコンパクトな情報の運び屋になる。この絵をみるとTomgggさんの音が思い浮かびますからね。
T:いい出会いをいただいたんだと思います。最初は「ポムポムプリン」とかサンリオ系のキャラクターが好きだったみたいですよ。
■へえー。
T:それがあるとき吾妻ひでおに出会って……
■ハハハ。すごいなあ。でもサンリオもいま総選挙とかやってますからね。
(一同笑)
■ポムポムプリンもセンターとらなきゃって、世知辛い時代ですよ(笑)。吾妻ひでおのほうにいってよかったんじゃないですかね。
ソウルフルな女性ヴォーカルはやりたいという気持ちもあるんですよ。
■さてヴォーカルのほうですけど、tsvaci(ツバシ/辻林美穂)さん。彼女もまた音楽を専門的に学ばれてる方ですよね。プロとしてのお仕事もけっこうされている。
T:そうですね、まだ事務所には入っていないようなんですけども。いろいろ呼ばれてやってますよね。出会いは、tofubeats(トーフビーツ)が去年のいまぐらいだったか、ラジオでミックスを流したことがあって、そのなかに入っていたのがtsvaciさんの“You know…”っていう曲だったんですけど、それがよさそうだなって思って声をかけたんです。それから何か月も経ってやっと曲ができましたという感じだったんですけど(笑)。
■戦略的に選ばれているのかもしれませんが、ロリっぽいものは素朴に好きなんですか?
T:うーん、いちばんイメージしやすかったんですよね。自分の音から。
■ああ、音との相性ということですか。個人的な嗜好として好きな女性ヴォーカルの名前は挙がります?
T:やくしまるえつこに衝撃を受けて。
■ああ、それは大きいですね。
T:太くてゆたかなアルトとかが素材としてあったとしても、それはピッチを変えてケロケロさせちゃうかもしれません。音に合わないから。
■ハハハ、なるほど。じゃあ時代にチューニングしてるみたいな部分もあるのかもしれないですね。自分の趣味だけでやるとしたら別ってことですか?
T:うーん、どうでしょう。でもソウルフルな女性ヴォーカルはやりたいという気持ちもあるんですよ。
■へえー。フェニックス・トロイさんとかも、グライムとか、あるいは白人ラッパーとかの雰囲気ではないですもんね。
T:自分のトラックに乗せたらギャップがあってすごいおもしろそうだなって思って。ほんとに、相手に合わせるんじゃなくて、こっちのやり方に合わせてもらうつもりでトラックを渡しました。
■なるほどー。ちなみに男の人の声はケロケロさせなくてよかったんですか(笑)?
T:ははは、あれはあのまま乗せましたね。
■男の人の声はケロケロさせたらどうなるんですかね。ていうか、女の子の声があふれていますけど、男の人の声ってなにかおもしろい展開ないんですかね。
T:はいはい(笑)、やっぱプログレやるしかないんじゃないですか。オペラを登場させるしか。
■ハハハ! つながったー。男声合唱やるしか(笑)。
T:声で音圧を高めなきゃ。
■挑戦はつづきますね。
放課後の部活というか、みんな社会人で、働いてるんですけど、土日は曲をつくって。
■ちなみに〈PCミュージック〉とかはどうですか? 熱かったですか。
T:すごくグッときましたよ。雑な感じというか、軽率な感じというか。
■はは、軽率な感じということなんですな(笑)。
T:ははは、このまま行っちゃうんだーみたいな感じですかね。雑なんだけど、何か新しいものを提示しているっていう、そういう気分を共有できました。
■雑さは織り込み済みの評価なわけですね。雑っていうのは……ヴェイパーウェイヴみたいな露悪性があるわけではなくて、ただ雑、っていう感じ?
T:そのへんですかね。新しさと、あとはミックスの感じにも不思議な印象を受けてます。好きになりましたね。
■〈Maltine〉の中ではとくに仲のいいアーティストって誰になりますか?
T:三毛猫ホームレスとかですかね。
■素敵ですね! なんでしょう、楽理系というか、そういう部分での共感もあるんですかね。
T:あとはHercelot(ハースロット)とか。テクニカルな感じの人たちでしょうか(笑)。スカイプで作曲講座みたいなものが展開されてたりするんですよ。
■いいですねー。
T:三毛猫、芳川よしの、Nyolfen(ニョルフェン)とか……、スカイプで日々会話してます。
■つくってるときのPCの画面を全部見せるみたいな感じですか。内輪でしか公開しないもの?
T:そうそう、新曲をそこで批評しあったり。
■楽しそう。オープンにしないのは、ショーではないという感じなんですかね。
T:うーん、そうですね。放課後の部活というか、みんな社会人で、働いてるんですけど、土日は曲をつくって、そういうところに集まる……。
■いいですねー。部活の楽しさもあるし、テクニカルな交歓もある。
T:テクニックは……それぞれお互いのやり方を見ながらも、実際のところそれほどテクニックに興味がなかったりもするんですよね。音圧とかもみんなわりと、どっちでもよくて(笑)。
■そうですか。それはほんとに……尊いというか。歴史に残る残らないという尺度とはまた別の次元で生きている音楽の例ですね。
T:そういう自覚があるわけではないですけど、そうかもしれませんね。歴史には残りたいですよ(笑)。
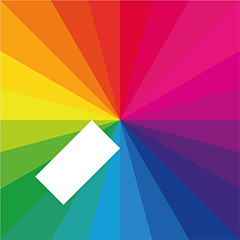 Jamie xx
Jamie xx ヤング・ファーザーズ
ヤング・ファーザーズ