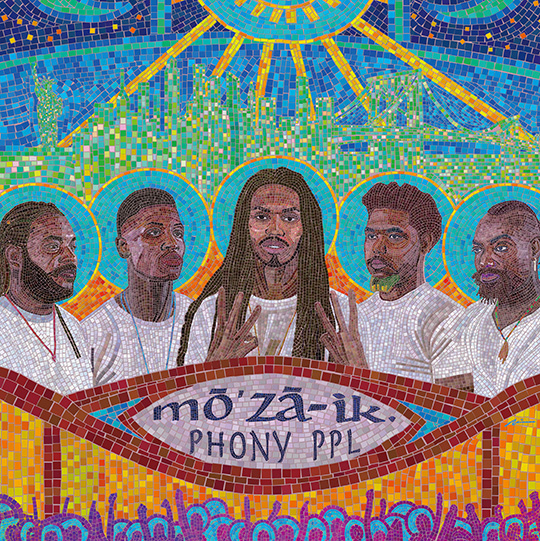偶然だったとしても素晴らしい。2017年、バーミンガムにおけるイギリスの極右団体への抗議の現場を報じたガーディアンのひとコマには、あるイスラム系の女性の姿が写っていた。当時20才だったサフィヤ・カーンの着ていたデニムジャケットの下には、「THE SPECIALS」と描かれたのTシャツが覗いている。さっそくザ・スペシャルズは彼女をライヴに招待した。そして、およそ40年振りのアルバムのなかの1曲でMCをまかせることにした。大役である。なぜなら、彼女が任せられたのはプリンス・バスターのいにしえのヒット曲、“10 Commandmentsl”をリライトすることだった。バスターは、ルードボーイ音楽の王様にして2トーンにとっての英雄、ザ・スペシャルズにとっての巨大な影響だ。が、しかし、“10 Commandmentsl”には露骨な性差別が歌われていた。ザ・スペシャルズは、若き勇敢なフェミニストを起用して、名曲の言葉を書きかえるという大胆なアイデアに挑んだのだった(プリンス・バスターはイスラム教徒でもあるので、イスラム系の若い女性がそれを改稿するというのは、二重の反転がある)。
ザ・スペシャルズ、さすがである。
いまさらぼくと同世代のリスナーにザ・スペシャルズの偉大さを説くのは釈迦に説法なので、ここではリアルタイムでは知らない世代に向けて書こう。
そもそもUKのパンクおよびポストパンクの多くがいまもなお参照点である理由は、彼ら/彼女らがサッチャリズム(新自由主義)に対する若者たちの最初の抵抗だったからだ。それゆえメッセージの多くは現在でも有効だし、音楽性に関していえば、そのメッセージを裏付けるように、彼ら/彼女らのほとんどは妥協なきオルタナティヴだった。
ザ・スペシャルズは、70年代末〜80年代初頭のポストパンク期におけるスカ・リヴァイヴァルを代表するバンドだった。スキンズが好んだジャマイカのスカを音楽のモチーフにした彼らは、自らも、そしてオーディエンスも人種を混合させ、スキンズとパンクとモッズをいっしょに踊らせた。分断されたサブカルチャーを混ぜ合わせたこと、これがザ・スペシャルズの功績のひとつだ。もうひとつの功績は、新自由主義時代における若者文化の虚無感を実直に綴ったことだった。
それは1980年のセカンド・アルバム『モア・スペシャルズ』であらわになる。スタジオでの多重録音を駆使したそのアルバムは、ご機嫌なスカを求めていたファンの期待を裏切るかのように、日々の生活における暗い心情が表現されている。それが1981年の傑作12インチ「ゴーストタウン」へと発展して、解散後はまったく楽しくない楽しい男の子3人(ファン・ボーイ・スリー=FB3)へと続いた。
スカはアッパーでのりのりの音楽だと思われていたし、多くの若者にポークパイハットを被らせたザ・スペシャルズはファッション・リーダー的な存在でもあった。が、ザ・スペシャルズにはのちのマッシヴ・アタックと連なるようなメランコリーがあったし、自己矛盾かもしれないがファッション文化を空虚なものだと見なしていた。『モア・スペシャルズ』の“Do Nothing”(なんもやらない)という曲は、ファッションばかりに金を投じる若者の空しさをこれでもかと表現している。個人的にもっとも好きな曲のひとつ、“I Can't Stand It”(がまんできない)では、私生活から職場にいたる生活のすべてにうんざりしている若者の気持ちが描かれているし、「誰もが着飾ったチンパンジー」と歌う“International Jet Set”はエリート層への嫌悪が歌われている。
いまの若い人には信じられない話かもしれないが、お洒落というのはある時期までは、お金のない抵抗者たちほど拘っていたものだった。パンクが服を重視したのもそういう事情があったからだ。服は、社会が強制するアイデンティティとは別の、個人が主張するアイデンティティを表現することも可能だからだ(家や車は買えなくても服は買えるからね、と昨年ドン・レッツは言っていた)。それゆえに、パンク〜ポストパンクはなるべくオルタナティヴな服装を選んだ。が、1980年のザ・スペシャルズによれば、ファッションはすでにエリート文化の一部になっていた。そう、このバンドは、オーウェン・ジョーンズの“エスタブリッシュメント”というあらたな上層階級の出現を40年も前に察知し、簡潔な言葉で皮肉っていたことになる。
「ゴーストタウン」に関していえば、セックス・ピストルズの「ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン」に次いで重要なシングルだという声もある。全英1位になったそのヒット曲は、この社会が生き地獄であることを歌っているのだから──。
新作のタイトルは『アンコール』で、これは本作が『モア・スペシャルズ』からの続きだということを意味している。メンバーは、リンヴァル・ゴールディング(g)、テリー・ホール(vo)、ホーレス・パンター(b)というオリジナルのフロントマンが揃っている。
『アンコール』は、ジ・イコールズのカヴァーからはじまる。
ジ・イコールズは60年代に結成されたUKのロック・バンドで、当時としては珍しい白黒混合のバンドだった。のちにレゲエ・アーティストとして有名になるエディ・グラントが在籍していたことで知られているし、ザ・クラッシュは『サンディニスタ!』において彼らの“ポリス・オン・マイ・バックをカヴァーしているわけだが、ザ・スペシャルズが選んだのは、1970年のヒット曲“Black Skin Blue Eyed Boys”だ。この曲に続く2曲目は、今作のためのオリジナル曲で“B.L.M.”……これはもうブラック・ライヴズ・マターということで間違いないだろうし、この2曲の並びをみても本作でのザ・スペシャルズのメッセージのひとつは見えてくる。
しかしながら、ぼくのような古いファンはノスタルジーを禁じ得ないだろう。3曲目の“Vote For Me”の曲調およびピアノのフレーズは、“ゴーストタウン”を思い出さないわけにいかない。FB3のカヴァー曲もある。ラテン調の“The Lunatics”(狂人たち)は、もともとは“The Lunatics Have Taken Over The Asylum”(狂人たちが弱者の場さえ支配した)という長い曲名で、FB3のファースト・アルバムに収録されていた。FB3には、“Our Lips Are Sealed”(ぼくらの口は封じられている)という最高のキラーチューンがあるのだけれど、本作で演っているのはへヴィーな曲である。
気怠いラテンのリズムは、今作のためのオリジナル曲のひとつ、インターネット社会の憂鬱を歌詞にしているという“Breaking Point”でも展開されているが、その曲が終わるとルードボーイ・クラシックのザ・ヴァレンタインズ“Blam Blam Fever”(別名“ガンズ・フィーヴァー”)のカヴァーが待っている。そして、銃について風刺したその曲が終わると、冒頭で紹介した“10 Commandmentsl”がはじまる。このあたりは『アンコール』におけるクライマックスだ。
8曲目は、“Embarrassed By You”(あんたのおかげで困窮している)という、いかにもザ・スペシャルズらしい曲名のレゲエ・ナンバー。難解な言葉や文学的な言い回しはしない、シンプルで直球な言葉遣いは彼らの魅力のひとつで、それは本作でも変わっていない。そして、座ってでしか音楽を聴いていない連中を嘲るかのように、踊れない曲はつまらない(労働者階級ほど踊る音楽好きである)というアプローチも一貫している。しかしながら、踊れる曲であっても楽しげである必要はないということを実践したのもザ・スペシャルズだった。“The Life And Times (Of A Man Called Depression)”(うつ病と呼ばれた男の人生と時代)は、曲名が言うように物憂げな曲で、UKガラージのリズムが取り込まれている。『アンコール』の最後は、“We Sell Hope”(我々は希望を売る)というアイロニカルな題名の曲で締められる。このなんとも後味の悪い終わり方がいい(笑)。
そもそもパンクたるもの、アンコールなんてものには応じないのが流儀だった。だからこの『アンコール』には、バンド内でもやや自嘲的な思いがあったのかもしれない。それでもザ・スペシャルズは、その21世紀版としてよくやったと思う。40年前にはできなかったことをやってのけたのだから。ちなみにもう1枚のCDには、ファン・サーヴィスというか、お約束というか、この手のベテラン再結成にありがちなライヴ演奏(2014年、2016年)が収められている。これは、ま、ご愛敬ということで。
追記:ぼくは知らなかったんだけれど、ザ・スペシャルズはテリー・ホール抜きの(もちろんジェリー・ダマーズ抜きの)メンバーで、1996年から2001年のあいだに4枚のアルバムを出している。この時期のオリジナルのメンバーは、リンヴァル・ゴールディングとネヴィル・ステイプルズのふたり(ともに元FB3)。で、これが意外と良かったりするから困る。ザ・クラッシュの“誰かが殺された”や“プレッシャー・ドロップ”のカヴァーなんてかなり良い。主役抜きのバンドが名前だけで続ける──よくある話だが、ザ・スペシャルズのおそろしいところは、それさえも素晴らしいという点だ。テリー・ホールの陰鬱やジェリー・ダマーズの作り込みはない。しかし、ゴールディング&ステイプルズはバンドの魂を保持していたと。ちゃんと聴いておけばよかったな。