ダブステッパーに限らず、ダブを愛するモノたるやオーガスタス・パブロの名前はマスト。家に最低3枚。これ常識。僕は、若い頃、パブロのライヴは2回とも行った。これ超自慢です。
今週末、パブロの息子(お父上は1999年に亡くなられている)のアディス・パブロが来日します。名義は、SUNS OF DUB。西から東へ5都市でツアーを開催します。東京では、こだま和文さんが出演します。その低音で、台風なんか吹っ飛ばして。
===================================================
SUNS OF DUB JAPAN TOUR 2014
10/10(金) 大阪 @ROCKETS info: https://nambarockets.com/
10/11(土) 愛知 @TOYOTA ROCK FESTIVAL info: https://toyotarockfestival.com/
10/12(日) 静岡 @朝霧Jam info: https://smash-jpn.com/asagiri/
横浜 @ex-Bodega info: 045-242-5553
10/13(月・体育の日) 東京 @KATA + Time Out Cafe & Diner[LIQUIDROOM 2F]info: LIQUIDROOM 03-5464-0800 https://www.liquidroom.net/
===================================================
<東京公演概要>
liquidroom presents
──PABLO & KODAMA──
オーガスタス・パブロ、そのダブの系譜を継ぎ、そして前進させる者たち
1973年のルーツ・ダブのクラシック中のクラシック『King Tubbys Meets Rockers Uptown』をはじめ、自身のメロディカ、そしてタビーによるミックスによってルーツ・ダブのスタイルを提示したオーガスタス・パブロ。自身のレーベル〈Rockers Internationl〉を中心に展開した、ストイックにラスタな、そのルーツ・スタイルは、1999年の没後も、ルーツ・ダブに限らず、さまざまなダ ブ/ベース・ミュージックに影響を与え続けている。その“系譜”を継ぐ”SUNS OF DUB、彼らがKATAにてライヴを行う。パブロの意志を引き継ぐメロディカ・マスター、ADDIS PABLOとセレクターのRAS JAMMYによるプロジェクト。〈Rockers Internationl〉を引き継ぎ、さらにはこれまでにディプロ率いるMajor LazerやToddla Tといった新世代のデジタル・ダンスホール系のアーティストとも共演するなど、現存のベース・ミュージックとの邂逅など、新たなスタイルの創出に余念がない。さらには、MUTE BEAT時代の名曲"Still Echo"にて、オーガスタス・パブロとの共演も果たし現在も日本のレゲエ・ダブ・シーンを牽引するトランペッター、こだま和文、そして“Apach”のカヴァー7インチをリリースしたばかりのトロンボーン奏者、KEN KEN率いるKEN2D SPECIAL、とダブを新たな解釈で突き進める、2アーティストのライヴも行われる。
featuring live
SUNS OF DUB(ROCKERS INTERNATIONAL)
ADDIS PABLO(SON OF AUGUSTUS PABLO MELODICA MASTER)
RAS JAMMY(ROCKERS INTERNATIONAL SELECTA)
feat. JAH BAMI
こだま和文 from DUB STATION
KEN2D SPECIAL(Reality Bites Recordings)
dj
Q a.k.a. INSIDEMAN(GRASSROOTS)
Yabby
SEIJI BIGBIRD/LITTLE TEMPO
2014.10.13 monday/holiday
KATA + Time Out Cafe & Diner[LIQUIDROOM 2F]
open/start 16:00 close 21:00
adv.(9.13(sat) on sale!!)* 2,000yen door 2,500yen
*PIA[P code 243-948]、LAWSON[L code 74932]、e+、DISK UNION(取扱店選定中)、Lighthouse Records、LOS APSON?、LIQUIDROOM
info LIQUIDROOM 03-5464-0800 https://www.liquidroom.net/
---
▼SUNS OF DUB(ROCKERS INTERNATIONAL, Kingston, Jamaica)
ADDIS PABLO[Melodica], RAS JAMMY[Selecta]
ジャマイカの若獅子、アディス・パブロは99年に44歳の若さで亡くなったルーツ・ロック・レゲエ/ダブ・プロデューサー、メロディカ奏者の父、オーガスタス・パブロのスピリチュアルな音楽を21世紀に継承、発展させる新世代アーティストである。89年生まれのアディスはニュージャージーとジャマイカを行き来して過ごし、キーボードとメロディカを習得。2005年にはオーガスタス・パブロの追悼公演でステージに立ち、ロッカーズ・インターナショナルのヴェテラン・ミュージシャンや伝説的ギタリスト、アール・チナ・スミスと共演、これを機にソロ奏者としてダブ・レゲエの作曲を開始する。10年、アディスはトリニダードからジャマイカにやって来たラス・ジャミーと意気投合し、"サンズ・オブ・ダブ"として伝統的なロッカーズ・サウンドをニューエイジのフォーマットによるダブ・レゲエで提示するべく活動を共にする。11~12年の"For The Love Of Jah"、"13 Months in Zion"以降、100作以上をデジタル・リリース、またメジャー・レイザーのウォルシー・ファイアー、クロニックス、プロトジェイ、クライヴ・チン、マイキー・ジェネラル等、幅広いコラボレーションを展開している。13年には初のヴァイナル・レコード"Selassie Souljahz In Dub"を発表、ヨーロッパ・ツアーを成功させ、英BBCのデヴィッド・ロディガンの番組では「キング・タビー、オーガスタス・パブロ以来のベスト・ダブ・レコードの1枚」と評される。14年にはオランダのJahsolidrockからアディス・パブロ名義の1stアルバム『IN MY FATHERS HOUSE』がリリースされ、北米、ヨーロッパ各国のフェスティヴァル出演で賞賛を浴びている。サンズ・オブ・ダブはダブのニューウェイヴ、ドラム&ベース、ダブステップ、トラップ、ハウス等のクラブミュージックとの触媒として貢献する、ロッカーズ・インターナショナルの新世代である。
https://sunsofdub.com/
https://soundcloud.com/sunsofdub
https://www.facebook.com/sunsofdub
https://www.facebook.com/sunsofdub
▼こだま和文 from DUB STATION

1981年、ライブでダブを演奏する日本初のダブバンド「MUTE BEAT」結成。通算7枚のアルバムを発表。1990年からソロ活動を始める。ファースト・ソロアルバム「QUIET REGGAE」から2003年発表の「A SILENT PRAYER」まで、映画音楽やベスト盤を含め通算8枚のアルバムを発表。2005年にはKODAMA AND THE DUB STATION BANDとして 「IN THE STUDIO 」、2006年には「MORE」を発表している。プロデューサーとしての活動では、FISHMANSの1stアルバム「チャッピー・ドント・クライ」等で知られる。また、DJ KRUSH、UA、EGO-WRAPPIN’、LEE PERRY、RICO RODRIGUES等、国内外のアーティストとの共演、共作曲も多い。現在、ターン・テーブルDJをバックにした、ヒップホップ・サウンドシステム型のライブを中心に活動してしている。また水彩画、版画など、絵を描くアーティストでもある。著述家としても「スティル エコー」(1993)、「ノート・その日その日」(1996)、「空をあおいで」(2010)「いつの日かダブトランペッターと呼ばれるようになった」(2014)がある。
▼KEN2D SPECIAL(Reality Bites Recordings)
TRIAL PRODUCTIONのトロンボーン兼MCを務めるKEN KEN(トロンボーン&MC)によるソロDUBプロジェクトとしてスタート。現在はICHIHASHI DUBWISE(DUB mix)、Gulliver(guitar)の3人編成で活動中!BEASTIE BOYSからの影響を独自にREGGAE DUBにトランスフォーム!!!??したサウンドは、DUCK SOUP PRODUCTIONS、PART2STYLEから数々のアナログ7インチをリリースし、そのほとんどは即完売し入手困難なアイテム多数。2008年にはPART2STYLEから初のアルバム『Reality Bites』をリリースしイギリス国営放送BBCの番組など複数で紹介され、有名誌"WIRE"にレビューが載るなど注目を集めた。2013年自らのセルフ・レーベル<Reality Bites Recordings>を立ち上げ7枚目の7インチ・シングル「I Fought The Law」をリリース、あのDon LettsもBBCで即座にプレイ!前代未聞のド・オリジナル解釈で驚きのカバー曲を連発してるKEN2D SPECIALですが、今年2014年9月には8枚目の7インチEP、APACHEをリリース、こちらもまたKEN2D節炸裂してます!要チェック!!!!
https://m.facebook.com/profile.php?id=503540573038521&_rdr
▼Q a.k.a. INSIDEMAN(GRASSROOTS)
東京・東高円寺の桃源郷レゲエ・バーNATURAL MYSTIC育ち。レコードショップWAVEにてバイヤー経験の後に、NATURAL MYSTIC閉店後の97年同所にてGRASSROOTSをオープンする。「MUSIC LOVERS ONLY」を掲げ、バーであってバーでない、クラブであってクラブでない、人間交差点音楽酒場代表となる。INSIDEMAN名義でのMIX-CDは異才フィメール集団WAG.より『YGKG』、 POSSE KUTから『DEAR』、地下最重要レーベルBlack Smokerより『Back In The Dayz』などリリースしている。
https://insideman-q.blogspot.jp/
https://www.grassrootstribe.com/




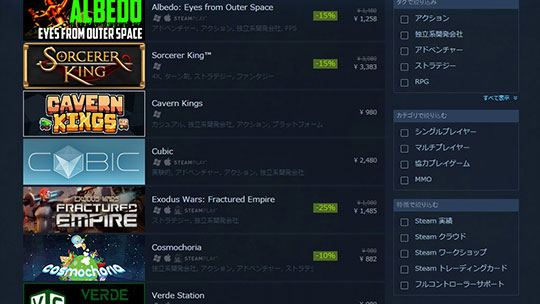
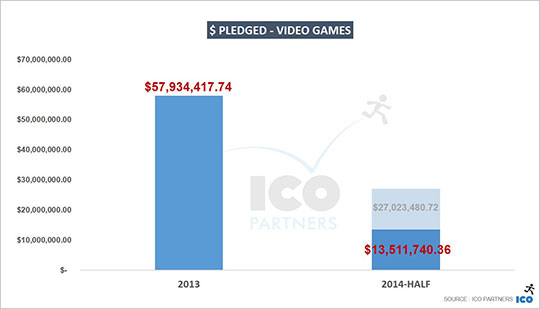







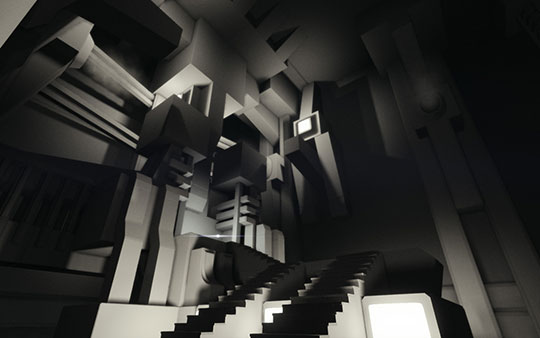








 五野井郁夫/Ikuo J. Gonoï
五野井郁夫/Ikuo J. Gonoï 若山忠毅/Tadataka Wakayama
若山忠毅/Tadataka Wakayama

