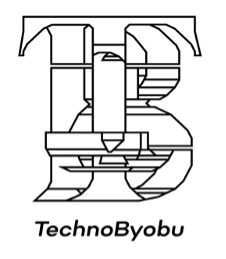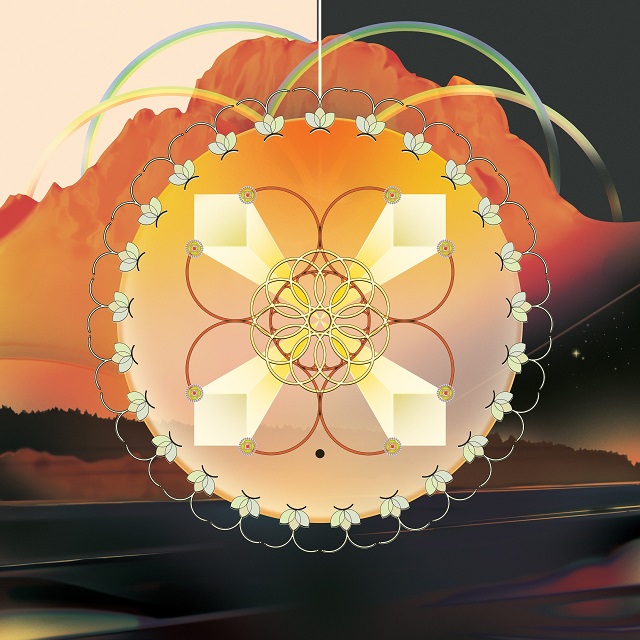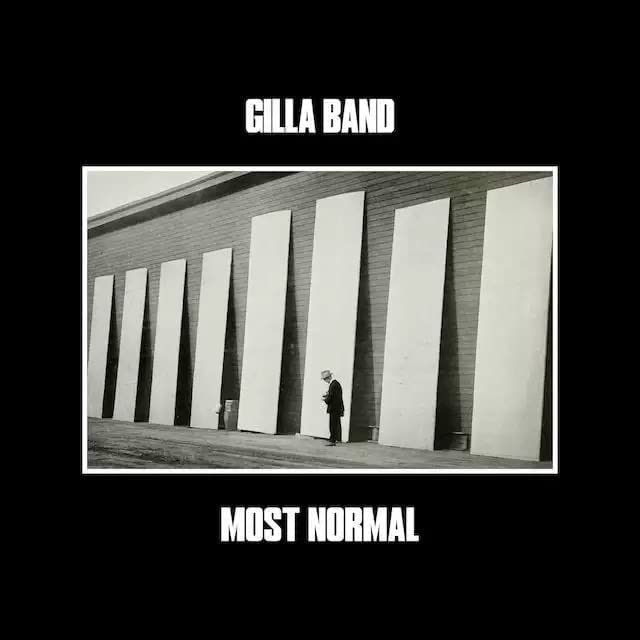自分はジャズ・シンガーになるんだと思っていた。でも、インディ・ロックもジャズも、実験的で自由なように思えて、じつはすごく保守的。フリー・ジャズとかも、音的には形は自由かもしれないけれど、服装や演出の面ではスタイル的にコントロールされていると思う。
掛け値なしに素晴らしいアルバムだ。ケレラ・ミザネクリストスの、実に5年ぶりのニュー・アルバム『RAVEN』。ここには──素晴らしい作品が常にそうであるように──個人的な経験や生々しい現実の語りと、内面世界の探究の結晶化の両方がある。「私」と外の世界との摩擦から生じたもがきや苦しみ、そして、ひとり部屋に閉じこもって、ときには涙を流しながら音やテキストと戯れて深めた思索。『RAVEN』は、彼女の外にも中にも存在しているそういった二面性、多面性を積極的に肯定する作品だ。
キーになっているのは、ブラック・フェミニズムやインターセクショナリティについての思惟である。2022年9月、まだアルバムのリリースすらアナウンスされていなかった頃、『デイズド』に載ったインタヴューには、『RAVEN』を理解するためのヒントが散りばめられている。たとえば、序文には、彼女が、黒人差別やフェミニズムに関する本、ポッドキャスト、動画などの詰め合わせを友人や家族、ビジネス・パートナーたちに送った、と書かれている。自身が学んだことを人びととシェアして、自分が所属する小さなサークルから少しでもベターな社会を構築していくための、ささやかでたしかな行動。『RAVEN』は、そういった抵抗と対話のアクションの延長線上で、ケレラからリスナーの手に直接渡された小包のような作品でもある。
さらに、次のインタヴューでは、彼女が誰に語りかけているかを明言している。歌詞は、黒人たち、女性たち、ノンバイナリーたちのためのものだと。そして、明確な対象に語りかけているそれらの言葉は、そうであるからこそ、誰にとっても力強く歌えるものなのだ、とも言う。バラバラに散らばって、疎外され、抑圧された「ひとりたち」のあいだに細い糸を通して結びつけ、小さくひそやかな声で交信すること。ケレラの音楽は、差異と分断の時代に、差異と分断を前提にしながら、苛烈な闘争と政治のその先を優しく提示しているようにすら思える。
だからこそ、『RAVEN』は、アップリフティングなダンス・アルバムでもある(まるで、ビヨンセの『RENAISSANCE』のように)。“Happy Ending” の扇情的なジャングルから “On The Run” のセクシーなレゲトン、“Bruises” のミニマルなハウス、“Fooley” のダブまで、ダンス・カルチャーやレイヴへの愛に満ちている。彼女はダンス・ミュージックの逃避性について「クラブは現実を知るための場所だ」と言い切るが、その言葉はクラブの音楽やカルチャーについての、とても誠実で聡明なコメントだと思う。そうでありながらも、ここでは、たゆたうアンビエントR&Bすらも等価に溶け合っている。ケレラはいま、サウンドの海を自由に泳ぎまわっているのだ。
『Cut 4 Me』(2013年)や『Take Me Apart』(2017年)の頃から考えると、彼女はずいぶん遠くまで来た。言い換えれば、彼女の新たな音楽の旅がここからはじまっている、とも言える。さあ、あなたもオールを握って、ケレラと新しい海に漕ぎだそう。ただ、そこに浮かんでいるだけでもいい。目の前には、苦痛も涙もよろこびも受け入れる、穏やかな場所がある。
エレクトロニック・ミュージックは白人の判断が基盤になっていて、「白人、テクノ、ストレートな男」みたいなイメージがあるし、一方で伝統的なR&Bやソウル・ミュージックを聴くのは黒人女性のイメージで、そういう人たちはエレクトロニック・ミュージックは聴かない。私はずっと、このふたつの間でつねに交渉をしているような状態だったんです。でも、「もういいや」と思えた。
■こんにちは。本日はよろしくお願いします。そちらは朝ですよね?
Kelela:そう。もしかして私の声でわかったとか(笑)? 昨日ニューヨークからロンドンに来たところで、まだこっちの時間に慣れようとしているところで(笑)。
■そうなんですね(笑)。早速インタヴューをはじめさせていただきますが、『RAVEN』は本当に素晴らしいコンセプト・アルバムでした。ダンサブルなのに、聴いていると、あなたの内面世界に深く導かれたような気分になります。
Kelela:ありがとう。
■まず、アルバムについて具体的にお聞きします。一貫した流れを感じるダンス・アルバムだと感じるのですが、ダンス・カルチャー、クラブ・カルチャーからあなたが得たもの、学んだことを教えてください。
Kelela:まず、私が初めてダンスやクラブ・カルチャーに触れたときのことを思い出すと、私は普通とは違うレヴェルのパーティーに足を踏み入れていたんですね。説明するのがすごく難しいんだけれど、LAには本当に様々なクラブ・シーンがあって。言語は同じだったかもしれない。けれど、ストレートな白人によるテクノ・シーンと、私がLAに来たときに初めて衝撃を受けたダンス・ミュージックの空間は全く違うものでした。私が入り込んだダンス・ミュージック界にはいろんなタイプの人たちがいたんです。アメリカには、ブラック・ダンス・ミュージック限定の空間もある。でも、私が通っていたのは、そっちでもなかった。ハウス・ミュージックやテクノをベースとした音楽が多いなか、私が通っていたのは、フリークス(変わり者たち)がいる空間だったんです。つまり、エキセントリックなキャラクターや様々なバックグラウンドを持つクィアたちが集まっていて、とてもミックスされた空間だった。
■なるほど。
Kelela:でも、私のクラブ・カルチャーの経験でいちばん印象的だったのは、「匿名性」ですね。初めて本物のパーティーに足を踏み入れたような感覚を覚えたんです。その空間に私を連れてきてくれたのは、私の友人のアシュランド(トータル・フリーダム)です。彼は、私を誘い込んだ張本人で、私のレコーディング・セッションに立ち会っていたことがあるらしく、私が歌っているところを目撃したときに、そのシーンが私に合うと思ったみたいで。あれは、大晦日のパーティーでした。当時はLAにぜんぜん友だちもいなくて、ひとりで過ごすことも多かったし、ちょうど別れを経験したところでもあったから、彼にメッセージを送ったんです。私は、そのときはまだ彼のことをよく知らなかったんだけど、メッセージを送ってみたら、彼からの返事に書いてあったのは、4つの数字と住所だけ。
■えっ(笑)!?
Kelela:すごくミステリアスな文章に惹かれて、私はその家に行ってみたんです。そしたら、そこがとにかく巨大な家で、びっくり。それで、入ってみると、本当にたくさんのキャラクターがいて。コスプレしてる人もいれば、仮面をかぶっている人もいるし、とにかくいろんなキャラクターがいて、本当に楽しかった。そして、「この場所では自分がなりたいものになれる」という感じがしました。判断や批判をされることもなく、他人とちがうことをしたり、変わった方法で自分を表現したいと思ったりすることで、仲間外れにされることもないんだって。他にも経験したダンスやクラブ・カルチャーのシーンはあるけれど、それが私がLAにきて入り込んだ空間でした。
■素晴らしい経験ですね。
Kelela:私が音楽を作りはじめたとき、その基盤は、私がそのシーンに触れる前から築かれていたと思う。ジャズもそうだし、どのように実験し、どのように音楽を作るのかを教えてくれたものは、たくさんあるから。でも、あのシーンは、私になんの制限もない居場所を与えてくれたように感じます。そして、もっと探求できる方法があることに気づかせてくれた。最終的に、自分にはいろいろな姿があるんだ、と思えるようになったんです。それまでは、自分はジャズ・シンガーになるんだと思っていたけど。私はポスト・バップ系のジャズ・シンガーになるんだろうなって。でも、インディ・ロックもジャズも、実験的で自由なように思えて、じつは、実験をしながらもすごく保守的。彼らの実験は特定の枠のなかでおこなわれていて、私にはジャズにも音楽のルールがある気がして。フリー・ジャズとかも、音的には形は自由かもしれないけれど、服装や演出の面ではスタイル的にコントロールされていると思う。それに、ジャズ・ミュージシャンになると、ジャズ・ミュージシャンとしてジャズの空間に追いやられているようなところもあるんじゃないかと。ジャズ・シンガーがダンス・ミュージックやポップ・ミュージック、インディ・ミュージックのような世界に進出するのは難しいし、稀なことなんですよね。いまでこそ、少しはそれができるようになってきたかもしれないけれど、当時はとても無理な話だった。そういう意味でも、他のシーンは、将来は他のサウンドを追求したい、実験してみたいと思っていた私にとっては、良い踏み台にはならなかったと思う。
■そうだったんですね。
『Aquaphoria』は、初めて存分にアンビエント・ミュージックの実験ができたレコードなんです。あのレコードで私は、アンビエント・ミュージックを完全に探求することを自分自身に許したんですね。『Aquaphoria』を作ったあとも、あの感覚から抜け出せなかったんですよね。
Kelela:あと、私は、自分に本当にヘヴィでハードなプロダクションが必要なこともわかっていました。私の声は風通しがいいというか、柔らかいんですよね。だから、私が一生懸命に叫んで、声で怒りを表現しているときでも、なんだかかわいらしく聞こえてしまう(笑)。なので、基本的には、自分の声とプロダクションでバランスを取りたくて。それが、よりヘヴィなプロダクションを選んだ大きな理由のひとつです。それは、さっき話したダンス・シーンが私に与えてくれたもののひとつだと思う。最初にそのシーンに触れたときの衝撃は、私にとってすごく爽快なものだったし、すごく豊かだった。だから、このシーンに惹かれたんです。このシーンは、遠くに飛躍するための本当に自由なキャンバスを私に与えてくれたし、そのキャンバスの上ではなんでも探検できるような気がして。『Aquaforia』(2019年に〈ワープ〉の設立30周年を記念しリリースされたミックスで、エングズエングズのアスマラとの作品)はその典型的な例ですね。多くの人は、私がダンス・ミュージックを作っているから、ヘヴィなプロダクションで、純粋にソフトなアンビエント・サウンドを探求することには興味はないだろうと思うかもしれない。でも、私は『Aquaforia』で、そのキャンバスを皆に提供しようとしたんです。
■『Aquaforia』は素晴らしいミックスでした。
Kelela:もうひとつは、クィアと黒人、黒人と女性であることを同時に経験するような、インターセクショナルな経験がある場合、その交差によって、様々な拠りどころや特異なアイデンティティを理解できるようになると思うんですよね。もちろん、ストレートの白人男性たちがみんな偏った考え方でセンスがない、というわけではないけれど、正直に言って、厳格さというものは、大抵の場合、白人性から生まれる。というのも、有色人種のクィアたちは、みんな白人社会の中で育ってきたから、多くの白人の拠りどころを理解しているんです。そして、それに加えて有色人種の間でも育ってきた経験のある彼らは、他の多くの拠りどころを理解することもできる。だから、私が投げかけるものがなんであれ、彼らはそれを理解しようとする気持ちがあるんです。それが、私が感じたダンスやクラブ・カルチャーの美しさだった。それは、私が音楽業界に入ったときのシーンの雰囲気や前例とは非常に対照的でした。私が最初にこのシーンに入ってきたときは、インディの全盛期のような雰囲気だったから。でも、LAに引っ越してきて、初めてそのカルチャーに出会ったんです。
■よくわかりました。『RAVEN』のサウンドとビートは、ジャングルからUKガラージ、ダブなど、とても多彩ですよね。特に、ジャングルのビートが印象的でした。これらのダンス・ミュージックは、若い頃、思春期に出会ったものなのでしょうか?
Kelela:ダンス・ミュージックに関して言えば、アメリカのメインストリーム以外のものに初めて触れたのは、ナップスターが登場したとき。私は、周りで最初にナップスターをはじめたひとりだったんです。友だちと一緒にナップスターに夢中になっていて。大抵、周りは年上のお兄ちゃんやお姉ちゃんを通してそういう音楽を見つけていたけど、私には兄も姉もいないから、すべてはナップスターでした。当時、家のコンピューターが私の寝室にあって、私はそれを大きな特権だと感じていて(笑)。それで、寝る前にランダムにいろんなものをクリックして、音楽をダウンロードしていたんです。ダウンロードされるまで、何が出てくるかわからない。寝る前にサイコロを振って、朝にその目が出る、みたいな感じ。朝起きると、まるで抽選会みたいでした(笑)。運が良ければ、良いトラックに出会えた。ダウンロードがうまくいかなかったり、まだ70%しかダウンロードできていなかったり、ダウンロードできてもめちゃくちゃだったりするから。
■ナップスターとは意外ですね(笑)。でも、世代的によくわかります。
Kelela:私はいろいろなものをダウンロードしていたけど、ある日アートフル・ドジャーの曲がダウンロードされてたのは、いまでも覚えています。それから、クレイグ・デイヴィッドの曲もたくさんあった。まだクレイグ・デイヴィッドがソロ・アーティストとして登場する前の話。彼の曲をベッドルームで発見したとき、そのプロダクションがあまりにも衝撃的で、信じられなかったのを覚えています。いま、説明しながら汗ばんじゃうくらい(笑)。新しい何かを見つけた感覚と、秘密というか、私だけの何かを自分で見つけたような気がして。イギリスではすごく人気だったんだろうけれど、ワシントンDCの郊外に住んでいた私にとっては、ものすごく大きな発見でした。そのあとから、それ系のダンス・ミュージックや関連するものを探し続けて。そうやって、自分にとって神秘的なものを見つけていったんです。「このスピードアップしたヴォーカルはいったい何!?」って思っていましたね。当時、アメリカにはそんな音楽はなかったから。インターネットがいまほどは普及していなかったから、美的感覚が太平洋を越えるのには、まだ時間がかかっていた時代だった。だから、私にとって、そういう音楽を見つけられたのは、すごくパワフルなことでした。
■その話題につなげると、あなたは以前からUKのプロデューサーやシーンとの関わりが深いですよね。今回、特にUKのダンス・ミュージックの要素が色濃くなった理由は?
Kelela:今回のアルバムを作りはじめるとき、私は、「自分が望むものであれば、何をつくってもいいんだ」と思うことができていたんです。ヴォーカル曲みたいな領域から初めて、それをリミックスでダンス・ミュージックの領域に移動させたり、改めて解釈しようとしたりしなくてもいい、と思ったんですね。以前は、いまはいない観客を取り込むことに興味がありました。でも、同時に、R&Bが好きな人たちが留まることができるものを作りたかった。つまり、ヘヴィなヴォーカルの瞬間がある一方で、プロダクションが好きでエレクトロニック・ミュージックに傾倒している人たちも満足できるような音楽。だから、私は音楽を作りながら、その両者を満足させようと、ずっと考えていました。
■まさに、それこそが、あなたの音楽のアイデンティティですよね。
Kelela:その理由は、私は自分がそのふたつのものに繋がっていると感じているから。このふたつは、私がやっていることの大きな柱なんです。でも、この二面性を行ったり来たりしてしまうと、一体どっちなのかがわからなくなってしまうので、なんとかできないかと考えていました。だって、そのふたつって、全然ちがうからね。エレクトロニック・ミュージックは、白人の判断が基盤になっていて、「白人、テクノ、ストレートな男」みたいなイメージがあるし、一方で伝統的なR&Bやソウル・ミュージックを聴くのは黒人女性のイメージで、そういう人たちはエレクトロニック・ミュージックは聴かない。だから、もし実験的な音楽が盛り込まれすぎていたら、彼女たちは、いったい何が起こっているのかって混乱してしまうかもしれない。それもあって、私はずっと、このふたつの間でつねに交渉をしているような状態だったんです。
■なるほど。
Kelela:でも、『RAVEN』を制作しているときは、「もういいや」と思えた。難しく考える必要はなく、ふたつの場所を行き来しようとしなくても、自分がいる場所をそのまま表現すればいいんだって。直感的なものを書いて、サクサク進めていけばいいんだと思えたんです。ポップ・ライターと一緒に曲を書くつもりもなかったし、参考にするものも自分の身近に存在しているものでよかった。それもあって、自然に、いままででいちばんダンス・ミュージックにフォーカスしたレコードになったんだと思います。
[[SplitPage]]
私は、泳ぐことができるんです。このアルバムで、私は、サウンドの海を泳ぎまわれているような気がします。アルバムを理解できない人や興味を持てない人がいても、そんなことはどうでもいい、と思えた。それを理解してくれる人たちだけに、何かを届けたいと思ったんです。
■その一方で、ビートのないアンビエント的なプロダクションの曲も要所に配置されています。ドラムレス、ビートレスの曲にシンガーとしてどのようにアプローチしましたか?
Kelela:『Aquaphoria』は、初めて存分にアンビエント・ミュージックの実験ができたレコードなんです。あのレコードで私は、アンビエント・ミュージックを完全に探求することを自分自身に許したんですね。あのプロジェクトであそこまでアンビエントを感じ、それを探求できたことは、とても実りのある経験だった。だから、『Aquaphoria』を作ったあとも、あの感覚から抜け出せなかったんですよね。あのレコードを制作したあと、もっとアンビエントな音楽を聴きつづけて、特に2019年の秋はずっとずっとそういうものを聴いていたから、あのとき、私はまさにアンビエントのゾーンにいたんです。そして、そのときから OCA のレコードも聴きはじめたんだけれど、それはまるで、私が美しいゾーンにいるような感覚だった。それが『RAVEN』に引き継がれたんだと思います。
■ええ。
Kelela:2020年の1月に、今回のアルバムの制作を始めた頃、OCA に声をかけました。OCA に「次のアルバムでもっとアンビエントを実験したい」と言ったら、彼らは「もちろん」と答えてくれたんです。しかも、彼らは、自分たちの曲の私のミックスを聴いて、「泣いた」とも言ってくれた。しかも、そこから深く影響を受けて私を気に入ってくれたらしく、じつは私が声をかける前から、私といつかコラボできたときのために、すでに曲を作ってくれていたんです。それを聴いて、私は「すごい!」と思いました。本当に美しくて、とても意味があった。そして、初めて彼らと一緒に作業をはじめたときは、もう魔法みたいな瞬間でしたね。アンビエントなサウンドを、実験しながら即興を乗せていく、すごくリッチな時間。
■素敵なエピソードですね。
Kelela:私は、ハードなサウンドが好きな人も、ハードなサウンドだけが好きとはかぎらないと思うし、実際、みんな、柔らかさというものをどこかに求めていると思うんです。だから、私は、LSDXOXO のビート主体のトラックと、アンビエントでビートレスな私自身が探求したいサウンドを合わせて、その意味を見出そうとした。それをどうやったらいいのかはわからなかったけど、とにかく納得できるまでやってみようと思ったんです。そうやって夢中になって作業していると、その週の終わりには、15曲中13曲が完成していました。そして、それらの曲は、ビートをベースにしたトラックとアンビエントなトラックのあいだを行ったり来たりしていたんです。正直なところ、そのふたつの組み合わせがどう意味をなすのか私にも完全にはわからない。でも、説明のできない意味をなしているように感じるんですよね。とても自然に、それができ上がっていました。
■そのふたつの同居こそが、このアルバムの肝だと思います。
Kelela:このアルバムは、私がアーティストとして生きている場所と同じ。私は、泳ぐことができるんです。このアルバムで、私は、サウンドの海を泳ぎまわれているような気がします。今回は、アルバムを理解できない人や興味を持てない人がいても、そんなことはどうでもいい、と思えた。それを理解してくれる人たちだけに、何かを届けたいと思ったんです。いまの私は、そんなふうに考えられるようになっている。そして、その場所にいることがとても幸せです。この場所にいたら、もっと良い音楽を作ることができると思うから。
私にとって、クラブは何かから逃げ、忘れる場所ではないんです。クラブは、現実を知るための手段であり、感情的な体験から抜け出すのではなく、むしろ、そこに入っていくためのもの。
■「海を泳ぐ」ということに関連してお聞きすると、前作やそれ以前と比べて、あなたのファッションやヴィジュアル表現もずいぶん変化しましたよね。カヴァーアート(ジャケット)の写真は、プレス・リリースにある「社会の中で虐げられた黒人女性としての視点」というテーマを表しているように感じます。カヴァー写真が表しているもの、カヴァーの制作プロセス、『RAVEN』のヴィジュアル・コンセプトについて教えてください。
Kelela:あのアヴァターのことは知ってます? ケレラ・アヴァター。彼女は、何年か前からすでに何度か登場していて、最初のひとつはリミックス・プロジェクトでした。あのプロジェクトでは、私の顔を3Dスキャンしたんです。で、実際に3Dの胸像を作った。で、それにいろんなウィッグをかぶせて実際に写真を撮りました。つまり、あなたが見ているのは偽物。要するに、すごくメタヴァースなイメージなんです。『Aquaphoria』のアートワークにもアヴァターを使ったけれど、私は、彼女はもう一度命を吹き込まれる必要があるんじゃないかと感じたんですよね。
■なるほど。
Kelela:私は、このアルバムは、「水」が中心になっていると思うんです。水の中を移動しているような、もしくは洗礼を受けて生まれ変わったような、そんな感じ。私が経験したことの再生、みたいな感じがする。そして、水は浮遊するのを助けるだけでなく、地面に叩きつけてあなたを痛めつけることもできるように、幅広さを持っている、という面もあります。私も同じなんです。だから、水の中に存在する、あの幅が好きなんだと思う。そして、私は、その両方を表現したかったんだと思います。何か困難なことを乗り越えつつも、浮かんでいる私。水が、私をどこかに導いて、連れて行っているんです。私の顔は水に完全に取り囲まれているけれど、私の顔には穏やかさがある。私自身には、あのカヴァー写真は、水に沈められそうになりながら浮いているような、そして、困難な状況にいながらももがき苦しんでいる様子を感じさせない何かがあると感じるんです。水が暗くて、色が黒いのもあり、不吉な海だという雰囲気を漂わせながらも、私は空回りしているわけでも、苦労しているわけでもない。あの水は、深くて暗い海で、感情の奥底のようなもの。あれは、その深海に身を置きながら、その中に完全に入り込む方法、居場所を見つけた私の姿。私の中の交点があの場所なんだと思います。
■歌詞についてもお聞きしたいです。“Raven” に「I’m not nobody’s pawn」というリリックがあり、タイトル・トラックがアルバムのメッセージを集約しているようにも感じます。“Raven” のリリックについて教えてください。
Kelela:“Raven” は、サウンド的には、最初にアスマラのシンセで実験したサウンドに魅了されて作りはじめた曲です。そのサウンドをどう表現しようか、という感じで作りはじめました。あの曲は、すぐにビートが来るんじゃなくて、長いビルドアップがあるんですよね。そして、そこに到達したとき、私にとっては、ダンスフロアを一掃するような瞬間を思い起こさせるんです。あれは、クラブでいちばん美しい瞬間だと思う。DJがそれをやれば、それがその夜のピークになるような。一掃するというのは、みんながいなくなるという意味ではなくて、立ち止まって両手を挙げるような感覚。個々のカタルシスのようなものかな。誰もが自分だけの時間を過ごしているような、でも、それを他の人びとと一緒に経験しているような、そんな感じのことです。
■わかります。
Kelela:シンセを聴いた瞬間に、「これならあの感覚を味わえる!」と思った。クラブに活力を与えるような、そんなサウンドを作りたいと思ったんです。クラブ・ミュージックやクラブ・カルチャーでは、何かから逃げるような──特に、生き延びるためのエスケーピズム(実生活や現実などからの逃避主義)が構成要素になっている部分がある。私はそれを批判するつもりはないけれど、アーティストとしての私は、自分の貢献や自分の音楽が、逃げるのではなく、人びとが物事に直面するのを実際に助けることを望んでいます。私の音楽が、人びとが実生活に直面するのを助け、彼らが得るカタルシスが、それに対処する助けになることを本当に願っているんです。クラブから帰って朝目覚めたとき、本当に起こっていることについて何も考えられない状態でいるよりも、実際に直面していることに対処するための活力を感じてほしい。私にとって、クラブは何かから逃げ、忘れる場所ではないんです。クラブは、現実を知るための手段であり、感情的な体験から抜け出すのではなく、むしろ、そこに入っていくためのもの。クラブで涙を流すというのは、『Cut 4 Me』以来、私のモットーでもあるんです。その感覚を伝えたいとずっと思っていたんだけれど、それがうまく表現できずにいました。私は、自己発見、自己肯定、そして解放的な音と文化の体験に興味があって、それが、私が自分の音楽を通して人びとに与えたいものなんです。クラブにいる人たちにとって、実際に起こっていることを忘れるための手段は提供したくない。だって、それは現実ではないから。逃げるだけでは、朝起きたときにその現実が戻ってきて、最悪な気分になってしまう。私は、クラブをそんな存在にしたくないんです。クラブは、私にとって大好きな場所であってほしい。私が好きなクラブは、帰り道で私を泣かせてくれるクラブなんです。朝起きて、友だちに電話して、「すごいクレイジーな経験をしたんだ!」って言えるような。泣いて、話して、すごく気分が良くなるような。ちょっと二日酔いで頭が痛くたって、自分に気合を入れられたと思うことができればそれでいいんです。
私たちがダンス・ミュージックとして知っているものの多くは、黒人が発明したもの。それなのに、そのシーンで黒人が疎外感について話したり、尋ねられたりするのはどうしてなんでしょうか?
■さらにアルバムの核心に迫りたいのですが、昨年の『デイズド』や『ガーディアン』のインタヴューでは、ブラック・フェミニズムについて熱心に語っていましたよね。『Take Me Apart』などの過去の作品では表現されていなかったので、驚きました。冒頭でもインターセクショナリティについて言及していましたが、アフリカン・アメリカンであること、かつ女性であることが、『RAVEN』のコア・コンセプトになった背景について教えてもらえますか?
Kelela:自分のなかで、ブラック・フェミニズムという枠組みが、より明確になったんだと思います。これが革新的な概念だとはまだ言いがたいけれど、言えることは、ブラック・フェミニズムの理論が、多くの社会正義に枠組みの原動力になっている、ということ。エイジアン・ライヴズ・マター運動のようなものも、そのひとつ。アメリカや世界の有色人種にとって、こういった運動の理解の枠組みは、女性であるアメリカの黒人理論家に由来するところが大きい、というのはあると思う。私にとって、それはつねに明確ではあったんだけれど、この場所にもっと足を踏み入れる前に、もっと調べたり読んだりする必要があった。いまは、それができた状況なんです。そういう研究を、私はずっと続けてきました。
■そうだったんですね。
Kelela:でも、ここ数年は、ダンス・ミュージックにおける自分の経験、つまり交差的な経験を点と点で結びつけ、この領域で自分が直面している疎外とは何なのかを理解しようとしているんです。肌の色が明るいアーティストではない私は、色彩主義(colorism)というのは、国際的な言説になっていないような気がします。たしかに、アメリカでは黒人が虐げられているけれど、少なくとも、ダンス・ミュージックや音楽ビジネス全般において、色彩主義をめぐる言説は、世界中の多くの人びとがもっと注目して、考えるべきことだと思う。黒人女性は、音楽業界からの初期投資がない限り、オーディエンスから発見してもらうこともできません。そして、音楽業界は、反射的に肌の色が明るいアーティストに投資するんです。私が白人女性としてこれまで作ってきたような音楽を作っていたら、もっと大きな存在になっていたと思う。地球上のもっと多くの人が、私の名前を知っていたと思う。それが起こらなかったのは、サウンドのクオリティのせいではないんです。ただ、人びとがより明るい肌の身体からこの種の音楽が生まれるのを見たいということと、音楽ビジネスの専門家たちにとって、より市場が強いことが関係しているだけ。
■ええ。
Kelela:ブラック・フェミニズムは、これらのことが同時に進行していることを理解するのに役立つ枠組みだと思います。音楽全般、特にダンス・ミュージックにおいて、黒人女性としての自分の現実を解体するために使える枠組みなんです。私たちのジレンマは、自分の仲間たちに関係している空間のなかで、どうしてこんなに疎外感を感じてしまうのか、ということ。私たちがダンス・ミュージックとして知っているものの多くは、黒人が発明したもの。それなのに、そのシーンで黒人が疎外感について話したり、尋ねられたりするのはどうしてなんでしょうか? これは本当にクレイジーな現実で、そのなかで経験する不協和音の体験はおかしなものです。そこで何が起こっているのかを理解するためには、たくさんの本を読み、リサーチをする必要があります。このアルバムで、誰に語りかけるかという点で中心になっているのは、黒人、女性、ノンバイナリーの人たちです。歌詞を書くときは、車を運転しながら、歌詞を叫んでいる彼らの姿を想像しながら書きました。彼らが叫べるような歌詞にしたいと思って。彼らが叫べば、その周りの人びとにも力を与えられるから。ノンバイナリーである黒人が叫べる歌詞なら、それはどんな人も力強く歌えるような歌詞になるはずだと思ったんです。
■そのとおりだと思います。いま、エイジアン・ライヴズ・マター運動にも言及されましたが、パンデミックの影響で日本を含むアジア人は酷い差別を受けました。また、同質性の高い日本社会には、いまも外国人差別があります。レイシズムや色彩主義に対して、歌や音楽ができることはどんなことだと思いますか?
Kelela:アジア人差別は、私がとても興味を持っていることのひとつ。次のインタヴューでは、ぜひそれについて話してみたい。日本でそのような経験をしたことがある人に話を聞いてみたいんです。誰かがこういうトピックについて自分が考えていることを話せるような場を設けることができたら、最高。歌や音楽は、そういう問題に対して、間接的に何かをしているとは思います。人びとがもっと勇気づけられ、もっと肯定され、もっと自分の価値を明確に感じられるようにすることで、その手助けをしていると思う。そうすれば、この世界で人びとがもっと大きな声を出すことができて、自分はひとりではないんだということを知ることができるから。そして、その体験がつながりを生み、その人たちが解放される瞬間になる。それは、すごく意味があることだと思います。
■わかりました。質問は以上です。ありがとうございました。
Kelela:素晴らしい質問をありがとう。