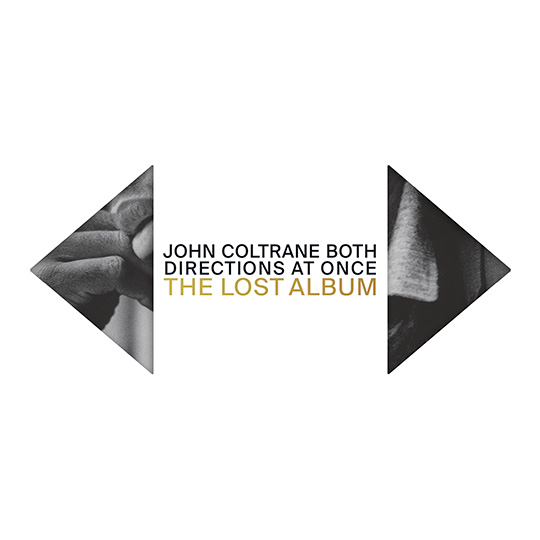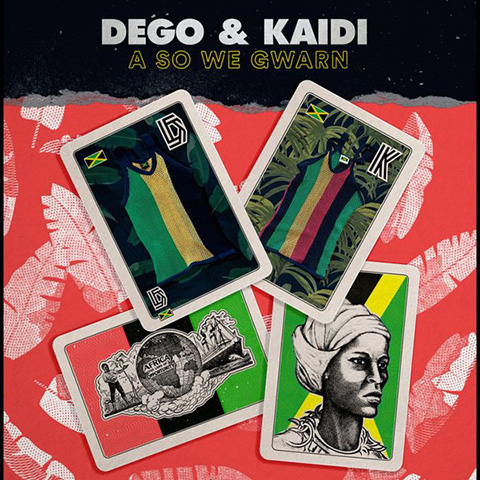XXX(エックスエックスエックス)テンタシオンとジミー・ウォポが相次いで撃たれて亡くなった。20歳と21歳。前者はこのところアメリカのヒップホップにおいて高まっていた世代間の確執では中心人物とも言える存在で、しかし、そのことと撃たれたことは関係がなかったらしい。後者も同じくで、強盗か何かに撃たれたらしく、メジャーと契約を交わしたばかりというタイミングだった。このふたりの死から導き出されるのはヒップホップとか文化に関する話題であるよりは、やはりアメリカの銃社会にまつわる議論に終始するべきだろう。警察とのトラブルではないので、ブラックライヴスマターの案件ですらない。
実は紙エレキング用に5月の時点で書いた原稿にXXXテンタシオンにも触れていて、そのときにはドレイクやミーゴスと対立するXXXテンタシオンをケンドリック・ラマーが支持するのかしないのか曖昧なままにしてあったんだけれど、訃報が伝わった直後にケンドリック・ラマーどころか「どれだけ君にインスパイアされたかわからない」というカニエ・ウエストやディプロ、ジューシー・Jやマイリー・サイラスなど多くのミュージシャンたちが彼の才能に賛辞を惜しまないツイートをアップする事態となっている(意外とマンブル派ではなくJ・コールのようなリリカル派からリアクションが多い。マンブル・ラップというのは何をラップしてるのか内容がわからないと揶揄されているラッパーたちのことで、フューチャーやミーゴスが代表とされる)。もしかすると黒人版ニルヴァーナのような存在になったかもしれないことを思うと、それなりに納得はするものの、一方で、白人の男の子をステージ上で絞首刑にするという映像表現や妊娠中のガールフレンドに暴力を振るい、その映像をバズらせて喜んでいたことは彼の死に同情できないという声を多く呼び寄せる事態にもなっており、彼の才能の是非についてはXXXテンタシオンが生きていて、彼自身の活動によって証明する以外に方法はなかったとも思う。この3月にはビルボードで1位を獲得したというセカンド・フル・アルバム『?(Success&Victory)』もケンドリック・ラマーと同じく僕も5回ほど聴いてみたけれど、そこまでの作品には思えなかったし(大ヒットした“Sad!”より“Moonlight”の方が良かった気が)、やはり昨年、オーヴァードーズで亡くなったリル・ピープ同様、ロックになったりラップになったりというスタイル(エモ・トラップ)は興味深いものの、これまでのラップのスタイルに取って代わる「叫び」を体現したという評価はやや早計な見解ではなかっただろうか(叫んでいるときはラップじゃないし)。
ちなみに紙エレキングの記事でXXXテンタシオンはスポティファイから削除されたと書きましたが、正確にはレコメンド機能から外されただけで、聴くことは可能のようです。(三田格)