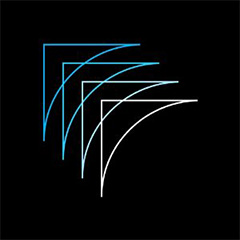この日ユニットに集まった人びとは、ピンチが2台のターンテーブルの前に立っていた150分間に一体何を期待していたのだろう。やはり、彼がシーンの立役者として関わったダブステップか? それとも、彼の新しいレーベル〈コールド・レコーディング〉で鳴らされる、テクノやUKガラージがベース・ミュージックと混ざり合った音だったのだろうか? ピンチがフットワークを流したら面白いな、なんて想像力を働かせていた人もいたのかもしれない。
実際に会場で流された音楽は、それら全てだった。
ジャー・ライト、エナに続いたピンチのステージは、テクノの轟音とともにはじまった。そこに重低音が混ざるわけでもなく、リズム・パターンが激しく変化するわけでもなく、ストイックな四つ打が会場を包み込んでいく。
ピンチがロンドンでダブステップの重低音を体感し、それをブリストルへ持ち帰り自身のパーティを始めるまで、彼はミニマルやダブ・テクノのDJだったのだ。ここ1年でのピンチのセットのメインにはテクノがあるわけだが、自分自身のルーツに何があるかを理解しないうちは、新しいことなんぞ何もできない、と彼は証明しているようにも見える。
〈コールド・レコーディングス〉から出たばかりの彼の新曲“ダウン”はまさにテクノと重低音、つまりピンチ過去と現在が混ざり合った曲だ。
先日発売された同レーベルの初となるコンピレーション『CO.LD [Compilation 1] 』は、去年の4月からレコードでのみのリリースをまとめたものになっており、参加しているエルモノ、バツ、イプマン、エイカーという新進気鋭のプロデューサーたちは、自分たちを形作っているジャンルの音を現在のイギリスのシーンに置ける文脈のなかで鳴らしている。
例えば、イプマンはダブステップの名門レーベル〈テンパ〉や〈ブラック・ボックス〉からのリリースで知られていたが、〈コールド・レコーディング〉から出た彼の曲“ヴェントリクル”では、テクノの要素が前面に押し出されており、意外な一面を知ったリスナーたちを大きく驚かせることになった(イプマンがレーベルのために作ったミックスではベン・クロックが流れていた)。
「アシッド・ハウス、ハードコア、ジャングル、UKガラージ、ダブステップ以降へと長年続く伝統からインスピレーションを受けた、進化し続ける英国のハードコア連続体の新たなムーヴメントのための出口」が〈コールド〉のコンセプトだが、ピンチ自身と彼が選んだプロデューサーたちは、伝統から学ぶスペシャリストである。このコンピを聴くことによって、それぞれのプロデューサーたちの影響源だけではなく、彼らの目線を通してイギリスのクラブ・ミュージックの歴史までわかってしまうのだ。
Ipman Cold Mix
開始から30分ほどして、流れに最初の変化が訪れる。ピンチは若手のグライムのプロデューサーであるウェンによるディジー・ラスカルのリミックス“ストリングス・ホウ”をフロアに流し込んできた(彼のミックスの技術はずば抜けて高く、色の違う水が徐々に混じっていくようなイメージが浮かぶ。手元にはピッチを合わせてくれたり、曲の波形を可視化してくれるデジタル機器は一切無く、レコードのみだ)。今年に入りアコードをはじめ、多くのDJにサポートされてきたアンセムはオーディエンスたちにリワインドを要求させたが、「まだ早いよ!」といわんばかりにピンチは4つ打へと戻っていく。
Dizzee Rascal-Strings Hoe-Keysound Recordings ちなみに、この日流れていたテクノも面白いチョイスだった。「うおー! これDJリチャードの〈ホワイト・マテリアル〉から出たやつだ!」という情報に富んだ叫び声が聞えてきたのだが、DJリチャードはジョーイ・アンダーソンやレヴォン・ヴィンセントと並ぶ、アメリカ東海岸のアンダーグラウンド・シーンにおけるスターだ。彼らが作る曲はときに過剰なまでのダブ処理が施され、リズムにもヴァリエーションがあるため、ベース・ミュージックのシーンでもたびたび耳にすることがある(ペヴァラリストのセットにはしばらくレヴォン・ヴィンセントの“レヴス/コスト”があった)。
おそらく、アメリカで育った彼らも、スコットランド生まれブリストル育ちのピンチと同じようにベーシック・チャンネルのうつろに響くミニマル・テクノを聴いてきたのだろう。国境を越え、似たルーツを持ち違った土壌で生きるプレイヤーたちが重なり合う現場には驚きと喜びがつきものだが、この夜はまさにそんな瞬間の連続だった。
とうとう、この日最初のリワインドがやってくる。ピンチがマムダンスとともに〈テクトニック〉からリリースした“ターボ・ミッツィ”が流れるとフロアが大きく揺れ、DJはレコードを勢いよく、そして丁寧に巻き戻す。だが、直ぐに頭から曲は始まらない。ピンチは拳で自分の胸を叩いて、フロアに敬意を示す。するとイントロのシンセサイザーがじわじわとフロアに流れ始めた。気がつくと、フロアはオーディエンスではなくパーティの熱気を作り上げるDJの「共犯者」で埋め尽くされていたのだった。
「Yes, I’m」という声ネタとハンド・クラップが鳴り始めた瞬間、フロアの熱気はさらに上がる。それは、ブリストルのニュー・スクールの優等生であるカーン&ニークの“パーシー”を、ふたりが成長する土壌を作り上げたピンチが流すという、感動的な場面でもあった。世代から世代へと時代は嫌でも変わっていくものだが、この日34歳の誕生日だったピンチはその変化を楽しんでいるようだった。
ラストのダブステップからジャングル、フットワークという流れにいたるまで、フロアをDJはロックし続けた。曲が鳴り止むとピンチはフロアへ合掌し、オーディエンスとゴス・トラッドに拍手の中で150分間のロング・セットは幕を閉じた。