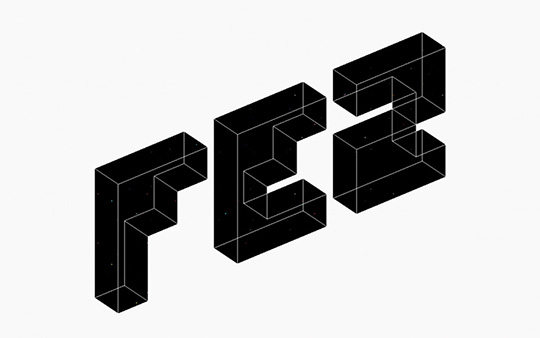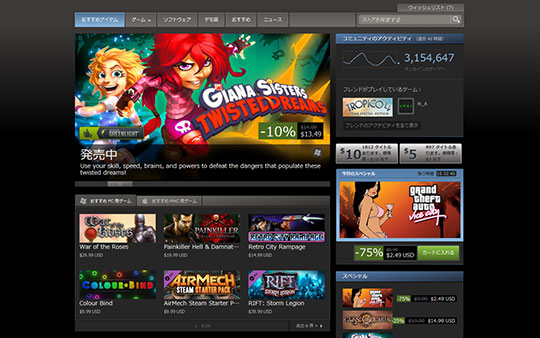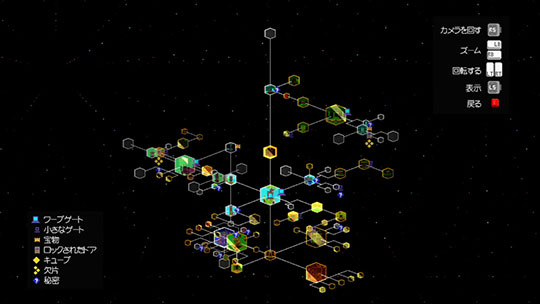トクマルシューゴ In Focus? Pヴァイン |
素敵なメロディのポップ・ミュージックとして気軽に楽しむこともできるし、次々に変化していく緻密な音の組み合わせや謎めいた歌詞をじっくり味わうこともできる。トクマルシューゴの『イン・フォーカス?』はそんなアルバムだ。
80年代末から90年代の前半にかけて、既成の音楽の要素をサンプリングして再構成する作り方が広まったとき、編集感覚という言葉が脚光を浴びた。しかし既成の要素を再構成するだけでは、批評的な機能は果たせても、新しい音楽は生まれにくい。方法のいかんにかかわらず、創造的であるかないかを分かつのは、意識的にせよそうでないにせよ、作り手の音楽的意志の存在ではないのか。手法の目新しさが一段落したとき浮上してきたのは、やはりそのような伝統的な原則だった。
とはいえ、いったん編集感覚を体験した後で、それ以前の世界に戻ることもできない。トクマルシューゴの音楽は、そんな時代の悩みと喜びの渦の中から登場してきた。
制作や記録方法のデジタル化が進むにつれて、音楽の制作や流通でサーヴィスやおまけ化と、アート志向への分極が進んでいるが、彼の音楽はそのどちらでもない。彼は自分で楽器を演奏して多重録音するという、いまでは伝統的となった方法のひとつで音楽を作っている。『イン・フォーカス?』でも彼は世界のさまざまな文化から生まれたアコースティックな楽器を数多く演奏している。そこには響きが出会い、交錯しては、別れていく豊かな空間と時間がある。それでいて音楽全体はデジタルな時代の編集感覚に包まれているのだ。
ぼくにとっては不思議なところをいっぱい持っている彼に会える機会をいただいて、話を聞いてきた。
自分のなかの世界に閉じこもって作っちゃっていたからかもしれないですが、曲たちが勝手に人格を持ちはじめたというか......キャラクターのように見えてきたんですね。それぞれの曲が自我とおのおのの意見を持つようになったという感覚が生まれてきて(笑)。
■今回のアルバムのレコーディングはどんなふうにしてはじまったんでしょう?
トクマルシューゴ(以下トクマル):前作を2年半ほど前に作り終えて、そのあといろんな種類の曲をいっぱい作りたいなと思いまして。好きな音楽を聴き直して、こんな音楽をやりたいなというのをもういっかいあらためて試して、録りためていったという感じですね。そうやってはじまりました。コンセプトを決めて作ろう、と考えていたわけではなくて。わりとファースト・アルバムとか、初期のアルバムを作るような感覚に近いかもしれないです。
■最近はデジタルの配信なども多くなってきていて、アルバム単位ではなくて楽曲単位で発表される方が増えていると思うんです。でも今回のアルバムは、1曲1曲もとても丁寧に作っていらっしゃいますが、間にインストの曲がはさまっていたり、エンディングも工夫があって、アルバムとしてのまとまりを意識されているのかなと。
トクマル:世代的には、まだ音楽はアルバムで聴くという習慣があったほうですし、性格的にもそうなんです。でも1曲単位で聴いたり、適当につまんできて聴いたりする時代でもあるのは事実なので、欲張りに(笑)、どちらにも対応したくなってしまいますね。1曲にもものすごく時間をかけて、1曲でも聴けるように。さらにアルバムにしたときにアルバムっぽくも聴こえる、っていうのが理想だとは思っていて。それを追求してるんですけど、まだまだ先は長いですね。
■いやいや。バランスがとれていて素晴らしいなと思いますよ。曲順やアルバム・タイトルは、ある程度曲がたまってから決められたんですか。
トクマル:そうですね。そういうパターンが多いです。
■その場合、たとえばこの曲を1曲めにしようとか、ここにインストゥルメンタルを入れようとかっていうのはどんなふうにして決まっていくんですか?
トクマル:そうですねえ......それが今回いちばん難しくって、曲を作りすぎたというのもあるんですけど、まずアルバムにしたときに聴きやすい時間――自分がいつもアルバムを聴いてちょうどいいなと思うくらいの時間なんですけど――に収めようとすると、だいたい15曲ぐらいかなと。それで、ほんとは歌ものとインストゥルメンタルを半々くらいで入れたかったんですけど、やってみるとあんまりうまくいかなくて、インストゥルメンタルが、歌もののあいだにちょっと挟むっていうアクセント的な扱いになってしまったところはあります。曲順は迷いながらですね。
■インストゥルメンタルのほうも同時進行ですか?
トクマル:同時進行です。インストの楽曲の方ができる確率が高くて。「歌ものを作ろう」っていうふうにはやってなくて、インストっぽいかたちを作ってから歌を乗っけるほうが多いからかもしれないです。
■タイトルの『イン・フォーカス?』というのは、「?」がついていますがこのタイトルに込められているのはどんなようなことなんでしょう。
トクマル:自分のなかの世界に閉じこもって作っちゃっていたからかもしれないですが、曲たちが勝手に人格を持ちはじめたというか......キャラクターのように見えてきたんですね。それぞれの曲が自我とおのおのの意見を持つようになったという感覚が生まれてきて(笑)。それで、見ているうちにそれらが揉めだすというか、争いだすというか......(笑)。それがなんか、現実世界と似たような感じになってきまして。ひとつの国ではないですが、たとえば日本とかアメリカとか、同じひとりの人間が作った曲なのにキャラクターがわかれて争いだして、けれどそれで成り立っているという感じが出てきたんです。いいのか悪いのかちょっとわからないんだけど、そのままで進んでいるっていう。これが正しいのか正しくないのか、焦点が合っているのか合っていないのか、というところで「?」がついています。「フォーカス」という言葉をつかったのは、ジャケットの写真のように、螺旋階段に虫眼鏡をあてて、フォーカスがあっているのかな? っていう感じにしたかったからです。
■そういうアイディアは昔から自然に湧いてくるほうだったんですか?
トクマル:そうですね、わりとひとりで考えて想像しているタイプではありましたけど......創造的なタイプ、という感じではないと思うんですけどね。
■ぼくも閉じこもってぼんやりしていることが多いんですけど、文字通りぼんやりとして、空白のままなんですね。
トクマル:(笑)
■だからいろいろイメージが湧いてくる人がうらやましいですけどね。あと、夢を見てすぐ忘れる人と覚えてる人がいますが、ぼくはたぶん見てるはずなんですけど、すぐ忘れちゃうんです。だから夢を見てノートをつけている方は、素晴らしい記憶力と才能だなあと。
トクマル:はははは。無理やり起きて、日記をつけてる感覚なんで、記憶力より意地でつけてる感じはありますね。
[[SplitPage]]子どものころはピアノをやっていて、10代半ばでギターをはじめて、ギターを突き詰めようと思ったんですけど、突き詰めようと思えば思うほど、だんだんほかのこと、ほかの楽器がやりたくなったりもしてきて。それで、いろんな楽器をいいなと思ってちょっとずつ買い集めているうちに、楽器のかたち自体というものにすごくとりつかれてしまって......
 トクマルシューゴ In Focus? Pヴァイン |
■歌でいちばん最初に録音したのはどの曲ですか。
トクマル:うーん、よく覚えていないんですよね。たぶんまとめて歌は録ったんだと思います。
■アルバムにまとめようという段階で歌詞をつけていって、歌も録っちゃったという感じですか。
トクマル:歌詞はいちばんあとですね。
■歌詞のイメージはどこから湧いてくるんでしょう? 曲によるかとは思うんですが。
トクマル:夢日記をつけたりしていたんで、いままでのアルバムはそこからとっていたんですけど、今回のは半々くらいですかね。1曲1曲に夢のイメージとプラス自分の言葉をつけ加えるといったかたちです。でも、歌詞はすごく苦手なので......
■曲も詞もできない凡人から見ると、そのプロセスは本当に不思議なんです。
トクマル:そうですねえ、僕もポンポン出てくるわけではないので、どうやっていいのかわからないまま無理やりひねり出しているという感覚があって。もともと本当に作れなくて、たまたまつけていた夢日記からとってみたらなんとなく合った、というのが最初なので、その延長で足したり引いたりしています。単語のストックがあんまりないし、本もそんなに読むほうではないので、自分の想像できる範囲内でしか言葉が浮かんでこない。そのなかでなんとか......「でてこい」って感じで(笑)、がんばって当てはめてますね。
■かつてロック畑には、でたらめな英語の鼻歌で歌って、後からそれに近い日本語に入れかえて、つじつまを合わせて歌を作っていった人もいました。一種の遊びなんだけど、遊びに終わらないものに仕上げていく。そういう、鼻歌で歌って、そのあと整えるといったようなことはあるんですか?
トクマル:そうですね、鼻歌のような感じでメロディを入れていくという、仮歌というのはありますね。
■トクマルさんにとって歌詞はどのくらい重要なんでしょう? 夢日記からも使われているということですが。
トクマル:うーん、そうですね......。歌詞に関しては難しいところですけど、まずはじめに、夢日記を使い出したというのは、歌詞を書く段階でとくに誰かに伝えたいことがなかったからということがあったりして。夢日記の言葉を使うときでも、具体的な言葉を削除していくようにしていて、たとえば「Pヴァイン」っていう言葉があったとすれば「Pヴァイン」という言葉を使わないで、なにかほかの言葉に置きかえていく。そうすると自然とふわっとした歌詞になってしまって。それを乗せて自分の曲を聴いてみると、その、なにもわからないですよね(笑)。もう、なにを言いたいのかがまったく。自分でさえわからないという状況で、ただなんとなく物語や想像はどんどんふくらんでいくし、その状態をただただ楽しんでいるという感じに近いですね。歌詞が重要かといえば、その意味では重要なんですかね。逆に選び抜かれた言葉というか。
■『新古今和歌集』の象徴的な言葉とか、説明されなければよくわからない、あるいはもうすでに意味のわからなくなっている枕詞とか。そういうようなものに近いんでしょうか。後世の人はそんなふうにこの詞を読むかもしれないですね。押韻はどうですか? 意識されているように感じますが。
トクマル:どうなんでしょうね。自然になっちゃうものかもしれないです。
■フォークの人がギターでコードを弾きながら曲の構成を考えて、メロディを作っていったというのが一方にあるとすれば、ヒップホップ以降だと思いますが、リズム・トラックやループみたいなものを作ってそれにあわせてあまり起承転結のないメロディやフレーズを乗せていくものが他方にあるのかなと思うんですが、トクマルさんの音楽を聴いているとどちらでもないという感じがするんです。シンプルなメロディとギターがいちばん基本にあるのかなと思ったりはするんですが。
トクマル:いちばん強いメロディというか主旋律を軸にして、それを一本立ててから、そのまわりにたくさんの細かいフレーズをまとわりつかせているというか。ひとつの塔のようにしている感じです。コードで作りはじめたり、リズムで作りはじめたりというのではなくて。リズムから作るにしても、それはメロディアスなリズムであったりとか、わかりやすいものであることが多くて、そこにフレーズや楽器で色づけをして曲を大きくしていくっていう、そういうかたちですかね。
■典型的なロックのバンドだと、まずドラムのパターンを決めてベースのパターンを決めてといったふうにフォーマットで曲を作っていくということが多いかと思うんですが、そういう束縛から自由であるように見えますね。
トクマル:作曲のしかたについては、現代音楽の人たちのやり方とかをよく本で読んだりするんですけど、固定の概念にとらわれない作り方がいっぱいあって、そのなかから自分に合うやり方を探していったというのが近いです。僕はなにかすごくアーティスティックなやり方ができたりするわけではなかったので、まずメロディを作って、というわりと基本的な方法をとっています。
■ひとりでレコーディングをされているということが、それを助けてもいるんでしょうね。伝統的な意味でのポップスやR&Bに似ている部分もあるんだけれども、なにかちがうなと感じるのは、そういう根本的な曲作りのあり方のちがいなんですね。定形のポップスにおもしろさがあるのはわかるけれども、そこには同時に不自由さもあって、どちらかに開き直っちゃうとつまんなくなるんだけど、両方の可能性を探りながらやってらっしゃる感じがおもしろいです。
ところで、楽器をたくさん使ってらっしゃいますね。ディスクにいろんな楽器の音源のサンプルが収録されて付属しています。これは何か、わけがあるのですか?
トクマル:子どものころはピアノをやっていて、10代半ばでギターをはじめて、ギターを突き詰めようと思ったんですけど、突き詰めようと思えば思うほど、だんだんほかのこと、ほかの楽器がやりたくなったりもしてきて。それで、いろんな楽器をいいなと思ってちょっとずつ買い集めているうちに、楽器のかたち自体というものにすごくとりつかれてしまって......なんだろう、これは? っていう(笑)。宇宙人とかからしてみれば、なんだか得体の知れないかたちをした、そのモノ自体。今度はそれを集めたいという衝動に駆られるようになってしまって、どんどん買っていくから楽器だらけになって、せっかくなんで録ってみよう、という感じが強かったですね(笑)。
■そうは言っても、それぞれの楽器が要求する技術というものがあると思うんですが。すべての楽器に習熟されているわけではないでしょうし、大変だったでしょうね(笑)。
トクマル:そうですね、大変でしたね! もっと時間があれば。もっと楽器を練習してすべてうまくなりたいという気持ちはあるんですけどね......。
■基本的にはめずらしいサウンドやかたちであったりというのが、使うきっかけみたいなものになったんですね。で、それが自分の音楽にふさわしいと。あるいは自分で探していた音に近いものが、そこでたまたま見つかったり。
トクマル:ああ、たまたま見つかる、ということはありますね。楽器を好きになったせいか、いろんな音色を探すためにいろいろなCDを買ったりするようにもなりました。「めずらしい楽器」みたいなCD。
■自分で新しい楽器を作っちゃったりとか。
トクマル:そこまではしないですね(笑)。
[[SplitPage]]だんだん自分の音の1個1個のなかにオリジナルをちょっとずつ超えてるものがあるのが見えたりすることもあって。たとえばリズムであったりメロディであったり。それをちょっとずつ積み重ねて、組み合わせていってみよう、それがわりと間違いじゃないと考えられるようになってきましたね。
 トクマルシューゴ In Focus? Pヴァイン |
■"Gamma"って曲を聴いたときに、マリンバ風っていうか、パーカッシヴな心地よい音が入っていて・・・ブラジルのウアクチってバンドご存じですか?
トクマル:はい、はい。
■彼ら、ビニール・パイプとかで打楽器みたいなの作ったりしていますけれども、そういうものに通じるような気がしたんですが、特に関係はないですか?
トクマル:これはパーカッシヴなイメージと民俗っぽい音色を足して、子どもが喜びそうな、スピーディでわかりやすいメロディを作ってみたいと思って。
■トクマルさんはいっぱい音楽を聴いていらっしゃると思うんですが、世界には伝統的なスタイルのポピュラー・ミュージックがたくさんありますね。それぞれ独特の間とかリズムを持っているんだけど、そういうものを真似ようというつもりはないんですよね? 、「トップランナー」というテレビの番組に出られたとき、観客の人たちに手拍子を打ってもらうくだりがあって、あれはキューバ音楽のクラーべというパターンに近いものですよね。
トクマル:そうですね。
■でも、曲自体はキューバ音楽とは縁もゆかりもないという(笑)、その組み合わせがおもしろいなと思ったんですね。日本人は几帳面だから、自分が素晴らしいと思う音楽があったら、勉強してまねることができちゃう。けれど、そういう方向性じゃないですね。トクマルさんが几帳面じゃないという意味ではないんですが。
トクマル:ぼくも、どちらかというと几帳面で、はじめはまず完全に真似てみたりするんですよ。
■あ、そういうプロセスを経てるんですか。
トクマル:いちど完全に真似てみて、でも聴き比べてみると、やっぱりどう考えても追いつけないレベルだったりするんです。結局それはぼくでしかないというか、ぜんぜん本物の音楽の足元にも及ばないなって気づいてしまうと、やっぱり人には聴かせられないというか。でもそういう作業をいっぱいしていくと、だんだん自分の音の1個1個のなかにオリジナルをちょっとずつ超えてるものがあるのが見えたりすることもあって。たとえばリズムであったりメロディであったり。「あ、この音楽にはないけど、僕の作ったものにはちょっといいメロディがあるな」とかって思えたものをちょっとずつ積み重ねて、組み合わせていってみよう、それがわりと間違いじゃないと考えられるようになってきましたね。
■リズムの面でも音色の面でも、ロックだけやっている人よりずっと間口が広いですよね。トクマルさんの音楽をロックと呼ぶのかどうかわからないんですが(笑)。今回はいつもより各地の伝統的な生楽器の音が目立つようには作ってあるかなと思いました。これは意識されていたんですか?
トクマル:さっきの音の人格化の話のつづきのようでもありますけど、だんだん(アルバムのなかに)いろんな世界の人たちを住まわせよう、みたいな感覚になってきて。たとえば東南アジアの人とか南アメリカの人とかを、ちょっとだけ限定的に、現実寄りに想像してみたときに、南アメリカなら南アメリカの楽器を持ってきちゃおうと思ったんです。それでその音を入れてみたら、いままでのアルバムよりもうちょっとだけ現実味が出たというか。
■あまりアーティストに曲のことをこまごまときくのは申し訳ないんですけれども、"Decorate"という曲はどのようにしてできたんですか?
トクマル:ジャケットのデザインもそうなんですが、螺旋というか、円というか、回っているという自分のなかのイメージを再現したものですね。ちょっとサビも強めの曲を作ってみたいなと思って。
■アレンジの段階で、ラテン系の曲とかあるいはカリプソなんかを参照にするようなことはあったんですか?
トクマル:特別にこれということはないんですが、今回はわりとそういうものが残りましたね。
■スティール・パンっぽい音の聴こえる、"Call"ですとかね。"Shirase"は、ちょっとフォルクローレっぽい。他にアメリカの伝統的なフォークを思わせるものもあるし、サンバっぽいものもある。一枚岩ではぜんぜんないですね。10代の頃はアメリカにいらっしゃったそうですけど。
トクマル:アメリカに行ったのは、そもそもアメリカの古いミュージシャン、レジェンド的なミュージシャンを観たいと思ったのがきっかけだったんです。
■古いというのはどのあたりの?
トクマル:たとえばジャズの大御所......エルヴィン・ジョーンズとか。演奏できるおじいちゃん、他にも日本に来ないような人たちがいっぱいいたので。来てもブルーノートとか、大きなところでしか観れなかったりしましたし。そういう人たちを身近に、真後ろとかから観たい! と思いました。そうするとサポート・ミュージシャンが南米の人たちだったりすることが多かったし、連れまわっているので、どうしても目が行っちゃうんですよね。そういう人びとに惹かれたというのが、当時の体験として強く残っていますね。
■そのあたりから南米の音楽も聴きはじめたということですか。
トクマル:はい。特にキューバ、行きたいなと思ってるんですがまだ行けてないんですよね。
■アメリカに行ったらキューバや南米の人たちとかがいっぱいいた、という感じなんですね。
トクマル:そうですね。いてくれた、という感じです。それ以外にもさまざまな国の凄腕ミュージシャンたちが集まっていて、その体験は大きいですね。
■レコードやCDをこっちでたくさん聴いてから行ったというよりは、まず向こうで生で体験したことなんですね。
トクマル:そうですね。ギターから入ったので、ギター・ミュージックの中に入っているパーカッションってイメージで、ラテンの音楽も聴いていました。生で聴くと、CDに入らない音っていっぱいあるんだなって思うことがありましたね。そこでしか伝わらない......音というか。そういう体験がはじめにありました。
[[SplitPage]]ひとつの楽器に精通してる人はとくにそうなんですけど、それだけしか見てない感じだと思うんです。それで、そういう生き方もあるんだなって。それは「仕事にする」という感覚じゃないなと思ったんです、たぶん。それがその人にとって生きるということなんだなと思って。
 トクマルシューゴ In Focus? Pヴァイン |
■そのころはジャズをやっていたんですか? ジャズ・ギターが好きだった?
トクマル:ジャズ・ギターがそんなに好きになれなかったので、ジャズ・ピアニストの音楽ばかり聴いていたんですが。ジャズ・ピアノをギターで弾いてみる、みたいなことをやってましたね。
■じゃあ、そのころはもう音楽を仕事としてやっていこうと思っていたわけですか。
トクマル:うーん......そうですねえ、たぶん。仕事という感覚もなかったかもしれないですけどねえ。なんか、そういう生き方ができるんじゃないかなあって......。やっぱり、アメリカに住んでいるミュージシャンたちもそういう感覚というか。見てないんですよね、まわりを。ひとつの楽器に精通してる人はとくにそうなんですけど、それだけしか見てない感じだと思うんです。それで、そういう生き方もあるんだなと思って。
それは「仕事にする」という感覚じゃないなと思ったんです、たぶん。それが、その人にとって生きるということなんだなと思って。僕はそれができなかったんですけどね。いろんな楽器に手を出して、作曲をしたりして。
■どうしてそういう興味の持ち方になったか、考えたことがありますか。
トクマル:それは、ひとつのものに執着している人を見てたからかもしれませんね。そういうことはぼくにはできないなという諦めでもあったかもしれないですけど。ほんとはやってみたかったという気持ちもあったんですけど、でもほかにやりたいこともありましたしね。作曲だとか、楽器を集めたり、弾いたり、CDを出してみたいって気持ちもあったり。
■トン・ゼの影響についても耳にしてるんですが。
トクマル:もちろん好きで(笑)。変わった人が好きで、よく聴いていました。たまたまそれに影響されてるような曲が何曲か入ってたっていうお話じゃないかと思うんですが。
■具体的には、どのあたりの曲なんでしょう?
トクマル:"Porker"とかじゃないですかね。ああいう、へんな音楽を追求している人は大好きで、よく聴いてますね。
■ブラジルはほんとに、へんな人が多いですよね。ほかの国だと、伝統なら伝統、伝統に背くなら背く、ってはっきりしてるんだけど、ブラジルはすごく曖昧な人がいっぱいいて。
トクマル:ははは! 曖昧な人多いですよね(笑)。
■あとこの、"Ord Gate"。どういう意味なんでしょう?
トクマル:「オード」は「オーディナリー」の「オード」ですね。
■歌詞の世界が、カフカに通じるような気がして。
トクマル:特に何かを意識したというわけではないんですが......
■トクマルさんの歌を十分理解できているかどうか自信がないんですが、イメージとしてカフカに通じる作品が他にもいくつかあるように思いました。
トクマル:(激しく咳き込んで)すみません、咳がとまらなくて。あさって雅楽を観にいくのに、こんなんじゃ追い出されそうですね......。
■雅楽お好きなんですか?
トクマル:はい、すごい好きで。たまたま宮内庁で定例でやっている演奏会に行けることになったので、行ってみようと思ってるんですが、咳が出そうになって、地獄のように耐え忍ばなければならないかもしれないですね(苦笑)。
■雅楽っていえば、奈良の春日大社で12月におん祭りっていうお祭りがあって、山の中にいる神様をその日だけ公園のお旅所ってところまでお招きして、民の奏でる音を楽しんでもらってお帰しするっていう日なんですけど、午後から夜10時くらいまでずーっと芸能の奉納があって。
トクマル:へえー、うんうん。
■暗くなってからは雅楽とか舞楽が延々と続くんです。実際その場で聴いたのは去年がはじめてだったんですけれど、いやすごいなと思いました。あれは何なんだろうとか思いますよね。
トクマル:思いますよね。ほんとに不思議な世界です。なんか、すべてをくつがえされるような思いになります。いつも聴くと。
■ああいうテンポというか、リズムがあるのかないのかわからないような世界とトクマルさんの音楽とは、いちおう対極にありますよね。
トクマル:そうですね(笑)。でもそういう「瞬間」みたいなものを取り入れることはあるんですけどね。それをフルに1曲にするということはいままでのところないですね。いつかやりたいとは思うんですけど。
■今回のアルバムは、果てしなく楽器が出てくるなかで、雅楽的な音色に聴こえる部分もあったりするかもしれませんね。(封入されているイラストを見ながら)ボーナス・ディスクに入ってる楽器の中で、これは笙でしょう?
トクマル:そうですね。
■以前、若いアーティストさんに笙を吹いてもらうレクチャー・コンサートを開いたことがありますが、あれはすごいですね。こんな音が出るのかって。
トクマル:あれも僕は正確な演奏の仕方がわからなくて。
■電熱もってきてあたためながらね。
トクマル:そうですそうです、大変ですよね。むかしの人はどうやってたんだっていう。
■(笑)。ちょっと変わった印象を受ける"Pah-Paka"ですが、クラシック風の曲ですけれども、これはどのようにしてできたんですか。
トクマル:音数の多いものを声でやったらおもしろいかなって。どうやって作ったかとなると言いづらいんですが、一瞬だけクラシックっぽい旋律を入れたりして......遊んでますね。気に入ってる曲です。
■インストの曲で、"Micro Guitar Music"ですけど、この弦楽器の部分のリズムは、たとえばアイリッシュ・フォークとか意識したものですか?
トクマル:特に考えていたわけではないですが、ギターだけで遊んでみようかなって、早回しの技術も好きだったんで早回しもやってみたり、それで展開のあるような、小曲っぽい感じにしました。これもクラシックっぽいつくりで展開していくような曲ですね。
■"Katachi"って曲では途中で不思議な弦楽器の音がするんですが、これは何ですか?
トクマル:シタールと大正琴の音を混ぜたらどうなるのかなと思ってやってみたら、こんな音になりました。
■スタッフ・ベンダ・ビリリってコンゴ民主共和国の車椅子ストリート・バンドご存知ですか? そこに男の子がいて......
トクマル:ああ、へんな自作楽器弾いてますよね。
■1弦のね。音色がちょっと、あれに近いかなと思ったりして(笑)。
トクマル:ははは!
■これ、合成されたということは、発想としてはシンセサイザーと近いものがありますよね。
トクマル:ああ、そうかもしれないですね。
■でも基本的には、電気よりは生の楽器の音がお好きなんですね。
トクマル:そうですね、電気を使う楽器はよく使いますけど、打ち込みってことはあまりしないですね。というか、自分で演奏してマイクで拾うというやり方をとりあえず守ってます。
■何がそうさせるんでしょう。
トクマル:うーん、やっぱりそのときの空気を録りたいっていう気持ちがあるのかもしれないですね。ラインですべて済ませてしまうと、今日と明日とあさってでほぼ同じ音が録れるわけですよね。でもマイクで録ると次の日やってちがう音になる。それがやっぱりおもしろいというか......なにかあるんじゃないかって。そのときしか録れない、なにかが(笑)。
■合成された音があふれてる時代に、生楽器の音のほうが好きというのは、そういう環境に育ったりしたからですか。
トクマル:いや、そういうわけではないんですけどね。いろんな人の音楽を聴いていくと、やっぱり生で演奏して生で録られた音にはっとするんですね。新鮮に思えるというか。ラインで録られたありきたりの音を聴くと、あ、これはこの音だなってすんなり入っていけちゃう。それも良さだとは思うんですけど、そうじゃないものを探しているというか、そんなところはあります。
■じゃあ、機材にもこだわったり?
トクマル:わりかし、ですけど。マイクが好きでマイクを集めたりはしてますね。
■奥の細道ですね(笑)。今日はどうもありがとうございました。これからも素晴らしい音楽をつくり続けていってください。