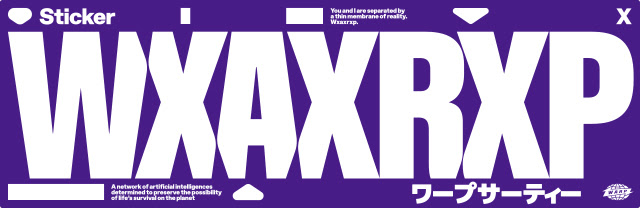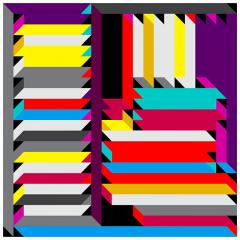私はかつて外国人にサインをねだられたことがある。ひとりはサーストン・ムーア、もうひとりがダニエル・ジョンストンである。最初にサインしたのはダニエルだった。21世紀になってはいたが、もう何年も前のことだ。だれかにサインを書いたのはじつはこのときがはじめてだった。サイン処女というものがあるなら、この言い方はいまだとジェンダー的によろしくないかもしれないが、私はそれをダニエルに捧げた。私は当時雑誌の編集部員で、取材でダニエルに会ったとき、彼は手渡した号の表紙をしげしげと眺め、この本はあなたが書いたのですかとたずねた。正確にはダニエルが隣のオヤジさんに耳打ちし、オヤジさんが通訳の方に訊ねたのを彼だか彼女だかが私にそう伝えたのだった。私はその質問に、雑誌なので全部私が書いたのではありませんが、編集はしましたと答えた、するとまたオヤジさんがサインをしてくださいとにこやかに述べられた。私はサインなどしたこともなかったので、おどろいてかぶりをふったが、外国では著者が著書にサインするのは至極あたりまえのことなのだと、のちにサーストンに諭され納得したが、そのときは恐縮しきりだった。楷書で書いた私の名前にダニエルは満足そうだった。その印象があまりに強烈で肝心のインタヴューの内容はほとんど思いだせないが、彼のビートルズへの愛の一端にふれた感覚はかすかにのこっている。ポールやジョンの話をするとき、ダニエルはなんというかきらきらと輝くのである。その発光の具合はほかの音楽家との対話ではなかなかえられない曇りのない純度だった。
ダニエル・ジョンストンは1961年にカリフォルニア州サクラメントで敬虔なクリスチャンの家庭に5人兄弟の末の弟として生をうけた。第二次世界大戦に従軍経験のあるパイロットだった父親の仕事の都合でウエストバージニアに移ったダニエルは当地で熱心に絵を描き、ほどなくして作曲にも手をそめはじめる。たしか9歳のころでした、私はピアノを叩いてホラー映画のテーマ曲をつくりました、とダニエル・ジョンストンは公式ホームページのバイオグラフィで述べている。とはいえ湯水のように湧きでる自作曲を記録するところまでは頭がまわらなかった。彼がカセットテープに自作曲をふきこみはじめたのは十代にはいってしばらくたってから。多感な時期の音楽の影響源はボブ・ディラン、ニール・ヤング、セックス・ピストルズに、もちろんビートルズがいた。おもに友だちにくばるのに録音したカセットテープは双極性障害と統合失調症に悩まされたダニエルの他者との交感のための媒介であるとともに、移り気な自身の精神の記録媒体でもあった、私はいまにしてそのように思うが、録音という行為はおそらく、彼の念頭で瞬く音楽の速度にはおいついてはいなかった。
ゆえにダニエル・ジョンストンにおいて音楽はしばしば「失われた録音(Lost Recording)」としてたちあらわれる。『The Lost Recordings』とはダニエルの83年のカセットのタイトルだが、そこにはピアノ基調の弾き語りが細かい文字でしたためた日記のようにびっしりつまっている。初期ビートルズを彷彿する楽曲はティーンポップの面持ちで、アレンジの工夫はほとんどみられないものの、作曲のセンスは非凡このうえないが、そのポップでキャッチーなメロディに賞賛をおくろうとしたときにはもう次の歌がはじまっている。愛着も執着もなく、歌ができたから歌う、歌うからまた歌がうまれる、日々の営みにおいて歌は「録る」ときすでに過去のものであり、録音物は失われたものの残像にすぎない――あらかじめ失われゆく才能の底知れなさ、あるいは無垢さと狂気をあわせもつ歌唱でリスナーをなごませつつおののかせたのが『The Lost Recordings』とその続編にあたる『The Lost Recordings II』を発表した1983年だった。この年はジョンストン家がテキサス州ヒューストンに越した年でもあるが、環境が変わり一年発起したのかなにかの堰を切ったのか、同年ダニエルはほかに『Yip / Jump Music』『Hi, How Are You: The Unfinished Album』など、彼のキャリアでも重要作と目されるアルバム(カセット)をたてつづけに発表している。
ことにあとにあげた2作はあのニルヴァーナのあのカート・コベインに影響を与えたことで、ダニエルの知名度を高めるきっかけにもなった。というのも、『Nevermind』のメガヒットを受けた1992年のMTV主催の「ヴィデオ・ミュージック・アワード」でコベインが『Hi, How Are You』のジャケットをあしらったTシャツを着用したこと、コベインの死後に刊行した『日記(Journals)』の「ニルヴァーナにとってのトップ50」に『Yip / Jump Music』があげていたこと、これらのお墨つきでで、90年代なかばにはダニエルは全国区のカルトスターの座に躍りでたのである。もっともその少し前、80年代終わりから90年代初頭にかけても、ダニエルはハーフ・ジャパニーズのジャド・フェアとの共作『Daniel Johnston And Jad Fair』(1989年)をだしていたし、ユージン・チャドボーンらとのショッカビリーの元メンバー──という紹介がこのご時世にどれだけ伝わるかははなはだ心許ないが──であるクレイマーがボング・ウォーターやらをリリースし意気軒昂だったころの〈シミー・ディスク〉からも、やはりジャドやソニック・ユースの面々らの助力を得て『1990』(1990年)をものしていた。私はダニエルの音楽をちゃんと聴いたのはこのアルバムが最初だったが、「ぼくは悪魔の町に住んでいた──」と歌いだす“Devil Town”にはじまり、神の降臨を言祝ぐ賛美歌風の“Softly And Tenderly”で幕を引くこのアルバムの剥き身の歌心と、宗教心の裏にひそむ、赤むけの怒りや恋情に、60年代のフォークとか70年代のシンガー・ソングライターとか、そういった言い方ではあらわせない産業化以前の音楽のてざわりを感じた憶えがある。当時はそれをあらわすうまいことばもみつけられなかったし、いまでもうまいことばのひとつも書けないわが身を呪うばかりだが、たとえばアラン・ローマックスやハリー・スミスのデッドストックというか、米国建国当時の入植地の空気感が色濃くのこる片田舎の古道具屋の片隅に置き去りのままのSP盤の埃だらけの盤面に刻まれた音楽というか。不易流行はむろんのこと、時空さえ捻れさせるなにかを私はそこに聴いた気がしたのである。

ロウファイなるタームはいまでは音響と同じく録音の風合いをさすことばになった趣きもあるが、ダニエルやハーフ・ジャパニーズやゴッド・イズ・マイ・コーパイロットやらをさしてロウファイと呼びならわした90年代前半には脱形式的な方法を意味していた。パンクともポストパンクとも、フリーや即興ともちがう、直観的で身体的なその方法論は当時、鵜の目鷹の目でグランジの次を探しもとめる好事家のみならず、熱心なロック・ファンをもにぎわせた記憶もある。すなわちオルタナティヴの一画だったということだが、そのような風潮をあてこんだ唯一のメジャー作『Fun』(1994年)はダニエルの作曲の才と瑞々しい声質に焦点をあてたものの、その背後の野蛮さと狂気をやりすごしていた観なきにしもあらあらず。ふつうのオルタナなる言い方は本来語義矛盾だとしても、ポップな才覚と特異なキャラクター(の無垢さと純粋さ)の図式のなかに整理しすぎてはいなかったか。括弧つきの「アウトサイダー」としてダニエル・ジョンストンを捉えることは至便だがそこで抜け落ちるものもすくなくない。アウトサイダーとはおのおのの実情に即した雑多な振幅そのものであり、ダニエル・ジョンストンほど性も俗も清も濁もあわせもつ歌い手はそうはいないのだから。むろんそのようなことはおかまいなしに、ダニエルは曲を書き歌い、初対面の人間にサインをねだり、また曲を書いた。病状は一進一退をくりかえしたが、人気もおちついた分、理解者の裾野は広がりつづけた。2000年代なかばには、ジャド・フェアとティーンエイジ・ファンクラブら古株からマーキュリー・レヴやらベックやらTV・オン・ザ・レディオやら、オルタナティヴの大立て者が参加し御大トム・ウェイツが〆たカヴァー集+自作曲集2枚組『The Late Great Daniel Johnston : Discovered Covered』(2004年)がでたし、2005年にはジェフ・フォイヤージーグ監督による映画『悪魔とダニエル・ジョンストン』も公開した。めまいのする出来事――そのひとつに、同乗した飛行機乗りだった父親のセスナを墜落させたエピソードがある――に事欠かないドキュメンタリーはグランジやロウファイにまにあわなかった観客にもダニエルの人物像を伝えるのにひと役買ったかもしれない。あれから15年弱、干支がひとまわりするあいだの活動は以前よりは散発的だったが、それでもときおり届くリリースのニュースに、私は健在ぶりを確認してうれしかった、その矢先、ダニエル・ジョンストンは58歳に短い生涯を閉じた。海外メディアが伝えるところによると、彼ののこした音源は優にアルバム一枚分のヴォリュームがあったという。失われた録音はこんごさらに増えていくであろう。私はそれらをリリースするなら、なるべく手をくわえず生のままにだしてほしい。おそらくそこには時間と空間を同時に志向する「生の芸術」たる音楽だけが届く場所が記録されているだろう。できればカセットがいいな。