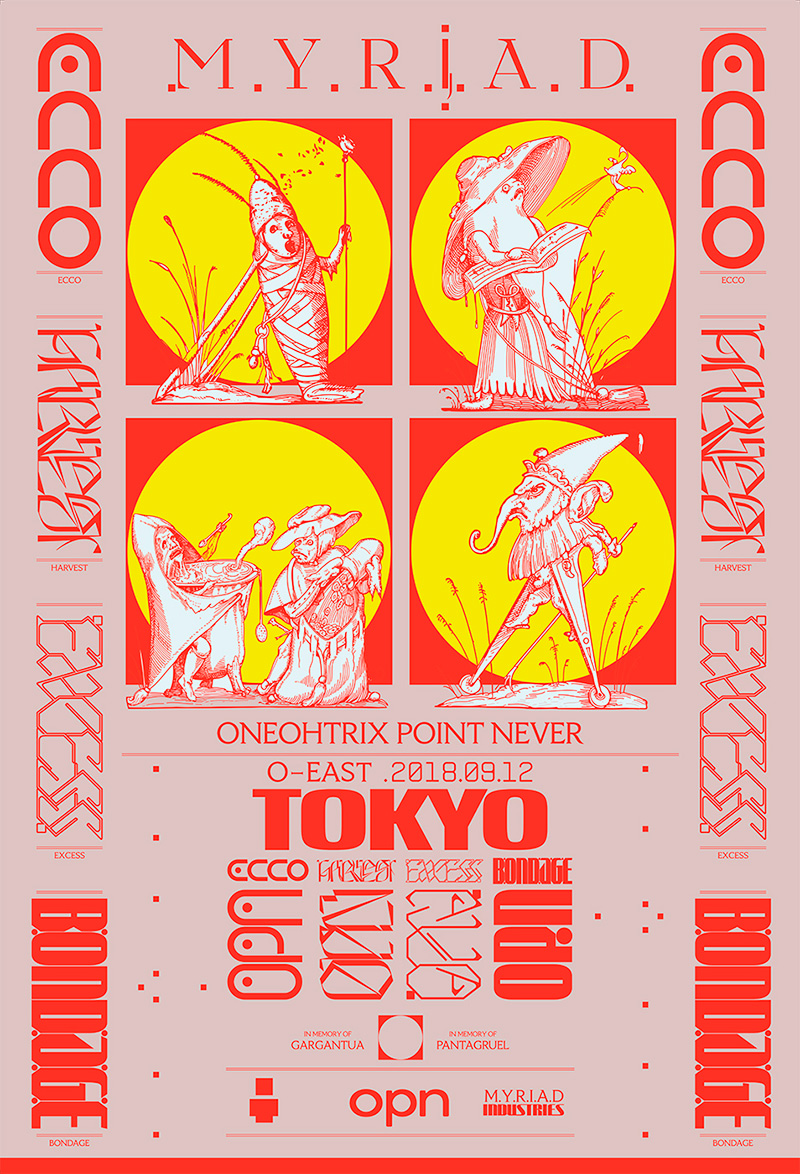Unknown Mortal Orchestra Sex & Food Jagjaguwar / ホステス |
60年代に産声を上げたサイケデリック・ロックは、ある時期までのロック史観においては、その時代にのみ瞬間的な爆発をみた徒花的存在として扱われてきたきらいもあった。しかし、商業ベースに乗らない自主制作盤の世界では、サイケデリック暗黒時代と言われる70年代にも少なくないアーティストが蠢いていたことが近年振り返られつつ有るし、オルタナティヴ・ロックの興隆以降、ペイズリー・アンダーグラウンド・ムーヴメントなど80年代におけるリバイバルを始めとして、折に触れてサイケデリックという奴は歴史に顔を出し続けてきた。そしてそれに伴っていつからか、一個の音楽スタイルという括りを越えて、特有のテクスチャーやムードを持ったもの/ことに対して使う形容詞としても定着し、時には安易に使われ過ぎる言葉ともなっていった。
アンノウン・モータル・オーケストラこそは、そういった捉えがたい霧のようになってしまった「サイケデリック」というものを、今一度リスナーの耳元に引き据えてみせる。しかも、この「サイケデリック」は、往時に描かれたムードとはかなり質感を異にする。それは、これまでサイケデリックを表象してきた攻撃的酩酊感とでもいうべきものと、一般的にはそれと相反すると思われてきた所謂「メロウネス」との巧みかつ大胆な融合によるものだと言えるだろう。90年代後期から米国中心に再び勃興してきたローファイでガレージーなインディ・バンド/アーティスト群や、チルウェイヴやシューゲイザー・リバイバルとの共振も感じさせた初期作品を経て、彼らは徐々に仄暖かでメロウな海へと漕ぎ出してきたのだった。それは一見、かねてよりギャラクシー500やヨ・ラ・テンゴといったアクトが住処としていた海であるようにも見えるが、アンノウン・モータル・オーケストラの眼前に広がるそれは、各種のブラック・ミュージックやビート・ミュージックからの影響も垣間見える、コンテンポラリーなメロウネスと躍動に満ちたものだ。その沖合では既にアリエル・ピンクが帆船を浮かべていたかもしれないが、彼らはそれを横目に見ながら密航者のように鮮やかな手つきで彼らだけの海域を見つけ、そこで巧みに遊んでいる。
……そして時に言われるように、サイケデリックへ沈潜し時にノスタルジーの蠱惑にも誘われながらそこに遊ぶことにより、ライブリーな生活圏や政治的世界と隔絶するという現象は、どうやら確かに起こることなのかもしれない。もしかするとここに聴かれる世界は、現在の政治空間からのスキゾ的逃避ととらえられても仕方のないことかもしれないが、しかしながらそもそも逃避とは、その表現者自身に社会に対する鋭敏な問題意識が蟠っているからこそとも言える。この逃避の欲求というのは、かねてよりこの世界に生きる我々皆が少なからず背負い込んでいる問題でもあろうし、その重荷を肩に感じながら、音楽そのものに耽溺するとき、ひょっとしたらメロウネスこそが鬱屈を和らげるオピウムのような役割を担いつつあるのかもしれない。
サイケデリックは今新たなフェーズを迎えつつある。「官能と飽食」という、いかにも示唆深いタイトルを与えられた今作は、その象徴として捉えられる傑作であるとともに、メランコリーに揺られるからこそメロウネスがひとりでに立ち昇るという仮設を提供してくれていることで、サイケデリック・ロックに限らない昨今の音楽シーンを読み解く優れたテクストにもなるだろう。
今作での音楽性の深化や、メロウな音楽への関心、シーンを取り巻く状況、ドラッグ・カルチャーについてなど、バンドのリーダーであるルーバン・ニーソンに話を訊いた。

音楽を作る時も、すごく馴染みのある気持ちになることもあれば、暗闇を歩いている気持ちになったりもする。様々な気持ちになるんだけど、時にはその暗闇を歩いている時こそがいい時だったりするんだよね。
■今作『セックス&フード』、とても素晴らしい内容で非常にワクワクしながら聴かせていただきました。第一印象として、これまでに増してメロウな感覚が強まったと感じます。バンドにとって、70年代のソウルなどのファンキーでメロウな音楽はどんな存在でしょうか? また、それらはインスピレーション源として大きなものでしょうか?
ルーバン・ニールソン(以下RN):ありがとう! そう言ってもらえて嬉しいよ。そうだね、70年代の音楽にはすごく影響を受けたって言えると思う。ソウルやファンクは、小さい頃に聴いていたような音楽だった。家の中で流れていたものだから自然と聴いて育った音楽なんだ。今でもその頃の音楽は聴いたりするよ。
■一方、リード・トラック“アメリカン・ギルト”などのように、鮮烈なギターリフが先導するガレージーな楽曲も収録されています。ガレージロック的なものとメロウなものというのは、一般的には一見背反する要素のように捉えられているかと思うのですが、アルバム全体ではその融合を目指しているようにも感じました。制作にあたってそういった意識はありましたか?
RN:曲作りをアコースティック・ギターで作り始めるから、最初はメロウな感じでいつも始まるんだ。だけど書いていくうちにもっとロックになってきたり、他に試してみたいことが出てきたりして、プロダクションを重ねていくうちにそういう感じに変化して行ったんだ。
■ミックスなどの音響面でも、これまで皆さんに対して言われてきたようなローファイな感覚から、曲によってはかなりハイファイな音作りに変化したような気がするのですが、これはなぜなのでしょうか?
RN:僕はレコーディングする時に用いる手法があるんだけど、ヴィンテージのテープレコーダーやカセットテープを使って作業しつつ、コンピューター処理も行う。昔ながらのアナログな手法とモダンな手法が混ざっているんだよね。ディストーションとかはわざと残したりしているよ。でもアルバムを重ねるごとに、自分の技術も上がってきて、よりいい機材を使ったりしているんだ。アルバムごとに少しずつ手法やスキルも上がってきてるからサウンドも変わってきたんだと思う。
■近年脚光を浴びている、いわゆる「ヨットロック」のリバイバルについては、どんな認識をもっていますか? ここ日本でも自国の「ヨットロック」である70~80年代の音楽が「シティ・ポップ」として海外からも注目されるなど、今までダサイとされていたものの問い直しが起こっています。
RN:僕が幼い時は、父親がジャズ・ミュージシャンっていうこともあって、家ではジャズ・ミュージックが主に流れていて、ヴォーカル・ミュージックを聴くことが少なかった。でも唯一父親も好きで聴いていた「ポップ」と呼べる音楽は、スティーリー・ダンだった。だからスティーリー・ダンは自分にとってすごく心の中に残ってる音楽なんだよね。今またなんでヨットロックが注目されているかというと、多分今の時代に生まれる音楽とすごく違うからだと思う。あの頃はプロダクションレベルとかミュージシャンシップとか、今よりもすごく高いものが多かったと思う。だからそういう音楽に触れるとすごく珍しい気持ちになる。それに、昔聴いていた音楽はノスタルジーに浸れるっていうのも大きい気がする。ノルタルジーってやっぱり人の心や記憶の中でとても強いものだと思うから。
■メキシコシティやアイスランドのレイキャビク、韓国のソウルやベトナムのハノイなど世界各地でもレコーディングを行ったとのことですが、創作にあたって、どんな刺戟がありましたか? また、そういった地域のポップスや民族音楽からの影響はあったのでしょうか?
RN:ローカルの音楽を聴いたりもしてみたんだけど、あまり影響されないようにはしてたんだよね。でもベトナムでは、レコーディングしてたスタジオでいつも顔を会わせるバンドがいて、いつも会うから彼らと仲良くなったんだ。一緒に音を鳴らしたりしているうちに、いろんな音楽ができて行った。結果的にすごくたくさんの楽曲が増えたから、また別の形でそれは出そうと思ってる。音的にはエレクトロニック・ジャズとかクラウトロックみたいな感じなんだけど、それを年内か来年出す予定だよ。あとは、ローカルなライブとかも何度か行ったよ。でも自分的には影響されて、まるでそこの土地の音楽を盗むような真似をしたくなかった。
■昨年米国の再発レーベル、〈ライト・イン・ジ・アティック(Light in the Attic)〉より日本のフォーク・ロックを集めたコンピレーション・アルバム『木ですら涙を流すのです』が発売されました。そういったフォーク・ロックに限らず、サイケデリック・ロックなど、ここ日本の音楽に興味はおありですか? また特定の好きなミュージシャンがいれば教えてください。
RN:当然YMOは大好きだよ! あと僕たちが一回日本で共演した、Tempalayっていうバンドがいるんだけど、彼らはすごく好きだよ! でも残念ながら日本のサイケロックはあまり詳しくないんだ。誰かオススメいる? いたらぜひ知りたいよ!
■高度資本化した社会、またポストインターネットといわれる現代の時代状況において、様々な情報や音楽ジャンルが並立し、時にガラパゴス化した様相を呈するようになってきたと感じます。その中で、一部で「死んだ」とすら言われるロックを今演奏し続けることの意義はどんなものだと思いますか?
RN:ロックが死んだって言われたり、どんな状況になっても僕自身は気にしないかな。僕自身、レッド・ツェッペリンやローリング・ストーンズ、僕の中ではロックンロールと思っているデヴィット・ボウイとかを聴いて育って、今でも僕にとって大切な音楽だから、そういうロックな部分が自分の音楽の一部となってしまうことは変えられないと思う。だからロックが死んでようが生きてようが僕には関係ないな(笑)。あと、僕たちのバンドは僕たちの世界というかコミュニティがあるというか、あまり流行に左右されたりするようなポジションには身を置いていないと思う。

人はずっとモーツァルトもベートーヴェンもジミ・ヘンドリックスも聴き続ける。そういうものって政治を超えている気がして、それに比べると政治的なものってちっぽけに感じてしまったりするんだよね。
■これまで、ポピュラー・ミュージックは「新しい」ということを至上の価値として歩んできたと思います。しかし、昨今ではそういった感覚すらも相対化されて、特にインディ・シーンでは各々が各々の表現を自身の尺度で自由に行うようになっているようにも思います。そんな中で今一度、「新しい」とは一体どんなことだと思いますか?
RN:すごくいい質問だね。難しいけど、僕にとって新しい音楽とは、まだその音楽が評価されたり、意見を言われたりしていない時だと思う。例えば、音楽を聴いた時に、まだその音楽がいいかどうか分からなくて、でも何か強い思いみたいなものは抱く時とかあると思うんだけど、そういう時が新しいって思っている瞬間なのかもしれない。自分の音楽を作る時も、すごく馴染みのある気持ちになることもあれば、暗闇を歩いている気持ちになったりもする。様々な気持ちになるんだけど、時にはその暗闇を歩いている時こそがいい時だったりするんだよね。それがいいのかどうか自分でも分からず、でも何かすごく強い思いがこみ上げてくる時こそが新しいものを誕生させられる時なのかもしれない。
■ルーバンさんはバンド活動を続けてく中で娘さんを授かったと聞きます。彼女の存在が創作に与えた刺戟はどんなものでしたか? また、家庭人と、ロック・バンドのメンバーとしての活動を並立して続けていくことに、時になにか葛藤があったりするのでしょうか?
RN:僕自身音楽一家で育ったんだ。父親もミュージシャンだったし、父親の父親もミュージシャンだった。だから幼い頃から音楽は普通の仕事として見て育ったんだ。人によっては音楽なんて趣味の延長にしか見えないものかもしれないけど、僕はちゃんとした職業として捉えていたよ。僕は父親のツアーに同行したり、サウンドチェックを見たり、常に仕事の現場を見ていたから、音楽が仕事なのは僕にとってはすごく自然なもの。だから自分に娘ができても同じなんだよね。父親であり音楽家でもある姿は自分が見てきたものだから、すごく自然なものだよ。
■様々な文化の分野でポリティカル・コレクトネスが更に敷衍されつつあるように感じる昨今、自身の創作にあたって、そういったものを(肯定的か否定的かいずれにせよ)意識したりすることはありますか? または、そういったことへの問題意識が歌詞表現へ反映されていたりしますか?
RN:政治はすごく大事なことだと思うけど、あまりそれに支配されないようにしているよ。政治よりも音楽の方が大きいものだと思っているから。音楽は歴史を変えることはできないかもしれないけど、帝国が建てられては滅び、イデオロギーも立てられては壊され、それでも人はずっとモーツァルトもベートーヴェンもジミ・ヘンドリックスも聴き続ける。そういうものって政治を超えている気がして、それに比べると政治的なものってちっぽけに感じてしまったりするんだよね。だから僕はあんまり政治的なことに左右されたりしないようにしているよ。
■ポートランドのシーンの面白さがここ数年で日本でも認知されているのですが、みなさんが注目する新たなポートランドのアクトはいますか? また、そういったミュージシャンとは交流もあるのでしょうか?
RN:仲良いバンドはたくさんいるよ! 特に自分たちのピアグループ(仲間)とはすごく仲が良くて、すごくいいアーティストがたくさんいるよ。例えば、Portugal the man(ポルトガル・ザ・マン)、The Dandy Warhols(ザ・ダンディー・ウォーホールズ)、Star Fucker(スター・ファッカー)、Wampire(ワンパイアー)とか、ポートランドでは人気があって、僕たちとも仲がいいバンドだよ。新しいバンドでは、Reptaliens(レプタリアンズ)と仲がいいよ。あと僕のバンドのベーシストがいたBlouse(ブラウス)っていうバンドもすごく良いよ。
■今年からカリフォルニア州で大麻の販売が解禁されたことが日本でも報じられ、一部で話題となりました。日本ではいまだマリファナも麻薬の一種と捉えられ、大きなタブーとして扱われています。米国における現在のドラッグ・カルチャーは、インディ・ロックの文化圏にとってどのような役割を演じていると思いますか?
RN:やっぱりシーンにドラッグは当然存在はしていると思う。でも僕は、いい大人になってきたし、ドラッグのことを考えたり関わったりする時間はすごく減った。個人的には、ドラッグが僕の愛する人たちを破滅させたりするのを見てきたんだ。でも、時にはすごく創造性を掻き立てるものにもなるものなのだと思う。でもやっぱりパワフルなものは、危険も伴うんだよね。だから僕はあまりドラッグはやるべきではないと思ってるよ。
■ニュージーランドご出身ということでお訊きします。80年代前半、米国で「ペイズリー・アンダーグラウンド」と呼ばれるサイケデリック・ロック復興的なシーンがありましたが、The CleanやThe Batsなど、同時期のニュージーランドにも「ダニーデン・サウンド」と呼ばれるようなザ・バーズなどの60年代ロックからの影響を感じさせるギター・ロックのシーンがあったとききます(日本ではあまり知られていません)。そういったシーンが何かあなた達の活動にも影響を与えていると思いますか?
RN:まずペイズリー・アンダーグラウンドといえば、ザ・バングルズの“マニック・マンデー”を思い出す。ペイズリー・アンダーグラウンドの最大のヒットなんじゃないかな。あとは、プリンスのアルバムに“ペイズリーパーク”っていう曲があるんだけど、きっとプリンスもペイズリー・アンダーグラウンドのフェーズがあったんだと思う。
ニュージーランドのダニーデン・サウンドは、たくさんのバンドが〈フライング・ナン・レコーズ(Flying Nun)〉からリリースされた時代だった。僕が初めて組んだバンドが兄とのもの〔質問者註:ザ・ミント・チックスのこと。2003年デビュー〕だったんだけど、実は〈フライング・ナン・レコーズ〉からリリースしているんだよ。このレーベルからリリースすることが多くの少年の夢だった。〈フライング・ナン・レコーズ〉やダニーデン・サウンドのアーティストは、すごく強いDIY精神をもっていて、レコーディングやアートワーク含め、大きな会社のバックアップがない状況で全て自分たちでやってしまうアーティストばかりだった。僕はそれにとても憧れていたから、自分に必要なスキルを身につけるという点ですごく影響を受けたよ。バンドをやる上で何が必要なのかを学べたし、それができてすごく良かったと思っている。
■これまで聴いてきた中で、ベスト・サイケ・アルバム(一般的にサイケとされていなくても自分がサイケと思うものでもOK)3枚を教えていただけますか?
Sly and the Family Stone / Stand! (1969)
https://open.spotify.com/album/7iwS1r6JHYJe9xpPjzmWqD
Love / Forever Changes (1967)
https://open.spotify.com/album/2amHBpP8C0EUy6yBNy6nN6
The Soft Machine / The Soft Machine (1968)
https://open.spotify.com/album/1ve9AXU2FPr7CZTRg3AboS