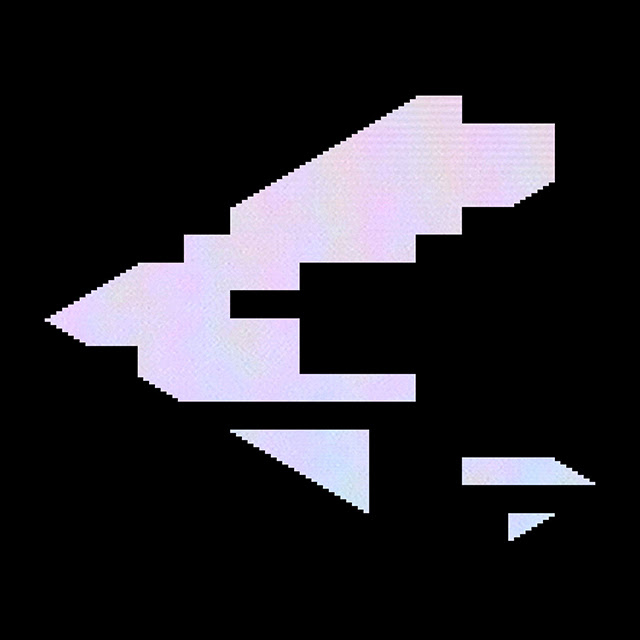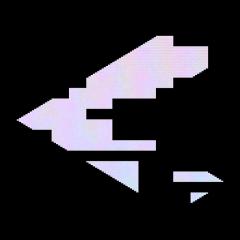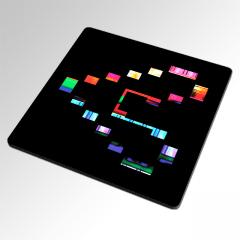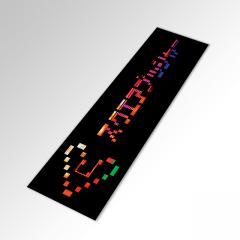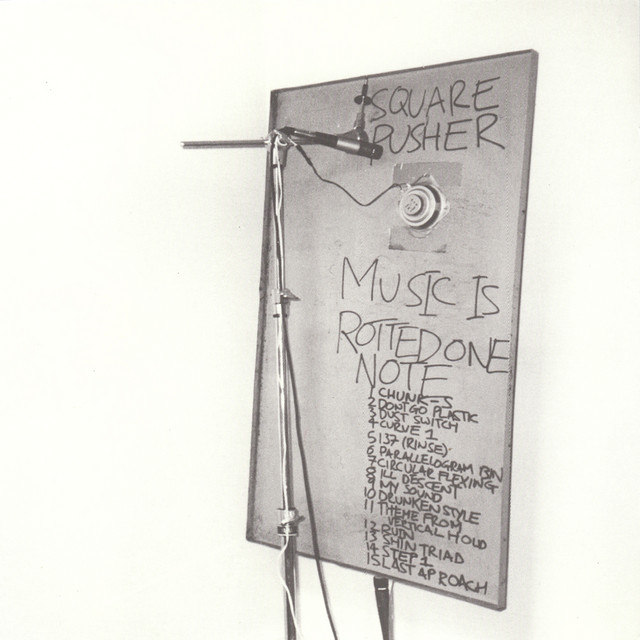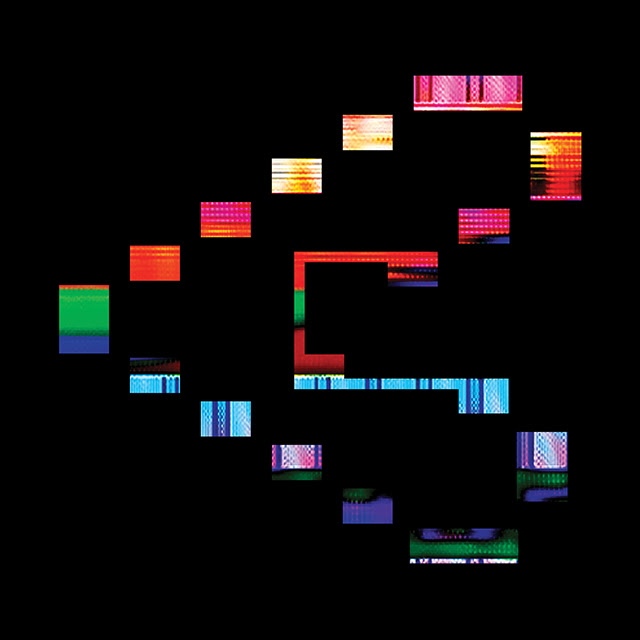石原洋の23年ぶりのソロ・アルバムは、一か八かの思い切った作品だ。聴けたもんじゃねーと思う人もいるだろうし、稀に見る最高作だという人もいるだろう。これをやれば受けるだろーとか、こういうことを言えば評価されるだろーとか、媚びたところはまるでない、いかなるトレンドともまったく無縁な、いまどきなんとも大胆な作品である。
石原洋はアルバムにおいて、街の雑踏における音を蒐集し、生演奏によるロックの曲にミックスする。がやがやした雑踏の向こうから聞こえるロック・バンドの演奏──などと書くと詩情も覚えそうだが、ここで聞こえるノイズは、子供から大人までの生々しいクソ日常的な声、笑い声、奇声、ボソボソ声、あるいははっきり言葉が聞き取れる声であったり、電車のホームのアナウンスであったり、ロマンティックな要素の欠片もない。しかも、作品においてはこれら耳障りな声やノイズのほうがバンドの演奏よりも前景化されている。が、しかしこの“音楽”にはある種の快楽性もある……かもしれない。
まあ、音楽における快楽とは普遍的ではないのだ。それはその人の世界の見方に関わっている。つまり本作『formula』には、不可避的に石原の世界観が投射されている。思いきり、まるで容赦なく。
石原洋は、ゆらゆら帝国のプロデューサーとして広く知られている人物であり、オウガ・ユー・アスホールの『Homely』から『ペーパークラフト』までのアルバムのプロデューサーである。偏ってはいるが、音楽リスナーとしての造詣も深い人物で、アーティストたちからも一目置かれた存在だ。
また、彼がかつてやっていたホワイト・ヘヴンやスターズといったバンドのアンダーグラウンドにおける名声は、その筋のマニアから聞いてもいる。それはまあ、ぼくなりの印象をもってわかりやすく言えばスペースメン3のようなバンドで(異論は認めます)、慣習に従えばサイケデリック・ロックと括られる。厭世的で、いわば精神的シェルターのような音楽だ。が、石原洋の『formula』は、あたかもそうした“ありがちな体験”を反転させているかのようだ。
たとえば君はスペースメン3を聴いている。そのサイケデリック・サウンドへの没頭をはばむかのように、鳴り止まぬことのない生々しい猥雑な日常音が鼓膜を覆う。それは君の「スペースメン3の白昼夢に耽溺したい」という欲望を踏みにじるかもしれないが、実は、いままで覚えたことのない〝気づき〟をうながすことにもなる。
これはエクスペリエンス=体験である。以下のインタヴューが、この風変わりな作品を理解する一助になればさいわいだ。石原洋はじつに親切に、作品についていろいろ話してくれた。あとは各自勝手に妄想すること。

〝遠さ〟というものをずっと考えていてね。自分とそれ以外との距離感というか。昔はアナログ時代の音の悪いブートレグとかあったじゃないですか。会場で録ったような。はるか遠くのほうで演奏をしているのをマイク1本で録っているような。近くの客の声のほうがでかく入っている。そういう感じがいいなと当時からなぜか思っていたんです。
■まずは今回のソロ・アルバムを作った経緯を教えてください。
石原:何年も何もやっていなくて。やりたい方法が見つからないというか、どんなやり方をすればいいのかというのをずっと考えていたんですよね。
■作りたいという気持ちはつねにあったんですね。
石原:どこかにはあったと思います。このやり方だったらできるかもしれないというのが思い付いたのが2年前。そこから動き出したという感じですかね。ただ、最初に思いついた時点でこの完成形は頭のなかにあったので。
■いちどバンドで録音した音源に雑踏の音を加えていく。
石原:そうです。雑踏というイメージも最初にあった。それと実際の演奏をどういうふうに混ぜ合わせてどういうバランスでミックスしていくかというのが難しいことでした。
基本的に〝遠さ〟というものをずっと考えていてね。自分とそれ以外との距離感というか。昔はアナログ時代の音の悪いブートレグとかあったじゃないですか。会場で録ったような。音の良いやつもあるけど、すごいひどいものになるとはるか遠くのほうで演奏をしているのをマイク1本で録っているような。近くの客の声のほうがでかく入っている。そういう感じがいいなと当時からなぜか思っていたんです。ヴェルヴェットの音が悪いやつとか、ルー・リードの音が遠いやつとかありますよね。
■なんでなんでしょう?
石原:それは……なぜかはよくわからない(笑)。もともとこれだと言って、バコンッと目の前に提示するやり方が苦手だったんじゃないかと思います。アーティストにしてもミュージシャンにしても、みんな「これが」「俺が」って言って出すじゃないですか、「俺を見ろ」という感じで。もともとそれが苦手だったんです。「表現」なので当たり前のことなんですが、それが強すぎるのが苦手だったんです。
■それは自己矛盾ですよね。
石原:そうですね。でも凸型の表現が昔から苦手でした。もちろんいいものとか好きなものはいっぱいあったけど。
■その〝遠さ〟には、いろんな表現の仕方があるのかもしれないですね。人のざわめきのなかに埋もれてしまうことというのは重要だったんですか?
石原:すごく重要でしたね。雑踏とかざわめきを僕はデータみたいなものだと思っているんです。インフォメーション。たとえばそこを歩いている人と一生会うこともないわけじゃないですか。みんなスマホをやりながら歩いていたりで、見えはしないけれど、そこに会話とかサブリミナルな情報とか、BGM、Wi-Fi、電波とかものすごい量のデータがひしめき合っている。そのなかに埋没しかかっているんだけど、まだ完全には埋没していない音楽という。
ある意味コンセプチュアル・アートという捉え方もできると思うんです。ジャケも含めて。でもコンセプチュアルではあるけれど、アートだとは思ってないですね。だから本当に日常。日常を切り取ったものという感じ。
これは感覚として10代の頃からあったなと自分で認識しています。なので、急に思いついて「これいいんじゃない?」みたいな感じで作ったわけではなくて、たぶん10代の頃からこの感じがずっとあったんだなというか。ただずっとそのやり方がわからなかった。
■それはある種の陶酔感ですか? サウンドに陶酔するような。快楽というか。
石原:自分にとっては快楽的だと思います。
■ホワイト・ヘヴンやスターズといったバンドではそれをやってこなかった。なぜですか?
石原:バンドというものへの幻想はがすごくあったんだと思います。ひとつの思惑を持って集まってきた人たちで、何かを作れるというような。あの時点ではああいうやり方しかできなかったといえば正しいのかわからないけれど、それがギリギリできることだったのかなと思います。
■石原さんの感覚にもっとも近い既存の作品は何かありますか?
石原:ひとつの切り取り方として、リュック・フェラーリの“ほとんど何もない”とか、ジャン=クロード・エロワという現代音楽の作曲家の作品とか。でも、これらはあくまでも現代音楽のアプローチであって。僕はどうしてもロックの属性からは逃れられない。聴いてみていいなと思うけれど、それらと同じような方法論でやろうとは思わない。だから、自分のやり方でやるしかなかったんです。
■石原さんがそこまでロックにこだわるのは何故でしょうか?
石原:それはけっこうみんなに言われますね(笑)。ここまで何十年も音楽をずっと聴いていたら普通違うジャンルとかいろんなものにいくでしょという話は聞きますね。実際に聴いてないわけではないです。興味があって、ジャズとかクラシックとかそれこそクラブ系とかね……インダストリアルも好きでしたね。ただ、どんな聴き方をするかというと、それと自分の考えるロックとの接点という聴き方をしちゃうんですよね。たとえばフリー・ジャズとロックとの接点。クラブ・ミュージックとロックとの接点みたいな。
[[SplitPage]]これは感覚として10代の頃からあったなと自分で認識しています。なので、急に思いついて「これいいんじゃない?」みたいな感じで作ったわけではなくて、たぶん10代の頃からこの感じがずっとあったんだなというか。ただずっとそのやり方がわからなかった。
■モダーンミュージックで働かれていたのは何年から何年頃までですか?
石原:80年代後半、86とか87とかじゃないですかね。それから90年代。それまではお客さんでしたね。行き出したのは20代前半。店でバイトをしはじめたのは20代後半でした。
■レコードを好きになったのは何歳くらいのとき?
石原:洋楽ですけど、中1ですね。最初は深夜放送ですよね。上の世代と同じで、洋楽のヒット曲とか。それでT・レックスを聴いて。聴いたことがない音楽だったのでね。その頃は“Easy Action”かな。すごいじゃないですか(笑)。すごい曲があるなと思って。そこから洋楽、ロックを聴くようになった。それが73年くらいですかね。
当時でも洋楽を聴いている友だちってクラスに何人かはいますよね。中1のとき、ものすごいマニアックに聴いているクラスメートがいて、「何聴いているの?」と訊かれたから、「T・レックス」とかって。「帰りに俺んちこい」って言われて。行ったら、他にもうひとり友だちが来ていて、そこで聴いたことがないような音楽が流れていたんです。それがキング・クリムゾンでした(笑)。
「こういうのもロックなの?」って聞いたら、「これがロックだ」って言われて(笑)。その友人ふたりがすごくマニアだったので、プログレ、ジャーマンロックとか聴きましたね。で、毎日帰りにレコード屋に行って、「これがいいよ」とか「あれがいいよ」とかやって、彼らから教わりましたね。高知だったのでそういうマニアックな少年たちはめずらしかったと思います。
■当時はレコード屋さんが日本全国どんな地方都市にもありましたからね。
石原:東京で生まれたんですけど、親の転勤で大阪に引っ越しになって、小学校のときに高知に引っ越したんです。高知で中高を過ごして、中高のときはその友人たちに影響を受けて、日本で出ていない輸入盤を買ったり、よりマニアックに聴くようになってしまったという感じです。
■石原さんにとってプログレは大きいですよね。
石原:大きいと思いますね。リスナー体験としてはね。ハード・ロックよりは大きい。結局僕もプログレからドイツのロックを聴き出して、でも高校生になった頃だんだんドイツのロックがどれも同じに感じてきて、聴いてはいたけどいまひとつ違和感があったときにパンクがきた。ジャーマン・ロックとパンクとニューウェイヴの一部が10代の頃の僕にとってはいちばん大きかったと思います。1977年に『ホテル・カリフォルニア』にいった人とピストルズにいった人で残りの人生が違うという説もありますよね(笑)。
■その頃には音楽どっぷりの生活を?
石原:ほぼそれしかないという感じですね。ただ、バンドを自分でやることに当時は興味がなかった。いまでいえばポスト・パンク──当時はそういう言葉はなかったんですけど──ポストパンクが出てきて、「これはもしかしたら誰がやってもいいんじゃないか」とは思いました。あのスピード感がおもしろかったですね。半年前に「これがいまいちばんすごい」って言われていたものが、半年したら「まだそんなの聴いているの?」って言われる感じになっていく速さ。あの頃に10代後半を過ごしたのはすごい影響あった。
大学でこっちに来て、でも大学にはそんなに行かずにひたすら渋谷でレコードと本を買って。その時代って日本盤が出るのがすごく遅かったり、ほぼ出なかったり。情報だけは入ってきたけど聴けなかったので、大学というよりも、東京にレコードを買いにきたようなもんですよ(笑)。
住んでいたのが横浜なので、東横線で渋谷にきて、渋谷をまわって大盛堂とかで本を買って、かかえて帰って、朝まで聴いて、昼寝るという暮らしをしていました。ほとんど大学にはいかず(笑)。友だちもひとりもいませんから。大学にも行ってないし、引きこもりですよね。
そうやって誰かと情報交換もせず感想も言い合うこともなく、ひとりでひたすら聴く行為によって、けっこうオブセッションみたいなものが育まれる。「これはなんだ?」と思って自問自答しながら聴いて、自分のなかで腑に落ちるところをみつけて……そんなふうに人の助けを借りずに、それが何かというのを考えていく作業はすごく重要だったし、重要な時期だったなと思います。
でも当時、もしいまみたいなシステムがあったとしたらあのときほど驚かなかったでしょうね。たとえば雑誌でスロッビング・グリッスルのすごいのが出たって見かけて、YouTubeで聴いて「はぁなるほど」で終わっていたら、こんなことはなかったかもしれない。
■当時、石原さんご自身の将来のことは考えていました?
石原:まったく考えてなかったです。何になりたいとかどうやって食っていこうとか、そういうことは考えたことがなかったですね。お金がなくなるとレコードが買えないなとか、頭の片隅にはありましたけど。食いもんとかどういでもよくなるくらい、そっちに必死で。
■最初に働いたのがモダーンミュージックだったんですか?
石原;ちょこちょこしたバイトはやりましたけど、長期でやるということはなかったですね。ある日いきなり生悦住さんに「買い付けにいかない?」と言われて。単なる客なのに。「普通客に頼まないよな」と思ったんですけどね(笑)。
知識があったから何かいいものを買ってくると思ったのかな。それで行って帰ってきたら、「前のバイトがやめたので、ひと月でいいからバイトしない?」と言われて。
■それはおいくつのときだたんですか?
石原:26かな。もうそのときには東京に引っ越して。働きはじめて、その前からバンドの真似事はやっていました。
■もうホワイト・ヘヴンははじまってますね?
石原:はじまってましたね。同じ世代の友だちとけっこう何かの縁でばったり、80年代半ばに会って。暇だしバンドやるかみたいな感じ。NYパンクとかが好きなので、そういうのをやらないかという話で。ノイズ、アヴァンギャルド的な音楽も好きでしたけど、それを僕があらためてやってもしょうがないみたいな感じはありました。
■いわゆるサイケデリック・ロックによく分類されますけど、追求されたんですか?
石原:83年か84年くらいまで、ぼくはずっと最新の音楽をずっと聴いていたんですよ。83年か84年にロックからほとんど「これは!」と思うものが出てこなくなった。「もう聴くものないな」と思って、何を聴けばいいのかと思っていました。そこで聴いていなかったものを聴こうと思って。そういやサイケデリックってあったけど、聴いたことがなかいから聴いてみたいなと思って、聴きだしたのが最初です。『ポストパンク・ジェネレーション』という本を読んだら、まったく同じことが書いてあってびっくりしましたね。83年84年で新譜を聴くのをやめて、いままで聴こうとも思わなかったバーズやラヴを聴いて、それを良いと思う自分がいましたね。そこからは一直線にもっとマイナーなサイケ、ガレージに。個々のバンドが、というよりそれが総体としてどういうものだったのかを知りたかった。
■それがホワイト・ヘブンに繋がっていくわけですね。
石原:その頃何を考えていたかといま思い出すと、すごく難しいこと。演奏の速さみたいなことはずっと考えていました。具体的な速さではなくて、意識の速さ、自分の演奏しているときの意識の速さと、演奏している肉体とのズレみたいな。そういうことを意識しながらやったりしていました。それが一足飛びに言うと今回のことにつながるんです。雑踏をミックスしている最中に雑踏の、というかデータの集積が持っているスピード感、速さというのがただごとじゃないということをプレイバックしていてわかって。意識してないのに、データとしてのものすごい速度というのがあって、これは普通に音楽をのせても絶対はじかれるなという速さだったんですよね。そう考えるとそれはずっとテーマにあるかもしれないです。
■楽器はけっこう練習されたんですか?
石原:本当に嫌ですね……(笑)。楽器は嫌ですね。友だちもみんな知っていますけど、持つのも嫌なので、練習がまず本当に嫌いなんです。高校のときにギターを買ったことがあって、ロックとか聴いていたし、ギターを買ったらすぐに弾けるんだろうなと思っていて、やってみたら全然弾けないじゃないですか。まぁ当たり前ですけど(笑)。2、3日やったんですけど、めんどくさくてすぐやめちゃって。それからもうやらなくなって。一応曲は作りたいので、曲を作るときに何か楽器がいるなと思い、それでまたギターを。ただ握り方とか、AとかCとかDマイナーとかそういうのがいまだに僕はわからないです。こうこうこうってスタジオのメンバーに押さえ方を見せて。みんなが集まってきて、「これなんとかマイナーセブンですね」とか言って(笑)。それで練習に入る。
■坂本慎太郎氏とはどういうふうに知り合うんですか?
石原:最初はモダーンのお客さんですね。そのときは親しくはなかったです。ゆらゆら帝国とホワイト・ヘブンの対バン。一緒にやりませんかと誘われて。でもいまみたいな関係ではないです。2バンドでライヴをやりましょうということで誘われて。それが何年か続きましたね。クロコダイルとかが多かったですね。
まだゆら帝がインディーの時代なので、恰好もすごかった時代ですね。上半身裸とか、髪型もすごい髪型で。おどろおどろしくやっていたんだけど、実際に会ってみると普通に良識のある人だったので、その流れでプロデュースという話になったんですよね。
■プロデュースははじめて?
石原:そのときははじめてですね。坂本くんがこういう感じにしたいと言っても当時普通のエンジニアってわからないじゃないですかと。CANみたいな感じにしたいと思ってもカンを知らないし、ミニマルとかジャーマン・ロックとか言ってもわからないし。ガレージのこういう音とか言ってもわからないから。そういうのを具体的に伝えて欲しいみたいな感じだった。それがだんだんと、どういうものを作りましょうかというような関わり方をするようになってきた。
■石原さんご自身は自分がプロデューサーとしてやろう、続けていこうというような意識はありました?
石原:頼まれたらやるみたいな感じですよね。リミックスもそうですけど。まったく接点がなかったらどうかと思いますけど、何かできそうだったらやるという感じです。自分のなかには一部のポストパンクへの愛着があって、でもホワイト・ヘブンやスターズでは意識的にそれを出さないようにしていたんです。たぶん、ポストパンク的なアプローチはプロデュースのところで僕は出していると思う。ゆら帝後期とか、オウガとか、ポストパンク的な手法を使っているということが自分でもわかる。坂本くんなんかはパンク、ニューウェイブをまったく通らなかった人らしいので逆に新鮮だったのかもしれないですね。ソロになってからの彼の音楽とゆら帝を比べればわかると思います。それから、オウガにそっちが受け継がれていった感じはありますね。オウガの『Homely』は、もう1枚ゆら帝でやっていたらこういうのになっていたのかなと思います。
■自分のバンドをやろうとは考えなかったんですか?
石原:スターズを辞めた時点でバンドをやるつもりはなかったです。
[[SplitPage]] 今回のテーマは無関心とかアノニマスとか。そういうことはすごくありましたね。雑踏のなかに含まれている。「あのさー」とか喋っている人たちがスマホひとつで日々を送っている。そういった膨大な情報、データが背後にずっとあって。そうはいかなかった自分というのがそのなかに混じっている。
■では、今回の作品に戻りますが、作業的にもっとも時間を要したのはどこですか?
石原:ミックスですね。演奏の部分は3日か4日で終わっています。雑踏のトラックが30〜40あるんですよ。細かく刻まれた雑踏をいろいろ録ってきたやつが。で、それを全部自分の家で聴いて(笑)。
■雑踏は録った場所には意味がありますか?
石原:そういう意図が入らないように、いろんな人に声をかけて、録ってきてって頼んだんです。そうしたら、渋谷とか新宿とかいろんなところに行って、みんなが録ってきてくれました。それでも足りなくて、けっきょく最後は自分で行きましたけど(笑)。それをパソコンに入れて、聴いて、使う箇所を決めて、それを全部スタジオに送って……。
■使える雑踏と使えない雑踏があるんですね。
石原:ありますね。まず音楽が入っているのはダメだし。有名な曲とかが流れているとかね。使えないものがすごくあった。音が小さすぎて聞き取れないとか。
■でも東京はすごくうるさい街です。
石原:それをはじくのが大変でしたね。一昨年から録りはじめて、去年の春前からレコーディングに入りました。ミックスを半年やっていましたね。
■ちなみにバンドの演奏はどうやって録ったんですか?
石原:普通にスタジオで。ピース・ミュージックですよね。中村(宗一郎)さんのスタジオですよね。
■バンドでは何曲録ったんですか?
石原:7、8曲録りましたね。ボツになったのが2曲くらいあって。実際雑踏と混ぜたら使えないというのがありましたね、楽曲と雑踏のスピードの齟齬がキツすぎて。とくにアクセントがウラに入っている曲は使えなかった。
■今回は全部を2曲にまとめましたよね。1曲のなかにもいくつかの曲がある。それはなぜ?
石原:実質1曲なんですよね。最初から最後までで1曲なんです。アナログ制作をまず考えたので、1回切れて、B面みたいなイメージ。そこでフェードアウトするんじゃなくて、カットアウトするということがすごく重要だったので、最後にブツっと終わる。その間の曲が1曲2曲3曲というふうな考え方はしていなかった。
■全部で1曲。つまり1曲ですよね。
石原:その前があるかもしれない。うしろがあってもいいんだけど、ここだけを切りとったものが作品になったという感じですね。
■この感覚を共有できる人がいるかどうかみたいなところはどう考えました? つまりこれをおもしろがってくれるのかどうかという。
石原:難しいなというのはわかりますけど、作品って自分が思ってもみなかった楽しみ方、思ってもみなかったような使われ方でもいいですけど、そういうことが起きるかもしれない。僕はこう思っているけどそうではない捉え方をする人がいればそれは面白いし聞いてみたいなと思います。
できてしばらくしてから、ウォークマンみたいなやつにこれを入れて渋谷のスクランブルから歩いてみたことがあるんですよ。どれが現実の音でどれが録音された音なのか本当に混ざってけっこうおもしろかったですよ。
■死んでいくロックを描いたという言い方はできるんでしょうか?
石原:僕の感じでは更新という意味では83年くらいに死んでいるので、いまさら感があるんですけど。遠ざかっていくロックという気はしますよね。すでに実際には終わっているんだけど、記憶のなかからすらも遠ざかっていくものがあるじゃないですか。忘れ去られはじめている。
■逆説的に言えば、石原さんがそれだけすごくロックに執着されているということですよね。
石原:それはそうですね。クラブ・ミュージックにいけなかった自分のコンプレックスとは言わないですけど、なぜ純感覚的にそっちにいった人がいるのに、自分はとどまらなきゃいけなかったんだろうというのは一時は自問自答していましたね。
■ロックでなければいけない理由が石原さんのなかにはあったわけですよね。
石原:自分との関係性があまりにも一方的に深かったということがありますね。
■しかしなぜすべてを1曲に? 全部で8曲という構成でもよかったんじゃないのかなという気がします。
石原:曲単位で曲を聴くというのが習慣としてあると思うんですけど、1曲目が良かったとか2曲目が良かったとかになると、もう一回聴いて、ちゃんと曲の構造、例えばベースのこのラインとバスドラの何拍め位置が、とかを聴きとろうとするようになっていく。そこが主眼ではなかったので。そういう聴かれ方はしたくなかった。
とにかく、こういうものが作りたかったとしか言えないです。曲単位で、3曲目がいいとか4曲目がいいという感じではない。
■物語性がまったくないですよね。
石原:物語性がなるべく出ないようにしました。それでも多少は出てしまっている。
■それはなぜ嫌なんですか?
石原:そういう質問をされるのはすごくわかります。ある種のヒューマニズム的なものに対する自分のなかでの折り合いのつかない感覚がずっと子どもの頃からあるんですよ。パンクのなかでもクラッシュとか、そういうのがいまひとつダメだったし。クラッシュが好きな人と話が合わなかった。僕はそっちにいかなかったんですよ。
■クラッシュが好きだった人の音楽ではないですよね(笑)。
石原:今回のテーマは無関心とかアノニマスとか。そういうことはすごくありましたね。雑踏のなかに含まれている。「あのさー」とか喋っている人たちがスマホひとつで日々を送っている。そういった無数の人たちの発信受信する膨大な情報、データが背後にずっとあって。そうはいかなかった自分というのがそのなかに混じっている感じですよね。すでにその一部になってるのかもしれないけれど。
■アイロニーはないんですか?
石原:アイロニーではないです。本当にリアルですね。これ(スマホ)に入ってないものは世界ではないと言われる可能性があるということでしょ。
────────
最後に。このアルバムを聴く場合は、間違ってもPCなんかで聴いてはいけないし、安っぽいイヤフォンも避けたほうがいい。家のスピーカーで聴くのが最善である。
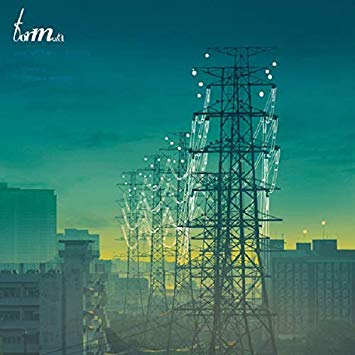
 これがSTOLENの面々。マジ格好いいし、じつはこのインタヴューが載せられるのも彼ら経由でもあります。応援しましょう!
これがSTOLENの面々。マジ格好いいし、じつはこのインタヴューが載せられるのも彼ら経由でもあります。応援しましょう!