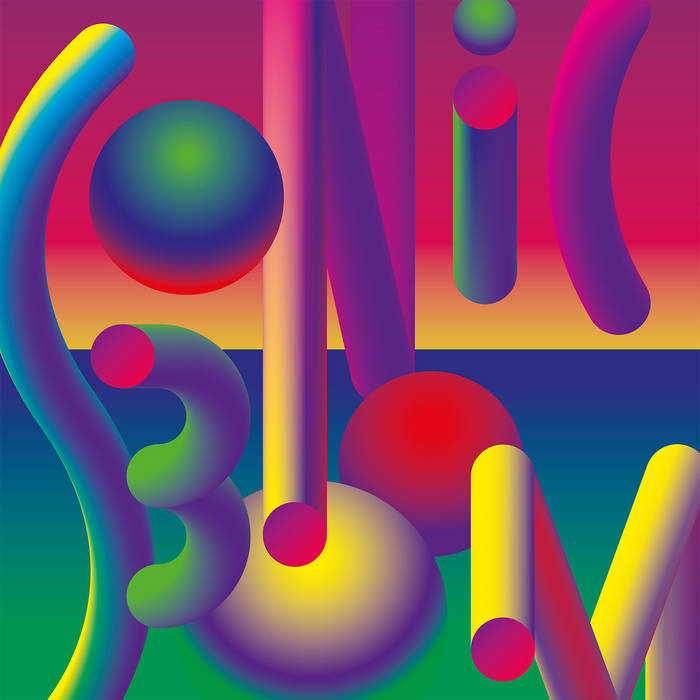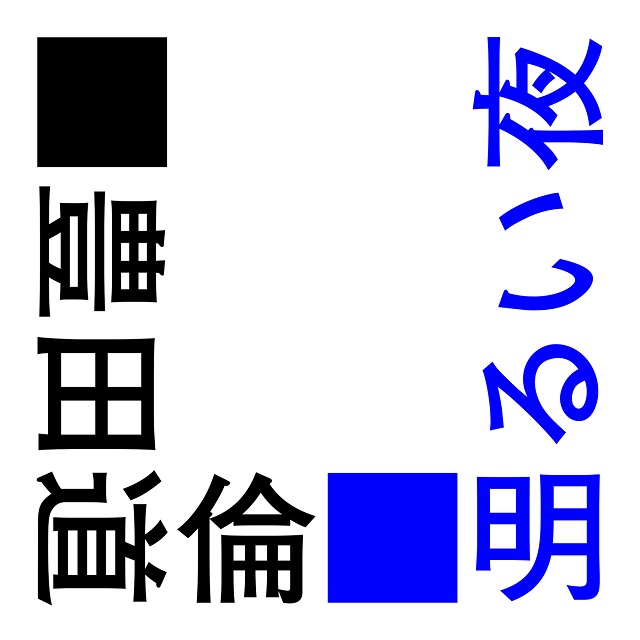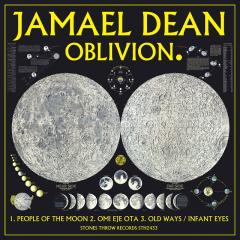コロナ・ショックが起きるまで最も的確な未来像を描いていたフィクションはTVドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』(2011〜2019)だと思っていた。ポピュリスム政治と移動の自由、商人たちが政治的に独立した要塞都市で暮らし、荒野をさまよう主人公たちの姿が新自由主義によって再帰した「万人の万人における闘争」と重なって見えたことも大きかった。実際にはイギリスの南北格差を復讐劇の骨子とし、フェミニズムの機運を商業的なタームに取り込んだことがバカ当りの要因だったのだろうけれど、あまりにもマーケティングの手の平の上で転がされている気がしてしまい、「シーズン5」までで観るのはやめてしまった(なので、デナリス・ターガリエンがどうなったのかいまだに気になっている)。『ゲーム・オブ・スローンズ』で描かれたヴィジョンはコロナ・ショックが移動の自由に制限をかけたことで一気に揺らぎ、女性指導者の優位が示されたことでファンタジー性も薄くなった(日本では在宅勤務が増えることで日本的集団制に変化の兆しがあるかもしれない)。ハンガリーやブラジルのように独裁政治が際立った国もあったけれど、多くの国では社会主義的な政策がとられ、同じディストピアを構想するにしても、これからは『ゲーム・オブ・スローンズ』が示したものとは異なるムードを模索するようになるだろう。最初に『ゲーム・オブ・スローンズ』を勧めてくれたのはLAに住むフェミニストの友人で、彼女は「セックス・シーンが多すぎる」と留保をつけ、作品的には「あまりにソープ・オペラなんだけど」と苦笑まじりではあった。しかし、『悪徳の栄え』や『結晶世界』、『愛の嵐』や『獲物の分け前』など官能性に裏打ちされたアナーキズムの傑作は数多く存在する。『ラスト、コーション』、『LOVE 3D』、“Je T'aime“、“好き好き大好き”、『マダムとお遊戯』、『先生の白い嘘』……なかでもロレンス・ダレル『アレクサンドリア四重奏』は松岡正剛が「恋愛一揆」と評するほど、その筋では古典として名が通っている。コロナ・ショックが『ゲーム・オブ・スローンズ』から奪ったものはむしろそうした「ソープ・オペラ」の背徳性だったのかもしれない。エスカイア誌が選ぶ「最も官能的なセックスシーン」では「シーズン3 第5話」で行われたジョン・スノウ(童貞)のオーラル・セックスが堂々の1位を獲得している(7位と8位に入った『マッドメン』と10位と11位に入った『アウトランダー』も確かにすごかった)。
プリミティヴ・ワールドことサム・ウィリスのセカンド・アルバムはロレンス・ダレルが『アレクサンドリア四重奏』から約10年後に発表した『アフロディテの反逆』を題材にしている。現在では入手困難なので詳細はわからないけれど、パリの五月革命にインスパイアされた政治的な要素の強い風刺小説とされ、多国籍企業やメンタル・ヘルスに焦点を当てたものらしい。主人公の妻イオランテは死んでロボットとして生まれ変わり、それが自壊してしまうまでのお話。思想的にはニーチェの影響が色濃いという。“イオランテが踊る(Ioanthe Dances)”、”理想が凝縮した肉体(Flesh Made From Compressed Ideals)”、”皮膚は鉛を混ぜた石膏(Skins Plastered With White Lead)”と確かに曲のタイトルは小説に沿っている。“墓の間にキアシクロゴモクムシ(Harpalus Among The Tombs)”とかはよくわからないけれど……はっきりとわかるのはサウンドがあまりにもカッコいいということ。オープニングは神経症的なグリッチ・ミニマルで、同じくグリッチで再構成されたUKファンキーと続き、これだけで軽くDJプリードやサム・ビンガは超えてしまった。なんというケレン味。ブレイクダンスの新世紀が視覚化されたよう。タラタラとした“Into The Heart Of Our Perplexities”で焦らしたあげく“Skins Plastered With White Lead”ではディーゴを意識したらしきブロークン・ビーツをアルヴァ・ノト風に仕上げたジャズ・ドラム。
リズム・オデッセイは後半も続き、最後を飾る”The Foetus Of A Love Song”では無機質なドローンへなだれ込み、ディストピアの余韻を存分に染み込ませる。使用した機材は前作『White On White』(駄作です)とまったく同じだそうだけれど、出来上がったものは何もかもが異なっていて、同じ人物がつくり出したサウンドだとは思えない。2010年にベッドルーム・ポップのアレシオ・ナタリツィアと組んだウォールズで独〈コンパクト〉からデビューし、3枚のアルバム(とダフニー・オーラムの音源を再構成したアルバム)をリリース。ナタリツィアはノット・ウェイヴィングなどの名義で多様なソロ活動を行い、ジム・オルークやパウウェルらとジョイント・アルバムをリリースしたり、ジェイ・グラス・ダブと新たにユニットを結成するなど2010年代の才能として加速度をつけていたなか(ドナルド・トランプのスピーチを延々とサンプリングした”Tremendous”はタイトル通り実に途方もない)、一方のサム・ウィリスには目立った動きがなかったものの、ここへ来て一気に逆転という感じでしょうか。むしろノット・ウェイヴィングがトランスやアシッド・ハウスに回帰しつつあるいま、ウィリスの先見性は異様に目立っている。当たり前のことだけれど、人の才能というのはわからない。サム・ウィリスとアレシオ・ナタリツィアがもう一度、タッグを組んだら、そして、どんな作品をつくるんだろう。