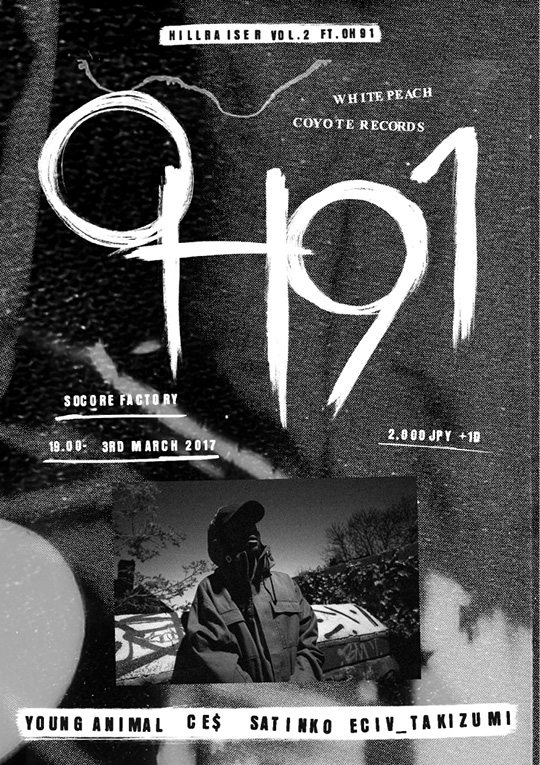あんたのビスケットを盗み
あんたのツレを笑い
あんたのトイレでマスをかく
“You're Brave”(2014)
ひとりの人間の狂おしい思いが世界の見方を変える。こういうのは久しぶりだ。ぼくは日本におけるスリーフォード・モッズ過小評価を覆すためにライナーノーツの執筆を引き受け、書いた。同じテンションのまま違う言葉で彼らについてもういちど書くことは無理な話である。何クソという気持ちがぼくを駆り立てたのだから。だいたいこのぼくに、20代、30代とちやほやされたことのなかった人間の燃え上がる魂を、どうして否定できようか。
19.4度 高いな
18.6度 ボブ、ちょうどいいよな?
19.2度 高い
18.4度 ちょうどいいな(註)
求職者!
ストロングボウの缶
俺は取っ散らかってる
うつ病についてのパンフレットを絶望気味に握りしめる
NHSからもらったやつだ
どうして俺がこうなっちまったか
これから俺がどうなっていくのか
どいつもこいつもこう思ってるわけだ
おれは手巻きを吸う
「ズボンをちゃんとはきなさい!」
くそったれ 俺は家に帰るぜ
求職者!
「それではウィリアムソンさん、
最後にお見えになってから実りある雇用にむけて、
あなたは何かしてこられましたか?」
クソくらえ!
ずっと家でごろごろしながらマスかいてたよ
それからさ
コーヒーの一杯くらい出してもいいんじゃねぇのか?
約束の時間は11時10分のはずなんだけどよ
もう12時だぜ
この臭うクズ野郎どもめ
くたばったちまえよ
“Jobseeker”(2013)
(註)トラックで鶏を輸送する労働者間での会話。ウィリアムソンの説明によれば、輸送中、鳥かごの温度は22度以下に保たなければいけない。温度計を見ながらふたりの作業員が話している。
“Jobseeker(求職者)”──こんな曲をBBCで演奏するぐらいの度胸がスリーフォード・モッズにはある。面倒なので、スリーフォード・モッズにおいて重要なポイントを要約してみよう。
・ジェイソン・ウィリアムソンは10代でモッズ・カルチャーに影響を受け、アンドリュー・ファーンは菜食主義になるくらいザ・スミスのファンだった。
・ジェイソン・ウィリアムソンとアンドリュー・ファーンのふたり組になってからのスリーフォード・モッズのアルバムのタイトルが、『緊縮財政下の犬ども(『オーステリティ・ドッグス』)であったように、彼らはキャメロン前首相から加速した福祉予算カット時代の申し子として現れた。
・スリーフォード・モッズは緊縮時代の英国を見事に記述している。と、いう評価はさんざん英メディアに書かれている。
・とにかく彼らは怒っている。
・ガーディアンいわく「彼らを非凡にしているのは、怒りとその激烈さにあり、それは今日のポップにおいて絶対的に不足している感覚である」。
・その音楽は、ラモーンズ的でもあり、ESG的でもあり、スーサイドっぽくもあるが、なんだかんだいいながらダンス・ミュージックになっている。言葉ばかりに目がいきがちだが、パウウェルが言うように、彼らは音楽的にもユニーク。
・とはいえ、そのライヴにおいて、ファーンはPCのリターンキーを押すか缶ビールを片手に乗っているかで……。
・ウィリアムソンはジェレミー・コービンの支持者として知られるが、彼らの歌詞を読めばわかるように、スリーフォード・モッズは必ずしも政治的メッセンジャーというわけではない。
・むしろファンキーで、頻繁に出てくる「マスかき」も意訳すれば「惨めさ」であり「当てつけ」であり、また「やりたいことを自分がやりたいようにやったる」ってことだろう(さすがに)。
・ツイッターやSNSもまた彼らの批判対象である。
パッとしねぇ火曜のはじまりだ
バスの窓についた汗のシミ
コートを台無しにしたかねぇけど
なるようにしかならねぇ
「がんばれよこのクソ野郎!」
あいつはたしかにそう言った
白いバンのセイント・ジョージ・フラッグ
これが人類ってやつだ
UKIP 貴様の恥さらし
ロンドンの路上の 脳ナシども
うじゃうじゃいやがるゾンビどもが
Tweet Tweet Tweet
売女を回す車
このバスはゲス野郎でパンパンだ
ゲドリング・カウンシルでの8時間
まったくクソな人生だな
予備部屋でのつばぜり合い
重荷になってんのは生身の体
俺らはもうはや特別じゃねぇ
後ろ髪を引っ張られまくる
生きられねぇ人生
俺はそんなの気にも止めねぇ
これが人類ってやつだ
UKIP 貴様の恥さらし
ロンドンの路上にたむろする 脳ナシども
うじゃうじゃいやがるゾンビどもが
Tweet Tweet Tweet
俺は自分のメシを半分食ったとこ
地下鉄に体をブチ込む
電車で帰る頃にゃ
ステラでぶっ飛ぶのさ
“Tweet Tweet Tweet”(2014)
その昔ザ・ストリーツの『オリジナル・パイレーツ・マテリアル』で描かれた日常は、緊縮財政時代の地方の小さな街において、よりハードかつダーティなリアリズムへと変換される。彼らの遺伝子にはセックス・ピストルズからザ・ジャム、あるいはオアシスからクラブ・ミュージックまでと、さまざまな英国流の抗い方が含まれているようだ。「かまうもんか、やっちまえ」的な大胆不敵さもまたUKミュージックならではの魅力であったわけだが、スリーフォード・モッズがいるお陰でそれが途絶えることはなかったと。彼らこそいまこの時点でのジョーカー(最強のカード)である。
そしていま、〈ラフトレード〉からリリースされる新作『イングリッシュ・タパス』によって、ようやく日本でちゃんとこのバンドが紹介される。さあ聴こう。我々がいまいちばん忘れてしまっている感性を呼び起こすためにも。
これはロンドンの坂本麻里子宅からノッティンガムのジェイソン・ウィリアムソン宅への電話取材のほぼすべてだ。答えてくれたウィリアムソンはスリーフォード・モッズのヴォーカリストであり、ブレイン。怒りと同時に自己嫌悪めいたわだかまりも打ち明けつつ、彼のモッズ精神も垣間見れるロング・インタヴューとなった。彼らを理解するうえでの助けになれば幸いである。

“アナーキー・イン・ザ・UK”ってのは、フラストレーションのエネルギッシュな爆風、みたいな曲だったわけで。その意味で、あれは俺たちが初期にやっていた楽曲にかなり近いよね。ところがいまの俺たちっていうのは、自分たちのソングライティングの技術をもっと磨くべく努力する、そういう領域にグループとして達しているわけだ。
 Sleaford Mods English Tapas Rough Trade/ビート |
■最新のプロモーション写真でもうひとりのメンバー、アンドリューの着てるピカチューのTシャツ、いいっすね。
JW:んーと……あー、それってどのTシャツのことを言ってるんだろ??
■ポケモンのキャラの、ピカチューのTシャツですけど。
JW:ああ、(急にピン! ときたように)絵が描いてあるやつ、あれのことかな?! うん、わかる。うんうん、あれは俺もいいなと思う! あれはたしか、あいつがどっかから仕入れて来たシロモノで……っていうか、あいつ、どこであのTシャツを手に入れたんだっけな??
■(笑)。
JW:あれを、奴はエドウィン・コリンズからもらったはずだよ。俺たち、(元パルプの)スティーヴ・マッケイ所有のスタジオで作業していたんだ。そこで、あのTシャツをゲットしたんだと思うけど。
■(笑)マジですか!?
JW:うんうん、俺たち彼のスタジオで作業してたし……っていうか、俺がいまここで思い描いてるのって、「白地に黒でドローイングの描いてある」、そういう図柄のTシャツのことなんだけど?
■いやいや、それのことじゃないですね。
JW:あー、そう!?
■あの、あれ。「ピカチュー」です。日本の「ポケットモンスター」というアニメを元にした、ゲームでも有名なキャラのピカチューのことなんですけどね。
JW:(素直にびっくりしたように)へえ! なんと! そうなんだ。
■はい。
JW:(どう返答していいのかわからない&どのTシャツなのかサッパリ見当がつかない、といった風で困った様子)ワーオ……オーケイ……。
■ともあれ、アンドリューはあの手の妙なノベルティTシャツ(※他にも、米アニメ「シンプソンズ」の警察署長キャラ:ウィガムをフィーチャーしたTなどを着用)をたくさん収集してるみたいですよね?
JW:ああ、うん。あいつはそれこそ他に誰も着ないような、ケッタイな古い服を見つけてくるんだよな(苦笑)。
■(笑)アハハ。
でまあ、それってあんまりこう、一般的には「すごくクールな服ですね!」って風には思われない、そういうシロモノなわけで。
■(笑)いやー、あのピカチューTシャツはかっこいいな! と思いましたよ。まあ、それはあのキャラが日本のアニメ発だから、というのもあったかもしれませんけど。
JW:ふーん、なるほど。
■でも、アンドリューがロゴTだのキャラの描かれたTシャツ姿なのが多いのに対して、あなたは無地/モノクロームというか、何も描かれてない服装が多いですよね?
JW:うんうん、たしかに……。
■それって、あなたにとってのファッション面でのこだわり、みたいなものだったりします?
JW:いやぁー、それはないよ! ただ……だからまあ、俺は服を買いに行くとか、ショッピングするのはかなり好きな方だし……そうは言っても、俺の好みは(ノベルティTとかとは違う)、もうちょっと高級なタイプのファッション、みたいなものなんだけどさ。
■へえ(笑)!?
JW:いやいや、だからさ、「高級」って言ったって、それはなにも「金がかかってる、これみよがしに派手な服」っていうのじゃなくて、一見したところ、ものすごーく平凡なんだよ。
■ああ。
JW:ただ、見た目は地味でも非常に良く仕立てられているし、だからこそ長いこと付き合い愛用できる服、という。
■なるほど。ちなみに、そんなあなたにとって、リアム・ギャラガーが関与しているモッズ系なブランド:Pretty Greenの服はどうですか?
JW:あれはひどい! うん、ひどい。
■(苦笑)気に入らないみたいっすね……
JW:あれはダメだろ? っていうか、リアム・ギャラガー本人を非難するつもりは、俺には一切ないんだけどね。そこはわかってほしいし……言うまでもなく、彼はとても良いシンガーだしさ。ただ……(息を深く吸い込んで)彼の関わってるブランドの服、あれは、好きじゃない。ノー。あれはヒドいよ。
■(笑)でも、彼はあのブランドを通じて「現代のモッズ」をやろうとしているんじゃないですか?
JW:あー、うん。そうだよな。ただ、あのブランドの「モッズ」って、とにかくミエミエ過ぎなんだって。
■(苦笑)なるほど。
JW:だから──たとえばの話、かつての時代のモノホンのモッズを振り返ってみれば、彼らはあそこまでわかりやすい、ミエミエに「モッズ」って見た目じゃなかったわけ。
■ええ、わかります。
JW:だから、「モロにモッズ!」な格好じゃなくて、実際の彼らは、ある意味もうちょっと控えめだった、という。だろ? それこそ、「これはファッショナブルとは言えないな」とすら映るような、野暮ったさの一歩手前なルックスだった。で、なんというか、そういう面に俺は魅力を感じるんだよ。「お洒落だろうか?」と気にしていないっていう。
■なるほど。まあ、お金って面もあるでしょうしね。リアムみたいにいったん大金を手にしたら、その人間は道楽のように「モッズが好きだから、じゃあ自分自身の『モッズ・ギア』のファッション・ラインを作ってみるか」なんて考えるものなんでしょうし。
JW:ああ、だよな〜。でもまあ、あれってのは……いや、きっとあれ(Pretty Green)をやるのは、彼(リアム)にとってはいいヴェンチャー・ビジネスの機会でもあるんだと思うよ。
■ええ、もちろん。
JW:きっと、あのブランドをやることで彼もいくらか稼いだんだろうし。だけど、こと……あのブランドそのもののテイスト/趣味って意味で言えば、ありゃあんまり上品とは言えないだろう、俺が思うのはそれだけだな。
■はっはっはっはっはっ!
JW:(苦笑)分かるだろ?
■(笑)それに、かなり高いお店ですしね。
JW:うん、ファッキン・イエス! 大枚はたかされるよな。とんでもない……ってのも、Pretty Greenはここ、ノッティンガムにも支店を出しててね。
■あ、そうなんですか。
JW:ああ、まだ順調に経営が続いてる。うん……でまあ、あの店はたくさんの人間に受けててさ。こっちで言う、いわゆる「若い野郎連中向けのマーケット」にね。だから、アークティック・モンキーズだとか、もちろんオアシスもそうだし、それとか……カサビアンとか? とにかくまあ、その手の音楽にハマってる若いラッズをターゲットにしたマーケットのこと。で、Pretty Greenは、そういう音楽が好きでフレッド・ペリーなんかを買いに走る若い野郎、それとか若い女性連中の関心を掴んでるわけだ。だからそういう類いの「市場」がちゃんと存在してるってことだし、実際、もうかるマーケットなんだよ。かなりの額の金が動くからね。
■ええ。
JW:というわけで……ただまあ、俺から見るとあれは「あんまり趣味が良くないな」。と。うん、服としてのテイストは良くないし、見てくれもヒドいよ。
■(笑)了解です。
JW:おう。
[[SplitPage]]
ノッティンガムってのはかなりの多文化都市だしね。多様なカルチャー、色んな人びと、様々な肌の色、それらが混ざり合っている……それは快適で気持ちの良いミクスチャーであって、人びとはみんな、他の連中の持つ独自のカルチャーをリスペクトし合ってきたよ。ただ、そんななかにもごく一部に分派、かなり人種差別な傾向を持つ団体が存在している、だけど、それってもう、昔からずーっとそうだったわけだろ?
 Sleaford Mods English Tapas Rough Trade/ビート |
■ブレグジットが浮上して、半年以上が経ちますが、ノッティンガムに変化はありますか?
JW:(軽く「ハーッ」と息をついて)「これ」といった変化はまだ起きていないと思うけど?
■そうですか、それは良かった。
JW:(つぶやくように)まだ、この時点ではなにも起きてないよ。まだ、ね……。(一拍置いて)ただ──そうは言っても、いまの俺はもう、昔みたいな単純作業系の職には就いていないしね(※ジェイソンは2014年から専業で音楽活動をやっている)。だから、そうだな……俺は、いわゆる「クソみたいな仕事」であくせくしてはいない、ってこと。というわけで、ブレグジットが民営セクターにまで影響を与えているのかどうか、本当のところは俺にもわからないんだ。いままでのところは、ね。
■そうは言っても、たとえば地元でパブに行ったり通りを歩いているうちに、ノッティンガムのなんらかの「変化」に気づくことはありませんか?
JW:ああ、ノッティンガムの都市部ではなく周辺の田舎のエリア、それはちょっとあるかも。俺の住んでるあたりでは、そういうのはそれほどないな。だから……なんというか、ある種の「人種差別的な気質」はたしかに存在するし、そうした面が表に出てきて目につく、というのはある。でも、そんなことを信じてるのはごくごく少数な連中だし、なのにあいつらは脚光を浴びて不相応な注目を集めている、と。
■はい、わかります。
JW:だろ? だけど、連中の言ってることは広く伝わってしまうんだよ。というのも、あいつらの発しているメッセージはものすごく卑しいもので、だからこそ人目を引く。音を立ててる人間の数そのものは少ないのに、それが倍の音量で伝わってしまう、みたいな。
■ですよね。
JW:でも……ノー、だね。「これ」といった、あからさまな経験は自分の身には降り掛かっていないな、正直言って──いまの段階では、まだないよ。うん、とりあえず、いまのところは、まだ。っていうか、ノッティンガムってのはかなりの多文化都市だしね。多様なカルチャー、色んな人びと、様々な肌の色、それらが混ざり合っている、そういう場所なんだ。だから……それは快適で気持ちの良いミクスチャーであって、人びとはみんな、他の連中の持つ独自のカルチャーをリスペクトし合ってきたよ。ただ、そんななかにもごく一部に分派、かなり人種差別な傾向を持つ団体が存在している、そこは俺にもわかっていて。だけど、それってもう、昔からずーっとそうだったわけだろ?
■はい。
JW:ただ、ブレグジットってのは……さっきも俺が言ったように、そういう不満を抱える少数の人間たちが、自分らの意見をもっと声高に叫ぶ機会を与えてしまった、と。
■なるほど。それを聞いていると、日本も似たような状況なのかな? と感じます。イギリスと日本はどちらも島国ですし、そのぶん「自分たちの国境を守る」という意識が強いと思うんです。もちろん、日本人の9割は善良で優しいタイプだとは思いますけど──
JW:もちろん、そうだろうね。
■ただ、一部にバカげた差別意識を持つひとがいるのは事実だ、と。
JW:ってことは、日本だと人種差別って結構多いの?
■いや、おおっぴらで頻繁ってことはないと思いますけどね。ただ、イギリスがヨーロッパ大陸に面しているように、日本も中国・アジア/ロシアという大陸を背にしている国で。でも、アジアからやって来る人びとを蔑む傾向があったりしますし。
JW:うん、なるほど。
■それってまあ、「日本は島国で、純粋な民族である」みたいな、アホでナンセンスな認識が残っているからだろうな、と思ってますけど。
JW:だろうね……うん、言ってることはわかるし、そうだよね。うん、いまの話は面白いな。でも、訊きたいんだけど、ってことは、いまも日本には「アンチ西洋」、あるいは「反米」みたいなフィーリングが強いのかな?
■いやー、それはないと思いますよ!
JW:そう?
■ええ、それはないですよ。心配しないでください。だから……日本人の奇妙なところって、知性とか文化の面で「こいつらは自分たちよりも進んでいるな」と感じる相手には、好意を示すんですよ。
JW:なるほど。
■だから、外国人に対しても……これはとても大雑把な言い方になりますけども、もしもその外人がいわゆる「金髪青眼」だったら、日本人は「わー、かっこいい!」と気に入る、みたいな。
JW:あー、なるほど。
■それってまあ、おかしな感覚ですけどね。
JW:うんうん……。
■自分でも、そういうノリは理解できないんですけど。ただ、そういう感覚はまだ残っていて……うーん、すみません、自分でもうまく説明できない。
JW:オーケイ。興味深い話だ。
■というわけで要約すると:「あなたがアングロ・サクソン系の見た目であれば、日本でトラブルに遭うことはまずないでしょう」というか(笑)。
JW:(苦笑)おー、オーケイ、わかった! だったら安心だな。俺たちもひとつ、日本に行くとしようか!
■(笑)ぜひ、お願いします。
JW:クハッハッハッハッハッ!
この生まれたばっかの地獄には
悲しみまでもが積もってく
“Time Sands”(2017)

俺としてはさほど「怖がってる」わけでもないし、あるいは「連中を恐れてる」っていうんでもないんだけどね。そうではなくて、俺はあいつらが「憎い」んだ。ものすごい激しさで彼らを憎悪しているし、だからこそ、そんな俺にやれる唯一のことというのは、なんというか、自分自身をそこから切り離してしまうことだと感じる、みたいな。
■ブレグジット、トランプ、世界はこの1年で大きな衝撃を経験しましたが、いまどんな気分でしょうか?
JW:うん、うん……(咳き込んで声を整える)いやほんと、かなり不安にさせられるよな。だから、だから……このあり得ない、ひどい状況をすべてギャグにして笑い飛ばすのは、ほんと簡単にやれるんだよ。ってのも、ある意味色んなヘマを起こしながら進んでいるわけで。
■ただ、政治なんでジョーク沙汰じゃないですよね。
JW:ああ、もちろん冗談事じゃないよ。ノー、これはジョークなんかじゃない。だから、いまのこの事態を大笑いしている人間が多くいるのに気づくわけだけど──でも、そうやって笑っていないと、泣くしかないしさ。だろ?
■たしかに。
JW:で……まあ、うん、これからどうなるのか、まだわからないよね。ってのも、俺としても彼らが一体なにをやってるのか理解できない、彼らがイングランドでなにをやっているのか、さっぱりわからないんだ。彼らは本当にひどいし、とても残酷なことをやっていて……だから、どうしてそうなってしまうのか、理解できないっていう。混乱させられるばかりだし、俺は完全に疎外されてしまった。彼ら脱退賛成派を人間として理解できないし、どうして彼らがああいう風に動いているのかも理解できない。ってのも、ブレクシットを進めながら、彼らは緊縮財政で予算削減も続けてるわけだろ? この国はいまや、完全にどうしようもない状態にあるってのにさ。
でも、まあ……かといって、俺としてはさほど「怖がってる」わけでもないし、あるいは「連中を恐れてる」っていうんでもないんだけどね。そうではなくて、俺はあいつらが「憎い」んだ。ものすごい激しさで彼らを憎悪しているし、だからこそ、そんな俺にやれる唯一のことというのは、なんというか、自分自身をそこから切り離してしまうことだと感じる、みたいな。わかる?
■ええ。
JW:でも、思うに……トランプ政権に対しては、そこまで感じないな。というのも、あれはアメリカ人の問題であって、俺の国じゃない。アメリカに住んでるわけじゃないからね、俺は。だから、自分に(トランプの)直接的な影響が及ぶことはない、と。
■ただ、あなたたちはもうすぐアメリカをツアーしますよね(苦笑)?
JW:ああ、アメリカ・ツアーを控えてる。うん、これから5週間後くらいにあっちに行くよ。だから、いまのアメリカがどんな感じなのか、現地で見聞きできるのは興味深いよな。
■そうですね。
JW:それでもまあ、共有されてるコンセンサスっていうのはいまだに──「あなたが健康な身で、銀行口座に残高がある限りは大丈夫です」なんだよ。ところが、いったん健康を損ねたり、あるいはお金が尽きてしまうと、途端にその人間はおしまい、アウトだ、と。
■ええ。
JW:というわけで……そういうもんだろ? その点はほんと、ちっとも変わっていないよな。ところがいまというのは、やかましい主張を掲げたもっと声のでかいアホどもが権力を握ってしまったし、しかもあいつらはひどい信念の数々を抱いてるわけで。でまあ……そうだね、前政権よりはわずかに劣るよな。
■その前政権とは、キャメロンのこと?
JW:いやいや、アメリカの話、オバマだよ。だから、多くの意味で「みんなおんなじ」って感じじゃない、実は? いやまあ、俺だって無知な人間みたく聞こえる物言いはしたくないし、様々なことを実現させるべくオバマは最大限の努力をした、というのは承知しているんだよ。彼は「大統領を退任して優雅に引退」するに値する、多くのリスペクトを寄せられるにふさわしい、それだけの働きはしたんだし(※ちなみに:2月初め、引退後さっそくイギリスの大富豪リチャード・ブランソン所有のカリブ海にあるネッカー島でのホリデーに招かれ、ボート遊びやカイトサーフィンに興じるオバマの姿がSNSに登場。批判する声も多かった)。
ただ、やっぱり人間ってエリート主義が抜けないんだなぁ、と。それってもう、ダメだよ。とにかく終わってるって。それって問題だよ。でも、そこで生じる問題というのは、これはとてもでかい問題だけど、じゃあ、そこでどうすればいいんだ?と。誰かが去って行っても、また代わりに他の人間が入ってきて「これからはこうなる」と指図するわけで。
■なるほど。それってもう、「椅子取りゲーム」みたいなものですよね? 主義がリベラルであれ保守派であれ、エリートのグループに属していればいつか順番が回ってくる、みたいな。
JW:まさにそういうことだよな。で、こうしたことについてくどくど話してる自分自身が、我ながら嫌でもあってね。そうやって現れる小さな側面をいちいち理解しようとトライしているわけだけど、支配する側の集団はおのずと生まれている、という意味で。ってのも、ある意味同じ「鋳型」から彼らは出てくるんだし……だけど、人民ってのは巨大だし、ものすごい数の人類が存在するわけだろ? なのに、俺たちはみんな、ひとりの人間に、それからまた次のファッキン誰かさんの手へ、って風に振り回されているだけっていう。自分らがどこからやって来たのか、それも一切関係なし。
だから、俺たちはあちこちに振り回されたらい回しされてるだけ、なんだよ。「これをやりなさい」、「あれをやりなさい」って命じられるばかりで、俺らは隅の一角にどんどん押しやられていく。戦争が起きると、ひとつの国は完全な悪者として処罰を受け、国土をすっかり破壊されてしまう。かたや相手の国は、そこまでひどい扱いを受けることはないわけで……ただまあ、世界って常にそういうものだったわけじゃない? で、そこが……(勢いあまって、やや言葉を詰まらせる)そこ、そこなんだよ、俺としてはとても混乱させられるし、そしてフラストレーションを感じさせられるものっていうのは。とにかく、「それ」なんだ。だから、統治する側は永遠に優勢な立場にいるし、それが変化することもないだろう、と。その状況にフラストレーションを感じるっていう。
■その「諦め」に近い感覚は、日本にもあると思います。イギリスほど階級制が強くないとは思いますけど、やっぱり一部にエリートの支配層が根強いですし。「なにも変わらないんじゃないか」と感じるひとはいるでしょうね。
JW:うん、きっとそうだろうね。
俺たちはこれ以上魂を売らねぇ
でも3ポンドでくれてやるよ
お願いだよ もう最悪
ブレクジットはリンゴ・スターのアホを愛してる
“Dull”(2017)
[[SplitPage]]
『イングリッシュ・タパス』という言葉は、いまのイギリスの現状を大いに物語るものでもあるよな、と思ってね。だから、無学だし、チープ。そんな風に、人びとはとりあえずのありもので間に合わせざるを得ない状態にある、と。
 Sleaford Mods English Tapas Rough Trade/ビート |
■「英国的」と言われているスリーフォード・モッズですが、自分たちの音楽が英国以外で聴かれることについてどう思いますか?
JW:(即答)グレイトだと思うよ!
■(笑)なるほど。
JW:うん、最高。だって、自分たちとしては「きっと俺らはノッティンガム止まりに違いない」とばかり思ってたしね。
■あっはっはっはっはっ! そうだったんですか?
JW:(ややムキになった口調で)いや、マジにそう思ってたんだって! ってのも、俺たちの音楽ってのは、こう……とてもローカルで地方限定なものなわけじゃない? 他の地では通じないような言葉だらけ、ローカルな通語でいっぱいな音楽だしさ。
■ええ、そうですよね。
JW:だから……「地方喋り」そのまんま、なわけ。それに、俺が歌のなかで語っている事柄にしたって……ぶっちゃけ俺以外の誰にも理解できないであろう、そういう話を扱ってるんだし。
■(苦笑)なるほど。
JW:もちろん、その「正直さ」が伝わる、ってところはあるんだろうけどね。だから……うん、俺たちとしても、(英国以外の国の人びとが聴いている、という事実に)本当にびっくりさせられたよ。
■そういえば、あなたたちはドイツで人気が高いなって印象を受けてるんですけども。
JW:ああ、あっちでは人気だね。
■それってどうしてなのかな、なんでドイツ人はスリーフォード・モッズに反応してるんだろう? と不思議でもあって。やはりドイツだと、「言葉の壁」はあるわけですし。
JW:うん、それは間違いなくあるよ。ただ、俺が思うに……ドイツってのはパンク、あるいはポストパンクのあれだけ長い歴史がある国なわけで。だから、ミニマリストな国なんだよな。で、彼らが俺たちに惹かれるのは、俺らの音楽にあるミニマリズムもひとつの要因なんじゃないか? そう、俺は思っていて。で、んー……俺自身としては、自分たちの音楽にはかつてのなにかを思い起こさせる面もあると思う。と同時に、この歌い方のスタイルにしても、おそらく聴いていると昔いた誰かを思い出させるんだろうし……だからまあ、これってちょっと奇妙なバンド、なんだ。ただ、考え抜いた上でこういう音になったわけじゃない、っていう。うん、色々と考えあぐねたりはしないよ。
■新作を『イングリッシュ・タパス(English Tapas)』と命名した理由を教えていただけたらと思います。
JW:まあ、俺たちはこれまでも「スペインのタパス」は体験してきたわけだよね。「スパニッシュ・タパス」と言っても、そのバリエーションの一種、ということだけど。だから、スペインのバーで出てくるタパスといえば、一般的にはピンチョス(※パンを使ったカナッペ風、あるいは楊枝を刺したバスク風の軽食。屋台他でも供される)なんかがそれに当たるよね。でも、その一方でもっと高級な「タパス」なんてのもあって……だからまあ、とにかく俺たちはスペインのタパスは経験豊富、色々と触れてきたわけ。で、ある日、アンドリューがイギリスでどっかのパブに入ったとき、そこのメニュー板に「イングリッシュ・タパス」って書かれているのを目にしてね。それがどういうシロモノかと言えば、スコッチ・エッグ(※ゆで卵を味付けしたミンチでくるみ、衣をつけて油で揚げた庶民的なスナック)にお椀に入ったフライド・ポテトが添えてあります……みたいな、(さも可笑しそうにクククッと半分吹き出しながら)とにかく、あーあ、これってマジにしょぼくてクソじゃん、(苦笑)、そういうメニューでさ。
■(笑)。
JW:だから、俺たちも「これは笑える!」とウケたけど、と同時に、このフレーズってある意味、いまのイギリスの現状を大いに物語るものでもあるよな、と思ってね。だから、(タパスのなんたるかを知らないで「タパス」という言葉を使っている意味で)無学だし、(料理そのものも安上がりで)チープ。そんな風に、人びとはとりあえずのありもので間に合わせざるを得ない状態にある、と。そんなわけで、「これってどんぴしゃなフレーズだな」、俺たちにはそう思えた、というだけのことなんだよ、ほんと。
■なるほど。フィッシュ&チップスみたいなありふれた料理のミニチュアでイギリス流に「スペインの伝統」をやっているのが滑稽に映った、と。
JW:うんうん、ほんとひどいよ! あれはひどい。せっかくタパスをやるんなら、もっと他に色んなやりようがあるのにさ……。ただまあ、これって一部のイギリス人にある態度だったりするけどね。だから、他のカルチャーに存在する美しいアイデアを引っ張ってきて、それをすっかり粗悪なものに歪曲してしまう、という。
■ああ。でも、それがまたイギリス人の長けているところ、でもあると思いますけどね? 粗悪にしてしまうとは限らず、他のカルチャーから影響を受けて、それを自分たちなりに解釈し直す、という。
JW:うん。
■たとえばレゲエのUK音楽への影響は大きいし、アメリカのブルースを、ローリング・ストーンズのようなバンドは1960年代のアメリカにある意味「逆輸入」したわけです。
JW:あー、うん、それはそうだよね……。たしかにそうだ。
■その意味で、他文化の翻案はイギリスの遺産でもあるのであんまり恥じなくてもいいかな、とも思いますが?
JW:いやいや、全然、そういうつもりじゃないんだ! だから、そうしたイギリスの遺産を恥じるっていうのは、俺にはあんまりないんだよ。ってのも、俺がこういう音楽をやってるのも、主にそうしたかつてのイギリス産のバンドたちのおかげなんだしね。ただ……最近の自分たちってのは、この国の持つ良い面よりも、そのネガティヴな側面の方ともっとつながってしまっていて。
■ああ、なるほど。
JW:だから、俺の考え方もネガティヴなそれになってしまうわけ。人びとに失望させられたって感じるし――保守党に投票した連中に裏切られた、EU脱退に賛成票を投じるのが得策だと考えた人びとに失望させられた、そう感じるっていう。というわけで、イギリスをネガティヴに捉えるのは俺個人の問題っていうか、うん、きっと俺の側にバイアスがかかっているんだろうね。
■でも、その感覚はもっともだと思います。自分の周辺の正気な人間、イギリス人の友人はみんな、いまが大変な時期と承知していますし。聖ジョージ旗(※白地に赤いクロスが描かれたイングランド国旗で、連合王国フラッグの意匠の一部)だのユニオン・ジャックを誇らしげに振り回す時期ではない、と。
JW:まったくその通り。そういうのをやるには、実に悪いタイミングだよな、いまってのは。
[[SplitPage]]
イギリスの遺産を恥じるっていうのは、俺にはあんまりないんだよ。ってのも、俺がこういう音楽をやってるのも、主にそうしたかつてのイギリス産のバンドたちのおかげなんだしね。ただ……最近の自分たちってのは、この国の持つ良い面よりも、そのネガティヴな側面の方ともっとつながってしまっていて。
 Sleaford Mods English Tapas Rough Trade/ビート |
■名前に“MODS”という言葉を入れたのは、ジェイソンがかつてザ・ジャムやMODカルチャーに影響されたからだと思いますが、最大級の皮肉にも感じます。
JW:だよな。
■あなたたちの音楽にはモッズ風なギター・サウンドも、ランブレッタも含まれていないわけで。
JW:うん、ないない! ノー、それはまったくない。
■では、バンド名になんでモッズと付けたのでしょうか?
JW:それはだから、俺が「モッズ」ってもんにすごく入れ込んでいるからであって。俺がハマってる「モッズ」の概念ってのは、新しいものを取り入れるって面なんだ(※モッズはもともと「Moderns」の略で、先進的な感覚を称揚した)。かつてのモッズというのは前向きに物事を考える、そういう考え方のことだったし……わかるだろ? 多くの人間が過去のなかで生きていたのに対して、モッズの姿勢は「過去に捕われずにいよう」、そういうものだった。それなんだよ、俺が好きな、多くの人間が抱いている「モッド」の概念ってのは。過去に留まってはいない、というね。
だから、「モッズ」の字義通りの意味合いを考えなくちゃいけないんだよ。あれは要するに、「モダニズム」から来ている言葉だしね。だから、その本来の意味は考えてもらわないと。で──その意味で、「モッズ」というのはクリエイティヴィティを生み出すってことじゃなくちゃいけないし、同時代的なものであり、それに今日(こんにち)についてなにかを語らせる、そういうものであるべきなんだよ。
■はい。
JW:ってのも、この世界の根本は変化していないしね。俺たちは永遠に、この「資本主義」っていうでかい傘の下で生き続けるんだろうし。まあ、この意見は「俺からすればそう思える」ってものだけど、少なくとも自分の知る限りはそう。だからこそ、その点について語るのは重要なんだよ。その点を音楽のなかに含めるのは大事なことなんだ、と。
■なるほどね。この質問の意図には、日本における「モッズ」というものの理解も混ざっているかと思います。日本だとモッズは常に「ファッションのひとつ」という捉えられ方で。
JW:ああ、そりゃそうだろうね。
■スクーターにモッズ・パーカ、映画「さらば青春の光」……とでもいうか、風俗として伝わっているけれど、さっきおっしゃっていた「(それそれの時代の)モダニスト」という真の意味はあまり伝わっていない気がします。
JW:うん。だけど、人びとはそこを理解しないといけないんだよ。だから、「モッズ=1963年」っていう概念は、捨ててもらう必要がある。ってのも、いまは1963年じゃないし、それは過ぎ去ってしまった。過去、だよ。
■ただ、さっきも言ったように、いまでもPretty Greenの服やフレッド・ペリーのポロシャツを買う若者は絶えないわけで──
JW:ああ、その通り。だから、根強い人気があるんだよね。いまだにすごくポピュラー。ということは、俺の持つ「モッズ」の概念ってのはいつだって、彼らの考える「モッズ」ってのにかなわないのかもしれないな(苦笑)。
■ハハハ!
JW:要するに、俺がスリーフォード・〝モッズ〟でなにがしかのトレンドをはじめたわけじゃない、と。ってのも、そんなの起こりっこないからさ!
■はい。
JW:んー、だから、そういう風に一般化した「モッズ」の概念ってのは、これまでも、これからも続いていくものなんだよ。ただ、俺はとある時点で、その一般像に辟易してしまってさ。すっかり、嫌気がさした。ってのも、そんな「モッズ」の概念はなにもやってなかったし、形骸化していた、とにかく俺にはそう思えて。だからこそ俺はより突っ込んでモッズについて考えるようになったし、それに取り憑かれてしまった、と。というわけで……うん、だから、スリーフォード・モッズには「モッド」がたっぷり含まれているんだよ。ただし、聴く人間にすぐわかるあからさまなものではない、というだけで。
■ちなみに、あなたたちのライヴをいわゆる「モッズ」なタイプは観に来る? それともそうした層からは無視されてる、とか?
JW:ああ、それなりの数のファンはいるよ。間違いなく、俺たちはモッズ連中からも共感は得ているね……うん、それは確実にそう。
■それは良かった。というのも、自分のイメージだとモッズは純粋主義者というか、「ひたすらノーザン・ソウルで踊る」みたいな。
JW:うんうん、その面はあるよな。たしかにそういう面は持ってる。そうだなぁ、その手の「純粋主義」な連中が俺たちのことをどう思うのか……俺にもよくわからないけども。まあ、たぶん気に入らないんじゃない?
■(笑)。
JW:きっと、全然俺たちの音楽を気に入らないと思う。聴いて即、「こいつらは却下!」だろうな。でも、そうは言ってもそうした純粋主義者のなかにもオープン・マインドな奴らはたくさんいるし、なんというか、「新しいこと」を取り入れるのに積極的って奴はいるからね。
**************
■あなたたちの音楽から、自分は「いまのブリテン」に対する失意を多く感じるんですね。
JW:ああ。
■では、10代、20代、30代のあなたがたは、人生に対してどんな夢を描いていたのでしょう? あなたの年齢だと10代は1980年代に当たりますが、まずそこからお願いします。1980年代のあなたの夢は?
JW:うん、とにかく生まれ故郷から脱出したかったね。そうやって外に出て行って……つまらない仕事に従事すること、その不快なリアリズムから逃れたかった。若いうちから住宅ローンを抱えていたし、それが鎖みたいに俺を縛り付けていたんだよ。
■ああ〜、そうだったんですね。
JW:でも、俺自身はそんなのまったく欲していなかったし……俺はいろんなことを体験したかった。(軽く息をついて)でまあ、そういう生き方にトライしてみたし、ある程度それは実現させたんだ。けど、俺は自分自身の面倒をみるのがあんまり上手じゃなくてね。だから、しょっちゅうどうしようもない状態に自分自身を落とし込んでいた、と。だけどまあ……うん、若いうちから、俺はエスケープを求めていたね。
■その状況は、20代=1990年代にはどう変化しました? この時期に、あなたはおそらく音楽をはじめて、バンドにも参加していたかと思いますが。
JW:うん、だからあの頃は、「音楽をつくる」のが夢だったんだよ。要するに、音楽活動を通じてどこかに出て行ければいいな、と。というわけで、俺は音楽について学び始めたし、自分の技術、クラフトを学んでいった。そこからだったんだよね、俺が「モッド」に対する疑問を非常に強めていったのは。「どうしてこうなるんだ?」と。ってのも、俺は以前にいろんなモッズ・バンドに参加していたし──それはまあ、「モッドな傾向を持つ」と言っていい類いのバンドのことで(※以下の発言からも伝わると思いますが、ここでジェイソンの言っている「モッズ寄りなバンド」というのは、一時のブラーやオアシスのように「ブリットポップにアレンジされて再燃した、広い意味でのそれ」のことだと思います)、そういうのに2、3、関与したことがあったんだ。で、それらは……とても限定されたものだと感じてね。リミットがあったんだよ。
だから、当時の俺には世のなかが変わりつつあるのが見えたし、そういうのは終わりを迎えていた。ブリットポップ熱はあっという間に過ぎ去ってしまった。世界は変化してしまったし、なのに「モッズ」という概念は旧態依然としていた、と。
■なるほど。ということは、あなたにとって最悪な時代というのは「その後」=30代に入った00年代、になりますか?
JW:うん、30代に最低な時期を迎えたね。まったくもって、良いとこなしの時期だった。
■それは、あなたが自分の方向性を見失ってしまったから? 「なにをやればいいのかわからない」みたいな?
JW:ああ、うん……でもまあ、「方向性を見失った」ってのはちょっと違うかな。ってのも、そんな時期にあっても、俺は「自分は音楽だ」って姿勢を崩さなかったし、曲を書き続け、学んでいたから。
■なるほど。
JW:ただ、こと「自分が持つ自己のイメージ」っていう意味では、「こうありたいと思う自分」という意味で、自らの方向を失っていたね。だから、俺は長いこと……かなり思慮に欠けた人間だったんだよ。それでも、この考え、「音楽で進路を切り開こう、音楽で生計を立てよう」って思いつきになんとか執着し続けてきたわけだけど、と同時に同じ頃、自分でも悟った、というのかな。だから、いったん30代になってみて、「音楽のなかにおける自分の〝居場所〟を理解し、学ばなくちゃいけない」って思いが浮かんだんだ。
というわけで、そんな俺にとって、ただ「自分以外の何者かのフリをする」ってだけでは物足りなくなってしまったんだよ。ってのも、あの手のバンドの多くがやってるのってそういうことじゃない?
■はい。
JW:だから……うん、30代は「学びの時期」だったね。もちろんそうは言ったって、楽しい思いも味わったんだけどさ。でも……と同時に、あれは決して「グレイトな時期」ではなかった、という。
■“Jobseeker”の歌詞は実体験を元にされているんですか?
JW:もちろんそう。
■非常にタフな内容で、「うわぁ……」と感じてしまうんですが。
JW:あれは実体験に基づいてる。だから、あんな風に俺は長いこと、とても低調な状態にあったんだよ。職業斡旋所に申し込みをしなくちゃいけなくて……そうやって、職を見つけてなんとか事態を解決しようとするわけ。ところが俺にはそれができなかったし、最悪だった。どうにもうまくいかず、機会をおじゃんにし続けるばかりでね。というわけで、“Jobseeker”ってのはそういう状況にぱっと目線を落としてみた、という曲なんだ。で──あの曲のストーリーは、いまも語る価値のあるものだと俺は思っている。というのも、いまだに多くの人びとが毎日、あの体験を経ているわけだから。
■ええ、ええ。
JW:だから、成功したにも関わらず俺たちがあの曲をプレイし続けている、その点を批判されてもきたんだよ。だけど、あそこで歌われているのは俺が実際に体験した物事なわけだし。で……「のど元を過ぎれば」って具合に、その人間が過去に味わった経験を忘れるのは当然だと人びとが考えるのって、ほんと無礼な話だと思っていて。
だから、もしもあれが俺の実体験を歌ったものじゃなければ、なるほどそう批判されても仕方ない、ごもっともです、と。ところがあれは、俺自身がかなり何回も潜ってきた体験だからね。で、俺としてはあの経験/ストーリーはいまでも有効、伝える必要のあるものだと思っているし、“Jobseeker”はやっぱりまだかなりパワフルな歌であって。だから俺たちはいまも歌うよ、と。
■具体的にはどんなお仕事をされていたのでしょうか? 以前は区の失業手当のアドバイザーもやっていたそうですが、他には?
JW:うん、洋服屋、色んな洋服屋で働いてきたよ。洋服屋の経験は豊富だし……あれはかなり良い仕事だよね。ってのも、俺はもともと洋服が大好きだし、だからある意味、あれは興味深い仕事だった。それから……倉庫の人夫仕事に、工場勤めもやったし、警備員だったこともある。カフェで働いたこともあったな。
■(笑)あらゆる類いの仕事をやってきた、と。
JW:そう、なんでもやった。
(※ウィリアムソンの職歴に関して野田ライナーは間違えています。ここに訂正、お詫び申し上げます)
[[SplitPage]]
イギリスの遺産を恥じるっていうのは、俺にはあんまりないんだよ。ってのも、俺がこういう音楽をやってるのも、主にそうしたかつてのイギリス産のバンドたちのおかげなんだしね。ただ……最近の自分たちってのは、この国の持つ良い面よりも、そのネガティヴな側面の方ともっとつながってしまっていて。
 Sleaford Mods English Tapas Rough Trade/ビート |
■さて、音楽的な話をしたいのですが、『イングリッシュ・タパス』は、『オーステリティ・ドッグス』の頃にくらべて、機材的な変化はありましたか?
JW:それはない。変化なし。以前とおんなじ。
■(笑)。
JW:いやまあ、アンドリューは2、3個くらい、「おもちゃ(ガジェット)」を買ったけどさ……。
■はっはっはっはっ!
JW:ただ、それにしたって、たぶんたかがiPadとプログラムをいくつか購入、程度のもんだろうし。うん、変化と言ってもそれくらいだよ、ほんと。
■あなたたちのライヴの映像をネットで観ても、基本アンドリューはラップトップ1台きりで、実に「経済的」なセットアップですもんね。
JW:うんうん、だから、実際のとこ、俺たちはあんまり多くの機材を必要していないんだよ。ふたりともエレクトロニカに入れ込んでるし、それにヒップホップもいまだに好きで。その手の音楽はシンプルな機材を使う媒体だし、そういうのが好きな俺たちもまた、自然にコンピュータ使いに向かう、と。それに言うまでもなく、テクノロジーは発展しているわけで。あれらの装置……マシーンも、技術の進歩を受けて小型化してもいる。だから、それこそもう、(苦笑)「なにも使わず音楽をやってる」みたいな?
■(笑)なるほど。では2013年頃以来で、とくにレコーディングにおける機材面での変化はなし、と。
JW:ないない。唯一の変化と言えば、おそらく俺たちはもっとベターな曲を書く術を学んだ、その意味で、だね。だから、歌詞の面においてもいままでとは違う題材を扱うようになったし……それに、俺はシンガーとしても学んで、たぶん以前より良くなったんじゃないかな? だから……変化と言ったらとにかくそういう事柄だろうし、うん、そうやってなにもかも、実に絶え間なく発展している、と。
でもほんと、そうあるべきなんだよ。ってのも、この俺たちの「公式」はあんまりいじれないからね。そもそもとてもミニマルなフォーミュラだから、過度にその領界を押し広げようとすると、逆に良さをブチ壊すことになってしまう、と。わかるだろ?
■たしかに、ヘタにそれをやるとバカげたものになっちゃいますよね。
JW:うん。
■たとえばあなたがたが急にEDM系のビートを取り込み始めたら、それだけでも「ソールド・アウトした!」ってことになるでしょうし(笑)。
JW:(苦笑)そうそう、まさにその通り。
■マイクやサンプラーなどの機材はどのように集められたのでしょうか?
JW:まあ、「あっちでひとつ、こっちでひとつ」って具合に集めてきた、その程度のもんだよ。アンドリューは以前から色々機材を集めていたし、安物のラップトップだとか、チープなマイクロフォンなんかをいくつも持ってて。それに音楽づくりに使ってるプログラム群にしても、思うにアンドリューの奴は海賊版ソフトウェアとかをいくつか持ってた、程度じゃないかな。だから、他の連中の持ってたプログラムの複製、みたいな。でも、エレクトロニカをやるのに、そんなに色んな機材は必要じゃないんだよ。だから……エレクトロニカでためしになにかやってみるのに、最初の時点で大金をはたくことはまずない、と。
■ええ。
JW:もちろん、その人間が「本物の、高級なサウンドでエレクトロニカをやりたい」と思うのなら、話はまた別だよ。そういう考え方だと、(機材他で)高額の出費を覚悟することになるだろうし。だけど、俺たちのサウンドってのは──あれはむしろ、そこからどんなアイデアが生まれるだろうか?なんだ。俺たちの手元にあるツールの数そのものはごくわずかだよ。ただ、それらをすべてちゃんと活かしてやりたい、それが狙いなんだ。
■あなたたちの音楽はミニマルとはいえ、アルバムを聴き終わるとぐったりすることもありますしね。歌詞といい、その意味合いといい濃いので、40分足らずの作品でも大作を経験したような気がします(笑)
JW:うん、たくさん詰め込まれてるし、聴く側にはかなりの量だよな。
■新作『イングリッシュ・タパス』では、ドラムマシン・ビートがよりミニマル(音数が少なく)で、ときに冷酷になっている気もするのですが、そこは意識しましたか?
JW:フム。でも、なんであれアンドリューが持ち込んだものだし、ビートはあいつ次第だから。
■(笑)。
JW:要するに、ただあいつがつくってくるだけ、みたいな。で……彼がやっていることは、俺にもわかっちゃいないんだよ。彼がどんな影響を受けてああいうことをやることになったのか云々、そこらへんは俺も知らない。
■(笑)なるほど、そうすか……。
JW:だから、詳しいところまでは俺もよくわからない、ってこと。だから、彼はすごく……とにかくうまくやってのけてるし……ほんと、とても、とても腕が立つ奴なんだよな。彼がビートを持ち込んできて、そこから俺たちは一緒に音楽に取り組む、と。
■でも、アンドリューのつくる音楽部は、基本的にあなたの書く歌詞とそのムードにマッチしなくちゃいけないわけですよね?
JW:うん、基本的にはそういうこと。うんうん。ただ、俺の歌詞ってのは……型に合わせることが可能っていうか、ループに合わせるのも、ある程度までは簡単にできるものだからね。ばっちりハマるときもあるし、イマイチ合わないなってこともあるわけだけど……んー、だから、かなりストレートなプロセスなんだよ。
オーガニックのチキンを食った
ありゃクソだぜ
夕暮れの寝室で1日が終わる
“Cuddly”(2017)
■“Cuddly”なんかはダブっぽいんですけど――
JW:うん、あれもアンドリューが持ってきたビートで、とにかくかなりダビーなものだよね。あるいはスカっぽさがある。
■ということは、今作において音楽的な変化は意識しましたか? あなたたちのセットアップはとてもシンプルで、音楽的なバリエーションは決して多くないわけですけども。
JW:ああ、それはあるよね。「音楽的に広げなければ」の考えは俺たちにもあったし、ふたりともそこは自覚していたよ。だからスタジオに入るときも、その点はちゃんとケアしなくちゃいけないんだよ。でまあ──ラッキーなことに、これまでのところ俺たちには曲が浮かんできた、書き続けることができたわけだけども、今後「(書き手としての)壁」にぶつかることになったら、それはそれとして、やっぱ対峙しなくちゃいけないだろうな、と。
■つねに踊れる曲を意識していると思うんですけど、ダンス・ミュージックであることのポジティヴな点をどのように考えますか?
JW:うん、そういうポジティヴな要素は間違いなく含めたいね。ポジティヴだし、ほんと、俺たちの音楽って実はポジティヴな形式の音楽なんだ。というのも、中身が濃い音楽だし、たくさんの思考が注ぎ込まれてもいて……だから根本的に、俺たちのやってるのってポジティヴなことなんだよ。でも、うん、かなり「ノれてがんがんヘッドバングできる」、俺たち流のそういうなにかをやるのは、自分たちにとって大事だね。
■はい。でも、Youtubeとかであなたたちのライヴの模様を観ていると、お客のなかには「これってなに? どうリアクションしていいかわからない」みたいに当惑しているひともいますよね。
JW:……(沈黙)。
■いや、もちろん、ノリノリで踊ってるお客さんもたくさんいますよ! ただ、なかには「ワーオ……! なんでこのひと、こんなに怒りまくってるの??」と不思議そうな表情を浮かべている連中もいるな、と。
JW:ああ……そうだよね。ただまあ、俺がライヴでああいう風なのは、とにかくエネルギーが強いからであってさ。自分は曲そのものの持つエネルギーを取り入れているだけ、なんだ。
■なるほど。
JW:でも、俺はなにも……(ハーッと軽く息をついて)まあ、俺って気難し屋の厄介な奴になっちまうこともあるしね!(苦笑)
■あっはっはっはっはっ!
JW:(笑)だから、自分には「とてもポジティヴなひと」とは言いがたいときもある、と。思うに、そういう面もちょっと出て来るんだろうね。自分のパーソナリティに備わった側面をそこに乗せてもいる、と。
■でも、とくにライヴをやっているときですけども、基本的にハッピーで楽しんでいるオーディエンスと向かい合っていて、ふと「なんで俺はぎゃぁぎゃあわめいてるんだ? なぜ自分はこんなに怒ってるんだ? 俺ってフリーク?」なんて感じることはありますか?
JW:いやいや、それはまったくないよ。どのライヴでも、毎晩俺たちのやろうとしているのは同じこと。ステージに上がり、思い切りプレイして、曲を良く響かせよう、それだけのことだから。
■そうなんですね。いや、こっちにいるあなたと年代も近い知り合いには、普段の生活のなかで思わず怒りを感じる、「これは間違ってる」と思うような物事に遭遇して、人目をはばからず声を上げて怒るひとがいるんですよ。
JW:ああ。
■それは別に根拠のない怒りでもなんでもなくて、怒って当然ってシチュエーションなんですけど、それでも彼らが我慢せずに怒っていると、周囲の人間はそれが理解できずに「こいつ、なにに怒ってるの? 問題ないじゃん、チルしなよ〜」みたいな冷静なノリで。
JW:ああ、うんうん。
■で、そういう目に遭うと、彼らは疎外感を抱くそうなんですね。「みんな黙ってるのに、怒る自分の方がおかしいのか?」みたいな。
JW:(苦笑)だろうね。
■で、あなたもときにそんな風に感じるんじゃないか? と想像してしまうんですが。
JW:いやー、そういうのはないな。それはただ、俺たちのやってる音楽のフォームがそういうものだから、であって。ああいう「表現の形式」を、俺たち自身でクリエイトした、ということに過ぎないから。
■ふたりとも、レイヴの時代(89年〜91年)には、20歳前後だったと思いますが、その頃レイヴにはまることありましたか?
JW:うん、当時の俺はレイヴ・カルチャーに相当ハマってたよ。90年代前半、91、92年あたりだったかな? クラブにさんざん入り浸って、エクスタシーを食っていた。
■(笑)。
JW:だからしばらく間、レイヴ・カルチャーはつねに俺の一部だったね。
■あなたがヒップホップ好きだったことは知られていますが、ハウス・ミュージックもOKだった、と。
JW:うん、好きだったよ。
■ノッティンガムには、DiYというとんでもないレイヴ集団がいたのですが、ご存じでしょうか?
JW:あー、うんうん、DiYね。
■おー、ご存知ですか!
JW:DiYは、うん、ノッティンガムではかなり名が知れていたよ。それにいまも、形を変えてある意味続いているし。
■そうなんですね。
JW:ああ、彼らはその名の通りかなり「Do It Yourself」な連中だったし、ノッティンガムの歴史のなかに自分たちで塹壕を築いた、みたいな。
■彼らはフリーでパーティを企画していた集団ですよね。
JW:うんうん。いまだにフリー・パーティは続いているよ、折に触れて、ね。
■ちなみにあなたは、ゲリラ的な野外レイヴに参加したことは?
JW:ああ、1、2回行ったことはあったよ。でも、俺はそっちよりもクラブの方にもっとハマっていたんだけどね。無料の野外パーティに行くよりも、俺はクラビングの方が好きだったんだ。
■それはたとえば、野外レイヴには「どうなるかわからない」不安定さがあったから?
JW:いや、っていうよりも、とにかく俺は……クラブに出かけるときにつきものの、「良い服でキメる」みたいなのにもっと惹かれていたからさ(笑)。
やったな おい これがブツだ
家でフェイマス・グラウスを傾けながら
俺のケータイで良い感じの曲でも流して
俺とお前でキマるのさ
どうしようもないエクランド(女優)みたいな
俺らはダメイギリス人
クソ輸入モノの1パイン缶を飲み干す
スパーへの旅行は火星へ行くようなもん
“Drayton Manored”(2017)

 Sleaford Mods English Tapas Rough Trade/ビート |
■『オーステリティ・ドッグス』から『デイヴァイド・アンド・イグジット』にかけて、ガーディアンをはじめとする欧米の主要メディアはスリーフォード・モッズに対して最大限の賛辞を送りましたよね(※ガーディアンは2年連続で年間ベスト・アルバム/後者はWIREも年間ベストに選出)。スリーフォード・モッズは新人ではないし、それより何年も前から活動してきたあなたがたが、2013年頃から急に脚光を浴びたことについてはどのように思っていますか?
JW:ああ。まあ、あれはかなり妙な状況だったけれども、いまの俺はもう「大丈夫、気持ちの落とし前はついた」ってもんで。オーケイ、わかった、と。ってのも、これは俺にとっての「仕事」でもあるんだしね。だからああした突然の脚光についても、自分なりのパースペクティヴに収めることができてるよ。
■なるほど。
JW:だから、いまの俺はもう、ああいうのに驚かされたりショックを受けることはなくなった、と。ってのも……仮に自分たちがもっとビッグになって成功していたら、もしかしたら、ちょっとはそんな風に感じるのかもしれないよな? ただ、俺たちの音楽がそこまで「大きくなる、人気が出る」ってことは、まずないだろうと思っているし。
■(苦笑)そうですか?
JW:まあ、未来がどうなるかは誰にもわからないけどね(笑)?
■たしかに、あなたたちの音楽は聴き手に向き合う/ある種挑戦する類いJW:のものだし――
うん。
■いわゆる「万人に愛される」音楽ではないですよね。
JW:ああ、それはない! まったくそういうものではないよ。ただ、そうは言ってもいままでのところ俺たちの人気はますます伸びているみたいだし、「これからどうなるか、お楽しみに」ってところだね。でも、うん、急に脚光を浴びるとか、そういうのには俺も慣れたよ。
■なるほど。でも、そうなる以前はやはり違和感があった、「ええっ? 俺って急に人気者かよ?」みたいな感覚があった、と?(※新作では彼らの成功への妬みへの憤怒もちょくちょく出てくる)
JW:イエス! そうだった。だから、俺たちのギグに急に有名人なんかが来るようになった云々、そういうのはちょっとばかし妙だったね。けど、うん、いまはもうオーライ。これはとにかく自分のやってる「仕事」につきものの一部であって、だからいちいち「わあ!」なんて驚いちゃいられないしね。
■そうやって「突然の奇妙な状況」も受け入れられたのは、あなたのなかに変化に左右されないような、「スリーフォード・モッズとはなにか」っていう強い理解があったから、でしょうか?
JW:うん。だから、それはまあ……
■あなたにとって、こういう音楽をやる動機ってなんですか? もちろん、あなたは音楽が好きで、だから音楽をできるだけ長くつくり続けたいひとだ、そこはわかってますよ。
JW:ああ。
■でも、それ以外でスリーフォード・モッズをやる目的、動機と言えば?
JW:とにかく「良い曲を書きたい」、それだよ。そうやって良い曲を書き続けたいし……
■そこで言ってる「良い曲」というのは、長く聴き継がれる曲、という意味で? たとえば“アナーキー・イン・ザ・UK”みたいな?
JW:まあ、“アナーキー・イン・ザ・UK”ってのは、フラストレーションのエネルギッシュな爆風、みたいな曲だったわけで。その意味で、あれは俺たちが初期にやっていた楽曲にかなり近いよね。ところがいまの俺たちっていうのは、自分たちのソングライティングの技術をもっと磨くべく努力する、そういう領域にグループとして達しているわけで。どこまで自分のソングライティングをプッシュできるかやってみよう、と。それに俺たちは、必ずしも以前のように「ものすごく怒っている」というわけでもないからさ。だからいまの俺たちは、それよりむしろ「曲づくりという技」を研究している、というのに近いんだ。
俺たちは国会を乗っ取り
アイツらをぶちのめさなきゃならねぇ
当然だろう?
あいつらは貧乏人を殺そうとしてるんだぜ
“Dull”(2017)
■なるほど。そこはちょうど次の質問にも被りますが:怒り(rage)がスリーフォード・モッズの音楽の根源にあるとよく言われますが、新作においてもそれは変わりないと思います。あなたがたは明らかにブレグジットに対して怒っている。ジェレミー・コービンが非難されたことにも怒った。いま、いちばん怒っているのはナンに対してですか?
JW:あーんと……(フーッ! と軽く息をつく)いま、俺がもっとも怒りを感じるもの、かい? そうだなぁ〜、クソみたいなバンド連中とか(笑)?
■はっはっはっ!
JW:(苦笑)クソみたいな、ファッキン・バンドども。
■(笑)でも、ダメなクソ・バンドはずっと嫌ってきたじゃないですか。
JW:シットなバンド、同じくクソな音楽業界。ギョーカイは自己満なマスカキ野郎だし、政治もマスカキ。
■でも『イングリッシュ・タパス』には、ダイレクトに「名指し」してはいませんけど、ボリス・ジョンンソン(※元ロンドン市長で、現英内閣の外務大臣である保守党政治家。EU懐疑派として知られ、ブレクシットでも大きな役割を果たした。ブロンドのおかっぱ髪と一見温和そうで政治家らしからぬ親しみやすい「クマのぬいぐるみ」的キャラで人気がある)のことかな? と解釈できるキャラが何度か出てきますよね(※“Moptop”、“Cuddly”の歌詞参照)。
お前がやってることなんてまったく可愛くねぇよ
クソテディ・ベア野郎
“Cuddly”(2017)
仲良くしろよって俺が言う前に
そう言う前にセリフを忘れちまった
あの野郎はブロンドだ
おまけにモップトップだぜ
“Moptop”(2017)
JW:ああ〜、うんうん。
■ということは、ボリス・ジョンソンはいまあなたが大嫌いな「道化野郎」のひとりなのかな?と思いましたが。
JW:ああ、最低なオマ*コ野郎じゃない、あいつ?
■(苦笑)。
JW:ファッキン・オマ*コ野郎。ただのクソだよ。
■(笑)その通りだと思います……。
JW:っていうか、あいつはただの「ガキ」なんだよな。成長してない「子供さん」だから、こっちもどうしようもない、お手上げ、と。あいつはいまいましい子供だよ。というわけで……まあ、今回の作品で扱っている対象は色々だけど、その意味では、これまでとそんなに変わっていないんだ。
■とはいえ『イングリッシュ・タパス』では、これまでにくらべて実在人物の名前を歌詞に含める、というのをあまりやっていませんね。
JW:ああ、そうだね。というのも、バンドとしてビッグになればなるほど……とにかく無理、ああいうことはやれなくなってしまうんだよ。ちょっとした嘆きの種をこっちにもたらすだけだ、みたいな。わかるだろ?
■(苦笑)なるほど。
JW:それもあるし、自分のこれまでやってきたことを繰り返す、というのは避けたいわけで。だから、俺としてもただ他のバンドだの誰かをクソミソに罵るとか、そればっかり続けていたくはないっていう。仮にそれをやりたいと思ったら、(これまでのように実名ではなく)もっとさりげなくやるよ。だから……ビッグになればなるほどこちらに跳ね返ってくるものも大きくなるわけで、それにいちいち対応してると時間もやたらかかるし──
■時間の無駄だ、と。
JW:そう。だからこっちとしてもわざわざ関わりたくないよ、と。俺は議論はそんなに得意な方じゃないし、誰かさんがなにか言ってくる、俺に反論してくるような状況って、対応に時間ばっかりかかるからさ。
■それもありますけど、いまの過度なPC(ポリティカル・コレクトネス)の風潮、とくにSNSにおけるそれが怖い、というのもあります?
JW:ああ、その面もあるよね。
■ツィッターや発言の一部が、前後の文脈とまったく関係なしに取り上げられて、意図したこととは違うものが大騒ぎになったりしますし。
JW:うんうん。
■でもツイッター上でのあなたはかなり活発ですよね? まあ、バンドをやっているから仕方ないでしょうけど。
JW:まあ、あれはやらないといけないしね。だから、間違いなくそういう面もあるけれど、んー、とにかくああしたもののベストな利用の仕方を自分で見極めようとトライするのみ、だからね。
■SNSを罵りながら、あなたはツイッターを使い、たまに炎上していますよね? あなたがたは明らかにツイッターやSNSを嫌っていますが、使ってもいます。現代では必要なものだと思うからですか?
JW:ああ。まあ、欠点もあるけど、俺自身はそこまで気にしてないんだ。だから、乱用し過ぎると悪い結果に結びつくけど、そうならないように、たまにSNS等から離れるように心がけていればオーライ、と。
■批判を受けたりツィッター上での粘着された経験があっても、別に構わない、やり続ける、と?
JW:ああ、もちろん! 全然、俺は構わないから。以前にいくつかそういうのもあったけど、そこにあんまりかかずらわっちゃいないしね。自分はそれほどあれこれと悩まされたりはしないし、そうならないようトライしてもいるし。
■かつてよりも面の皮が厚くなった、と。
JW:イエス。まったくその通り。
**************
■スリーフォード・モッズがケン・ローチの『わたしは、ダニエル・ブレイク』のプロモーションをサポートしたという話を聞きましたが、あなたがたは、あの映画をどのように解釈し、どこに共感しているのでしょうか?
JW:あの映画は、まだ観てないんだけどね。
■ええっ、そうなんですか!?
JW:ああ。
■でも、FBにあの映画の台詞を朗読するヴィデオ・メッセージをアップしてましたよね??
JW:うん、それはやったよ、うんうん。ただ、映画そのものはまだ観てないっていう。
■あら〜、そうなんですね。
JW:だから……これから観なくちゃいけないんだけど、でも、あの映画がどんなものなのか、俺には観る前からすっかりわかっているよ。で……んー、だからまあ、どうなんだろうな? もちろん、どこかの時点で観るつもりなんだよ。ただ、あのヴィデオへの協力で俺がやろうとしたのは、あの映画の発するメッセージを応援する、ということだったわけでさ。
■なるほど、わかります。でも、まだ観れていないというのは、単純に忙しくて観に行く時間がなかったから? それとも、あなたの知る現実にあまりに近い話なので、当事者として逆に観る気がなかなか起きない、という?
JW:うん、身近過ぎるよね。だから、あれは……心に深くしみる、そういう映画になるだろうし、自分が現役を退いたらやっと観れる、そういうものだろうね。でも、うん、いつか観るつもりだよ。
**************
■最後に、UKのロック文化はなぜ衰退したんだと思いますか?
JW:どうしてだろうね? 俺にもわからないけど、やっぱりそれは、『The X Factor』でロックってものの概念にとどめが刺されちゃったから、じゃないの? だから、人びとはもうロック文化とはなにか? について学んだりしないし、なにもかも額面通りに受け止めるだけ、と。それにまあ、ここ10、15年くらいの間、イギリスで音楽的にすごいことってあんまり起きてこなかったしね。だから、いま出てきてる若い連中にとっても、励みになる、目指すような対象が正直そんなにたくさんいないっていう。で……いまのキッズが聴いてるバンドってのは、おそらく90年代発のバンド連中なんだろうし、それとか70年代勢に入れ込んでる子たちもいるよね。ただ、ただ……ギター・ミュージックってのは、もうさんざん複製されてきたものなわけでさ。だから、人びとにはもうちょっとイマジネーションを働かせはじめる、その必要があるんじゃないのかな?
■はい。
JW:でも、バンド連中がやってないのはまさにそれ、であって。そんなわけで、レコード会社の側も「なんとなくいまっぽい」風に仕立て上げたアクトを色々と送り出してくるわけだけど、そこにはなにもない、空っぽなんだよ。そうしたアクトは、利益を生むためにコントロールされているからね。だから、イギリス産のアクトで伸びている、そういう連中はあんまりいないよね。ほんと。
■ということは、もしかしたら90年代のオアシス以来、イギリスのロック界は変わっていない、と?
JW:ああ、そうだね。おそらく最後のグレイトなバンドだったんだろうな、オアシスが。
■あ、オアシス、お好きなんですか?
JW:うんうん。素晴らしいよ──初期作はね。
■(笑)なるほど。1枚目のアルバムはすごい! みたいな?
JW:ああ、(苦笑)1枚目ね。
俺は自由にマスをかき
生まれながらにして自由
“Dull”(2017)
だからどうしたってんだ
オレはやりてぇようにやる
“Army Nights”(2017)
(註)
『Xファクター』:2004年から始まり、現在も続くイギリス産の大人気リアリティTV。公募オーディション+視聴者投票による勝ち抜き音楽コンテストでレオナ・ルイス、ワン•ダイレクションら人気スターもこここから出発。「カラオケ・コンテスト」と揶揄する声もある。