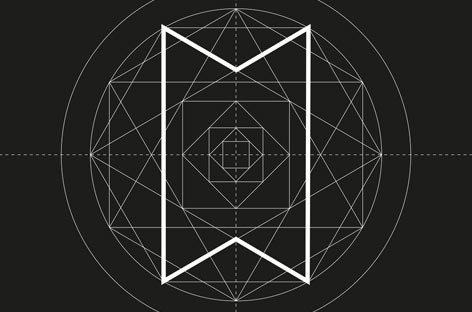はじめに言っておくと、オープンリールというのは記録再生装置であって、けっして楽器の名ではない。しかし「オープン・リール・アンサンブル」なるこの5人組ユニットの発言にはたびたびそれを「演奏する」という表現が登場するから、困惑する人もいるだろう。
はたして彼らはそれを本当に「演奏する」のである。
東京を拠点として、いまや世界を舞台に活躍する5人組、オープン・リール・アンサンブル(以下ORE)。言葉を積み上げるよりも、ここは一見にしかず。ライヴ映像を一本ご覧になれば、彼らがどんな「演奏」をするのか、そのおおよそが見てとれるだろう。そして同時に、彼らがいかに定義と説明の困難な表現活動を行っているかということも、一瞬でご理解いただけるはずだ。
以下は、そのオープンリールを「演奏する」男たちに、彼らの活動原理と理念、表現内容について解きほぐしてもらったインタヴューである。
それは音楽のようであり、パフォーマンス・アートのようであり、ただ実験であり、遊びのようでもあり、歴史の研究であり、ワークショップ(教育)でさえある。さまざまな形態に分化しながらも、彼らは、はじめてオープンリールに触れたときの驚き──テープが回り、手のひらでダイレクトに音が歪む感触を得たという、その鮮やかな感動に駆動されて、いまも活動と探求を続けている。「オープンリール」と発音するときの彼らの目は、表現者というよりも、ほとんど冒険者であり科学少年のそれだ。
 Open Reel Ensemble Vocal Code Pヴァイン |
いったい彼らはオープンリール──歴史的にはいちどその役目を終えている装置を通して、何を再生しているのだろうか。
今月発売されたアルバム『Vocal Code』への質問から、話題はいつしか宇宙をめざすエキゾチズム、“空中特急”の隠されたテーマ──彼らの持つ近代観/未来観、そして文明という「主電源」をオンにすることの興奮と畏れについての述懐へと深まっていった。
演奏をご覧になったならばぜひ、「3ページめ」だけでもお読みいただきたいと思う。2020年、かの祭典の5つの輪に向かって5台のリールを回すのは彼らしかいない。
Contents
1)
ハロー、オープン・リールの伝道師たち。
OREとはこんな集団だ!
2)
オープン・リールとは究極の「エキゾ」を立ち上げる装置である……のか!?
OREとそのニューエイジ的宇宙観を探る
3)
“空中特急”の隠されたテーマとは?
僕たちが押す「主電源」は発展のためのスイッチか、それとも滅亡のためのそれなのか──。
OREの「近代的」未来観を解体する!
■Open Reel Ensemble / オープン・リール・アンサンブル
2009年より、和田永(Concept, Programming, Compose)を中心に佐藤公俊(Compose)、難波卓己(Vln)、吉田悠(Per)、吉田匡(Bass)が集まり活動開始。旧式のオープンリール式磁気録音機を現代のコンピュータとドッキングさせ、「楽器」としてして演奏するプロジェクト。リールの回転や動作を手やコンピュータで操作し、その場でテープに録音した音を用いながらアンサンブルで音楽を奏でる。2011年6月に発売されたNTTドコモのスマートフォン「GALAXY S SC-02B」”Space Balloonプロジェクト”(第15回文化庁メディア芸術祭エンターテイメント部門大賞プロジェクト)に音楽で参加し、10月には初となる音源作品『Tape to Tape』を5号オープンリールテープにて限定数リリース。ライブパフォーマンスへの評価も高く、Sonar Tokyo、Sense of Wonder、KAIKOO、BOYCOTT RHYTHM MACHINEなどに出演。海外ではSONAR 2011 Barcelona、ARS ELECTRONICA(in Linz of Austria)に出演している。2015年9月、佐藤と難波が「卒業」。
オープン・リールを初めて触ったときに、これは何かできるぞ、という感触があった──それがともかくもスタートなんです。(和田永)
■これ……すごいですよね。

『回転 ~En‐Cyclepedia』(学研マーケティング、2013年)
和田永:はははは!
■真面目な話、ネットにインタヴューもいっぱい上がってますし、なによりこの本を読めばOpen Reel Ensemble(以下ORE)については十分なんじゃないかと思います。編集者の方も素晴らしいですが、みなさんご自身もこの中ではかなり編集的に立ち回っておられますよね。誰にどんなインタヴューをするか、みなさんが決められたんですか?
吉田悠:そうですね。それぞれ要素に分けてお話をききたいと思ったんです。音楽的な面は誰で、機械の面は誰で、という感じで。
■そうそう。ただ憧れの人に訊きました、というのではなくて、一冊を「編んで」いますよね。
吉田匡:ドクター中松が入っていないのが……心残りなんですけど。
■お、では第2巻に期待ですね。そもそもOREはコンセプチュアルなバンドだなと思うわけなんですが、高木正勝さんへのインタヴューの中では、高木さんが「OREは僕と似ているんじゃないか」という旨のご発言をされていますね。いわく、「僕たちはプロではなくて“素人”なんじゃないか」と(※)。
和田:ああ、なんか思い出してきました!
※「いきなりですけど、実はね、オープンリールアンサンブルって僕と似てるなって思っているんです。僕って「音楽家」じゃないんですよ」「音楽のジャンルっていろいろあるじゃないですか。そこに「素人」っていうジャンルがあったら、僕はそこにぜひ入れてほしいなって思ってて(笑)」
■たしかに、たとえば「エレクトロニカを突き詰める」というようなジャンル・マスター的な性質のバンドではなさそうですし、「年間シングル何枚出さなきゃいけない」というような産業的な条件にしばられたポップ・バンドでもないですし、かといってアート・パフォーマンス集団、と言うには音楽的すぎる。「プロ」じゃないという独特のニュアンスはよくわかるんです。
みなさんご自身は、自分たちを何だと思っていらっしゃるんですか?
和田:そうですね、自分たちでそういう線引きを考えたことはあんまりないというか。オープン・リールを初めて触ったときに、これは何かできるぞ、という感触があった──それがともかくもスタートなんです。そのおもしろさや感触を伝えようと思ったし、どうやったら伝わるんだろうって考えた。それで生まれたものが、結果的にはジャンルの横断を起こしていたという感じでしょうか。オープン・リールによる演奏を見つけていく中で聞こえてきた音楽や見えてしまった世界を表現しているというか。
吉田匡:使える技術があって、知っている古い機械があって、それを併せたら新しいことができると思いました。しかも、オープン・リールをズラっと並べて、人も揃えれば、バンドみたいなことができるんじゃないか、って──感覚的にはバンドの結成みたいなものでしたね。僕や兄は楽器ができる人間だったし、バンドの経験があったので、そういう役割としてOREに加わったという感じです。
でも、やっているうちに、このオープン・リールっていう機械がどこまでのポテンシャルを持ったものなんだろうって、その可能性を掘りつくしたいという思いもどんどん出てきて。
和田:確かに(笑)。
吉田匡:だから、たとえばオープン・リールのことを知らない人たちに向けて、このデッキの素晴らしさを伝えるワークショップをやったりとか、そういうことに専念した時期もありましたね。
活動としては、CDを出したり、音楽事務所に所属したりでミュージシャンっぽいんですが、もう……ほとんど、オープン・リール宣教師というか。
和田:まさに。
吉田悠:うん。
■ははは! いや、まったく同じ表現を思い浮かべましたよ。「オープン・リール宣教師」──私のほうは「オープン・リール伝道師」かな。
吉田悠:高木正勝さんの言葉をいま思い出していたんですよ。先ほど「アート集団」とか「ミュージシャン」とか、いくつか表現が挙がりましたけど、そういう言葉には歴史とともにいろんなイメージが付随しているものじゃないですか。そういうイメージのために僕たちのやっていることが定義づけられてしまうのはもったいないなという感覚があるので、自分たちで自分たちのことをとくに名づける必要はないかなと思ってます。そういう意味で「素人」かもしれないですね。
やっぱり、なにか、答えられないんですよね……「ミュージシャンなんですか?」って言われても、「はい」って(笑)。
和田:ひとつひとつ、便宜的な表現でしかないんですよね。
もう……ほとんど、オープン・リール宣教師というか。(吉田匡)
やっぱり、なにか、答えられないんですよね……「ミュージシャンなんですか?」って言われても、「はい」って(笑)。(吉田悠)
■そうですね。まあ、資本主義においてはそれがないと流通していかないから、仕方なくプレス・リリースに一言で説明しなきゃいけない(笑)。
吉田悠:そうなんです、ぜったい訊かれますから。「何をする集団なんですか?」って。ビデオの資料をつくるときなんか、「何をする」っていうよりも、あれもこれもできることをすべて入れていきます。でも、それで納得してくれる人もいれば、「で、結局何に特化した人たちなの?」って困る人も多くて(笑)。
■わかりますよ。
和田:それでもやっぱり、言葉に区切りきれない部分があるんです。ただ、いちばん中心にあるのはヴィジョンかもしれないですね。オープン・リールっていうものの、まさに宣教師、伝道師──それを使った独自の進化、風景を見せるものというか。OREっていうのは、ガムラン・アンサンブルをもじってるものでもあるんですよ。オープン・リールでアンサンブルをすることを中心にして、いろんなところに触手が伸びていってる。
どこかに到達したということはなくて、いまもつねにそのときの興味で模索している感じです。CDをリリースするというのは、アウトプットのひとつですね。
■ええ。アルバム制作の論理とか動機が、いわゆるミュージシャン的なものとはちょっとちがいますね。
和田:いろんな表現の架け橋として、オープン・リールという媒体があるというか。オープン・リールは、いろんなものをつないでミックスしていくメディアみたいなものです。
「OREのパフォーマンスはとてもおもしろいけど、CDになるとあのよさがわからなくなる」って言われて。(吉田悠)
■なるほどなあ。根本の動機というか、オープン・リールの伝道師という面では、みなさんは本当に強烈なライヴを行っていらっしゃると思うんですよ。伝道師というからには、その魅力を言葉なり何なりの方法で伝えなければならないですよね。
吉田匡:そうですね。
■ワークショップとか本も効果的かもしれませんけど、みなさんの場合はなんといってもライヴがすごい。オープン・リールがズラっと並んで、まず視覚的なカタルシスがやばいじゃないですか。もう、教会のミサでパイプオルガンに向いあうようなもので、儀式性がハンパないですよ。
吉田悠:正面向けてますからね、オープン・リール。
■そう、奏者が背中を見せている(笑)。音を出す道具ってだけなら、卓みたいなものだから、こっち向けばいいんですよ。だけど、あくまでオープン・リールを神というか、祭壇みたいに──
和田:おっ立てて、照明で光らせるという。そして回転を見せる。
■そう(笑)。ステージであれが5台、神々しく発光している。それに、あの和田さんの楽しそうに飛び回る姿、みなさんがなにかめちゃくちゃ真剣に回したり止めたりしているパフォーミング。あれを見ると、なんだかわからないなりに、いっしょに感染して打たれるというか……「ああー、なんか、オープン・リールすごいな万歳」って(笑)。一種敬虔な気持ちになってしまう。ほんと、ミサか何かなんですよ。
和田:たしかにそれはあるかもしれないですね(笑)。オープン・リールっていうものを前の世代から受け取って、自分たちなりに命を吹き込んでいく、新解釈を加えていく、っていうことなんですけどね。
■「自分たちなり」すぎる(笑)。しかし、先ほども少し話題に上がりましたが、そうなるとますますOREにおけるアルバムの位置づけが気になりますね。もう、あの「ああ、回っている!」というライヴの瞬間に途方もないエネルギーがあるので。
吉田悠:今作の前に、〈コモンズ〉さんからリリースになったファースト・アルバムがあるんですが、あれはOREがパフォーマンスとして蓄積してきたものを一度音源化しようという試みだったんです。そのときにいろんな問題が表面化したんですよ。「OREのパフォーマンスはとてもおもしろいけど、CDになるとあのよさがわからなくなる」って言われて。
自分たちも薄々そうかもしれないと思っていたことでもあったので、それはやっぱりひとつの壁になりました。もちろん意識してパフォーマティヴに見せているし、ORE自体が映像作品的な面を持っているとも思っているんですけれど、そうでありつつも、どうやって音でOREの世界に引き込むことができるのかというのは課題だと思っていて。そんなふうなことを感じながら、次のアルバムはどうするべきかということが話し合われたんです。
■なるほど。
CDを出すって、ものすごく普通のことなんですけど、OREにとって「挑戦」になっている(笑)。(和田永)
吉田悠:だから、今回は「テープ・ポップ」なんてキーワードが出たりもしたんですが、ORE的な解釈に基づいてポップ・ソングをつくってみようということになりました。OREというものを音で伝えるための手段というか……「曲」的であるというか。
■「曲」的。そうだと思います。
吉田悠:ORE的エッセンスが、「曲」というフォーマットの中で聴こえてきたほうが、アルバムをつくる上では武器になるんじゃないか、と。
■ええ。
和田:まぁ、けっこういろんなフィードバックがある中でできあがっているので、ある瞬間にアルバムのすべてが決まったということではないんですけどね。
吉田匡:ひとつわかりやすい手法としては、声が吹き込まれていて、それがテープの中で歪(ゆが)んでいくというのは、きっと作品として魅力になるだろうと。それはたまたまみんなが出してきたもののなかで一致した要素でした。メンバーごとに曲を出し合ったんですけど、結果として声はひとつのテーマになっていきました。
和田:アルバムをリリースするというのは、アウトプットのかたちを選ぶときにいちばんスタンダードなフォーマットでもありますよね。そのスタンダードなフォーマットに対してどんなことができるだろう、っていうところに興味もありました。
──というか、CDを出すって、ものすごく普通のことなんですけど、OREにとって「挑戦」になっている(笑)。
■ははは! たしかに。CDなりレコードなり配信なり、アルバムっていうものが自明で絶対的な単位になっていないってことですね、OREにとっては。CDを出すっていう普通のことが実験になってしまう。音楽産業というレールの上で何ができるのかという実験。
和田:そうなんですよね。それがインタヴューとかをしながら不思議な感覚に陥る瞬間なんですけど(笑)。OREのひとつの側面を切り取って、それがどう伝わるかという挑戦だったりもして。
オープン・リールにはアート的な側面にも可能性を感じているのですが、一方で、そこから出てくる音、奏でて出てくる音が純粋に特徴的で。あるときは暴力的で、ある時は幻想的。音それ自体にもキャラクターを感じます。今回はメンバー全員が作詞か作曲を通して「楽曲」に携わっているんですけど、そういうバンド的な作曲行為と、僕たちがこれまでに見つけてきた「オープン・リールのおいしさ」だなっていう音とがうまく結びついたらいいなという思いはありました。テクノロジー的なアプローチと、音楽的なアアプローチをつなげたいなと。
オープン・リールというものから想像した物語とか景色を歌ってもらっているんです。オープン・リールの歴史とシンクロしていたり。……物語の中の登場人物。(和田永)
Open Reel Ensemble - 帰って来た楽園 with 森翔太
■そのふたつを結びつける上で、ポップ・ソングというフォームが機能するのではないかと。ということであればすごく今回のアルバムの意味はわかって、本当に、まず「曲」っぽいですよね。あと、それぞれの歌い手さんたちも、どういう原理で呼び寄せられているのかなということをお訊きしたかったんです。以前参加されていたやくしまるえつこさんや高橋幸宏さんは、「歌(唄)」をうたってもらうというよりは、もう少し「声」として、解体して戯れるという関係だったのかなって感じますが、今回は歌を歌ってもらっているという感じでしょうか。
吉田匡:そうですね。1曲めはいきなり「ヴォーカリスト」ではないですが(笑)。
和田:オープン・リールというものから想像した物語とか景色を歌ってもらっているんです。オープン・リールの歴史とシンクロしていたり。……物語の中の登場人物。キャスティングさせていただいたという感じに近いですかね。
1曲目に関しては、ザ・フォーク・クルセダーズの“帰ってきたヨッパライ”の勝手な続編をつくるっていう着想があって──歌とオープン・リールということで浮かぶのがあの曲だったんです。それで、勝手なオマージュを捧げようと思って、ヨッパライの息子が登場したらいいな、と。それで、お酒が飲めなくてミルクが大好きで、上京してきて社会に揉まれる髪が薄めのサラリーマンという設定が生まれてきて、森翔太さんにお願いすることになりました。
■なるほど、息子はiPhoneユーザー。21世紀です。
吉田悠:森翔太さんについては、歌声を知らずにオファーしていました。
■あ、声をずいぶん歪めている?
吉田匡:いえ、まるで編集したかのようなんですが、ほとんどそのままなんです。
■すごい。『回典』の中の大友良英さんとの対話の中に出てきましたね、「レコード・ウィズアウト・ア・カバー」(クリスチャン・マークレー)。もともとノイズだけ録音されていて、カバーがないから後からどんどん傷が付くんだけど、再生するとそれがもともとのノイズか盤の傷のノイズかわからないっていう。あれみたいな(笑)。
吉田匡:ははは! 森さんの存在がすごい。
和田:森さんがふざけるとオープン・リールの声みたいになるもんね(笑)。
■もう一回聴きなおしたい。すごいインパクトの冒頭曲です。2曲目の“回・転・旅・行・記 with 七尾旅人”ですが、七尾旅人さんはご自身の歌と世界と声、それぞれにあまりに強い個を持っておられると思います。それこそ簡単に解体なんてできるものではないですよね。
吉田悠:解体というより、これはもう完全にコラボレーションでしたね。両者が制作者でした。
和田:七尾さんと僕らの世界が一体になったような。
吉田匡:歌の部分はほぼ、歌詞もメロディも七尾さんにつくっていただいたような感じです。キャスティングといいつつ、本人役で出ていただいているような。それじゃただの歌い手と変わりないじゃないかとも言えますが、その方の持っておられるバックグラウンドをそのまままるごと中に置けるような人にお願いしています。七尾さんも、七尾旅人として入っていただいているので、そこはもう全部出してくださっていいというか。
■なるほど。先にトラックはあるということですか?
吉田匡:トラックと曲のテーマから、歌詞もメロディラインも七尾さんのアウトプットでつくってもらって。
■あ、テーマは先に伝わってるんですね。
吉田匡:曲名は決まってないですけど、ニュアンスとしてはお伝えしてました。
■回転とか、そういうイメージですかね。歌詞にも「磁気テープ」って触れられていましたよね。
吉田匡:あれは、七尾さんからのウインクだと思ってます!
■なるほど! 七尾さんの声自体を加工しようとは思いました? それこそ高橋幸宏さんのヴォーカルを加工したい、挑みたい! というのとは別の原理の歌や声かと思うんですが。
吉田悠:僕たちも高橋さんのときはそんな気持ちがありました。僕たちのテープの世界へようこそ! みたいな。連れ込ませていただいたからには、いじらせていただくぞ、と。
■ええ、ええ。七尾さんの歌はその意味で崩すのが難しい?
和田:基本的に、中心にある歌はほとんどそのままにさせてもらって、僕たちの世界がそのまわりにあって、という感じです。ただ、いくつか声の素材としていただいたものについては、ちょっとオープン・リールを使って加工したりして、音源ではバランスをとってやらせてもらいました。ライブではけっこう歪ませていたりします(笑)。
■そういう作業は、やっぱりPCも使ってですよね?
和田:そうですね、行ったり来たりですね。5人の家のすべてで、ほとんどつねにオープン・リールとパソコンとかつながったままになっているんです。それでデモを投げ合ったり、素材を投げ合ったり。
やっぱりオープン・リール伝道師的には、「回転崇拝」は重要なキーワードです(笑)。(和田永)
「Cyclatrous(サイクラトラウス/回転崇拝)」という言葉もできましたから。(吉田悠)
■なるほど。七尾さんの歌詞は、地名とか国の名前がつながっていって、それ自体に反復的な雰囲気もありながら、意味の上でも、ああ、地球は丸いよなっていうモチーフが生まれていくような内容で。本当にたくみで。
吉田悠:そこは本当に七尾さんが素晴らしいんですよ。僕たちの世界を汲み取っていただいたので、それに応えたいという気持ちでした。これ、曲名も「回転」+「旅行」だから、「オープン・リールと七尾(旅人)さん」になっていると思いません? そのくらいいっしょにできたなって。
■やけのはらさんとの“Rollin' Rollin'”って曲があるじゃないですか。あの曲もMVふくめて回転がモチーフになっていますよね。なにか、レコードが回ることに対する──みなさんはテープですけど、回転と音楽ということに対するある種の感覚には、通じるところがあるんじゃないでしょうか。
吉田匡:それはあるかもしれないですね。
和田:やっぱりオープン・リール伝道師的には、「回転崇拝」は重要なキーワードです(笑)。
吉田悠:「Cyclatrous(サイクラトラウス/回転崇拝)」という言葉もできましたから。
和田:“Cyclatrous”っていう、4楽章ある曲を作ったんですよ(※)。時間や反復は回転として空間に展開されますよね。音楽が時間であるならば、それは回転運動で視覚化するとやっぱりしっくりくる──
※『回典 ~En-Cyclepedia~』に「特転」DVDとして付属・収録されている。
■わかりますよ。
吉田悠:ははは。大抵のひとは「は?」なんですけどね。
■いや、よくわかりますよ(笑)。
吉田悠:うれしいな(笑)。
■しかもテープの場合は、ほんとに手のひらの感覚として、それが現実の空間を歪めてるんだってことが感じられるわけでしょう? 音とつながってるんだって、和田さんがどこかで言っておられた。まさにその感じがすべてのはじまりというか、OREがダテではないんだということがわかるお話です。
和田:それは……すごく大事なことですね。(微笑む)
(一同笑)
■うれしそうっていう(笑)。なにか、和田さんは中学くらいの頃からオープン・リールで始終遊んでいた、みたいなエピソードを読んだんですが。「ボールは友だち」的な。
吉田悠:実際、彼がオープン・リールに出会ったのは中学で、その前から自作楽器とか、自分の世界で何かをつくることには興味があった奴なんですよ。だから、オープン・リールだけが特別というよりは、その中の出会いのひとつという感じだと思います。
でも他にも楽器をいろいろ作っていた中で、オープン・リールがいちばん大きいプロジェクトで、いまでも続いているという点では、やっぱりポテンシャルの高さがあったんだろうね。
和田:(感慨深げに)そうなんだねえ……。
Next→→
オープン・リールとは究極の「エキゾ」を立ち上げる装置である……のか!?
OREとそのニューエイジ的宇宙観を探る
僕たち自身がまさに、正しい使い方を知らずに(オープン・リールに)出会ってるんですよ。僕たちが勝手に解釈したおもしろさから入り込んでいるんですね。(吉田悠)
■いや、たとえばオーディオ・ファンのひととか、あるいは古くからご活躍のミュージシャンとかがオープン・リール愛を語るときって、もっと角度がちがうと思うんですよね。「オープン・リールだと太くて丸い音がしてね……」とか、もっぱら音質の話であって、みなさんはちょっとヘンですよね。オープン・リールそのものへのフェティッシュな愛というか……。
吉田悠:世代かな?
吉田匡:うん。それなりに値段も高くて、立派な現役の機材として使われていた時代があったわけですよね。僕らはそれが廃れた後の世界で、引っぱり上げてきて使っている。その感覚には差があると思います。
吉田悠:よく和田が譬え話として言うんですけど、オープン・リールがアマゾンとかを漂流していって、奥地にたどりついて、何も知らない原住民たちがそれを拾い上げて、用途を誤解したままそれを使いはじめた──結果、生まれてきたパラレル・ワールドなんです。僕たち自身がまさにそうで、正しい使い方を知らずに出会ってるんですよ。僕たちが勝手に解釈したおもしろさから入り込んでいるんですね。
■うんうん。
吉田悠:そこは機械が現役だった時代の人たちからすれば楽しみ方がちがうというか、もしかしたら怒られるかもしれない部分ですよね。
吉田匡:テープだから音がいいとか、音楽編集においても優れているというような部分は、ある種、追求され尽くして廃れていった部分だと思うんですね。それとはまったく別のレールを歩いていると思います。
■……ですよね。だから、オーディオ・マニアとかが抱く興味とはまるで関係ない。
和田:ああー、そういう関心とはちがうね。
■ええ。もっとワンダーな感覚というか。
吉田匡:ワンダーですね。
和田:そう、エキゾチズムですよ。
■そう、エキゾチズム。
ワンダーですね。(吉田匡)
そう、エキゾチズムですよ。(和田永)
和田:本(『回典』)の中で宇川直宏さんもおっしゃっていたキーワードですね。オープン・リールに対して抱く感情にはいろんなレイヤーがあるんですけど、出会いの瞬間はなんだこの異物はっていう。そしてそこから出て来るサウンドに異国性を感じましたね。一種の民族楽器のような。音や魅力の謎を紐解こうとするとサイエンスな興味関心も湧いて来る。磁気録音の仕組みとか、松岡正剛さんともお話ししているような──回転と自然界の関係性とか、っていう。で、次のレイヤーには触って楽しいとかっていう身体感覚がある。あとは、もうキュイーン! って回ることの高揚感とか。
吉田悠:僕らが高い塔の上にオープン・リールを置いてライヴをやったりするのも、単純にそのプロポーションがかっこいいとか、その程度の理由だったりするんですよね。
■うん、うん。その驚きというか、ワンダーな感覚を、思いっきりきちんと表現できているから、見ているわれわれもつい感染してしまうんですよ。なんだろう、ドラえもんが取り出してくる道具みたいな驚き──あ、そうそう、古い機器なのに、まるで未来の道具かのような感触があるのかなあって。
和田:古い機械だけど、録音というテクノロジーのやばさをつねに体験できますね。
古い機械だけど、録音というテクノロジーのやばさをつねに体験できますね。(和田永)
■だから、世代っていうのはそのとおりかも。リアタイ世代のおじさんが同じようなことをやっても、あの未知のものに触れるような楽しそうな感じって出ないかもしれませんね。
和田:もう、オープン・リールを早回しにして出てくる音とか、エキゾ以外のなにものでもない。ぐにゃーって歪む感じとか。
吉田悠:練習中にサウンド・チェックとかをしていると、中に何が入っているかわからないままテープを再生することがあるんです。そうすると前回のライヴの音が残っていたりするんですね。それがまた関西とかの公演だったりすると、電圧の関係で回転速度がちがっていることがありまして。急にヘンなピッチの音が流れてくるんですよ。その瞬間、みんな同時に手をとめて、「いいねー」みたいな(笑)。
■あはは!
和田:そう、もう結成から5年経ってますけど、まったく変わらないですね。ヘンな音が出てきた瞬間に「いいね~」って(笑)。
■アナログの可能性ですね。宇川さんが本の中で、エキゾチズムは究極的には宇宙に向かうっていうようなことを言っておられましたよね。アフリカだ何だっていうワールド志向は2000年代の半ばにも一回すごくリヴァイヴァルしましたけど、そういう借りてきたトライバリズムなりエキゾチズムではなくって、OREにはOREならではの、なんか別次元にスイッチするものがありませんか? 異界との出会いなんですよ、きっと。関西と東京の電圧の差の中に宇宙があって──
和田:50ヘルツと60ヘルツの境界にね。
(一同笑)
吉田匡:地理的なものじゃなくて、ちがうヘルツの世界に行ったっていう(笑)。
和田:関東と関西でモーターの速度が変わって音楽が変化する。そこにバージョン違いが生まれる(笑)。
■そう、地理では分けられない異界なんだけど、地理も存在する。つまり、大阪なら大阪という現実の場所を何層にも分けるような感じ方なんですよ。異界をつくりだして何倍も楽しめる。──不況型かもしれないですね。お金かけないで世界を2倍にする楽しみ方。
実際、祭りにして巡礼したいと思ってるんですよね。(吉田悠)
■とすると、ニューエイジ的でもあるというか。現実が変わらないなら薬でとんで脳内を変えよう、っていうのとある意味で似ていて、オープン・リールひとつを通して現実を変えないまま変えるという。
和田:そうなのかもしれない……。
吉田匡:しみじみしとる(笑)。
■そうすると、やっぱりエキゾチズムの極致なのかもしれない。
吉田悠:実際、祭りにして巡礼したいと思ってるんですよね。
■え、祭ですか? 「充電」……?
吉田悠:巡礼です。伝統と呼ばれているもの──いつ誰がつくったのかわからないお祭も、遡っていけば必ずそれをスタートさせた人間たちがいるわけじゃないですか。僕らがオープン・リールを通していつのまにかその第一回をやっていた、というふうにならないか。何十年か経ったときに、「この地域ではこの時期になるとオープン・リールの祭りをやるんだよ」ってふうにならないかなと思うんですよ。そういうかたちでのエキゾチズムへの接続もあるかもしれません。
■ああ、なるほど。
和田:オープン・リールを紐解いていくと、すでにいろんな先人たちが築いてきた歴史が積み重ねられていますし。
■オープン・リールを囲んで男たちが踊っている様子が、絵巻になって残ったりとか。「初期はこのように催されていたのだ」みたいな(笑)。
吉田悠:やぐらを建ててね(笑)。
吉田匡:俺たちのライヴ映像が資料として残る(笑)。
和田:「オープン・リール・トラディショナル」っていうキーワードも出たりしましたね。オープン・リールっていう歴史の軸に、われわれも登場したいです。大野松雄さんがいたりとかスティーヴ・ライヒがいたりする──
吉田匡:せまい(笑)。
■おもしろいですね。ふつうトラディショナルな祭りって土地に紐付いて存在しているものだと思うんですよ。東京で催されていたとしても、河内音頭は河内のものだし、よさこいは北海道のもの。その意味では土地からは離れられないものなんですよね。でも、モノを介して、大野さんとかライヒとか、時空を超えたところにフラグを立てる祭があってもいいですよね──四次元祭みたいな?
和田:うふふふ。毎年録音して声を重ねていったり。
■時空を超えた地図の上の祭なんて、やっぱりエキゾチズムの究極なんじゃないですか(笑)。
オープン・リールの最期を見届けるっていうのもやってみたかったり……(微笑)。(和田永)
だから、僕たちは「こういうお葬式をしてください」っていうことを遺していけばいいと思うんです。(吉田匡)
回典 ~En-Cyclepedia~ Open Reel Ensemble PV
■ところで、オープン・リールってもう生産されていないわけじゃないですか。ということは、みなさんを見て「楽しそうだな」「やってみたいな」って思ったとしても、これからさらにどんどん手に入れにくくなる……?
和田:まあ、徐々には。
吉田匡:所有している方から譲ってもらったり、買ったりということになりますね。
和田:僕らのデッキについては、近所に偶然すごいエンジニアの人がいて、修理してもらえるんですよ。
■ええ、すごいですね。おいくつくらいの方ですか?
和田:もう定年退職されて……。
■やっぱりそんなご年齢なんですね。じゃあ、またみなさんの課題が見つかりましたね。グループの中で、修理できる能力を持った奴を育てないと。
和田:うふふふ。たしかに。製造もしないといけないし。
吉田悠:そういう意味では、CDのリリースだったりとか産業的な流れに僕たちがコミットしているのは、オープン・リールの需要を活性化させていきたいなということでもあるんですよ。世間を巻き込んでいって、未来にこの機材を生き残らせるぞという。内輪の楽しみだけじゃなくて、外の世界に関係していかなきゃというところもあります。
■ああ、なるほど。
吉田匡:僕たちを見て、捨てようと思っていたデッキを譲ってくださる方もけっこういらっしゃるんですよ。「可愛がってあげてください」って。そもそも、捨てられようとしているものでもあるんです。
■うん。みなさんが消えたら消えてしまうかもしれない。だから残さないと。
和田:そうですよねえ……。……でもどうなんだろう。なんか、こう……。
■そんな文化的社会的な貢献とかよりも、もっと、パーソナルで原初的な楽しみを大切にしたい?
和田:いや、そういうことじゃなくて、(オープン・リールの)最期を見届けるっていうのもやってみたかったり……(微笑)。
(一同爆笑)
■(笑)フェティシズムの極みだな。
吉田匡:結成と同時に解散の要件も決めているんですよ、僕たちは。
和田:でも、僕らが死ぬ頃くらいじゃ、きっとまだぜんぜん残っていますから。そういう意味では、まぁ、まだ遊んでていいかなって思ってます。
■狂ってるよ……。
吉田匡:だから、僕たちは「こういうお葬式をしてください」っていうことを遺していけばいいと思うんです。
■(笑)
和田:でも、この、死が前提っていう感じもいいというか、制約の中で今しかできないとか、テクノロジーの宿命も感じさせるじゃないですか。
■うん、なるほど。みなさんの場合、オープン・リールが一度終わったところからはじめていますしね。
和田:そうですね。僕らが結成する前年にテープの生産がほぼ終了しました(笑)。
■そうそう。逆に、そのあたりから、フォーマットとしてカセットテープを選択するアーティストが増えましたね。ブームというか。
吉田悠:僕たちはいちおう、もともとのテープ世代ですよ。カセットテープからMDに、っていう時代を知っています。
■そうか、テープはいちおう日常にあったんですね。……というか、どうしよう。ぜんぜんアルバムの話きけてないですよ。
吉田匡:こういう話のほうがいいかもしれないです。
たとえば「テープが泣く」って表現したりするんですよ、エンジニアの人とか。立ち上がりのときにちょっとピッチが歪むことを指すんですけどね。そういう音をデジタルの世界で細かく構築していくということには、興味があるんですよね。(和田永)
■ははは。でも、いちおうアルバムの話に戻りますと、資料には「声」がコンセプトとして挙げられていますね。便宜的な説明ではあるかもしれないですが、もう少し音と声の話をきかせてもらえませんか?
和田:オープン・リール自体が、そもそも肉声を録るというところからはじまったものなんですよね。
吉田悠:録音の歴史の最初が、人間の声の録音ですから。僕たちも、史上最初の磁気録音と言われる、フランツ・ヨーゼフ一世の声を楽曲に使ったりしているんです。
■前作ですよね。ちょっと不思議なのが、「音」ということにこだわるなら、それこそ波形を気にしながら、画面とにらめっこして整えていくみたいな道もあるじゃないですか。そういう意味でのこだわりは、あまりないんでしょうか?
吉田悠:僕たちが空間が歪んだように感じて楽しいと思うときの音を、波形レベルで調べてみようとしたことはないですけど、たとえば“NAGRA”とかは、テープでパーツをつくって、その音を多用して構築していますね。ちょっと質問からはずれるかもしれないですが。
和田:この“Telemoon(with Babi)”という曲は、オープン・リールで出したピョーンという音をコンピュータにどんどん蓄積していって、それを音楽編集ソフトで細かく刻んで、こと細かに配置してつくりましたね。
なんていうんだろう……シズル感というか、ちょっと、いじったことのある人にしか伝えづらい感覚があるんですけど……(笑)、たとえば「テープが泣く」って表現したりするんですよ、エンジニアの人とか。立ち上がりのときにちょっとピッチが歪むことを指すんですけどね。そういう音をデジタルの世界で細かく構築していくということには、興味があるんですよね。
■それって、波形っていうようなレベルよりは、もうちょっと神秘的なものへの興味だと思うんですよね。
和田:そう……ですね。波形からつくるというよりはある音がオープン・リールによってぐにゃっと変化する瞬間に、不確定な、ゆらぎが生まれて。
吉田悠:それはある意味では波形をいじることにはなるかもしれない。
和田:やっぱり最初に耳に入ってくる感触に対して、何かもっとできないかなというのは、いつも思っていることですね。
僕たちはオープン・リールのヴィブラートのことも「ヴォーカル・コード」って呼んでいたんですね。テープが起こす音の震え。だから「人の声にフォーカスした」というのは、ほんとはちがうんです(笑)。(吉田悠)
■なるほど。その、最初に出てくる音って、みなさんの場合、マウスで削ったり計算したりじゃなくって、手でテープを押したり止めたりして出てくる、何かすごく身体的なものじゃないですか。本当に楽器を演奏しているような。
和田:そうですね。でもそのへんはほんとに行き来している感じですよ。なんか、いちどコンピュータで構築した音を、崩したいなってなったときに、オープン・リールに通して戻す。コンポジションするときにもそういうフィードバックがあります。
ただ、今回はそうやってつくったトラックにヴォーカルを乗せているので、そこはあんまりオープン・リールを通しているわけではないですね。
■なるほど。なんか、「声がコンセプト」って情報を読んじゃうと、音声というレベルとは別に、なにか人間主義的なものを感じさせるニュアンスも感じてしまって。
吉田悠:ああー。『ヴォーカル・コード』っていうタイトルは、当初はちょっと意味がちがっていて、「コード」のスペルが「cord」──つまり「声帯」っていう意味だったんですよ。のどの震え。僕たちはオープン・リールのヴィブラートのことも「ヴォーカル・コード」って呼んでいたんですね。テープが起こす音の震え。だから「人の声にフォーカスした」というのは、ほんとはちがうんです(笑)。
吉田匡:“Tape Duck”って曲はアヒルの声でやってますしね。クリウィムバアニーのように(“ふるぼっこ with クリウィムバアニー”)、歌じゃなくて叫び声でやることもあるし。
吉田悠:気持ちの上では、ひとがのどを震わせることと、テープが音を震わせることを掛けているんですよね。
■なるほど! 「裸足になって声を出す」とかね、生命とか人間を祝うというか、「初音ミクには表現できないもの」とかなんとか……そういう意味での「声」じゃないんですね。
なんだろう、こんなにコンセプトが一貫しているというか欲望が一貫しているというか、そんなバンドも珍しいと思います。
和田:いろいろ言われると、次にやりたいことが出てきちゃうな。プロモーションしなきゃいけないのに(笑)。
Next→→
“空中特急”の隠されたテーマとは?
僕たちが押す「主電源」は発展のためのスイッチか、それとも滅亡のためのそれなのか──。
OREの「近代的」未来観を解体する!
-
いや、僕らは僕らの現実認識がありますよ。でも、そういう素朴な科学少年の夢みたいなものが、オープン・リールに宿ってるんです。(吉田匡)
■これも訊きたいんですけど、OREにはレトロフューチャリスティックなヴィジョンがあるじゃないですか。昔の人が思い描いていた未来観みたいなもの──OREの世界とか音楽には、そういう「60年代かよ」的な明るい未来観を感じるんですよね。戦争は終わって、文明とか技術はさらに飛躍的に発展して、未来はどんどんよくなる、みたいな。それが不思議なんですよ。基本的に、同世代の人はもうちょっとシニカルじゃないですか? 右肩上がりの成長とかもうないでしょうし、みたいな。
和田:いや、まさにそういうテーマを隠した曲があるんですよ。
吉田悠:“空中特急”とかまさにいまおっしゃっていたような内容の曲なんです。
和田:希望と絶望を空中特急になぞらえて歌っている感じ。いや、ほんと、現実に対しては絶望してますよ。
(一同爆笑)
■そうなんだ(笑)。
吉田匡:いや、僕らは僕らの現実認識がありますよ。でも、そういう素朴な科学少年の夢みたいなものが、オープン・リールに宿ってるんです。
■……! ああ、なるほど、そういうことか! それはすごい。あれは「彼らの」夢なのか!
吉田匡:そうです。「彼らが」出している音なんです。
■それを再生しているわけだ……。また媒体になって。
吉田悠:また伝道師なんですよ。
吉田匡:オープン・リールって、『スパイ大作戦』じゃないですけど、当時の科学力の象徴じゃないですか。その立ち居振る舞いはそのまま借りているんですけど、でも僕ら自身が未来に超希望を持っていたりするわけではないんです。
吉田悠:(明るい未来観に対して)それがいいとも言ってないですしね。そういう映画は観るけど(笑)。
■たしかに、それがいいとは言っていない(笑)。
吉田匡:ただ、そういうヴィジョンをいやでも感じとってしまうほど、匂い立つものがあるんですよ、オープン・リールには。
和田:そういう音楽や世界観を楽器が引き出してくれる。
いや、ある意味いっしょなんですよ。未来に希望を抱いているということと、それの行きつく先が絶望であるというのは。(吉田悠)
科学が進歩すればより良い未来が来る、みたいなかつての明るい科学感と、確実にそうとも言えない現実と。(和田永)
■うんうん。なんか、OREはつねに躁状態というか、ハレとケでいえばケがない感じがするんですよね。穏やかな曲も気持ちのいい曲もあるけれどチルアウトしないというか。つねに、前に前に向かってめちゃくちゃ回転しているものがある。
吉田悠:つくってる側が鬱だから出てくるのが躁なのかもしれない(笑)。
和田:でもオープン・リールが持っている生命力っていうは確実にあるんですよね。
吉田悠:どうしようもない事実として60年代という時代が存在して、その時代の未来観や、その時代のテクノロジーが象徴していたものがあるわけですよね。それを歴史として僕たちは共有しているわけだけど、全面に押し出して表現しているというわけではないですね。
■なるほど。シンセ・ポップひとつとっても、ダークウェイヴだったり、ディストピックで暗いものっていうのはたくさんあるわけですよ。でもOREはその中の明るいものばっかり採ってきている感じがする、それはなんだろうって思ってたんです。
吉田悠:OREでディストピアはやりたいですよ。
和田:ディストピアなものは潜んでいますけどね。
■その明るい未来観自体がディストピックなのかなあ(笑)。
吉田悠:いや、ある意味いっしょなんですよ。未来に希望を抱いているということと、それの行きつく先が絶望であるというのは。
和田:科学が進歩すればより良い未来が来る、みたいなかつての明るい科学感と、確実にそうとも言えない現実と。
■なるほどね、結果が出たあとでみなさんはデッキを掘り出したんだから。
吉田悠:それが一体なのが現実というか、意外にそこに本質がある気もしますね。ネガティヴなものとポジティヴなもの。
和田:ふたつとも回ってるんですよ。互いに互いを生み出しながら、ぐるぐる。
■回ってるのか……。
吉田悠:“空中特急”も、曲調的には希望的で、どんどん上に向かって推進していくような曲になっているんですね。で──
和田:でも、そのままさよならなんですよ。
■はははは!
吉田悠:──このあと空中特急は墜落するしかないんです。それがわかっていても飛べるだけ飛ぶしかないってことなんですよ。もしこの曲のつづきがあるとしたら。
■そう、この曲はたしかにそういう後日談をもっている。
和田:もっとそこが伝わりやすい歌詞にすればよかったかな。
■いや、このほうがいい。象徴性があって。
和田:向かう先は闇。歌詞でいうと、「主電源」を点けることは、文明のスイッチを押す、みたいなことなんですよ。パンドラの箱を開けるというか。それに対する畏怖もあります。
■なるほど。電源を入れるっていうのは、かつてはもちろんポジティヴなことだったはずなんですよ。スイッチをオンするってことは。
吉田悠:いまや「再稼働」させるための行為ですからね。
■まさに。
和田:発展と滅亡、どちらのスイッチを押しているんだろうっていう。どっちも押しているのかも。
発展と滅亡、どちらのスイッチを押しているんだろうっていう。どっちも押しているのかも。
Open Reel Ensemble - 空中特急 short version (Official Video)
■「特急」って飛行機とかじゃなくて電車にしか使わない言葉でしょう? かのトルストイの『アンナ・カレーニナ』って、まあ「進歩」を呪う話なんですけど、アンナは当時の「進歩」の象徴たる汽車に飛び込んで死ぬんですね。だから何か、特急とか汽車っていうとすごく呪われた近代の感じがある。──あと「主電源」って、ドイツ語に聞こえる。
和田:もちろん、それで作詞しましたね。シュデンゲン、シュデンゲン(笑)。
吉田匡:めっちゃドイツ語っぽく歌ってみてって、やってて。
■編集長の野田努が……言っていいのかな、このあいだ「自転車は未来の乗り物だ」って言ってたんですよ。「テクノの最終形態だ」的に。なにげなく。
吉田悠:回転だ……。
■たしかに、合理的で効率的で、しかもエコで、かつ美しい。たしか、起源はドイツらしいんですね。クラフトワークの『ツール・ド・フランス』のイメージもありますが。これもまたテクノ観だなって。
和田:テクノロジーと人間っていうのはOREのひとつのテーマかもしれないですね。
吉田悠:ロスト・テクノロジーという感覚もありますよね。人類がかつて一度失ったものに、もう一回チャレンジしているだけかもしれないという。
■SFですね、ドキドキする。しかし自転車が未来で汽車が過去だとして、つくづく文明は車輪で回りますね。さっき「回転だ」っておっしゃったけど、オープン・リールしかり。
和田:いや、もう。
■“空中特急”っていちばんくらいに好きなので、こんなに掘れる曲だったというのはうれしいです。名曲ですね。
和田:嬉しいですね。オープン・リールを触っていると、高度経済成長期の素朴な憧れと、今の現実を行ったり来たりする感じがして、その中から生まれた曲ですね。
■オープン・リール(録音機)がモダンのひとつの象徴だとすれば、ニコ動なりがポストモダンにすごくおもしろい音楽のかたちを示しているいま、OREはわざわざモダンにフォーカスしていって、かつそれとは関係ないヘンなものを揺さぶり起こしている──
和田:モダンを再生しながら読み変えていくような。
■──っていうのは、なんなんだろうって(笑)。ライヴを観たときから消えないですね、その感じが。
経済性とか効率性とかと別のところでオープン・リールを回してあげたい。(和田永)
■さて、もうひとつ突っ込んでどうしてもおうかがいしたくて、変な意味はないので個人的な興味として聞いていただければと思うのですが──「モダン」って、まだ父権的なものに導かれる時代じゃないですか。前作の音源にも使用されているソニーの井深大さんとか、音効の大野松雄さんとかは、技術が国や未来を引っぱっていく時代の人だと思うんですね。その意味で彼らは父。で、フランツ・ヨーゼフ一世のエピソードにも顕著なように、技術と権力は結びつく。となると、けっしてみなさんをマッチョだと言うわけじゃないんですが、父権的なものへの漠然とした憧れってあるんじゃないかなと。
和田:うーん、権力は大嫌いですけど、言われれば漠然と父なるものへの憧れはあるかもしれないですね。ただ、さっきの話と同じで、それに対する揺らぎ、疑問はあるというか。近代的な当たり前っていう感覚は、ほとんど人為的につくり出されたものだから、そこに対してはつねに批評的な目線が必要だなって。経済性とか効率性とかと別のところでオープン・リールを回してあげたい。
■ええ、なるほど。みなさんジェントルというか、むしろ草食とかフェミニンとさえ言えるような、ほんと柔軟で配慮のある方々だと思うので、誤解されたくはないんですけれども。……でも、この“Tape Duck”とかも、こんなグリークラブみたいにやらなくてもいいわけじゃないですか(笑)。
和田:男の子的な「好きなもの」っていうのはあると思いますけどね(笑)。指摘されて「そうかも」っていう程度で、意識的なものではないですね。
吉田匡:父権的な、ってなると、個人レベルの興味になるかもしれないです。僕ら兄弟はとくにないかな……。
吉田悠:これはとても繊細なニュアンスの話なので、言うのを躊躇してしまいますが、ナチスって……もちろん、まったく認められるべきでない非道であることは間違いないですけれど、あのデザインであったり意匠であったりを、どこか「かっこいい」とする視点もずっと存在してきたわけじゃないですか。
■ええ、そうですね。
和田:ドイツにはそもそも、日用品なんかのレベルでも、ものすごいデザイン性があったわけじゃないですか。そういうものが、いい方向と悪い方向のどっちにも出ると思うんですが、その極端な例というか。方向がちがえば、ドイツにはバウハウスもあればクラフトワークもいるわけで。
■そうですね。効率性のデザインというか。擁護ではなったくないですが、ナチスだって、おそらく非道さのみで歴史に刻まれているわけではない。
何か新しい領域に踏み出すような技術が発見されるときに、最初にあるのは、戦争に勝ちたいというような目的意識ではなくて、それを発見しようとした人たちの初期衝動だと思うんです。(吉田悠)
和田:言葉を選びますけれど、井深大さんとかが生みだしてきた技術には、もちろん権力的なものが絡んできたりはしますけど、でも、根本的に魅力を感じるのはその初期衝動なんですよ。井深さんがレープレコーダーを日本で初めてつくった、その初期衝動にはある種の探究心が強くあって、それはオープン・リールという楽器にも通じる。
吉田悠:戦争があったからテクノロジーが進んだという言われ方もありますよね。まったく戦争を支持しませんが。でも、何か新しい領域に踏み出すような技術が発見されるときに、最初にあるのは、戦争に勝ちたいというような目的意識ではなくて、それを発見しようとした人たちの初期衝動だと思うんです。それが権力によって利用されてしまうというだけで。
和田:原爆に関わった「E=mc2」だって、人の命を奪うために追求されたわけじゃなくて、宇宙の秘密を紐解こうとしたものですからね。
■オープン・リールが再生する記憶には、そういう夢と影とが同時に宿っているわけですね。
和田:もはや壮大すぎてオープン・リールを越えすぎていますが(笑)僕らはオープン・リールを通して、楽園の側から現代を眺めてみるような。
日本だと、ものづくりにしろ、個人がいろんなものをつくれるようになっている技術とか、そういうものに希望を感じることもあるし、ある瞬間にはなんでこんなに頑張ってディストピアつくっているんだろうって絶望を感じることもあるし。(和田永)
■ええ、なるほど。どっちが楽園かという議論も複雑で、回転するものかもしれない。いま現在において、夢を見る余地って、それほどヴァリエlーションがないかなって思うんですけど、OREは夢を見るための資材をオリジナルなやり方で掘り出してきてますね。
和田:そうかもしれませんね……。でも、いやいや、さっき「絶望してる」って言いましたけど、もちろん希望を感じる瞬間もある訳で。
■都度、未来が書き換えられている(笑)。
和田:日本だと、ものづくりにしろ、個人がいろんなものをつくれるようになっている技術とか、そういうものに希望を感じることもあるし、ある瞬間にはなんでこんなに頑張ってディストピアつくっているんだろうって絶望を感じることもあるし。いい未来がくるかもしれないとも、いや、このままどん詰まりだとも、どっちも思いますね。諦めも奮起も絶望も希望も、個人のレベルでも国のレベルでもあります。
■ええ。回るっていうのがね……生命とか宇宙とかのレベルでもそうだし、輪廻的な理もそうかもしれないし、もっとちいさな、近代とか現代という枠組みの中にも回転があるんだろうし。あまりにもリールとか回転ということの持つ哲学的な深度が深いものだから──
和田:ありますよね(笑)。ほんとに。
吉田匡:何でも回転って言っちゃう。
■たとえば、ゼロって概念を表す記号がマルだっていうのも、ねえ(笑)。
吉田悠:無限とゼロがつながりますよね。
■あはは、そうそう。きっとそういうものを最初からコンセプチュアルに見出したわけじゃないでしょうけど、オープン・リールを触っておもしろいなっていう感覚の中から、その「円」とか「回転」っていうコンセプトを拾い上げていったのは興味深いです。
吉田匡:後から発見したことも多いんですよ。僕らが思っていた以上のことばっかりで、いろんなものに接点があって。でも回転というモチーフに興味を持ってもらいたいという思いは一貫してありますね。
■やっぱり……OREはオリンピックに何かしなきゃいけないですね。あれこそ近代の象徴にして棺桶っていうか(笑)。
和田:なるほどねー(笑)。僕らが──
吉田匡:代理をやる。
■だって、シンボルマークだって、円がいくつ重なってんだよっていう。
吉田悠:五大陸の連帯だって言ってるけど……ほんと、近代の光と闇ですね。
■ポストモダンにおいて、しかも東京で、なぜモダンの再現にわずらわされねばならないのか……。でも、今日のお話だと、OREは近代というものをその両側から見る目を持っていて、若くて、アイディアと衝動に溢れている。これはみなさんがなんとかしないと。5年後だから、ちょうどいろいろ脂が乗ってるころじゃないですか?
吉田悠:5年後にその目標設定しなきゃ(笑)。
和田:毒を隠し持ちつつやりたいですね。
吉田匡:解釈次第では真逆になってしまうようなことをやる。
■それをやってくれるんだったら、私はオリンピックを楽しみにしますよ。
(一同笑)
和田:課題がたくさんあるなあ。CDの宣伝してる場合じゃない(笑)。近代の光と闇。
■そんなこと大上段で言ってるやついないよ(笑)。
吉田悠:そういうことに思いを馳せるきっかけはありますけどね。アナログテレビが終わっちゃったとか。そんなときにはっと気づくんです。別の世界線の存在に……。
■ああ、なるほど。そしてそれがもっとも祝祭的に表現されるのが──
和田:それがやっぱりライヴですね。儀式的なものを通して何かを感じて、気づいてもらう。でもそこに音楽があるというか、そこで音楽を生みだしているというのは、なにか大きいことだと思うな。やっぱりすごく音楽の力を感じる瞬間ですね。