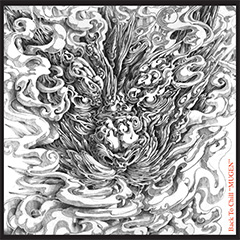今年作業中に聴いていた音楽の中から選んでみました。順不同。
 |
Theo Parrish - American Intelligence - Sound Signature |
|---|---|
 |
Todd Terje - Todd Terje Live 2014 Oya Festival - https://www.youtube.com/watch?v=RQsVftr3H-M&feature=youtu.be |
 |
MB - Woody Green - Rita Records |
 |
Sam Amidon - All Is Well - Bedroom Community |
 |
EVISBEATS - いい時間 - AMIDA STUDIO (https://www.youtube.com/watch?v=06yIzV8HToM) |
 |
DJ Spinna - Hip House Revisited - The Basement Archive Sessions Vol.2 - Tube Records |
 |
SAYURI - 暗夜の心中立て - テイチクレコード (https://www.youtube.com/watch?v=Mkjf9QNr9TE) |
 |
Amp Fidder - Afro Strut - Genuine |
 |
BLANKEY JET CITY - TEXAS - 東芝EMI (https://www.youtube.com/watch?v=5GVgWwKz9Zk) |
 |
泰葉 - フライディ・チャイナタウン - ポリドール・レコード (https://www.youtube.com/watch?v=X4JT1boWL_c) |
グラフィックデザイナーです。
今年作業中に聴いていた音楽の中から選んでみました。順不同。
3/29から4/26まで高円寺にあるヒミツキチで
グラフィック作品の展示をしています。
良かったら散歩がてらにでもよろしくお願いいたします。
Terrapin Station
東京都杉並区高円寺南2-49-10
03-3313-1768
https://www.facebook.com/Koenji.TerrapinStation
AHAU EXHIBITION "ROOM"
高円寺 TERRAPIN STATION 2F ヒミツキチ
3.29.SUN-4.26.SUN
12:00-20:00
CLOSE.WED
AHAU(アハウ)、Tomoaki Sugiyama
グラフィックアーティスト、グラフィックデザイナー
1976年横須賀生まれ、東京在住
Facebook
https://www.facebook.com/AHAUts
ahau shop
https://ahau.thebase.in/