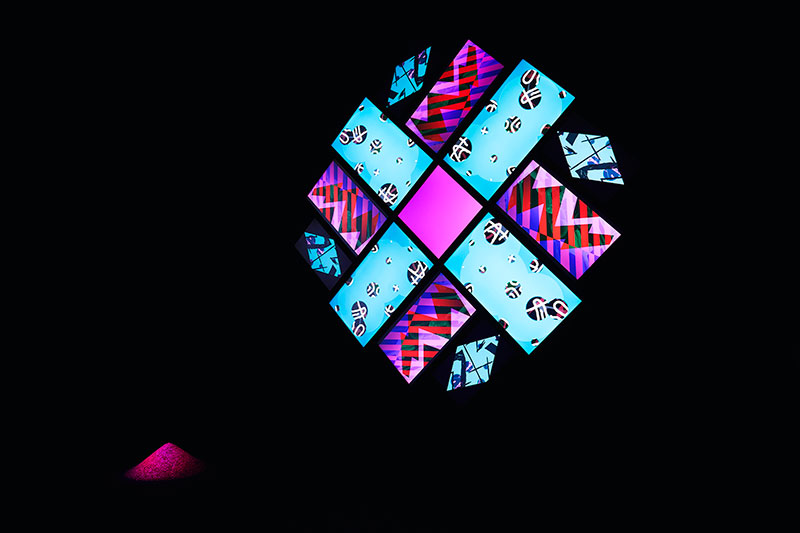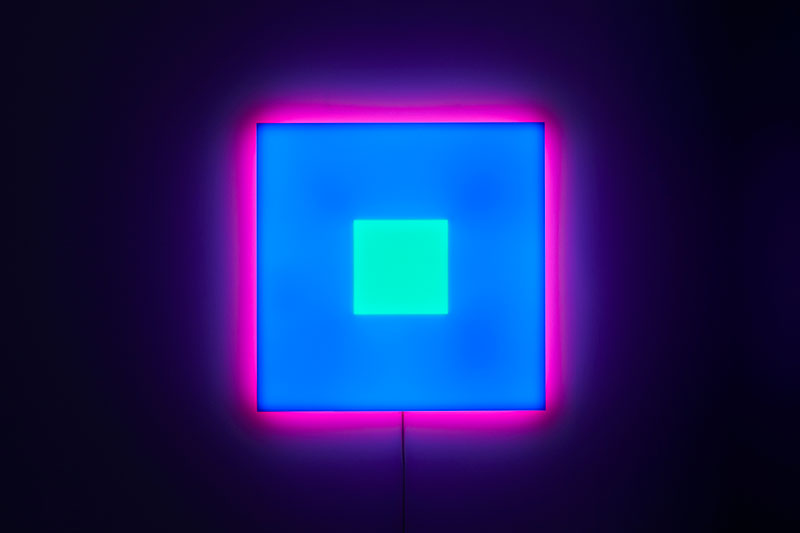山本アキヲとシークレット・ゴールドフィッシュ
文:三浦イズル
「ほな、行ってきますわ」
アキヲと最後に電話をした数日後に、アキヲの突然の訃報が届いた。シークレット・ゴールドフィッシュの旧友、近藤進太郎からのメールだった。
2021年秋頃からアキヲは治療に専念していた。その治療スケジュールに沿っての入退院だった。その間もマスタリングの仕事をしていたし、機材やブラック・フライデー・セールで購入するプラグインの情報交換なども、電話でしていた。
スタジオ然とした病室の写真も送って来た。Logic Proの入ったMacbookProや、小型MIDIキーボード、購入したてのAirPodsProも持ち込んでいた。Apple Musicで始まった空間オーディオという技術のミックスに凄く興味を持っていて、「これでベッドでも(空間オーディオの)勉強ができるわ〜」と嬉しそうだった。
「夏までに体力をゆっくり戻して、復活やわ」
明日からの入院は10日間で、これで長かった治療スケジュールもいよいよ終了だと言っていた。
「ほな、行ってきますわ。じゃ10日後にまた!」
近所にふらっと買い物にでも行く感じで電話を切った。その日は他の友人にも連絡しなくてはいけないということで、2時間という短い会話だった。
アキヲと俺はお互い本当に電話が好きで、普通に何時間も話す。あいつが電話の向こうでプシュッと缶を開けたら「今日は朝までコースだな」と俺も覚悟した。明日の仕事のことは忘れ、まるで高校生のように会話を楽しんだ。話題が尽きなかった。
電話を切った後、アキヲが送ってきた写真をしばらく眺めていた。
それは先日一気に購入したという、2本のリッケンバッカーのギターとフェンダーUSAのテレキャスターを自慢げに並べたものだった。
「リッケン2本買うなんて気狂いやろ!」
中学時代父親にギターをへし折られて以来、ギターは弾いていなかったらしい。
「最近無心でギターずっとジャカジャカ弾いてんねん。気持ちええな」
「今さらやけどビートルズってほんますごいわ」
「ほんまいい音やで。今度ギターの音録音して送るわ」
アキヲの声がいまだにこだまする。
赤と黒のリッケンバッカーたちが眩しかった。
俺はそいつを知っていた——アキヲとの出会い
シークレット・ゴールドフィッシュは1990年に大阪で結成された。英4ADの人気バンド、Lushの前座をするためだ。その辺りのエピソードに関しては以前、デボネアの「Lost & Found」発売の際に寄稿したので、そちらをご覧になっていただきたい。
1990年、Lushの前座が終わり、ベースを担当していたオリジナルメンバーのフミが抜けることになった。フミも経営に携わっていたという、当時はまだ珍しいDJバーの仕事に専念するためだ(その店ではデビュー前の竹村延和が専属DJをしていた)。
そんななか、近藤が「同級生にめっちゃ凄い奴がおるで」と言って、ベーシストを紹介してくれることになった。
「学生時代番長や」近藤は得意のハッタリで俺をビビらせた。当時勢いのあった大阪のバンド、ニューエスト・モデルのベース・オーディションにも顔を出したことがあったという(*)。「むっちゃ怖いで〜、顔が新幹線みたいで、まさにゴリラや」そして俺の部屋にアキヲを連れてきた。たぶん、宮城も一緒だったと思う。
現れたのは近藤の大袈裟な話とは違い、体と顔はたしかにゴツイが、気さくで物腰の柔らかい男だった。しかも俺はそいつを知っていた! 忘れることもできないほど、俺の脳裏に焼きついていた人物だったからだ。
(*)現ソウル・フラワー・ユニオンの奥野真哉氏の回想によれば、「ええやん、やろや!」となったそうだがその後アキヲとは連絡取れず、この話は途絶えてしまったそうだ)
1989年か1990年に、(たぶんNHKで放送していたと記憶しているが)「インディーズ・バンド特集」的な番組を観ていた。新宿ロフトで演奏する大阪から来たというパンク・バンドの映像が流れた。彼らはインタビューで語気を強めて答えた。
「わしらぁ武道館を一杯にするなんてクソみたいなこと考えてないからやぁ」
そう語る男の強面な顔と威切った言動が強く印象に残った。
しばらくして、バイト帰りに梅田の書店で無意識に「バンドでプロになる方法」らしきタイトルの本を立ち読みした。その本の序文の一説に、先日NHKで見た「武道館クソ発言」とそのバンドについて書いてあった。それは否定的な内容で、そういう考えのもとでは一生プロにはなれない、と著者は断じていた。
「あいつや……」
忘れようとしても忘れられない、あの大阪のバンドの奴の顔が浮かんだ。
そう、近藤が連れてきた番長の同級生、目の前の男こそが「あいつ」だった。山本アキヲ。物腰の柔らかさと記憶とのギャップに驚いた。
俺も最近知ったのだが、シークレットのメンバーは大阪市内の中学の同級生が半分を占めていたらしい。近藤進太郎、山本アキヲ、朝比奈学、近所の中学校の宮城タケヒト。皆、俺と中畑謙(g. 大学の同級生)とも同い年だった。彼らは「コンフォート・ミックス」というツイン・ヴォーカルのミクスチャー・バンドをやっていて、自主制作レコードもその時持参してくれた。同じ日に宮城も加入した。
「コンフォート・ミックス」のLPは在庫がかなりあったらしく、シークレットがCDデビューする前の東京でのライヴで便乗販売していた。当時の購入者は驚いただろうが、今となっては超貴重盤である。
こうしてアキヲがしばらく、シークレットのベースを担当することになった。俺にとっては運命的な出会いだった。その友情はその後30年以上も続くのだから。

1991-アキヲと宮城が゙加入した頃-京都にて
アキヲはシークレットのベースとして多くライヴに参加したが、仕事の都合で渡米したりするので、アキヲの他にも朝比奈、ラフィアンズのマコちゃん(後にコンクリート・オクトパス)など、ライヴの際は柔軟に対応していた。
2nd EP「Love is understanding」では、アキヲが2曲ベースでレコーディングに参加している。東京のレコーディング・スタジオまで飛行機で来て、弾き終えると大阪へとんぼ帰りだった。今思えば仕事との両立も大変だったろうに、本当にありがたい。アキヲが他のメンバーよりも大人びていると感じたのは、そういう姿も見ていたからかも知れない。
LOVE IS UNDERSTANDING / SECRET GOLDFISH 1992
シークレットは多くの来日アーティストのオープニング・アクト(前座)を務めていた。その中でも英シェイメン(Shamen)のオープニング・アクトは特に印象に残っている。
俺たちのライヴには「幕の内弁当」というセットリストがあった。「もっと見たいくらいがええねん」と、踊れる7曲を毎回同じアレンジ、ノンストップで30分ほど演奏していた。
せっかくシェイメンと一緒のステージだし、いつもの演奏曲も宮城のエレクトロ(サンプラー)を前面に出したアレンジに変えた。練習も久しぶりに熱が入った。アキヲはそのスタイルに合わせ、ベースラインを大きく変えて演奏した。
「ええやん、そのベース(ライン)」
「せやろ!」
そのライヴでの「Movin’」のダンスアレンジは今でもかっこいいと思う。その時のアレンジが先述のEP「Love is〜」や「Movin’」のリミックス・ヴァージョンに、宮城タケヒト主導で反映された。
MOVIN' / SECRET GOLDFISH (Front act for SHAMEN,1992)
1991年の大阪にて
シークレットの最初期こそ京都を中心にライヴをしていたが、活動場所は地元の大阪へと移っていく。心斎橋クアトロをはじめ、十三ファンダンゴ、難波ベアーズ、心斎橋サンホール、大阪モーダホールなどでライヴをした。
ちなみに91年難波ベアーズでのライヴの対バンは、京都のスネーク・ヘッドメンだった。「アタリ・ティーンエイジ・ライオット」を彷彿させるパンク・バンドだった。アキヲとTanzmuzikのオッキーことOKIHIDEとの出会いはその時だったのかもしれない。
心斎橋サンホールでは「スラッシャー・ナイト」にも参加した。出演はS.O.BとRFDとシークレット。そのイベントに向けてのリハーサルは演奏より、メンチ(睨むの大阪弁)を切られても逸らさない練習をした記憶がある。なんせ近藤と宮城が真顔でこういうからだ。「ハードコアのライヴは観客がステージに上がって、ヴォーカルの顔面1cmまで顔近づけてメンチ切るんや。イズルが少しでも目逸らしたら、しばかれるでぇ」
アキヲは笑ってたと思う。俺も負けじとドスの効いたダミ声で「Don't let me down」と歌うつもりで練習した。当日、S.O.BのTOTTSUANがシークレットのTシャツを着て登場し、「次のバンドはわしが今一番気に入ってるバンドや!」とMCで言ってくれたおかげでライヴは超盛り上がった。予期せぬ事態にメンバー一同胸を撫で下ろした。
10月にはデビュー・アルバムも発売され、そこそこヒットした。あまり実感はなかったが、心斎橋あたりを歩いていると、その辺の店から自分の下手な歌が聞こえてくる。と、同時に多くの「ライヴを潰す」とか「殺す」などの噂も耳に入った。それはかなり深刻で、セキュリティ強化をお願いしたこともあったほどだ。

1992-心斎橋クアトロ-4人でのステージ
そんな状況下でアキヲとの関係が深まる出来事が起こる。英スワーヴ・ドライヴァーの前座、クラブチッタ川崎でオールナイト・イベントがあり、その夜にはそのまま心斎橋クアトロでワンマンという日だった。諸事情で近藤と宮城はそれらに参加できなくなった。ステージを盛り上げる二人の不参加に俺は不安になった。
「ガタガタ抜かしてもしゃあない、わしも暴れるし思い切りやろうや!」
その言葉通りアキヲは堂々と4人だけのステージで、近藤のコーラス・パートも歌いながらリッケンバッカーのベースを弾いた。その姿とキレのある動きはまさにザ・ジャムのベーシスト、ブルース・フォクストン! しかもチッタでは泥酔&興奮してステージに上がろうとする外国人客を蹴り落としたり、演奏中に勢い余って転んで一回転しながらも演奏を続けたりしてめっちゃパンク! 派手なステージングに俺のテンションも上がった。
大阪行きの新幹線で初めてアキヲと向き合って話した。距離が少し縮まった気がした。
Taxman - Secret Goldfish 1992 @ CLUB CITTA'
祭りの後
心斎橋のワンマンも無事に終え、シークレットはさらに勢いづいた。が、元来気性の荒い個性的な集団だっただけに、ぶつかり合いも多々あった。若さだけのせいにはしたくないが、未熟でアホやった。俺も独善的だった。
祭りはいつかは終わるものだが、神輿の上に乗ったまま、知らない間にそれは終わっていた。バンドもメンバー・チェンジをしながら、音楽の新しいトレンドが毎月現れる、激流のようなシーンのなかで抗った。次第にメンバー同士が会う機会も減った。
正式に解散したわけでもなくフェード・アウトしていく。それは単に、皆がそれぞれ違う音楽や表現手法に興味が向かっただけだった。無責任ではあるが、ごく自然なポジティヴな流れで、決して感傷的ではない。もともと皆新しもの好きだったのだから。
アメ村で見たフードラム
暫くアキヲをはじめとするメンバーとは連絡を取り合っていなかったが、96年頃大阪に行った時、アメ村の三角公園前にある、アキヲが働いていた古着屋に立ち寄った。
Hoodrumのメジャー・デビュー直後で、レコードショップでは専用コーナーも作られていた頃だ。アキヲがどんどん有名になっていくのは俺も嬉しかったし、誇らしかった。
その店に立ち寄ったのも、単に一緒にいた仲間にアキヲの店だよ、と自慢したかっただけだが、レジのカウンター越しで怠そうに座っていたのはアキヲ本人だった。メジャー・デビューであれだけメディアに露出してるのに、普通に店番もしているなんて、まさにシークレット時代のアキヲのままだ。かっこ良すぎる。
まだ携帯もメールもない時代。アキヲは当時と変わらず接してくれた。考えてみるとアキヲとは、過去から今に至るまで一度も衝突したことがない。それだけ大人だったんだな、とふと思う。
それ以来、時々また連絡を取り合うようになった。
ミックス作業が上手くいかなくなった時などアキヲに聞くと、
「ミックスっちゅうんは一杯のコップと考えればいいんよ。その中で音をEQなどで削って、上手に配置するんやで」
今ではAIでもやってくれるマスキングという作業についてだ。
当時その情報は目から鱗だった。今でもミキシングの真髄だと思っている。
2000年の夏、河口湖にて。居候・山本アキヲ
2000年の夏、アキヲが河口湖の俺の仕事場兼自宅に、2ヶ月ほど滞在(と言えばかっこいいが居候だな)することになった。その経緯は割愛するが、アキヲはちょっといろいろと精神的に疲弊していたんだと思う。俺も同じ経験をしているので、それは思い違いではないだろう。
「富士山をみると背筋が伸びんねん。叱られてる気分やわ」

2000-西湖にて富士山をバックにするアキヲ
富士北口浅間神社では「今まで訪れた神社で一番空気が凛としてるわ」など気分転換になったと思う。慣れてくると自転車に乗って一人で河口湖を一周したり、俺の実家の父親の仕事を手伝ったりして汗も流していた。
夜になると必ず一緒に音楽を爆音で聴きながら酒を呑んだ。湖畔の古民家だったので、夜中の大音量に関しては問題ない。まだSpotifyなどの配信は当然ない時代。俺のレコードやCDライブラリを聞いた。時には湖畔で夜の湖を眺めながら。
日課のように聴いていたのは、B-52'sやThe Clash、JAPANやコステロなどのニューウェイヴ、他にもグレイトフル・デッド、ティム・バックリィ等々。音楽なら何でも。クラシックから民謡までも聴いたりした。Cafe Del Marを「品質がええコンピ」と紹介してくれたのもこの時期だった。
酒が深くなると職業柄のせいか、制作側の視点へと熱を帯びながら話題も変化していく。例えばこんな感じに。
「The Clashの『London Calling』 (LP)のミックスは研究したけど、あれは再現不可能や。誰にも真似できひん」
「(Tanzmuzikの2ndのつんのめるようなリズムについて)あれはな、脳内ダンスなんや。頭の中で踊るんやで」
「(大量に持参した89年辺りの当時一番聴かないようなDJ用レコードについて)今は陽の目を見ないこれらの音楽を切り刻み、そのDNAを生かして再構築して再生させるんや」──その手法で作られたSILVAのリミックスには本当に驚いたのを覚えている。
「リヴァーブは使わんとディレイだけで音像を処理するんよ」
アキヲには音のみならず、何事に対しても独特の哲学とインテリジェンスがあった。感心するほどの勉強家で、読書家でもあった。何冊かアキヲの忘れていった本があるが、どれも難しい評論や硬派な文学だった(吉本隆明著『言語ににとって美とはなにか』など)。
例えば不動産の仕事に就けば、一年掛かりで宅建資格を取得して驚かせる。他の仕事に就いた時も常にそうだ。そして、楽しそうにその仕事のことを話す。とことん深く掘り下げる。高杉晋作の句に置き換えると「おもしろき こともなき世を おもしろく」を体現していた。
俺たちはギターの渡部さん(渡部和聡)とアキヲと3人で、シークレット・ゴールドフィッシュとして4曲レコーディングした。2000年の夏の河口湖の記録として。

2000-河口湖のScretGoldfishスタジオにてくつろぐアキヲ
あの最高の感覚
いつだったかアキヲがまた大阪から河口湖に来た際、旧メンバー数人でスタジオに入った。
まず「All Night Rave」を合わせたのだが、その刹那、全身が痺れた。これだよ。この感覚。タツル(Dr)のドラムとアキヲの太くうねるベース。全員の息の合った演奏とグルーヴ。一瞬で時が巻き戻された。そう感じたのは俺だけではないはず。皆の表情からも伝わってきた。
バンドは結婚と似ているというが、俺は今でもそう思う。シークレット以来パーマネントのバンドは組んでない。ごくたまにベースで手伝うことはあったが、まあ正直興奮はしない。だけど、このセッションではアドレナリンが溢れた。この快感が忘れられないからだったんだな。
山本アキヲとシークレット・ゴールドフィッシュ
今回のアキヲの訃報で多く人の哀悼の言葉を読んだ。アキヲの音楽と人柄が愛されていることを知り、本当に嬉しかった。と同時にモニター越しに「厳然たる事実」を突きつけられ、不思議な感覚に陥った。3月から気持ちの整理を徐々にしているつもりだったのに。
俺の知らないアキヲの側面を知っている仲間もたくさんいるし、各々がアキヲとの大切な思い出や関係性を持っている。近藤や宮城たちは謂わば幼なじみだ。その心中は俺には計り知れない。
ただ、今こうしてシークレット・ゴールドフィッシュのメンバーと気兼ねなく電話やメールもでき、本当に幸せだと感じる。アキヲの訃報を直接口で伝え、アキヲとの馬鹿な思い出話を笑いながらできたことは良かった。ネットニュースで聞いたという形にはしたくなかった。
バンドとしての在籍期間や活動期間は短かかったが、20歳そこそこの多感な時期、一緒に経験したあの密度の濃い瞬間は永遠だ。
アキヲのマスタリングで過去のアルバムをサブスク(配信)に入れる話もしてたが、今後どうするかはまだ決めていない。
アキヲは昨年から、河口湖にマンションを買って引っ越すつもりで調べていた。冗談なのか本気だったのかは、今となってはわからない。俺も地元の仲間も、その話には大歓迎だった。これからも酒を飲みながら音楽の話をしたり、一緒に制作したりする将来を楽しみにしていた。そういえば河口湖は第二の故郷だといっていたなあ。
アキヲとの話はここでは語りきれないし、語らない。ただ、全部を胸に秘めておくだけでもいけない、ともう一人の自分が言う。アキヲという人間の一面を知ってもらうためだ。
アキヲの音楽がそれを一番多く語ってくれている。そう、俺たちは音楽家だ。
「イズルも俺もミュージシャンやないねん。抵抗あるやろ? アーティストとか」
「音楽家や。今でも俺らはこうして音楽に携わっている。感謝せなあかんくらい、これってむっちゃ幸せなことやで」
酒をごくりと飲む音と一緒にあいつの叱咤する声が聞こえた。
最後にアキヲが言った一番嬉しく、一番心強かった言葉を記して終わることにする。
「イズルがシークレットやるって言うんなら、わしゃあいつでもやるで!」
アキヲ、ありがとう。
2022年6月30日
三浦イズル(Secret Goldfish)
"All Night Rave" Secret Goldfish (12/07/15)
https://secretgoldfish.jp/
Secret Goldfish in 1991 ;
Drums:Tatsuru Miura
Bass: Akio Yamamoto
Guitar:Ken Nakahata
Vocal & Guitar:Izuru Miura
Dance & Shout: Shintaro Kondo
Synth & Sampler: Takehio Miyagi
アキヲさんとの思い出のいま思い出すままの断片
文:Okihide
■出会った頃
たぶん91年かそこらの、なんかやろうよって出会った頃にアキヲさんが作ってくれた「こんなん好きやねん曲コンパイルテープ」。当時みんなよくやった、その第一弾のテープには、そのちょっと前にくれたアキヲデモのテクノな感じではなく、フランス・ギャル(お姉さんからの影響だと、とても愛情を込めて言っていた)やセルジュ・ゲンズブールの曲が入っていた。僕がシトロエンに乗っていたのでフレンチで入り口をつくったのか、そこからのトッド・ラングレンの“ハロー・イッツ・ミー”や“アイ・シー・ザ・ライト”、その全体のコンセプトが「なんか、この乾いた質感が好きやねん」って、くれたその場のアキヲの部屋で聴かせてくれた。その彼は当時タイトに痩せながらもガタイが良く、いつものピチピチのデニム、風貌からもなんとなくアキヲさんは乾いたフィーリングを持っていて、で、その好きな音への愛情や気持ち良さをエフェクトのキメや旋律に合わせて手振り身振り、パシっとデニム叩きながら、手で指揮しながら語ったくれた。
その部屋には大きな38センチのユニットのスピーカーがあって、周りを気にせずでかい音で鳴らしてたのは僕と同じ環境で、その音の浴び方もよく似ていたが、昭和な土壁の鳴りは乾きまくってて、そんなリスニングのセッティングもアキヲさんの一部だった。
そのテープの最後に入っていたYMOは、彼が少年期に過ごしたLA時代に日本の音として聴いたときの衝撃について話してくれた。初期のTanzmuzikに、僕がよく知らなかった中期のYMOへのオマージュ的な音色がときどき出てくるのも、こうした出来事があったから。
そんなことがあって、アキヲさんには、その体格を真似できないのと同じように、真似できない音楽的感性の何かがあって、そこにはお互いに共鳴するものがあると気づいて、リスペクトする関係になった、そんな初めの頃のエピソードを思い出す。
〈Rising high〉 のファーストが出て、やっとお互いいちばん安いそれぞれ違うメイカーのコンソール買って、少しは音の分離とステレオデザインがマシになったけど、それまではほんとにチープなミキサーと機材でやっていた。そのチープ機材時代の印象的な曲として、“A Land of Tairin”という曲がある。アキヲさんがシーケンスやコード、ベースなど全ての骨格の作曲を作って、こんなん……って聴かせてくれたものに僕がエフェクトやアレンジを乗せた曲。このノイズ・コードをゲート刻みクレシェンドでステレオ別で展開させたいねん!って、アキヲさんに指と目で合図しながら、2人並んで1uのチープなゲートエフェクタのつまみをいじって、当時のシーケンス走らせっぱなしで一発録りしたのを思い出します。
あの曲のそんなSEや後半〜ラストに入れたピアノは僕がTanzmuzikでできたことのもっとも印象的なことのひとつで、アキヲさんだからこそさせてくれたキャッチボールの感謝の賜のひとつです。
■最後の頃。
こんなして思い出すとキリがないので、最後の頃。アキヲさんが亡くなる前の数ヶ月ほどは不思議とよく会いました。僕が古い機材をとにかく売って身軽になってからやりたいなぁ、って機材を売りにいくって言うと、着いてきてくれてね、帰りに大阪らしいもの食べよって 天満の寿司屋に連れてってくれて、そしたら「久々こんなに食べれたわ!」って8カンくらい食べたてかな、ありがたいわって。その前のバカナルのサラダも。
帰りに2人で商店街歩いてたら、民放の何とかケンミンショーのインタヴュー頼まれて、断ったけど「危ないわ、こんなタンズて」って笑ってて。
たぶん最後に会ったときなのかな、気に入って買ったけどサイズ合わへんし、もしよかったら着てくれへん?ってお気に入りのイギリスのブランドの僕の好きなチェックのネルシャツを色違いで2枚。おまけに僕の両親に十三のきんつばも。
で、最後のメールは、僕におすすめのコンバータのリンクだったと思います。
彼はもちろん平常心、良くなるはずでしたから、マスタリングの仕事からそろそろ自作をと、ギターやベースも買ったばかりで意気込んでたし、なかなか音に触れない僕にも常に機材や音の紹介をしてくれていました。
そんなことともに、僕のなかのアキヲ臭さっていうのは、クセのある人でパンクで短気であると同時に、20代の頃から僕と違ったのは、ことあるごとに、〇〇があってありがたい、〇〇さんには感謝やねん、って僕によく言っていたことで、アキヲさんは僕の感謝の育ての親でもあると今さら思うのです。
彼が面白がって興味を持った作曲のきっかけになったモチーフには、彼なりの独自な愛情が注がれてます。ターヘル名義のハクション大魔王やタンツムジークのパトラッシュ(たまたま思い出せるのがアニメ寄り)……、色々あるけど、アキヲさんの曲を聴いてる人のなかで産まれるおもしろさや気分を覗いてみたい気分にもなってきました(笑)。音楽は不思議です。アキヲさんと、アキヲさんの音楽に感謝。
■トラック5選

Dolice/Tanzmuzik
アルバム『Sinsekai』のあと、追って〈Rising high〉から出た5曲入りEPのなかのB1の曲。アキヲさんのセンチメンタルサイドの隠れ傑作と思ってます。〝最終楽章” のたまらん曲!です。実はデモはもっとすごくて、なにこれ!って絶賛するも再現なく、「あれ、プロフェットのベンダーがズレてたわ……」

Countach/Akio Milan Paak
着信音にしたい、この1小節。

Mothership/SILVA..Akio Milan Paak Remix
Silvaのリミックス、強いキックの隙間にノイズの呼吸するエロティックなアキヲ・ファンクの特異点。これもデモテイクは下のねちっこいコードから始まって上がってそのまま終わってしまうという、もっと色気のある展開だったのに……

Classic 2/Hoodrum
Fumiyaのフィルターを通してアキヲさんが純化されたカタチの傑作と思う。PVによく表現されたベースラインもアキヲさんらしくたまらないし、他に絡む抑えの乾いた707(?)のスネアは707のなかでいちばんカッコいいスネア。あの当時の2人の僕のなかの印象を象徴する。
ほかにも、“HowJazz It”のサックスとオルガンの〝お話”合いのような裏打ち絡みも好きだし、“Classic 1”は青春期の鼻歌アキヲ節全開な面あって、シークレットのイズルやトロンのシンタロー……アキヲの好きな旧友の顔が不思議と浮かんでくる。
あと1曲挙げようと思ったけれど、いっぱい出てくるのでここまでにします。
サブスクにもあまり出てこないマニアックな曲も多いけど、是非機会があれば聴いてみてください! Radio okihide が出来ればかけたい曲やテイクが山ほどあります。
アキヲさん、ありがとうございます。
文:Okihide


 GEORGE KANO
GEORGE KANO


 在りし日のタンツムジークのふたり。左にアキヲ。右にオキヒデ。アトム・ハートが好きだったから〈ライジング・ハイ〉に決めたという、その頃のアーティスト写真。
在りし日のタンツムジークのふたり。左にアキヲ。右にオキヒデ。アトム・ハートが好きだったから〈ライジング・ハイ〉に決めたという、その頃のアーティスト写真。 フェリーに乗って大阪から福岡に向かうふたり。「オッキー、今度せっかく九州行くから、フェリーのらへん? 楽しいやん」
フェリーに乗って大阪から福岡に向かうふたり。「オッキー、今度せっかく九州行くから、フェリーのらへん? 楽しいやん」 2019年ぐらいのふたり。
2019年ぐらいのふたり。