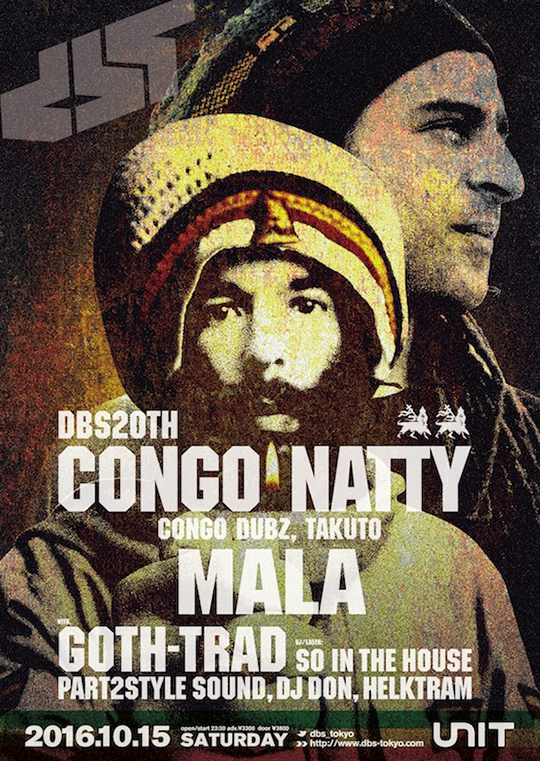パンソニックの「新作」がリリースされた。チェルノブイリ事故以降に初めて建設されたフィンランドの原子力発電所を巡るドキュメンタリー映画『リターン・オブ・ジ・アトム(Atomin Paluu)』のサウンドトラックである。監督はパンソニックのふたりとも交流のあるミカ・ターニラとユッシ・エロール。
その内容からして現代文明社会への警告ともいえるドキュメンタリー映画だろうが、ここ日本でも(エンターテインメント映画であっても)『シン・ゴジラ』や『君の名は。』など、「3.11以降の表現」を模索した作品が相次いで公開されているので、ぜひとも公開を期待したいところである。
パンソニックのオリジナル・アルバムとしても、2010年のラスト・アルバム『グラヴィトニ』から、じつに6年ぶりのリリースとなる(お馴染み〈ブラスト・ファースト〉から)。もっとも制作自体は2005年からスタートしていたらしく、工事中の原子力発電所でミカ・ヴァイニオとイルポ・ヴァイサネンがフィールド・レコーディングした音素材をベースにしつつ、昨年2015年にミカ・ヴァイニオが単独で最終編集作業をおこなったという。
このタイムラグは諸般の事情で映画の制作と公開が遅れていたことも原因だったらしい。その結果として、ラスト・アルバム「以降」の新作であり、同時に、ラスト・アルバム「以前」から制作が始められていた未発表アルバムという、いささか複雑な成立過程の作品となったのだろう(ちなみに本サウンドトラックは2016年「フィンランド・アカデミー賞」の音楽部門受賞作品である。このようなエクスペリメンタルな作風の音楽が、国民的な映画賞において受賞をしたというのは素晴らしいことに思える)。
だが、私としては、本作を彼らの「2016年新作」と称しても、まったく差し支えないと思っている。音響の質感が『グラヴィトニ』以前の脳内に直接アジャストするようなバキバキとしたサウンドから、「霞んだ音色のダークな質感」へと変化を遂げていたからだ。これは1曲め“パート1”のイントロの音響的質感からして明白である。
むろん、その「変化」は、映画のテーマ性を反映してのことかもしれないし、工事中の原子力発電所で録音した音素材の質感ゆえの変化かもしれない。また、ミカのソロ作品『キロ』(2013年)のダークなサウンドに近い印象でもあり、ミカ・ヴァイニオ単独作業の影響かもしれない。だが、2曲め“パート2”や3曲め“パート3”など、あのヘビー&メタリックなビートも炸裂するのだから、まぎれもなく「パンソニックの音」なのだ。
となれば、5曲め“パート5”以降のアルバム中盤で展開される霞んだ質感のドローンと不穏な環境音の交錯などは、2010年代以降のインダストリアル/テクノなどの「先端音楽」へのパンソニックからの応答といえなくもない。同時に4曲め“パート4”の冒頭など、どこか武満徹の「秋庭歌一具」を思わせるタイムレスな響きの持続も生成されてもいた(たしかミカは武満ファンでもあったはず)。
聴覚にアディクションする強烈なノイズから空気を震わすような淡く不穏な音響へ。そう、本作においてパンソニックは音響と空間のあいだに、これまでにない「空気」を生成している。そして、その空気は、工事中の原子力発電所から採取された音素材がベースになっている。となれば、本作特有の「不穏さ」は、やはり原子力発電という制御不能な「力」への畏怖なのではないか?
「力への畏怖としての電子音楽」。このダークなサウンドは、「われわれ」への警告なのかもしれない。3曲め“パート3”冒頭に鳴り響く、あの暗い雷鳴のように……。さまざまな領域から「資本主義の終わり」を感じつつある現在だからこそ、深く聴くべき問題作といえよう。