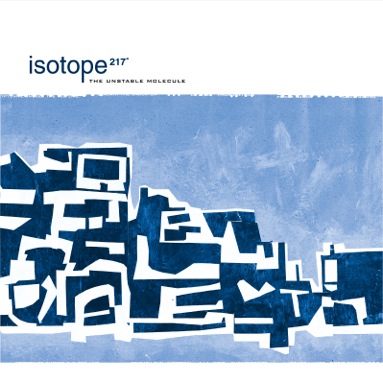リー・ギャンブルの次はクラインときましたか。〈Hyperdub〉、やりますね。先日ローレル・ヘイローのアルバムへの参加が話題となったブラック・エレクトロニカの俊才=クラインが、〈Hyperdub〉とサインを交わしました。いや、これはビッグ・ニュースですよ。同時に、8曲入りEP「Tommy」のリリースも発表されています。リリースは9月29日。じつに楽しみです。

Artist: Klein
Title: Tommy
Label: Hyperdub
Release date: 29 September 2017
https://klein1997.bandcamp.com/album/tommy-hdb112
Tracklist:
01. Prologue feat. atl, Jacob Samuel, thisisDA, Pure Water & Eric Sings
02. Act One feat. Embaci & Jacob Samuel
03. Cry Theme
04. Tommy
05. Runs Reprise
06. Everlong
07. B2k
08. Farewell Sorry

アーティスト:Klein / クライン
タイトル:Only / オンリー
発売日:2017/07/19
品番:PCD-24644
定価:¥2,400+税
解説:大石始
※ボーナス・トラック2曲収録 ※世界初CD化