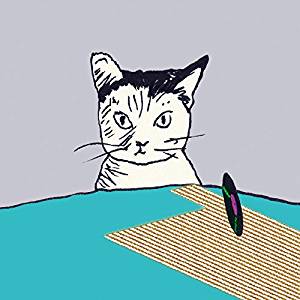 Various Artists 合成音声ONGAKUの世界 Pヴァイン |
ボーカロイドやその他の音声合成ソフトを用いて作られた音楽はいまその幅を大きく広げ、アンダーグラウンド・シーンも成熟へと向かっている(そのあたりの流れは『別冊ele-king 初音ミク10周年』や『ボーカロイド音楽の世界 2017』を参照のこと)。そんな折、『合成音声ONGAKUの世界』なるタイトルのコンピレイションがリリースされた。帯には、まるでそれが正題であるかのように、「ボカロへの偏見が消えるCD」と記されている。監修を務めたのはスッパマイクロパンチョップ。1998年に竹村延和の〈Childisc〉からデビューを果たした彼は、最近になってボーカロイド音楽の持つ魅力に気がついたそうで、それまでの自分のように偏見を持った人たちに少しでも興味を持ってもらおうと、精力的に活動を続けている。今回のコンピもその活動の成果のひとつと言っていいだろう。じっさい、ここに収められているのはシンプルに良質なポップ・ミュージックばかりで、もしあなたがなんとなくのイメージで避けているのであれば、それはほんとうにもったいないことだ。そんなわけで、監修者のスッパマイクロパンチョップと、同コンピにも参加している古参のクリエイター、キャプテンミライのふたりに、このコンピの魅力について語り合ってもらった。あなたにとってこれがボーカロイド音楽に触れる良い機会とならんことを。
※ちなみに、スッパマイクロパンチョップのブログでは、今回の収録曲から連想される非ボーカロイド音楽のさまざまな曲が紹介されており、ロバート・ワイアットやエルメート・パスコアール、ダーティ・プロジェクターズやディアンジェロなど、興味深い名前が並んでいる。そちらも合わせてチェック。
たまたま耳に入った曲が自分の好きな感触じゃなかったら、そのイメージしか残らなくて、それ以外が想像できないという状況だと思うんですよね。 (スッパマイクロパンチョップ)
対バンした相手と表面上は仲良く話していても、心の底では「なんだあいつ」みたいに思っていたり(笑)。〔……〕ボーカロイドを始めてみたらみんなすごく開けていたんで、それもすごく驚きましたね。 (キャプテンミライ)
■スッパさんがボカロの音楽を聴くようになったのはわりと最近のことなんですよね?
スッパマイクロパンチョップ(以下、S):そうですね。ボカロの音楽を聴き始めたのは去年の8月末からなんです。初音ミク10周年のタイミングですね。それまではあまり興味がなかった。でも、Twitterでたまたま流れてきたyeahyoutooさんとPuhyunecoさんのふたりの曲を聴いてとても感動したんですよ。それ以来ニコニコ動画でアーカイヴを掘りまくっていますね。そこから自分でも曲を作り始めるようになって、10月にはもうボカロに関するトークイベントをヒッキーPと始めていましたね。
キャプテンミライ(以下、C):最近スッパさんという方がボーカロイドに熱中しているという噂は僕も聞いていて、ちょっと前からTwitterとかでスッパさんの発言を拝見しているんですが、ようはその2曲がボーカロイド音楽を聴き始めるきっかけになったわけですよね。
S:そうですね。
C:僕も似たような感じで、ボーカロイドを始めるきっかけになった曲があるんですけど、やっぱりそれって、ボカロ云々を抜きにして音楽として良かったっていうことで、ようはすごくかっこいい曲に出会ったということですよね。
S:ですね。キャプミラさんの出会いの曲はなんだったんですか?
C:すんzりヴぇrP(sunzriver)という人の曲ですね。僕はもともとバンド畑の人間で、「ライヴハウスだ、バンドだ、ギターだ」みたいな世界でやっていたんですが、じつはその頃からすんzりヴぇrとは知り合いだったんですよ。彼は最近何をやっているんだろうと思って調べてみたらいつの間にかボーカロイドを始めていて。もちろん僕もボーカロイドの存在は知っていたんですが、なんとなくの見た目のイメージくらいしかなかったんですね。でも彼の楽曲を聴いてみたら、彼がそれまでやっていたものとぜんぜん変わらない、むしろボーカロイドによって魅力が増しているかもしれないと感じたんです。これはおもしろいなと思って、自分でもやってみることにしたという流れですね。
S:それは2008年ですか?
C:2008年ですね。
■けっこう初期ですよね。
C:そうです。当時はまだ偏見もいまより大きかったし、バンド畑の人間だったので、ライヴハウスとかで周りに「ボーカロイドというのを始めてさ」って言うと、反応が冷たくて。「お前、何やってるんだよ」みたいな反応をされることが多かったですね。でもそれからどんどん初音ミクがメジャーになっていったので、やっている側としては広まりきった感はあったんです。でも今回のスッパさんの活動を見ていると、まだまだ広がりきっていなかった部分があったんだなというのを感じましたね。
S:その「広がった」というのも、もしかしたら偏見が広がったということかもしれないですよ(笑)。
C:まあ、同時なんでしょうけどね。ただ若い世代にはふつうに広まっている感はありますね。だからいまスッパさんが届けようとしているのは、若い子よりも少し上というか、ミドルで音楽好きの人たちという感じですよね。それこそバンド畑の人とか、ロックやエレクトロニカを聴いているようないわゆる音楽好きの層というか。
S:そこにも届けたいってことですよね。自分もライヴハウスとかクラブとかはよく出演しているんですけど、そういうところで出会う人たちの偏見ってすごく根強くって。キャプミラさんが「お前、何やってるんだよ」と言われたときと、いまもまったく同じ状況なんですよ。
C:そうなんですね。難しいですねえ。たとえば「初音ミク」という名前自体はそれこそ誰でも知っているものになっていますけど、じっさいにそれを聴いているかは別問題ってことですよね?
S:たまたま耳に入った曲が自分の好きな感触じゃなかったら、そのイメージしか残らなくて、それ以外が想像できないという状況だと思うんですよね。だから、このコンピを聴いて考え直してほしいってことですね(笑)。
C:でもどうなんでしょうね。偏見ってじっさいそんなに強いのかな……いや、やっぱり強いのかなあ。
S:強いと思いますよ。Twitterで「これ最高! ヤバい!」ってYouTubeのリンクを貼るのと、ニコニコ動画のリンクを貼るのとでは違いがあるというか。ニコニコ動画なんか誰も覗いてくれないんですよ。「そっちの世界は行きたくない」みたいな偏見はあると思います。
■音楽ファンって、ほかの何かのファンと比べると、なかなかそういう壁を崩さない感じはありますよね。オープン・マインドに見えて、じつはすごく閉じているというか。
S:ですよね。だから今回はそういうボカロのネガティヴなイメージをすべて取っ払って、音楽だけに集中して見せたいんですよね。音楽活動をしている知り合いには若い子が多いんですが、若い子でも外へ出て音楽をやる人と、家のなかだけで音楽をやる人とではちょっと違いがあって。やっぱり外でやるおもしろさを知っている人は偏見を持ちがちですね。キャプミラさんの場合はボカロとの出会いが早かったから良かったというのもあると思うんです。すんzりヴぇrさんやディキシー(Dixie Flatline)さんとは、ちょっと仲間意識みたいなものもあるんじゃないですか?
C:そうですね。当時はボーカロイドをやっている人たちの横の繋がりがすごくあったんですよ。初投稿日が近い人たちなんかで良く会ったりしていて。バンドをやっていると意外にギスギスしているところがありますよね。たとえば対バンした相手と表面上は仲良く話していても、心の底では「なんだあいつ」みたいに思っていたり(笑)。ライヴハウスではそういう空気をバンバン感じることがあったんですが(笑)、ボーカロイドを始めてみたらみんなすごく開けていたんで、それもすごく驚きましたね。だから10年前に出会った人たちとはいまだに会ったりするような仲になっていますし、それが世代ごとにいろいろとあるんじゃないですかね。いまの若い人は若い人たちでコミュニティがあるんじゃないかという気はします。
僕が言う「偏見」って、世代的な断絶でもあるんですよね。高年齢の音楽マニアとのあいだにすごく大きな壁があるというか。 (スッパマイクロパンチョップ)
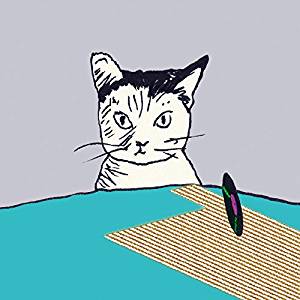 Various Artists 合成音声ONGAKUの世界 Pヴァイン |
■今回のコンピはどういった基準で選曲していったのでしょう?
S:これを聴けば偏見が吹き飛ぶだろう、という選曲ですね。よくあるボカロのイメージにそぐわない曲というか。「え、これボカロなの!?」って、あっさりボカロを好きになっちゃうような選曲のつもりです。とはいえボカロのおもしろい曲ってすごくバラエティに富んでいるので、それを「ベスト・オブ・ボカロ・ミュージック」みたいにひとつにまとめるのは難しい。そこへ、「音楽好きの人がさらっと聴ける」「BGMとして心地良く聴ける」のがいいというお話をいただいたので(笑)、それもテーマにしました。もちろん自分の趣味も入っているんですけど、それだけじゃなくておしゃれに聴けることを意識したというか。ボーカロイドってべつに「おしゃれ」のイメージはありませんよね。
C:そうですかね。
S:偏見を持っている人たちは、アニメとか萌えとか、そういういわゆるオタクな世界に悪いイメージを抱いていて、それは「おしゃれ」とは正反対だと思うんです。もちろん音楽ファンも「おしゃれ」だけを基準に聴いているわけではないですけど、やっぱりイメージってあると思うんですよね。「このサウンドがいまいちばんかっこいい」っていう感覚って、「(そのサウンドが)おしゃれ」ってことでもあると思うので、そのラインは守っているというか。「ボカロっておしゃれかもしれない」とか「意外と気持ちいいんだな」と思ってもらえるよう選曲していますね。たとえばでんの子Pさんの曲でも、選曲を間違えたら「え……」って思われちゃうかもしれないので(笑)。だから、突出した才能を持っているけど、その人のなかでも耳触りが良いもの、たとえばエルメート・パスコアールなんかと同列に聴けるもの、という基準ですね。キャプミラさんも名曲揃いですから、どの曲でもよかったんですが、せっかくなので僕がいちばん感動した“イリュージョン”を選びました。僕、ボカロを聴いて泣いたのはその曲だけですからね(笑)。
C:おお(笑)。ありがとうございます。
■今回の収録曲のなかではいちばん古い曲ですよね。
C:そっか、ディキシーさん(Dixie Flatline)より古いのか。
S:ディキシーさんのは最近の曲なんです。2015年。古いのはTreowさんとキャプミラさんだけです。おふたりはクラシック代表なんですよ。
■ということは、この曲で使われている鏡音リンのヴァージョンも初代ということですよね?
C:そうです。初代のリンってソフトウェアのエンジンがVOCALOID2という古いヴァージョンなんですけど、いまの環境で動かすにはちょっとめんどくさいんですよね。Windows10とかだとけっこう微妙な感じになっちゃっていて。データをコンヴァートしたりしなきゃいけなくて、かなりたいへんなんです。
■この曲に感動して同じような音を鳴らしたいと思った人がいても、それはもう難しいという。
C:そうなんですよね。ソフトはどんどん新しくなっていって、もちろん内容は素晴らしくなっていっているんですけど、やっぱり声が違うので「初代のほうが良い」みたいなことはありえますよね。
■楽器だといわゆるヴィンテージの機材を追い求める人たちもいますが、これからVOCALOIDもそういう感じになっていくのかもしれませんね。
S:そういう時代は来そうですね。
C:そしたらリヴァイヴァルするかもしれないですよね。いまのエンジンで当時の声がそのまま出るよ、みたいな感じのライブラリを出してもらえるといいんですけどね。
■今回のコンピには入っていませんが、多くの人がボカロと聞いて思い浮かべるだろう、テンポの速いロック系の曲についてはどうお考えですか?
S:数年前に流行った高速ロックの流れもまだそんなに廃れていないというか、「ボカロと言えばとにかく速い」みたいなイメージが一般的にもあると思うし、じっさいそういうものがたくさん聴かれているのはすごく感じるんですよね。わりと再生数を稼げる人たちのなかでも、ボカロのそういう側面を追求する層と、どうやったら「おしゃれ」に作れるかで競っている層と、ロックか「おしゃれ」かみたいなふたつの線があるように思いますね。
C:いまのバンド・シーンの若い子たちのなかでも、あの頃の高速ロックの流れを汲んだバンドは多いですよね。BPMが速くて、四つ打ちで、速いギター・リフみたいな。中学生のときにもうボーカロイドがふつうにあってそれを聴いて育ったから、大きくなってバンドをやろうってなったときにおのずとそういう楽曲が出てくる、そういう世代がもうけっこういるのかな。やっぱり高速ロックは影響力ありますよね。
S:ありますね。だから僕が言う「偏見」って、世代的な断絶でもあるんですよね。高年齢の音楽マニアとのあいだにすごく大きな壁があるというか。若い子が音楽を始めようと思ったときに、いまだとやっぱりコンピュータで音楽を作るという選択肢があって、それで作ったものをアウトプットする場所としてボーカロイド・シーンがすごく身近なんだろうなと。曲を作ってアップロードするだけならべつにSoundCloudでもいいんですけど、若い子からしてみると華やかな感じというか、SoundCloudにアップするよりもキャラクターとビデオのあるボーカロイド・シーンのほうが注目されるんじゃないか、というような期待があるんでしょうね。そもそも音楽と最初に出会った場所がニコニコ動画だったという人も多いでしょうし。それでいろんなタイプの音楽が集まってきているような気がします。
■キャプミラさんが今回の収録曲のなかでいちばん印象に残った曲はどれですか?
C:羽生まゐごさんの“阿吽のビーツ”かな。民族っぽいパーカッションのリフで始まる曲。でも、たしかに全体的におしゃれだなとは思いましたね。
S:1曲目とその羽生さんの“阿吽のビーツ”はガチでおしゃれだと思います。それ以外はオーソドックスな感じもあって、「エヴァーグリーン」という感じですね。僕はどんな音楽を聴くときも普遍的かそうでないかみたいなところでジャッジしていて、もちろんそうでなくてもいいんですけど、コンピを組む場合は50年後とかに聴いても古いと思わないような強度のある曲を選んでいるつもりなんですよね。それでいてサラッと聴ける曲。あまりにも濃いと引っかかっちゃうので。作業しながら聴いていて「えっ!」って(笑)。
■僕は松傘さんやでんの子Pさんが好きなので、その両方が入っていたのは嬉しかったですね。でも、彼らの曲のなかではわりと聴きやすいというか、比較的癖のない曲が選ばれていますよね。
S:松傘さんの個性ってずば抜けているところがあるんですが、松傘さんが単独で作っている曲をこのコンピに入れるのはちょっとエグいかなあと(笑)。でんの子さんもそうなんですよ。でも彼らのおもしろさはなんとか伝えたいので、誰が聴いても「良いな」って思ってもらえそうな曲を選びましたね。
C:そういう意味では、最近のボーカロイドをそれほどチェックできていない僕みたいな人向けでもあるというか、ここからいろいろ漁っていくという聴き方もできそうですね。
S:そうなんです。たとえばある曲に惹かれて、もっと掘ろうと思ってその作り手の他の曲を聴いてみると、そっちはそれほどでもなかったり、というようなことがボカロではわりと多いんですよ。だから今回のコンピも、その曲に出会った人がもっと掘っていったときにがっかりしないように、そもそも作っている曲が全体的におもしろい人たちのなかから選りすぐっていますね。あと、ぜひ入れたいと思ったけど、そもそも連絡先がわからないというパターンもありました。連絡が取れないとどうしようもないので、現実的にコンタクトできてOKしてくれそうで、それでいて誰が聴いても良いと思える曲がある人、という基準で選んでいます。
C:そうなるとけっこう難しそうですね。連絡の取れない人、多そうだから(笑)。
S:難しかったですね(笑)。でも良い内容にできたとは思っています。
試しに作ってみると世界が変わると思いますよ。声を合成するというのは、やっぱり音楽をやっている人ならおもしろいと思える部分があるはずですので。 (キャプテンミライ)
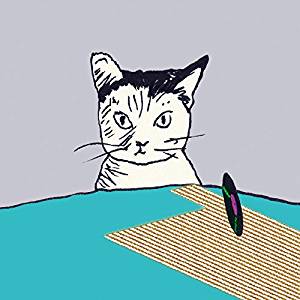 Various Artists 合成音声ONGAKUの世界 Pヴァイン |
■今回のコンピに収録されているような、シンプルにグッド・ミュージックだったりちょっと尖った曲を作っている方たちって、やっぱり再生数は低かったりするんでしょうか?
C:たとえば鈴鳴家さんも音作りがものすごくて狂気じみていますけど、再生数の面ではそこまで評価されていませんよね。だからボカロ界にはもったいない人がいっぱいいますよ。
S:なぜなんでしょうね。プロモーションのしかたなのかなあ。
C:でもディキシーさんやTreowさんはすごく再生数の高い曲を持っていて、数字が付いてきているというか。
S:そうですね。ちなみに羽生まゐごさんはむちゃくちゃヒットしていますね。あと、1曲目の春野さんもわりとおしゃれ系でヒットしています。まだ20歳らしいですよ。
C:おお。いや、まさにそこなんですよね。最近の音楽自体ちょっとヤバいというか、いまは若くても本当にすごいものを作ってくる。むかしはそんなことはなくて、若い子は若い音楽しか作らなかった。町田町蔵が出てきたときに、「すごい10代」みたいに言われていたんですけど、ボーカロイドをやっていると、そのすごい10代がいっぱいいる感じがするんです。環境が良くなっているのかな。コンピュータで音源も安く買えて、いきなりすごい音が出せるみたいなことの影響もあるんですかね。
S:あると思いますね。
C:2007~09年にボーカロイドが盛り上がっていった時期って、いろんなインフラが整っていった時期でもあると思うんですよ。音楽制作をしたい人がコンピュータでそれをできるようになって、プラグインも安くなって手が届くようになった。動画もそうですよね。動画編集ソフトにも手が届きやすくなって、個人で作れるようになった。絵もデジタルで描く方法が確立されて、pixivのようなものが出てきて盛り上がっていった。そういった人たちが集まって何かを作ろうというところにちょうど初音ミクが登場して、ニコニコ動画という場もあって、「僕が楽曲」「僕が動画」「僕が絵」みたいな感じでどんどん盛り上がっていった。それがおもしろかったんですよね。同じような時期に、アメリカやヨーロッパではインディ・ゲームのシーンが盛り上がっているんですよ。それもたぶん同じように誰でもプログラミングできたりグラフィックを作れたりする環境が生まれて、じゃあ何を作るかってなったときに、日本みたいにニコニコ動画があるわけじゃないから、みんなでゲームを作ろうというような感じで盛り上がっていったんじゃないかと思うんです。それがいまはまた分裂して、絵を描く人は絵だけで行こう、みたいになっているような気がしますね。当時ボーカロイドをやっていた人のなかでも、いまはプロの作家にスライドして曲を作っているような人も多くなっているので、音楽は音楽でやっていこうという感じなんですよね。あのときにみんなでガーっとやっていたところからどんどんひとり立ちしていって。そう考えると10年の歴史の流れを感じるというか、じーんときますね(笑)。いや、でもやっぱりみんな若いんですねえ。
S:詳細な年齢まではわからないけど、新着の初投稿の曲を聴いていても、いきなり成熟したポップスみたいなものがわりと多いんですよ。そこは謎なんですよね。最初からスケッチ的なものじゃなくて、しっかりポップという。
C:ポップスってけっこう理論とかがわかっていないと作れないものなのに、それをさらっと作っちゃいますよね。それは、たんにツールが良くなっただけじゃできない。耳も良いのかな。
■音楽活動はべつにやっていて、匿名で投稿しているケースもあるんでしょうね。
S:それはいっぱいあると思いますよ。
C:言いかたの問題もあるでしょうね。ずっと音楽はやっていたけどボーカロイドは初投稿です、みたいなケースもあるのかもしれないですしね。
S:いまはまだ偏見を抱いているクラブ・ミュージックの作り手とかが、いつか「ボカロっておもしろいんだな」と気づいて、自分でもボカロで歌ものを作ってみてハマる、そういう可能性を持った作り手ってじつは山ほどいるんじゃないかと思っていて。
C:僕がそうだったんですけど、イメージで偏見を持っていても、じっさいにボーカロイドを使ってみると、打ち込んで、機械が歌ったときにちょっと感動があったんですよね。「声が聴こえてきた!」みたいな。それで急にキャラクターにも愛着が湧いてくるというか、「このソフトはこんな声をしているのか」という感じで世界が広がったことがあったんです。だから作り手の人に、もちろんまずは聴いてほしいですけど、じっさいに作ってみてほしいんですよね。べつにニコニコ動画やYouTubeにアップロードしなくてもいいんで、試しに作ってみると世界が変わると思いますよ。声を合成するというのは、やっぱり音楽をやっている人ならおもしろいと思える部分があるはずですので。
S:そういうものを作らなさそうな人にこそ作ってみてほしいですよね。
C:あとは音質の話ですけど、ニコニコ動画にアップロードしている人たちには、ミックスやマスタリングの癖みたいなものがありますよね。とにかく音がデカくてバチバチにしているし、低音も切り気味だし。もしかしたらそれをクラブ・ミュージックの人が聴くと、物足りない感じに聴こえちゃうのかもしれない。パッと聴きでもう質感が違うと思っちゃうのかなという気もします。
S:自分は家ではデスクトップのパソコンに大きなスピーカーを繋げて聴いているんですけど、どんなにクオリティの低い曲でも小さな音で再生しているぶんにはなんにも気にならないんですよ。でも、ヘッドフォンで聴くと不快になるってことは多いですね。なので今回のマスタリングでは、全体的に高域をちょっと削ってマイルドで優しい聴き心地になるようリクエストしています。ボカロの声って高音が痛かったり刺さることが多いですし、そもそもそれが嫌いだと言われちゃったら薦められなくなりますからね。
C:じっさいに作っていると声の癖も気にならなくなるんですけどね。僕の場合、ボーカロイドはちょっと楽器的に使っているんですよ。使い方を楽器的にするということじゃなくて、人間が歌うときとはオケも変わってくるので、アレンジ含めてボーカロイドを楽器として扱ったほうがおもしろくなるんですよね。僕がボーカロイドですごく良いと思っているのは、歌詞がそんなに聴こえてこないところなんです。ものすごくクサかったり恥ずかしかったり中二っぽい歌詞でも、ボーカロイドが歌うと成り立つんですよ。人間がこれを歌ったらちょっと恥ずかしいだろうというものでもボーカロイドだとさらっと歌えちゃう。それはやっぱり機械が歌っているからこそで、ようするに歌詞の幅がものすごく広く取れるんですよね。じっさいボーカロイドの歌詞ってすごく個性的というか、振れ幅が大きいですよね。癖のある歌詞も多いですけど、それはボーカロイドならではですよね。
S:素人の方々の「歌ってみた」ヴァージョンを聴いて、ボカロ・ヴァージョンより良いと思うことはあんまりないんですよね。人間が歌うとエゴが入ってくるというか、味がありすぎて。
C:そうなんですよ。歌詞も聴こえてきちゃうんですよね。
S:たとえばライヴでどっぷり浸かるようなときはそれでもいいんですけど、部屋のパソコンで聴いていると、その人間の味がうるさすぎるよなって感じるケースが多い。だからたぶんボカロで曲を作ったことがない人は、そういう匂いの消し方とか、そういう力をあまり知らないというところもあるんじゃないかなと思いますね。だから、そういう人たちをうまい具合に引き寄せられたら、第二次ブームみたいなことも可能だと思うんですよね。いや、ブームになってほしいなあ。
C:まあ、ある意味ではずっとブームなんですけどね(笑)。







