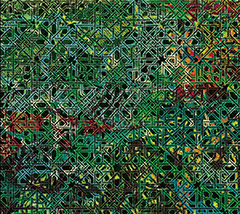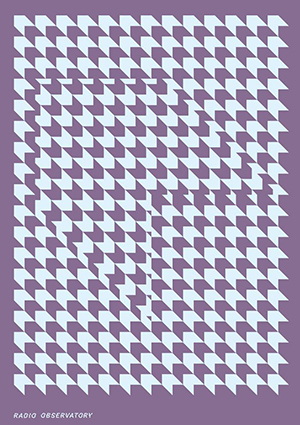アメリカ西海岸/LAが誇るモダン・ファンク・シーン最強アーティスト、デイム・ファンクが6年振りとなるフル・アルバム『Invite The Light』をリリース。2年ぶりのJAPANツアーがおこなわれ話題を呼ぶなか、5年ぶりとなるフル・アルバム『Lotta Love』を発表したG.RINAとのスペシャル対談が実現。どうぞ、お楽しみ下さい。
ベッドルームスタジオはある意味、最善の方法だと思ってる
G.RINA「Lotta Love」ダイジェストMV
 G.RINA Lotta Love TOWER RECORDS |
 Dam-Funk Invite the Light Stones Throw |
G.RINA(以下、RINA):G.RINAです、はじめまして。これはわたしのアルバムなんですが、話している間アルバムを聴いてもらえますか?
DaM FUNK(以下、D):もちろん、どんなスタイルなの?
RINA:ファンク、ディスコ、ヒップホップの要素があって、そしてわたしなりのソウル音楽です。
D:いいね、聴いてみよう。日本生まれなの?
RINA:はい。
D:『Lotta Love』G.RINAね。プロデューサーも日本のひとなの?
RINA:あ、これはわたし自身がプロデュースしてるんです。
D:そうか、いいね! 聴こう聴こう。リリースしてどれくらい経つの?
RINA:1ヶ月前にリリースしたんです。
D:曲も作ってるの?
RINA:はい、曲を書いてプログラミングもしています。
D:音を最大にしよう。……クールだね。演奏もしているの?
RINA:はい、バンド・メンバーと一緒に。
D:ドープ! そしてすばらしいね。
RINA:わたしはディスコ・ファンクやソウルやヒップホップが大好きでしたが、その影響を自分のやり方で消化するのにとても時間がかかりました。自分自身のファンク・ミュージックをつくるときにとくにどういう部分に気を遣っていますか?
D:ハートだよ。自分に対して誠実に、心をこめてやるってことが大事なんだ。それに尽きる。俺は夜中の12時から制作を始めるんだ。キーボードに向かって、自分のヴァイブスを探していくんだよ。……この曲いいね、なんていう曲?
RINA:「音に抱かれて」……なんて言ったらいいかな、Music Embrace Us……?
D:へえ、いいね。ところでこのアルバム一枚もらえるかな?
RINA:もちろんです。
D:ありがとう。好きだなこの曲。……このコードがいいね。間違いないコード感だ。ときどき自分の作った曲で、自分であんまり良くないって思うものもあるんだ。ハハハ。でもこれはいいね。
RINA:またまた(笑)
D:ブギー、ファンク、ディスコ、ハウス、ヒップホップいろんな要素があるね。
RINA:ありがとうございます。いろんなジャンルの音楽をチェックしてるんですよね?レコードで?
D:そうだよ、ロック、ソウル、ニューウェイヴ……あらゆる音楽だよ。ファンクだけじゃなくてね。プリファブスプラウトにもハマってる。知ってる?
RINA:知っていますよ。
D:え、ホントに知ってるの? 彼らの音楽こそ俺のお気に入りだよ!
RINA:幅広さがわかりますね! ところで、今回のアルバムはどの曲も好きですが、なかでも「Surveilance Escape」がとくにすきです。
D:ありがとう。すべて自分のベッドルームで録音したんだよ。
RINA:あのアルバムは一発録りですか?
D:いや、たしかに普段一発録りもよくやっているんだけど、実はこのアルバムの録音には4年かかったんだ。でも全ての音をベッドルームで録音したよ。ベッドルーム・スタジオさ。
RINA:今回の収録曲は全部ベッドルーム・スタジオで録音したんですか?
D:そうだよ。
RINA:わたしもそうですよ!
D:クールだね、それがある意味で最善の方法だと考えてるよ。でも次回はスタジオに入りたいと思ってる。グランド・ピアノやストリングス、そういうものを録音したいからね。
RINA:ピアノもご自分で弾くんですね?
D:うん、生の感触を入れたいんだ。ライヴ感のある作品さ。だけどその前にアンビエントアルバムも出したいと思ってる、インターネットで公開するような形でね。いま進行中だよ。……このアルバム・ジャケットの足はきみの足? なかには顔写真もあるの?
RINA:はい、あります。
D:いいね、あとでまたゆっくりチェックさせてもらうよ。
[[SplitPage]]
自分のスタイルを追い求めて自分を信じて、こだわりから手を放さなかったんだ
DâM-FunK ”We Continue” from『Invite The Light』
RINA:数年前にJzBratでライヴをされていましたね、あれが日本で最初のライヴでしたか?
D:〈ストーンズ・スロウ〉のパーティだとしたら、そうだよ。
RINA:そのときわたしも観に行ったんですが、初めてあなたのライヴを観たとき、あなたのスタイルに新しさを感じました。そしてそれにとても勇気づけられたんです。そこから、わたしも自分が影響を受けたこういった音楽の要素を自分の作曲のなかに活かす方法をじっくり考えるようになったんです。
D:それはうれしいね。そしてそれはうまくいっていると思うよ。その調子でがんばって良い曲を作ってほしいね。
RINA:ありがとうございます。あなたはモダン・ファンクのシーンの開拓者として大きな存在で、同時にとてもユニークな存在でもあると思うんです。アメリカにはおそらく良いプレイヤーはたくさんいると思うんですが、そんななかで自分が他のプレイヤーたちと異なっていたのはどんな部分だと感じていますか?
D:俺は本当にやりたいことだけをやってきた。自分のスタイルを追い求めて自分を信じて、こだわりから手を放さなかったんだ。いろんなスタイルに手を出さずに、なんでも屋みたいにならないようにね。ひたすら自分に正直でいたことで、サヴァイヴしてこれたんだと思う。
RINA:普段はいろんな音楽を聴くんですよね。それでも自分で作るものはファンクにこだわってきた。
D:そう、なぜならこどもの頃からそういった音楽に助けられてきたからさ。プリンス、ジョージ・クリントン、エムトゥーメイ、チェンジ、スレイヴからルースエンズ……そういった音楽に助けられてきたし、良い思い出が沢山あるんだ。いろんな音楽がすきだけど、そのなかでもファンクは俺の血液みたいなものなんだよ。
RINA:わたしにとっても好きなアーティストたちばかりです。とくに影響を受けたといえるのは? プリンスですか?
D:そうだね、ただし1989年まで。それ以降はそうでもないね。サルソウル、プレリュード、影響を受けたレーベルもたくさんあるね。
RINA:では音楽に限らなければ?
D:人生に影響を与えているもの? 夕陽、うつくしい夕陽を眺めることだよ。
RINA:ロマンティックですね!
D:それ以外では年代ものの車で近所をドライヴすること、ファッションそしてインターネットだよ。
RINA:インターネットといえば、あなたのインスタグラムをフォローしていますが、ポジティヴなフレーズやメッセージを写真とあわせて発信していますね。ほぼ毎日されているので、どんな考えでそうしているのか聞いてみたかったんです。
D:そうだね、それはできるだけやりたいことなんだ。俺は他人にしてもらって良かったことを、自分もしていきたいと思ってる。スマートフォンを眺めてたくさんの情報に触れるとき、せっかくなら誰かをインスパイアするようなことばを、諦めるなっていうようなメッセージを発していきたい。
RINA:そういうことに対して強い信念があるのを感じます。
D:俺たちはただの人間だろう、自分が発するメッセージが誰かをひどく傷つけたり人生を壊してしまうことさえある、そんなことをするかわりに、ポジティヴな影響を与えたいんだ。そしてその良いエネルギーがきっとまた自分に返ってくる。もちろん俺だってパーフェクトじゃないし、馬鹿なこともするさ。だけどお互いに影響を与えあう時、良いエネルギーこそが必要とされてると俺は感じてるんだよ。
RINA:その通りですね、そしてそれはあなたの音楽の中にもあらわれていると思います。
D:ありがとう。そうだといいね。
RINA:最後に、短いことばで自分のことをあらわすとしたら?
D:ファンクスタだね。それと同時に良い人生を送りたいと思ってるひとりの人間さ。
RINA:今日はお話しできてよかったです、ありがとうございました。