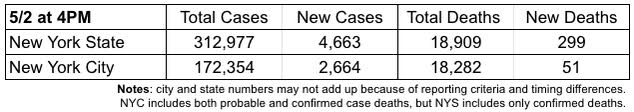いちばん好きなバンドは? と聞かれるのがずっと苦手だった。世代に沿ったド定番のバンドはある程度聴いてきたし、流行りの曲や新譜のチェックもできるだけ欠かさないようにしてきた。だが、いまだにフェスの季節が来るたび新しいバンドの存在を知らされたり、お気に入りのアルバムがセカンドかサードかも曖昧になったり、素朴な質問にすら悩んでしまったりする。そう、自分はどのバンドのファンにもなったことがなかったのだ。ところが最近、ついに胸を張ってファンと名乗れるバンドができた。そのバンドこそが、ウクライナのポップ・パンク・バンド、ПОШЛАЯ МОЛЛИ (Poshlaya Molly:ポシュラヤ・モリー)だ。
ロシア・ウクライナ語で「モリ―(MDMA)を贈る」という意味の名を冠し、甘やかされて育ったティーンエイジャーをコンセプトに活動する ПОШЛАЯ МОЛЛИ。日本ではまだ知名度が低いどころかほとんど知られていないが、彼らの活動拠点であるロシア・ウクライナでは人気急上昇中のバンドだ。グランジ、オルタナティヴ・ロックを軸に、エレクトロニック・サウンドをミックスしたキャッチーな楽曲と、現代のユース・カルチャーを映し出した特徴的な世界観で若者たちを魅了した。また、デビュー当時の2017年前後に流行したマンブル・ラップを、ポップなパンク・ロック・サウンドに落とし込み、よりユースの心情の解像度を高めたマンブル・ロックのシーンを構築した。その後も数々のライヴを重ね、2018年には〈Warner Music Russia〉に所属するなど、さらなる人気を集めている。
彼らを知ったのは2017年の秋、ちょうどデビュー・アルバム『8 способов как бросить …』が出されてすぐの頃。収録曲 “Любимая песня твоей сестры” のMVを YouTube で偶然見つけたのがきっかけだった。このMVは計1,000万回もの再生数を記録し、現地のSNSサイト Vk.com を中心に話題となった。最初は耳慣れている、聴きやすいオルタナティヴ・ロック・バンドくらいの印象でしかなかったが、初めて触れるウクライナのシーンは退廃的ながらもどこか新鮮だった。
その後もなんとなくチェックするようになり、気づけばデビューからいまこうして筆を執るまで彼らを追い続けている。現在のサウンドに近づきはじめたEP「Грустная девчонка с глазами как у собаки」、「ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ МОЛЛИ 3」もすべてリリース当日に聴きこんだ。サブスクがある時代に生まれて本当に良かったと思う。楽曲ももちろんのこと、ユース・カルチャーをリスペクトしてるのか、はたまた皮肉ったかのようなMVも何度再生しただろうか。
ここまで愛を語るとどれだけすごいバンドなのかと期待を持たせてしまうかもしれないが、彼らは特にこれと言って画期的なサウンドを奏でたり、新しいシーンを構築してるわけでもない。人によっては割と普通のポップ・パンクといった印象を受けるであろう。それでも彼らに惹かれてしまう理由が、最新作EP「PAYCHECK」でやっと解き明かされた。
前作同様、お腹いっぱいになるほどポップ・パンクな楽曲が全6曲収録された本作。1曲目 “Самый лучший эмо панк” ではバンド名をコーラスさせたり、2曲目 “Беспечный рыцарь тьмы” の間奏ではいわゆるお決まりのようなブレイクダウンが挟まっていたりと、とにかくド定番な演出が詰まっている。ありきたりな演出と捉えられるかもしれないが、欲しい音を欲しいところでぶつけてくるところが彼らの魅力でもある。
本作のリリースに先駆け、シングルとしてもリリースされた5曲目の “Мишка” は、ロシアのモデル・シンガーの KATERINA をフィーチャリングに起用。併せて公開された同作のMVでは、キャスケットにフレンチネイル、細身のスキニーとテーラードジャケットといった懐かしのファッションに身を包んだふたりの男女、レッドカーペットに集うパパラッチにアワードのトロフィー……と2000年代のセレブ、ゴシップ・ブームを彷彿させる世界観を、かつてのヒットチャート風の楽曲と共に披露した。
ПОШЛАЯ МОЛЛИ のコンセプト「甘やかされて育ったティーンエイジャー」とは、まさに彼らが演じるキャラクターであり、それらを見て育った彼ら自身そのものだ。これまで影響を受けたロック・バンドやポップ・カルチャーをリスペクトし、過去の産物になってしまったスタイルを否定せず当時の憧れをサウンドにアップデートすることで、ПОШЛАЯ МОЛЛИ はいつまでもティーンエイジャーであり続けている。そんな彼らと同じ憧れを自分も持っていたからこそ、あの聴きやすいサウンドや新鮮ながらもどこか共感してしまう世界観に惹かれ、お決まりの展開ですら心地良く感じていたのだと、本作で気付かされてしまった。そして、かつての憧れに対して真剣に向き合う彼らの姿勢に、いま自分は憧れている。
こうして愛を語れるようになったのも、実は彼らのおかげである。ライターとして活動をはじめたのも、自身の note にロシア・ウクライナのアーティストについて記したのがきっかけだった。新卒で出版社を受けたものの全滅した自分を、ライターというかたちで憧れの姿に近付かせてくれた彼らには頭が上がらない。もうすっかり彼らの虜になってしまったいまなら、いちばん好きなバンドを問われたとしても躊躇なく答えられる、ПОШЛАЯ МОЛЛИ であると。