昨年ブラック・ミュージックの大絵巻、『Untitled (Black Is)』と『Untitled (Rise)』の2枚のアルバムを送り出し大いに話題を呼んだUKの匿名のグループ、SAULT が早くも新作をリリースしている。『NINE』と題されたそれは、99日間に限り、ストリーミングまたはダウンロードすることができる。ときが経つのはあっと言う間なので、お早めに。
「Ordã€ã¨ä¸€è‡´ã™ã‚‹ã‚‚ã®
〈Mute〉の創始者ダニエル・ミラーとガレス・ジョーンズの2人の超ベテランによるモジュラー・シンセサイザー作品が〈Mute〉からリリースされた。
ふたりが初めて一緒に作業したのは1982年のデペッシュ・モードの『Construction Time Again』のときで、以来、ガレス・ジョーンズは、パレ・シャンブルグ、ファド・ガジェット、アインシュツルテンデ・ノイバウテン、ダイアマンダ・ギャラス、ワイヤー、イレイジャー、そしてイルミン・シュミット……などなどの、〈Mute〉や〈Some Bizzare〉などの諸作に関わっている、テクノ/インダストリアルの分野では高名なエンジニアだ。
2人はそして、大のシンセ好きでもあり、2019年から限られた数チャンネルを使ってセッションをはじめて、サンルーフ名義による今作を制作した。
ガレスによれば「マーティン・ゴアとクリス・カーターのやり方にインスパイされた」そうだが、長年エレクトロニック・ミュージックに関わり、しかもモジュラー・シンセには一家言を持つ2人による共作なだけに、奥深い、アブストラクトでアンビエントな作品になっている。ちなみにサンルーフはすでに、CAN、クライドラー、トゥ・ロココ・ロット、MGMTなどのリミックスをしている。
収録曲1.1- 7.5.19 (Edit) (Official Visual)

Sunroof
Electronic Music Improvisations Vol. 1
Mute/トラフィック
クルアンビンのサード・アルバム『モルデカイ』のリミックス盤が8月6日に出ます。タイトルは『MORDECHAI REMIXES(モルデカイ・リミクシーズ)』。これが予想通りの気持ちよさ。ハウシーで、トライバルで、ときにダビーで。まさにsoud of summerの1枚です。ためしに1曲聴いてみましょう。
Khruangbin - Pelota (Cut a Rug Mix) - Quantic Remix
全リミキサーは以下の通り。
Kadhja Bonet(LAの女性シンガー/マルチインストゥルメンタリスト)、Ginger Root(カリフォルニア出身のインディ・ロッカー)、Knxwledge(LAのプロデューサー/ビートメーカー)、Natasha Diggs(NYをベースとするDJ/プロデューサー)、Soul Clap(マサチューセッツ州ボストン出身のモダン・ハウスDJデュオ)、Quantic(イギリスのDJ/プロデューサー)、Felix Dickinson(UKアンダーグラウンド・ダンス・シーンの実力者)、Ron Trent(シカゴ・ハウスのレジェンド)、Mang Dynasty(UKディスコ・シーンを代表するDJ/プロデューサー/リミキサー、Ray Mangとイギリスの作家/ディスクジョッキー、Bill Brewsterによるユニット)、Harvey Sutherland(メルボルンのクラブミュージックシーンで注目を集めるアーティスト)
2021年8月6日にデジタル、10月29日にLPでリリース。CDは日本のみでのリリース。

KHRUANGBIN(クルアンビン)
MORDECHAI REMIXES(モルデカイ・リミクシーズ)
ビッグ・ナッシング/ウルトラ・ヴァイヴ
■収録曲目:
1. Father Bird, Mother Bird (Sunbirds) (Kadhja Bonet Remix)
2. Connaissais De Face (Tiger?) (Ginger Root Remix)
3. Dearest Alfred (Myjoy) (Knxwledge Remix)
4. First Class (Soul In The Horn Remix) (Natasha Diggs Remix)
5. If There Is No Question (Soul Clap Wild, but not Crazy Mix) (Soul Clap Remix)
6. Pelota (Cut A Rug Mix) (Quantic Remix)
7. Time (You and I) (Put a Smile on DJ's Face Mix) (Felix Dickinson Remix)
8. Shida (Bella's Suite) (Ron Trent Remix)
9. So We Won’t Forget (Mang Dynasty Version) (Mang Dynasty Remix)
10. One to Remember (Forget Me Nots Dub) (Harvey Sutherland Remix)
「誰もが大きな試練を乗り越えてきた。これを作り上げるために、僕らは泥の中を突っ走ってきたような気がする。そしてこの勇敢(valiant)で誇らかな感覚が、嵐の中から穏やかな海に流れ出した。サウンドの響きと感情の奥行きに誇りを感じる。この辛い毎日に、人々にちょっとした安らぎを届けることができたらと思う」
──ポール・ベンダー(アルバム・インフォメーションより)
ハイエイタス・カイヨーテが6年ぶりにアルバムを引っさげて帰ってきた。あのパンク・ロックっぽいアートワークでネオ・ソウルなヴァイブスを奏でる前作『Choose Your Weapon』はギャップも含めかなりのインパクトがあったし、ジャズやソウル、ロックやポップスなどの絶妙なバランスを縫ったサウンドとヴォーカルのネイ・パームが放つ独特の雰囲気と歌が、ジャンルの垣根を超えた日本のオーディエンスにもバッチリ支持されている証拠だろう。
新作『Mood Valiant』はなんとブラジリアン・サウンドの「生ける伝説」とも言えるアルトゥーロ・ヴェロカイとのコラボレーションが実現。そして引き続き飛ぶ鳥を落としまくっている〈ブレインフィーダー〉からのリリースということで、僕らの期待をいい意味で裏切ってくれたと思う。しかしながらアルバム・リリースまでの道のりは決して順風満帆ではなく、メルボルンの4人組バンドはここ6年間で様々な出来事に直面してきたのである。世界中を飛び回るハードなツアー・スケジュール、過去に母親を同じ病で亡くしたヴォーカル、ネイ・パームの病気が発覚、そして誰もが予想だにしなかったコロナ禍を乗り越えて……。
個性的なサウンドが彼らを反映するように、「ユニーク」な時間を大事に制作に取り組んだそう。「“Mood Valiant” というふたつの単語は、“二重性”、“双対性” を表現した言葉なんだ。“ポジティヴ” と “ネガティヴ”、“陰” と “陽”。物事や人間には全てはふたつの面があるからね」と語ってくれたポール・ベンダーは、数多くのネガティヴなシチュエーションを忍耐強く乗り越えたポジティヴなアンサーを僕らに届けてくれた。
〈Brainfeeder〉とすでにけっこう繋がっていたんだ。だから、僕たちにとっては自然の流れだったし、まあそうなるだろうねって感じだった。
■アルバム制作に6年かかったと伺いました。前作『Choose Your Weapon』がリリースされてほぼすぐのタイミングだと思いますが、そのときからすでに次のアルバムを作ろうと思っていましたか? それとも、ライヴやツアー、新しい曲の制作の過程で自然な流れになったのでしょうか?
PB:『Choose Your Weapon』のツアーのあとは少し休んだんだ。けっこうツアーがハード・スケジュールだったから、ちょっと休みたくてね。皆でスタジオに集まるまでには時間は多少かかったけど、アルバムのなかには、その前からずっと存在していて今回のアルバムで使うことにしたアイディアや曲なんかもある。そういった昔のアイディアと新しくできあがったもので新作は成り立っているから、ピンポイントでいつアルバム作りをスタートさせたかを断定するのは難しいんだ。僕たちの場合、いつも自然の流れに任せているから、何がきっかけだったかを考えるのは毎回難しいんだよね(笑)。ハイエイタスのアルバムってのは作るのが本当に難しい。メンバーそれぞれのこだわりが強いから、それを全て落とし込むとすごく複雑になる。だから時間がかかるんだ。
■アルバムのタイトル『Mood Valiant』にはどんな思いやコンセプトが込められていますか?
PB:ネイ(・パーム)の母親が、ネイが子どものときに白と黒のヴァリアント(クライスラーの車)を持っていて、その日のムードによってその2台を乗り分けていたんだ。学校にネイを迎えにくるとき、もし母親が黒いヴァリアントに乗っていたら、その日は母親に逆らわない方がいいという意味だった(笑)。同じ車でも、ムードによって変わる。つまり、同じ人、物でも様々な情緒状態を持っていて、様々な面があるということ。“Mood Valiant” というふたつの単語は、“二重性”、“双対性” を表現した言葉なんだ。“ポジティヴ” と “ネガティヴ”、“陰” と “陽”。物事や人間には全てふたつの面があるからね。
■インタヴューの前に曲それぞれの解説を読ませていただきました。ネイ・パームの作詞や曲に対するアプローチが本当に独創的だなと感じました。ユニークなサウンドを作るためにバンドとして心がけていることはありますか?
PB:メンバーの誰かがユニークなアイディアを持ってきて、最初からそのアイディアを元にユニークなサウンドを作りはじめるときもあるし、シンプルなサウンドができあがってから、そのなかで何かユニークなことをしようとするときもある。でも僕らの場合、4人それぞれが異なるアイディアを持ってくるから、それを組み合わせる時点ですでに十分ユニークなものが自然にできあがることが多いと思う。セッション・ミュージシャンたちのなかには、直感を大事にするミュージシャンも多い。でも僕たちは、もしシンプルなものができあがったら、それをもう少し追求して、掘り起こしていくタイプなんだ。

■例えば他のバンドのメンバーがネイの歌詞に何かリクエストや書き換えをお願いしたりすることもあるんでしょうか?
PB:いや、それはないな。僕たちはメンバーそれぞれの役割を尊重しているから、お互いにあまりリクエストをすることはない。まあときどきはあるけど。ネイが歌詞を書いたら、それがその曲の歌詞ということは決まってる(笑)。それは彼女の仕事だから、僕らは立ち入らない(笑)。
■“Get Sun” がリリースされたときアルトゥール・ヴェロカイとのコラボレーションは正直驚きました。彼との出会いのキッカケを教えてください。
PB:アイディアを出したのはネイなんだ。曲ができあがったとき、ネイがその案を出したら、全体の意見としては「それが実現したら最高! でもまあ無理だろうな」っていう感じだった(笑)。そこでマネージメントに連絡をとってもらったんだ。いきさつはそれだけ(笑)。僕らがただ彼の音楽の大ファンで、アプローチしたのさ。彼だったらパーフェクトだと思ってね。彼が乗り気になってくれるかはわからなかったけど、人生一度きりだし(笑)。ダメもとで頼んでみるしかないと思って連絡したんだ。そしてブラジルへ行く1週間ほど前にメールをもらって、そこに短く「この曲にはすでにかなりの種類の楽器が使われているようだし、これ以上何をすればいいのか考えあぐねている。健闘を祈る」と書いてあって。実際彼からは事前に何も送られてこず、初めて彼が書いたものを聴いたのは実際にリオのスタジオに行ったときだったんだ。アルバムがほぼできあがりそうなギリギリのタイミングだったのに、そこからさらにアルバムがぐんと進化したんだ。あのセッションで、シングル級の作品が新たに生まれたんだよ。
[[SplitPage]]失恋したり、病気になったり、誰かが亡くなったり、大変な状況に置かれているときは、音楽の意味が増すと思う。いまはコロナやその他様々な複雑なことが世界では起こっている。だから、アートのなかには美しさを増している作品もあるんじゃないかな。
■アルバムで “Stone Or Lavender” がいちばん好きなんですが、このストリングスもアルトゥール・ヴェロカイが弾いたものですか?
PB:そう。そのトラックのためにブラジルに行ったわけではなかったけど、ブラジルでのレコーディングで運良く時間があまったから、彼に弾いてもらったんだ。
■ブラジルでの制作活動はいかがでしたか? 地元メルボルンのスタジオとはまた違ったテンションになると思いますが、制作の雰囲気など具体的なエピソードがあれば教えてください。
PB:素晴らしい経験だった。あのセッションは、いままでの活動のなかでも最高のセッションのひとつだね。もともとの目的は “Get Sun” のホルンとストリングスのレコーディングだったし、実際にブラジルに行かなくてもどうにかなったんだろうけど、経験のために実際あの場にいられて本当に良かったし、すごくエモーショナルになった。実際にやってみるまで何が起こるか想像もつかなかったけど、いざはじまると、彼の演奏が本当に素晴らしかったんだ。皆ものすごく興奮して、勢いで延長してその日の残りの時間もスタジオを借りることにした。その時間でレコーディングしたのが “Stone Or Lavender” と “Red Room”。あの2曲はあの場で本当にサッとできあがった。最初のレコーディングでそれくらい興奮したし、活力を得たからね。
通訳:何か具体的なエピソードはあったりしますか?
PB:ホルンとストリングスが完成したとき、僕は感動してコントロール・ルームで泣いてしまったんだ(笑)。あの瞬間は本当に素晴らしかった。どんな瞬間とも置き換えられない特別な経験だったからな。
■〈Brainfeeder〉との契約もサプライズでした。レーベルとの出会いのキッカケはなんでしょうか?
PB:〈Brainfeeder〉のメンバーとは、数年かけてだんだんいろんな人と出会っていった。Timeboy こと John King は僕たちのライヴのステージ・デザインを手がけてくれているから近い存在だし、サンダーキャットとはたくさんのショウやフェスティヴァルで共演する機会があって親しくなった。フライング・ロータスも同じ。テイラー・マクファーリンはずっと昔に僕たちの音楽を広めてくれたし、ミゲル・アトウッド・ファーガソンは前回のレコードでストリングスを担当してくれた。そんな感じで、僕らは〈Brainfeeder〉とすでにけっこう繋がっていたんだ。だから、僕たちにとっては自然の流れだったし、まあそうなるだろうねって感じだった。バンドにすごく合うレーベルだと自分たちも感じているし、彼らの一員になれてすごく嬉しいね。
通訳:〈Brainfeeder〉とサインしたことで変化したことや、プラスになったことはありますか?
PB:〈Brainfeeder〉のクルーは、皆すごく前向きで自分たちがやりたいことを応援してくれる。最高のレーベルだと思う。インスパイアもされるし、こっちの方から自分たちの活動にぜひ関わってほしいと思える存在。彼らは真のクリエイティヴ・コミュニティだと思う。彼らと一緒に仕事ができるなんて夢みたいだよ。
■6年間もかけて1枚のアルバムを作る作業は途方もない作業のように思えます。制作の過程で「途中でアルバムを作るのを辞めよう」と挫折するような瞬間はありましたか? 約10年近くに及ぶハイエイタス・カイヨーテの活動のなかで、バンドが継続していける秘訣のようなものがあれば教えてください。
PB:どうだろう。波はもちろんあったけど、僕ら4人が一緒に曲を作るというのは、自分たちが楽しめる瞬間だし、何かユニークなものが生まれる時間でもある。僕らはいまや家族のような存在だし、すでに様々なことを一緒に乗り越えてきている。だから挫折するということは特になかったし、意識しなくても自然と続けたいと思えるんだ。僕たちはそれぞれ全く違う人格だから、ときには複雑な場合もある。でも、だからこそスペシャルなものができあがるんだと思う。自分にできることは、自分の役目以外は人に任せて自分は自分の仕事をきちんとこなすこと。長く活動していれば波があるのは当たり前だし、それに流されず自分が提供できるクリエイティヴィティを提供し続けていけばいいんだと思う。流れのなかで自分はとにかく創作を続け、それを皆が合わせたいときに一緒に合わせればいいんだと思うね。バンドの音楽活動は、大変だけどそのぶん大きなやりがいも感じる。必要なのは忍耐とパッションを持ち続けることさ。
■コロナの影響を受けて、フェスティヴァルやイヴェントの形や、音楽の聴き方や存在自体が変化していますね。皆さん自身は今回の期間を経て行動や音楽に対する価値観が変わりましたか?
PB:人生のなかで、より大変な状況に自分が置かれているときは、自分にとっての音楽の意味が増すと思う。例えば、失恋したり、病気になったり、誰かが亡くなったりしたときは、これまで以上に意味と繋がり、美しさを感じるようになると思うんだ。いまは、コロナやその他様々な複雑なことが世界では起こっている。だから、アートのなかには美しさを増している作品もあるんじゃないかな。
■ネイ・パームを除いた3人でのトリオ Swooping Duck や、最近インスタグラムで見かけた Space Boiz (!?)などいろんなプロジェクトも進行してますね。Patreon でも積極的に活動してますが、今回のアルバム以降の活動の予定を教えてください。
PB:まだわからないんだよな。8月にシドニーのフェスに出演することは決まってる。国内のショウはいくつかありそう。いまはショウのための準備をしている感じだね。あとは、タイニー・デスクの出演も決まっていて、それはもうすぐ収録なんだ。個人的には、リリースの予定はまだないけど、自分のソロ・アルバムのミックスを終えたところ。今年のどこかでリリースできたらいいんだけど。僕が初めて歌っている作品なんだ。本当に悲しいハートブレイクのレコード。すごく良い作品に仕上がったと僕は思ってる。誇りに思えるし、とりあえず世に送り出してみたい。それは僕にとっての大きな予定だな。
■日本ではまだ Patreon が浸透していないのですが、ハイエイタス・カイヨーテとして利用してみていかがでしたか? 良いプラットフォームであればぜひ日本のアーティストにもオススメして欲しいです。
PB:良いと思う。メンバー全員が気に入ってるし、素晴らしいプラットフォームだと思うよ。舞台裏でも他のプロジェクトでも何でも、自分が載せたいものを載せられるんだ。そのページのファンクラブの会員みたいなものになるために、ファンの皆が月額で会費を払う感じだね。それに入ると、他の人には見られない特別な作品を見ることができる。そんな仕組み。僕とサイモンがたくさんのシンセにプラグを差し込んでクレイジーなジャムをしているビデオだったり、僕がチェロで即興をやったり、舞台裏の様子だったり、本当になんでもあり。面白いと思うよ。チェックしてみて。

■昨年、今年と立て続けにオーストラリアのアーティストやバンドが活躍しています。もしご存じであれば地元メルボルンでぜひ注目して欲しいアーティストはいますか?
PB:レニアス(Laneous)をチェックしてみて。特に『MOSNTERA DELICIOSA』っていうアルバム。僕がプロデュースしてるアルバムで、作品のなかで演奏もしてる。すっごく良いアルバムなんだ。作業していていちばん楽しかったレコードのひとつ。バンドキャンプやスポティファイで聴けるから、ぜひ聴いてみて。
■日本にももう何度も来日されてますね。19年はフジロックにも出演されましたが来日時に特に記憶に残る思い出はありますか?
PB:買い物した。けっこう面白いものを買ったんだ。ギラギラのシルクのガウンとか、クラゲの柄のショーツとか、フラミンゴ柄のシャツとか(笑)。めちゃくちゃ派手な服ばかり(笑)。日本で買い物するのって本当に楽しいんだよね。あと、言うまでもないけど食事も最高。日本に行くときは毎回良い時間をすごしてる。ただ歩き回って、レコード屋や服屋で買い物をして、ハイボールを飲みまくる(笑)。
■聴く人それぞれに解釈はあると思いますが、ハイエイタス・カイヨーテが『Mood Valiant』を通してオーディエンスやリスナーへ伝えたいメッセージはありますか?
PB:アルバムを聴いて、素晴らしい時間を過ごしてくれたら嬉しい。アルバムの音楽が必要な感情を引き出して、皆がそれに浸り充実感を感じてほしい。何か必要なものがあるとしたら、それを僕らのアルバムのなかで見つけてもらえたら最高だね。
通訳:今日はありがとうございました!
PB:こちらこそ。またね。
UKの工業都市ニューカッスル・アポン・タインを拠点とするエクスペリメンタル/インダストリアルなレーベル〈Opal Tapes〉から本年2021年にリリースされた日本人アーティスト Kentaro Hayashi のアルバム『Peculiar』(https://opaltapes.com/album/peculiar)をご紹介する。
本作は、やや複雑な経緯で〈Opal Tapes〉からリリースされたアルバムだ。もともとは2020年に日本は大阪のレーベル〈remodel〉からリリースされたCD作品だったが、かの〈Opal Tapes〉の耳にとまり、2021年にふたたび「新作」(LP/デジタルでのリリース)として世界に送り出されたアルバムなのである。今回のリリースにあたり〈remodel〉盤からアートワークも一新され、新たに2曲が追加収録されている。完全版『Peculiar』とでもいうべき仕上がりだ。
ちなみに〈remodel〉は、かつては故・阿木譲氏が主宰していたレーベルだが、現在は彼の意志を継いだ形で運営されているインディペンデント・レーベルである。
Kentaro Hayashi のことは生前の阿木氏も高く評価していたようで、「KENTARO HAYASHIのsubstratum音響は柔らかい機械だ。バロウズの「世界を律しているのは音でパターンとしての聴覚」であるという、あるいはガタリのそれぞれの組織や諸機械を具えて蠢いている宇宙の卵胞=器官なき身体かも」と書いていたという(https://studiowarp.jp/slowdown/remodel-08-kentaro-hayashi%E3%80%8Epeculiar%E3%80%8F/)。
そのような縁(?)もあってか Kentaro Hayashi は、阿木氏晩年の「0g」などのデザインを行っていた edition.nord (秋山伸)がリリースしていた阿木譲「Bricolage Archiveシリーズ」や「Vanity Tapes: Box Set / Cassette edition」の編集とマスタリングを担当などを担当もしている。彼は優れたサウンドエンジニアでもあるのだ。その意味で本作は大阪(edition.nord は新潟を拠点としている)の阿木譲/「0g」のネットワークから世界へと飛びだっていった逸材ともいえよう。
だが、これまでの話は彼の音楽そのものからみれば周辺の話題にも過ぎないとも思う。それほどまでに本アルバムに収録された電子音楽はエレクトロニック・ミュージックとエクスペリメンタル・ミュージックの新たな可能性に満ちているように思えるからだ。
あえて分かりやすい例えを使わせてもらえば、デムダイク・ステアとワン・オートリックス・ポイント・ネヴァーなどの10年代エクスペリメンタル・ミュージック・サウンドの可能性を新たに解釈し、別の並行世界のサウンドスケープとして生成・構築したような音響作品なのである。
これは大袈裟な比喩ではない。特に1曲目 “Gargouille” を聴いてほしい。讃美歌のような「声」のサンプルに、それをバラバラに解体していくような電子音/ノイズが重なり、時間と空間を遠近法を変換していくかのごときサウンドを作り上げているのだ。ノンビートのさなか不規則に、まるで新たな生命体のようにノイズが蠢く驚き。そこで変換される讃美歌のようなヴォイスは、この世界の美しさと受難の瞬間を結晶化させたかのようである(ちなみにこの曲の前ヴァージョンは〈remodel〉のコンピレーション・アルバム『a sign 2』に収録されている)。まさにアルバムを代表するサウンドといえよう。
2曲目 “Vakuum” は、一転して重厚なリズムが刻まれるネオ・インダストリアルなムードの曲だ。メタリックなノイズの横溢も刺激的である。3曲目 “Peculiar” ではリズムとノイズの交錯がより高密度で展開する。いわばアフター・グリッチとでもいうような強烈なノイズと、アフター・テクノとでも形容したいほどの高速の反復感覚が凄まじい。
以降はメタリックなサウンド・ノイズと解体されるリズムとでもいうべき音響がアルバムを貫く。人間の肉体感覚を越境するような独自のサウンドだ。
〈Opal Tapes〉盤では〈remodel〉盤にない “Arrowhead” と “Anabiosis” が6曲目と7曲目というアルバムの中心位置に近い場所に収録されている(おそらくは氏がネット上にアップしていたトラックを元にした曲だろうか)。ストレートにして異質なテクノを展開する “Arrowhead” と、重厚な「間」の感覚を持ち、まるで楔を打ち込むような “Anabiosis” をアルバムの中心に収めたことで、作品全体の「動と静」のコントラストがより明確になったように思う。
これらの曲はライヴで用いていたハードウェアのサンプル・データをもとに再構築したトラックのようで、その意味でこの時点の Kentaro Hayashi の集大成とでもいえるサウンドともいえよう。
じじつ、徹底的に磨き上げられたトラック/音響は聴き手の聴覚を一気に拡張するような強度に満ちている。特に低音の響きと高音のヌケが抜群で、聴けば聴くほどに身体が強烈な音響によって浄化していくような感覚すら感じてしまう。ノイズとエレクトロニカの融合、いわば「ノイズトロニカ」とでもいうべきか。
さて、アルバムの最後には爆弾級(?)の重要トラックが収めれている。あのジム・オルークによる “Vakuum _ Jim O'Rourke Remix” と、メルツバウによる “Gargouille _ Merzbow Remix” の2曲である。
オルークがこれほどまで電子音響的グリッチ・テクノなトラックを手掛けたのは近年では稀ではないか。オルークは原曲を解体しつつ、原曲にあった解体的テクノの側面をより抽出してみせる。オルークと Kentaro Hayashi の「解体的交感」とでもいうべき仕上がりである。オウテカの現在へオルークからの返答のような完成度の高い電子音楽であり、オルーク・マニアも必聴のトラックである。
そしてノイズ・ゴッド、メルツバウのリミックスは原曲にあった讃美歌的ヴォイスを残し、そこに抑制されたメルツバウ・ノイズが絡むといった異色の仕上がりだ。轟音ノイズのメルツバウというパブリック・イメージとは異なる、いわば「メルツビエント」的なサウンドに思わず唸ってしまった。
そして『Peculiar』は、アルバム冒頭の曲のリミックスで終局を迎えるわけだ。時間と空間、歴史と現在が円環を描くような見事な構成である。
最後に『Peculiar』のトラックは、あの KMRU のミックス音源に選曲されたことを書き記しておきたい(https://groove.de/2021/05/21/kmru-groove-podcast-297/)。しかも冒頭だ。彼のサウンドは、新たなリスナーへと届き始めている。
もしきみがアナキストなら、スペシャル・リクエストを聴かねばならない。いや、アナキストでなくてもいいが、こんな時代だからこそ彼らのパンク・サウンドに耳をすますべきだろう。
昨年の『The Passion Of』が高く評価されたニューオーリンズのこの4人組、なんと〈Rough Trade〉と契約を交わしたそうだ。と同時にアルバムのリリース1周年を記念して、同作収録曲 “Street Pulse Beat” のMVも公開されている。監督はバンドのヴォーカルのアリ・ログアウト。短編映画仕立てです。
ちなみに、2016年にカセットでリリースされたデモテープ「Trust No Wave」も〈Warp〉傘下の〈Disciples〉からヴァイナルでリイシュー中。今後の動向に注目を!
Special Interest
ニューオーリンズ在住の4ピース・バンド
スペシャル・インタレストが名門〈Rough Trade〉と契約!
アルバム『The Passion Of』の1周年を記念してパワフルな
最新ビデオ「Street Pulse Beat」を公開中。
ニューオリンズのノーウェイブ・パンク・グループ、スペシャル・インタレストは、最新アルバム『The Passion Of』のリリース1周年を記念して、アルバム収録曲 “Street Pulse Beat” の超パワフルなMVを公開した。スペシャル・インタレストのボーカルであるアリ・ログアウトが監督を務め、FADERで初公開された。独自の世界観が醸し出す不思議空間とストーリー、さながら映画の中にいるような臨場感を感じられる。
Special Interest- STREET PULSE BEAT (Official Conspiracy)
https://www.youtube.com/watch?v=6sGAN9y-HnQ&feature=youtu.be
スペシャル・インタレストは、ニューオーリンズのDIYシーンから生まれた。デモテープ「Trust No Wave」とデビュー12インチ「Spiraling」を経て、2020年に2枚目のLP『The Passion Of』をリリース、カオティックかつメロディックなアルバムの世界観が各所で注目された。さらに9月にはアルバム『The Passion Of』サポートするツアーを敢行することを明かしている。 Pitchfork Festivalへの出演や、ブルックリンのMarket Hotelでの公演も予定されている。〈Rough Trade〉は、スペシャル・インタレストの次のアルバムに向けて、彼らと契約したことを先日発表した。その詳細は後日発表される。

label: BEAT RECORDS / DISCIPLES
artist: Special Interest
title: Trust No Wave
release date: NOW ON SALE
BEATINK.COM:
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=11826
めっちゃいいこと言ってます。7月にサヴェージズのジェニー・べスとの共作をリリース、年内には自伝の刊行を控えるボビー・ギレスピーが、CANについて大いに語る!
CANをヨーロッパ版のヴェルヴェッツだと喝破する彼は、他方でCANにはスリッツやポップ・グループとも目に見えない繋がりがあったと指摘する。
なかでも “Halleluwah” に触発された彼はその影響を『Screamadelica』に応用するのみならず、“Kowalski” で同曲のドラムスをサンプルしてもいる。それをヤキ・リーベツァイト本人に聴かせたところ……
ほかにもカンの音の「民主的」な側面についてやリアム・ギャラガーとのセッションなど、興味深いエピソードがいろいろ出てきます。これは観ておいたほうがいいやつです。
CANのライヴ・シリーズについてのイルミン・シュミットのインタヴューはこちらから。
ボビー・ギレスピー(プライマル・スクリーム)、CAN愛を語るコメント映像が公開!
CAN、歴史的ライヴ音源を最高の音質でお届けする〈CAN:ライヴ・シリーズ〉第1弾、大好評発売中!
「CANはヴェルヴェット・アンダーグラウンドのような存在かもしれない」 by ボビー・ギレスピー(プライマル・スクリーム) *コメント映像より
CANの伝説のライヴを最先端技術を駆使してお届けする『CAN:ライヴ・シリーズ』の第一弾、『ライヴ・イン・シュトゥットガルト 1975』(Live in Stuttgart 1975)の発売に寄せて、ボビー・ギレスピー(プライマル・スクリーム)のコメント映像が日本語字幕付きで公開された。CANとの出会い、影響、リアム・ギャラガーも参加したジャム・セッションの思い出など8分にわたりCAN愛を語り尽くしている。
■ボビー・ビレスピー(プライマル・スクリーム)コメント映像(日本語字幕付)
https://youtu.be/vQ7fvsseJAs
■ダニエル・ミラー(〈MUTE〉創始者)コメント映像(日本語字幕付)*公開済み
https://youtu.be/l_DqYNK6IkI
■ライヴ盤ダイジェスト音源
https://youtu.be/da6bXpkbwzs
■カタログ関連リンク
[Buy+Listenリンク]
https://smarturl.it/CAN1
[カタログ作品内容]
https://bit.ly/3mfeLxK

CAN は1968年にケルンのアンダーグラウンド・シーンに初めて登場し、初期の素材はほとんど残されていないかわりに、ファン・ベースが拡大した1972年以降は、ヨーロッパ(特にドイツ、フランス、UK)で精力的にツアーを行い、伝説が広がるにつれ、多くのブートレッガーが集まってきたのだ。『CAN:ライヴ・シリーズ』は、それらの音源の中から最高のものを厳選し、イルミン・シュミットとルネ・ティナ―による監修で、21世紀の技術を駆使して、重要な歴史的記録を最高の品質でお届けする。小説家であり、よく知られたCANファンであるアラン・ワーナーは言う──「彼らのライヴ・パフォーマンスは、壮大な物語が語られているかのようだ──異なる章からなり、気分や天候、季節、異国情緒あふれる風景など、変化に富んだ小説のような」。
60年代後半に結成され、10年余りで解散したCANの、ヒプノティックなグルーヴと前衛的なインストゥルメンタルのテクスチュアの、前例のない大胆なマリアージュは史上最も重要で革新的であり、これらのアルバムがバンドの全く異なる視点を明らかにしてくれる。
ジャムでは、おなじみのテーマ、リフやモチーフが飛び出し、波紋を広げるのが聴こえてくるが、多くの場合、それは渦巻く群衆の中で束の間、認識された顔に過ぎない。他にも、公式アルバムでは採用されなかった音楽を聴くことができる。CANはこれらの録音で、スタジオ・ワークを行う時よりもさらに極端な範囲にまで到達する──メロウ、アンビエントなドリフト・ロックから、彼らが “ゴジラズ” と称したホワイド・ドワーフ(白色矮星)状態における、音がメルトダウンする瞬間まで。また彼らが分刻みのリズムを追いかけて合わせて行く過程にも、メンバーが共有していた並外れた音楽のテレパシーを聴くことができるのだ。

■商品概要
アーティスト:CAN (CAN)
タイトル:ライヴ・イン・シュトゥットガルト 1975 (LIVE IN STUTTGART 1975)
発売日:2021年5月28日(金) / 2枚組CD
品番:TRCP-291~293 / JAN: 4571260591011
定価:2,700円(税抜)
海外ライナーノーツ訳 / 解説: 野田努(ele-king)
-Tracklist-
CD-1
1. Stuttgart 75 Eins
2. Stuttgart 75 Zwei
3. Stuttgart 75 Drei
CD-2
1. Stuttgart 75 Vier
2. Stuttgart 75 Fünf
[Pre-Order]
https://smarturl.it/CAN_Live
■プロフィール
CANはドイツのケルンで結成、1969年にデビュー・アルバムを発売。
20世紀のコンテンポラリーな音楽現象を全部一緒にしたらどうなるのか。現代音楽家の巨匠シュトックハウゼンの元で学んだイルミン・シュミットとホルガー・シューカイ、そしてジャズ・ドラマーのヤキ・リーベツァイト、ロック・ギタリストのミヒャエル・カローリの4人が中心となって創り出された革新的な作品の数々は、その後に起こったパンク、オルタナティヴ、エレクトロニックといったほぼ全ての音楽ムーヴメントに今なお大きな影響を与え続けている。ダモ鈴木は、ヴォーカリストとしてバンドの黄金期に大いに貢献した。2020年に全カタログの再発を行い大きな反響を呼んだ。2021年5月、ライヴ盤シリーズ第一弾『ライヴ・イン・シュトゥットガルト 1975』を発売。
https://www.mute.com/
https://www.spoonrecords.com/
https://www.irminschmidt.com/
https://www.gormenghastopera.com/
特集:ハイプじゃないんだ──日本ラップの現状レポート
巻頭ロング・インタヴュー:ISSUGI
シーンの現在を知るための大カタログ
曲50+アルバム50
⇒すぐ聴ける! 曲紹介はQRコード付き
インタヴュー:
ralph × Double Clapperz
NENE(ゆるふわギャング)
Seiho
Kamui
あっこゴリラ
田我流
ほか、磯部涼と二木信による対談、荘子it(Dos Monos)によるコラムなど盛りだくさん。
たんなる流行を超えた先にある「音楽」としてのヒップホップ、
そのサウンドの深まりと拡がりを探求!
編集協力:二木信
アート・ディレクション&デザイン:鈴木聖
表紙写真:堀哲平
contents
巻頭ロング・インタヴュー:ISSUGI
ISSUGI selected discography (大前至)
〈Dogear〉15周年──その功績を振り返る (大前至)
対談:磯部涼 × 二木信──日本のラップ・ミュージック、ここ5年の変遷
インタヴュー
ralph × Double Clapperz
NENE
Seiho
Kamui
あっこゴリラ
田我流
必聴ジャパニーズ・ラップ/ヒップホップ大カタログ
・曲50選
・アルバム50選
(二木信 / 市川タツキ、韻踏み夫、上神彰子、荏開津広、小林拓音、つやちゃん、272、MINORI、ヨシダアカネ、吉田雅史)
コラム
ギターの速弾きコンテストと音楽は違う (宮崎敬太)
荘子itが好きな日本のヒップホップ3選 (荘子it)
〈音響〉をディグするビート・アルチザンたち (吉田雅史)
ヒップホップと即興音楽シーンの交点 (細田成嗣)
リアルとフィクションのはざまで (小林拓音)
其処・個々に拡散するフェミニズム (水越真紀)
ストリーミング時代におけるDJミックスの楽しみ方 (上神彰子)
ヴィジュアルの変化──オートチューンとマンブルの果てに (つやちゃん)
The Catcher in the Suicide Country (泉智)
「インディラップ」的視点から聴く日本のヒップホップ (Genaktion)
【オンラインにてお買い求めいただける店舗一覧】
◆amazon
◆TSUTAYAオンライン
◆Rakuten ブックス
◆7net(セブンネットショッピング)
◆ヨドバシ・ドット・コム
◆HMV
◆TOWER RECORDS
◆disk union
◆JET SET
◆紀伊國屋書店
◆honto
◆e-hon
◆Honya Club
◆mibon本の通販(未来屋書店)
【P-VINE OFFICIAL SHOP】
◆SPECIAL DELIVERY
【全国実店舗の在庫状況】
◆紀伊國屋書店
◆三省堂書店
◆丸善/ジュンク堂書店/文教堂/戸田書店/啓林堂書店/ブックスモア
◆旭屋書店
◆有隣堂
- - - - - - -
お詫びと訂正
フライング・ロータス史上、もっともまとまりのある作品──。言われてみればたしかにそうかもしれない。とくに最新オリジナル・アルバムの『Flamagra』が、あまりに多くの要素をぽいぽい詰めこんだ鍋のような作品だっただけに、この『Yasuke』のサウンドトラックを聴いているとそう感じる。
本人が「自分自身の作品」だと主張しているように、今回のサントラはこれまでの彼のオリジナル・アルバムに連なる作品として聴くことができる。サウンド面での変化は、ヴァンゲリスに触発されたというアナログ・シンセの活用、和太鼓や拍子木のごとき打楽器とアフリカン・パーカッションとの並存、部分的に顔をのぞかせる東洋的な旋律の3点に要約することができよう。いくつかの曲においてトラップが披露されているのも感慨深い。そこには、「これまでだってトラップをやろうと思えば余裕でできたんだぜ、でも流行ってることをやってもしかたないだろ」という、00年代に完全に独自の音楽を生み出したプロデューサーの、力強い矜持が感じられる。さらに、ちょいちょいセンティメンタルなムードの曲も用意されていて、心地いいインスト・ヒップホップを求める向きにもおすすめだ。
他方で──当たりまえだが──これはアニメを愛するひとりのオタク(最近は『呪術廻戦』に夢中のようだ)が手がけた、アニメのサントラでもある。その観点で捉えてみた場合、これほどつくり手の個性がにじみでたサントラというのも、なかなかお目にかかれないのではなかろうか(少なくとも、日本のアニメのサントラでこんな音の鳴りは出てこないだろう)。かつてケンドリック・ラマー『To Pimp A Butterfly』に提供されたトラックがそうだったように、フライング・ロータスの生みだすサウンドは、べつの文脈に放りこまれたときにより一層その特異さを際立たせ、輝かせる。
作家性を失わず、しかしどんどん柔軟になっていくフライング・ロータス。これはアニメ・サントラであると同時に、ひとりの独創的な音楽家による新たな挑戦の、ドキュメントでもあるのだ。
※補足。実際のサムライは長らく支配層であり人びとを抑圧する側だった。いま生きている日本人はほとんどが農民の子孫だろう。念のため。(7月1日追記:アカデミックな場にいたコード9でさえ “9 Samurai” という曲をつくったことがあるくらいなので、フライローだけの問題ではないのだけれど……いやはや、海外におけるサムライへのポジティヴな評価は根が深い……)
このプロジェクトも「自分自身の作品」として扱った。まとまりのあるプロジェクトという感じがするし、今作で自分がとても気に入っているのもその点だね。自分の他のアルバムと較べても、この作品はもっともまとまりがある気がする。
■ここ1年は世界的に大変な時期でしたが、どう過ごしていましたか? 精神的に参ったりしませんでしたか?
FL:状況を考えれば、俺はかなりうまくやれてきたね。うん、これまでのところOKだったと思う。取り組めるクリエイティヴな仕事があったことを非常に感謝していたし、この間にキャッチアップできた良い作品などもあり、そのおかげで気をまぎらわせることもできたから。
■今回スコアを書くうえで参考にした、あるいは影響を受けたスコア~サウンドトラックはありますか?
FL:ああ、インスパイアされたものは多い。でも今回は、ヴァンゲリス的なシンセサイザーへのアプローチを用いて何かやってみようとトライする、そのアイディアが非常に気に入ってね。映画でシンセサイザーを使う、という。そのアイディアにとてもインスピレイションを掻き立てられることになった。どうしてそうなったのかは自分でもわからないけれども、シンセサイザーとそれをミックスすることに惚れ込んでしまったし、そういうことをやるのにパーフェクトなプロジェクトだった。
■今回、ある程度は先に映像がある状態で音をつくっていったのですか? それとも映像はまったくない状態で?
FL:その両方をやった。映像を観ることが可能だったときもあれば、番組のもつフィーリングを自分なりに解釈し、そのフィーリングにもとづいて音楽をクリエイトしただけという場合もあった。ある場面を観て、俺は「この場面の持つ意味合いは? ここでのフィーリングはなんだろう?」と考え、そこで映像をいったん消し、なにかをクリエイトしていったり。うん、双方のプロセスを用いたね。一方で、大きな闘いや戦闘場面といったがらっと異なる趣きの場面もあったから、ふたつの映画をやろうとしたというか。それにいくつかのシーンでは、まず音楽をつくってみることもやった。というのも監督のラショーン(・トーマス)、彼はたまに、曲に対してこちらとは異なるヴィジョンを持つこともあったから。たとえば俺が何かクリエイトして、それを俺は予想もしていなかった場面で彼が使う、とか。それでこちらも「フム、これは興味深い」と思ったり(苦笑)。
■監督に自由に選んでもらうために、余分にマテリアルをつくりもしたんですね。
FL:そういうこと。時間をかけたし、「この作品にだけ専念する」と決めた。サウンドからなにから、自分がいまクリエイトしているのはこの作品向けのものであって、うまく合うものもあれば、そうはいかないものもあるだろう、と。
■ご自身で映画を監督なさったこともありますし、映画に限らず様々な視覚メディア/視覚アートに関する仕事をしてきました。音楽言語だけではなくヴィジュアル言語も理解しているわけで、ラショーン監督もあなたとは仕事しやすかったんじゃないでしょうか。
FL:ああ、その面は助けになるだろうね。それに加えて、俺はこのプロジェクトに最初期から関与していたぶん作品のすべてをすでに知っていたわけで、そこも大いに役に立った。
■製作総指揮としても参加し、キャラクターの造型やストーリー面でも関わったそうですね。まさに一からこの作品と付き合ってきた、と。
FL:ああ、そうだね。
■これまでのフライング・ロータス作品と今回の最大の違いはパーカッションにあると思います。和太鼓やアフリカン・ドラムを積極的に使用したのは、それが『YASUKE』の映像や物語とマッチしそうだから、という理由だけでしょうか? まあ、日本にいるアフリカ人という設定なので、そうなって当然かもしれませんが……
FL:(苦笑)その通り。
■とはいえ、なにか他に理由はあるでしょうか?
FL:そうだな……んー、自分にもわからない。ただとにかく、この番組にはやはり(メインになるのはシンセであっても)日本のサウンドを含めなくてはならないな、そう感じただけであって。なにかしら、非常に日本的なものをね。かといってまた、俺は日本音楽のパロディっぽい印象を与えるもの、そういうことはやりたくはなかったというか?
■はい、わかります。
FL:日本音楽を侮辱しているように映ることは避けたかった。というわけでとにかく、自分からすれば敬意に満ちていて、ユニークで、と同時に「俺」らしくもある、そういうなにかをクリエイトしたかったんだ。
■実際に聴くまでは、「もしかしたら海外作品でよくある、日本の異国趣味を感じさせるものになるかもしれない?」と思ったこともあったんですが、さすがあなただけあって、日本のカルチャーや伝統へのリスペクトのある内容です。ありがとうございます。
FL:フフフッ!
■先ほどヴァンゲリスの名前を挙げていたように、上モノのシンセもオールドな響きがあり、これまでのフライング・ロータス作品とはだいぶ異なっています。
FL:ああ、80年代のシンセだ。
■アナログ・シンセですよね?
FL:そう。大好きだね。うん、あれは本当に好きだ。
■今回この音色を用いようと思ったのはなぜ? 1980年代のサウンドを16世紀に合わせようとしたのはなぜでしょう?
FL:とにかくあのサウンドにはなにかがあるし……これまで、あのサウンドがアニメで使われたのを俺は耳にしたことがなくてね。アニメ界においてなにか新しいことにトライしたいと本当に思っていたし、アニメ作品のなかでも強く記憶に残る、そういうサウンドをぜひクリエイトしたいと思っていた。俺たちが過去にもう聴いたことのあるものとは異なるなにかをね。というわけで、この音楽をユニーク、かつ俺にとって正直なものにするのに、自分にできることはなんだろう? と考えたんだ。シンセサイザーにものすごくインスパイアされていたし、その面と、自分が観ているもの(=アニメ)を感じさせるもの、それらすべてをどううまく機能させればいいだろうか、と。
■アニメは残念ながら全話観ていないのですが、このサントラは音楽作品として独立して聴けると思っています。
FL:ああ、それはグレイト! そう言ってもらえて嬉しいよ、ありがとう。
■いくつかの曲でトラップのビートが用いられていることに驚きました。あなたはトラップの潮流からは距離を置いていると思っていたのですが、かならずしもそうではなかったのですね?
FL:(笑)大好きだよ! 好きだし、自分でもつくる。あの手のビートだってつくるし、ただ、あまり世に出していないだけ。まあたしかに、誰もがやっていることをやるのは安易だ、みたいに感じることもあるけれども、実際、あのサウンドはときに戦闘シークエンスでとても活きるんだ。うん、あれをやるのはクールだよ。それに、キッズはあのサウンドがお気に入りだし(笑)。
■エキサイティングで盛り上がるビートですし。
FL:ああ。やっぱり、なにもかもダウンテンポで……というわけにはいかないんじゃないかな。
■(笑)たしかに。
FL:アクション・シーンなんかは特にね。でも、その手の場面には♪ダンダンダンダン・ダンダンダン・ダッ!(と、スリル感を増す激しいタイプのビートを口真似する)という音楽がよく使われるけれども、ああいうのは俺にはとても退屈に思えたし、もっと違うものを書きたかった。
[[SplitPage]]これまで戦争のための音楽をつくることを考えたことは一度もなかったんだよ、俺は戦争を嫌悪しているから。けれども今回は戦争とはどんなふうに聞こえるのか? と考えることを自分自身に強いることになった。
■自身のオリジナル・アルバムをつくるときとの最大の違い、苦労はなんでしたか?
FL:まあ、俺は同じものは二度つくらないわけで。でも、このサントラでの仕事について言えば……戦争をつくり出さなくてはならなかったんだよな。戦争のサウンドと音楽をもっと、もっと、とクリエイトしていった。ひとつのシリーズのなかに戦闘シーンが3回あるからね。これまで、戦争のための音楽をつくることを考えたことは一度もなかったんだよ、俺は戦争を嫌悪しているから。けれども今回は、戦争とはどんなふうに聞こえるのか? と考えることを自分自身に強いることになったし、俺のヴァージョンの戦争とはどんなサウンドだろう? と考えた。で、とにかくそうやって自らの能力とこれまでやってきたことをストレッチしさらに伸ばすのは、非常に、非常に楽しく、かつ試されもするチャレンジだった。
■想像力でギャップを埋めていかなくてはならないわけですね。平和主義者であるあなたが、フィクションの世界では戦士や人殺しをイメージしなくてはならない、と。
FL:そう。ただ、ありがたいことに、こちらはヴィデオでイメージを観ることができたから、「なるほど、いま自分の目に映っているものを音楽でサポートしさえすればいいんだ」と思えた。というわけで、いったん自分の使おうとするサウンドと音のパレットとを見極めたら、ギャップを想像力で埋めていく作業は非常に楽になった、みたいな。それでも、戦争絡みの音楽をやるのはとても難しかった。なにせ俺は、ああいうことはいっさい考えないから(笑)。
■その他に、なにか苦労なさった点は?
FL:スケジュールだな。スケジュール調整がとてもむずかしかった。うん、スケジュールの面はとても大変だった。というのも、自分の作品をつくるとき、締め切りはないんだ。スケジュールは存在しない、という。けれども映画やテレビの仕事の場合はスケジュールが決まっていて納期までに仕上げなくてはならないし、締め切りも非常に厳しい。その意味でむずかしかったとはいえ、おかげで自分のアイディアに確信をもち、作品をどんどん仕上げていくのを自分に強いることができた。
■時間のせいでもっと断定的になり「よし、これで完成」と決断しやすくなった、と。
FL:そう。うだうだ考えているわけにはいかない、とにかくやるのみ、とね。
■映画やアニメは音楽に較べて関わるスタッフの数も桁違いですし、タイトなんでしょうね。
FL:ああ。クレイジーなことになる。
■逆に、これまでの自身のオリジナル作品と共通しているもの、連続しているものはなんだと思いますか?
FL:このアルバムも自分のやってきた他の作品と同様、アルバムとして流れがあるように曲順をアレンジするようにした。単に番組から派生したものではなく、このプロジェクトも「自分自身の作品」として扱った。まとまりのあるプロジェクトという感じがするし、今作で自分がとても気に入っているのもその点だね。自分の他のアルバムと較べても、この作品はもっともまとまりがある気がする。だから、もっとも……ステイトメントというか、アイディアがもっとも凝縮されている作品という感触がある。要するに、「これはサムライ・アルバムだ」というふうに(笑)。
■ある意味、他の作品よりも定義しやすい、と。
FL:イエス。対して以前の俺がやっていたのは、「こういう感じのもの」、「ああいう感じのもの」という具合にあれこれ持ってきて、それらを混ぜ合わせることでこの、大きなピースというか、ひとつのコラージュをつくっていたんじゃないかと。ところがある意味今作は、まとまりのあるひとつの大きなピース、という感じがある。ひとつに統合されたアイディア、というね。
■1曲1曲が短く収録曲数が多い、というのはサウンドトラックの特徴ですが、奇しくもこれまでのあなたの作品もそうでした。
FL:(苦笑)その通りだ。
■これまでもどこか架空のサウンドトラックをつくるような意識があったりしたのでしょうか?
FL:ああ、いつもそうだった。いつもそう。つねに自分の作品にテーマやヴィジョンを持たせようしてきたし、そうやって音楽をマインドのなかでたどる旅路に感じられるようにしてきた。けれども、いま感じているのは、今後、自分が通例的なアルバムづくりに戻るのはむずかしくなりそうだな、ということで。自分は大きく成長したし、自分の限界を押し広げようと本当に努力もしたわけで、その進みを維持していかなくてはならない、そう思うから。
■たとえば映画『ブラックパンサー』は、当時のトランプ政権やBLMなど、時代や社会の状況とリンクする側面があったと思うのですが、『YASUKE』にもそのような部分があると思いますか?
FL:とても多くある。社会/時代に対する非常に多くのコメンタリーが含まれている。あの番組が明かし開いて見せるものは、じつに多くある。うん、いくらでもある。
■『YASUKE』という作品のもっとも重要なテーマあるいはメッセージは、なんだと言えるでしょうか。ラショーン監督の作品とはいえあなたも大きく関わっていますし、「このひとつ」とは選びにくいかもしれませんが、それはなんだとあなた自身は思いますか?
FL:フム……『YASUKE』を通じて俺が見つけたもっとも重要なメッセージ、それは「正しいことをやれば、われわれみんながヒーローになれる」ということだね。正しいことをやること、それさえちゃんとやればヒーローになれる。だから、ときに人びとは、だれかの表面だけを見てその人間を判断し、その人の内面/リアリティにまで目が届かないことだってある。けれども、それは無意味だし気にすることはない。とにかく自分自身をつらぬき、正しいことをやっていく、と。言葉より、行動そのもののほうが大きくものを言うからね。『YASUKE』で俺が好きなのもそこだと思う。見た目が他とは違うというだけの理由で誰かが彼をおとしめることを彼はけっして許さないし、彼は自分が抜きん出ていること、ほかをしのぐ存在であることをつねに証明していく。言葉ではなく、ひたすら行動を通じてね。
■だからYASUKEはサムライなのですね。
FL:フフフフフッ!

『YASUKE』を通じて俺が見つけたもっとも重要なメッセージ、それは「正しいことをやれば、われわれみんながヒーローになれる」ということだね。
■ゲストについて。サンダーキャットやニッキ・ランダは長年のおなじみのコラボレイターですが、今作唯一のラップ曲でデンゼル・カリーを起用したのはなぜ? 彼は『Flamagra』にも参加していましたが、そのときのコラボが他のラッパー以上に良かったのでしょうか?
FL:それもあったし、彼は友人でよく知っているし、しかも俺の近所に住んでいる(笑)。彼もアニメが大好きだし、YASUKEという人物のことも知っていた。だからもう俺からすれば、ラップしてくれと彼に頼まないほうがおかしいだろう、みたいな。
■(笑)なるほど。
FL:俺にとっては彼もこの一部だし、彼のあのラップは俺も大好きなんだ。というのもあれはたんなるラップ曲ではなくて、YASUKEのヒストリーを語っている。キャラクターの物語をラップで語っているということだし、そういう曲をアルバムに入れられたのはとてもクールだった。
■ちなみに、日本のラップ/ヒップホップで好きな作品や注目しているアーティストはいますか? ラッパーでもビートメイカー、プロデューサーでも。
FL:うん。あの子は……彼の名前はHakushi Hasegawa(長谷川白紙)、だな。ブリリアントなミュージシャンだ。彼の音楽は大好きだ。彼は新人で、キーボードの弾き語りをやるんだけど、非常にトリッピーで、めちゃいいんだ。チェックしてみて。
■『YASUKE』の制作会社がMAPPAなのは渡辺信一郎さんの紹介?
FL:いいや、それはないね。ノー。俺はただラショーンと一緒に日本に行き、彼らとミーティングを持ち、そこで彼らも「イエス」と答えてくれた、と。
■すでに存在している映画やアニメで、できることなら自分がスコアを書きたかったと思った作品はありますか?
FL:それはしょっちゅう感じるよ、しょっちゅうね。テレビ版の『ウォッチメン』、あれの音楽を自分がやれていたら……と思う。
■未見ですが、出来はどうなんでしょう?
FL:俺は気に入った。ただ、音楽を自分が担当していれば、すばらしいことをやれていただろうなと思う。その他で、好きな作品で自分が音楽をやれたらよかったのに、と本当に思うものといったら……? ああ、現在進行中の映画『ブレイド』の新作。あれは、ぜひやりたい。
■おお! ウェズリー(・スナイプス)が主演なんですか?
FL:(苦笑)いやいや、違うよ。
■違う役者なんですね。
FL:ああ。あれは、あと何年かかかるだろうな(訳注:『ブレイド』はMCU内でリブートされる予定で、ブレイド役はマハーシャラ・アリが引き継ぐ予定)。
■『ブレイド』は好きなので、楽しみに待ちます。
FL:うん、『ブレイド』は最高。
■亡くなったMFドゥームとはEPを制作していたのですよね。それが世に出る可能性はあるのでしょうか?
FL:そう祈っている。そうだといいよね。あれに関してはなんの連絡も受けていないから、俺にはなんとも言いにくい。ただ、出たらとても嬉しいね。
■音源はご遺族が管理されている、ということ?
FL:そのとおり。できあがった音源を俺自身聴いたことはないんだけど、俺が送った音源を使って何曲かやったと彼が話してくれたことがあったんだ。でも、どうなるかは俺にもわからない。
■というわけで、質問は以上です。お時間いただき、ありがとうございました。
FL:こちらこそ、取材してくれて、本当にありがとう。
■お元気で。
FL:きみもね。
Netflixオリジナルアニメシリーズ『Yasuke -ヤスケ-』
4/29(木)よりNetflixにて全世界配信中
ブラック・ミディの存在は、2018年からロンドンより漏れ伝わってきていたものの、情報は少ないし、レコードも聴けないし、彼らを知るすべといえば、おもにルー・スミス(Lou Smith)が撮影したウィンドミルでのライヴ映像だった。そして、2019年、2つのシングル(アルバムには収録されていないけれど、ラフ・トレードからのファースト・シングル「Crow’s Perch」にはほんとうに興奮した)とデビュー・アルバム『Schlagenheim』で、彼らはじぶんたちがどんなバンドなのかを、ようやくはっきりと示した。聴き手の前にぬっと現れた、奇妙でいびつなかたちをしたその音楽は、まるでキング・クリムゾンが1969年が1984年までの間にリリースしたレコードをぎゅっとひとまとめに固形化したような、あるいはジョン・ゾーンが指揮を執ってポップ・グループとシェラックがいちどきに演奏しているような、とにかく強烈なものだった。つまり、破格の存在感を放っていたのだ。
ブラック・ミディの演奏は常に性急で、なにかから追われているかのように切迫した感覚があるのがよかった。それでいて、どんなポスト・パンク・バンドよりもうまく、タイトで、おまけに自由に伸び縮みするプレイを聴かせていた(その様子を知るには、彼らを一躍有名にしたKEXPでのパフォーマンスを観るのが手っ取り早い)。それに、セッションがベースにある彼らのライブとレコードには、ロック・コンボで演奏するよろこびが宿っていた。ブラック・ミディの音楽を聴いていると、4人の人間が手足と喉と4つの楽器を使って、音によるコミュニケーションをしている様子がありありと伝わってくる。だからこそ、演奏のなかに、なんとなく予感や余白、可能性が残されているように感じられるところもよかった。
ただ、ブラック・ミディの4人は、居心地のよいところに安住せずに、定型化や様式化を忌避して、早くも新しい表現を模索している。というのも、このセカンド・アルバム『Cavalcade』は、セッションではなくコンポジションとアレンジメントによる孤独な作業を深く追求して、それをバンドに持ち寄って演奏したことで完成された。ギタリストのマット・クワシニエフスキー・ケルヴィンはメンタル・ヘルスの問題によって現在バンドから離れているため、作曲のみの参加に留まるが、サポート・メンバーのサクソフォニストであるカイディ・アキニビ(Kaidi Akinnibi)とキーボーディストのセス・エヴァンズ(Seth Evans)らの助力によって、音はかなり厚みを増した。そのあたりの内情やプロセスは、次のジョーディ・グリープへのインタヴューでたっぷりと語られている。とくに、クラシカル・ミュージックについての情熱的な語りには、『Cavalcade』が纏っているエレガンスの出どころが見えてくるんじゃないだろうか。
2019年に日本でインタヴューした時のジョーディ・グリープは、移動や取材が重なっていたためか、ちょっとナーバスなムードを醸し出していた(そのときの記事は、インディペンデント・ファッション・マガジン『STUDY7』で読める)。でも、今回はかなりリラックスして話してくれたみたいだ。この見慣れない「隊列」がどうやって組まれ、どこからやってきて、さらに次(サード・アルバム)はどこへ向かって行くのか。『Cavalcade』がどうやらバンドにとって通過点でしかないことが、さまざまな固有名詞やエピソードに彩られたジョーディの語りから伝わってくる。
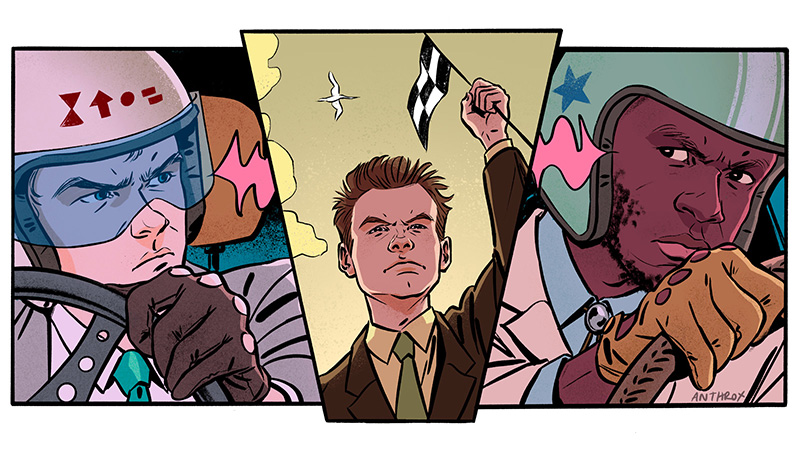
子供のころからポピュラー・ミュージック、ロック、ジャズとかに加えて、常にクラシックを聴いていた。だから、自分の音楽にもクラシック音楽からのインスピレーションをいつも取り入れるようにしている。
■以前インタヴューした際、ジョーディさんがゲームの『ギターヒーロー』で演奏を学んだと楽しそうに語っていたことをよく覚えています。『Stereogum』のインタヴューでは、インスパイアされたものとして『タンタンの冒険』を挙げていましたが、そういった子どものころに触れたもので現在もバンドに活かされているものはありますか?
ジョーディ・グリープ(以下、GG):子どものころは『ルーニー・テューンズ』や『トムとジェリー』が大好きで、そういうアニメをたくさん観ていたよ。番組で流れるドタバタ感のある音楽が大好きだったんだ。ブラック・ミディの音楽をやるときも、それに似たような、直感的な衝撃やエネルギーを音楽に持たせたいと思っている。
それから映画もたくさん観ていたね。(アルフレッド・)ヒッチコックの映画とか、ウディ・アレンの映画とか。かなり前に、そのあたりの映画をたくさん観ていた。特に、『ウディ・アレンのバナナ』(1971)や『スリーパー』(1973)といったウディ・アレンの初期の作品なんかをね。
■そういう経験は、いまも音楽に反映されていますか?
GG:そう思うよ。俺たちが長年好きだったもののすべてが、いまの音楽に反映されていると思う。

■新作『Cavalcade』では、インプロビゼーションやジャム・セッションで作曲された前作『Schlagenheim』とは対照的に、メロディやコード・プログレッションの妙など、コンポジションに重きが置かれているそうですね。作曲の段階ではメンバー個々の孤独な作業になるのでしょうか? それとも、作曲中にも意見交換をするのでしょうか?
GG:どちらのパターンもあるけれど、最近多いのは、個々で曲をすべて完成させるほうだね。少なくとも、俺は曲を全部完成させてから他のメンバーに聴いてもらうほうを好む。その理由は、自分の曲を自分でコントロールしたいからかもしれないし、完璧主義だからなのかもしれない。それに、そのほうが曲に継続性があるんだ。曲の終盤が、曲の序盤と合っていなかったり、曲のある部分が残りの部分と調和したりしていなかったら、よくないだろう? でも、曲の、音楽の部分だけを完成させて、それを他のメンバーに紹介して、他のメンバーが歌詞を書いたり、ヴォーカルを加えたりするという共同作業はあるよ。
■なるほど。では前作と比べて、もっとも対照的な作りかたになった曲は?
GG:“Marlene Dietrich”と“Hogwash and Balderdash”とアルバム最後の曲“Ascending Forth”、それからアルバムには収録されていない“Despair”(国内盤にボーナス・トラックとして収録)という曲は、俺が自宅で作曲したから全部俺が作って、「これができた曲だよ」とみんなに紹介したものだよ。“Diamond Stuff”も同様に、(ベーシスト、ボーカリストの)キャメロン(・ピクトン)がすべて自宅で作った曲だ。だからいま挙げた曲はすべて、ファースト・アルバムの大部分の曲とはまったく対照的な作り方になっているね。
■リズムやグルーヴに対する考えかたは変化しましたか?
GG:とくに変化していないと思うけど、今回作った曲の方が複雑になっているし、従来の構造に倣って作られているからリズム・セクションに関してもやりがいがあったんじゃないかな。つまり、(ドラマーの)モーガン(・シンプソン)が曲を聴いて、どういうリズムを加えるのかを考える際に、今回のアルバムの曲には様々な要素が既にあったから、いろいろな可能性を感じられたと思う。おもしろく聴こえるような曲にするために、その曲の流れに合わせてクレイジーなおもしろいリズムを加えたというわけではなくて、今回の曲にはリズムが既に存在していた。だから、そこにあった自然のリズムを活かして、それを前面に出していった、という感じ。
■アルバムに全面的に参加しているサクソフォニストのカイディ・アキニビ、キーボーディストのセス・エヴァンズについて、どんなミュージシャンなのか教えてください。
GG:カイディと俺たちは同じ学校(ブリット・スクール)だったからもう8年の付き合いになるんだ。セスはロンドンでライブをやっているときに知り合った。俺たちが当時やっていた他のバンドでセスも一緒にやっていたんだよ。
俺とカイディは、もう何年もいろいろな音楽を一緒にやってきている。だから、サックス・プレイヤーを入れようとなったときに、カイディに頼むのは自然な選択肢だった。カイディのいいところは、熟練した演奏者であると同時に、俺たちがやろうとしているどんな種類の音楽に対してもオープンだし、クレイジーな音楽に対してもオープンだというところだ。彼もクレイジーな音楽を色々と聴いているからね。一緒に音楽をやるには最高だよ。
キーボード・プレイヤーのセスも、演奏者として素晴らしい。あまりやり過ぎないというか、派手すぎないし、そういうすごい演奏ももちろんできるんだけど、曲に最適な演奏をしてくれる。
カイディもセスも俺たちの仲のいい友だちなんだ。みんなで楽しく作業ができるし、カイディとセスの相性も良い。だから最初は去年のツアーに参加してもらって、ライブに出てもらおうという話になった。それがすごくいい結果になったから、アルバムに参加してもらうのも自然な流れだった。すごく楽しかったよ。今年の秋からはじまるツアーにも彼らに参加してもらおうと思っている。それに、サード・アルバムにもね。
■へえ! サード・アルバム、楽しみです。今回はアレンジも構築的になっていて、とくにギター・ロックと管弦楽の融合が印象的でした。管弦楽やパーカッションなどのライブ・インストゥルメントによって音楽性を拡張した理由は?
GG:ブラック・ミディ関連の音楽以外だと俺はほとんどクラシック音楽しか聴かないんだ。子供のころからポピュラー・ミュージック、ロック、ジャズとかに加えて、常にクラシックを聴いていた。だから、自分の音楽にもクラシック音楽からのインスピレーションをいつも取り入れるようにしている。クラシック音楽という領域のなかから、自分が好きなものを選んで活用しているんだ。
クラシック音楽やオーケストラ音楽からインスピレーションを得るなんてレベルが高過ぎて無理だろう、それは思い上がりだ、高望みしている、という考えもあるけれど、俺に言わせれば、人生は長くないし、自分が情熱を感じている大好きな音楽があって、それを自分の音楽に取り入れたいなら、そうすればいい。時間は限られている。明日死ぬかもしれないんだぜ? だから、そういう音楽の影響を今回のアルバムにも取り入れた。
アルバムの曲にはクラシック音楽の影響が入っているものがいくつかあって、クラシック音楽に使われているテクニックは、ほとんどそのままブラック・ミディの音楽にも使えるんだ。俺が好きなクラシック音楽と同じくらいにすばらしくはできないかもしれないけど(笑)。インストゥルメンテーションにおいてクラシックで使われているテクニックを今回のアルバムの曲にも使ってみたんだ。
■たしかに、クラシカルで荘厳な音を構築しているアプローチだと思いました。ライヴ・インストゥルメントではなく、エレクトロニクスを取り入れるアプローチも考えていますか?
GG:可能性としてはあるよ。俺はあまりエレクトロニクスには精通していなくて、そういうのはキャメロンが全部やっている。キャメロンはDJもやっていて、曲のリミックスもやっているんだ。だから、キャメロンはすごいよ。今後はいつか、そういうアプローチで曲作りをしたり、ブラック・ミディの音楽を作っていったりすると思うよ。
[[SplitPage]]アルバムをもう1枚作るのには、じゅうぶんな数の曲ができている。2時間分の音楽があるよ。この数か月でサード・アルバムのレコーディングができると思う。そして来年の3月ごろまでにはリリースできていると嬉しいね。
■話は戻りますが、弦楽器のアレンジメントについて教えてください。“John L”などでのストリングスは、どこか不協和な響きを持っています。こういった緊張感のある響かせかた、アレンジのしかたは、どのようにして生まれたのでしょうか?
GG:“John L”はフリースタイルでできたんだ。ロンドンのアーティストで俺たちの友人でもあるジャースキン・フェンドリクス(Jerskin Fendrix)を呼んで、“John L”の基本的なリフや曲のパートを教えたんだけど、あとは彼が自由にバイオリンを演奏しながら、一緒に曲を作っていった。“Ascending Forth”のストリングスは、ジャースキンがヴァイオリンを演奏して、別の友人のブロッサム(・カルダロン、Blossom Caldarone)がチェロを演奏したんだけど、曲のなかでストリングスを入れたいところでトラックを止めて、俺がピアノでそのパートを弾いて、「じゃあ、これを演奏してくれ」と彼らに頼んで、彼らが演奏するのを録音した。そしてまた別のセクションにトラックを進めて停止させて、「次はこれを演奏してくれ」と俺がピアノで指示を出す……という作業をずっとやっていた。3時間くらいかかったよ。“Marlene Dietrich”のチェロのアレンジメントも俺が作曲をして、ブロッサムに演奏してもらった。
■それに関連して、楽器の音の美しいハーモニーとノイジーに重なるタイミングと両方が共存している様子が今回のアルバムは特に印象的でした。作曲やアレンジ、演奏における音の調和と不協和について、どんなことを考えていますか?
GG:調和と不協和は対になっているというか、どちらか一方が欠けても成り立たないと思う。不協和ばかりだと意味のない不協和になってしまうし、すべてが調和していたらベタな感傷主義になってしまう。だから、常に調和と不協和の両方が必要だ。不協和の脅威があるからこそ、調和という息抜きがある。そういうところにおもしろみを感じるんだ。
俺たちは、常に緊張感がギリギリのところで漂っている音楽を作りたい。でも、そういう緊張感があるからこそ、その後に来る脱力感や穏やかな感じが引き立つ。だから、その両方が必要なんだ。
■そういった点では、ブラック・ミディの緊張感やダイナミック感はすばらしいですよね! すごく刺激的で、ユニークな音楽だと思います。
GG:ありがとう!
■さきほど言及した『Stereogum』のインタヴューでは、イーゴリ・ストラヴィンスキーの“カンタータ”とオリヴィエ・メシアンのオペラ“アッシジの聖フランチェスコ”を挙げていましたよね。そういったコンテンポラリーなクラシカル・ミュージックからは具体的にどんなインスピレーションを得られるのでしょうか?
GG:俺が10歳くらいのとき、地域の学校の生徒全員が行くというコンサートがあって、それに行ったんだ。子どもたちにクラシック音楽に興味を持ってもらおう、という学校の行事だ。それで、ロンドンにあるバービカン(・センター)というコンサート・ホールに行った。そのときの観客はみんな生徒だから子どもで、オーケストラは様々な作曲家による曲を10〜15曲くらい演奏していた。クラシックの歴史を学ぶ、みたいな感じで。それを聴いたときには衝撃を受けたよ。でも、そのときは学校の行事だったから、俺は「つまらねえ音楽だよな」なんて他の子どもたちと言いあっていたけど、内面では「なんてかっこいい音楽なんだ!」と思っていたんだ。そのコンサートで演奏されていた音楽は、すごくよかったよ。具体的なものは思い出せないけど、ひとつ覚えているのは、チャールズ・アイヴズの「答えのない質問」。これを聴いたとき、俺はこの曲はあんまり好きじゃないなと思ったけれど、どうして好きじゃないのかという具体的な理由を説明できなかった。でも、この音楽には、聴き続けていたいと思わせるなにかがあった。そういう体験をしたのは、それが初めてだったな。そういう感覚を自分の音楽でも喚起させたい、という気持ちがある。
ストラヴィンスキーに関しては、俺の父親と母親は色々な音楽を聴く人で、ストラヴィンスキーの音楽もよく聴いていた。ストラヴィンスキーは、『スター・ウォーズ』のような、クレイジーな映画音楽の祖先みたいなものだ。だから、そういう映画を観てきた人がストラヴィンスキーの音楽を聴いても、あまり異常なものや、異世界のもののように感じることがなく、自然に受け入れられる。それはリズムがベースになっているからなんだ。
俺が12歳か13歳のころ、学校の音楽の先生で、すごく好きな先生がいた。すごく親しくなって、昼休みにはよくその先生のクラスに行って、俺は彼と音楽の話を一緒にしていたんだ。その先生が学校を去っていったあと、別の先生が来た。この先生はかなり歳がいっている人で、昔ながらの伝統を好む人だった。誰も新しい先生のことが好きじゃなくて、俺も同じだった。こいつはイケてないし、おもしろくもないと思っていた。俺はその先生と1年くらい過ごして音楽について話したり、音楽の課題を一緒にやったりしていたから、じょじょにこの先生も悪くないな、と思いはじめていた。まだ彼のことは尊敬していなかったけどね。普通にいい付き合いはできていた。ある日、彼はストラヴィンスキーの“春の祭典”を聴かせてくれたんだ。そのときに俺は、先生がどれだけやばい人かに気づいた。先生は「この作品は史上最高の楽曲です」と言って、スピーカーから大音量でかけたんだ。俺は先生に向かって「はいはい、先生はおかしいよ」と言っていた。先生の前では平然を装っていたんだけど、内面では「これはまじでクレイジーな音楽だな!」と思っていたんだ。
■では、実際にはいい音楽だと思っていたんですね。
GG:まあね。でも先生には「そんな風に思う先生は変だよ。これは全然良い音楽じゃない」って言っていた。俺と先生は10分くらい曲を聴いていたんだけど、そのときに彼はこう言ったんだ。「この音楽を初めて聴く瞬間に戻れるなら、私は何だってしますよ」って。それには心を打たれたね。俺はいま、その瞬間を実際に体験していて、それを当然の権利のように感じていたから。俺はそのときは、「先生の言うことはでたらめで、あの老いぼれは馬鹿げている」と思っていて、その場はそれで終わったんだけど、“春の祭典”は常に俺の頭の片隅にあった。その6か月後くらいにまた聴いてみて、それ以来、何度も繰り返して聴いてみた。もう何年もそうやって聴いてきている。ストラヴィンスキーの音楽も全部聴いたし、バッハの音楽もたくさん聴いたし、メシアンの音楽も、ブラームスやベートーヴェンの音楽も聴いてきた。非常に楽しめる音楽だよ。
■クラシックから、それほどの影響を受けていたとは思いませんでした。話は変わりますが、今回のアルバムにおけるジョーディさんの歌について教えてください。ヴォーカリゼーションが以前よりもシアトリカルなふうに変化したように感じました。これは、「三人称のストーリーを重視した」という楽曲ごとのテーマから生じたものなのでしょうか?
GG:そうかもしれない。主な理由としては、俺が好きな音楽や歌手の多くが、おおげさだったり、度を超えた感じの歌いかたをしているからだと思う。でも、今回のアルバムの曲でヴォーカルを歌っているときはある特定の歌手を意識したり、まねたりしているという感じではなくて、ある特定の感情や風変わりな映画や演劇などをイメージしながら歌っていたんだ。確かに今回のアルバムでは全体的に名作のおおげさでドラマチックな、メロドラマに近い雰囲気を体現しようとした。マルセル・オフュルスの映画や、マイケル・パウエル&エメリック・プレスバーガーが監督した『赤い靴』みたいな。おおげさなドラマや、奇妙なくらいおおげさな感じ。あまりやりすぎてもだめだけど、ドラマティックさを体現することも必要だと思う。
最近の音楽を聴くと、おおげさにならないように、感情的になりすぎないようにと意識し過ぎている人ばかりだと思うんだ。まるで、そういう表現が意図的に禁止されてしまったかのように。すべては控えめにしないといけないかのように。それはそれでいいんだけど、俺はあのシアトリカルな感じも好きなんだ。だから、そういう表現方法をたまにはしても悪くないんじゃないかと思って。今回はやりすぎたかもしれないけど、どうだろう。サード・アルバムで、次はどうなるかな、というところだね。

■さきほどからサード・アルバムについて言及していますよね。どんな内容になるんですか?
GG:アルバムをもう1枚作るのには、じゅうぶんな数の曲ができている。2時間分の音楽があるよ。この数か月でサード・アルバムのレコーディングができると思う。そして来年の3月ごろまでにはリリースできていると嬉しいね。音楽制作は、音楽が完成していてもリリースまでに時間がかかるときもある。だからリリースのタイミングを遅らせることなく、なるべく早くリリースできたらいいと思っている。
■ものすごい創作意欲ですね。たのしみです。最後に、たびたび共演しているブラック・カントリー・ニュー・ロードについてお聞きしたいです。彼らの音楽について感じていること、彼らとブラック・ミディが共有していることと、あるいは両者の相違点について教えてください。
GG:ブラック・カントリー・ニュー・ロードはメンバーもみんないい奴ばかりだし、バンドとしても最高だ。演奏も素晴らしいし、ライヴも観ていて爽快感がある。音には重みが感じられるけど、繊細に感じるときもある。彼らの新曲の多くは、バンドの微妙なニュアンスが感じられるものになっているよ。演奏も上手だから、クリスマスの時期に彼らと共演できたのはとても楽しかった。
相違点については、これは彼らも同じことを言うと思うけれど、ブラック・ミディとブラック・カントリー・ニュー・ロードは、似たようなところからはじまったけれど、そこからちがう方向へと枝分かれしていった。彼らが最近作っている音楽は、ボブ・ディランに近い感じで、軽音楽というわけではないけれど、よりシンプルで、ひたむきな感じなんだ。それはそれでクールだと思うけど、ブラック・ミディがやるような音楽ではない。ブラック・カントリー、ニュー・ロードの音楽を聴くと、俺は「すごくいいね。俺たちだったら絶対にやらないけど」と思う。ブラック・カントリー・ニュー・ロードが俺たちの音楽を聴いても、「最高だね。俺たちはけっしてそういう音楽は作らないけど」と言うと思うよ。でもその状態が気に入っている。お互い、友好的なライバル関係で競争心もあるけれど、同じ領域・分野にいるわけではない。隣の芝生はいつも青い、ってことだよ。




