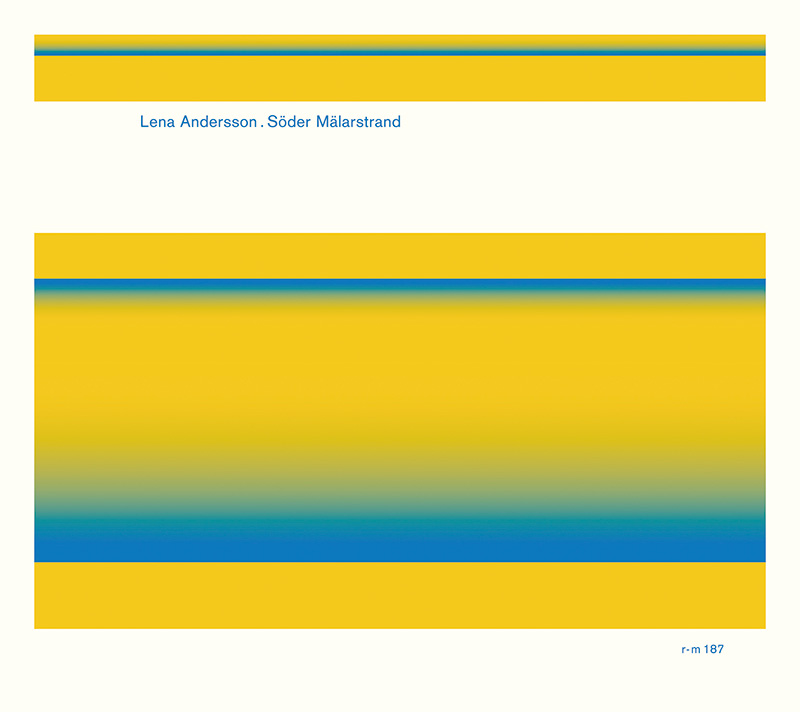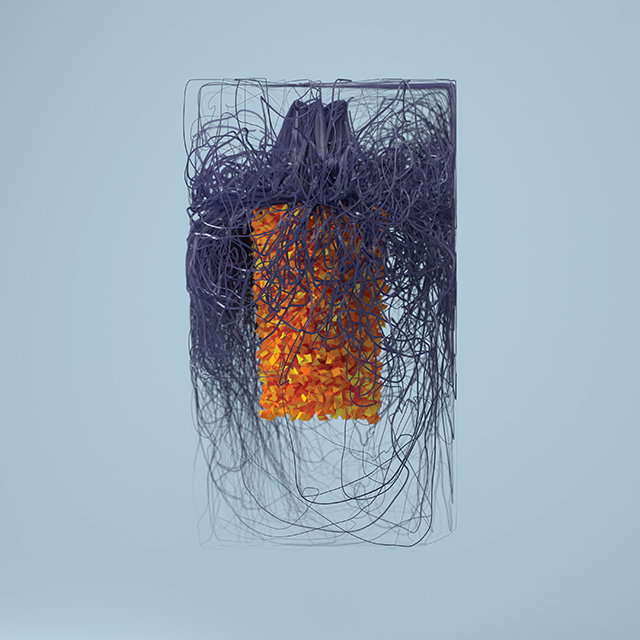日本のLaurent Garnierのファンの皆さんへ、
フランスのドキュメンタリー映画監督Gabin Rivoireは過去3年間世界中でLaurent Garnierをフォローし、Laurentのツアー人生を記録して来ました。
今日、何とFeaturistic Filmsは「珍しい」Kickstarterキャンペーンでドキュメンタリー映画『Laurent Garnier:Off the Record』を立ち上げ、今回のプロジェクトでLaurent Garnierコミュニティーをまとめることを目指しています。
Kickstarterのリンクは以下になります。
Alex from Tokyo