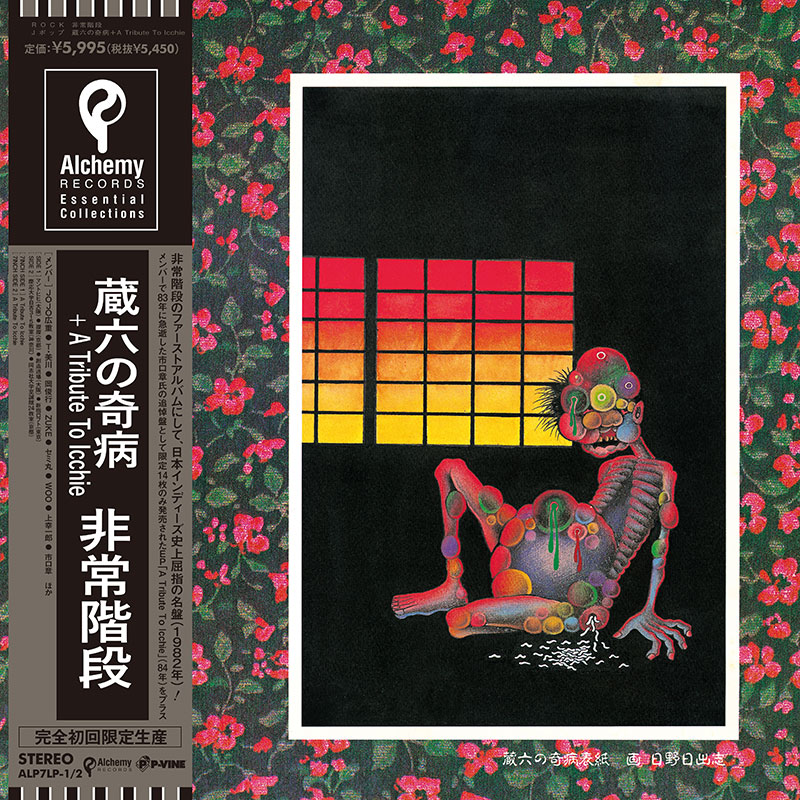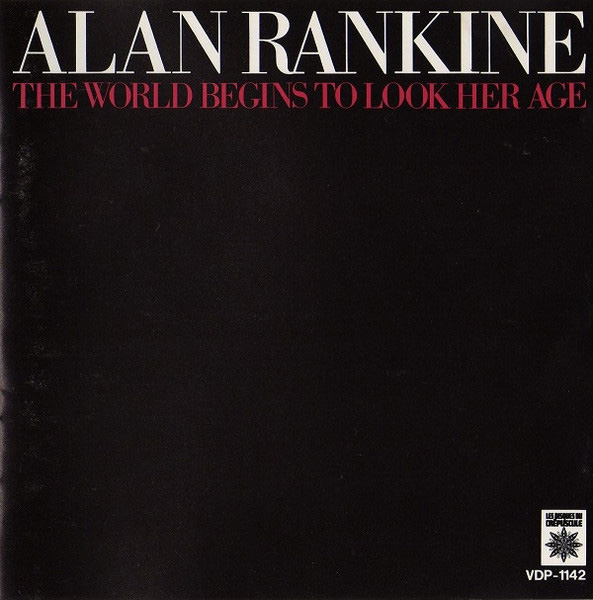少しでもUKのダンス・ミュージックに関心のある方なら、今年はオーヴァーモノのアルバムをチェックすべし。エレキングでもかれこれ10年ほど前からレコメンドしてきたTesselaとTrussのふたり(兄弟)によるユニットで、この名義でのシングルもまず外れがなかった。エレキング的にはTesselaによる2013年の「Hackney Parrot」という、ジャングルをアップデートさせた12インチが最高なんですけどね。
とにかく、彼らはそれこそジョイ・オービソンと並ぶUKダンス・シーンの寵児であって、ここ数年はディスクロージャーやバイセップなんかと並ぶ、ポップ・フィールドともリンクできるダンス・アクトでもある。90年代世代には、かつてのケミカル・ブラザースやアンダーワールドに近いと説明しておきましょうか。
まあ、とにかくですね、最新のビート搭載のオーヴァーモノがついにアルバムをリリースします。タイトルは『Good Lies(良き嘘)』で、発売は5月21日。楽しみでしかないぞ!

Overmono
Good Lies
XL Recordings / Beat Records
release: 2023.05.12
BEATINK.COM:
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13234
国内盤CD
XL1300CDJP ¥2,200+税
解説+歌詞対訳冊子 / ボーナストラック追加収録
限定輸入盤LP (限定クリスタル・クリア)
XL1300LPE
輸入盤LP(通常ブラック)
XL1300LP
以下、レーベルの資料から。
UKベースやブレイクビーツ、テクノの最前線に立つトラスことエド・ラッセルとテセラことトム・ラッセルの兄弟によるデュオ、オーヴァーモノが名門レーベル〈XL Recordings〉から5/12(金)に待望のデビュー・アルバム『Good Lies』をリリースすることを発表。同作より先行シングル「Is U」を公開した。
Overmono - Is U (Audio)
https://youtu.be/monJkVSJUQ0
デビュー・アルバム『Good Lies』は、オーヴァーモノのこれまでの音楽キャリアが凝縮されており、新型コロナの規制撤廃とともにクラブ・シーンで大ヒットとなった「So U Kno」や昨年リリースされた「「Walk Thru Water」」などダンス・フロアの枠を超えた12曲を収録。彼らの定番と言ってもいいアイコニックなボーカル・カットを織り込み、マルチジャンルのエレクトロニック・サウンドに再構築している。
先行シングル「Is U」は、長年のコラボレーターである写真家、映像作家のロロ・ジャクソンが撮影、監督したシネマティックなイメージや映像とともにビジュアルと同時に本日リリースされた。「Walk Thru Water」と合わせて、ダイナミックで複雑なプロダクションと印象的なビジュアルとなっている。
Overmono - Is U
https://youtu.be/8WomErURVb8
Overmono - Walk Thru Water feat. St. Panther
https://youtu.be/L3jfTb9cb1k
トラスとテセラはそれぞれ〈Perc Trax〉や〈R&S〉、兄弟自身が主宰する〈Polykicks〉から次々と作品をリリースし、お互いのプロジェクトに邁進する中で新たな一歩としてオーヴァーモノを結成。2016年に〈XL Recordings〉からデビューEP『Arla』を突如リリース、2017年にかけて『Arla』シリーズ3部作をリリースし話題を集めたほか、ニック・タスカー主宰の〈AD 93(旧:Whities)〉からも作品群を世に打ち出してきた。これまでにフォー・テットやベンUFOなど名だたるDJたちがダンス・フロアでヘビロテし、デュオとしての名を確固たるものとして築き上げていった。
同じくUKダンス・シーンを牽引するジョイ・オービソンとのコラボも精力的に行い、中でもシングル「Bromley」は数々の伝説的クラブ・イベントを主催するマンチェスターのThe Warehouse Projectで“5分に一回流れた”という逸話も流れるほどの話題作となった。また、彼らはリミックスにも積極的に取り組んでおり、ロザリアやトム・ヨークなどのリミックスも手掛けている。
2020年と2022年に〈XL Recordings〉からリリースされたEP『Everything U Need』と『Cash Romantic』は、エレクトロニック・ミュージック界で最も権威のあるオンライン・メディアResident AdvisorやPitchfork、DJ Mag、Mixmagなど各メディアの年間ベスト・ランキングに選出された。また、グラストンベリーや電子音楽のフェスDekmantelなどのフェスやツアーも積極的に行い、DJ Magのベスト・ライヴ・アクトにも選ばれるなどオーヴァーモノは結成以来UKで最もオリジナルなライブ・エレクトロニック・アクトとしてもファン・ベースを着実に築き上げてきた。
待望のデビュー作『Good Lies』は、5/12(金)に世界同時発売!本作の日本盤CDには解説が封入され、ボーナス・トラックとして未発表曲「Dampha」を特別収録。輸入アナログは通常盤に加え、数量限定クリスタル・クリア・ヴァイナルがリリースされる。
この2年間できる限り音楽を作りながら、多くの時間をツアーに費やしてきた。常に移動することは本当に刺激的で、たくさんの実験をして、コードを作ったり、ボーカルを刻んだり、ピッチを変えたりして楽しんでいた。このアルバムは、これまでの旅に捧げる愛の手紙であり、私たちがこれから進むべき道を示してくれているんだ。 ——トラス / テセラ (Overmono)