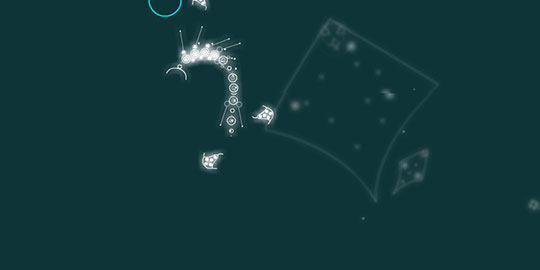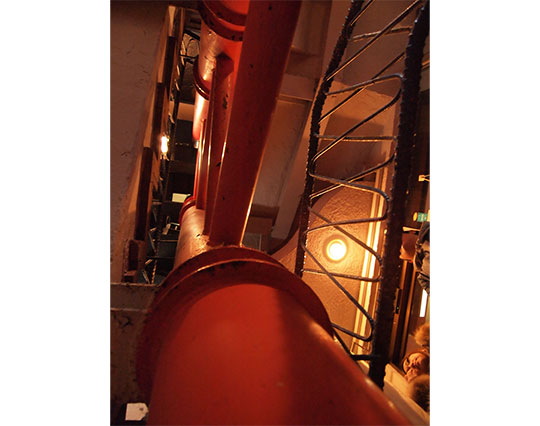ジ・オー・シーズは、USのライヴハウス・シーンではもっぱら愛され続けているバンドで、どのくらい愛されているかというのは、沢井陽子さんのレポートを読んでください。
ポジティヴな意味で、アメリカらしい足を使って、汗を流しているバンドである。東京公演には、ゲラーズ、そしてザ・ノーヴェンバーズも出るし、来週の月曜は渋谷〈O-nest〉、火曜日は名古屋〈KD JAPON 〉、そして、水曜日は大阪〈Conpass 〉で騒ごう。
[いいにおいのするThee Oh Sees JAPAN TOUR2013]
サンフランシスコ発世界中で大ブレイク中のアヴァンギャルドでpopなガレージ・サイケ・バンド、 Thee Oh Sees 、遂に日本に降臨!
なんと、大阪公演には、西宮の狂犬・KING BROTHERS(キングブラザーズ)が、東京公演には、トクマルシューゴ含むGellers、いまをときめくTHE NOVEMBERSが出演!

東京編 2/18@O-nest
Open/18:00 Start/19:00
adv/3.000 door/3,500
■Pコード:【191-065】,
■Lコード:【76462】,
e+
【出演】
Thee Oh Sees
Gellers
THE NOVEMBERS
Vampillia
名古屋編 2/19@KD JAPON
Open/18:00 Start/19:00
adv/2.500 door/3.000(+1drink )
■Pコード:【191-065】 ,
■Lコード:【46947】,
e+
【出演】
Thee Oh Sees
MILK
Nicfit
Vampillia
大阪編 2/20@Conpass
Open/18:00 Start/19:00
adv/3.000 door/3.500(+1drink )
■Pコード:191-314 ,
■Lコード:54081 ,
■e+
【出演】
Thee Oh Sees
KING BROTHERS
Vampillia
■Thee Oh Sees
Thee Oh Sees は、John Dwyer (Coachwhips, Pink and Brown, Landed, Yikes, Burmese, The Hospitals, Zeigenbock Kopf) の、インスト・エクスペリンタルな宅録作品をリリースするためのプロジェクトとして開始された。
その後、いくつかの作品を経て、フルバンドへと進化を遂げたのである。彼らのサイケデリックな作風は、一見するとレトロなものとして、とらえられるかもしれない。
だが、彼らは、数々の最先端のアレンジを細部に施すことで、サイケデリックでありながらもしつこさを感じさせない、スタイリッシュでキレの良い全く新しい音楽として、リスナーに強く印象づけているのである。
その作品群はPithforkをはじめとする数々のレビューサイト、音楽雑誌で軒並み高評価を獲得している。
だが、数々のメンバーたちと共に録音されたこれら作品群だけでなく、常軌を逸したエネルギッシュなライブパフォーマンスこそが、ライトニングボルトと同じベクトルにある彼らの本質ともいえる。



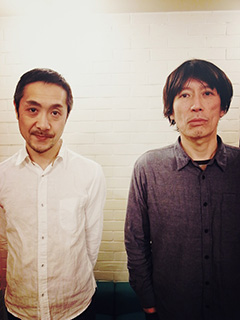 森俊二(Natural Calamity)と石井マサユキ(Tica)の二人によって2000年に結成されたギター・インストゥルメンタル・ユニット。2004年にファースト・アルバム『Straw Hat, 30 Seeds』を発表。続いて2006年に発表したセカンド・アルバム『Nicky's Dream』はその年のベスト・アルバムとして多くのメディアで取り上げられた。同アルバムからの楽曲は、様々なコンピレーションや映画『ホノカアボーイ』のサウンドトラックにも収録。2012年4月には渾身のサード・アルバム『Twilight For 9th Street』をリリースした。また、トリップ感溢れるライヴ・パフォーマンスも各方面で絶賛され、これまでにFUJI ROCK FESTIVAL、GREENROOM FESTIVAL、Sense of Wonder、SUNSET LIVEなどの大型フェスへも出演を果たしている。
森俊二(Natural Calamity)と石井マサユキ(Tica)の二人によって2000年に結成されたギター・インストゥルメンタル・ユニット。2004年にファースト・アルバム『Straw Hat, 30 Seeds』を発表。続いて2006年に発表したセカンド・アルバム『Nicky's Dream』はその年のベスト・アルバムとして多くのメディアで取り上げられた。同アルバムからの楽曲は、様々なコンピレーションや映画『ホノカアボーイ』のサウンドトラックにも収録。2012年4月には渾身のサード・アルバム『Twilight For 9th Street』をリリースした。また、トリップ感溢れるライヴ・パフォーマンスも各方面で絶賛され、これまでにFUJI ROCK FESTIVAL、GREENROOM FESTIVAL、Sense of Wonder、SUNSET LIVEなどの大型フェスへも出演を果たしている。 ハワイで生を受け、2歳の時に日本へと移住。中高時代はパンクやオルタナに開眼し、ハイティーンの頃には友人のユタカ、Delawareの点、そして立花ハジメとLow Powersのメンバーでもあったエリと、携帯電話の着信音をオケに使用し歌うというユニークなバンド、The Japaneseを結成し活動した。そしてボルティモアに渡った後、マット・パピッチとエクスタティック・サンシャインの活動を始める。同時に彼は通っていた美術大学のクラスメート達と共にポニーテイルを結成。カオティックなサウンドと怒濤のライヴ・パフォーマンスは瞬く間に話題となる。また、エクスタティック・サンシャインとしても〈カーパーク〉からデビュー・アルバムをリリースし、多方面から高評価を得るもののダスティンは脱退する。ポニーテイルもさらなるブレイクを期待されていたが突然活動休止を発表(2011/9/22に解散を発表)。そしてダスティンは〈スリル・ジョッキー〉と契約し、サード・ソロ・アルバムをリリースした。多数のエフェクターを足元にならべ、ディレイ、ループ等を駆使し、ミニマルでカラフルなレイヤーを描き出していくギター・パフォーマンスは注目を集めている。2012年通算4作目となるアルバムをリリースし、4月にはレコード発売記念の日本ツアーも敢行。NHKライヴ・ビートへの出演も果たす。7月にはNYで行われたダーティー・プロジェクターズの最新作のリリース記念ライヴのオープニングに抜擢され、10月の日本ツアーでも全公演オープニングを務めた。9月から10月前半にかけてビーチ・ハウスとのUSツアーを行った後、朝霧JAM2012にも出演を果たした。
ハワイで生を受け、2歳の時に日本へと移住。中高時代はパンクやオルタナに開眼し、ハイティーンの頃には友人のユタカ、Delawareの点、そして立花ハジメとLow Powersのメンバーでもあったエリと、携帯電話の着信音をオケに使用し歌うというユニークなバンド、The Japaneseを結成し活動した。そしてボルティモアに渡った後、マット・パピッチとエクスタティック・サンシャインの活動を始める。同時に彼は通っていた美術大学のクラスメート達と共にポニーテイルを結成。カオティックなサウンドと怒濤のライヴ・パフォーマンスは瞬く間に話題となる。また、エクスタティック・サンシャインとしても〈カーパーク〉からデビュー・アルバムをリリースし、多方面から高評価を得るもののダスティンは脱退する。ポニーテイルもさらなるブレイクを期待されていたが突然活動休止を発表(2011/9/22に解散を発表)。そしてダスティンは〈スリル・ジョッキー〉と契約し、サード・ソロ・アルバムをリリースした。多数のエフェクターを足元にならべ、ディレイ、ループ等を駆使し、ミニマルでカラフルなレイヤーを描き出していくギター・パフォーマンスは注目を集めている。2012年通算4作目となるアルバムをリリースし、4月にはレコード発売記念の日本ツアーも敢行。NHKライヴ・ビートへの出演も果たす。7月にはNYで行われたダーティー・プロジェクターズの最新作のリリース記念ライヴのオープニングに抜擢され、10月の日本ツアーでも全公演オープニングを務めた。9月から10月前半にかけてビーチ・ハウスとのUSツアーを行った後、朝霧JAM2012にも出演を果たした。 エレクトロニクスと生楽器を絶妙なバランスで調和させ、力強さと繊細さを自然体で同居させる。湘南・藤沢を拠点に活動を続け、人間味溢れる温かいサウンドを志向するアーティスト、鎌田裕樹による電子音楽団tickles(ティックルズ)。2006年発売のファースト・アルバム『a cinema for ears』リリース後から続けてきたバルセロナやローマ、韓国などを巡ったライブ・ツアーでは、人力の生演奏を取り入れたスリリングでドラマチックなライブ・パフォーマンスで大きな賞賛を得た。そんな数々の経験を経て紡がれた珠玉の楽曲をたっぷりと詰め込んだ待望のセカンド・アルバム『today the sky is blue and has a spectacular view』(2008年)は自身のレーベル〈madagascar(マダガスカル)〉よりリリースされ、TOWER RECORDS、iTunesを中心にセールスを伸ばし、高い評価を得た。2011年、次なるステップへと進むべく〈MOTION±〉と契約。ピアノ、シンセサイザー、フェンダー・ローズ、ピアニカ、オルガン、鉄琴、オルゴール、ギター、ベースなど、様々な楽器を駆使しながら感情的なメロディーと心地良いリズムを生み出していくスタイルに更なる磨きをかけ、2012年4月にニュー・アルバム『on an endless railway track』をリリース。6月にはSchool of Seven Bells来日公演のサポート・アクトを務めるなど、リリース後はエレクトロニクスとリアルタイム・サンプリングを駆使するライブ活動を精力的に展開。柔らかいビートの上で胸を震わせる旋律が幾重にも重なり合い、交錯していく夢幻のサウンドスケープは、聴く者の心を捉えて離さない。
エレクトロニクスと生楽器を絶妙なバランスで調和させ、力強さと繊細さを自然体で同居させる。湘南・藤沢を拠点に活動を続け、人間味溢れる温かいサウンドを志向するアーティスト、鎌田裕樹による電子音楽団tickles(ティックルズ)。2006年発売のファースト・アルバム『a cinema for ears』リリース後から続けてきたバルセロナやローマ、韓国などを巡ったライブ・ツアーでは、人力の生演奏を取り入れたスリリングでドラマチックなライブ・パフォーマンスで大きな賞賛を得た。そんな数々の経験を経て紡がれた珠玉の楽曲をたっぷりと詰め込んだ待望のセカンド・アルバム『today the sky is blue and has a spectacular view』(2008年)は自身のレーベル〈madagascar(マダガスカル)〉よりリリースされ、TOWER RECORDS、iTunesを中心にセールスを伸ばし、高い評価を得た。2011年、次なるステップへと進むべく〈MOTION±〉と契約。ピアノ、シンセサイザー、フェンダー・ローズ、ピアニカ、オルガン、鉄琴、オルゴール、ギター、ベースなど、様々な楽器を駆使しながら感情的なメロディーと心地良いリズムを生み出していくスタイルに更なる磨きをかけ、2012年4月にニュー・アルバム『on an endless railway track』をリリース。6月にはSchool of Seven Bells来日公演のサポート・アクトを務めるなど、リリース後はエレクトロニクスとリアルタイム・サンプリングを駆使するライブ活動を精力的に展開。柔らかいビートの上で胸を震わせる旋律が幾重にも重なり合い、交錯していく夢幻のサウンドスケープは、聴く者の心を捉えて離さない。 クラブのみならず、ファッションショーやホテル、ショップ、カフェなど、およそ音楽と触れ合うことが出来る空間すべてに良質な選曲を提供してきた山崎真央(gm projects / AKICHI RECORDS)、鶴谷聡平(NEWPORT)、青野賢一(BEAMS RECORDS)の3人の頭文字を並べて命名されたユニット「真っ青」。20年以上のDJキャリアに裏付けされたスキル、レコード・CDショップのバイヤー経験がもたらす豊潤な音楽的バックグラウンド、そしてアート、文学、映画などにも精通する卓越したセンスから生まれるそのサウンドは、過去、現在、未来に連なる様々な心情を呼び起こし、聴くものの目前に景色を描き出すものである。リミックスを手掛けた「中島ノブユキ/Thinking Of You (真っ青Remix)」 はまさに青いサウンドスケープ。
クラブのみならず、ファッションショーやホテル、ショップ、カフェなど、およそ音楽と触れ合うことが出来る空間すべてに良質な選曲を提供してきた山崎真央(gm projects / AKICHI RECORDS)、鶴谷聡平(NEWPORT)、青野賢一(BEAMS RECORDS)の3人の頭文字を並べて命名されたユニット「真っ青」。20年以上のDJキャリアに裏付けされたスキル、レコード・CDショップのバイヤー経験がもたらす豊潤な音楽的バックグラウンド、そしてアート、文学、映画などにも精通する卓越したセンスから生まれるそのサウンドは、過去、現在、未来に連なる様々な心情を呼び起こし、聴くものの目前に景色を描き出すものである。リミックスを手掛けた「中島ノブユキ/Thinking Of You (真っ青Remix)」 はまさに青いサウンドスケープ。