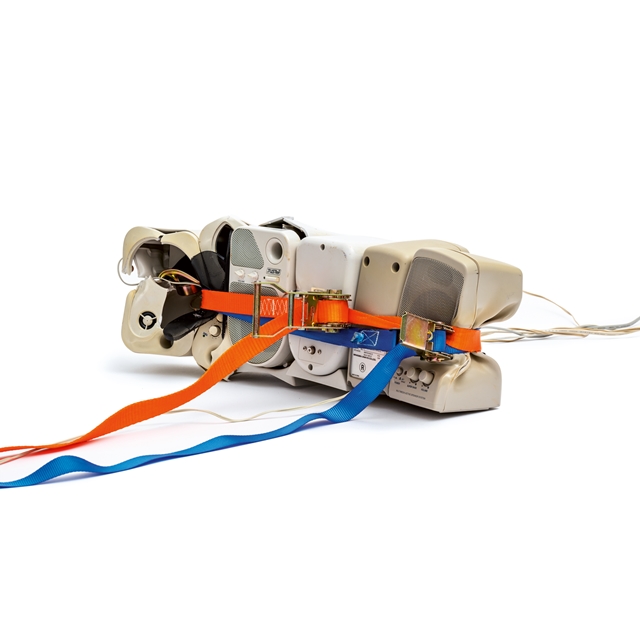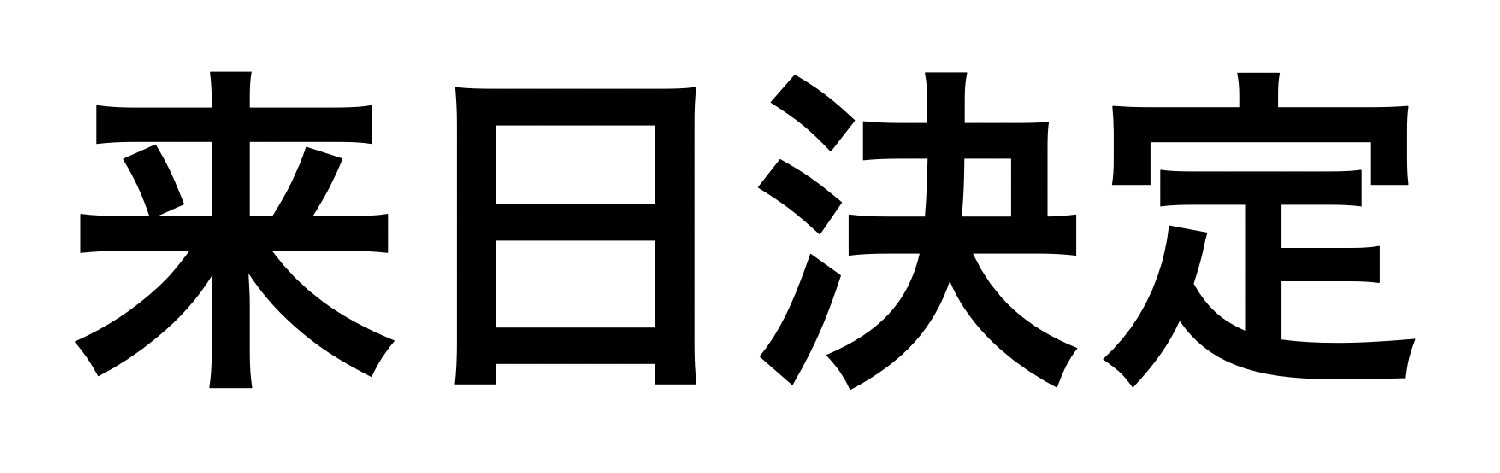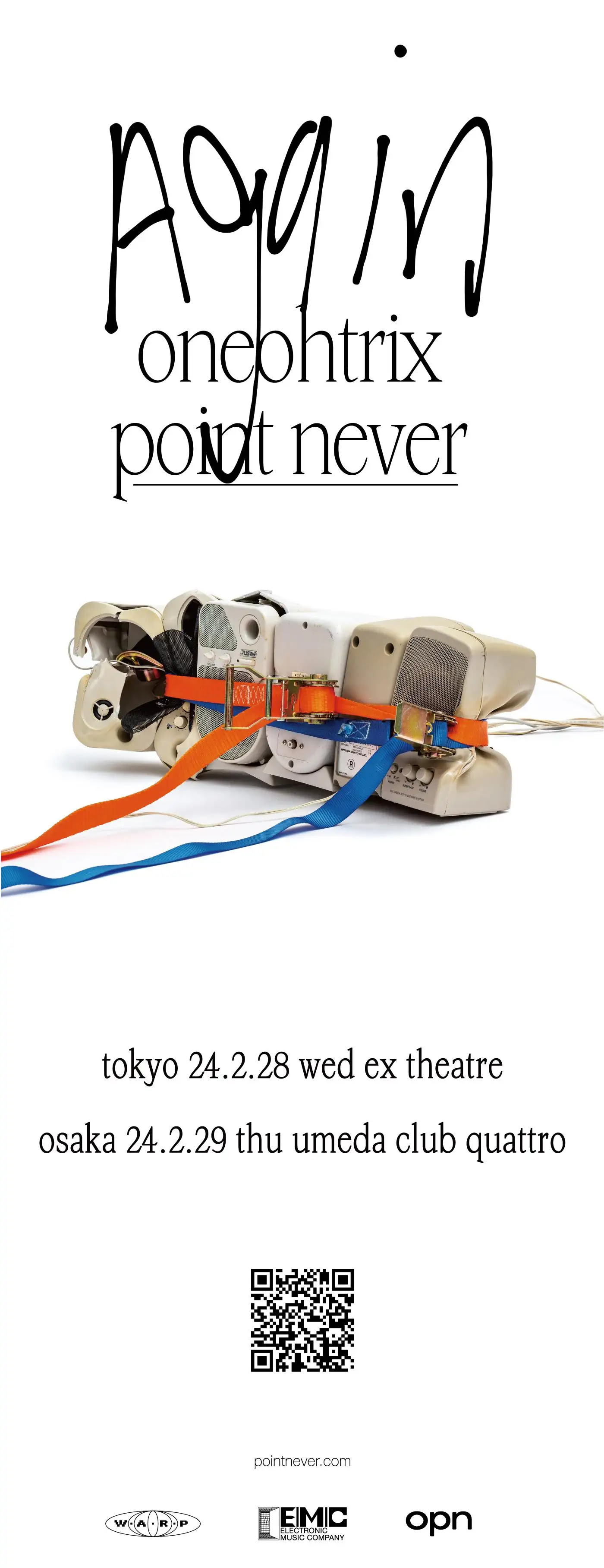私がこれまでリリースしてきた全てのアルバムに共通するコンセプトがある。それはモロコのときから続いているテーマで、個人主義と自由。そして繊細さと降伏する勇気。
まさかの〈Ninja Tune〉からのリリースとなったシンガー、ロイシン・マーフィーの新作アルバム『Hit Parade』。プロデューサーというかほぼ共作といった方がいいだろう、アンダーグラウンドの、ジャーマン・ハウスのトップ・プロデューサー、DJコッツェが今回そのサウンド全体を担っている。ロイシンは、アイルランドに生まれ、そして1995年、UKのトリップホップの隆盛とともにシェフィールドのマーク・ブライドンとのユニット、モロコにてキャリアをスタートさせている。ある意味でUKのお家芸ともいえるダウンテンポ~トリップホップを、シンガーによる、UKのダンス・カルチャーを出自に持ったポップ・フィールドでの展開を示したアーティストとも言えるだろう。なんというか当時は、UKブレイクビーツの牙城だったことを考えれば〈Ninja〉からのリリースもどこか因縁めいたものを感じてしまう。そして2005年以降、ソロに転じてからのファースト・ソロは、マシュー・ハーバートにプロデュースを頼んだり、また2020年前後の〈Skint〉からの近作では、エレクトロ・ハウス系のベテラン・プロデューサー、〈DFA〉からもクロックド・マン名義でリリースするリチャード・バレット(その正体は元スウィート・エクソシストのDJパーロットという、実はシェフィールド人脈)とともに、しっかりと大箱系のハウス、エレクトロ・ディスコを展開、そのキャリアはほとんどダンス・カルチャーとともにある。
そして本作へと至るDJコッツェとの出会いは、コッツェの2018年の『Knock Knock』で、コッツェ・オファーによるコラボにて2曲でスタートしている。DJコッツェといえば2000年代中頃、いわゆる〈Playhouse〉などのエレクトロニックなジャーマン・ディープ・ハウスと、ケルンの〈Kompakt〉あたりのミニマル・テクノを結ぶ当時のドイツ産ハウスの、オリジナリティ溢れるトップ・アーティストとも言える存在だ。ヒップホップに出自を持ちDMCのドイツ大会で準優勝もしている。その卓越してテクニックもあって、2000年代中頃、当時のヨーロッパのDJなどに取材した折に、「現在のヨーロッパで優れたDJは?」というような質問に対して返ってくるのは、自分の経験則でしかないが多くの場合、彼の名前だったことも覚えている。また2000年代初頭にはポップなエレクトロ・グループ、インターナショナル・ポニーで、ドイツの〈Columbia〉からそれなりのヒットを飛ばすなど実は昔からメジャーなポップ路線も含めてマルチな才能を持ち合わせているミュージシャンでもある。ある意味でこうしてみてみるとふたりの相性というのも不思議と乖離したものではなさそうだ。チョップ&早回しのヴォーカル、ソウルやディスコのストリングス・サンプルが重層的に絡み合う、どこかノスタルジックでウォーミーなダウンテンポやハウスを展開、そこにときにアンニュイに、ときに茶目っ気たっぷりに表情豊かに歌いあげるロイシンのヴォーカルとともに、どこかおとぎの国に迷い込んだようなサイケデリックなクラブ・ポップスを作りあげていく。なにより、彼女のキャリアの根底たるダンス・ミュージックへの愛を多分に感じることのできるアルバムだ。DJコッツェのキャリアを考えれば、ヒップホップからハウスまでを横断した『DJ-KICKS』のようなDJ的なコラージュ、サンプリング・センスを背景に、さらにそうしたセンスを楽曲へと昇華した『Knock Knock』のサウンドを、ロイシンというシンガーの声なくしてはできなかったポップ・アルバムとして1枚に作りあげたと言ってもいいだろう。
先月、二次性徴抑制剤に関する発言で物議を醸した彼女だったが、今回無事取材に応じてくれた。
ムーディーマンの大ファンだから(笑)。彼はいつだって私の最初の選択肢。
■今回のアルバム1枚のコラボレートへと発展したのは、2018年のDJコッツェの『Knock Knock』への参加、つまりはそのリリース少し前からスタートしていると思いますが、まずはその突端となった『Knock Knock』収録曲でのコラボレートはどのようにスタートしたのでしょうか? コッツェからどのようなオファーがきたんでしょうか?
RM:そう。私の最初のソロ・アルバムをプロデュースしてくれたマシュー・ハーバートから私のメールアドレスをもらって彼が連絡してきて。そして、その時点で彼は他にもたくさんの音源を持っていて、そのうちのいくつかが私にピッタリだと思ったみたいで、その後も私に曲を色々と送り続けてくれた。その後、あるときそれぞれがリモートで作業できるようにするために、彼と同じ音楽ソフトウェアを使って欲しいと言ってきた。そこから今回のアルバムの作業がはじまって。何年もの間、私たちは作業しては休み、作業しては休みを繰り返しながら、一緒に曲を作っていった。何ヶ月も作業しないときもあったし、かと思えば、3日間超集中して曲作りをしたときもあった。あの頃はそれぞれ他のプロジェクトで忙しかったし、作業ができるタイミングを見つけながら、マイペースにゆっくりと制作を進めていって。だから、すごくリラックスしながら作ることができた。
■今回は〈Ninja Tune〉からのリリースとなりますが、彼らとの契約が本作の制作より先でしょうか? それとも、契約よりも前にコッツェとのコラボが自発的におこなわれたのでしょうか?
RM:レコードは〈Ninja Tune〉との契約より前に完全に完成していた。レコードができ上がってから、いくつかのレコード会社を回って曲を聴いてもらったんだけど、私はそのとき数曲聴かせることができれば、くらいに思っていたのね。でも、どのレコード会社も一度曲を聴かせると、アルバムの全曲を聴きたがった。そのときに、自分たちが何か特別な作品を作ったんだな、と気づいて。
■新作『Hit Parade』をDJコッツェとのコラボレーションで最終的にアルバム1枚を制作しようと思った明確な理由があればお教えください。
RM:彼のように並外れたプロデューサーから仕事を依頼されたら、ノーとは言えない。私の中の好奇心が、彼のような才能ある人と仕事がしたいって背中を押した。彼みたいな人と仕事をしたらどんな発見があるんだろうってワクワクした。
■DJコッツェのプロデューサーとしてのすごいところはどこでしょうか?
RM:彼はとにかく本当に素晴らしい耳を持っていると思う。私が気づかないどんな音でも細かにハッキリと聴き取れるのよね。だから、彼は余計な音を取り除くことができる。それがいい音かよくない音かを明確にして、使うか使わないかを決めていく。ある意味とても分析的なやり方ね。それは作品にとってすごく重要なことだと思う。あまり同じ空間で彼と作業することはなかったけど、彼との作業はすごく心地よかった。ひとりで作業する時間も多かったけど、彼と作業しているときは、一日中やりとりをしたり、電話で会話をしたりして、すごく親密だった。
■先ほどの話だと長い間制作がすすめられたようですが、今回はあなたがABLETON LIVEの使い方を覚えるところからはじまり、文字通りインターネットを介しておこなわれたようですね。ネットでの制作はどのような体験でしたか?
RM:初めてだったから最初は大変だった。これまでもひとりで曲を書いたことはあるけど、レコーディングはプロデューサーの夫がやってくれたり、ヴォーカルを調整したければロンドンの小さなスタジオに行ってエンジニアと一緒に作業していたから。でも今回は、全て自分の家での作業だった。それがいちばんの違いだった。だから、作業時間が本当に自由だった。掃除や洗濯をしながらも作業できたし、メロディを思いついたらそれをその瞬間に録音できたし、それをそのままレコードに使うことだってできた。それは私にとってすごく新鮮だった。

私にとって最も偉大な音楽教育者たちはDJたちだった。あらゆるダンス・ミュージックに精通し、あらゆるジャンルやスタイルをミックスできる人たち。
■全体的に、ふたりがとにかくコラボーレションを楽しんでおこなったことが伝わってくるサウンドだと思います。ですが実際は、ピッチフォークのインタヴューによれば、あなたが作った仮歌が例えば4つの曲に分かれたり、ちょっとしたしゃべり声をヴォイス・サンプルに使われたりと、そのコラボレートはかなりトリッキーで驚かされる瞬間ばかりだったようですね。
RM:私のインタヴューの音声をYouTubeからサンプリングしたり、彼に私が送った音声メモを使ったりした。あのレコードにはたくさんの私が散りばめられている。そういう要素を使って、レコードに質感や感覚を加えたかったの。ただ曲を1曲聴いているだけじゃなくて、同時にいくつか音を聴いている感覚というか。ラジオを聴いていて複数のラジオ局の音が聴こえてくるときってあるでしょ? あんな感じ。トリッキーというか、予期せぬ幸運ばかりだった。ルールもなければ目指すジャンルもなかったし、全てが私たちの中から自然に出てくるものだった。
■あなたからサウンドに関してなにかリクエストやコンセプトを伝えるなどはあったんですか?
RM:いや、リクエストは許可されてなかった(笑)。彼はそんなタイプのDJじゃないから(笑)。でも彼はとても分析的だから、それについて話し合うことは多かったかもしれない。例えば、彼は彼なりに分析して、その曲はもうダメだって曲に見切りをつけようとしたことがあって。でもそこに私が入って、いや、これは本当にいい曲だと思うって意見を言うことはあった。それは今回のレコード制作における私の役割の一部だったと思う。この音、この曲はよくないって思い込んでしまっている彼を一度止めて考え直させること。曲づくりと歌詞を書くこと以外に、捨てる必要のないものを捨てようとしていないかを明らかにするのも私の仕事だった。
■曲ごとに、たとえば、あなたの仮歌から始まったり、もしくはコッツェからガイドとなるループやBPMが指定されたりなど、起点・出発点は異なったのでしょうか?
RM:制作方法はどの曲もほぼ同じだった。彼がバッキング・トラックを送ってくれて、私がそれに乗せてこれでもかってほど歌って、それを全て彼に送った。そして、そこからリズムやアレンジメントを変えたり変えなかったりという感じ。デモのまますごくシンプルにでき上がるときもあれば、複雑なときもあった。テニスの試合みたいな感じね。例えば “CooCool” や “The Universe” のような曲は最初のヴォーカルがそのまま使われているし、逆に “Two Ways” や “You Knew” はオリジナルものと全然違うの。
[[SplitPage]]シネイド・オコナーは、アイルランドの新しい一面を世界に見せてくれた人だった〔……〕完全にアイコン的存在だった。だから一時期、10代のときは彼女みたいな格好をしていた時期もあった。
■今回の制作でもっとも困難だったことはなんでしょうか?
RM:ソフトウェアの使い方を学ぶことだったと思う。でも少なくとも、私の夫がプロデューサーだから、彼にいろいろ教えてもらえたのは助かった。いまだに使い方をマスターしたわけじゃなくて、ヴォーカルをレコーディングするとか、ハーモニーをレコーディングするといった自分にとって必要なことができるだけだけど、まずは自分だけでそれができるようになることが最優先だった。
■歌詞に関して、今回はアルバムを通してコンセプトなどはありましたか?
RM:歌詞に関しては、私がこれまでリリースしてきた全てのアルバムに共通するコンセプトがある。それはモロコのときから続いているテーマで、個人主義と自由。そして繊細さと降伏する勇気。それは、つねに私の作品に存在しているコンセプト。
■先日リリースされた先行シングルではムーディーマンをリミキサーに迎えていました。彼を起用したのはあなたのアイディアですか?
RM:そう。私がムーディーマンの大ファンだから(笑)。彼はいつだって私の最初の選択肢。
■『Hit Parade』というタイトルは、どのような意味でつけたんでしょうか?
RM:DJコッツェが、「もし脱落せずに僕との作業を続けてくれたら、君を『ヒットパレード』や『トップ・オブ・ザ・ポップス』に出して有名にしてあげるよ」って冗談で言ってたんだけど、もう『ヒットパレード』も『トップ・オブ・ザ・ポップス』もやってないでしょ(笑)? だからその皮肉が面白いって思ってそのタイトルにしたの。「トップ・オブ・ザ・ポップス」、いい番組だったよね。いまはもうあの番組が成り立つほどのポップ・スター自体が存在していない気がする。
■話しは変わりますが、あなたの少し上の世代になるかと思いますが、同じくアイルランド出身のシネイド・オコナーが先日亡くなられました、あなたにとって彼女はインスピレーションを与えてくれるシンガーのひとりでしたか?
RM:もちろん。私は子どもの頃、12歳でアイルランドからイギリスに引っ越したんだけど、私が引っ越したとき、彼女のような存在の人がいてくれたのはとても幸運だった。シネイド・オコナーは、アイルランドの新しい一面を世界に見せてくれた人だったから。そのおかげで、私のようなアイルランド人の子どもたちは生きやすくなったと私は思う。昔、イギリスではアイルランド人に対する人種差別がけっこうあった。アイルランド人は、穴を掘ったり道路を作ったりする建設業者、労働者階級の人たちが多く、そのステレオタイプが強かったから、イギリス人とは別の人種だという扱いを受けていた。でも、ティーンエイジャーだった私にとって、シネイド・オコナーのような人たちがいたおかげで、アイルランド人がただの貧しい人種ではなく、それ以上に大きな展望を持った現代的な人間であり、クールでとても重要な存在なんだという誇りを持つことができた。それは私にとってすごく大切なことだったと思う。美しかったし、彼女は完全にアイコン的存在だった。だから一時期、10代のときは彼女みたいな格好をしていた時期もあった。ショートヘアにしたりなんかして。

シェフィールドの人たちが皆DIYでいろいろなことをやっていて、音楽文化に貢献しているのを見てすごくいいなと思った。マンチェスターやロンドンに比べるとシーンは小さかったけど、もっとDIYでもっと活動的で、特徴があったと思う。
■あなたのキャリアはそのスタートから、DJカルチャー/ダンス・カルチャーとともにあると思うのですが、今回のようなDJ出身のアーティストとのコラボレーションはあなたのクリエイティヴィティ、もしくはアーティストとしてのキャリアになにをもたらしたと思いますか?
RM:私たちは、ある特別な音楽を作ろうとしたわけじゃなくて、ただ木が成長するように今回のアルバムを作った。でもDJカルチャーに関して話すなら、私にとって最も偉大な音楽教育者たちはDJたちだった。あらゆるダンス・ミュージックに精通し、あらゆるジャンルやスタイルをミックスできる人たち。DJパーロットやウィンストン・ヘイゼル(注:〈Warp〉のファースト・リリースとなったフォージマスターズのひとり)のような人たちね。何年もの間、私は彼らのようなDJたちに興味を持っていて、週に3、4回くらい、シェフィールドのいろんなヴェニューに彼らのプレイを見に行っていた。彼らのセットは毎回違っていたし、その度に、私は新しい何か、音楽同士の繋がりを学ばせてもらっていた。彼らは音楽に関する百科事典のような知識を持っていて、のちに私の人生の中に入り、その知識を私と共有してくれた。それは私にとって本当に大きな意味があり、重要なことだった。彼らのおかげで、私のダンス・ミュージックとのつながりは、うわべだけの関係ではなく真の関係に築き上げられていった。私はそういう環境で育ってきたし、その中でDIYであること、自分自身の音楽を自分自身のシチュエーションの中で作ることを学んでいった。
■またモロコが結成されたのも1990年代前半のシェフィールドですよね。当時のシェフィールドのシーンはどのような雰囲気だったのですか?
RM:私本当に素晴らしかった。たくさんの人たちがいて、みな音楽を作り、パーティーをして、スタジオを作っていた。当時、シェフィールドにはデザイナーズ・リパブリックっていう素晴らしいデザイン・スタジオあったし、〈Warp〉もあったし、重要なアンダーグラウンドのダンス・ミュージック・シーンが存在していた。そして世界中の音楽が広がっていた。だから、素晴らしいDJやプロデューサーたちから音楽を学びたければ、シェフィールドを出る必要は全くなかった。様々な活動をしている人たちが周りにたくさんいたから。私はその前マンチェスターに住んでいて、マンチェスターのクラブ・シーンにどっぷり浸かっていたし、レコード屋を回ってレコードを買い漁っていた。でもシェフィールドに引っ越したとき、シェフィールドの人たちがみなDIYでいろいろなことをやっていて、音楽文化に貢献しているのを見てすごくいいなと思った。マンチェスターやロンドンに比べるとシーンは小さかったけど、もっとDIYでもっと活動的で、特徴があったと思う。私にとって新たな扉を開く鍵をくれた場所だと思うし、自分では気づけなかった可能性の存在を教えてくれる場所だった。
■今後の予定を教えてください。
RM:いまのところはアメリカでのツアーと、いくつかライヴをすることになってる。南米にも行くし、ヨーロッパにも行く。イギリスでもライヴがあるし、あと、来年の夏はいくつかフェスティヴァルにも出る予定。前回日本に行ったのは相当前で、マシュー・ハーバートと一緒だった。もう20年くらい前じゃないかしら。私の子どもたちが日本の文化が大好きで。だから、また日本に行けたら嬉しい。