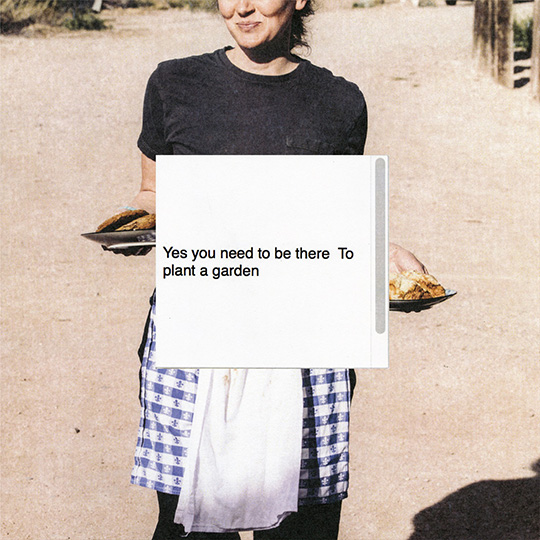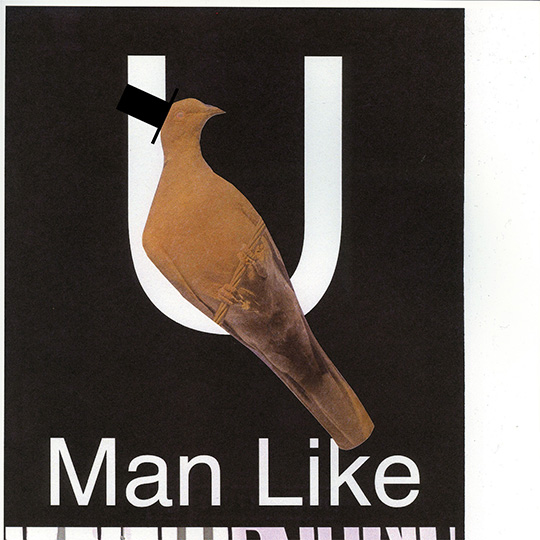7月12日(金)、大阪の梅田クアトロにデトロイトからアンプ・フィドラーとアンドレスがやって来る。どちらもまったく素晴らしいブラック・ミュージックを聴かせてくれること請け合い。
アンプ・フィドラーはライヴセット、アンドレスはDJセットです。ムーディーマンも新しいアルバムが出るというし、また、アンドレスのほうもアルバム『Andrés Ⅳ』のリリースを間近に控えているし、期待大です。大阪梅田クアトロの初のオールナイト・イベント。行くしかないでしょう。
■公演詳細
会場:梅田クラブクアトロ
〒530-0051 大阪市北区太融寺町8番17号プラザ梅田10F TEL.06-6311-8111
https://www.club-quattro.com/umeda/
公演日:2019年 7月 12日(金)
開場/開演:23:00
料 金:前売¥3,000【税込】/当日[1\4,000、2\2,500(24:00までに入場)、3\3,500(with Flyer)【税込】]
入場時ドリンク代600円別途必要
※オールナイト公演のため20歳未満の入場はお断りいたします。
※エントランスでIDチェックあり。必ず顔写真付き公的身分証明書をご提示ください。
(運転免許証、taspo、パスポート、顔写真付マイナンバーカード、顔写真付住基カード、外国人登録証)
ご提示いただけなかった場合、チケット代のご返金はいたしかねます。
整理番号付・営利目的の転売禁止
■Amp Fiddler
Amp Fiddler(アンプ・フィドラー)は、ミシンガン州デトロイトを拠点とするキーボーディスト/シンガー/ソングライターである。
George Clinton率いるParliament/Funkadelicに在籍し、またMoodymann, Brand New Heavies, Fishbone, Jamiroquai, Maxwell, Princeのレコーディングやツアーに参加してきた、現代を代表するSOUL/FUNKミュージシャンの1人である。
テープ編集でビートを作っていた若い頃のJ Dillaに、サンプリング・ドラムマシーンAKAI MPC60での制作をAmpが薦め教えたことでも知られ、そしてそのDillaをQ-Tipに紹介したのもAmpである。その後DillaはThe Ummahに参加する。
1990年、ベースプレイヤーであるBubz Fiddlerとの兄弟ユニット、Mr.Fiddlerとして、アルバム『With Respect 』をリリース。Amp Fiddlerとしてソロ名義ではアルバム『Waltz Of A Ghetto Fly』(2003年)、『Afro Strut』(2006年)をリリース、2008年にはSly & Robbieとの共作アルバム、Amp Fiddler/Sly & Robbie『Inspiration Information』をリリースしている。
2016年には10年ぶりとなるソロアルバム、『Motor City Booty』をMidnight Riot Recordings(UK)よりリリース。
2018年、Moodymann主宰Mahogani Musicから、最新アルバム『Amp Dog Knights』をリリース。
https://www.ampfiddler.com
https://twitter.com/AmpFiddler
https://www.instagram.com/Amp_Fiddler/
https://open.spotify.com/artist/39g75EmRFeFbvHhsGjUpLU?si=shLDKOFsTGSg2lD-12-wow
■Andrés (aka DJ DEZ / Mahogani Music, LA VIDA)
Andrés(アンドレス)は、Moodymann主宰のレーベル、KDJ Recordsから1997年デビュー。
ムーディーマン率いるMahogani Musicに所属し、マホガニー・ミュージックからアルバム『Andrés』(2003年)、『Andrés Ⅱ 』(2009年)、『Andrés Ⅲ』(2011年) を発表している。
DJ Dezという名前でも活動し、デトロイトのHip Hopチーム、Slum Villageのアルバム『Trinity』や『Dirty District』ではスクラッチを担当し、Slum VillageのツアーDJとしても活動歴あり。Underground Resistance傘下のレーベル、Hipnotechからも作品を発表しており、その才能は今だ未知数である。
2012年、 Andrés自身のレーベル、LA VIDAを始動。レーベル第1弾リリース『New For U』は、Resident Advisor Top 50 tracks of 2012の第1位に選ばれた。2014年、DJ Butterとのアルバム、DJ Dez & DJ Butter 『A Piece Of The Action』をリリース。
パーカッショニストである父、Humberto ”Nengue” Hernandezからアフロキューバンリズムを継承し、Moodymann Live Bandツアーに参加したり、Erykah Baduの “Didn’t Cha Know”(produced by Jay Dilla)ではパーカッションで参加している。
Red Bull Radioにてマンスリーレギュラー『Andrés presents New For U』を配信中。