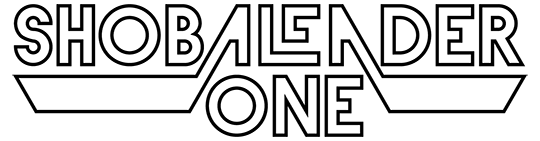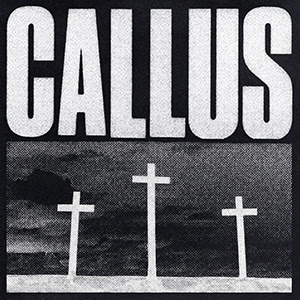2月某日、筆者自宅には僕を筆頭にいつものダメな3人が集っていた。しかしこの日は悪巧みではなく、エンドンの新譜、『スルー・ザ・ミラー』のプロモーションを意図したインタヴュー、という名目であった。リリックを書かないヴォーカリストでありながらスポークスマンとしてバンドとシーンを引率する那倉太一(兄)、楽器を演奏しないプレイヤーでありながら文筆家としてバンドの言語を伝える那倉悦生(弟)。僕にとってこの兄弟がエンドンというバンドの特異性、異常性を象徴しているからこそ、今回のインタヴューに相応しいと呼び出したわけだ。
というのはあくまでも言い訳に過ぎず、以下のお喋りは極度に繊細ないい歳こいた男子の戯言である。エンドンは都内を拠点としながら、ヨーロッパでのルフ・フェスティヴァルへの出演や、幾度となく行うアメリカ・ツアーなど、グローバルに活動する非常にうるっさいバンドである。フリージャズの即興性と瞬発力を骨組みとしながら構築されたメンバーの高い技術力と経験から生み出される“情報過多”なロックンロールは現在の東京、もとい日本の究極体現音楽である。彼らの最新作、『スルー・ザ・ミラー』は言語化するのも馬鹿馬鹿しいほど(仕事放棄)素晴らしい。病的に過剰な密度で構成されながらも、罪深いほどにわかりやすいレコードである。以下は人生においてクソの役にも立たないプライドや拘りに葛藤し、それでもなにかを生み出そうとするクズ男子の女子会である。

兄がセンターで弟が左端。
俺:エンドンの音楽、とくに今回の『スルー・ザ・ミラー』は顕著な気がするけど、感傷的であるほど真価が聴ける気がするよね。
兄:感傷的になって自分たちの曲聴いたことないからわかんないけど、幻想だとしてもそういうことはあるかもね。
俺:いや100%幻想なんだけど。
兄:やっぱりそういう偏りがある人間がやったり聴いたりするっていうバイアスは当然あるよね。
俺:歳食ってくなかでなるべく音楽への幻想を捨てようって思いが強くなるんだけど結局あきらめきれない。でも今回のアルバムがいいなって思うのは、幻想を抱かずとも正当に評価できるものに仕上がってるからかな。
兄:同じ幻想向けるんでも、アイドルに流れていってるっていう感じはするんだよね。結局は演者が醜くない形をしてることっていうのはすごい強い作用があると。黒いメタルのシャツきた臭くて太った俺たちが好きな曲を自分たちみたいな醜いヤツがやってるか、少女がやってるかでオーディエンスでいるときの自分たちの気持ちは全然違うでしょ。アイドルにそういった中二病的なものを投影するっていうのは結構みんなやってるっていうか。可愛いだけじゃないってのはあるよね。バンド辞めた人たちがそういうのですごいモッシュするとかっていう現場もあるんじゃない?
俺:アイドルわかんないんだけど例えば?
弟:怪我をしてるとかね。包帯巻いてるみたいな。
兄:衣装としてそういうのもあるんだけども、曲としてもね。だからメタルとかも本当そうだと思うよ。メタルのキメを楽しむ現場でいちばん機能してるのはアイドルなんだと思う。
弟:アイドルは商品だから、バカになって恥ずかしげもなくキメを楽しめる。
兄:商品って言い方ももちろん可能だけど、実際アイドルっていまいちばん同一視しやすい勇者だと思うんだよね。圧倒的に男も女も女の子が頑張る姿の方が同一視しやすいと思うんだよね。
俺:キメって具体的に?
兄:メタルのアレンジのなかでの決まりごとだよ。そういうのってみんなマトモだったりお洒落な大人になろうとしたら置いていくものじゃん? 中二病的なそれを誰かが代行してくれる。エージェンシーだよね。それを少女に代わりにやってもらうというのは最高なんじゃないかな。
俺:それは的を得てる気がする……
兄:うちの曲で、“パリサイド・エージェント・サーヴィス(PARRICIDE AGENT SERVICE)”、『親殺し代行業』っていうタイトルなんだけど、音楽性としてもキャラクターとしても「代わりにやってくれてる」って思われるような。手が汚れてて、ガキで、不必要にウルサイ音楽を代わりにやってくれるひとに思われたかったというか。
俺:そういうバンドは一杯いて、エンドンは違う気が。
兄:いるけど狭いじゃない? 共振作用が。
俺:エンドンの共振作用の広さってのは、単純に音楽的背景の違いかな。
兄:曲がいいって言えよ(笑)。
俺:GodCity Studio(コンヴァージ/Convergeのギタリスト、カート・バルーのスタジオ)で録ったってことがこのアルバムにはかなり作用してるよね。
兄:そりゃもう(苦笑)。結局のところ、ハードコア化させてもらえたかもしれないよね(笑)。
弟:時間がなかったのもあるかもしれないけど、ノイズの位置が定位されてて、アツオさんにやってもらったみたいに(前作『MAMA』はボリスのアツオ氏によるプロデュース)音量をボコボコさせたり、右行ったり左行ったりしてなくて。今回は編集の段階でノー・エフェクトだし、俺のノイズなんか定位でずっと鳴ってて。ノイズの勝手に暴れてくれる制御不能性の古き良き“手に負えない”ノイズじゃなくて、楽器としてアレンジの地図の中にポンと置けているってことはポイントだと思う。
俺:ギミックがないわけだ。
兄:全くない。カートは仕事の特性としても自己完結させないタイプだし、プロデューサーがいないことの効果があるね。でもいわゆるボストン・ハードコアの音っていうか、DCハードコアの音のテイストは感じるよね。
俺:めちゃめちゃ感じる。
兄:で、その相性の良さを調整したのは、ギターという楽器を扱う人間達なんだと思った。スキルというか、コウキ(ギタリスト)がカートと対等にやれる人間だってのはスタジオで見ててすごく思った。カートもギターを録ってるとき楽しそうでよかった。
俺:表現行為は無が有となる変換行為だと思ってて、その変換行為中だけは自意識から解放されるっていうか、忘我だよね。『スルー・ザ・ミラー』じゃないけど鏡に映る自分を消滅させたい欲望みたいなもの? が表現行為に繋がるのかなって思ったんだけど。
兄:そこに関しては俺はスパっとあきらめがあって、もう全ては自己愛っていう立場。だから『スルー・ザ・ミラー』っていうのは現実には起こり得ないこと。鏡の向こう側はあるけど行けない、「現実そのもの」なんじゃないかな。
弟:鏡に映ってるのは自分の像で、その像は死んでて、自分じゃないものに自分が投影されてるから自分が盗まれてるっていう気分になって、それで、あれも私、これも私、でも全部私じゃないっていう気分になってしまって、それを解決するのが法としての言葉ってことになってるんだけど。『スルー・ザ・ミラー』だとメタ的な解決の法は現れない。
兄:『スルー・ザ・ミラー』ってタイトルを俺は「自己愛を超えるというフィクション」、ありえない、起こり得ないことという意味で使ってる。
昔のミッキーで「スルー・ザ・ミラー」ってタイトルのがあって、家具があって鏡があって、なんか粘着質の鏡の中にズバーって入るの、で、そのまま左右反転した奥行きのある世界があっち側に拡がってるんだけど、あっち側では全ての無生物が生きてる。ソファに座ろうとするとソファに拒絶される。結局夢オチなんだけど。無生物だと思ってたものが生きてて、拒まれたり、踊ったりするっていうのは統合失調症的だけれど、人間が人間として成立する条件から解放されるっていう楽園的な感覚として描かれてるように受け取ったわけ。
俺:それは自己愛からの解放にも捉えられるけどな。
兄:イメージとしてはね。自己愛でしか語れないということから解放されたいという願いを込めたタイトルではある。こんな見栄えだけどやっぱり街中で鏡に映る自分を見てしまうわけよ。地獄だよね。自己像からの解放はパラダイスよ。他人の音も無生物じゃなくて、自分じゃないものと共に生きて、一筆書きの曲をやるっていうことだよね。だから自分じゃない。団体芸としての美しさをそのまま受け入れるっていう自己愛からの解放がある。ある種の正しさ、健康への方略、というものを今回は信じてやってる。
弟:自分が失くなるっていう意味が、自分も他者も失くなるってことじゃなくて、群れになれるときがある。
俺:内と外の輪郭が消失する瞬間だ。
兄:デュオニュソス的な熱狂とも言えるね。いま人間関係の倫理で言うと、バウンダリーが優先されているわけじゃない? つまり境界線、私は私、あなたはあなたってのがいちばん倫理的なことで、やっぱりいま世の中をまともに生きてくってルールは知性も含めて、それはそれ、これはこれ、って言えるってこと。そういったものに対するデュオニュソス的なものの勢力範囲を拡げたいという意識はある。俺はデュオニュソス芸術ってのは例えばクラブのなかに閉じ込めておくものではないっていう意識があって、デュオニュソス芸術やってる人が喋る機会が少ないのは寂しい。
弟:プレーヤーが喋るってこと?
兄:プレーヤーが喋るっていうか、最近はむしろインタヴューの場に出てきてしまったらそういうものを司ってる人間として出てくるんじゃなくて、喋る用のアポロン的な知性を持ってでてくる。デュオニュソス的なものとアポロン的なものがミックスされた状態で人前で喋るのは、女の人の方がいまは長けていて、自然な言葉で、自分と他人との間を厳密に線をひかずに理性的な状態で出てこれる。それこそコムアイなんかその代表格。基礎教養という重力と、なおかつ踊りで重力に抗えることの美しさ。でもそれをできるのが女の人ばかりなのが寂しい。俺なんかが、ガキだった頃に女性のメンヘラ芸能を享受したという記憶は強いんだけども、いまや女の人のメンヘラ芸能の時代はとうに終わっているわけよね。
俺:今回は言葉を使わないヴォーカリスト、楽器を弾かない演奏者である君らがある種エンドンの象徴だと思って声をかけたんだけど。
兄:関係性がそうさせてる。俺がこういうことやってるのはエッくんがいるからだし。エッくんがいなかったら恥ずかしげもなく歌詞書いてたかもね。
俺:え〜(笑)。
兄:いや、そりゃそうだよ。身内のなかで俺は文章書くのいちばんじゃない。いちばんのことだけを結晶化させたい。俺の取り柄は興奮すること、要はエモーション、情動的であることと音楽の関係にまつわる何かのほんの少しを体現したいだけ。だから言葉とは遠いもの、むしろ反対のものかもしれない。
弟:言語=法、形式だとすると、(たいちゃんの言う)情動とか興奮を形式が殺すのか、あるいはそれらを助長する武器なのか、それが個人的なテーマかな。形式を共有しないと他人とは通じ合えないけど、単なる情報のやり取りならバンドやイカれた文章を使う必要はないよね。でも、靄のような、「神秘的な隠された真実」とかはどうでもいいっていうかキモい。裏に崇高な真実が隠れてるんじゃなくて、即時的、即自的に、表面化する効果がエモいかどうか。それは形式の後に現れる自然だね。退行の対象の、もともとあった自然とは違う。やっぱり天然の天才が無垢な気持ちで自己実現するアートっていうのは、俺らには無理だし、つまらないものだと思う。そうじゃなくて、コードやリズム、音色っていう選択可能な意匠=形式を使って、この”新しい自然”を表現できるかどうかだと思う。それが新しい形式を生産することになるというか、更新するというか。
俺:既存の形式を昇華する楽しみはある。そこからは絶対に逃れられない。バンドだろうと一人だろうと常に表現を考える上で立ち上がる問題じゃない? 非音楽的な部分への挑戦っていう欲求が最優先だけど、所謂伝統的なルールを踏襲した時に自分の中に湧き上がる高揚感は絶対に否定できない。だからリスナーとしての感覚は引きずるよね。
兄:引きずるけどもただただ受け手として演る側にいるわけにはいかない。お客さんがバンドやってるってことになっちゃうから。エモい音楽を聴いてエモくなってる自分たちのことをエモとか激情って標榜するのはお客さんがライブやってるように見えるんだよね。
弟:リョウくんが言ってるような、0が1になる変換行為中に価値が表出するっていうこと、それは新しい形式から情動が生稀るっていうことだと思う。エモコアがやってんのは既存の形式をそのまま飼い殺しにして、抑圧された昔の記憶を解放するとか、そもそも存在してた自然に退行するとか、そういう暗〜い後ろ向きな欲望。自然と合一するのは無理だし、退行だから。そんな状態、あった試しはないんだしね。そもそも。現状に満足できない感傷的なのに不感症な連中が、過去に遡行して妄想してるだけの「お噺」。
兄:その「お噺」があるとされることがフィクションだし、いま風に言うとポストトゥルースじゃない? でもある意味本当の自然との合一はあると思うよ。それは退行なんじゃなくて、今でしょ。今この瞬間と合一してれば、それが自然との合一。だって過去に退行して、人間が自然だと思うものへの合一ってある種保守じゃない。今の現実と、時間的なものを超えてこの瞬間と合一するってのが自然との一体化なんじゃないかな。森とか木とか水のことじゃないから、自然って。そういう発想自体が保守だよ。
俺:でもそれもエモと繋がるんじゃない? だってエモって大地讃頌的なリリックのバンド多いじゃん(笑)。
兄:人間の感情自体をそういうものに措定してるってのが保守的だよね。
超基本的過ぎて、昔はくだらないと思ってたけどヒア&ナウみたいな感覚から今の日本は離れてるよね。
俺:具体的には?
兄:保守的になってるってことじゃない? ある種の正嫡性? 過去から続くものの良さとかさ、そういったことを口にしがちだよね。そもそも身体性に正しさを担保すること自体が保守なわけよ。
俺:極論キタ。
兄:極論大事。ブルース・リーが言うじゃない、考えるな、感じろって。あれって良いことのように言うけど保守の原則だから。だからあれは俺の超嫌いな言葉。俺は感じるな、考えろ、お前らバカなんだからって思うよ。感じたら、相手も自分ってことになっちゃうから。一個いい話があるよ。ロフトプラスワンで石田さん(ECD)が観客から「在特会がどういう人間だと思いますか?」って質問されて「分析しない」って答えたの。この発想は大事で保守ではない。間違ってるから切るだけの父性による切断だよ。石田さんは在特会のなかに自分がいる可能性があることをわかってて言ったんだよ。だから分析しないと。それはある種の『スルー・ザ・ミラー』、ルールそのものの正しさ。だから母性と父性って対にはなってるよ。1枚目が『MAMA』で今回が父性で、ある種の切断があって、ノイズがもう全能感もなければ、夢も見れない、そして曲が曲らしくなって。俺もエログロナンセンスのサブカル青春を送ってきて、弱者がぶん殴られたり殺される映画のシーン観て、横にいる彼女にコレいいね! とか言っちゃってきたわけじゃない(笑)? そこは、あんまり言いたくないけど、ゾーニングのソフト入れたみたいな感覚があって。成長って言葉は使いたくない、ルールを知る=成長じゃないでしょ? 父性だよ。父性を知るってことは男子だと成長って言葉で言われがちだけど、父性を知るか、母性を知るか、単にそれだけでいい。成長も成熟もどうでもいい、頭が良くなるか、良くならない。だから、エッくんがよく使う言葉としてアンチ・ビルディングス・ロマンていうのがあるじゃない?
弟:そうだね。
俺:アンチ・ビルディングス・ロマンってのはこういった音楽の最大のテーマではあるよね。
兄:俺たちはそれを真っ向から取り組んでいるつもりです(笑)。成熟っていう命令とか、成長物語を生きなきゃいけないことに対してアンチがある。
俺:(年齢に関係するような話が出てきたから言うけど)世代論的な話はしたかったんだ。でもそれは友達の関係になる以前に直感したことが俺の中であって。エッくんが出してくる文章しかり、それからヴィジュアル・イメージ、君たち自身が作ってないものもあるけどさ……
兄:ほとんど作ってないよ。
俺:初めてエンドンの顔のステッカー見たときに……
兄:あ、あれは唯一俺で。平野くん(ドッツマーク代表)が並べてくれた。
俺:あれ見たときにシリアルキラーが描く絵だって思ったの。そこに狂気を感じたわけじゃないけど、やっぱり少年Aとか、僕らと同世代の猟奇的な事件のイメージとオーヴァーラップしたんだよね。これ描いた奴は絶対ヤバいなって、サイコパスだって(笑)。

兄:あれはペルー人のモンタージュなんだよ。
弟:少年Aの絵はお手製の神様を作るってことだったよね?
兄:エンドンっていうのもお手製の神様の名前だよね。
俺:エンドンって仏教用語かなんかの円頓じゃないの?
兄:それは天台宗の円頓だよね。完璧で超早いって意味だよね。確かあの世とこの世の間の魂を移動させるものっていう意味もあるし、エンドンは色々あるよ。折り紙用語で……
俺:折り紙用語(笑)!?
兄:別に折り紙用語ってわけじゃないけど、紙の右端と左端あるでしょ? それを相手の前でこうする(実際に紙を折って)のを「END ON」ていう。
俺:マジかよ(笑)
兄:最高でしょ?
弟:コンヴァージと一緒だよね?
兄:違う。あれは遠近法的な収束、消失点のことでしょ。だから「END ON」はもっと雑だよ。右翼の端っこと左翼の端っこを折ってその隣接線を相手の前にセンターとして見せて「これブルータルじゃない?」ってくらい雑(笑)。あとはベケットの『マーフィー』のなかで主人公マーフィーのチェスの相手をする統合失調症の患者もエンドン。まあいいやとくに意味ないよ(笑)
俺:世代論に戻ろう。
兄:少年Aとバスジャックのネオむぎ茶と秋葉原通り魔事件の加藤は全部同い年だよね、昭和57年、1982年生まれだから。少年Aのああいうある種のすごい強烈なキャッチーさとわかりやすさってことに対して、禁欲を強いてきたわけじゃない? それをやっぱり分散させてみんながちょっとづつ昇華させてるってのは思うんだよね。最近でた彼の本は退屈で汚らしい印象を受けたけどね。
俺:昇華させてる人は少ないんじゃない?
兄:あの事件にまつわることを昇華してるわけではないけど、一部のヴィジュアル系はすごくそういうセンスがあって、加害欲求みたいなモチーフに拘るバンドもいたよね。今はその辺りをすごく禁欲的にならざるを得ない。例えば黒夢なんかは生きていた中絶児……とかそういうタイトルじゃん? あとはやっぱり好きな子を殺しちゃう、なんで好きな子殺しちゃうの!? 俺らがガキの頃のそれ系の歌詞ってやっぱ基本的に好きな子殺しちゃうからさ(笑)
一同:(笑)
兄:で、今回のツアー・タイトルをサディスティック・ロマンスというタイトルにした。自分で自分をモヤモヤさせることを選んだわけ。世のなかの構成要素は多ければ多い方がいいと思ってるから、人を傷つけたいって気持ちは世のなかにない方がいいかって言ったら、俺はあった方がいいと思う。実際に表現されてしまうと別の問題になるという考え方。あくまでゾーニングってこと。人をブン殴って回るツアーでもないし、各地をレイプして回るツアーではないけど、今回のツアーは世代論的にもタイトルをサディスティック・ロマンスにしたかった。やっぱりある種の「問題」を扱っていきたいという意識がある。
俺:エンドンがエクストリーム・ミュージックであることの必然性ってそこにあるよね。
兄:あるある。ある種の加害性なんだろうね。私とあなたは違うんです……とかっていうような意識からくる加害性とか、出生を恨むとまでは言わないけど、そういうものとの折り合いのつけ方をただの抑圧にしない。
俺:ぶっちゃけいまのエクストリーム・ミュージックのシーンがどうとかは俺はどうでもよくて、単に音楽以外の文脈を音楽にこれだけふんだんに盛り込んでる日本のバンドってエンドン以外にそんな知らない。しかも盛り込まれてる文脈が一方向的なメッセージじゃなくて拾った人が好きに膨らませられるような投げかけになってるのが重要かなと。
兄:情報量を多くしようとはしてる。ある種の「ノイズ」 っていうか。ノイズの意味性=不可能性ってのはもうどうやってもそれこそが不可能だから。過剰性なんじゃないかな。たくさんの情報が乗り入れまくってる、そういう意味でのノイズ。何かにとって整合性のあるものは、別の何かにとってはノイズ(雑音)になってしまうという関係性を整理しないでそのまま置いてあるというか。だからまぁ本当はノイズなんて言葉使う必要ないんだけど、やっぱりエッくんが小説も発表すれば、ギターソロもあるし……
俺:そこに最高のギターソロがちゃんと入ってるってところに海外に輸出して文脈を理解されなくても音楽的な強度で勝負できるってことだよね。
兄:それはあるね。
俺:……でやっぱり改めて俺が思うのは俺はハイドラヘッド・レコーズ(元アイシス/のアーロン・ターナーのレーベル)のおかげでグローバルな視点で活動できるようになったし、俺の世代が影響を受けてきた、そういった音楽以外の文献をふんだんに持ち込んだ音楽を提供してくれて視野を広げてくれたエクストリーム・ミュージックってハイドラヘッドだし、君たちがそこからリリースするってことに必然性を感じる。
兄:ハイドラヘッドのインテリジェンスって、俺が19くらいの頃だけど、憶えてるよね。ギリシャ神話を使うとか、フーコーとか。それでいまインタヴュー録ってるお前がハイドラヘッドと関係が深いってのもあるし、不思議なもんだよね。でもまさか、こういった形の階段を登るのが俺たちだっていうのは当時は思いもしなかったよ。もっと暗くてアヴァンギャルドで前衛的なことをやってる未来を考えてた。こういうロック・バンドをやるとは思ってなかった。だけどずっと学んできたことってすごくシンプルなロックの歴史を正当に評価するってことだから。例えばT・レックスを特権的に思うのは親から貰ったものなのかもしれないけど、あるとないとでは全然違って、バンドやるってことが友だち同士の音源の貸し借りからはじまった話じゃないっていうか。白人が黒人のパワーに触れて、ブルースと衝突してってところから自分たちの親の文化もはじまってて、それと同じとこから自分らのロックへの考え方もはじまってるというのはすごく重要なことじゃない? コウキと俺がストーンズとツェッペリンを偏愛してることは、むしろこのアルバムでは如実に表れてるんじゃない? 時代的に身の回りにブラック・サバスみたいなバンドが多すぎたってことへの反動もあるけども。
俺:この後アルバムが海外でハイドラヘッドからリリースされて、ロック・バンドとしての正当な評価は得られると思うんだ。だけどそれに+してエンドンが内包する膨大な文脈みたいなものがちゃんとインターナショナルに変換されたら君たちはまだ誰も到達してないステージに上がれるんじゃないかな? メタル・マーケットとかってアメリカやヨーロッパには日本の比じゃないほど大きなものがあって、そこでも充分やってけるんだけど、少なくとも君らはそれじゃ満足しない気がする。
兄:しないしない。メタルの延命措置に躍起になってはいるけど、メタル・シーンなんて端的にダサっとしか思ってないもん。膨大な文脈と言えば、映像とテキストと絡む作品をもっと作りたいんだよね。引用の化け物になりたいのよ。俺はやっぱりニヒリストだからさ、自分なんかどうでもいいわけよ、ゴミだから。
俺:アメリカンな発想だな……
兄:そうね。消費の化け物でもあるしね。俺たちがやってることってやっぱりメイド・イン・オキュパイド・ジャパンってことじゃないですか、完全に。照り焼きバーガーみたいなグローカルメニューしか作れませんみたいな。だからひとまずは引用の化け物になりたいなって思うんだよね、文章もそうだし、映像もそうだし、例えば映像のカットアップ、コラージュにナレーションで他人の文献も、自分たちのテキストも、人の音楽も自分たちの音楽もブチ込んだ4時間くらいのDVDを作りたい(笑)。
弟:俺ら、っていうかこういうジャンルのプレイヤーって、すげぇアメリカナイズドされてるから、反米っていう主張をするときに、じゃあオリエンタルな意匠で対峙しようっていうのは無理なんだよ。アメリカの消費文化をコラージュするのがいちばんいいかなっていうか、それしかできない。固有のアジア的身体性、精神性、それももともとあったはずの偽装された自然だね、そういうものに退行したらテロリズムになっちゃう。じゃなくて、内戦。内側から、外に出る。
兄:DVDとCDが結構な枚数で入ってるような箱物ができたらいいよね。膨大な情報量で攻めるってのを本当にいつかやってみたい。
弟:質って稀なものだよね。
兄:質って全部固有のものだから、量に還元した時に批判されるだけで、それとはやっぱり別の話で圧倒的な量の引用の塊で、幽霊が中に大量にいるようなスクラップの塊みたいな、ヒプノシスがやったアンスラックスのストンプ442のジャケットのアレみたいな化け物を作るってのはやっぱ野望だよね。
俺:次の作品じゃないですか。
兄:いや次の次の次くらいで……
俺:いやだめでしょ。トリロジーだから。3が物すごく重要。
ENDON / THROUGH THE MIRROR (Daymare Recordings)
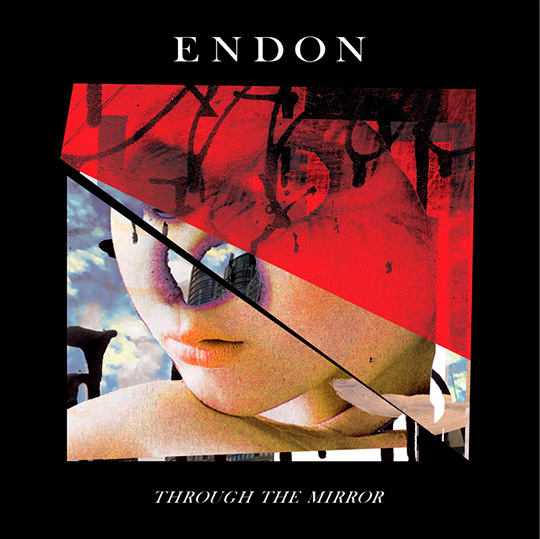
ENDON "SADISTIC ROMANCE TOUR 2017"
w/DJ 行松陽介
3/11(土)東京: 新大久保Earthdom (ワンマン)
3/18(土)名古屋: 今池Huck Finn
3/19(日)大阪: 東心斎橋Conpass