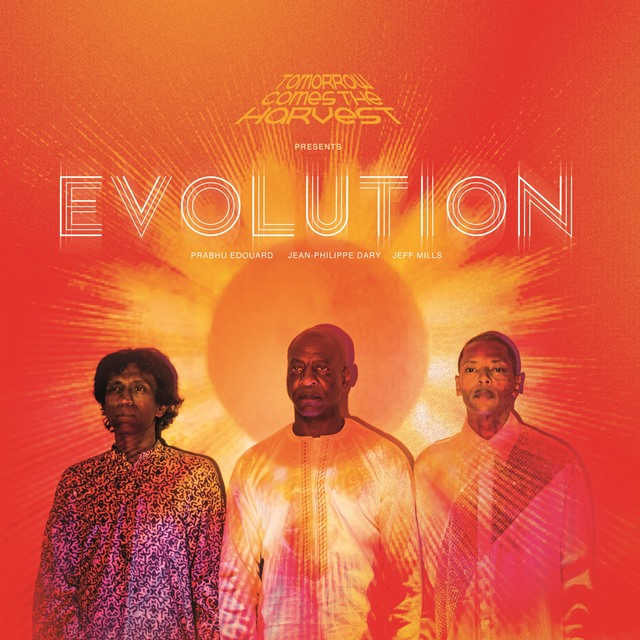1961年8月ニューヨークはヴィレッジ・ゲイト、ジョン・コルトレーン・セクステット(エリック・ドルフィー含)完全未発表ライヴ音源発掘。そんな令和一大ジャズ・ニュースに触れて「待ってました」と色めき立つ人が、はたしてどれくらいいるだろうか。狂喜する往年のジャズ・ファンを横目に、それがいったいどれほどの意味を持つことなのかよくわからぬまま、とりあえず様子を見るか、あるいはすぐに忘れてしまうか、ようするに大して関心を持たない人たちが大勢目に浮かぶ。そんな諸兄諸姉に対して説得力のある何事かを訴えるのはなかなか難しそうであるし、かといって往年のジャズ好事家諸賢にとり為になるような何事かを私なんぞが書けるはずもなく、さて。

John Coltrane with Eric Dolphy
Evenings at the Village Gate
Impulse! / ユニバーサル
■通常盤(SHM-CD)
Amazon
Tower
HMV
disk union
■限定盤(SA-CD~SHM仕様)
Amazon
Tower
HMV
disk union
ともあれいまさら基本的な情報は不要であろう。なにしろいまや岩波新書の目録にその名を連ねるほどの歴史的偉人である。その岩波新書赤版1303『コルトレーン ジャズの殉教者』の著者であり世界有数の “コルトレーン学者” たる藤岡靖洋は、『The John Coltrane Reference』(Routledge, 2007)というコルトレーン研究の決定版と言うべき巨大なディスコグラフィーの編纂にも関わっている。コルトレーンの足取り・演奏データを詳細に記したこの本を眺めていると、「when you hear music, after it’s over, it’s gone in the air, you can never capture it again(音楽は聴き終わると空中に消え去り、もう二度と捕まえることはできない)」という呪文のようなエリック・ドルフィーの言葉を思い出す。ようは録音されずに空中に消えた演奏のほうが録音されたものより圧倒的に多いという当たり前の事実に改めて直面するわけだが、したがって録音されているという事実だけを根拠に、今回発掘された1961年8月ヴィレッジ・ゲイトでの演奏に何か特別な意味を持たせる理由はないこともまた、肝に銘じておくべきことなのかもしれない。ごく一部の(ほぼ関係者に近い)人を除けば、「待ってました」というわけではなく不意の棚ぼた的サプライズ発掘音源であり、つまりコルトレーンが日常的に行なっていた数あるギグのほんの一コマが、当時たまたま新しい音響システムのテストの一環としてリチャード・アルダーソンによって録音されており、永らく行方不明になっていたそのテープが近年たまたまニューヨーク公共図書館に眠る膨大な資料のなかから発見されただけの話である。発掘音源をめぐるいたずらな伝説化を避けるなら、そういう物言いになる。
ジョン・コルトレーン(ss, ts)、エリック・ドルフィー(fl, bcl, as)、マッコイ・タイナー(p)、レジー・ワークマン(b)、アート・デイヴィス(b)、エルヴィン・ジョーンズ(ds)のセクステット、つまりこの時期数ヶ月間にわたって実験的に試みていたツー・ベース編成による全5曲。“My Favorite Things”(①)、“When Lights Are Low”(②)、“Impressions”(③)、“Greensleeves”(④)といった定番のレパートリーが並び、ドルフィーが編曲したことで有名な『Africa/Brass』(1961年5月録音)収録曲 “Africa” のライヴ録音(⑤)は他のどこにも残されておらずこれが唯一の記録である。すべての曲が10分を超え、“Africa” に至っては22分。この時期に顕著となるこうした演奏の長尺化は、コルトレーンの音楽の発展にとって不可避の事態であり、従来のコードチェンジに縛られずにひとつのハーモニーを延々と展開し続けることの可能性を示していた。とりわけライヴ演奏は一種のトランス状態の渦を作り出すかのごとき様相で、当時は「ジャズの破壊」とまで言われたコルトレーン=ドルフィーの剥き出しのソロがここでは存分に堪能できる。
ふいと個人的な話になるが、私が初めて買ったコルトレーンのアルバムは、『That Dynamic Jazz Duo! John Coltrane – Eric Dolphy』(1962年2月録音)と題された見るからにブートレグ感が漂うレコードだった。実際おそらく1970年頃につくられたブート盤である。中古で確か500円。安っぽいモノクロ・ジャケットの裏面にはなんとコルトレーンの直筆サインが油性のマジック(つまり魔術的な力)で書き込まれており、すわ!歴史がねじれる不思議!とひとりひそかに喜んだ。私が高校生の頃なので2003年とかそのあたりの話であるが、当時巷では「スピリチュアル・ジャズ」と呼ばれる古い=新しい潮流が盛り上がっていた時代である。クラブ・ジャズ/DJカルチャーのシーンが発端となったスピリチュアル・ジャズなる言葉が指し示していたのは、簡単に言うと「コルトレーン以後のジャズ」だった。どことなく神秘的だったり民族的だったりアフロセントリックだったり、場合によっては宇宙的だったりする崇高なムードを纏ったグルーヴィーな黒いジャズが対象で、代表格はファラオ・サンダースやアリス・コルトレーン、アーチー・シェップ、そして〈ストラタ・イースト〉や〈ブラック・ジャズ〉、〈トライブ〉などといったレーベル、またはそのフォロワーが定番のネタであり、スピリチュアルを合言葉に一気に再評価が進んだ。コルトレーン「以後」ということは当然ジョン・コルトレーンその人も含まれる、というよりまさにコルトレーンこそがスピリチュアル・ジャズの “元祖”、“伝説”、“永遠のアイコン” であるとして崇められてはいたが(参考:小川充監修『スピリチュアル・ジャズ』リットーミュージック、2006年)、実際の主たるところはその「後」のほう、コルトレーンの「子どもたち」だった。なぜならコルトレーンはとうの昔からビッグネームであったし、一部のDJにとってはグルーヴがレアであることのほうが音楽やその歴史的文脈より優先されたからである。
個人的な話を続けると、歴史捏造油性マジカル・ブート盤の次に買ったのが『Olé』(1961年5月録音)だった。表題曲におけるコルトレーンのソプラノサックスが「アンダルシアの土埃のなかで舞っているジプシーの肉体感覚に近いように聴こえる」と書いたのは平岡正明だが(『毒血と薔薇』国書刊行会、2007年)、このジプシー的感覚あるいはアラブ的感覚はスペインめがけて地中海を3拍子で突破することによって培われ、おそらくその後のコルトレーン流の高音パッセージをかたちづくる最も重要な要素であるはずだ。螺旋状に延びていく並外れた旋律=フレージングは、隣にエリック・ドルフィーを擁することでより際立ち強化・装飾される。コルトレーンのグループにドルフィーが加入していたのは1961年5月から翌62年3月までの約10カ月間。『Olé』の他に『Africa/Brass』、『Live At The Village Vanguard』、『Impressions』などがあり、ライヴ録音のブート盤を含めるとそれなりの数が残されている。この頃の “中期” コルトレーンはスピリチュアル・ジャズ隆盛の時代にあってはあまり顧みられていなかったようにも思うが、“Olé” や “Africa”、また “Spiritual”(『Live At The Village Vanguard』収録)といった比較的長尺の楽曲は、モーダルな “単調さ” ゆえの “崇高さ” があり、明らかに後のスピリチュアル・ジャズを預言している。『A Love Supreme』(1964年12月録音)や『Kulu Sé Mama』(1965年6、10月録音)を差し置いて、どうやら私はこのどちらに転ぶかわからない危うさ、神に対する卑屈と人間的な尊厳を兼ね備えた “中期” コルトレーンがいちばん好きだった。「ファンキーズムから前衛ジャズにジャズ・シーンがきりかわった前後から、卑屈さや劣等感を額のしわにほりこんだ黒人くさい黒人がジャズの世界から減り、人間的な尊厳にみちた人物が数多くあらわれた」(平岡正明「コルトレーン・テーゼ」『ジャズ宣言』イザラ書房、1969年)。言ってみればコルトレーンはその中間のような、というより明らかに相反するふたつの性質を有しており、かの有名な「笑いながら怒る人」ならぬ、キャンディーをペロペロ舐めながら神妙な面持ちの人、導師の顔をした弟子キャラ、といった具合の、まるでレコードにA面とB面があるような二面性である。それならコルトレーンの毒血はAB型か。
にもかかわらず片面をなきものとされ、生前より聖人的尊厳を投影され、死後さらに伝説とされ、まるで神様のように祀られている状況について、コルトレーン本人は少なからず戸惑いを感じているようだ。「自分でも考えられねごどだ」──1975年、恐山のイタコに “口寄せ” されて地上に舞い降りたコルトレーンは津軽弁でそう語った。FM東京「ジャズ・ラブ・ハウス」という番組で放送されたこのときの口寄せ実況はなかなか傑作で、しまいにはコルトレーンの親父さんまで降霊してくる始末(「まさかあのようにジョンが有名になるとは思わなかった」云々)。書き起こしが『季刊ジャズ批評』誌46号(阿部克自「宇宙からきたコルトレーン(恐山いたこ口寄せ実況)」)に掲載されているので、ご興味のある方はぜひ。
口寄せは英語だと necromancy に相当するか、あるいは conjure でもいいかもしれない。たとえば『マンボ・ジャンボ』で知られる作家イシュメール・リードにとって最重要キーワードのひとつが conjure であったことを考えると、(ジャズの下部構造としての)ブルース衝動は死の概念と不可分であり、そこにはすでに何らかの魔術的な力が内在していることに気がつく。黒人霊歌以前のニグロ・スピリチュアルすなわちヴードゥーの精霊か、それこそ奇病ジェス・グルーの発症を促す何らかの魔法か。かくして、キャプチャーされることなく空中に消えた無数のサウンドに、大西洋に沈んだ無数の死のイメージが重なる。まずはレコーディングされていた奇跡を真摯に受け止めるべきなのだろう。録音は呪文であり救済である。1961年8月ニューヨークはヴィレッジ・ゲイト、ジョン・コルトレーン・セクステット(エリック・ドルフィー含)完全未発表ライヴ音源発掘。アフリカ大陸へ延びるテナーサックスのミドル・パッセージに、いまだ見ぬ過去と失われた未来が立ち現れる。もうしばらく、ジャズは「コルトレーン以後の音楽」でしかありえないことを確信する。