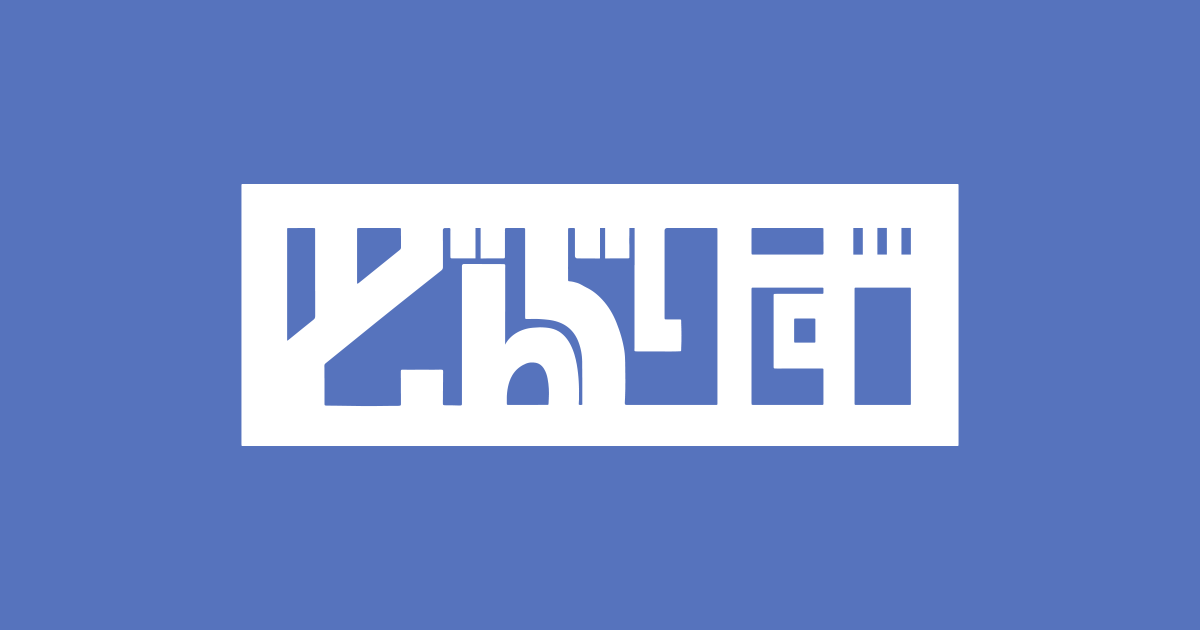Olive Oil との共作やユニット U_Know としても作品を残す MILES WORD と、昨年 DJ BUNTA とのミックステープをリリースした SHEEF THE 3RD。このふたりのMCから成る神奈川は藤沢のヴェテラン、BLAHRMY がセカンド・アルバムを発売する。オリジナル・アルバムとしてはじつに9年ぶりだ。
プロデュースは〈DLiP Records〉の NAGMATIC、客演には盟友 DINARY DELTA FORCE の RHYME BOYA、Rahblenda(calimshot+Fortune D)、そして仙人掌が参加。現在、収録曲 “Woowah” のMVが公開中だ。チェック!
MILES WORDとSHEEF THE 3RDによるユニット、BLAHRMYによる実に9年ぶりとなるセカンド・アルバム『TWO MEN』、本日ついにリリース! リリースに合わせ、"Woowah" のMVも公開!
神奈川は藤沢をREPするMILES WORDとSHEEF THE 3RDによるユニット、BLAHRMY。2010年に自主制作での1st EP『Duck's Moss Village』、〈DLiP Records〉に所属して2012年に1st ALBUM『A REPORT OF THE BIRDSTRIKE』をリリース。その後はBLAHRMYとしての活動と並行して個々の活動にも力を入れ、MILES WORDはソロでのEP『STATE OF EMERGENCY』やNAGMATIC、Olive Oilとの各コラボ作を、SHEEF THE 3RDはソロでの1st ALBUM『MY SLANG BE HIGH RANGE MOSS VILLAGE』やRHYME&B(DINARY DELTA FORCE)、DJ BUNTAとの各コラボ作をリリース。数々の客演もこなし、BLAHRMYだけでなく各々でも名前を広めていったもののBLAHRMYとしてのまとまった作品は2014年のEP『DMV2-TOOLS OF THE TRADE-』のみで近年はアナログやデジタルでの単発のリリースに留まっていたが…実に9年ぶりとなるセカンド・アルバム『TWO
MEN』をついにリリース!
客演には〈DLiP Records〉の同胞DINARY DELTA FORCEからRHYME BOYA、DINARY DELTA FORCEのcalimshot a.k.a. Cally WalterとFortune DのユニットであるRahblenda、そしてMONJUから仙人掌が参加し、全曲を〈DLiP Records〉のNAGMATICがプロデュース。
また、リリースに合わせて "Woowah" のミュージック・ビデオも公開!
* BLAHRMY "Woowah" - MV
https://youtu.be/CHN7fvLMOqw

[作品情報]
アーティスト: BLAHRMY
タイトル: TWO MEN
レーベル: DLiP Records
配給: P-VINE, Inc.
発売日: 2021年6月15日(火)
仕様: CD/デジタル
品番: DLIP-0068
Stream/Download/Purchase:
https://p-vine.lnk.to/V5uMSTgQ
[トラックリスト]
01. Woowah
02. B.A.R.S. Remix feat. RHYME BOYA
03. Skit #Twenty-Five
04. Aliens
05. One, Two
06. Rap Up
07. Hey B.
08. Fiesta feat. Rahblenda
09. Recommen'
10. Thrilling
11. Flight Numbah
12. ASBNIK
13. Interlude #It's Tough Being A Man
14. Living In Da Mountains feat. 仙人掌
15. 続、
[プロフィール]
神奈川は藤沢をREPするMiles Word & Sheef The 3rdの2MC。
2010年 1st EP「Duck's Moss Village」を自主発売でリリース。
〈DLiP Records〉に所属し2012年 1st ALBUM「A REPORT OF THE BIRDSTRIKE」リリース。
この2枚の音源をきっかけに全国へ活動を広めていくことになる。
2014年にEP「DMV2-TOOLS OF THE TRADE-」をリリース後は互いにソロでの活動を活発化。
2014年、MILES WORDはNAGMATICとの共作「INPOSSHIBLE」をリリース。
そのLIVEツアーで出会ったOlive Oilと共に2016年、ジョイントALBUM「Word Of Words」を発表。
Olive OilとのユニットU_Knowを結成し、2018年に2作目となる「BELL」をリリース。音楽性の幅を広げ、更に進化したスキルを見せつけた。
2020年には緊急事態宣言中に制作したEP「STATE OF EMERGENCY」をリリースし常にその歩みは留まることを知らない。
対して、SHEEF THE 3RDも2016年にRHYME BOYAとのJoint作品「D.O.B.B.」をリリース。
そして、2018年DJ LEXプロデュースにて1st ALBUM「MY SLANG BE HIGH RANGE MOSS VILLAGE」をリリース。
2020年にはDJ BUNTAとのジョイントで新録音源中心のMIX TAPE「Duck’s Juice Mix Vol.6」を発表し、更に深みが増したリリカルなライムを披露している。
ソロとしての活動を着実にこなしつつも、BLAHRMYとしての活動も継続。
クルーとしてはSingle Vinylを定期的にリリースするに留まっていたが2021年6月15日、9年ぶりに2nd ALBUMをリリース。