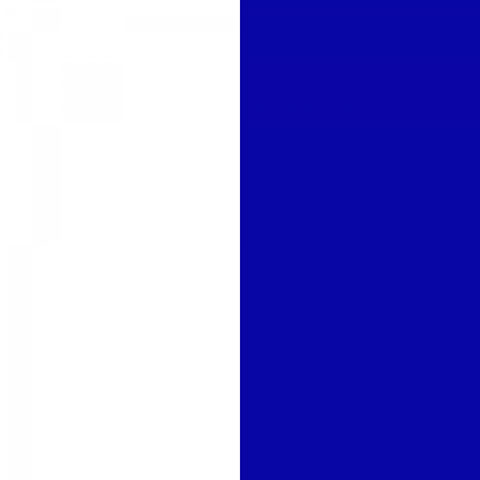demolition。取り壊し。破壊。打破。解体。爆破。そのタイトルにふさわしく、ディストーションで歪みきったドラム・サウンドでブルータルに幕を切るMartin Revのソロ・アルバム最新作。
もはやSUICIDEの新作を望めなくなった今、ソロと書くのも蛇足でしょうか。A面B面ともに17曲ずつ、1分前後の曲が並ぶ怪作です。彼のこれまでの作品群が、多種多様なソングライティング能力を既に証明していますが、これまでは比較的アルバム単位で楽曲の大まかな傾向を揃えていた節も見受けられました。しかし今作は非常に混沌とした内容です。そして冒頭の“Stickball”のように歪みきったドラム・サウンドはこれまでになかったもの。何かがこれまでとは違う。そう感じずにはいられません。
その混沌とした内容の中でも、主にフィーチャーされているのは映像作家Stefan Roloffとのコラボレーションの成果をソロ・アルバムで披露したと思しき、亡き妻Mariに捧げられた前作『Stigmata』の流れを汲んだ楽曲です。シンセ・オーケストレーションと声だけで壮大な曲や優しいメロディーにあふれた曲を構成していた前作。Stefanとのコラボレーションをチェックしていなかった僕は『Stigmata』が出た時点でその作風にとても驚きました。そしてその内容とタイトルに対して、自ら十字架を模したかのようなジャケットの写真がただならぬ気配を漂わせていました。
SUICIDEとして今は亡きAlan Vegaと共に活動し、ことによるとディズニーのサントラも担当できそうなMartin。そんな彼の最新作は全体的にはサウンドトラック・アルバム的と言えそうですが、サウンドトラック・アルバムにありがちな、ひとつのテーマのヴァリエーションが様々に変奏されるのではなく、ひとつひとつの独立した楽曲が34曲収録されています。そして短い曲ばかりなのですが、アイデアのスケッチという感じがなく、プリミティヴではあるけれどもそれぞれが確固たる完成度を誇っているように感じられます。
“My Street”はお得意のオールディーズ・リファレンスなフレーズに歪みまくったディストーション・ギター(キーボードかも)でリフを弾くという、これが俺の道だと言わんばかりの格好良さ。でも2分しかやってくれませんのでループ再生をオススメします。“Into The Blue”はまたしても歪みきったディストーションまみれのドラム・サウンドが炸裂します。音を出してご家庭で聴かれる場合には、非常に迷惑な音量設定です。次にかかるとても美しい“Requiem”になると“Into The Blue”であわてて下げにいったボリュームをまた上げにいかないといけません。しかしここまで楽曲間の音楽性や音量のギャップが共に激しいアルバムもそうそう無いと思います。
“Now”は新機軸で、激しく、深いリヴァーブのかかったドラム・サウンドが、『Stigmata』の流れを汲んだ壮大なオーケストレーションと融合しています。とてもかっこいい。この曲は2分半もやってくれています。でももっと長くやってほしい。“In Our Name”はなにやら意味ありげで歌詞をちゃんと聴き取れれば良いのですが、最後に「Now you're gone」と言っているのは僕にもわかります。我々の名において。SUICIDEの事なのでしょうか。美しい“Vision Of Mari”はおそらく亡き妻の事を想って作られた曲でしょう。本当に美しいメロディーを書ける素晴らしいソングライター。3、3、7拍子のようなリズムを刻む“RBL”も非常にノイジーな音色に包まれています。
この流れでRock'n'RollなMartin節炸裂の“Creation”が来るとそのギャップにも興奮しますが、次の“Toi”がまた可愛らしい曲で、子供をあやすかのような優しさを湛えています。続く“Pièta”では優雅なメロディーが奏でられますが30秒で終わってしまい、次の“It's Time”も30秒で終わってしまいます。冒頭の“Stickball”、“Into The Blue”、“Back To Philly”、“Beatus”、“Concrete”と、ドラム・ソロがインタールードのように挿入され、主にシンセサイザー・オーケストレーションによる短い楽曲が多数収録された本作も終盤に差し掛かり、“She”ではドラム主体のサウンドにMartinの囁くような歌がのり、壮大な、しかし非常に短い“Darling”、“Excelsis”の2曲がアルバムを締めくくります。
最後の2曲のような楽曲をもっと構築した、長い組曲のようなものを作ってほしいし、David Lynchの映画をAngelo Badalamentiの代わりにMartinがサウンドトラックを担当したら面白そうだから、何かの間違いでそんな事が起こりはしないかと期待し続けていたいし、もっと彼の楽曲で驚かされたいので、まだまだ元気でいてほしいと願う僕の胸をジャケット・アートワークの1stアルバムとの相似性が妙に騒がせますが、Alanの遺作となってしまった『IT』のジャケットの「EXIT」大写しに比べれば安心できるというもの。
YouTubeで見られる最近のLive映像では、インナースリーヴの写真のように、色とりどりのカラフルでどぎつい色合いに照らされたMartinの音が、全体的にノイジーな音色になってきているのが感じられます。ウィキペディアによると彼は1947年12月18日生まれ。この情報が正しいとすると今年で70歳になる彼。老いてますますアグレッシヴになっていますが、それは78歳で亡くなったAlanとて同じ。『IT』は現行の〈Jealous God〉などのEBMリヴァイヴァル的楽曲群やインダストリアル・トラックなどと混ぜても使えるような曲満載のアルバムでした。それに比べてMartinの『Demolition 9』はほとんどの曲が1分前後、長くても2分台、短くて奇妙な曲が多く収録されたNot DJ friendlyなアルバムですが、音楽の価値は当然そんな事とは関係なく、“Requiem”や“Vision of Mari”、“Toi”などの美しい曲と荒々しい楽曲たちを壮大なオーケストレーションでつないだMartin Rev独自の孤高のアルバム。そしてこのこれまでにない荒々しさは、MariとAlanに先立たれた喪失感と無縁ではないでしょう。
先日DOMMUNEのECD 7時間特集番組でECD氏がDJの最後にSUICIDEの“Cheree”をかけていましたが、今YouTubeではMartinのソロ・パフォーマンスによる“Cheree”を見ることができます。キーボードを指ではなく拳や手の平、腕で叩くように演奏し、音階とリズムとノイズを同時に出しながら歌うMartin。長年の経験に裏打ちされた荒々しい演奏です。
ECD氏とRev氏の健康を願って、筆を置きたいと思います。