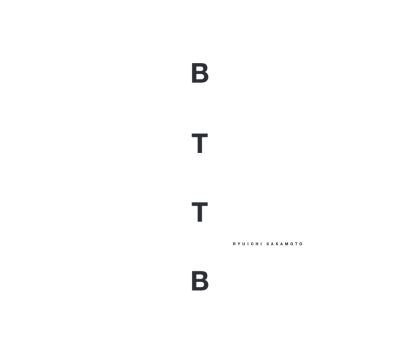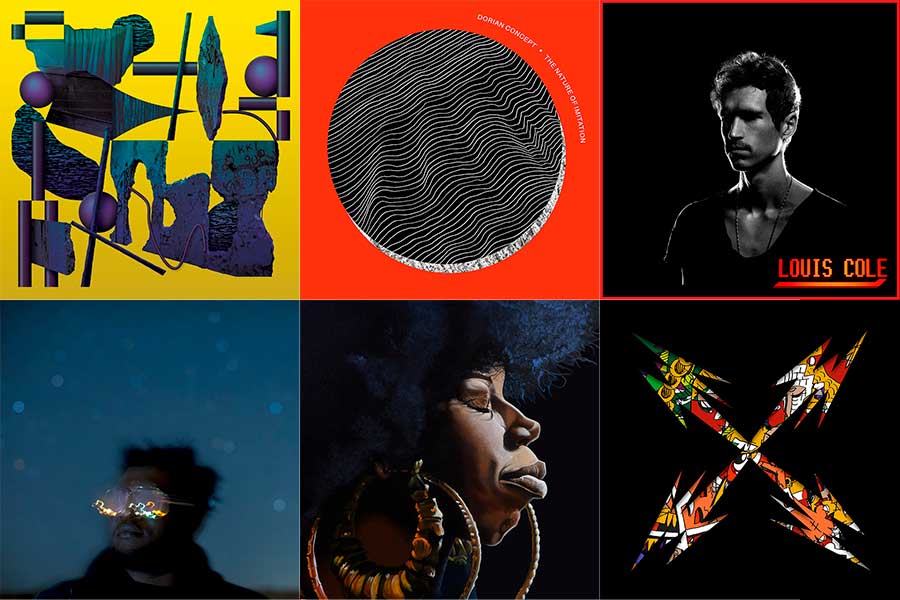数年前から軸足をソロ活動のほうに向けじはめた Phew はアナログ~モジュラー・シンセをはじめ、もろもろの機材にとりまかれ、ヘッドセットをしたその姿に私はコクピットに腰をすえた宇宙飛行士を連想したものだが、スピーカーからとびだす予測不可能な音の群はレトロな近未来感をうっちゃる独特な響きがあった。みたこともない世界とアマチュア無線に興じるさまをのぞきみるような、空間に散らばった音をハンダゴテで接着するような、音の連なりにはソフトウェア主体の音づくりではとどかない太さと強さがあり、名づけるならその呼び名はやはりエレクトロニック・ミュージックというより電子音楽のほうがしっくりくる。むろん古典的な電子音楽のセオリーに属しているというより、出てくる音が発明的なのがそう思わせるのだった。2015年の『A New World』は電子音楽の方法と歌をポップに折衷した、2010年代の Phew のドキュメントというべき重要作だが、音響の探究はとどまるところを知らず、昨年には声のみのサウンドストラクチャー『Voice Hardcore』をものしている。これはほとんど無明の荒野をひとりすすむような、その名のとおりハードコアな作品であり、未聴の方はすべからくお聴きいただくにしくはないが、ソロでの究極的な自己対話の傍らで Phew はコラボレーションもおこなっていたのである。
アナ・ダ・シルヴァがそのお相手で、彼女の名前になつかしさをおぼえた方もそうでない方も、あのレインコーツでギターとヴォーカルを担当したひとだといえば、ピンとくるであろう。メンバー全員が女性のレインコーツは70年代末の〈ラフ・トレード〉からレッド・クレイオラのメイヨ・トンプソンがプロデュースした同名のファーストで、パンクの以前と以後を截然と劃したばかりか、『Odyshape』(1981年)、『Moving』(83年)の3枚で90~2000年代を予期しながら時代のなかに雌伏したが21世紀に復活し2010年には初の来日公演をはたしている。ふたりの交流は、Phew がレインコーツの公演をサポートしたときにはじまったというが、それがいかにしてアブストラクトでありながら多彩で自在な純電子音響+ヴォイス作品にむすびついたか、Phew にその背景を訊いた。
楽器は道具にすぎないんです。それはアナもおなじ気持ちだと思います。最初に自分の身体がある、それはふたり共通していると思います。
■いまライヴではおもにアナログ・シンセとヴォイスですよね。
Phew:それとリズムボックスですね。
■そのようなスタイルでソロ活動をはじめられてから、海外でライヴされる機会が増えましたよね。
Phew:ソロ・ライヴではじめて海外に行ったのが2年前で、ポーランドのフェスでした。フェスに出演したあと、ロンドンでもライヴをしたんです。お客さんも多くて、会場もあたたかい雰囲気だったんですが、そこにアナも来てくれました。アナとはレインコーツが来日したとき、私がサポートをした縁で知り合いました。とはいえ、そのときは会うには会ったものの、話はあまりしなくて、こんにちは、くらいのものでした。震災の前の年だったとので2010年ですね。
■ロンドンのライヴで再会したんですね。
Phew:その前に私、CDRで作品を出していたんですね。それをアナに送ったらすごく気に入ってくれて、その後にできたアルバム『A New World』も送って、それも気に入ってくれて、みにきてくれたという経緯がありました。
■メールや手紙でのやりとりがあったんですね。
Phew:でも、CDすごくよかったです、といったやりとりくらいですよ。それだけで、ライヴを観に来てくれて、しばらくしたらアナから写真が送られてきたんです。「モジュラーシンセ買いました」と文章を添えて(笑)。
■Phewさんの影響ですか?
Phew:買ったのはけっこう前だったみたいですが、「いまは離れていてもファイルの交換で音楽がつくれるから一緒にやりませんか」と書いてあったんです。
■連絡が来たのは何年ですか?
Phew:2016年。なので2年前ですね。連絡が来てしばらくして、彼女が録りためた音が届いたんです。たしか5、6曲。そのなかの何曲かに音を重ねたのが最初でした。
■その曲はアルバムに採用したんですか。
Phew:はい。1曲目の“Islands”、6曲目(“Here to there”)もそうかな。けっこうちゃんとした曲になっていました。それまでアナに電子音楽をつくった経験があるかとか、つっこんだ話はしたことはありませんが、アナはモジュラー以前にシンセサイザーはもっていたみたいです。前のソロのアルバムは自分でミックスもやったといっていましたから。
■チックス・オン・スピードのレーベル〈Chicks On Speed Records〉から2004年に出した『The Lighthouse』ですね。
Phew:機材やエンジニアリングにもともと興味をもっていたのだと思います。
■音源にたがいに反応し合ううちに曲になっていったということですか。
Phew:とっかかりはアナが録ったものに私が音を重ねていった曲です。アナから来たものに音をかさねて、そのラフミックスをアナに送り、足りない部分を補い、それをまたこっちに送り返してもらう。“Konnichiwa!”とか“Bom tempo”は私が音を録った音源にアナが音を重ねています。往復1~2回でだいたいの曲ができました。作業自体はすごく早かった。
■曲によって主導権がちがう?
Phew:主導権というより、きっかけですね。どういうものにするというのも、ことばでのやりとりはなくて、いきあたりばったり(笑)。とはいえ、アナはロンドンに住んでいますけどポルトガル人で、私は日本人。おたがいちがう文化をもっていて離れたところに住んでいるのは最初から意識していました。わりと早い段階でアナにこのコラボーレションのテーマはコミュニケーションということはいったと思います。それでおたがいの言語をとりかえたんです。私がポルトガル語でアナが日本語をつかうという図式ができました。
■Phewさんはポルトガル語ができるんですか。
Phew:できるわけないじゃないですか(笑)。でもノリはよかったし早かったですよ。おたがいにパンク出身だから(笑)。
[[SplitPage]]だれがこの曲をつくったとか、そういった事態は避けたかった。記名性で詮索するのではなく、たがいにすごく離れたところにいて、ことばで説得するのではなく、その中間でなにができるか。そういったテーマが私にはあった。
■世間的な見られ方としては、レインコーツのアナ・ダ・シルヴァとアーント・サリーのPhewさんのコラボレーションというのがまず最初にくると思います。
Phew:そうでしょうね。
■Phewさんはレインコーツを当時どう思っていて、その評価はどのように変化しましたか?
Phew:レインコーツは好きでしたよ。でも好きの度合いは正直薄かった。すくなくともアイドル的なものではなかった。で、2010年にライヴを観て、すごいバンドだと再認識しました。ライヴをするとどうしても慣れてくるじゃないですか。同じ曲を何度もやっていると当然そうなる。けれども彼女たちはそれをはじめて演るような新鮮さで演奏していたんです。それは巧いとか下手ではなくて、やっぱりすごいと思いました。おそらく数えきれないくらい演った曲を演奏しているのに慣れていない、それがすごくスリリングだったんです。
■当時イギリスのパンクとニューヨークだったらPhewさんはどちらに肩入れしていましたか?
Phew:音楽的にはニューヨークでした。圧倒的にそうでした。ただ世代的にイギリスのパンクのひとたちは同世代でしたから、直接的な影響を受けました。バンドを始めるきっかけになりましたね。ニューヨークはひと世代上でしたから。若者がバカやっているというのは圧倒的にロンドンのほうでしたよね。
■女性性みたいなことをいうのはふさわしいかわかりませんが、女性バンドとしてレインコーツに共感した部分はありますか。
Phew:そういう面での共感はなかったです。そういうところで、このひとはかっこいいと思ったのはむしろトーキング・ヘッズのティナ(・ウェイマウス)ですよ、あの当時は。だから私はスリッツとか、女の子バンドですよというのを全面的に打ち出しているバンドはどちらかといえば敬遠していて、私のなかではティナがいちばん好きでした。ライヴを観る機会があったのなら、また違ったかもしれませんが。
■ティナのどのへんに共感したんですか。
Phew:ファッション(きっぱりと)。スリッツなんかすごい恰好だったけど、ティナはショートカットに白いシャツに黒いズボン、それがすごくかっこよかった。むかしから地味好みなんですよ。けっしてパティ・スミスとかじゃない。音楽というよりファッションでいちばんかっこいいと思ったのがティナでした。アーント・サリーをやっていた当時の話で、トーキング・ヘッズの1枚目のころの話ですよ。
■ジム(・オルーク)さんもティナのベースは独創的だと以前いっていた憶えがあります。
Phew:じゃあやっぱり私は正しいんだ(笑)。トーキング・ヘッズの曲なんて私、ベースで憶えていますからね。
■ヤング・マーブル・ジャイアンツとレインコーツではどっちがお好きですか。
Phew:何ヶ月前にイギリスの『The Wire』という雑誌の「インヴィジブル・ジュークボックス」という連載の取材を受けたんですよ。それでレインコーツの2枚目がかかって、私ヤング・マーブル・ジャイアンツって答えちゃったんですよ(笑)。それくらいいい加減な認識なんです。でもヤング・マーブル・ジャイアンツもすごく好きでした。リズムボックスや声、スカスカのギター、音の質感が好きでした。私は当時、同時代の音楽をあまり聴かなかったのと好みがフライング・リザーズとかああいったものが好きだったから、生のバンドの音楽はあまり聴いていなかったんです。
■『Island』は根を詰めてつくったというよりは日常的にやりとりをしながらできあがったという感じだったんですか?
Phew:文通するみたいな感じでやりとりして、ある程度たまったときに「SoundCloudやBandcampで発表する?」と訊ねたら、アナのほうからレーベルがあるからそこからアルバムを出しましょうとなったんです。だから一枚のアルバムをつくるという気持ちは最初はなかったです。作品をつくるよりやりとりすること自体が楽しかったんですね。
■アルバムが念頭になかったということはどの楽曲がアルバム上でどういった役割を担うというふうな構成面は意識していなかったということですか。
Phew:アルバムの最後に収録している“Let's eat pasta”が最後にできた曲は、日常的で具体的なことをテーマにした曲がほしいとは思い、私から提案してアナに音源を送りしました。曲の構想は、ふたりで離れたところで、スパゲッティをつくって食べるということ。材料を買ってスパゲッティを茹でで食べる、作品が全体的に抽象的だったのでそういったところに着地したかったんです。
■抽象的といいながら、全体をとらえると抑揚のある作品にしあがったと思いますが。
Phew:それはあくまで結果であって、全体のながれはあまり考えていなかったです。アナは考えていたかもしれないですけど、私はぜんぜん。
■ヴォイスと各種機材での活動に入ってからのPhewさんの音楽には物理的にせよ心理的にせよ、距離というか空間性からくるコミュニケーションがテーマのひとつだと思うんですよ。
Phew:ああ、はい。
■『Island』もいうなればそのようなながれに位置づけるべき作品かと思いました。
Phew:そうともいえますが、この作品はソロとは向いている方向がちがうと思います。この作品での私は外向きだと思うんです。
[[SplitPage]]感傷は安易すぎる、その失敗を私たち人類はおかしつづけています。
■前作『Voice Hardcore』は2010年代の傑作のひとつだと思いますが、あのアルバムに較べると開放的ですね、真逆といってもいいかもしれない。おなじような形式をもちいても、別の方向を向かっている感じがあります。
Phew:この作品ではおたがいに電子楽器をつかっていますが、楽器は道具にすぎないんです。それはアナもおなじ気持ちだと思います。最初に自分の身体がある、それはふたり共通していると思います。モジュラーシンセをつかった最初の曲がとどいたとき、「ああアナの曲だ」とわかる。なので、このアルバムは、純粋電子音楽とはいいにくいですね。
■身体、声という側面ではおふたりともヴォーカリストですから、歌らしい歌を入れる選択もあったと思いますが。
Phew:またやろうという話にはなっているので、今後も続いていくなら、そういうものも出てくるかもしれない。今回はそういうことを考える暇もなく、制作がすすんでいって、はじめてメロディらしきものがきたのは“Konnichiwa!”でした。私が送ったトラックにアナがリフをくわえてきたんです。おそるおそる、メロディックすぎないかしら、といいながら(笑)。その意味では、メロディアスな要素はおたがい抑制していたのかもしれない。私がメロディっぽい側面を出したのは9曲目の“Dark but bright”。ストリングスの音は私がつけました。たしかにそのときもちょっとためらいはありました。メロディや声という要素は、すごくつよくてそれだけでなんとかなってしまう部分もあって、最初のうち私はそれを極力避けていました。できればヴォイスもあまりつかいたくなかった。声を最初に入れたのも“Konnichiwa!”でした。
■声をつかいたくなかったのは音を聴かせたかったから?
Phew:メロディをつかってしまうと曲がそれに支配されてしまい、だれがこの曲をつくったとか、そういう観点で聴かれがちじゃないですか。そういった事態は避けたかった。記名性で詮索するのではなく、たがいにすごく離れたところにいて、ことばで説得するのではなく、その中間でなにができるか。そういったテーマが私にはあったので、なるべくメロディとか歌詞も私もメッセージ性のあることばはなるべく避けようとしていました。
■タイトルはどなたのアイデアですか?
Phew:アナです。詩的な連想性があることばですよね。そのようなことばはおもにアナから来たものです。私はコミュニケーションのことばと考えると、どうしても「コンニチハ」とかになってしまうんです。
■事物的ですよね。私は『Voice Hardcore』のときのPhewさんのことばの散文性はすばらしいと思いますが、それも事物性に由来するとは思います。とはいえ、コミュニケーションを考えるなら、エモーショナルなことばのほうが共感度が高いので適しているともいえますよね。
Phew:真ん中になにかをつくるということです。音楽とか文学も、アートとはそういうものだと思うんです。感傷は安易すぎる、その失敗を私たち人類はおかしつづけています。
■突然すごく大きな問題を提起されましたが(笑)、そのとおりです。
Phew:人類はなにも学べない(笑)。オリンピックはやるしね。私も、感情に訴える話が読んで楽しい、泣ける話に感動するというのもわかりますが、私は子どものときから犬と暮らしているんです。
■藪から棒になんの話ですか。
Phew:(笑)。コミュニケーションについては犬から多くのことを学びました。これまでの人生で、9年ほど、犬のいない生活を送りましたが、いまでも2匹飼っていて、うち1匹はリコーダーやバンドネオンの音に反応して歌うんですよ。犬も1匹ごとに個性があります。それでも、犬には人間のことはわかってもらえない。さびしい気持ちもありますが、それで気持ちが離れることはまったくない。そのようなコミュニケーションのあり方を犬に学びました。
■シンセには反応しないんですか?
Phew:笛や生楽器の倍音に反応しているようで、電子音は嫌いみたい。
■ではご自宅で『Island』を制作されていたときはたいへんでしたね。
Phew:自宅で録音していると、ほんとうにだれとも会わなくなるし、音を録っているから声は出しているけど、何日もだれとも話さないこともまれではないですからね。家族はしゃべらないといけないような場面にはいないから、そうなるとだれとも会話していないことに気づくんです。その点でも犬がいるといいですよ(笑)。
■でもにぎやかな場所が好きなわけでもないですよね。
Phew:人混みが苦手で、きのうはライヴでたくさんのひとに会ってひと酔いしちゃいました。
■とはいえコラボレーションの機会は多い。
Phew:こういうかたちはひさしぶりですけどね。
■プロジェクト・アンダークで(ディーター・)メビウスさんとやりとりして以来ですか?
Phew:そうですね。でもね、あれは全部曲が最初にできていたんですよ。今回みたいにやりとりしてつくったわけではなくて、トラックに声を乗せていった感じだったので、一緒につくった感じはあまりなかったです。
■バンドともちがいますよね。
Phew:バンドはなつかしいですね。やりたいですけどね。
■やりたいお気持ちはつねにあるんですね。
Phew:バンドは楽しいですけど、練習の時間とかスタジオが必要じゃないですか。その手配がたいへん。そう考えるといちばんの問題はまちがいなく距離です。メンバーがみんな近所に住んでいたらどんなに楽かと思いますよ(笑)。音楽をやるにあたって、最初に曲が決まっているのはつまらないです。それぞれのパートのひとがアイデアを出し合ってつくっていくのがいちばんおもしろい。
■モストのときもそうでした?
Phew:最近のモストのライヴではきまった曲をやることが多かったですが、ライヴの前はかならず練習していましたし、曲づくりのためにリハーサルではメンバーそれぞれがアイデアを出し合っていました。
■そういうふうに直にひとと会いながら音楽をつくるのと、今回のアナさんのように対面せずに曲をつくる場合とではなにかちがいを感じられましたか。
Phew:日本にいるミュージシャンと一緒に音楽をつくる場合は、相手が知っているひとのことが多いんですよね。会ってしゃべるといろんな情報が入ってきます、視覚的な部分もふくめて。インターネットを通じたやりとりだとそういった情報が入ってこない。今回も個人的な話はしていないんですね。アナってどういうひとか、私はほとんど知らなかったんですが、音をやりとりするなかですごく親しくなった気がする。なんにも知らないのに、この親密な感じはなんなんだろうという、それはアナも同感だったようで、去年1年ぶりにロンドンに行ったときにもアナが会いに来てくれて、すごく親しくなった気がするんだけど、とおたがいにいいあいました。きっと音楽ならではの感覚なんです。いいひととかわるいひとというレベルの話ではなく、これはミュージシャンどうしでしかなりたちえない独特の関係なのだと思います。音で伝わってくるものがあるんでしょうね。
■たとえば共通言語をもたない場合、Phewさんはコニー・プランクやカンのホルガー・シューカイ、ヤキ・リーヴェツァイトともアルバムをつくられましたが、彼らとの作業はどうでした?
Phew:コニー・プランクは家がスタジオだったから家族にも会いましたが、ホルガーやヤキについてはプライベートなことは知らないけど、録音する前と後では関係がまったくちがいました。独特の信頼感というか、個人的なことに興味もないのに信頼を置けるというか。だから亡くなったというのはショックでしたよ。ありえないんですけど、どこかでずっと死なないものだと思っていた気がします。
■音は他者を触発すると同時に当事者にもフィードバックするのだと思います。とくにソロ活動以後のPhewさんの音楽では自己との対話の側面があると思いますが。
Phew:音を出してはじめてわかることがあるんですね。録音物を制作するときは、機材を触っていて、この音なんか好きっていうのがあったらすぐ録音して、そこから発展させることが多いですね。
■録音という意味でなにかすすんでいる作品はありますか。
Phew:すすめていることはあるんですが……最近ヴィンテージのミニムーグを導入したんですよ。何年も迷って結局買ってしまったんですが、それでどうしようかと思っているところです。ミニムーグの音は記名性がつよいじゃないですか。なにをやってもミニムーグの音だから自分の音楽というよりミニムーグの音なんです。好きなんですが、困りものです。まだまだミニムーグに負けています。ミニムーグとの勝負にまずは勝たないと。
[[SplitPage]]安室奈美恵みたいな歌は絶対できない。まずリズムがむずかしいしメロディもむずかしいですよ。だからやっぱり向いていることってあるんですよ。
■『A New World』のようなポップ路線というと語弊があるかもしれませんが、そのような作品にとりかかる予定はありますか。
Phew:曲はありますよ、めずらしくメロディもリズムもあるちゃんとつくった曲が2曲ぐらい。『A New World』のあと、そっちの方向に行きかけて、ライヴでも何度か演ったんですが、なぜかいまいるところに来てしまった(笑)。『Voice Hardcore』はやっぱり大きかったのかもしれない。『Voice Hardcore』はけっこう短い期間でつくったし、性に合っているんでしょうね。ああいったことがなんの苦労もなくできることなんですよ。
■根っからハードコアですね。
Phew:何時間でもやっていられるし、何枚でもできますよ。
■とはいえ『Voice Hardcore』も構成がありますし曲になっていますよね。
Phew:あのかたちだと即興的に曲がつくれるんですよね。ライヴでもそうですよね。即興的に構成する。芸歴の長さの賜物です(笑)。向き不向きで考えると自分に向いているのだと思います。逆にメロディを歌うのはすごくむずかしい。たとえば、安室奈美恵みたいな歌は絶対できない。まずリズムがむずかしいしメロディもむずかしいですよ。だからやっぱり向いていることってあるんですよ。
■『Voice Hardcore』が向いているというのもすごい話ですけどね(笑)。
Phew:私からしたら安室奈美恵がすごいですよ。
■Phewさんの場合、とくにさいきんのPhewさんの音楽では声や歌だけでなく音楽空間のなりたちが焦点だから一般的な音楽のスキルだけでは語れない部分があると思うんですね。
Phew:それも向いているということです。『Voice Hardcore』の曲は何度か音を重ねている部分もありますが、そうするとながれができて、すると次になにをすればいいかおのずと明らかになってきます。足りない音が感覚的に理解できるんです。
■声を発するのは身体コントールがたいへんでもあると思うんですが。
Phew:そんなにたいへんなことはあの作品でやっていません、あと家でやっていたので大きな声を出せないという制約はありました。お隣のひとに聞こえたらマズいとか、歌詞もひとに聴かれたくないような内容だから夢中にもなれない。いっていることヤバいなと思いながらヤバいことをいう。
■Phewさんの音楽は主体と独特の距離がありますよね(笑)。声を出しているのを外からみてる感覚がありますよね。
Phew:それはつねにありますね。
■そのあとに『Island』を聴くと――
Phew:ホッとするでしょ(笑)。
■『Voice Hardcore』は真空状態だけど『Island』には広がりがある。
Phew:そうですよ。
■それがひとりのなかから出てくるというのはすごいと思いますよ。
Phew:でもアナの力が今回は大きかったと思います。選ぶ音もぜんぜんちがうし、異質なひとがふたりというのはいいことだと思いますよ。これが3人だとややこしいことになりそうですけど(笑)。ふたりが離れたところにいるのが功を奏した面もあると思います。