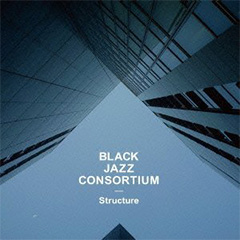今月の20日に東京でのDJを控えているダブステップのカリスマ、マーラが、ドミューンに生出演します。DJプレイは、本番でしかやらないという彼の主義のため、現場に行ってもらうしかないようですが、18日は公開インタヴューということで、喋ってくれます。盟友ゴス・トラッドも同席しての、ディープ・メディ・ミーティングといった感じになりそうです。夜7時から9時まで、お見逃しなく。ele-kingもサポートさせていただきます。たまにはdommuneにも来て下さいね。
それで、予習。『マーラ・イン・キューバ』の素晴らしいPVを見つけたので、まだの人、ご覧下さいませ。そしてDBSに行こう。
"Noches Sueños"--Mala featuring Danay Suárez [Official Video]
出演:MALA、GOTH-TRAD、野田努(司会)、チクヒコウイチ(通訳)
内容:UKダブステップ界の最重要人物MALAがDOMMNEに登場! アルバム『MALA IN CUBA』で新たなる新境地を開拓! 音楽革命家MALAが主宰するレーベルdeep mediを解説!
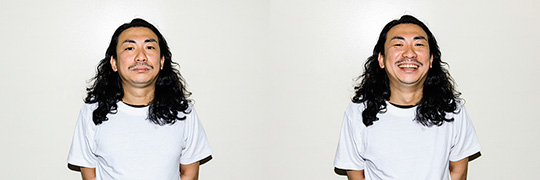











 尚4月8日DOMMUNEにて『コズモポリス』封切り直前特別番組が決定。Broad DJには東京アンダーグランドを代表してMASA a.k.a. Conomarkが満を持してDOMMUNEに初登場。この日は3時間SETでタップリお届けします。
尚4月8日DOMMUNEにて『コズモポリス』封切り直前特別番組が決定。Broad DJには東京アンダーグランドを代表してMASA a.k.a. Conomarkが満を持してDOMMUNEに初登場。この日は3時間SETでタップリお届けします。