このごろ90年代のことをよく考える。夢にみるほどである。そこで私はオシャレなサブカル雑誌の編集者で六本木にある編集部を出て大通りを交差点のほうから西麻布にむかって東北へ歩いていると、大きいだけで味気ないビルが建っているべき「六本木六丁目交差点」のあたりに、私は20余年前になくなったはずの小ぶりなビルが建っていた。
「WAVE」の文字をかかげた青灰色の窓のない概観はミズっぽさがなかなか抜けない六本木の空間で異彩を放っており、甘い水にさそわれる蛍のように建物内にすいこまれると、フロア一面を無数の棚がしめており、そこには世界各地から集めたレコードがびっしりならんでいる。そうだ、ここでは4階から順繰り降りながら全フロアをくまなくみてまわるのがノルマだったと気づいた私はエレベーターで現代音楽コーナーをめざすのだが、お客さんも店員も、建物内のすべてのひとたちが知り合いなのにしだいに気味がわるくなり、地下の映画館に逃げ込むも、次から次にあらわれるモギリのみなさんがまたしても顔見知りで、ことばにならない不安をおぼえながら、おそらくフィリップ・グラスが音楽つけただかなんだかの映画をみるともなくみて、逃げ帰るようにその建物をあとに、たちよった書店で手にした雑誌の表紙に、あっ、と声をあげたのはそこに「特集岡崎京子」とあったからである。
私はサラリーマン編集者だったときも競合他誌なるものを意識したことはないが、勤めはじめてほどない、たしか2000年あたりだったかに出た「スイッチ」のこの特集と、会社に三行半をつきつけたあたりに出た「ペン」のキリスト教の特集にはやられたと思った。なんとなれば、雑誌の特集には時代のほかにたよるあてもない。追認や迎合や、ましてや広告宣伝などではなく、それが世に出てはじめて、読みたかったのはこれなのだと気づかせるなにかを、私は先述の2誌の特集にみたのであろう。
とはいえ「スイッチ」の特集は「岡崎京子×90年代」だった(と思う)。また恐縮なことに、私はこの号を青山ブックセンター六本木店で購入したものの1ページもめくることなく編集部内で紛失してしまい、いまにいたるも内容のひとつも知らない。やられたとかいえた義理でもないのだがしかし、テーマや書名だけでなりたつ本や雑誌というものもある。2000年代初頭岡崎京子をとりあげるのはその典型であるように私に思われた、その一方で思うのである、なぜ90年代なのか。幕を下ろしたばかりの90年代への追慕の意味合いがあったにせよ、岡崎京子は90年代の表象なのか。岡崎京子の(六本木WAVEが開店した)1983年から96年にいたる(現状での)活動期間を考えると80年代のほうが長いではないか。そしてまた90年代は特定の人物や事象に収斂する時代なのか。それはひとことでいえるようなことなのか。
そもそもいつからが90年代なのか。この問いが多くの識者を悩ませてきたのはひとの世は数値ほどデジタルではないからである。2020年代に入った途端に2010年代が蒸発するはずもない。その線でいけば、90年代と80年代もたがいにのりいれているであろう。それさえもみるものによる視差がある――とはいえ90年代を起点に2年以上は前後しないのではないか。そうでなければディケイド切りそのものがあやふやになる。この点をふまえ、仮に1990年代のはじまりは2年前の88年だったとしよう。
1988年は昭和63年である。世はバブル景気に湧き、リクルート事件が起こり、4月の東京ドーム公演をもってBOØWYが解散した。その2年前のチェルノブイリ事故を受けたブルーハーツの「チェルノブイリ」は自主レーベルからは出せたけどRCの『Covers』は大手だったので発売できなかったのも88年。この年の3月10日号から掲載誌が休刊の憂き目をみる11月10日号まで『ジオラマボーイ・パノラマガール』は雑誌「平凡パンチ」に連載した、作者の経歴では中期の代表作ということになろうか。

物語は東京郊外の高校生である津田沼ハルコと神奈川健一のすれちがいと出会いを軸に、ふたりの家庭や学校生活がからまる構図をとっている。設定への特段の註記はないが、時制はおそらく作品連載時と同じく1988年、舞台は東京の郊外であることは主人公の名前があっけらかんとしめしている。本作はほかにも、岡崎作品を同定する指標である音楽、ファッション、風俗への遊戯的な言及があり、そのことは文化系男女の共感の入口であるばかりか、作者の人間観ひいては人物造形の土台ともなる。事物性をつきつめたはてにあらわれるモノになった身体同士が擦れるさいにたてるあの乾いた孤独な音が岡崎京子の主調音であれば、それは1989年の『Pink』で剥き出しになり、このあたりを90年代のはじまりとするのが至当だが、すでにしてそれは1988年の『ジオラマボーイ・パノラマガール』に潜んでもいた。
80年代から90年代へのグラーデションが『ジオラマ~』を彩っている。『リバーズ・エッジ』や『ヘルター・スケルター』など、映画にもなった後期の代表作と比して『ジオラマ~』には作家として洗練の課程で整理すべき雑多な要素が手つかずでのこっている。広津和郎なら散文精神とでも呼びそうなものと娯楽性の帳尻をどのようにあわせるか。瀬田なつき監督の『ジオラマボーイ・パノラマガール』にのぞむにあたって、私がもっとも興味をおぼえたのはその点だった。

結論からもうしますと、瀬田なつきは原作の輪郭をなぞりながらも『ジオラマボーイ・パノラマガール』をまったく新しい物語に「再生」している。主人公の渋谷ハルコと神奈川ケンイチを演じるのは山田杏奈と鈴木仁。俊英ふたりの存在感には高校生の男女の出会いとすれちがい、恋や片思いといった一大事を描くにうってつけのみずみずしさがある。
その一方で、物語の設定には異同がある。ハルコの苗字は津田沼から渋谷にかわり、彼らの生活圏もどこぞの匿名的な郊外から湾岸方面に移っている。そのことはスクリーンに映る光景が如実に物語るが、現在の空気と地続きの景色を前にして、私は90年代にはしぶとくのこっていた中心と周縁といった二項対立の枠組みがきれいさっぱりなくなっているのに気づいた。渋谷と津田沼は本来、パルコとパルコレッツ、ラフォーレ原宿とラフォーレ原宿・松山ほどの隔たりがあったはずだが、標準化の波にあらわれた世界における差異は類似性のバージョンとして誤差の範疇に収斂する。このことは些末なようでいて1990年代と2020年代の懸隔をみるうえで不可避であるばかりか物語の主題とも密接にかかわっている。なんとなれば『ジオラマボーイ・パノラマガール』とはタイトルがあらわすとおりトポスの物語なのである。

原作の副題「“BOY MEETS GIRL!” STORY “IN SHU-GO-JU-TAKU”」もまた、作者がこの作品を場所性から構想していたことをほのめかす。むろん創作における構想などきっかけにすぎず、マンガも映画も、ときにそのことをわすれたようにすすむが、彼らがよってたつのもそのような場所であるのにかわりはない。作中では集合住宅に住むハルコと戸建て住まいのケンイチの対比が基調となる。では集合住宅と戸建てとのちがいとはなにか。この問いに橋本治は『ぼくたちの近代史』で家には外があるがマンションには内側しかない、と答えている。さらに家庭の主婦などはちょっとばかしカンちがいしているのかもしれないが、彼女らは家庭に仕えるのでも家庭というカテゴリーに仕えるのでもなく、「家」という建物に仕えている、と喝破するのである。
「家というものが町の中に、そのような置かれ方をしてしまっているんだから、家に仕えるしかないわけで、これを断つ為には家から消えるしかないってんで、俺もう、家なんか見るのもやだってマンションに行っちゃったのね、逃げるように。
家っていうのは一つの観念なんだよね。この観念てのは、とっても土着的なもので、とってもオバサン的なもので、主人を待望するものでもあるけど、決して主人を存在させないようなもので、適応というものを強制するもの。「家庭が」じゃないのね。家ね。家という建物ね。建物が存在する為、存在するだけで、そこに意味というのが派生しちゃうから、家というものは、それだけの意味を持つのね」(橋本治/ぼくたちの近代史/河出文庫)

橋本の論旨は戸建て住まいのケンイチの両親が不在のかたちで空位になっているところなど、物語の無意識をいいあてるかにみえる。「オバサン的」など、PC的にどうかなーといわれそうなものいいもあるにせよ、そこにはおそらく江藤淳が『成熟と喪失』でこころみたような家父長制分析への橋本からの柔和な回答の側面もあっただろう。本稿ではただでさえ広げすぎの風呂敷をこれ以上広げないためにもこの点は指摘するにとどめるがしかし、橋本の上の発言が1987年11月15日のものであることには留意すべきであろう。
なぜ日づけまではっきしているかといえば、『ぼくたちの近代史』の元になった講演がこの日おこなわれたから。会場となったのはパルコやWAVEの親会社でもある西武百貨店は池袋店のコミュニティカレッジ、企画の担当者はカルチャーセンターに勤めていたころの保坂和志である。二度の休憩と三度衣裳替えをはさみ三部構成で都合六時間、しゃべりまくりだったという講演のテーマは多岐にわたる。先の発言があらわれるのは「リーダーはもう来ない」と題した第二部。ここで橋本は先の発言につづき「これ(家/筆者註)は何かに似ているって、実はこれ、「田舎」に似てるんだよ」とつづけている。なかなか刺激的な発言だが、そのことばはバブル期につきすすんだ80年代末の時代の空気をまとっている。そしてその空気はおそらく『ジオラマボーイ・パノラマガール』執筆時の岡崎京子が呼吸していたものでもある。
都市が郊外にむけて自己増殖するような、80年末から90年代初頭にかけたうわついた感じはいまはどこにもない。瀬田なつきはそれらを二度目の東京五輪をあてこんだ2019年の再開発の風景で代用する。舞台が湾岸らへんなのはそのせいだろうが、その一方で橋本のいう「マンション(都会)vs家(田舎)」的な対立の構図もいまでは描きづらい。90年代から現在にいたる失われた30年は成長だけでなくそこから派生する都会や理想的な生活への憧憬をも阻害した。原作のハルコが嫌悪する生活臭も都心へのあこがれも当時よりはずっとうすい。閉塞感の質がちがうといえばいいだろうか、ケンイチは原作でも映画でもある日衝動的に学校を退学するが、そのような高校生はいまでは稀少な部類なのではないか。いまなら辞める前にひきこもるか不登校になる。時間の重み、いや刹那の質みたいなものがきっと変わったのだろう――そんなふうにも30年前に高校生だった私は思う。
それらの変化にたいして場所性だけが例外というわけにもいかない。先に述べた『ぼくたちの近代史』の第二部「リーダーはもう来ない」につづく第三部を橋本は「原っぱの理論」と名づけている。橋本はそこで原っぱという社会がほしいという。世の中がいくら縮まってもみんなでつくる混沌を存在させる場所、町という秩序のなかにあって、私有権はありそうだけど世間の支配体制のおよばない子どもたちの社交の場のような。高度経済成長期はそんなのが近所のそこここにあった、昭和の最後にバブル景気がおこり、平成がはじまり時代が90年代にはいったころ、街中の原っぱは不動産になった。むろん拡張する都市は郊外をうみだしつづけその外殻には原っぱがある。とはいえ橋本のいう原っぱは阪神淡路大震災とオウム事件が分断する90年代の後半にいたって、岡崎京子が『リバーズ・エッジ』で描く不吉なものが横たわる現実界にも似た境界域になった。

『ジオラマボーイ・パノラマガール』が描くそこからさらに四半世紀後の世界である。そこではファッションも音楽も流行も、村上春樹の受容の程度も十代の男女の性愛の経験値も90年代とはへだたりがある。日々の暮らしの平坦さひとつとってもそうだ。あの時代からこの方ずっと真っ平らな日々ばっかだったわけはない――、大袈裟にいうとそのことの希望も絶望も描くのが物語の再生であり、この文字面からしてめんどくさそうなことを瀬田なつきは『ジオラマボーイ・パノラマガール』でやってのけている。注目すべきは終始すれちがいつづけたハルコとケンイチがはじめて出会うマンションを建設中のタワマンに置き換えたところ。それにより瀬田は原作の主題は現代的にアップデイトし、あからさまな文明批評を回避する。ゴダール風の冥府降り(昇り?)や不法占拠のパンキッシュさは瀬田なつきと岡崎京子というふたりの作家が二重写しになる場面である。そのはてにあらわれるハルコとケンイチの対面の場面での山田杏奈の表情の変化はとても印象にのこった。このときのハルコの表情の変化には顔色が変わるという慣用句をこえて物語のそれまでの時間をひきうける輝きがある。また余談めいて恐縮だが、映画版は「パン屋襲撃」のくだりがないぶん、『東京ガールズブラボー』が自転車泥棒の逸話を援用している。ほかにも、おばあさんの魂がのりうつるというオカルト要素がUFO的なセカイ系の話に置き換わるなど、90年来来のファンには原作との異同をくらべる楽しみもあるが、私をふくめた古株たちは作中で大塚寧々が演じるハルコの母親と同じ場所にすでに退いているともいえる。小沢健二の「ラブリー」が流れる場面は1990年代(前半)と2020年の若者をつなぐ回路となるが、時間的にも空間的にも多層性を潜在させる世界を側面から支えているのは山口元輝の音楽である。映画音楽を手がけるのははじめということだが、クラブのくだりやエンディング曲など、懐の広さと作品との距離のとりかたなど、映画音楽作家の資質のゆたかさをしめしている。
映画『ジオラマボーイ・パノラマガール』予告編



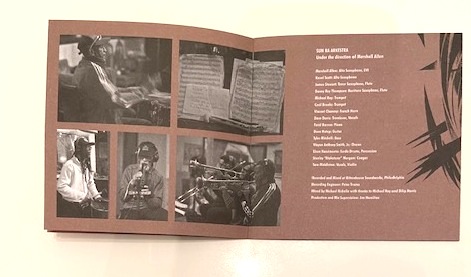




 Jam City
Jam City


