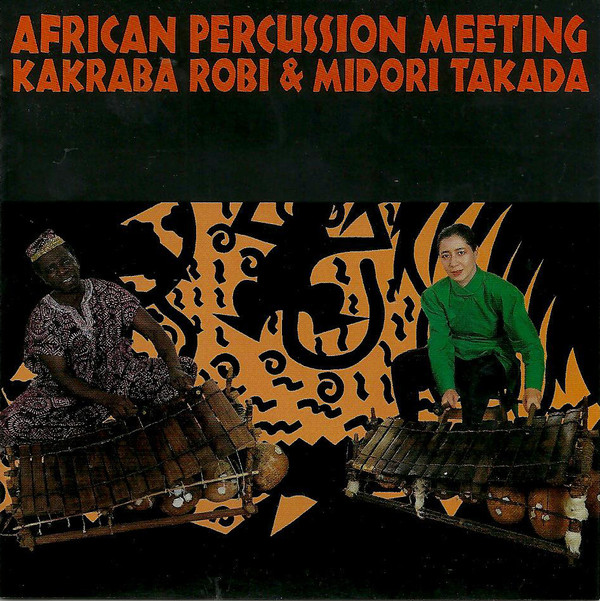このインタヴューは来年に延期されたテーリ・テムリッツ氏が出演予定のドイツの都市モンハイムで開催される音楽フェスティヴァル、《Monheim Triennale》から依頼を受け、英語でインタヴューをおこない執筆したものに若干の編集を加え日本語にしたものです。日本で20年、外国人でクィアで反資本主義なアーティストとして活動しているテーリさんの深い考察は、日本の人たちにこそいま読まれるべき示唆に富んでいます。
DJスプリンクルズとして知られるテーリ・テムリッツは世界を見渡しても、最も進歩的な芸術・音楽家たちのなかでさえも、極めてユニークな立場にある人物だ。批評性というものに深く向き合うことを決意している彼女は、あらゆる先入観や前提を疑うことを書く者に容赦なく迫るので、彼を題材にした記事を書くのは容易ではない。「私はかなり反パフォーマティヴで、どちらかというと文化評論家だと思っています。私は自分をアーティストやミュージシャンだとは思っていません」と彼女はさっそく私の第一の前提をはねのけた。
とはいえ、テムリッツは音楽制作・パフォーマンスをするアーティストとして最も広く知られているのは事実で、初期作品はドイツの電子音楽レーベル〈Mille Plateaux〉から、それ以降は東京の〈Mule Musiq〉やパリの〈Skylax Records〉といったレーベルから作品がリリースされている他、自身が運営する〈Comatonse Recordings〉がずっと彼の執筆活動や従来のフォーマットに収まらないプロジェクトのためのプラットフォームとなっている。最近では、76曲入りのアルバム『Comp x Comp』(2019年)や、オーディオ、ビデオ、テキストで構成されたマルチメディア・アルバム『不産主義』(2017年)などがそのディスコグラフィーに加えられた。
彼女のハウスDJ名義であるDJスプリンクルズは、過去10年ほど世界各地のクラブやフェスティヴァルのラインナップに名を連ねる人気を博している。特に、2008年に高い評価を得たアルバム『Midtown 120 Blues』をリリースした後、RAポッドキャストのミックスで国際的な注目を集め、さらに近年こうしたシーンでラインナップの多様性とジェンダー平等を実現しようとする取り組みに後押しされた側面もある。

ここまでに、「彼」、「彼女」と代名詞が混在していることに気づき、若干の混乱や読みにくさを感じている方もいると思うが、これは意図的である。トランスジェンダーであるテムリッツは、ひとつの代名詞に絞ることに抵抗を示す。近年、英語圏ではノン・バイナリーを性自認する人が、she/her でも he/his でもなく they/them を代名詞として使用することが一般化しつつある。自己紹介の際に、名前の次に代名詞は何かを本人が指定すること、あるいは相手に確認されることがマナーになってきている。しかし、彼女は第三のジェンダー代名詞(they/them)を使うことを拒否している。なぜかというと、「それは、家父長制の下でのジェンダー危機を解決しないからです。私は全く心地よさを感じません。読者には読みやすいかもしれませんが。それより私はむしろ、家父長制下での私自身のジェンダーの違和感を読者が共有することに興味があります。だから、代名詞が交互に入れ替わる文を読むのが心地悪いと感じるなら、いらっしゃい、私の世界へようこそ!」

移民という経験は、日本に順応したと公言することよりも、アメリカにいたときの自分を解体していくこと=“アンビカミング” に役立っているという風に考えています。そのような “それまでの自分のあり方を取り壊していく” =アンビカミングのプロセスこそが、私がより権威を持って語れることであり、より正確でより有益な情報となるのと思います。概して私は、「何かになる」ことよりも「規定されたあり方を壊す」ことの過程について語るほうが有益だと思っています。
■移民として日本にいること
この春、テムリッツが母国アメリカから日本に移住して20周年を迎えた。これは、彼が現在住んでいる千葉の田舎の農家と、私が住むベルリンを Zoom を介してかなりじっくりと話を聞かせてもらってまとめたものだ。私は日本人でありながら、オーストラリアとドイツに合計20年近く住んでいるので、移住という経験でいえばほぼ逆相関という関係にある。
芸術や非商業的な音楽に携わる者にとって、日本は通常、移住先として真っ先に浮かぶ国ではない。特に東京では生活費が高く、公的機関や社会一般からのサポートと言えるものがほとんどない。しかし彼女が日本に住む動機は、私たちの多くがごく当たり前に享受している、身体の安全であると言う。
「私はアメリカから日本に、トランスジェンダーとして来ました。アメリカでは、 “ファック・ユー(お前がどう思おうが関係ない)” という個人主義的な文化があり、誰もが気に入らないことがあれば、すぐにそれを表明する権利があると考えています。唾を吐きかけても、物を投げつけても、殴っても、何をしてもいい権利があると思っているのです。一方、日本では気に入らなければ、最悪の場合でも無視されるだけです。だから、私がいたアメリカ社会生活と比べれば、私にとって日本での “沈黙は金” なのです。嫌われても、放っておいてくれるなら構いません。ここでは、ボコボコに殴られずに済むんです。だからといって、ここでの生活を美化するつもりありません。この世界は相当酷い場所だと思っています。アメリカで散々バッシングにさらされて育ってきた結果、私は周りの暴力との関わりをなるべく減らす努力をしてきたのです」
彼が評価する日本の沈黙は、外の人からは礼儀正しさや、場合によっては「zen」な態度としてすら受け取られがちだが、彼女はそれが社会的抑圧のひとつの形態であり、外からは穏やかに見えていても、それがその裏では最も弱い立場の人を息苦しくさせていることがあることをよく知っている。
「ここでの日常生活は、表面的には信じられないほど礼儀正しく、フレンドリーです。おそらく地元の人同士でも。文化と言語の機能、そしてコミュニケーションという概念をめぐる人びとの心の動き……あるいはその欠如。それが自殺率の高さにも繋がっていると思います。この国の人々は、抑圧の概念とそれがもたらすダメージを受け入れられていないと思います」。このような問題意識を持ちながら、なぜ日本に住むことを選んだのかという質問に対して、テムリッツは次のように答えた。「多くの人は、移民というものを誤解していると思います。ほとんどの場合、移民や他国への移住は、いま置かれている状況から逃れるためのものであり、夢を追うためのものではありません。限られた可能な選択肢のなかで動き、それが上手くいくよう願うしかないのです」
◆「ビカミング(何かになる)」という感覚に抗うこと
日本の政治家や高官が女性やLGBTQの人びとに対して放った数々の “不適切” な発言を、世界も時折目にするようになった。森(元)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長や、内閣府特命担当大臣(男女共同参画担当)の丸川珠代の例が思い浮かぶが、数年前の自民党議員杉田水脈の「生産性がない」発言や、つい最近もLGBT理解増進法案が自民党によって見送られたばかり。現在の拠点が、彼にとって理想的な社会環境でないことは容易に想像できる。日本のジェンダーギャップ指数は、世界153カ国中120位(2021年世界経済フォーラム調べ)という厳しい状況にある。社会全体で保守的な風潮が強まっており、時代遅れな家父長制的な考え方が助長されているだけでなく、勢いを取り戻している。しかし、そのような背景があるからこそ、表現者としてのそれに準拠しない彼女の存在と批評的な表現の実践が、これまで以上に重要な意味を持つのではないか。
「日本における移民という立場に対する私のアプローチは、自分自身のジェンダーやセクシュアリティに対する反本質主義と平行していて、その知識を参考にしていると思います。私は、日本や日本での経験について権威を持って語る外国人になろうとは思っていません。移民という経験は、日本に順応したと公言することよりも、アメリカにいたときの自分を解体していくこと=“アンビカミング” に役立っているという風に考えています。そのような “それまでの自分のあり方を取り壊していく” =アンビカミングのプロセスこそが、私がより権威を持って語れることであり、より正確でより有益な情報となるのと思います。概して私は、「何かになる」ことよりも「規定されたあり方を壊す」ことの過程について語るほうが有益だと思っています。これは、私がアメリカに住んでいたときからの考え方だと思うのですが、私のクィアで非本質主義的なトランスジェンダリズムの観点からも言えることで、単一性(シンギュラリティ)のカミングアウトを指針とすることや、AからBへ移行することではなかったのです。私はいつも、痛みを伴う社会化のシステムに結びついたものや、離れたいと思っているものからどうやって距離を置くか、ということに興味を持ってきました。何か他のものに合わせるのではなく。そして、移民をめぐる支配的な言語は、トランスジェンダリズムやセクシュアリティや “カミングアウト” をめぐる多くの言語と同様に、つねに他の何かになること= “ビカミング” についての大衆的な感覚に根ざしています」
さらに彼は、支配的な社会的権力構造との調和ともなり得る、“ビカミング” の感覚に従うことの潜在的な危険性について説明を加えてくれた。それは冒頭の、代名詞に関する彼女の発言の意味するところとも繋がってくる。「私にとって、調和や可視性を強調することは、社会的関係性の本当の複雑さについて考えることを止めさせてしまうような、有害なことです。それどころか、アイデンティティ・ポリティクスの言語に陥らせ、それはすぐ本質主義的な議論になります。人びとは、社会的に構築されたアイデンティティを、“自然” の力に起因するものだと考えるようになるのです。これは、私は危険なことだと考えます。多くの偏見や暴力はこのような考え方から生まれているのです。
◆DJスプリンクルズ
DJスプリンクルズの「パフォーマンス」を体験したことがある人なら、彼の選曲とミックスは、単なる体感的なグルーヴ感や高揚感でパーティーを盛り上げる類のセットでないことはご存じかと思う。どちらかといえば、内省的で自分の内面を探っていくようなロングセットで真の持ち味を発揮するタイプのDJだ。彼女とこのようなDJ表現との関わりは、昨今の多くのDJとは異なる、極めて特殊なルーツに根ざしており、それはディープで繊細なテクスチャーのサウンドからも伝わってくる。
「私がDJをはじめたのは、88年から92年にかけての非常に特殊な時期でした。ニューヨークのゲイ・プライド・パレードで流すミックステープを制作していました。その後、〈Sally's II〉というクラブのレジデントになったのですが、このクラブはラテン系とアフリカ系アメリカ人の、トランスセクシャルのセックス・ワーカーたちが集まるクラブでした。週に3回プレイしていましたが、そのうちの2回はドリアン・コーリーと一緒でした。ドリアンはニューヨークのボール・シーンでは本当にオールドスクールの、オリジナルで重要なパフォーマーのひとりで、『パリは燃えている』などにも出演しています。ちょうど、ニュージャージーやニューヨークのローワーイーストサイドから、ハウス・ミュージックやディープ・ハウス・ミュージックが台頭してきたばかりの頃です。私はこのような明確にクィアでトランスセクシャルなセックス・クラブでプレイしていたのと同時に、ACT UP(AIDS Coalition To Unleash Power)にも参加していました。文化的には、当時アイデンティティ・ポリティクスの大きな波が押し寄せていました。
プライド運動が結晶化しつつあった、この周囲の誰もが「声高に、誇りを持って」いた時代に、テーリは、性的指向や欲求がそこまであからさまではない形で共有されていた〈Sally's II〉とそのクィアネスにより居心地の良さを感じたという。
「〈Sally's II〉の本当にありがたかったところは、私の “クィア” の理解と経験にずっと近かったことです。私はミズーリ州の出身ですが、そこに唯一あったゲイバーは西部劇に出てくるバーのようなところで、入るとそこには結婚指輪をした60代の男性が2人座っている。それぞれ田舎に奥さんと子供が住んでいるのは明らかで、彼らは奥さんや子供のところに帰る前に、そのバーで手をつないで一緒にウイスキーを飲むわけです。世界的な現実として、男性同士のセックスのほとんどは、自己実現をしている、声高に誇りを持っている男性間では起こりません。それは、片方か両方がゲイであることを否認している状況で起こる。それが、男性同士のセックスの伝統的なパラダイムです。だからこそ私は、“クローゼット”(*) 戦略や秘密主義や不可視性が自己防衛の手段であり、主流のプライド文化が主張するような、タブー視しなければならない単なる心の傷の原因ではないことを理解しています。この考え方はDJスプリンクルズ活動の一部であり、セクシュアリティの商品化とも関連する “プライド” の概念や構造に批判的なクィアネスのモデルと関連しています」
* 同性愛であることを公表していない状態のこと。カミングアウトの反義語。

“クローゼット” 戦略や秘密主義や不可視性が自己防衛の手段であり、主流のプライド文化が主張するような、タブー視しなければならない単なる心の傷の原因ではないことを理解しています。この考え方はDJスプリンクルズ活動の一部です。
◆組織化と教育の場としてのクラブ
このように、DJスプリンクルズが形成されたクラブ環境は、今日の一般的な「娯楽とエンターテイメントの場としてのクラブ」というイメージとは全く異なる意味を持っていた。彼女の関心対象と、彼が考える社会的空間としてのクラブが担う機能は、「グッド・ヴァイブス」や快楽主義をはるかに越えたところにある。
「例えば、アメリカには社会医療制度がなく、ほとんどの人が保険に加入していません。特に、家を追い出されたり、家族から勘当されたりしたホームレスのトランスのキッズたちであればなおさらです。ですから、ハウス・シーンやクラブは、ホルモン剤の投与量や移行期の治療法の効果・不効果、安全な医者とそうでない医者などについて、お互いに情報交換する場としても機能していました。また、薬をシェアする場でもありました。例えば、〈Sally's II〉の売人は、コカインだけでなく、ホルモン剤や処方箋も売っていました。いわゆる踊って楽しむような快楽主義的な従来のクラブの世界であるのと同時に、組織化、教育、セックス・ワークの場でもあったのです」
最近ではこのような場所が少なくなったため、彼女の表現方法は様々な場面に対応できるように、また生活のためにも、多様化した。
「クラブでは、誰もがハイになっているか、酔っ払っているかで、通常は攻撃的な批判をするスペースがありません。だから私は、クラブでは伝えきれない問題、困難、偽善、矛盾などを、執筆やインタヴューで伝えています。また、私はそのような状況に参加することの意味を複雑化するように心がけています。これらは雇用の場であり、私は収入を得ている。正直なところ、ヨーロッパのフェスティヴァルでDJをすることはできれば避けたいです。それらは、私がDJをしていた場所のルーツや、特定の時期にニューヨークで私をDJに駆り立てたものとは一切関係がないからです。また、最近ではクィア・イベントからDJ出演の依頼を受けることはほとんどありません。クィア・イベントには、日本から地球の裏側まで誰かを呼ぶような予算がないからです。だから、私はつねに間違ったオーディエンスに向けてプレイしているのです。でも、経済的な理由でそうしなければならない。同じように、私は “非演奏的” な電子音響作品をステージなどで演奏することを余儀なくされています。これらは、私にとって重大な妥協であり、現実的な問題です。私の作品のパフォーマンス的側面は、完全に経済的な理由からであり、完全に問題を抱えています。私はそれがいかに問題であるかをオープンにするようにしており、基本的にはそれも私の包括的なプロジェクトの一部としています。つまり、私たちがやらざるを得ないタイプの雇用にまつわる問題や矛盾を実際にオープンにしながら、どこまでできるかを検証するということです」
ハウス・シーンやクラブは、ホルモン剤の投与量や移行期の治療法の効果・不効果、安全な医者とそうでない医者などについて、お互いに情報交換する場としても機能していました。薬をシェアする場でもありました。組織化、教育、セックス・ワークの場でもあったのです。
◆テーリ・テムリッツ電気音響「パフォーマンス」
テーリ・テムリッツとして自身の電気音響作品を「パフォーマンス」することもある彼だが、彼女はこれを今日のパフォーマンス中心の経済に疑問を投げかける機会として捉えているという。
「通常、テーリ・テムリッツのショーのためにフェスティヴァルに呼ばれるときは、『不産主義』や『ソウルネスレス -魂の完全なる不在-』などの特定のプロジェクトをおこなうことが多いです。私の普段のパフォーマンスは、非演技的に構成されています。ある意味、初期の電気音響テープの再生作品のように、再生ボタンを押すと映像が流れ、私は基本的に何もせずに1時間座っているような構成になっています。これは、伝統的なアカデミックな電気音響テープのパフォーマンスを商業的なパフォーマンスの領域に持ち込むことへの言及でもありますが、一方でドラァグ・クイーンとしては、キャンプやパフォーマティヴィティ、派手さ、ジェスチャーといった従来のトランスジェンダーのステージに対する拒否反応でもあります。ですから、私はトランスジェンダーのステージに関連するパフォーマティヴィティにも批判的です。だからこそ、私はステージ上では静けさを好むのです」
グローバル・パンデミックの最中、私たちの多くがライヴ・パフォーマンスやその不在によってそれらの同空間での共有体験を「欲している」と感じている一方で、彼女はノンパフォーマティヴな作品に焦点を当てた文化的空間の不可能性に対する懸念を強めている。
「どこに向かっているかは明確だと思います。それは、ライヴ・ストリームや代理パフォーマンス・システムに焦点を当てたテクノロジーに表れています。さらに、ライヴ・パフォーマンスのモデル、真正性のモデル、即興のモデル、観客対演奏者のモデルなどに対する文化的な投資が結晶化し、具体化しています。そして、それは完全に保守的、徹底的に保守的で、根本的につまらないものです。私には、それは火を見るよりも明らかです」
彼が異なる名義を使い分け、多様な形態の活動で異なるコンテクストに関わっていることは、本質主義や単一性に抵抗するための戦略でもあることがわかる。すべてのものがロゴやサムネイル、ヘッドラインや短いプロフィールに凝縮されてしまう世界において、彼女は私たちに戸惑い、複雑さを受け入れることを強いる。
「異なるジャンルやさまざまな名義で活動することは、本質的なエッセンスや単一的な芸術的ヴィジョンを一般に投影されること──“存在の真実” とか “テーリ・テムリッツとは何者か?” とか、あたかも答えがひとつしかないかのように──を避ける、という私の批判的な関心と平行しています。ですから、このような断片化、グレーゾーンに入ること、白か黒かという考えからの脱却──単一の芸術的アイデンティティ、創造的プロセスの起源の単一性、原作者の単一性、何かが正真正銘自分のものであると信じること──これらすべてからの脱却が、私がサウンド・コラージュやサンプリングに取り組む理由です。純粋な音楽学や組成の真正性のようなものを起点としていないもの。そんなものはクソ食らえです。こうしたものこそが、私が対抗するものです」

実際には微積分レヴェルの問題を扱っているのに、私たちはいつも算数や足し算、引き算で語ることを強いられています。それより私は、オーディエンスに微積分をぶつけるような作品を発表したいのです。クィアな微積分をそのままぶつけたい。
◆クィアの微積分と向き合うことへの呼びかけ
さらに彼は、決してそれを簡単にはしてくれない。
「誰かがたまたまテーリ・テムリッツのイベントやDJスプリンクルズのイベントに行ったり、アルバムを手に取ったり、インタヴュー記事を読んだりして、それが何かをより深く知るための入り口になるのなら、それはそれでいいと思います。でも、私はビギナーのために手を差し伸べてあげるということには興味がありません。なぜなら、文化的にマイナーなレヴェルでは、メインストリームにつねにアピールしようとすることが、問題や危機についてより深く正確に話し合う方法を育むことを妨げるからです。メインストリームは、ある種の拡張主義的にフォーカスしていて、これは非常に西洋的なグローバリズムと資本主義の考え方です。聴衆はなるべく多い方がいい、より多くの人に届ける方がいい、というものです。支配的なポピュリズムの流通モデルを、非常にマイナーで文化的に特殊な形態のメディアに適用するという考え方は間違っている可能性があり、少なくとも私のメリットにはなりません」
彼女は数学をメタファーとして、詳細を省かない交流の必要性をさらに説明する。
「実際には微積分レヴェルの問題を扱っているのに、私たちはいつも算数や足し算、引き算で語ることを強いられています。それより私は、オーディエンスに微積分をぶつけるような作品を発表したいのです。クィアな微積分をそのままぶつけたい」
テーリ・テムリッツの微積分を受け入れようとしながら話をまとめようとしたとき、私はほとんど無意識のうちに、いつものように会話をポジティヴに終わらせる方法を探していた。彼女は最後にそれに対してもピシャリと応えた。
「私はニヒリストです。私たちはもうダメだと思います。私たちは社会に、いつも楽観的に終わらせなければならないと思わされていますが、できません。すべてが最低なクソです。つねに悪い方向に向かっています。私たちは、もう右か左かではなく、上か下かという世界に突入しています。これはセクシュアリティやジェンダーの権力関係とも通じていますね。それが私たちのいる世界です。良いことばかり考えるのではなく、私たちの周りで起こっている暴力や破壊に危機感を持つようにしなければなりません。暴力はあらゆる場面で助長されています。このような状況に希望を持つのではなく、希望を捨てて、『なんてこった!』と思う必要があるのです。バラ色の眼鏡は外してください。パニックしてもいいんですよ」