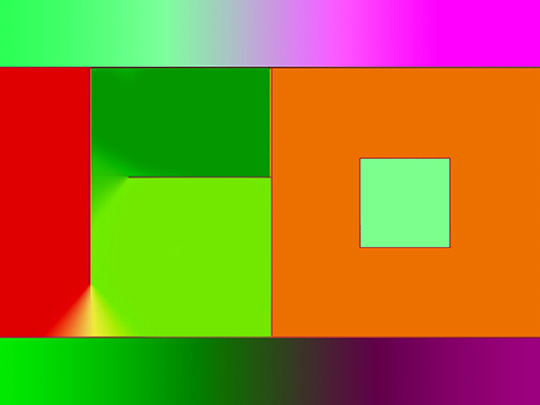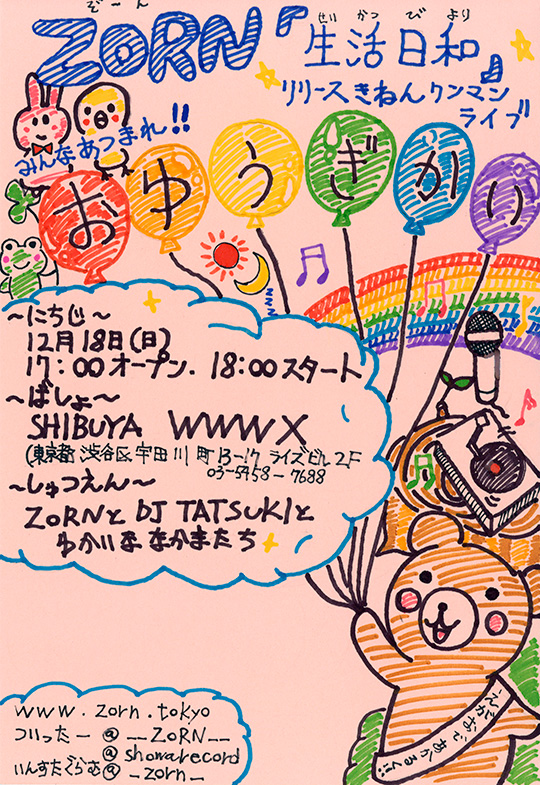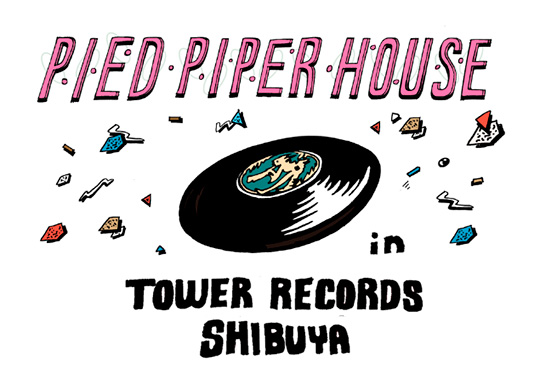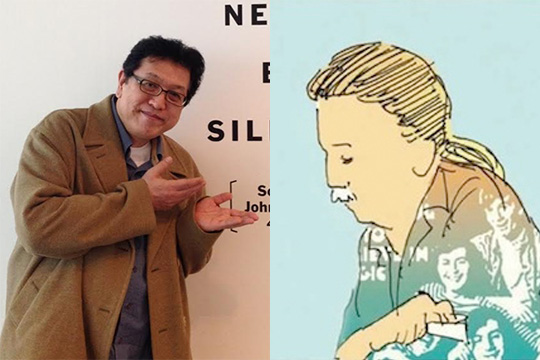パラダイス銀河3000
 1 |
BILY PAUL - Let's Make a Baby - Philadelphia Int'l もうタイトルからキテる!男と女、恥ずかしがらずに全てを解放、高鳴る鼓動、一緒に踊れば最高だね! https://www.youtube.com/watch?v=_CLbFtGn5Fk |
|---|---|
 2 |
MICHAEL JACKSON - Rock With You - Epic やっぱマイケルに間違いなし!終わらないグルーヴ。朝まであの娘を独り占め!ポゥッ! https://www.youtube.com/watch?v=5X-Mrc2l1d0 |
 3 |
DELEGATION - Oh Honey - State Records 気分は夢の中。大ネタとか関係無しにこの浮遊感はみんな好きだと思う。この曲をサンプリングしたBeenie ManのMemoriesのリミックスもかけたりします https://www.youtube.com/watch?v=BbMzoSVKp1Q |
 4 |
GEORGE DUKE - Just For You - Epic もう君しか見えない!揺れて、揺れて、揺れて。甘甘感全開120% https://www.youtube.com/watch?v=1CCErnrLK1A |
 5 |
ART WILSON - Unbelievable - Alexander Street デート中に街中からふと流れる音に反応しちゃう2人。今夜は何か起こるかも https://www.youtube.com/watch?v=Yl7m3BdZ9kQ |
 6 |
THE MANHATTANS - Shining Star - Columbia 止められない自分の気持ち全てを捧げよう!いつだって彼女はシャイニングスター。4人のダンスもツボです https://www.youtube.com/watch?v=C_VpjSv_4QM |
 7 |
KWICK - Let This Moment Be Forever - EMI 歌にコーラス、演奏がバッチリはまっててずっと聴いていたい曲。こういう80年代感あるソウル大好きです! https://www.youtube.com/watch?v=cRFCjzuth1A |
 8 |
EXECUTIVE SUITE - Your Love Is Paradice - Babylon Recording 出会った瞬間から全てが始まった!そんな気分にさせられる1曲です。裏面はインストの別曲なんだけどこれも使える! https://www.youtube.com/watch?v=zCWu_d3MyEo |
 9 |
CONTINENTAL FOUR - Loving You - Master Five やっぱファルセットボイスがソウルには欠かせない!メロメロ。手前味噌ですが自分の最新作"SUGAR M70"にも収録されてます https://www.youtube.com/watch?v=figp_AuH_ME |
 10 |
NATALIE COLE - Heaven Is With You - Capital 邦題"幸せの夜"から想像できるような最高な気分にさせてくれるナタリーはNat King Coleの娘。昇天確実 https://www.youtube.com/watch?v=aVaXdmN8EEU |
気づけば10回目の投稿、元気しか取り柄がないウホホ、ほぼゴリラのOGです。ウホッ!
今回のチャートは"パラダイス銀河3000"と題し大好きなソウルミュージック特集です。
有名、無名関係なしにこの時代の黒人音楽は素晴らしいものばかりで、レコードを見つけ出した時いつもドキドキが止まりません。
そんな俺が選んだ冬らしいソウル10曲をみんなと共有できたら嬉しいです。
そして早いもので今年も残りあと僅か。
今年は各地多くのパーティーに参加できたことや、夏には久々のMix TAPE!!!を出したりと非常に充実した1年でした。
まあ今年1年を振り返ることよりも前しか見てない俺が何を言いたいかと言うと、、、
12/5にBrand New Mix CD"SUGAR M70"をリリースしました!はい!宣伝です!
今回は初の、レゲエのミックスではなくここで挙げたような至極のソウルナンバーを集めました。
CDは全て手作りで、俺が出演する会場と自分のレーベルBad Man Wagonのweb shopのみの限定販売になっているので気になった人は是非よろしくお願いします。
最後に、今年出会えた最高の人たち、一緒にDJしてワッショイした人、パーティーに来て乾杯した人、色んなアドバイスをくれた人、本当に多くの人に支えられ駆け抜けることができた2016年。
本当に感謝しかありません。いつもありがとう!そして2017年は更にぶっ飛ばしていっちゃうんでよろしく!俺は止まらない!踊り続けよう!
それではみなさん良いお年を~
12/16 吉祥寺cheeky "FORMATION"
12/18 表参道wall&wall "TO BE CONTINUED"
12/19 六本木varit "東京ハウスパーティー"
12/20 dommune "MASTERED HISSNOISE broad DJ"
12/22 渋谷7th floor "86BABIES"
12/30 吉祥寺cheeky "弁天DANCE"
1/6 三軒茶屋orbit
1/11 新宿open "DISCO SHOOTER"
1/20 吉祥寺cheeky "FORMATION"
BMW dealer
https://badmanwagon.com/