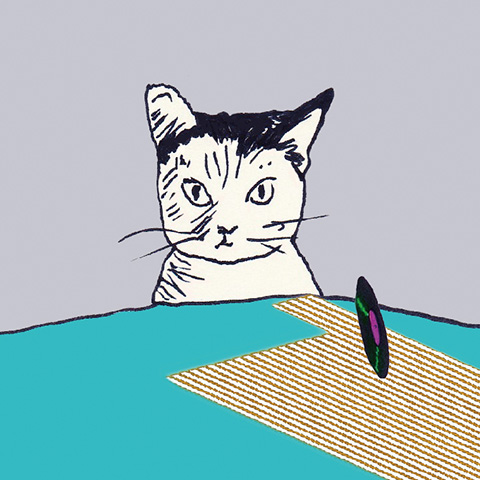昨年は映画『Good Time』の劇伴や坂本龍一のリミックスを手がけ、最近ではデヴィッド・バーンの新作に参加したことでも話題となったOPNが、5月にNYで開催されるライヴのトレイラー映像を公開しました。これ、新曲ですよね。しかもチェンバロ? 曲調もバロック風です。この急転回はいったい何を意味するのでしょう。そういう趣向のライヴなのか、それとも……。
ONEOHTRIX POINT NEVER
5月にニューヨークで行われる大規模コンサートの
トレーラー映像を新曲と共に公開!
昨年、映画『グッド・タイム』でカンヌ映画祭最優秀サウンドトラック賞を受賞したことも記憶に新しいワンオートリックス・ポイント・ネヴァーが、【Red Bull Music Festival New York】の一環として5月22日と24日にニューヨークで行われる最新ライブ「MYRIAD」のトレーラー映像を公開した。ダニエル・ロパティン(ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー)自らディレクションを行い、その唯一無二の世界観が垣間見られる2分間の映像には、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー名義の新曲も使用されている。
Oneohtrix Point Never - MYRIAD
https://opn.lnk.to/MyriadNYC
Video by Daniel Swan and David Rudnick
Directed by Oneohtrix Point Never
Animation by Daniel Swan
Produced by Eliza Ryan
Videography by Jay Sansone
Additional Animation by Nate Boyce
Thrash Rat™ and KINGRAT™ characters by Nate Boyce and Oneohtrix Point Never
Engravings by Francois Desprez, from Les Songes Drolatiques de Pantagruel (1565)
Additional Typography by David Rudnick
本公演が開催されるパークアベニュー・アーモリー(Park Avenue Armory)は、以前は米軍の軍事施設だった場所で、ライブが行われるウェイド・トンプソン・ドリル・ホール(Wade Thompson Drill Hall)は航空機の格納庫のような巨大なスペースである。当日にはスペシャルゲストやコラボレーターも登場し、ここでしか体験することのできない特別なライブ・パフォーマンスが披露されるという。
ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー|Oneohtrix Point Never
前衛的な実験音楽から現代音楽、アート、映画の世界にもその名を轟かせ、2017年にはカンヌ映画祭にて最優秀サウンドトラック賞を受賞した現代を代表する革新的音楽家の一人。『Replica』(2011)、『R Plus Seven』(2013)、『Garden of Delete』(2015)と立て続けにその年を代表する作品を世に送り出してきただけでなく、ブライアン・イーノも参加したデヴィッド・バーン最新作『American Utopia』にプロデューサーの一人として名を連ね、FKAツイッグスやギー・ポップ、アノーニらともコラボレート。その他ナイン・インチ・ネイルズや坂本龍一のリミックスも手がけている。さらにソフィア・コッポラ監督映画『ブリングリング』やジョシュ&ベニー・サフディ監督映画『グッド・タイム』で音楽を手がけ、『グッド・タイム』ではカンヌ・サウンドトラック賞を受賞した。

label: Warp Records / Beat Records
artist: Oneohtrix Point Never
title: Good Time Original Motion Picture Soundtrack
cat no.: BRC-558
release date: 2017/08/11 FRI ON SALE
国内盤CD:ボーナストラック追加収録/解説書封入
定価:¥2,200+税
【ご購入はこちら】
beatink: https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=4002
amazon: https://amzn.asia/6kMFQnV
iTunes Store: https://apple.co/2rMT8JI

label: Warp Records / Beat Records
artist: Oneohtrix Point Never
title: Good Time... Raw
cat no.: BRC-561
release date: 2017/11/03 FRI ON SALE
国内限定盤CD:ジョシュ・サフディによるライナーノーツ
ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーとジョシュ・サフディによるスペシャル対談封入
定価:¥2,000+税
【ご購入はこちら】
beatink: https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=9186
amazon: https://amzn.asia/gxW5H63
tower records: https://tower.jp/item/4619899/Good-Time----Raw
hmv: https://www.hmv.co.jp/artist_Oneohtrix-Point-Never_000000000424647/item_Good-Time-Raw_8282459