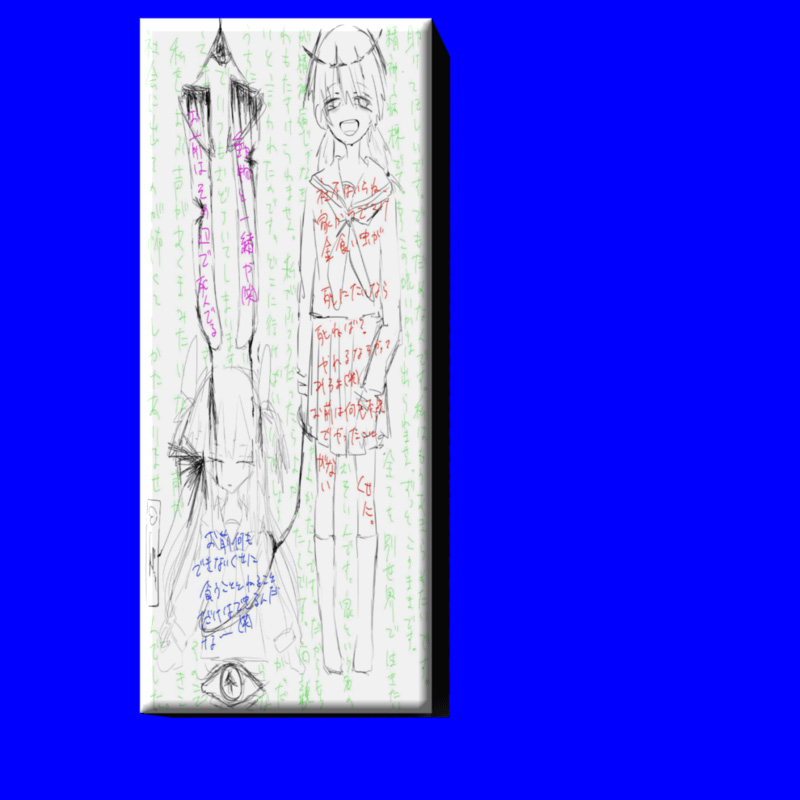これは興味深い組み合わせだ。アンビエント/ドローン・アーティストの畠山地平と、近年多方面で活躍をみせるジャズ・ドラマー、石若駿によるコラボ・アルバム『Magnificent Little Dudes』がリリースされる。2部作だそうで、まずはその「vol.1」が5月24日にリリース。事前準備なしでおこなわれた即興演奏が収録されるという。日本先行発売。いったいどんな化学反応が起こっているのか、注目です。
Chihei Hatakeyama & Shun Ishiwaka
Magnificent Little Dudues Vol.1
2024年5月22日(水)日本先行発売!
日本を代表するアンビエント/ドローン·ミュージック・シーンを牽引する存在となったChihei Hatakeyamaこと畠山地平が、この度ジャズ・ドラマーの石若駿とのコラボレーションを発表した。
ラジオ番組の収録で出会って以来、ライヴ活動などでステージを共にすることはあった2人だが、作品を発表するのは今回が初めて。『Magnificent Little Dudes』と名付けられた今作は、2部作となっており、2024年5月にヴォリューム1が、同夏にヴォリューム2がリリース予定となっている。
「その場、その日、季節、天気などからインスピレーションを得て演奏すること」をコンセプトに、あえて事前に準備することはせず、あくまでも即興演奏を収録。ファースト・シングル「M4」には日本人ヴォーカリストHatis Noitをゲストに迎えた。ギター・ドローンの演奏をしているとその音色が女性ヴォーカルのように聞こえる瞬間があることから、いつか女性ヴォーカルとのコラボレーションをしたいと思っていた畠山。「今回の石若駿との録音でその時が来たように感じたので、即興レコーディングの演奏中、いつもは使っている音域やスペースを空けてギターを演奏しました。ちょうどこのレコーディングの3週間くらい前に彼女のライヴ観ていたので、Hatis Noitさんの声をイメージしてギターを演奏しました」と話す。
世界を股にかけて活動する日本人アーティスト3組のコラボレーションが実現した『Magnificent Little Dudes Vol.1』は、日本国内外で話題となること間違い無いだろう。
アルバムはCD、2LP(140g)、デジタルの3フォーマットでリリースされる。
本日、収録曲の「M4」がファースト・シングルとして配信スタートした。

Chihei Hatakeyama & Shun Ishiwaka - M4 (feat. Hatis Noit)
[トラックリスト]
(CD)
1. M0
2. M1.1
3. M1.2
4. M4 (feat. Hatis Noit)
5. M7
(LP)
Side-A
1. M0
Side-B
1. M1.1
Side-C
1. M1.2
Side-D
1. M4 (feat. Hatis Noit)
2. M7
アーティスト名:Chihei Hatakeyama & Shun Ishiwaka(畠山地平&石若駿)
タイトル名:Magnificent Little Dudes Vol.1(マグニィフィセント・リトル・デューズ・ヴォリューム 1)
発売日:2024年5月24日(水)
レーベル:Gearbox Records
品番:CD: GB1594CD / 2LP: GB1594
※日本特別仕様盤特典:日本先行発売、帯付き予定
アルバム『Magnificent Little Dudes Vol.1』予約受付中!
https://bfan.link/magnificent-little-dudes-volume-01
シングル「M4」配信中:
https://bfan.link/m4
バイオグラフィー

[Chihei Hatakeyama / 畠山地平]
2006年に前衛音楽専門レーベルとして定評のあるアメリカの〈Kranky〉より、ファースト・アルバムをリリース。以後、オーストラリア〈Room40〉、ルクセンブルク〈Own Records〉、イギリス〈Under The Spire〉、〈hibernate〉、日本〈Home Normal〉など、国内外のレーベルから現在にいたるまで多数の作品を発表している。デジタルとアナログの機材を駆使したサウンドが構築する、美しいアンビエント・ドローン作品を特徴としており、主に海外での人気が高く、Spotifyの2017年「海外で最も再生された国内アーティスト」ではトップ10にランクインした。2021年4月、イギリス〈Gearbox Records〉からの第一弾リリースとなるアルバム『Late Spring』を発表。その後、2023年5月にはドキュメンタリー映画 『ライフ・イズ・クライミング!』の劇中音楽集もリリース。映画音楽では他にも、松村浩行監督作品『TOCHKA』の環境音を使用したCD作品『The Secret distance of TOCHKA』を発表。第86回アカデミー賞<長編ドキュメンタリー部門>にノミネートされた篠原有司男を描いたザカリー・ハインザーリング監督作品『キューティー&ボクサー』(2013年)でも楽曲が使用された。また、NHKアニメワールド:プチプチ・アニメ『エんエんニコリ』の音楽を担当している。2010年以来、世界中でツアーを精力的に行なっており、2022年には全米15箇所に及ぶUS ツアーを、2023年は2回に渡りヨーロッパ・ツアーを敢行した。2024年5月、ジャズ・ドラマーの石若駿とのコラボレーション作品『Magnificent Little Dudes Vol.1』をリリース。

[Shun Ishiwaka / 石若駿]
1992年北海道生まれ。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校打楽器専攻を経て、同大学を卒業。卒業時にアカンサス音楽賞、同声会賞を受賞。2006年、日野皓正special quintetのメンバーとして札幌にてライヴを行なう。2012年、アニメ『坂道のアポロン』 の川渕千太郎役ドラム演奏、モーションを担当。2015年には初のリーダー作となるアルバム「Cleanup」を発表した。また同世代の仲間である小西遼、小田朋美らとCRCK/LCKSも結成。さらに2016年からは「うた」をテーマにしたプロジェクト「Songbook」も始動させている。近年はゲスト・ミュージシャンとしても評価が高く、くるりやKID FRESINOなど幅広いジャンルの作品やライヴに参加している。2019年には新たなプロジェクトAnswer To Rememberをスタートさせた。2023年公開の劇場アニメ『BLUE GIANT』では、登場人物の玉田俊二が作中で担当するドラムパートの実演奏を手がけた。2024年5月、日本を代表するアンビエント/ドローン·ミュージシャン、畠山地平とのコラボレーション作品『Magnificent Little Dudes Vol.1』をリリース。