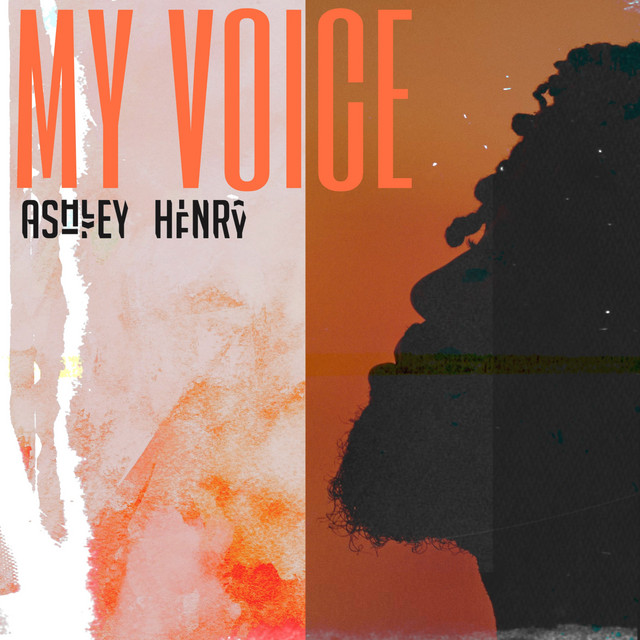『ロブスター』(恋愛禁止)や『ロニートとエスティ』(レズビアン)、あるいは『女王陛下のお気に入り』(死産)と、人口増加に寄与しないテーマの作品に出演が続いたからか、この4月にレイチェル・ワイズが10代の頃に見て衝撃を受けたデヴィッド・クローネンバーグのクラシック『戦慄の絆』をアリス・バーチとともにリメイクし、代理出産や人工授精、不妊治療やリモート出産など産科が直面しているイノヴェーションを軸に(出産というよりはもはや)「人間をつくる」というアメリカの生命観が色濃く反映されたTVドラマにアップデートさせた。同じ産科を扱っていてもヒューマン・ドラマとして感動的だったNHK『透明なゆりかご』とは様相が異なり、資本主義がビジネスとして生命の誕生に示す価値観が恐ろしいまでに強調され、「資本主義はそんなに悪い?」「朝から『共産党宣言」でも読んできた?」と、出産を自然現象よりは生産性を高めることができる産業のひとつとして推進していく感覚はこのところ右派によって後退ぶりを印象づけてきたアメリカが久しぶりに「先進国」だったことをがっつりと思い出させてくれた(少子化でオタついている東アジア諸国とは「産めよ増やせよ」の気迫が根底から違うというか)。昨年、アメリカの最高裁で覆された中絶禁止を違憲とするロー対ウェイド判決についての議論こそストレートには扱われなかったものの、ドラマ版には平和的な出産シーンなど皆無で、過剰に性的で血まみれ、ドラッグによる錯乱や投資家たちとの舌戦など全編にわたって暴力的な描写が続き、時間軸は乱れに乱れ、アートと結びつけていく演出などクローネンバーグのヴィジョンを愚直なほど継承・発展させた傑作といえる。オリジナルの設定ではジェレミー・アイアンズ演じる男の双子役をTV版ではレイチェル・ワイズが女の双子に変更しつつも役名はエリオット&ビヴァリー・マントルと男性名がそのまま使われ、オリジナルに登場するクレア・ニヴォーを演じたジュヌヴィエーヴ・ビュジョルドの名前がTV版では役名のジュヌヴィエーヴ・コタード(演じたのはブリトニー・オールドフォード)に援用されるなど形式的な移譲にもしっかりと気が配られ、兄弟(姉妹)の相克がアイデンティティの崩壊に発展していくというメイン・テーマもオリジナルに引けを取らないインパクトを維持した。冷静に考えてみると背景と主題は巧妙に結び付けられているとはいえ、不可分の関係にあるわけではないということも見失ってしまうほどの力技で、主要人物がほとんど女と黒人で占められていたのも現代的。非情な投資家を演じたジェニファー・イーリーがプロモーション・トークで2話まで観たらもう一度最初から観た方がいいとアドヴァイスしていたけれど、確かに2話まで観ると何が起きているのか混乱し始め、よくぞ全6話で話がまとまったと思う。

異端の独走状態を突っ走ってきたデヴィッド・クローネンバーグは前作の『マップ・トゥ・ザ・スターズ』があまりいい出来とは思えなかったので、天才のインスピレーションもついに枯れ果て(https://www.youtube.com/watch?v=ZpvNuH420W8)、このまま息子のブランドン・クローネンバーグにカルトスター的な地位を奪われてしまうのかなとも思っていたのだけれど、『戦慄の絆』のリメイクで改めてオリジナルの評価が急上昇しただけでなく、『戦慄の絆』でもとくに印象に残った「体内の美しさのコンテスト」という視点を骨子とした新作を完成させたことで、その地位はやはり磐石だと思わせる。80歳とは思えない想像力と時代に対する皮肉が『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』には迸り、揺るがないオリジナリティの強度が改めて印象づけられていく。脚本が書かれたのは20年前で、マイクロプラスティックが人類の80%で血液中に見つかったとされる現在、クローネンバーグはいまが映画化のタイミングだと判断したという。クローネンバーグ作品には「体内に何かいる」というテーマのものが多く、『シーバーズ』では寄生虫(性欲の象徴)、『ヴィデオドローム』では銃(暴力の象徴)、『ザ・フライ』ではハエの遺伝子(科学技術の象徴)、『イグジステンズ』ではゲームの端末(仮想現実の象徴)がそれぞれに人体を変形させていくというプロセスを追っていて(『戦慄の絆』もリメイクによって「体内に何かいる」シリーズに加わった)、『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』もオープニングから「現代文明」の断片が人間の体内に入り込んでいる状況を描いたものだということが推察できる。物語は海辺に横倒しになっている大きな船の遠景から始まり、船は明らかにタイタニック=文明の比喩で、人間のつくり出した技術がコントロールできなくなっている状態を表している。船からカメラが手前に移動してくると少年ブレッケンが海岸で遊んでいる。ブレッケンは母親ジュナに呼ばれて家に帰り、その夜、バスルームでポリバケツをバリバリと食べ始める。ジュナはブレッケンが寝たのを確認すると寝顔に枕を押しつけて我が子を殺す。場面は変わってヴィゴ・モーテンセン演じるソール・テンサーとレア・セドゥ(!)演じるカプリースが共に暮らす家。ソールは病人で、カプリースが看護をしているのかと思いきや、しばらく観ているとソールは体内で新たな臓器をつくり出すことができる人間に進化しており(加速進化症候群)、カプリースはそれを体外に取り出すショーを人前で繰り広げる芸術家だということがわかってくる。

最初はなかなか理解が追いつかないけれど、人類は痛みの感覚というものを失っており、体の不調を自覚しづらい世界で痛みをどう認識するかが人々の価値観をなし、観客はその世界観に慣れていくしかない。ソールはいつも苦しそうにしていて、進化という概念とはどうにも結びつかず、そのような違和感を残したまま作品の世界観に馴染んでいくと、加速進化症候群というのはマリリン・チェンバース演じるローズが『ラビッド』で与えられた設定と同じだということがわかってくる。ローズが体内でつくられた新たな臓器を生かすために人の血を欲したのに対し、ソールはその臓器を摘出して人に見せることで生計を立てられるという変化がある。加速進化症候群という病名がついているぐらいで体内に新しい臓器ができるのはソールに限った話ではなく、人類にはポツポツと認められる事態となっており、ソールのような人間は体内で新たな臓器がつくられると政府の秘密機関である臓器登録所に登録することが義務づけられている。臓器登録所のラング所長をスコット・スピードマン、助手のティムリンをクリステン・ステュワート(!)が演じていて、臓器登録所はそのようにして生まれた臓器が遺伝的に次の世代に継承されないことを目的としている。いわば「進化」を監視し、抑制する機関なのである。『イグジステンズ』や『クラッシュ』は制御できなくなった文明に人間が振り回されていく一方だったけれど、人類はもう少し文明をコントロールできるように設定されていて、むしろ人間の身体能力をここまで過大評価できるのかという強い視点にはたじろぐしかない。ダーウィン研究家のスティーヴン・ジェイ・グールドはダーウィンはあくまでも「適応論」を説いたのであって、生命は環境に合わせるために進化したり退化するとしたにもかかわらず、人類はこの150年、「進化」だけに過剰反応を示していると嘆いていた。クローネンバーグもそういった意味では「環境の変化」に対して人類が「進化」するという考えしか持たないようで、『スキャナー』や『デッドゾーン』など超能力に目覚めた例や『ザ・フライ』ではハエの遺伝子を獲得したセス・ブランドルがその能力を面白がるシーンは彼にとって至福のヴィジョンと思えなくもない。「体内に何かいる」というのは、それが外に出てくる痛みと引き換えに高い能力を得ることを意味し、処女受胎のイメージにも重なっていく。過去には『フランケンシュタイン』を撮る企画もあったようだし、クローネンバーグはこれまでの作品群を通じて何度も新たな人類を創造してきたということなのだろう(ちなみにクローネンバーグは無神論者)。

クローネンバーグの作品がすべてセックスの比喩だというのはフロイディアンに指摘されるまでもなく、クローネンバーグ自身が『シーバーズ』で商業デビューを果たす以前にソフトコア・ポルノを撮ろうとしていたこともあるので、リビドーが様々にトランスフォームした結果が後々の作品に結実していくというのはそうだろうし、それはわかりきっていることだから、「臓器の摘出ショー」を見ながらティムリンが言う「手術は新たなセックスよ」というセリフにもはや新鮮味はなく、交通事故を起こすことにエクスタシーを感じる『クラッシュ』と同じ価値観が繰り返されているのはやや時代遅れに感じられるところもあった。プラスチック可塑剤として使われるフタル酸ジエチルヘキチルがヒトの精子形成を妨げる要因となり、結果、この40年でマイクロプラスティックがヒトの精子を半減させてきたことはジ・オーブがサウンドトラックを務めたドキュメンタリー映画『Plastic Planet(https://www.youtube.com/watch?v=a7X-J1DhfjE)』(OST盤タイトルは『Baghdad Batteries』)でも言及されていたように、そのことを考えると、むしろ「人間をつくる」産科を構想したドラマ版『戦慄の絆』の方が『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』を取り巻く「環境」には対応していると僕には感じられた面もある。ヒトの精子が半減していることと子どもをつくらないセックスは直結する問題ではないはずなので、ティムリンが「手術は新たなセックスよ」と興奮する感覚がもうひとつ共有できず、「体内の美しさのコンテスト」というものが重視される世界観が僕にはまだわかっていないというだけかもしれないけれど。ドラマ版『戦慄の絆』が時にキューブリックを思わせる現代性をデザイン面でも強調した(真上からのショットも多め)のとは対照的に『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は終末というよりもはや場末といった雰囲気の未来像を美術的には構築している。いつものチームとともにつくりあげた陰のあるマニエリスティックな色調は世界が停滞し、失望の底にあることを告げ知らせるには充分で、テクノロジーだけが見たこともないものに入れ替わっているという対比を際立たせる。ドラマ版『戦慄の絆』は後半で中絶禁止法を復活させたアトランタに乗り込むというアグレッシヴな「場所の移動」を経験するのに対し、『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』はアテネをロケ地に選び、背景に歴史をにじみ出させたかったといい、起源とその終焉を意識させるというのか、それこそ新たなものが生まれることを待っているという雰囲気を充満させていく。話が少し進むと冒頭で母親に殺された少年の遺体が冷凍保存されていたことが明らかにされる。(以下、ネタバレ)少年はプラスティックを食べることが可能な臓器を生み出していたのに、これを気味悪がった母親が殺してしまったのである。そう、冒頭の短いシークエンスは人類にとっての大きな悲劇だった……のかどうかは観た人が考えるところ。ソールとカプリースは少年の遺体を使って新たな人類が生まれていたことを公に広く知らせるショーをやらないかと持ちかけられ、どうしようか迷っていると、全身に耳を植えつけたイアー・マンのダンス・ショーを観たことに刺激され、ショーを開くことにソールとカプリースの気持ちは傾いていく。