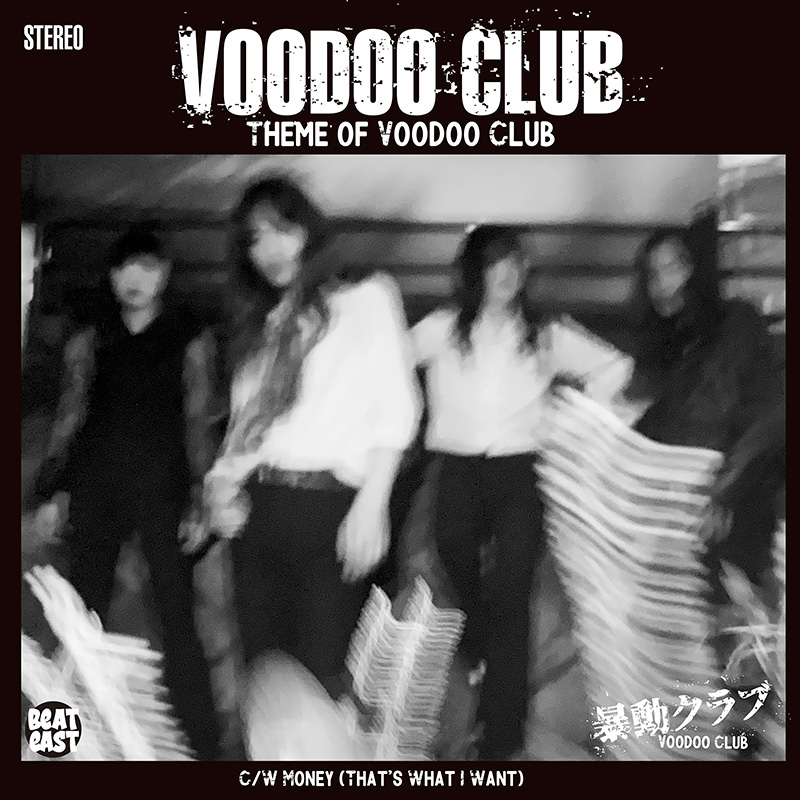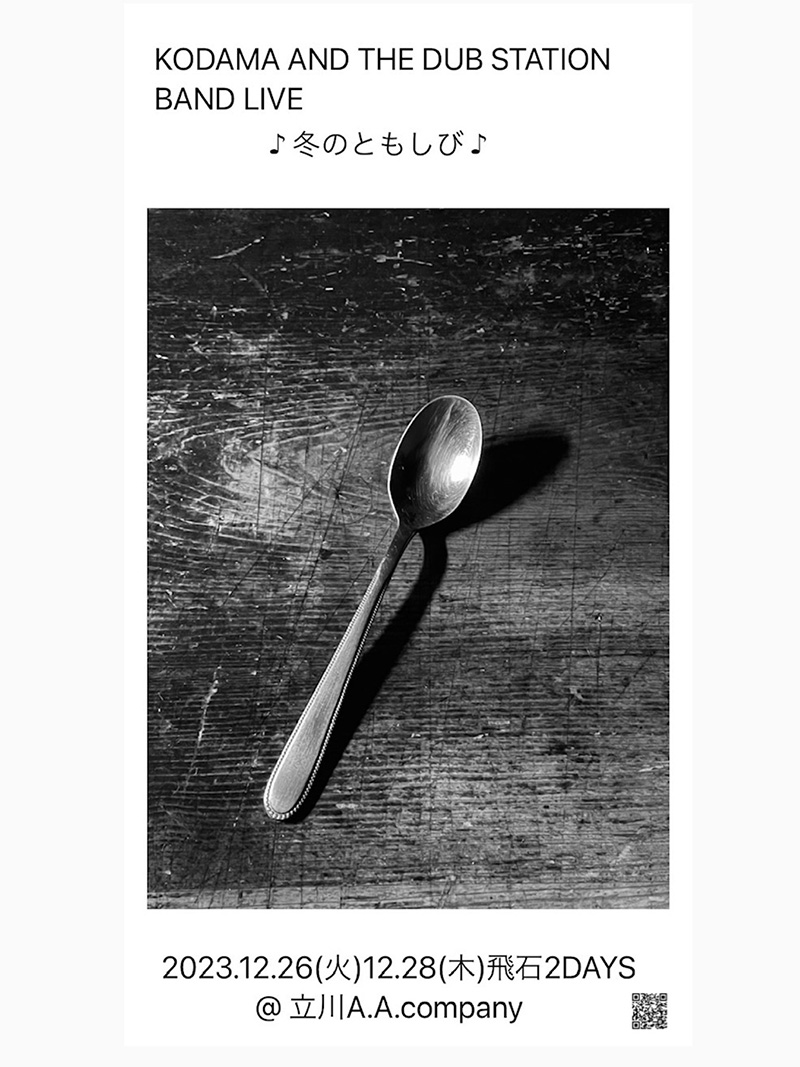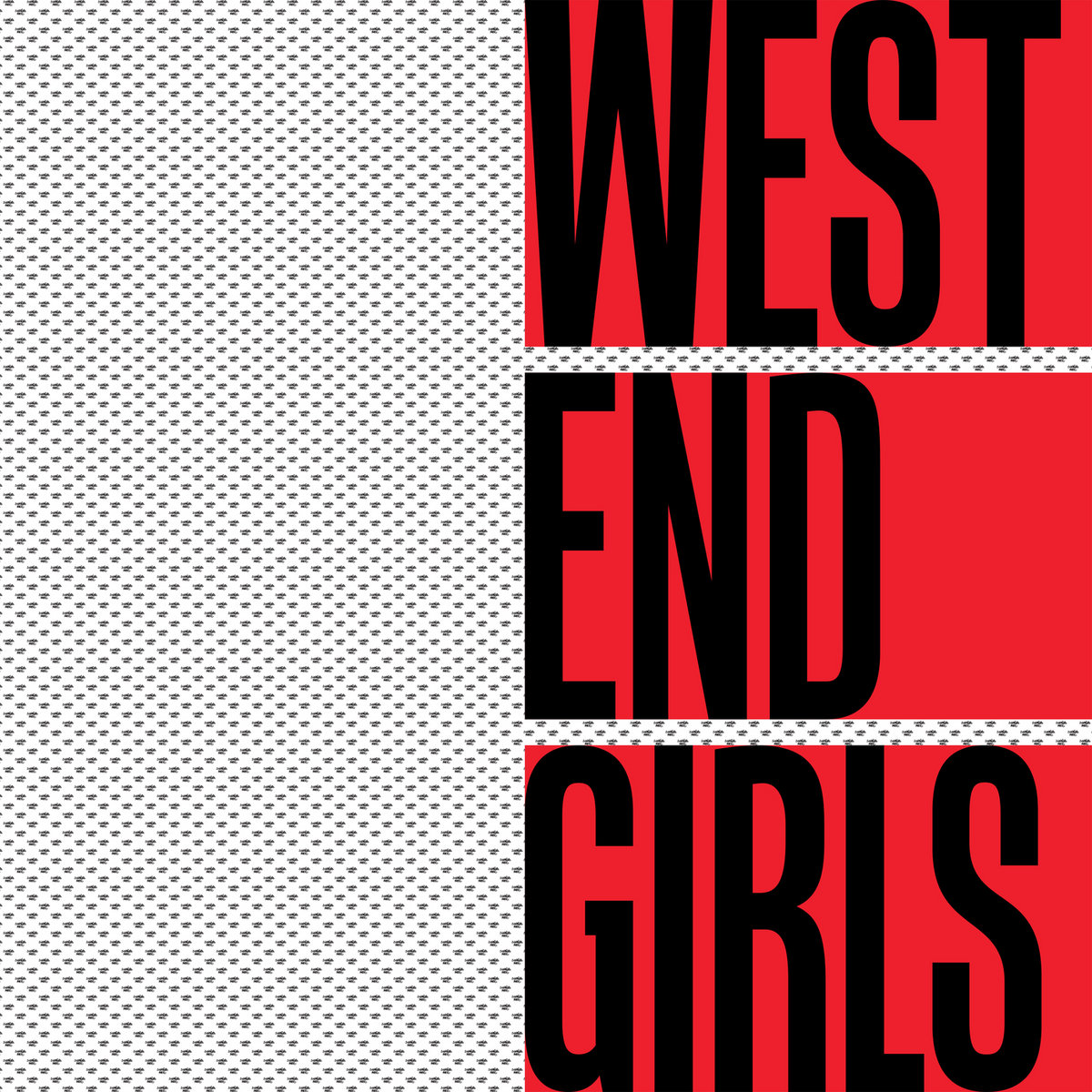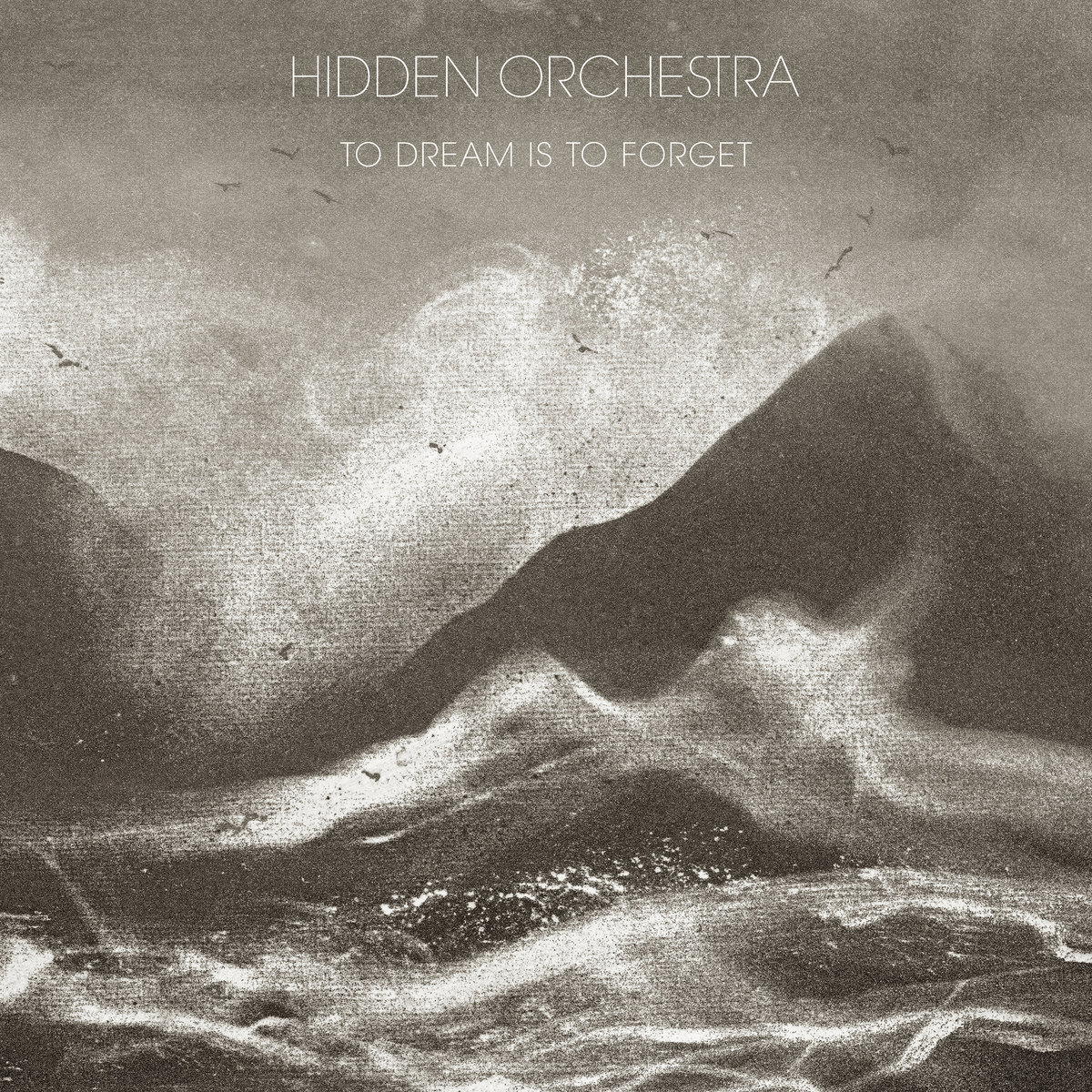2010年代──音楽は何を感じ、どのように生まれ変わり、時代を予見したのか
いま聴くべき名盤たちを紹介しつつ、その爆発的な10年を俯瞰する
目次
ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー
インタヴュー再び「2010年代を振り返る」(小林拓音+野田努/坂本麻里子)
特集:2010年代という終わりとはじまり
2010年代の記憶──幽霊、そして新しきものたちの誕生(野田努)
・入眠状態、そしてアナログ盤やカセットのフェチ化
・OPNからヴェイパーウェイヴへ
・「未来は幽霊のものでしかありえない」とはジャック・デリダの言葉だが
・フットワークの衝撃
・ナルシズムの復権とアルカ革命
・シティポップは世界で大流行していない
・そしてみんなインターネットが嫌いになった
・アナログ盤がなぜ重要か
・音楽市場の変化
・巨匠たち、もしくは大衆運動と音楽
オバマ政権以降の、2010年代のブラック・カルチャー(緊那羅:Desi La/野田努訳)
カニエ・ウエストの預言──恩寵からの急降下(ジリアン・マーシャル/五井健太郎訳)
絶対に聴いておきたい2010年代のジャズ(小川充)
活気づくアフリカからのダンス・ミュージック(三田格)
坂本慎太郎──脱力したプロテスト・ミュージック(野田努)
ジェネレーションXの勝利と死──アイドルとともに霧散した日本のオルタナティヴ(イアン・F・マーティン/江口理恵訳)
あの頃、武蔵野が東京の中心だった──cero、森は生きている、音楽を友とした私たち(柴崎祐二)
ネットからストリートへ──ボカロ、〈Maltine〉、tofubeats、そしてMars89(小林拓音)
ポップスターという現代の神々──ファンダムにおける聖像のあり方とメディア(ジリアン・マーシャル/五井健太郎訳)
マンブルコア運動(三田格)
BLMはUKをどう変えたのか(坂本麻里子×野田努)
ライターが選ぶ いまこそ聴きたい2010年代の名盤/偏愛盤
(天野龍太郎、河村祐介、木津毅、小林拓音、野田努、橋本徹、三田格、渡辺志保)
2010年代、メディアはどんな音楽を評価してきたのか
2023年ベスト・アルバム30選
2023年ベスト・リイシュー23選
ジャンル別2023年ベスト10
テクノ(猪股恭哉)/インディ・ロック(天野龍太郎)/ジャズ(小川充)/ハウス(猪股恭哉)/USヒップホップ(高橋芳朗)/日本ラップ(つやちゃん)/アンビエント(三田格)
2023年わたしのお気に入りベスト10
──ライター/ミュージシャン/DJなど計17組による個人チャート
(天野龍太郎、荏開津広、小川充、小山田米呂、Casanova. S、河村祐介、木津毅、柴崎祐二、つやちゃん、デンシノオト、ジェイムズ・ハッドフィールド、二木信、Mars89、イアン・F・マーティン、松島広人、三田格、yukinoise)
VINYL GOES AROUND PRESENTS そこにレコードがあるから
第3回 新しいシーンは若い世代が作るもの(水谷聡男×山崎真央)
菊判218×152/160ページ
*レコード店およびアマゾンでは12月15日(金)に、書店では12月25日(月)に発売となります。
【オンラインにてお買い求めいただける店舗一覧】
【12月15日発売】
◆amazon
◆TOWER RECORDS
◆disk union
【12月25日発売】
◆TSUTAYAオンライン
◆Rakuten ブックス
◆ヨドバシ・ドット・コム
◆HMV
◆honto
◆Yahoo!ショッピング
◆7net(セブンネットショッピング)
◆紀伊國屋書店
◆e-hon
◆Honya Club
【P-VINE OFFICIAL SHOP】
◆SPECIAL DELIVERY
【全国実店舗の在庫状況】
※書店での発売は12月25日です。
◆丸善/ジュンク堂書店/文教堂/戸田書店/啓林堂書店/ブックスモア
◆紀伊國屋書店
◆三省堂書店
◆旭屋書店
◆有隣堂
◆くまざわ書店
◆大垣書店
◆未来屋書店/アシーネ