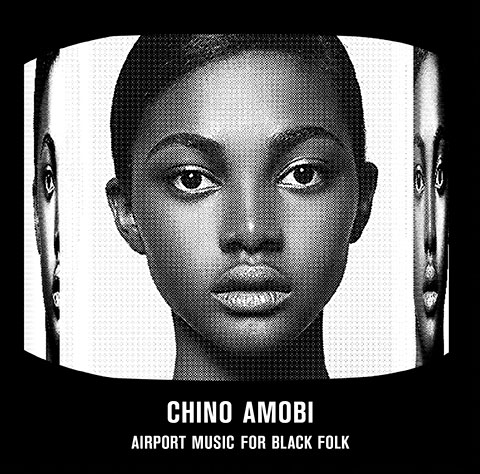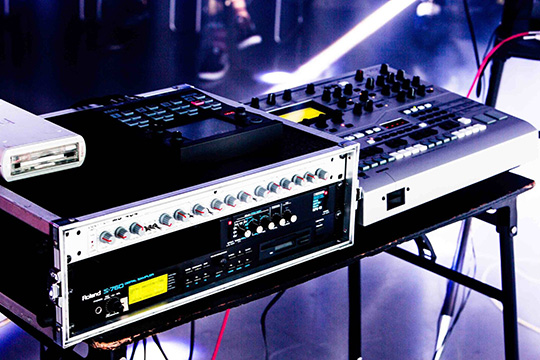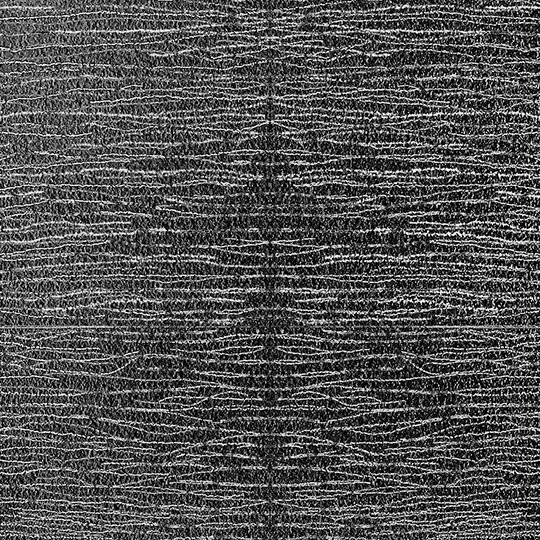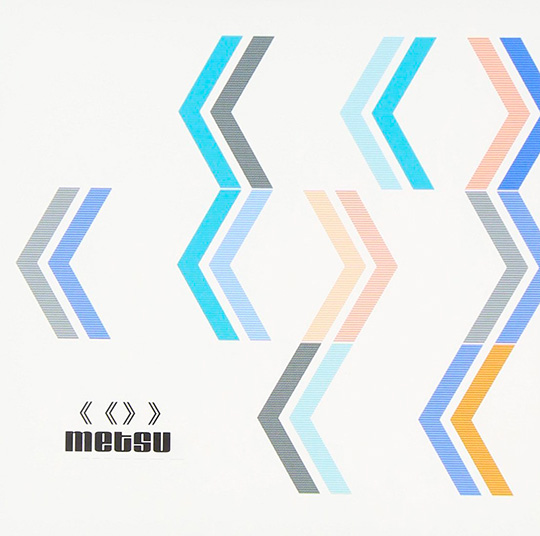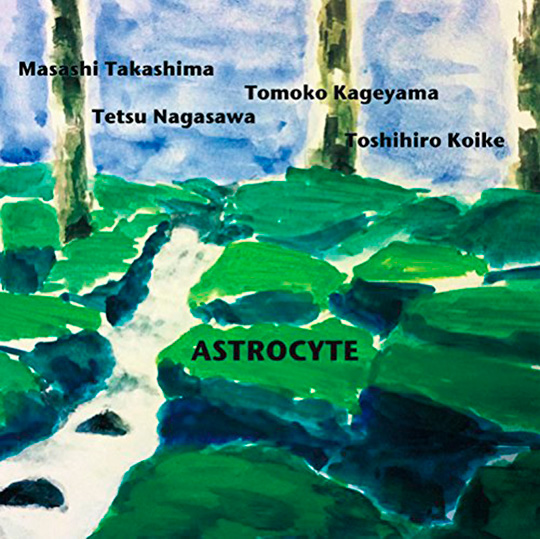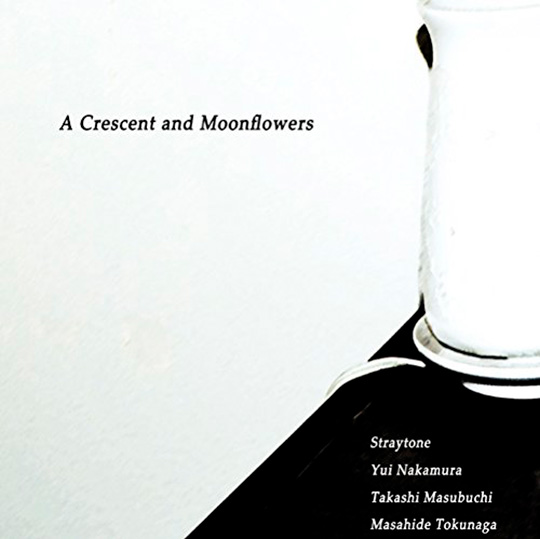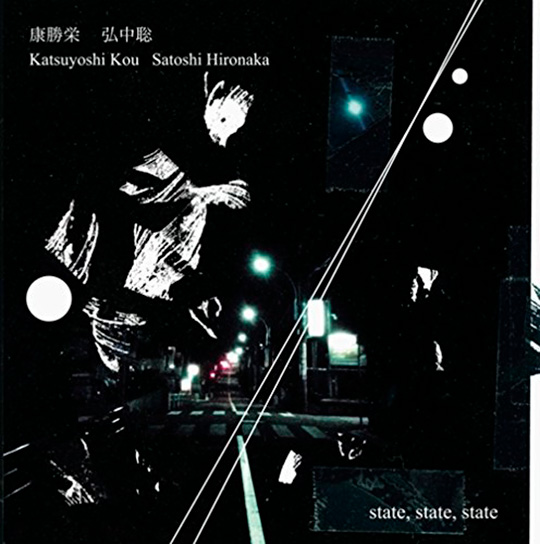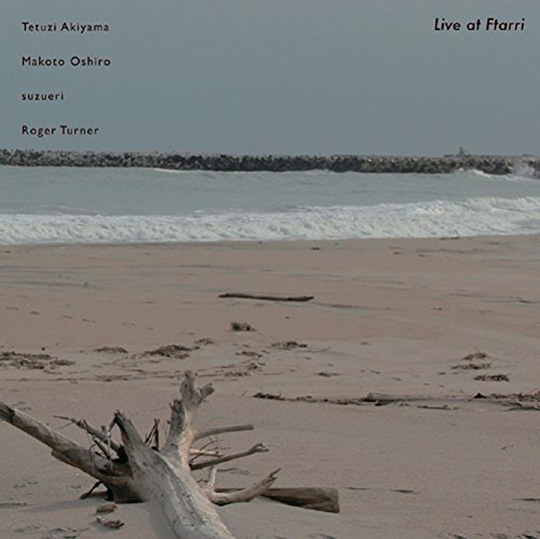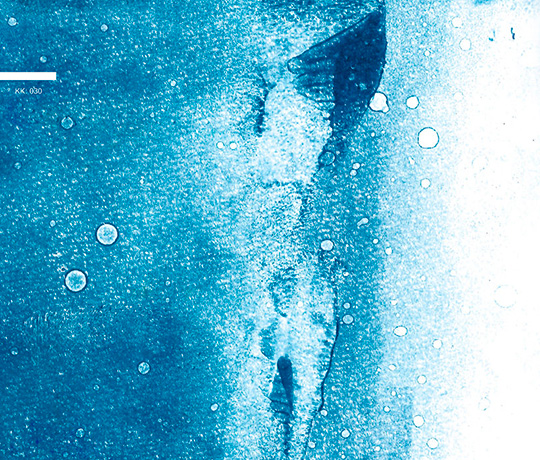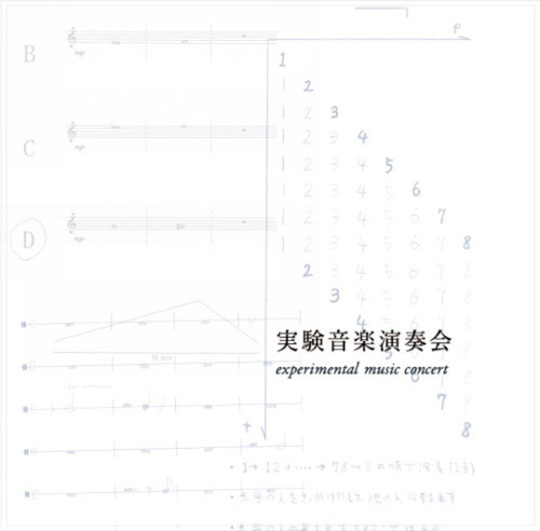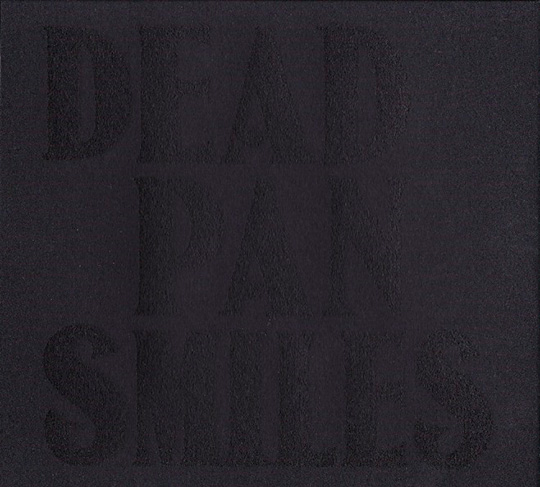あなたがジャジーでソウルフルなドラム&ベースをうんと浴びたいと思っているなら、このイベントがおあつらえ向きでしょう。
今年で創立21周年を迎えるUKのドラム&ベース・レーベル〈ホスピタル・レコード〉。そのボスであるトニー・コールマンのソロ・プロジェクトとして知られるロンドン・エレクトロシティが、7月21日に代官山ユニットで開催される「HOSPITAL NIGHT」に出演する。
昨年20周年を迎えた「Drum & Bass Sessions(DBS)」が開催する今回のパーティでは、ロンドン・エレクトロシティがレーベル21周年を祝す「21 years of Hospital set」を披露するそう。
さらに日本勢からは今年〈ホスピタル・レコード〉と契約し、9月にアルバムをリリース予定のマコトが出演する。競演はダニー・ウィーラーや、テツジ・タナカ、MC CARDZ、などなど。
UNIT 13th ANNIVERSARY
DBS presents "HOSPITAL NIGHT"
日時:2017.07.21 (FRI) open/start 23:30
会場:代官山UNIT
出演:
LONDON ELEKTRICITY (Hospital Records, UK)
MAKOTO (Hospital Records, Human Elements, JAPAN)
DANNY WHEELER (W10 Records, UK)
TETSUJI TANAKA (Localize!!, JAPAN)
host: MC CARDZ (Localize!!, JAPAN)
Vj/Laser: SO IN THE HOUSE
Painting: The Spilt Ink.
料金:adv.3,000yen door 3,500yen
UNIT >>> 03-5459-8630
www.unit-tokyo.com
Ticket 発売中
PIA (0570-02-9999/P-code: 333-696)
LAWSON (L-code: 74079)、
e+ (UNIT携帯サイトから購入できます)
clubberia: https://www.clubberia.com/ja/events/268846-HOSPITAL-NIGHT/
RA: https://jp.residentadvisor.net/event.aspx?974718
(出演者情報)

★LONDON ELEKTRICITY (Hospital Records, UK)
"Fast Soul Music"を標榜するドラム&ベースのトップ・レーベル、Hospitalを率いるLONDON ELEKTRICITYことTONY COLMAN。音楽一家に生まれ、7才からピアノ、作曲を開始した。大学でスタジオのテクニックを学んだ後、'86年にアシッド・ジャズの先鋭グループIZITで活動、3枚のアルバムを残す。'96年に盟友CHRIS GOSSと共にHospitalを発足し、LONDON ELEKTRICITYは生楽器を導入したD&Bを先駆ける。'98年の1st.アルバム『PULL THE PLUG』はジャズ/ファンクのエッセンスが際立つ豊かな音楽性を示し、'03年には2nd.アルバム『BILLION DOLLAR GRAVY』を発表、同アルバムの楽曲をフルバンドで再現する初のライヴを成功させる。’05年の3rd.アルバム『POWER BALLADS』はライヴ感を最大限に発揮し多方面から絶賛を浴びる。’08年には4th.アルバム『SYNCOPATED CITY』で斬新な都市交響楽を奏でる。そしてロングセラーを記録した’11年の名盤『YIKES !』を経て’15年に通算6作目のスタジオ・アルバム『Are We There Yet?』をリリース、多彩なヴォーカル陣をフィーチャーし、ピアノ、ストリングスといった生音を最大限に活かしたソウルフルな楽曲の数々で最高級のクオリティを見せつける。'16年にはTHE LONDON ELEKTRICITY BIG BANDを編成し、ビッグ・ブラスバンド・スタイルでのライヴを敢行する。
https://www.hospitalrecords.com/
https://www.londonelektricity.com/
https://www.facebook.com/londonelektricity
https://twitter.com/londonelek

★MAKOTO (Hospital Records, Human Elements, HE:Digital, JAPAN)
DRUM & BASSのミュージカル・サイドを代表するレーベル、LTJ BUKEMのGood Looking Recordsの専属アーティストとして98年にデビュー以来、ソウル、ジャズ感覚溢れる感動的な楽曲を次々に生み出し、アルバム『HUMAN ELEMENTS』(03年)、『BELIEVE IN MY SOUL』(07年)、そしてDJ MARKYのInnerground, FABIOのCreative Source, DJ ZINCのBingo等から数々の楽曲を発表。DJとしては『PROGRESSION SESSIONS 9 – LIVE IN JAPAN 2003』, 『DJ MARKY & FRIENDS PRESENTS MAKOTO』の各MIX CDを発表し、世界30カ国、100都市以上を周り、数千、数万のクラウドを歓喜させ、その実⼒を余すところなく証明し続けてきた、日本を代表するインターナショナルなトップDJ/プロデューサーである。その後、自らのレーベル、Human Elementsに活動の基盤を移し、11年にアルバム『SOULED OUT』を発表、フルバンドでのライヴを収録した『LIVE @ MOTION BLUE YOKOHAMA』を経て13年に"Souled Out"3部作の完結となる『SOULED OUT REMIXED』をリリース。15年にはUKの熟練プロデューサー、A SIDESとのコラボレーション・アルバム『AQUARIAN DREAMS』をEastern Elementsよりリリース。17年、DRUM & BASSのNo.1レーベル、Hospitalと契約を交わし、コンピレーション"We Are 21"に"Speed Of Life"を提供、同レーベルのパーティー"Hospitality"を初め、UK/ヨーロッパ・ツアーで大成功を収める。そして今年9月、待望のニューアルバム『SALVATION』が遂にリリースされる!
https://www.twitter.com/Makoto_MusicJP
https://www.twitter.com/Makoto_Music
https://www.facebook.com/makoto.humanelement
https://www.soundcloud.com/makoto-humanelements
https://www.humanelements.jp