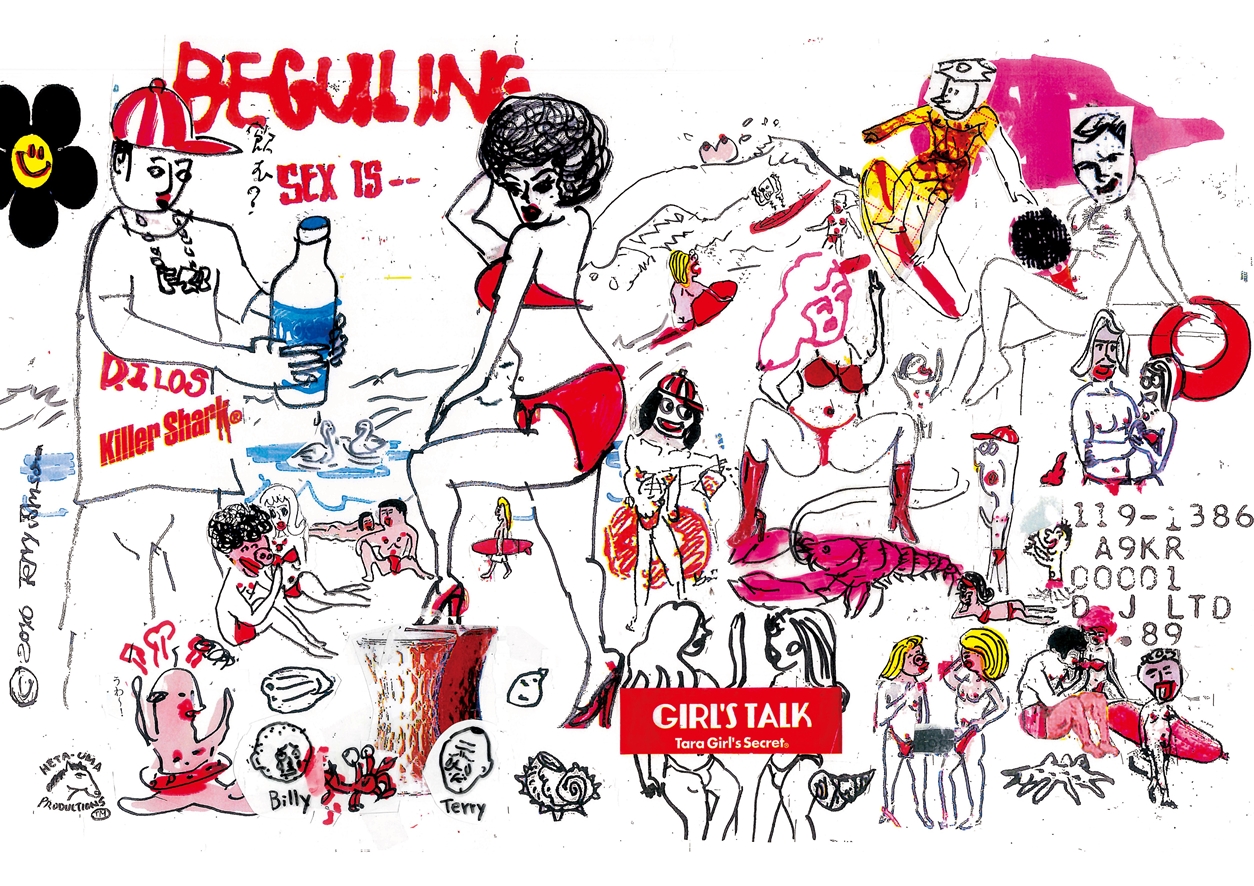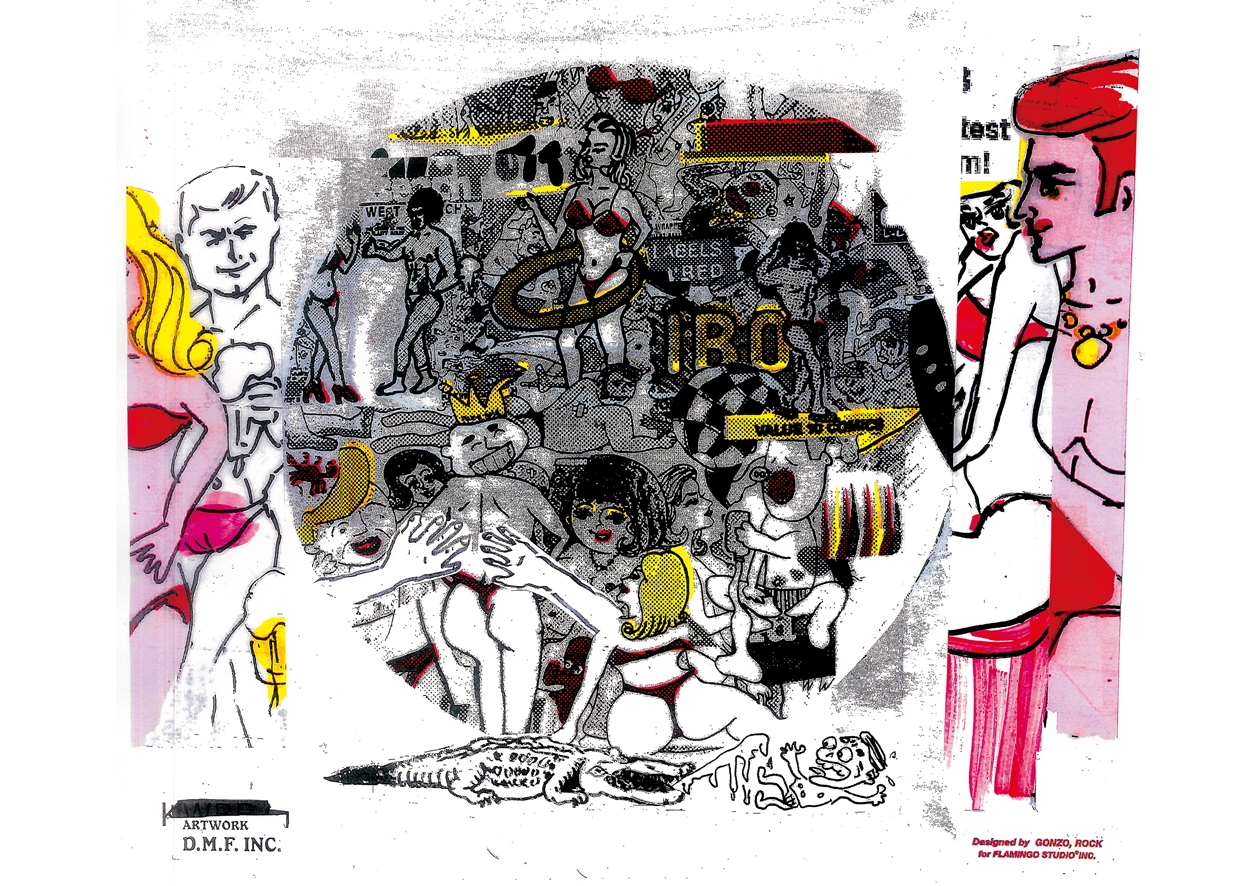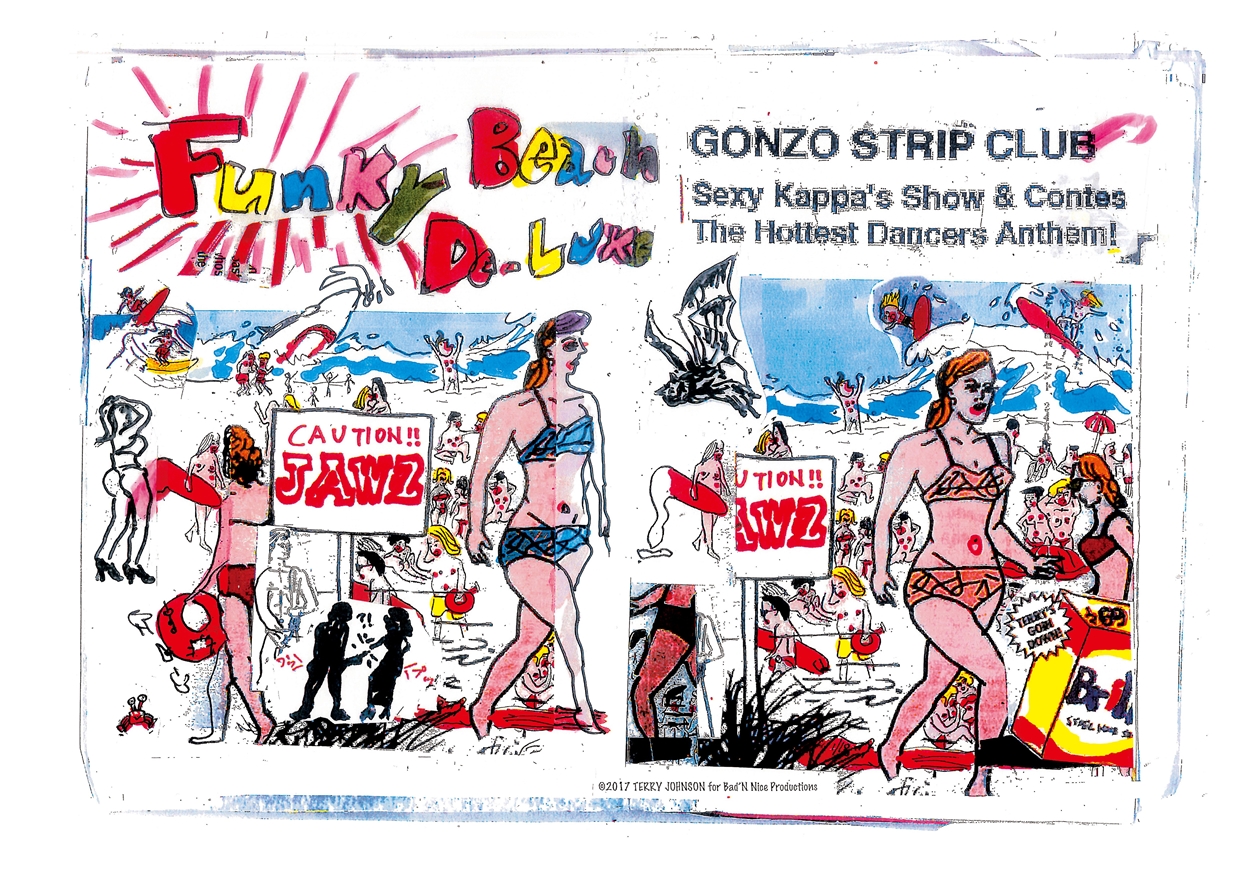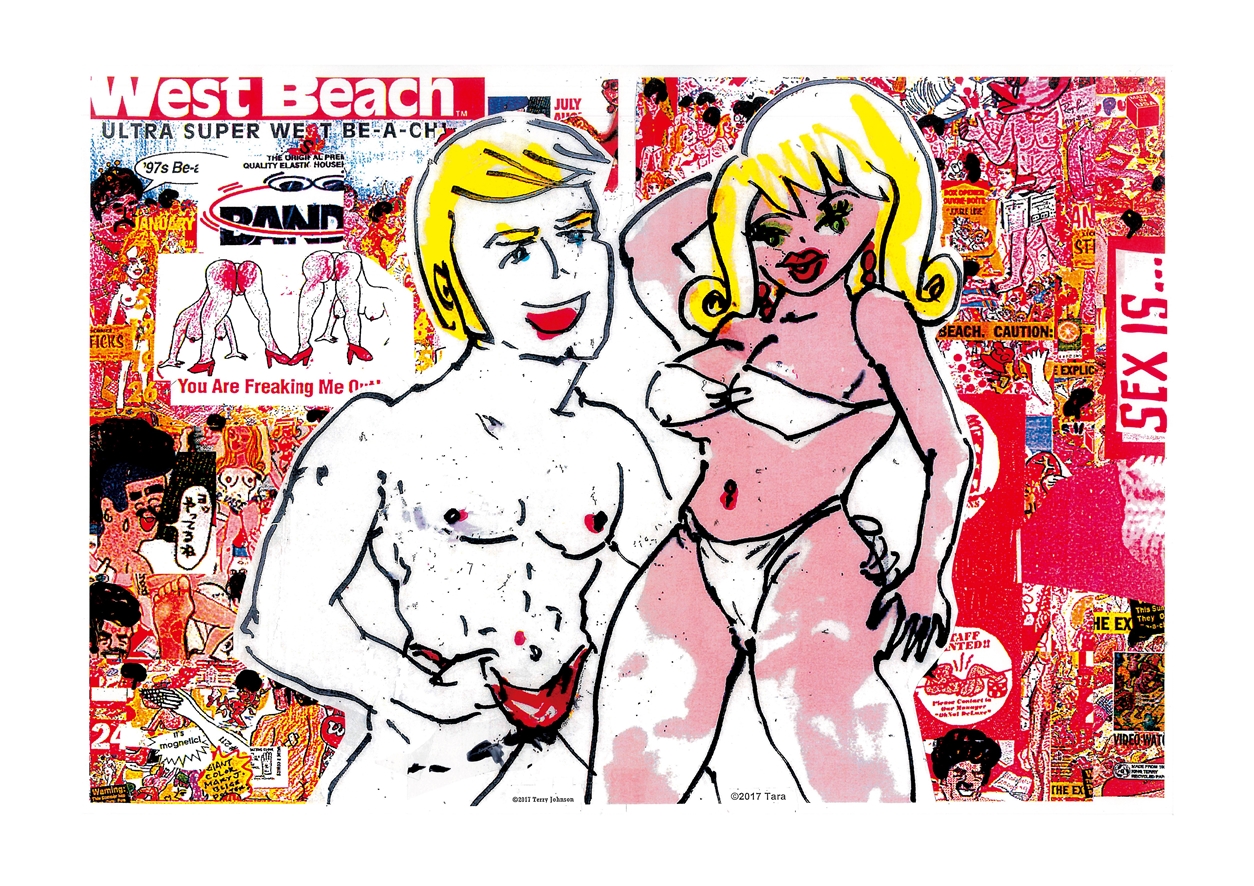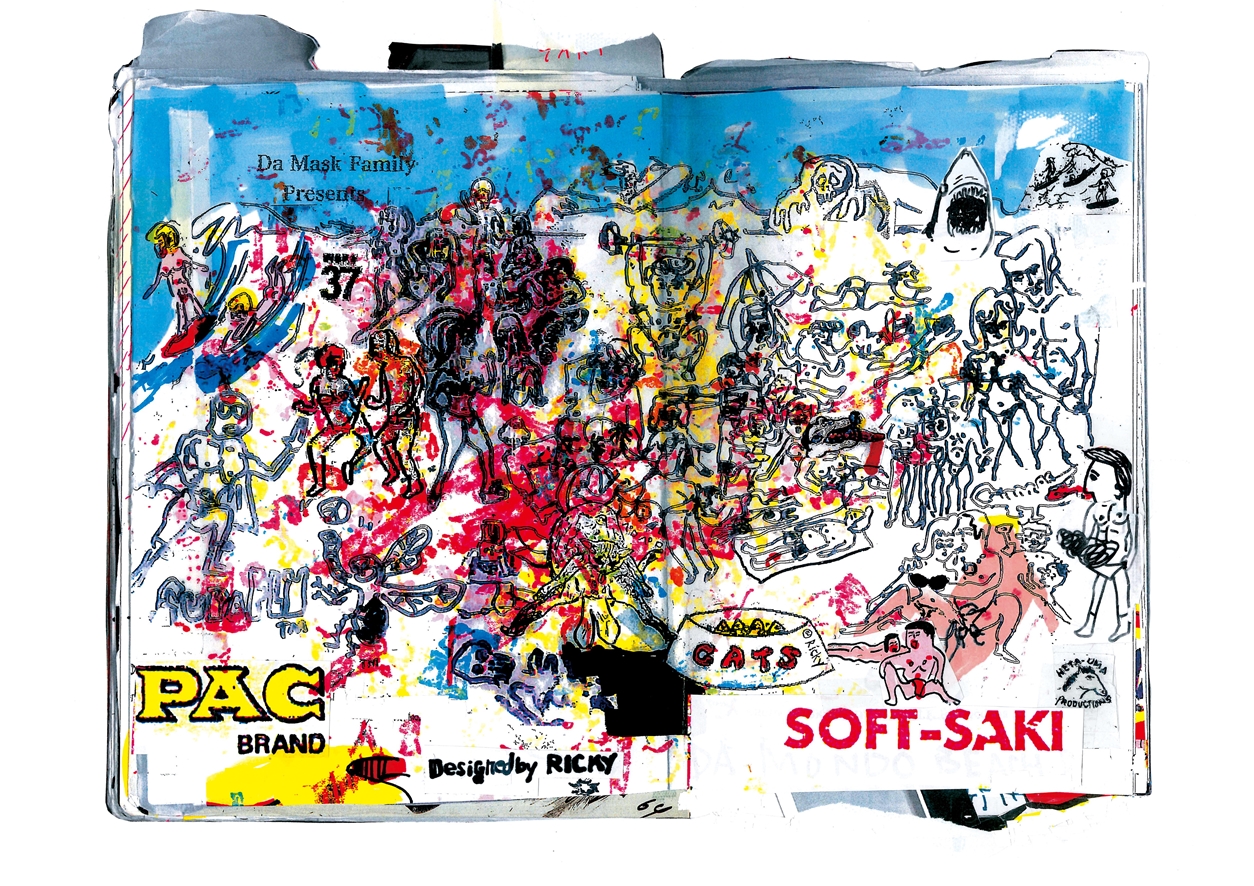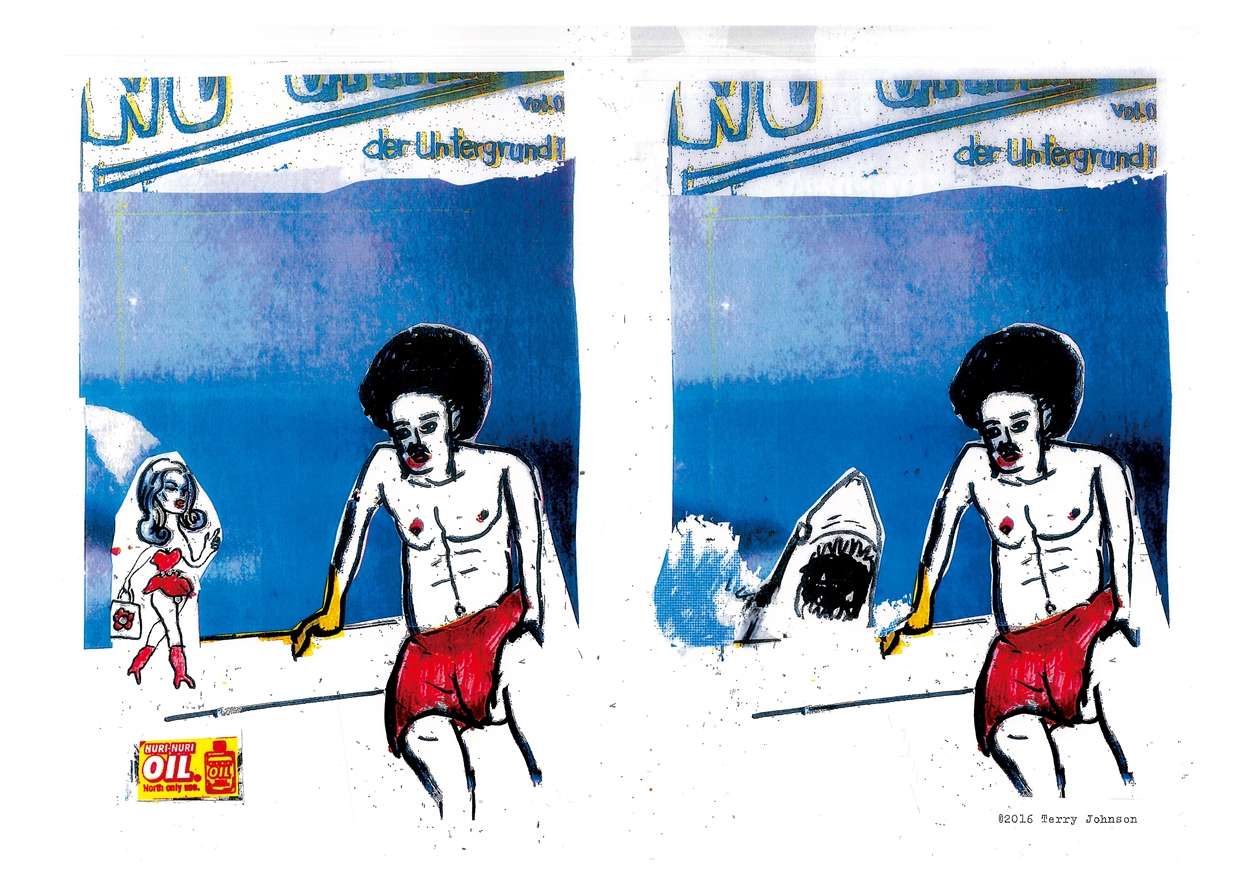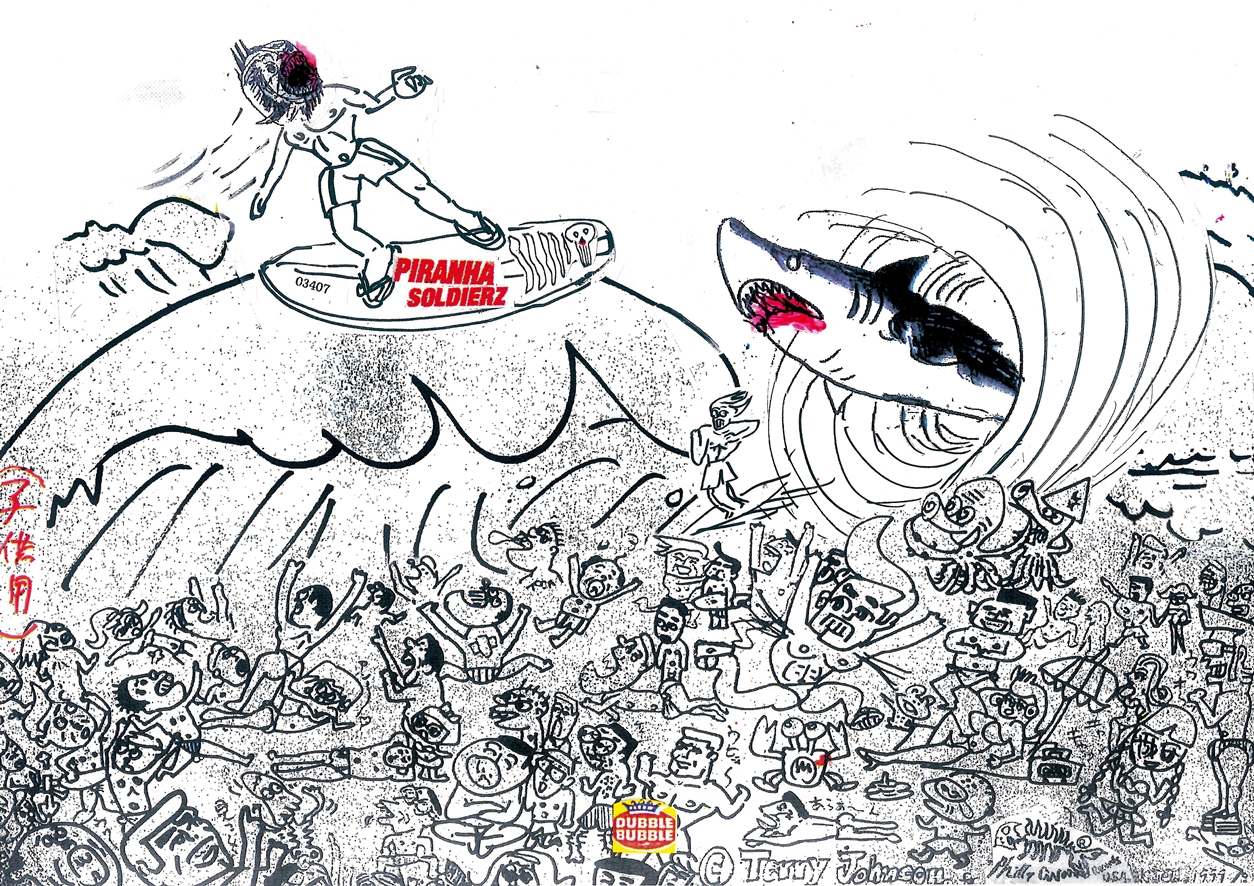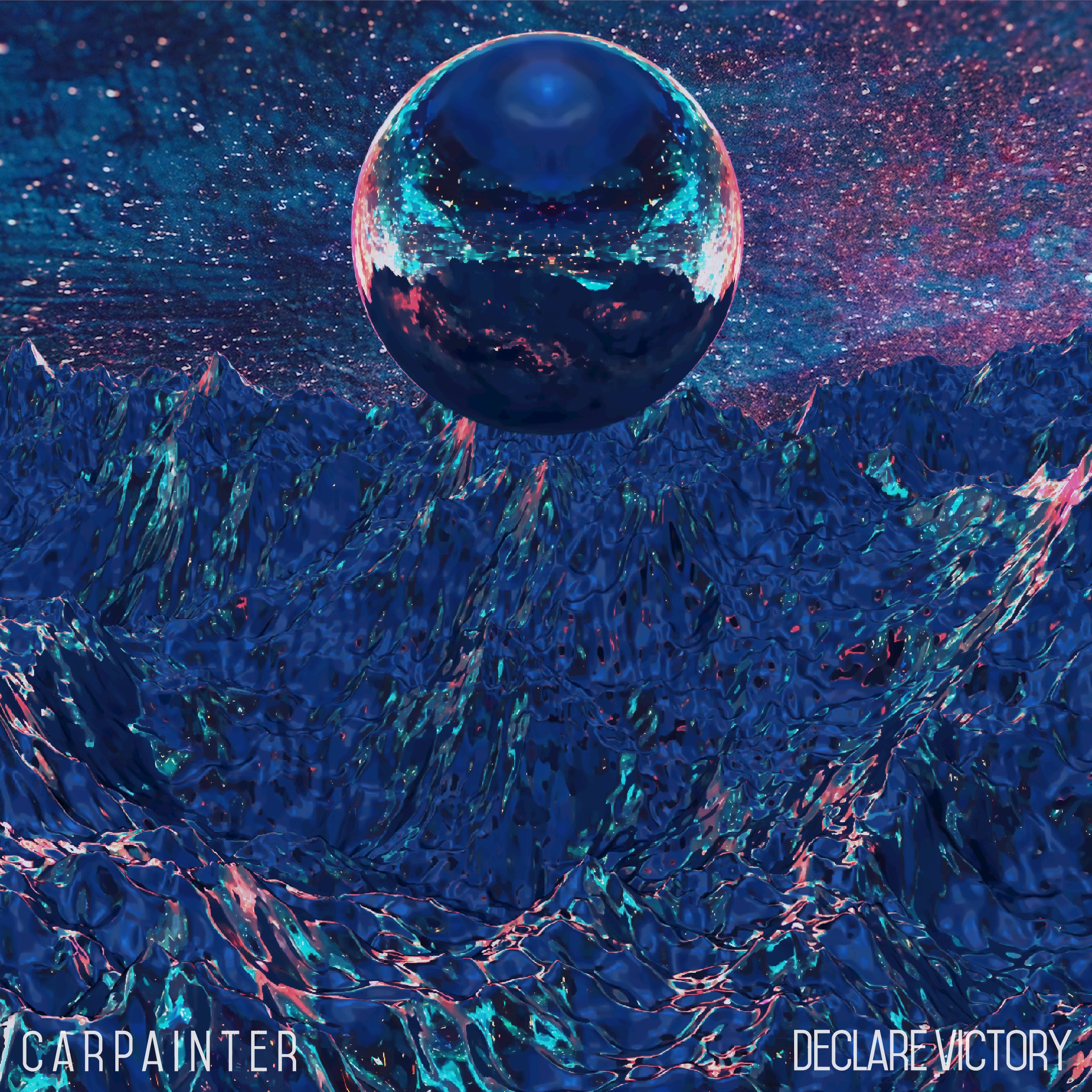思い返せばペイヴメントも、いわゆるオルタナのくくりで語られることが多かったような気がする。だがスティーヴン・マルクマスの背景はもっと違うところにあるのであって、それがマルクマスの音楽の分類の難しさもとい魅力にもなっていたわけだけれど──ともあれ彼はめでたく新しいアルバムを完成させた。今回はエレクトロニックに寄った内容になっている模様。現在、スーパーオーガニズムのメンバーが手がけたという新曲“Rushing the Acid Frat”のMVが公開されている(スーパーオーガニズム→スピーディ・J→「アシッド」……ってのは深読みしすぎか)。きっとマルクマスの第一声を聞いただけで往年のファンは悶えることだろう。発売は3月15日。
STEPHEN MALKMUS
ペイヴメントでの活躍でも知られるスティーヴン・マルクマス、3月15日に発売を控える最新アルバム『Groove Denied』から新曲をMVとともに公開! スーパーオーガニズムのメンバーが手掛けたポップでサイケなアニメからは目が離せない! 国内盤のみに収録されるボーナストラックも決定!

過去の音楽の単なる焼き直しではなく、これまでの歴史を守りつつ、自分たちのアイデンティティーを保ち、常に楽しみながら制作を続けてきたスティーヴン・マルクマス。昨年発売されたスティーヴン・マルクマス&ザ・ジックスのアルバム『Sparkle Hard』は Pitchfork、Rolling Stone、SPIN などの多数のメディアでアルバム・オブ・ザ・イヤーを獲得している。
〈Matador Records〉から3月15日にリリースされる新作アルバム『Groove Denied』は、スティーヴン・マルクマス曰く「(人々に)受け入れられなかった」作品で、マルクマスならではのエレクトロニック・アルバムに仕上がっている。
80年代のニュー・ウェイヴ・シーンなどの影響を感じさせる同アルバムから今回、新曲“Rushing The Acid Frat”がMVと合わせて公開された。マルクマスは、大学時代の友人との思い出からインスパイアされたという新曲を「スター・ウォーズに出てくるバーのシーンのサウンドトラック」だと表現している。同時に解禁された新曲のアニメMVは、スーパーオーガニズムの映像担当ロバート・ストレンジが手掛け、マルクマスが「トリップ」して幻覚を見ている様子を描いたサイケでポップな仕上がりとなっている。
待望の最新アルバム『Groove Denied』は、3月15日(金)に発売される。国内盤CDにはボーナストラックとして“Funeral Bias”と“Moog Police”の2曲が追加収録され、歌詞対訳と解説書が封入される。現在 iTunes Store でアルバムを予約すると、既に公開されている“Viktor Borgia”と今回公開された“Rushing The Acid Frat”がいち早くダウンロードできる。
Stephen Malkmus - Rushing The Acid Frat
https://youtu.be/LDiqO5VhFPw
Stephen Malkmus – Viktor Borgia
https://youtu.be/YlC8uz47qGo
おかしなポップの世界へと道を外れた心躍る作品 ──Rolling Stone
“Viktor Borgia”は80年代初めのポスト・パンクの影響を受けたシンセの要素が散りばめられ、一風変わった実験のよう ──NPR
たるんだ中年の米国人は、ギターを置いたエリートのロック・ミュージシャンというより、エレクトロニック・ミュージックに浸っている ──Vulture

label: Matador / Beat Records
artist: Stephen Malkmus
title: Groove Denied
cat no.: OLE14333
release date: 2019/03/15 FRI ON SALE
BEATINK: https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=10080
Tower Records: https://tower.jp/item/4857974
Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B07N6KXK6N/
HMV: https://www.hmv.co.jp/product/detail/9583967
Apple Music: https://itunes.apple.com/jp/album/groove-denied/1449105904?app=music&ign-mpt=uo%3d4
iTunes: https://itunes.apple.com/jp/album/groove-denied/1449105904?app=itunes&ign-mpt=uo%3d4
Spotify: https://open.spotify.com/album/4gaxzhvf4uihwxogaas4sx
[TRACKLISTING]
01. Belziger Faceplant
02. A Bit Wilder
03. Viktor Borgia
04. Come Get Me
05. Forget Your Place
06. Rushing The Acid Frat
07. Love The Door
08. Bossviscerate
09. Ocean of Revenge
10. Grown Nothing
11. Funeral Bias (Bonus Track For Japan)
12. Moog Police (Bonus Track For Japan)